53 手習(大島本) |
TENARAHI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十七歳三月末頃から二十八歳の夏までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March at the age of 27 to summer at the age of 28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 第六章 浮舟の物語 薫、浮舟生存を聞き知る |
6 Tale of Ukifune Kaoru gets to know Ukifune's exsitence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 第一段 新年、浮舟と尼君、和歌を詠み交す |
6-1 Ukifune and Ama-gimi compose and exchange waka at a new year |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1 | 年も返りぬ。春のしるしも見えず、 凍りわたれる水の音せぬさへ心細くて、「 君にぞ惑ふ」とのたまひし人は、心憂しと思ひ果てにたれど、なほその折などのことは忘れず。 |
年が改まった。春の兆しも見えず、氷が張りつめた川の水が音を立てないのまでが心細くて、「あなたに迷っています」とおっしゃった方は、嫌だとすっかり思い捨てていたが、やはりその当時のことなどは忘れなていない。 |
年が明けた。しかし小野の |
Tosi mo kaheri nu. Haru no sirusi mo miye zu, kohori watare ru midu no oto se nu sahe kokoro-bosoku te, "Kimi ni zo madohu" to notamahi si hito ha, kokoro-usi to omohi-hate ni tare do, naho sono wori nado no koto ha wasure zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.2 | 「 かきくらす野山の雪を眺めても |
「降りしきる野山の雪を眺めていても |
かきくらす野山の雪をながめても |
"Kaki-kurasu noyama no yuki wo nagame te mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.3 | 降りにしことぞ今日も悲しき」 |
昔のことが今日も悲しく思い出される」 |
ふりにしことぞ今日も悲しき |
huri ni si koto zo kehu mo kanasiki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.4 | など、例の、慰めの手習を、行ひの隙にはしたまふ。「 我世になくて年隔たりぬるを、思ひ出づる人もあらむかし」など、思ひ出づる時も多かり。若菜をおろそかなる籠に入れて、人の持て来たりけるを、尼君見て、 |
などと、いつもの、慰めの手習いを、お勤めの合間になさる。「わたしがいなくなって、年も変わったが、思い出す人もきっといるだろう」などと、思い出す時も多かった。若菜を粗末な籠に入れて、人が持って来たのを、尼君が見て、 |
などと書いたりする手習いは仏勤めの合い間に今もしていた。自分のいなくなった春から次の春に移ったことで、自分を思い出している人もあろうなどと去年の思い出されることが多かった。そまつな |
nado, rei no, nagusame no tenarahi wo, okonahi no hima ni ha si tamahu. "Ware yo ni naku te tosi hedatari nuru wo, omohi-iduru hito mo ara m kasi." nado, omohi-iduru toki mo ohokari. Wakana wo orosoka naru ko ni ire te, hito no mote ki tari keru wo, Ama-Gimi mi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.5 | 「 山里の雪間の若菜摘みはやし |
「山里の雪の間に生えた若菜を摘み祝っては |
山里の雪間の若菜摘みはやしなほ |
"Yamazato no yukima no wakana tumi hayasi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.6 | なほ生ひ先の頼まるるかな」 |
やはりあなたの将来が期待されます」 |
|
naho ohisaki no tanoma ruru kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.7 | とて、こなたにたてまつれたまへりければ、 |
と言って、こちらに差し上げなさったので、 |
という歌を添えて姫君の所へ尼君は持たせてよこした。 |
tote, konata ni tatemature tamahe ri kere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.8 | 「 雪深き野辺の若菜も今よりは |
「雪の深い野辺の若菜も今日からは |
雪深き野べの若菜も今よりは |
"Yuki hukaki nobe no wakana mo ima yori ha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.9 | 君がためにぞ年も摘むべき」 |
あなた様のために長寿を祈って摘みましょう」 |
君がためにぞ年もつむべき |
Kimi ga tame ni zo tosi mo tumu beki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.10 | とあるを、「 さぞ思すらむ」と あはれなるにも、「 見るかひあるべき御さまと思はましかば」と、まめやかにうち泣いたまふ。 |
とあるのを、「きっとそのようにお思いであろう」と感慨深くなるのも、「これがお世話しがいのあるお姿と思えたら」と、本気でお泣きになる。 |
と書いて来た返しを見て、実感であろうと哀れに思うのであった。尼姫君などでなく、宝とも花とも見て大事にしたかった人であるのにと真心から尼君は悲しがって泣いた。 |
to aru wo, "Sazo obosu ram." to ahare naru ni mo. "Miru kahi aru beki ohom-sama to omoha masika ba." to, mameyaka ni uti-nai tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
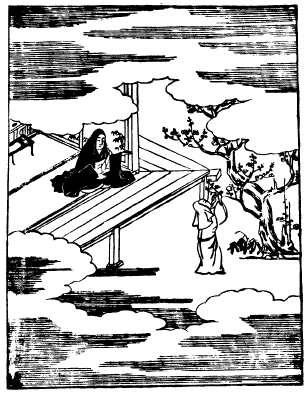 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.11 | 閨のつま近き紅梅の色も香も変はらぬを、「 春や昔の」と ★、異花よりもこれに心寄せのあるは、 飽かざりし匂ひのしみにけるにや ★。後夜に 閼伽奉らせたまふ。下臈の尼のすこし若きがある、召し出でて花折らすれば、 かことがましく散るに、いとど匂ひ来れば、 |
寝室の近くの紅梅が色も香も昔と変わらないのを、「春や昔の」と、他の花よりもこの花に愛着を感じるのは、はかなかった宮のことが忘れられなかったからあろうか。後夜に閼伽を奉りなさる。身分の低い尼で少し若いのがいるのを、呼び出して折らせると、恨みがましく散るにつけて、ますます匂って来るので、 |
寝室の縁に近い紅梅の色の香も昔の花に変わらぬ木を、ことさら姫君が愛しているのは「春や昔の」(春ならぬわが身一つはもとの身にして)と忍ばれることがあるからであろう。御仏に |
Neya no tuma tikaki koubai no iro mo ka mo kahara nu wo, "Haru ya mukasi no" to, koto-bana yori mo kore ni kokoro-yose no aru ha, aka zari si nihohi no simi ni keru ni ya? Goya ni aka tatematura se tamahu. Gerahu no Ama no sukosi wakaki ga aru mesi-ide te hana wora sure ba, kakoto-gamasiku tiru ni, itodo nihohi kure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.12 | 「 袖触れし人こそ見えね花の香の |
「袖を触れ合った人の姿は見えないが、花の香が |
袖ふれし人こそ見えね花の香の |
"Sode hure si hito koso miye ne hana no ka no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.13 | それかと匂ふ春のあけぼの」 |
あの人の香と同じように匂って来る、春の夜明けよ」 |
それかとにほふ春のあけぼの |
sore ka to nihohu haru no akebono |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.14 | 姫君のその時の作である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 第二段 大尼君の孫、紀伊守、山荘に来訪 |
6-2 Kii-no-kami who is a grand son of the old nun visits to Ono villa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.1 | 大尼君の 孫の紀伊守なりける、このころ上りて来たり。三十ばかりにて、容貌きよげに誇りかなるさましたり。 |
大尼君の孫で紀伊守であった者が、このころ上京して来た。三十歳ほどで、容貌も美しげで誇らしい様子をしていた。 |
大尼君の孫で |
Oho-Ama-Gimi no mago no Kii-no-Kami nari keru, kono-koro nobori te ki tari. Sam-zihu bakari nite, katati kiyoge ni hokori ka naru sama si tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.2 | 「 何ごとか、去年、一昨年」 |
「いかがでしたか、去年や、一昨年は」 |
大尼君の所で去年のこととか、 |
"Nani-goto ka, kozo, ototosi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.3 | など問ふに、ほけほけしきさまなれば、 こなたに来て、 |
などとお尋ねになるが、耄碌した様子なので、こちらに来て、 |
ぼけてしまったふうであったから、そこを辞して |
nado tohu ni, hoke-hokesiki sama nare ba, konata ni ki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.4 | 「 いとこよなくこそ、ひがみたまひにけれ。あはれにも はべるかな。残りなき御さまを、見たてまつること難くて、 遠きほどに年月を過ぐしはべるよ。 親たちものしたまはで後は、 一所をこそ、御代はりに思ひきこえはべりつれ。 常陸の北の方は、訪れきこえたまふや」 |
「とてもすっかり、耄碌しておしまいになった。お気の毒なことですね。残り少ないご様子を、拝し上げることもむずかしくて、遠い所で年月を過ごしておりますことよ。両親がお亡くなりになって以後は、祖母お一方を、親代わりにお思い申し上げておりました。常陸介の北の方は、お便り差し上げなさいますか」 |
「非常に老いぼれておしまいになりましたね。気の毒ですね。御老体のお世話をすることもできずに遠い国で年を送っていますのは相済まぬことだと思っているのですよ。両親のいなくなりましてからは、お |
"Ito koyonaku koso, higami tamahi ni kere. Ahare ni mo haberu kana! Nokori naki ohom-sama wo, mi tatematuru koto kataku te, tohoki hodo ni tosi-tuki wo sugusi haberu yo. Oya-tati monosi tamaha de noti ha, hito-tokoro wo koso, ohom-kahari ni omohi kikoye haberi ture. Hitati no Kitanokata ha, otodure kikoye tamahu ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.5 | と言ふは、いもうとなるべし。 |
と言うのは、その妹なのであろう。 |
と言うのはこの人の女の兄弟のことらしい。 |
to ihu ha, imouto naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.6 | 「 年月に添へては、つれづれにあはれなることのみまさりてなむ。常陸は、久しう訪れきこえたまはざめり。 え待ちつけたまふまじきさまになむ見えたまふ」 |
「年月のたつにつれて、することもないままに悲しいことばかりが増えて。常陸は、長いことお便り申し上げなさらないようです。お待ち申し上げることもできないようにお見えになります」 |
「歳月がたつにしたがって周囲が寂しくなりますよ。常陸は久しく手紙をよこしませんよ。上京するまでお |
"Tosi-tuki ni sohe te ha, ture-dure ni ahare naru koto nomi masari te nam. Hitati ha, hisasiu otodure kikoye tamaha za' meri. E mati-tuke tamahu maziki sama ni nam miye tamahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.7 | とのたまふに、「 わが親の名」と、あいなく耳止まれるに、また言ふやう、 |
とおっしゃるので、「自分の親の名前だ」と、無関係ながらも耳にとまったが、また言うことには、 |
浮舟の姫君は自身の親と同じ名の呼ばれていることにわけもなく耳がとまるのであったが、また客が、 |
to notamahu ni, "Waga oya no na." to, ainaku mimi tomare ru ni, mata ihu yau, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.8 | 「 まかり上りて日ごろになりはべりぬるを、公事のいとしげく、むつかしうのみはべるにかかづらひてなむ。昨日もさぶらはむと思ひたまへしを、 右大将殿の宇治におはせし御供に仕うまつりて、 故八の宮の住みたまひし所におはして、日暮らしたまひし。 |
「上京して何日にもなりましたが、公務がたいそう忙しくて、面倒なことばかりにかかずらっておりまして。昨日もお伺いしようと存じておりましたのに、右大将殿が宇治へお出かけになるお供にお仕えしまして、故八の宮がお住まいになっていた所にいらして、一日中お過ごしになりました。 |
「京へ出てまいってもすぐに伺えませんでした。地方官としてこちらでする仕事がたくさんでめんどうなことも中にはあるのです。それに |
"Makari nobori te hi-goro ni nari haberi nuru wo, ohoyake-goto no ito sigeku, mutukasiu nomi haberu ni kakadurahi te nam. Kinohu mo saburaha m to omohi tamahe si wo, Udaisyau-dono no Udi ni ohase si ohom-tomo ni tukau-maturi te, ko-Hati-no-Miya no sumi tamahi si tokoro ni ohasi te, hi kurasi tamahi si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.9 | 故宮の御女に通ひたまひしを、まづ一所は一年亡せたまひにき。 その御おとうと、また忍びて据ゑたてまつりたまへりけるを、去年の春また亡せたまひにければ、その御果てのわざせさせたまはむこと、かの寺の律師になむ、さるべきことのたまはせて、 なにがしも、かの女の装束一領、調じはべるべきを、 せさせたまひてむや。織らすべきものは、急ぎせさせはべりなむ」 |
故宮の娘にお通いになっていたが、まずお一方は先年お亡くなりになりました。その妹に、再びこっそりと住まわせ申していらしたが、去年の春またお亡くなりになったので、その一周忌のご法事をあそばしますことを、あの寺の律師に、しかるべき事柄をお命じになって、わたしも、その女装束一領を、調製しなければならないのですが、こちらで作ってくださいませんでしょうか。織る材料は、急いで準備させましょう」 |
宮の姫君の所へ通っておられたのですが、最初の方は前にお |
Ko-Miya no ohom-Musume ni kayohi tamahi si wo, madu hito-tokoro ha hitotose use tamahi ni ki. Sono ohom-otouto, mata sinobi te suwe tatematuri tamahe ri keru wo, kozo no haru mata use tamahi ni kere ba, sono ohom-hate no waza se sase tamaha m koto, kano tera no Rissi ni nam, saru-beki koto notamaha se te, Nanigasi mo, kano womna no sauzoku hito-kudari, teu-zi haberu beki wo, se sase tamahi te m ya? Orasu beki mono ha, isogi se sase haberi na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.10 | と言ふを聞くに、 いかでかあはれならざらむ。「 人やあやしと見む」とつつましうて、奥に向ひてゐたまへり。尼君、 |
と言うのを聞くと、どうして胸を打たないことがあろう。「人が変だと見るだろう」と気がひけて、奥の方を向いて座っていた。尼君が、 |
こう言うのを姫君が聞いていて身にしまぬわけもない、人に不審を起こさせまいと奥のほうに向いていた。尼君が、 |
to ihu wo kiku ni, ikadeka ahare nara zara m. "Hito ya ayasi to mi m." to tutumasiu te, oku ni mukahi te wi tamahe ri. Ama-Gimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.11 | 「 かの聖の親王の御女は、二人と聞きしを、兵部卿宮の北の方は、いづれぞ」 |
「あの聖の親王の姫君は、お二方と聞いていたが、兵部卿宮の北の方は、どちらですか」 |
「あの |
"Kano Hiziri-no-Miko no ohom-Musume ha, hutari to kiki si wo, Hyaubukyau-no-Miya no Kitanokata ha, idure zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.12 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
と問うた。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.13 | 「 この大将殿の御後のは、劣り腹なるべし。ことことしうももてなしたまはざりけるを、いみじう悲しびたまふなり。 初めのはた、いみじかりき。ほとほと出家もしたまひつべかりきかし」 |
「この大将殿の二人目の方は、妾腹なのでしょう。特に表立った扱いをしなかったのですが、ひどくお悲しみになっているのです。最初の方は、また大変なお悲しみようでした。もう少しのところで出家なさってしまいそうなところでした」 |
「大将さんのあとのほうの御愛人は八の宮の庶子でいらっしゃったのでしょう。正当な奥様という待遇はしておいでにならなかったのですが、今では非常に悲しがっておいでになります。初めの方にお別れになった時もたいへんで、もう少しで出家もされるところでした」 |
"Kono Daisyau-dono no ohom-noti no ha, otori-bara naru besi. Koto-kotosiu mo motenasi tamaha zari keru wo, imiziu kanasibi tamahu nari. Hazime no hata, imizikari ki. Hoto-hoto syukke mo si tamahi tu bekari ki kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.14 | など語る。 |
などと話す。 |
こんなことも語っている。 |
nado kataru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 第三段 浮舟、薫の噂など漏れ聞く |
6-3 Ukifune hears a rumour about Kaoru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.1 | 「 かのわたりの親しき人なりけり」と見るにも、 さすが恐ろし。 |
「あの方の親しい人であった」と見るにつけても、やはり恐ろしい。 |
大将の家来の一人であるらしいと思うと、さすがに恐ろしく思われる姫君であった。 |
"Kano watari no sitasiki hito nari keri." to miru ni mo, sasuga osorosi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.2 | 「 あやしく、やうのものと、かしこにてしも亡せたまひけること。 昨日も、いと不便にはべりしかな。川近き所にて、水をのぞきたまひて、いみじう泣きたまひき。 上にのぼりたまひて、柱に書きつけたまひし、 |
「不思議と、二人も同じように、あそこでお亡くなりなったことだ。昨日も、たいそうおいたわしゅうございました。宇治川に近い所で、川の水を覗き込みなさって、ひどくお泣きになった。上の部屋にお上りになって、柱にお書きつけなさった、 |
「しかもお二人とも同じ宇治でお |
"Ayasiku, yau no mono to, kasiko nite simo use tamahi keru koto. Kinohu mo, ito hubin ni haberi si kana! Kaha tikaki tokoro nite, midu wo nozoki tamahi te, imiziu naki tamahi ki. Uhe ni nobori tamahi te, hasira ni kaki-tuke tamahi si, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.3 | 見し人は影も止まらぬ水の上に |
あの人は跡形もとどめず、身を投げたその川の面に |
見し人は影もとまらぬ水の上に |
Mi si hito ha kage mo tomara nu midu no uhe ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.4 | 落ち添ふ涙いとどせきあへず |
いっしょに落ちるわたしの涙がますます止めがたいことよ |
落ち添ふ涙いとどせきあへず |
oti-sohu namida itodo seki-ahe zu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.5 | となむはべりし。言に表はしてのたまふことは少なけれど、ただ、けしきには、いとあはれなる御さまになむ見えたまひし。 女は、いみじくめでたてまつりぬべくなむ。 若くはべりし時より、優におはしますと見たてまつりしみにしかば、 世の中の一の所も、何とも思ひはべらず、ただ、この殿を頼みきこえてなむ、過ぐしはべりぬる」 |
とございました。言葉に現しておっしゃることは少ないが、ただ、態度には、まことにおいたわしいご様子にお見えでした。女は、たいそう賞賛するにちがいないほどでした。若うございました時から、ご立派でいらっしゃるとすっかり拝見していましたので、世の中の第一の権力者のところも、何とも思いませんで、ただ、この殿だけを信頼申し上げて、過ごして参りました」 |
というのでした。口にはあまりお出しにならない方ですが、御様子でお悲しいことがよくうかがえるのです。女だったらどんなに心が |
to nam haberi si. Koto ni arahasi te notamahu koto ha sukunakere do, tada, kesiki ni ha, ito ahare naru ohom-sama ni nam miye tamahi si. Womna ha, imiziku mede tatematuri nu beku nam. Wakaku haberi si toki yori, iu ni ohasimasu to mi tatematuri simi ni sika ba, yononaka no iti-no-tokoro mo, nani to mo omohi habera zu, tada, kono Tono wo tanomi kikoye te nam, sugusi haberi nuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.6 | と語るに、「 ことに深き心もなげなるかやうの人だに、御ありさまは見知りにけり」と思ふ。尼君、 |
と話すので、「特別に深い思慮もなさそうなこのような人でさえ、ご様子はお分かりになったのだ」と思う。尼君は、 |
この話を聞いていて、高い見識を備えたというのでもないこうした人さえ |
to kataru ni, "Koto ni hukaki kokoro mo nage naru kayau no hito dani, ohom-arisama ha mi-siri ni keri." to omohu. Ama-Gimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.7 | 「 光君と聞こえけむ故院の御ありさまには、並びたまはじとおぼゆるを、ただ今の世に、この御族ぞめでられたまふなる。右の大殿と」 |
「光る君と申し上げた故院のご様子には、お並びになることはできまいと思われますが、ただ今の世で、この一族が賞賛されているそうですね。右の大殿とはどうですか」 |
「それでも、光源氏と初めはお言われになったお父様の六条院の御容姿にはかなうまいと思うがねえ。まあ何にもせよ現在の世の中でほめたたえられる方というのは六条院の御子孫に限られてますね。まず左大臣」 |
"Hikaru-Kimi to kikoye kem ko-Win no ohom-arisama ni ha, narabi tamaha zi to oboyuru wo, tada ima no yo ni, kono ohom-zou zo mede rare tamahu naru. Migi-no-Ohotono to." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.8 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
to notamahe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.9 | 「 それは、容貌もいとうるはしうけうらに、宿徳にて、際ことなるさまぞしたまへる。兵部卿宮ぞ、いといみじうおはするや。女にて馴れ仕うまつらばや、となむおぼえはべる」 |
「あの方は、器量もまことに凛々しく美しくて、貫祿があって、身分が格別なようでいらっしゃいます。兵部卿宮が、たいそう美しくいらっしゃいますね。女の身として親しくお仕えいたしたい、と思われます」 |
「そうです。御容貌がりっぱでおきれいで、いかにも重臣らしい |
"Sore ha, katati mo ito uruhasiu keura ni, syukutoku ni te, kiha koto naru sama zo si tamahe ru. Hyaubukyau-no-Miya zo, ito imiziu ohasuru ya. Womna nite nare tukau-matura baya, to nam oboye haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.10 | など、 教へたらむやうに言ひ続く。あはれにもをかしくも聞くに、 身の上もこの世のことともおぼえず。とどこほることなく 語りおきて出でぬ。 |
などと、誰かが教えたように言い続ける。感慨深く興味深くも聞くにつけ、わが身の上もこの世のことと思われない。すっかり話しおいて出て行った。 |
などと今の世間を多く知らぬ |
nado, wosihe tara m yau ni ihi-tuduku. Ahare ni mo wokasiku mo kiku ni, minouhe mo konoyo no koto to mo oboye zu. Todokohoru koto naku katari-oki te ide nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | 第四段 浮舟、尼君と語り交す |
6-4 Ukifune talks with Ama-gimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.1 | 「 忘れたまはぬにこそは」とあはれに思ふにも、いとど母君の御心のうち推し量らるれど、なかなか言ふかひなきさまを見え聞こえたてまつらむは、なほつつましくぞありける。 かの人の言ひつけしことどもを、染め急ぐを見るにつけても、あやしうめづらかなる心地すれど、かけても言ひ出でられず。裁ち縫ひなどするを、 |
「お忘れになっていないのだ」としみじみと思うが、ますます母君のご心中が推し量られるが、かえって何とも言いようのない姿をお見せ申し上げるのは、やはりとても気がひけるのであった。あの人が言ったことなど、衣装の染める準備をするのを見るにつけても、不思議な有りえないような気がするが、とても口にはお出しになれない。物を裁ったり縫ったりなどするのを、 |
浮舟の姫君はおかしくも聞き、身にしむ |
"Wasure tamaha nu ni koso ha." to ahare ni omohu ni mo, itodo Haha-Gimi no mi-kokoro no uti osihakara rure do, naka-naka ihukahinaki sama wo miye kikoye tatematura m ha, naho tutumasiku zo ari keru. Kano hito no ihi-tuke si koto-domo wo, some isogu wo miru ni tuke te mo, ayasiu meduraka naru kokti sure do, kakete mo ihi-ide rare zu. Tati nuhi nado suru wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.2 | 「 これ御覧じ入れよ。ものをいとうつくしう ひねらせたまへば」 |
「これを手伝ってください。とても上手に折り曲げなされるから」 |
「これはいかがでございますか。あなた様はきれいに端がお |
"Kore go-ran-zi ire yo. Mono wo ito utukusiu hinera se tamahe ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.3 | とて、小袿の単衣たてまつるを、うたておぼゆれば、「 心地悪し」とて、手も触れず臥したまへり。尼君、急ぐことをうち捨てて、「 いかが思さるる」など思ひ乱れたまふ。紅に桜の織物の袿重ねて、 |
と言って、小袿の単衣をお渡し申すのを、嫌な気がするので、「気分が悪い」と言って、手も触れず横になっていらっしゃった。尼君は、急ぐことを放って、「どのようなお加減か」などと心配なさる。紅に桜の織物の袿を重ねて、 |
と言って |
tote, koutiki no hitohe tatematuru wo, utate oboyure ba, "Kokoti asi." tote, te mo hure zu husi tamahe ri. Ama-Gimi, isogu koto wo uti-sute te, "Ikaga obosa ruru?" nado omohi midare tamahu. Kurenawi ni sakura no orimono no utiki kasane te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.4 | 「 御前には、かかるをこそ奉らすべけれ。あさましき墨染なりや」 |
「御前様には、このような物をお召しになるのがよいでしょうに。あさましい墨染ですこと」 |
「姫君にはこんなのをお着せしたいのに、情けない墨染めの姿におなりになって」 |
"O-mahe ni ha, kakaru wo koso tatematurasu bekere. Asamasiki sumi-zome nari ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.5 | と言ふ人あり。 |
と言う女房もいる。 |
と言う女房があった。 |
to ihu hito ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.6 | 「 尼衣変はれる身にやありし世の |
「尼衣に変わった身の上で、昔の形見として |
あま衣変はれる身にやありし世の |
"Ama-goromo kahare ru mi ni ya ari-si-yo no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.7 | 形見に袖をかけて偲ばむ」 |
この華やかな衣装を身につけて、今さら昔を偲ぼうか」 |
かたみの |
katami ni sode wo kake te sinoba m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.8 | と書きて、「 いとほしく、亡くもなりなむ後に、物の 隠れなき世なりければ、聞きあはせなどして、 疎ましきまでに隠しける、とや思はむ」など、さまざま思ひつつ、 |
と書いて、「お気の毒に、亡くなった後に、隠し通すこともできない世の中なので、聞き合わせたりなどして、疎ましいまでに隠していた、と思うだろうか」などと、いろいろと思いながら、 |
と浮舟の姫君は書き、行くえの知れぬことになって人々を悲しませた自分の噂はいつか伝わって来ることであろうから、真実のことを尼君のさとる日になって、憎いほどにも隠し続けたと自分を思うかもしれぬと知った心から、 |
to kaki te, "Itohosiku, naku mo nari na m noti ni, mono no kakure naki yo nari kere ba, kiki-ahase nado si te, utomasiki made ni kakusi keru, to ya omoha m?" nado, sama-zama omohi tutu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.9 | 「 過ぎにし方のことは、絶えて忘れはべりにしを、かやうなることを思し急ぐにつけてこそ、 ほのかにあはれなれ」 |
「過ぎ去ったことは、すっかり忘れてしまいましたので、このようなことをお急ぎになることにつけ、何かしらしみじみと感じられるのです」 |
「昔のことは皆忘れていましたけれども、こうしたお仕立て物などをなさいますのを見ますとなんだか悲しい気になるのですよ」 |
"Sugi ni si kata no koto ha, taye te wasure haberi ni si wo, kayau naru koto wo obosi isogu ni tuke te koso, honoka ni ahare nare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.10 | と おほどかにのたまふ。 |
とおっとりとおっしゃる。 |
とおおように尼君へ言った。 |
to ohodoka ni notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.11 | 「 さりとも、思し出づることは多からむを、尽きせず 隔てたまふこそ心憂けれ。身には、かかる世の常の色あひなど、久しく忘れにければ、なほなほしくはべるにつけても、 昔の人あらましかば、など思ひ出ではべる。 しか扱ひきこえたまひけむ人、世におはすらむ。やがて、 亡くなして見はべりしだに、なほいづこにあらむ、そことだに尋ね聞かまほしくおぼえはべるを、 行方知らで、 思ひきこえたまふ人びとはべるらむかし」 |
「そうはおっしゃっても、お思い出しになることは多くありましょうが、いつまでもお隠しになっているのが情けないですわ。わたしは、このような世俗の人の着る色合いなどは、長いこと忘れてしまったので、平凡にしかできませんので、亡くなった娘が生きていたら、などと思い出されます。そのようにお世話申し上げなさった母君は、この世においでですか。そのまま、娘を亡くした母でさえ、やはりどこかに生きていようか、その居場所だけでも尋ね聞きたく思われますのに、その行く方も分からず、ご心配申し上げていらっしゃる方々がございましょう」 |
「どんなになっておいでになっても、昔のことはいろいろ恋しくお思い出しになるに違いないのに、今になってもそうした話を聞かせてくださらないのが恨めしくてなりませんよ。この |
"Saritomo, obosi-iduru koto ha ohokara m wo, tuki se zu hedate tamahu koso kokoro-ukere. Mi ni ha, kakaru yo no tune no iro-ahi nado, hisasiku wasure ni kere ba, naho-nahosiku haberu ni tuke te mo, mukasi no hito ara masika ba, nado omohi-ide haberu. Sika atukahi kikoye tamahi kem hito, yo ni ohasu ram. Yagate, naku nasi te mi haberi si dani, naho iduko ni ara m, soko to dani tadune kika mahosiku oboye haberu wo, yukuhe sira de, omohi kikoye tamahu hito-bito haberu ram kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.12 | とのたまへば、 |
とおっしゃるので、 |
to notamahe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.13 | 「 見しほどまでは、 一人はものしたまひき。この月ごろ亡せやしたまひぬらむ」 |
「俗世にいた時は、片親ございました。ここ数か月の間にお亡くなりなったかも知れません」 |
「あの時まで両親の一人だけはおりました。あれからのち死んでしまったかもしれません」 |
"Mi si hodo made ha, hitori ha monosi tamahi ki. Kono tuki-goro use ya si tamahi nu ram?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.14 | とて、涙の落つるを紛らはして、 |
と言って、涙が落ちるのを紛らわして、 |
こう言ううちに涙の落ちてくるのを紛らして、浮舟は、 |
tote, namida no oturu wo magirahasi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.15 | 「 なかなか思ひ出づるにつけて、うたてはべればこそ、え聞こえ出でね。隔ては 何ごとにか残し はべらむ」 |
「かえって思い出しますことにつけて、嫌に思われますので、申し上げることができません。隠し事はどうしてございましょうか」 |
「思い出しましてはかえって苦しくばかりなるものですから、お話ができなかったのでございますよ。少しの隔て心もあなたにお持ちしておりません」 |
"Naka-naka omohi-iduru ni tuke te, utate habere ba koso, e kikoye ide ne. Hedate ha nani-goto ni ka nokosi habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4.16 | と、言少なにのたまひなしつ。 |
と、言葉少なにおっしゃった。 |
と簡単に言うのであった。 |
to, koto-zukuna ni notamahi nasi tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | 第五段 薫、明石中宮のもとに参上 |
6-5 Kaoru goes to the Imperial Palace to meet Akashi Empress |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.1 | 大将は、 この果てのわざなどせさせたまひて、「 はかなくて、止みぬるかな」とあはれに思す。 かの常陸の子どもは、かうぶりしたりしは、蔵人になして、 わが御司の将監になしなど、労りたまひけり。「童なるが、中にきよげなるをば、近く使ひ馴らさむ」とぞ思したりける。 |
大将は、この一周忌の法事なをおさせにになって、「あっけなくて、終わってしまったな」としみじみとお思いになる。あの常陸の子どもは、元服した者は、蔵人にして、ご自分の近衛府の将監に就けたりなど、面倒を見ておやりになった。「童であるが、中に小綺麗なのを、お側近くに召し使おう」とお思いになっていたのであった。 |
薫は一周忌の仏事を営み、はかない結末になったものであると |
Daisyau ha, kono hate no waza nado se sase tamahi te, "Hakanaku te, yami nuru kana!" to ahare ni obosu. Kano Hitati no kodomo ha, kauburi si tari si ha, Kuraudo ni nasi te, waga ohom-tukasa no Zou ni nasi nado, itahari tamahi keri. "Waraha naru ga, naka ni kiyoge naru wo ba, tikaku tukahi narasa m." to zo obosi tari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.2 | 雨など降りてしめやかなる夜、 后の宮に参りたまへり。御前のどやかなる日にて、 御物語など聞こえたまふついでに、 |
雨などが降ってひっそりとした夜に、后の宮に参上なさった。御前はのんびりとした日なので、お話などを申し上げるついでに、 |
雨が降りなどしてしんみりとした夜に大将は |
Ame nado huri te simeyaka naru yoru, Kisai-no-Miya ni mawiri tamahe ri. O-mahe nodoyaka naru hi nite, ohom-monogatari nado kikoye tamahu tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.3 | 「 あやしき山里に、年ごろまかり通ひ見たまへしを、 人の誹りはべりしも、 さるべきにこそはあらめ。誰れも心の寄る方のことは、さなむある、と思ひたまへなしつつ、なほ時々見たまへしを、 所のさがにやと、心憂く思ひたまへなりにし後は、道も遥けき心地しはべりて、久しうものしはべらぬを、先つころ、もののたよりにまかりて、 はかなき世のありさまとり重ねて思ひたまへしに、ことさら道心起こすべく造りおきたりける、 聖の住処となむおぼえはべりし」 |
「辺鄙な山里に、何年も通っておりましたところ、人の非難もございましたが、そのようになるはずの運命であったのでしょう。誰でも気に入った向きのことは、同じなのだ、と納得させながら、やはり時々逢っておりましたところ、場所柄のせいかと、嫌に思うことがございまして以後は、道のりも遠くに感じられまして、長いこと通わないでいましたが、最近、ある機会に行きまして、はかないこの世の有様を重ね重ね存じられましたので、ことさらにわが道心を起こすために造っておかれた、聖の住処のように思われました」 |
「ずっと引っ込みました山里に、以前から愛していた人を置いてございましたのを、人から何かと言われましたが、前生の因縁でこの人が好きになったのだ、だれも心の |
"Ayasiki yamazato ni, tosi-goro makari kayohi mi tamahe si wo, hito no sosiri haberi si mo, saru-beki ni koso ha ara me. Tare mo kokoro no yoru kata no koto ha, sa nam aru, to omohi tamahe nasi tutu, naho toki-doki mi tamahe si wo, tokoro no saga ni ya to, kokoro-uku omohi tamahe nari ni si noti ha, miti mo harukeki kokoti si haberi te, hisasiu monosi habera nu wo, sai-tu-koro, mono no tayori ni makari te, hakanaki yo no arisama tori-kasane te omohi tamahe si ni, kotosara dausin okosu beku tukuri-oki tari keru, hiziri no sumika to nam oboye haberi si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.4 | と啓したまふに、 かのこと思し出でて、いといとほしければ、 |
と申し上げなさるので、あのことをお思い出しになって、とてもお気の毒なので、 |
薫のこの言葉から中宮は |
to kei-si tamahu ni, kano koto obosi-ide te, ito itohosikere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.5 | 「 そこには、恐ろしき物や住むらむ。いかやうにてか、かの人は亡くなりにし」 |
「そこには、恐ろしいものが住んでいるのでしょうか。どのようにして、その方は亡くなったのですか」 |
「そのお |
"Soko ni ha, osorosiki mono ya sumu ram. Ika yau nite ka, kano hito ha nakunari ni si?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.6 | と問はせたまふを、「 なほ、続きを思し寄る方」と思ひて、 |
とお尋ねあそばすのを、「やはり、引き続いての死去をお考えになってか」と思って、 |
とお尋ねになったのを、二人までも恋人の死んだことを知っておいでになって、幽鬼のせいと思召してのお言葉であろうと大将は解釈した。 |
to toha se tamahu wo, "Naho, tuduki wo obosi yoru kata." to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.7 | 「 さもはべらむ。さやうの人離れたる所は、よからぬものなむかならず住みつきはべるを。 亡せはべりにしさまもなむ、いとあやしくはべる」 |
「そうかも知れません。そのような人里離れた所には、けしからぬものがきっと住みついているのでしょうよ。亡くなった様子も、まことに不思議でございました」 |
「そんなこともございましょう。そうした人けのまれな所には必ず悪いものが来て住みつきますから。それに亡くなりようも普通ではございませんでした」 |
"Samo habera m. Sayau no hito hanare taru tokoro ha, yokara nu mono nam kanarazu sumi-tuki haberu wo. Use haberi ni si sama mo nam, ito ayasiku haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.8 | とて、詳しくは聞こえたまはず。「 なほ、かく忍ぶる筋を、聞きあらはしけり」と 思ひたまはむが、 いとほしく思され、 宮の、ものをのみ思して、そのころは病になりたまひしを、 思し合はするにも、さすがに心苦しうて、「 かたがたに口入れにくき人の上」と思し止めつ。 |
と言って、詳しくは申し上げなさらない。「やはり、このように隠している事柄を、すっかり聞き出してるのだわ」とお思いなさるようなのが、実に気の毒にお思いになり、宮が、物思いに沈んで、その当時病気におなりになったのを、思い合わせなさると、やはり何といっても心が痛んで、「どちらの立場からも口出しにくい方の話だ」とおやめになった。 |
薫はくわしく申し上げることはしなかった。こうして隠そうとしている話に触れてゆくのはよろしくないし、事実を自分に知られたと思うのはいたましいと思召されて、兵部卿の宮が |
tote, kuhasiku ha kikoye tamaha zu. "Naho, kaku sinoburu sudi wo, kiki arahasi keri." to omohi tamaha m ga, itohosiku obosa re, Miya no, mono wo nomi obosi te, sono-koro ha yamahi ni nari tamahi si wo, obosi-ahasuru ni mo, sasuga ni kokoro-gurusiu te, "Kata-gata ni kuti-ire nikuki hito no uhe." to obosi todome tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.9 | 小宰相に、忍びて、 |
小宰相に、こっそりと、 |
中宮は小宰相にそっと、 |
Ko-Zaisyau ni, sinobi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.10 | 「 大将、かの人のことを、いとあはれと思ひてのたまひしに、いとほしうて、うち出でつべかりしかど、それにもあらざらむものゆゑと、つつましうてなむ。君ぞ、ことごと聞き合はせける。 かたはならむことはとり隠して、さることなむありけると、おほかたの物語のついでに、僧都の言ひしことを語れ」 |
「大将は、あの人のことを、とてもしみじみと思ってお話になったが、お気の毒で、打ち明けてしまいそうだったが、その人かどうかも分からないからと、気がひけてね。あなたは、あれこれ聞いていたわね。不都合と思われるようなことは隠して、こういうことがあったと、世間話のついでに、僧都が言ったことを話しなさい」 |
「大将があの人のことを今も恋しいふうに話したからかわいそうで、私はあの話をしてしまうところだったけれど、確かにそれときめても言えないことでもあったから、気がひけて言うことができなかった。あなたは僧都にいろいろ質問もして聞いていたのだから、恥に感じさせるようなことは言わずに、こんなことがあったとほかの話のついでに僧都の言ったことを話してあげなさいね」 |
"Daisyau, kano hito no koto wo, ito ahare to omohi te notamahi si ni, itohosiu te, uti-ide tu bekari sika do, sore ni mo ara zara m mono yuwe to, tutumasiu te nam. Kimi zo, koto-goto kiki-ahase keru. Kataha nara m koto ha tori-kakusi te, saru koto nam ari keru to, ohokata no monogatari no tuide ni, Soudu no ihi si koto wo katare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.11 | とのたまはす。 |
と仰せになる。 |
とお言いになった。 |
to notamahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.12 | 「 御前にだにつつませたまはむことを、まして、異人は いかでか」 |
「御前様でさえ遠慮あそばしているようなことを。まして、他人のわたしにはお話しできません」 |
「宮様でさえお言いにくく思召すことを他人の私がそれをお話し申し上げますことは」 |
"O-mahe ni dani tutumase tamaha m koto wo, masite, koto-bito ha ikadeka." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.13 | と聞こえさすれど、 |
申し上げるが、 |
小宰相はこう申すのであったが、 |
to kikoyesasure do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.14 | 「 さまざまなることにこそ。また、まろはいとほしきことぞあるや」 |
「時と場合によります。また、わたしには不都合な事情があるのですよ」 |
「それはまたそれでいいのよ。私にはまた気の毒で言いにくいわけもあってね」 |
"Sama-zama naru koto ni koso. Mata, maro ha itohosiki koto zo aru ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.15 | とのたまはするも、心得て、をかしと見たてまつる。 |
と仰せになるが、真意を理解して、素晴らしい心遣いだと拝する。 |
これは兵部卿の宮がかかわりを持っておいでになるために仰せられるのであろうと小宰相はさとった。 |
to notamahasuru mo, kokoro-e te, wokasi to mi tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | 第六段 小宰相、薫に僧都の話を語る |
6-6 Kozaisho talks to Kaoru what Souzu has talked to Onna-Ichi-no-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.1 | 立ち寄りて物語などしたまふついでに、言ひ出でたり。 珍かにあやしと、いかでか驚かれ たまはざらむ。「 宮の問はせたまひしも、かかることを、ほの思し寄りてなりけり。などか、のたまはせ果つまじき」とつらけれど、 |
立ち寄ってお話などなさるついでに、言い出した。珍しくも不思議なことだと、どうして驚かないことがあろう。「宮がお尋ねあそばしたことも、このようなことを、ちらっとお聞きあそばしてのことだったのだ。どうして、すっかり話してくださらなかったのだろう」とつらい思いがするが、 |
小宰相の |
Tatiyori te monogatari nado si tamahu tuide ni, ihi-ide tari. Meduraka ni ayasi to, ikadeka odoroka re tamaha zara m. "Miya no toha se tamahi si mo, kakaru koto wo, hono-obosi-yori te nari keri. Nadoka, notamahase-hatu maziki." to turakere do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.2 | 「 我もまた初めよりありしさまのこと 聞こえそめざりしかば、聞きて後も、なほをこがましき心地して、 人にすべて漏らさぬを、なかなか他には聞こゆることもあらむかし。うつつの人びとのなかに忍ぶることだに、隠れある世の中かは」 |
「自分もまた初めからの様子を申し上げなかったのだから、こうして聞いた後にも、やはり馬鹿らしい気がして、他人には全部話さないのを、かえって他では聞いていることもあろう。現実の人びとの中で隠していることでさえ、隠し通せる世の中だろうか」 |
自身もあの人の死の真相を初めから聞かされなかったために、知ってからも疑いが解けないで人に自殺したなどとは言わなかった。かえって他へは真実のことが |
"Ware mo mata hazime yori ari si sama no koto kikoye some zari sika ba, kiki te noti mo, naho wokogamasiki kokoti si te, hito ni subete morasa nu wo, naka-naka hoka ni ha kikoyuru koto mo ara m kasi. Ututu no hito-bito no naka ni sinoburu koto dani, kakure aru yononaka kaha!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.3 | など思ひ入りて、「 この人にも、さなむありし」など、明かしたまはむことは、なほ口重き心地して、 |
などと考え込んで、「この人にも、これこれであった」などと、打ち明けなさることは、やはり話にくい気がして、 |
と思い続け、小宰相にも自殺する目的のあった人だったとは言いだすことにまだ口重い気がして薫はならない。 |
nado omohi-iri te, "Kono hito ni mo, sa nam ari si." nado, akasi tamaha m koto ha, naho kuti-omoki kokoti si te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.4 | 「 なほ、あやしと思ひし人のことに、似てもありける人のありさまかな。さて、その人は、なほあらむや」 |
「やはり、不思議に思った女の身の上と、似ていた人の様子ですね。ところで、その人は、今も無事でいますか」 |
「まだ今日さえ不審の晴れない人のことに似た話ですね。それで、その人はまだ生きていますか」 |
"Naho, ayasi to omohi si hito no koto ni, ni te mo ari keru hito no arisama kana! Sate, sono hito ha, naho ara m ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.5 | とのたまへば、 |
とお尋ねになると、 |
と言うと、 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.6 | 「 かの僧都の山より出でし日なむ、尼になしつる。いみじうわづらひしほどにも、見る人惜しみてせさせざりしを、正身の本意深きよしを言ひてなりぬる、とこそはべるなりしか」 |
「あの僧都が山から下りた日に、尼にしました。ひどく病んでいた時には、世話する人が惜しんでさせなかったが、ご本人が深い念願だと言ってなってしまったのだ、ということでございました」 |
「あの僧都が山から出ました日に尼になすったそうです。重くわずらっています間にも、人が皆惜しんで尼にはさせなかったのでありましたが、その人自身がぜひそうなりたいと言ってなってしまったと僧都はお言いになりました」 |
"Kano Soudu no yama yori ide si hi nam, ama ni nasi turu. Imiziu wadurahi si hodo ni mo, miru hito wosimi te se sase zari si wo, syauzimi no ho'i hukaki yosi wo ihi te nari nuru, to koso haberu nari sika." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.7 | と言ふ。所も変はらず、そのころのありさまと 思ひあはするに、違ふふしなければ、 |
と言う。場所も違わず、その当時のありさまなどを思い合わせると、違うところがないので、 |
小宰相はこう答えた。場所も宇治であり、そのころのことを考えてみれば皆符合することばかりであるために、 |
to ihu. Tokoro mo kahara zu, sono-koro no arisama to omohi-ahasuru ni, tagahu husi nakere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.8 | 「 まことにそれと尋ね出でたらむ、いとあさましき心地もすべきかな。いかでかは、たしかに聞くべき。下り立ちて尋ねありかむも、かたくなしなどや人言ひなさむ。また、 かの宮も聞きつけたまへらむには、かならず思し出でて、 思ひ入りにけむ道も妨げたまひてむかし。 |
「本当にその女だと探し出したら、とても嫌な気がするだろうな。どうしたら、確実なことが聞けようか。自分自身で直接訪ねて行くのも、愚かしいなどと人が言ったりしようか。また、あの宮が聞きつけなさったら、きっと思い出しなさって、決心なさっていた仏道もお妨げなさることであろう。 |
どうすればもっとくわしく聞くことができるであろう、自分自身が一所懸命になってその人を捜し求めるのも、人から単純過ぎた男と見られるであろう。またあの宮のお耳にはいることがあれば必ず捨ててはお置きにならずお近づきになり、いったんはいった仏の |
"Makoto ni sore to tadune-ide tara m, ito asamasiki kokoti mo su beki kana! Ikade-kaha, tasika ni kiku beki. Ori-tati te tadune arika m mo, katakunasi nado ya hito ihi-nasa m. Mata, kano Miya mo kiki-tuke tamahe ra m ni ha, kanarazu obosi-ide te, omohi-iri ni kem miti mo samatage tamahi te m kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.9 | さて、『さなのたまひそ』など 聞こえおきたまひければや、我には、さることなむ聞きしと、さる珍しきことを聞こし召しながら、 のたまはせぬにやありけむ。宮もかかづらひたまふにては、 いみじうあはれと思ひながらも、さらに、やがて亡せにしものと思ひなしてを止みなむ。 |
そのようなわけで、『そのようなことをおっしゃるな』などと、申し上げおきなさったせいであろうか、わたしには、そのようなことを聞いたと、そのような珍しいことをお聞きあそばしながら、仰せにならなかったのであろうか。宮も関係なさっていては、せつなくいとしいと思いながらも、きっぱりと、そのまま亡くなってしまったものと思い諦めよう。 |
もうすでに宮は知っておいでになって、その話を大将へくわしくはあそばさぬようにと頼んでお置きになったために、こうした珍しい話がお耳にはいっていながら、御自身では中宮が言ってくださらなかったのかもしれぬ。宮がまだあの関係を続けようとしておいでになるのであれば、どんなにあの人を愛していても、自分はもうあの時のまま死んだ人と思うことにしてしまおう、 |
Sate, 'Sa na notamahi so.' nado kikoye-oki tamahi kere ba ya, ware ni ha, saru koto nam kiki si to, saru medurasiki koto wo kikosimesi nagara, notamaha se nu ni ya ari kem. Miya mo kakadurahi tamahu nite ha, imiziu ahare to omohi nagara mo, sarani, yagate use ni si mono to omohi-nasi te wo yami na m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.10 | うつし人になりて、 末の世には、 黄なる泉のほとりばかりを、おのづから語らひ寄る風の紛れもありなむ。我がものに取り返し見むの心地、また使はじ」 |
この世の人として立ち戻ったならば、いつの日にか、黄泉のほとりの話を、自然と話し合える時もきっとあろう。自分の女として取り戻して世話するような考えは、二度と持つまい」 |
生死の線が隔てた二人と思い、いつかは黄色の泉のほとりで風の吹き寄せるままに逢いうることがあるかもしれぬのを待とう、愛人として取り返すために心をつかうことはしないほうがよかろう |
Utusi-bito ni nari te, suwe no yo ni ha, ki naru idumi no hotori bakari wo, onodukara katarahi yoru kaze no magire mo ari na m. Waga mono ni tori-kahesi mi m no kokoti, mata tukaha zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6.11 | など思ひ乱れて、「 なほ、のたまはずやあらむ」とおぼゆれど、御けしきのゆかしければ、 大宮に、さるべきついで作り出だしてぞ、啓したまふ。 |
などと思い乱れて、「やはり、仰せにならないだろう」という気はするが、ご様子が気にかかるので、大宮に、適当な機会を作り出して、申し上げなさる。 |
などと |
nado omohi-midare te, "Naho, notamaha zu ya ara m?" to oboyure do, mi-kesiki no yukasikere ba, Oho-Miya ni, saru-beki tuide tukuri-idasi te zo, kei-si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 | 第七段 薫、明石中宮に対面し、横川に赴く |
6-7 Kaoru meets to Akashi Empress and goes to Yokawa to meet Souzu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.1 | 「 あさましうて、失ひはべりぬと思ひたまへし人、世に落ちあふれてあるやうに、人のまねびはべりしかな。いかでか、さることははべらむ、と思ひたまふれど、 心とおどろおどろしう、 もて離るることははべらずや、と思ひわたりはべる人のありさまにはべれば、人の語りはべしやうにては、 さるやうもやはべらむと、似つかはしく思ひたまへらるる」 |
「思いがけないことで、亡くなってしまったと存じておりました女が、この世に落ちぶれて生きているように、人が話してくれました。どうして、そのようなことがございましょうか、と存じますが、自分から大胆なことをして、離れて行くようなことはしないであろうか、とずっと思い続けていた女の様子でございますので、人の話してくれたような事情では、そのようなこともございましょうかと、似ているように存じられました」 |
「突然死なせてしまったと私の思っていました人が |
"Asamasiu te, usinahi haberi nu to omohi tamahe si hito, yo ni oti-ahure te aru yau ni, hito no manebi haberi si kana! Ikadeka, saru koto ha habera m, to omohi tamahure do, kokoro to odoro-odorosiu, mote hanaruru koto ha habera zu ya, to omohi watari haberu hito no arisama ni habere ba, hito no katari haberi si yau nite ha, saru yau mo habera m to, nitukahasiku omohi tamahe raruru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.2 | とて、今すこし聞こえ出でたまふ。 宮の御ことを、 いと恥づかしげに、さすがに恨みたるさまには言ひなしたまはで、 |
と言って、もう少し申し上げなさる。宮のお身の上の事を、とても憚りあるように、そうはいっても恨んでいるようにはおっしゃらないで、 |
と言い、その話を以前よりも細かに申し上げ、 |
tote, ima sukosi kikoye-ide tamahu. Miya no ohom-koto wo, ito hadukasige ni, sasuga ni urami taru sama ni ha ihi-nasi tamaha de, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.3 | 「 かのこと、また さなむと 聞きつけたまへらば、かたくなに好き好きしうも思されぬべし。さらに、 さてありけりとも、知らず顔にて過ぐしはべりなむ ★」 |
「あのことを、またこれこれとお耳になさいましたら、頑固で好色なようにお思いなさるでしょう。まったく、そうして生きていたとしても、知らない顔をして過ごしましょう」 |
「拾われて生きていますことがあの方のお耳にはいっているのでございましたら、私が女を疑って見る能力の欠けた愚か者に見えることでございますから、なお生きているとも知らぬふうにしてそのまま置こうかとも思います」 |
"Kano koto, mata sa nam to kiki-tuke tamahe ra ba, katakuna ni suki-zukisiu mo obosa re nu besi. Sarani, sate ari keri to mo, sira-zu-gaho nite sugusi haberi na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.4 | と啓したまへば、 |
と申し上げなさると、 |
と申すのであった。 |
to kei-si tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.5 | 「 僧都の語りしに、いともの恐ろしかりし夜のことにて、耳も止めざりしことにこそ。 宮は、いかでか聞きたまはむ。 聞こえむ方なかりける御心のほどかな、と聞けば、まして 聞きつけたまはむこそ、いと苦しかるべけれ。かかる筋につけて、いと軽く憂きものにのみ、世に知られたまひぬめれば、心憂く」 |
「僧都が話したことですが、とても気味の悪かった夜のことで、耳も止めなかったことなのです。宮は、どうしてご存知でしょう。何とも申し上げようのないご料簡だ、と思いますので、ましてその話をお聞きつけなさるのは、まことに困ったことです。このようなことにつけて、まことに軽々しく困った方だとばかり、世間にお知られになっているようなので、情けなく思っています」 |
「僧都が宇治の話をした晩はね、こわいような気のする晩でしたからね、くわしくは聞かなかったあのことですね。兵部卿の宮が知っておいでになるはずは絶対にありません。何とも批評のしようのない性質だと私もよく歎息させられる方なのだから、ましてその話を聞かせてはめんどうをお起こしになるでしょう。恋愛問題では軽薄な多情男だとばかり言われておいでになる方だから、私は悲しんでいます」 |
"Soudu no katari si ni, ito mono-osorosikari si yo no koto nite, mimi mo todome zari si koto ni koso. Miya ha, ikadeka kiki tamaha m. Kikoye m kata nakari keru mi-kokoro no hodo kana, to kike ba, masite kiki-tuke tamaha m koso, ito kurusikaru bekere. Kakaru sudi ni tuke te, ito karoku uki mono ni nomi, yo ni sira re tamahi nu mere ba, kokoro-uku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.6 | などのたまはす。「 いと重き御心なれば、かならずしも、うちとけ世語りにても、人の忍びて啓しけむことを、漏らさせたまはじ」など思す。 |
などと仰せになる。「とても慎重なお人柄なので、必ずしも、気安い世間話であっても、誰かがこっそりと申し上げたことを、お漏らしあそばすまい」などとお思いになる。 |
中宮はこう仰せになった。 |
nado notamahasu. "Ito omoki mi-kokoro nare ba, kanarazu-simo, utitoke yogatari nite mo, hito no sinobi te kei-si kem koto wo, mora sase tamaha zi." nado obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.7 | 「 住むらむ山里はいづこにかはあらむ。いかにして、さま悪しからず尋ね寄らむ。僧都に会ひてこそは、たしかなるありさまも聞き合はせなどして、ともかくも問ふべかめれ」など、ただ、このことを起き臥し思す。 |
「その住んでいるという山里はどの辺であろうか。どのようにして、体裁悪くなく探し出せようか。僧都に会って、確かな様子を聞き合わせたりして、ともかく訪ねるのがよかろう」などと、ただ、このことばかりを寝ても覚めてもお考えになる。 |
住んでいる家は小野のどこにあるのであろう。どんなふうに世間体を作ってあの人にまた逢おう、何よりも僧都にまず逢ってみてくわしいことをともかくも知っておく必要があると薫は明け暮れこのことをばかり思い悩んだ。 |
"Sumu ram yamazato ha iduko ni kaha ara m? Ikani si te, sama asikara zu tadune-yora m. Soudu ni ahi te koso ha, tasika naru arisama mo kiki-ahase nado si te, tomo-kakumo tohu beka' mere." nado, tada, kono koto wo oki-husi obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7.8 | 月ごとの八日は ★、かならず尊きわざせさせたまへば、薬師仏に寄せたてまつるにもてなしたまへるたよりに、 中堂には、時々参りたまひけり。それよりやがて横川におはせむと思して、 かのせうとの童なる、率ておはす。「 その人びとには、とみに知らせじ。ありさまにぞ従はむ」と思せど、 うち見む夢の心地にも、あはれをも加へむとにやありけむ。さすがに、「 その人とは見つけながら、あやしきさまに、 形異なる人の中にて、 憂きことを聞きつけたらむこそ、いみじかるべけれ」と、 よろづに道すがら思し乱れけるにや。 |
毎月の八日は、必ず仏事をおさせになるので、薬師仏にご寄進申し上げなさろうとお出かけになるついでに、根本中堂には、時々お参りになった。そこからそのまま横川においでになろうとお考えになって、あの弟の童である者を、連れておいでになる。「その人たちには、すぐには知らせまい。その時の状況を見てからにしよう」とお思いになるが、再会した時の夢のような心地の上につけて、しみじみとした感慨を加えようというつもりであったのだろうか。そうはいっても、「その人だと分かったものの、みすぼらしい姿で、尼姿の人たちの中に暮らしていて、嫌なことを耳にしたりするのは、ひどくつらいことであろう」と、いろいろと道すがら思い乱れなさったことだろうか。 |
毎月八の日には必ず何かの仏事を行なう習慣になっていて、薬師仏の供養をその時にすることもあるので |
Tuki-goto no yau-ka ha, kanarazu tahutoki waza se sase tamahe ba, Yakusi-Butu ni yose tatematuru ni motenasi tamahe ru tayori ni, Tyuudau ni ha, toki-doki mawiri tamahi keri. Sore yori yagate Yokaha ni ohase m to obosi te, kano seuto no waraha naru, wi te ohasu. "Sono hito-bito ni ha, tomi ni sirase zi. Arisama ni zo sitagaha m." to obose do, uti-mi m yume no kokoti ni mo, ahare wo mo kuhahe m koto ni ya ari kem. Sasuga ni, "Sono hito to ha mituke nagara, ayasiki sama ni, katati koto naru hito no naka nite, uki koto wo kiki-tuke tara m koso, imizikaru bekere." to, yorodu ni miti-sugara obosi midare keru ni ya? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 5/17/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 5/17/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 5/17/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/17/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経