53 手習(大島本) |
TENARAHI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十七歳三月末頃から二十八歳の夏までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March at the age of 27 to summer at the age of 28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 浮舟の物語 中将、浮舟に和歌を贈る |
3 Tale of Ukifune Chujo composes and sends a waka to Ukifune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 尼君の亡き娘の婿君、山荘を訪問 |
3-1 Chujo who is a husband of nun's daughter comes to Ono villa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 尼君の昔の婿の君、今は中将にてものしたまひける、 弟の禅師の君、僧都の御もとにものしたまひける、山籠もりしたるを訪らひに、 兄弟の君たち常に上りけり。 |
尼君の亡き娘の婿の君で、今は中将におなりになっていたが、その弟の禅師の君は、僧都のお側にいらっしゃったが、その山籠もりなさっているのを尋ねるために、兄弟の公達がよく山に登るのであった。 |
尼君の昔の婿は現在では中将になっていた。弟の禅師が僧都の弟子になって山にこもっているのを |
Ama-Gimi no mukasi no muko no Kimi, ima ha Tyuuzyau nite monosi tamahi keru, otouto no Zenzi-no-Kimi, Soudu no ohom-moto ni monosi tamahi keru, yama-gomori si taru wo toburahi ni, harakara no Kimi-tati tune ni nobori keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 横川に通ふ道のたよりに寄せて、中将 ここにおはしたり。前駆うち追ひて、あてやかなる男の入り来るを 見出だして、 忍びやかにおはせし人の御さまけはひぞ、さやかに思ひ出でらるる。 |
横川に通じる道のついでにかこつけて、中将がここにいらした。前駆が先払いして、身分高そうな男が入ってくるのを見出して、ひっそりとしていらしたあの方のご様子が、くっきりと思い出される。 |
|
Yokaha ni kayohu miti no tayori ni yose te, Tyuuzyau koko ni ohasi tari. Saki uti-ohi te, ateyaka naru wotoko no iri-kuru wo mi-idasi te, sinobiyaka ni ohase si hito no ohom-sama kehahi zo, sahayaka ni omohi-ide raruru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | これもいと心細き住まひのつれづれなれど、住みつきたる人びとは、ものきよげにをかしうしなして、 垣ほに植ゑたる撫子もおもしろく、女郎花、桔梗など咲き始めたるに、色々の狩衣姿の男どもの若きあまたして、 君も同じ装束にて、 南面に呼び据ゑたれば、うち眺めてゐたり。 年二十七、八のほどにて、ねびととのひ、心地なからぬさまもてつけたり。 |
ここもまことに心細い住まいの所在なさであるが、住み馴れた人びとは、どことなくこぎれいに興趣深くして、垣根に植えた撫子が美しく、女郎花や、桔梗などが咲き初めたところに、色とりどりの狩衣姿の男どもの若い人が大勢して、君も同じ装束で、南面に迎えて座らせたので、あたりを眺めていた。年齢は二十七、八歳くらいで、すっかり立派になって、嗜みのなくはない態度が身についていた。 |
心細い家ではあるが住みなれた人は満足して、きれいにあたりが作ってあって、 |
Kore mo ito kokoro-bosoki sumahi no ture-dure nare do, sumi-tuki taru hito-bito ha, mono-kiyoge ni wokasiu si-nasi te, kakiho ni uwe taru nadesiko mo omosiroku, wominahesi, kikyau nado saki hazime taru ni, iro-iro no kariginu-sugata no wonoko-domo no wakaki amata site, Kimi mo onazi syauzoku nite, minami-omote ni yobi-suwe tare ba, uti-nagame te wi tari. Tosi nizihu-siti, hati no hodo nite, nebi totonohi, kokoti-nakara nu sama mote-tuke tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | 尼君、 障子口に几帳立てて、対面したまふ。まづうち泣きて、 |
尼君、襖障子口に几帳を立てて、お会いなさる。何より先に泣き出して、 |
尼君は隣室の |
Ama-Gimi, syauzi-guti ni kityau tate te, taimen si tamahu. Madu uti-naki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | 「 年ごろの積もりには、過ぎにし方 いとど気遠くのみなむはべるを、山里の光になほ待ちきこえさすることの、 うち忘れず止みはべらぬを、かつはあやしく思ひたまふる」 |
「何年にもなりますと、過ぎ去った当時がますます遠くなるばかりでございますが、山里の光栄としてやはりお待ち申し上げております気持ちが、忘れず続いておりますのが、一方では不思議に存じられます」 |
「過ぎた月日の長くなりましたことで、あの時代といいますものが遠い世のような気がいたされながら、おいでくださいますのを山里に添えられる光明のように思われまして、今でもあなたをお待ちすることが心から離れませんのを不思議に思っております」 |
"Tosi-goro no tumori ni ha, sugi ni si kata itodo kedohoku nomi nam haberu wo, yamazato no hikari ni naho mati kikoye sasuru koto no, uti-wasure zu yami habera nu wo, katu ha ayasiku omohi tamahuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
と言うのを聞いて、中将は湿った気持ちになり、 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.7 | 「 心のうちあはれに、過ぎにし方のことども、思ひたまへられぬ折なきを、あながちに住み離れ顔なる御ありさまに、おこたりつつなむ。 山籠もりもうらやましう、常に出で立ちはべるを、同じくはなど、慕ひまとはさるる人びとに、妨げらるるやうにはべりてなむ。今日は、皆はぶき捨ててものしたまへる」 |
「心の中ではしみじみと、過ぎ去った当時のことが、思い出されないことはないが、ひたすら俗世を離れたご生活なので、ついご遠慮申し上げまして。山籠もり生活も羨ましく、よく出かけてきますので、同じことならなどと、同行したがる人びとに、邪魔されるような恰好でおりました。今日は、すっかり断って参りました」 |
「昔のことの思われない時もないのですが、世の中から離脱したことを |
"Kokoro no uti ahare ni, sugi ni si kata no koto-domo, omohi tamahe rare nu wori naki wo, anagati ni sumi-hanare gaho naru ohom-arisama ni, okotari tutu nam. Yama-gomori mo urayamasiu, tune ni ide-tati haberu wo, onaziku ha nado, sitahi matohasa ruru hito-bito ni, samatage raruru yau ni haberi te nam. Kehu ha, mina habuki sute te monosi tamahe ru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.8 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
と言っていた。 |
to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.9 | 「 山籠もりの御うらやみは、なかなか 今様だちたる御ものまねびになむ。 昔を思し忘れぬ御心ばへも、世に靡かせたまはざりけると、おろかならず思ひたまへらるる折多く」 |
「山籠もり生活のご羨望は、かえって当世風の物真似のようです。故人をお忘れにならないお気持ちも、世間の風潮にお染まりにならなかったと、一方ならず厚く存じられます折がたびたびです」 |
「山ごもりをおうらみになったりしては、かえって近ごろの流行かぶれに思われますよ。昔をお忘れにならないお志は現代の風潮と変わったありがたいことと、お |
"Yama-gomori no ohom-urami ha, naka-naka imayou-dati taru ohom-mono-manebi ni nam. Mukasi wo obosi wasure nu mi-kokorobahe mo, yo ni nabika se tamaha zari keru to, oroka nara zu omohi tamahe raruru wori ohoku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.10 | など言ふ。 |
などと言う。 |
などと言うのは尼君であった。 |
nado ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 浮舟の思い |
3-2 Ukifune thinks her life |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 人びとに水飯などやうの物食はせ、君にも 蓮の実などやうのもの出だしたれば、 馴れにしあたりにて、 さやうのこともつつみなき心地して、 村雨の降り出づるに止められて、物語 しめやかにしたまふ。 |
供の人びとに水飯などのような物を食べさせ、君にも蓮の実などのような物を出したので、昵懇の所なので、そのようなことにも遠慮のいらない気がして、村雨が降り出したのに引き止められて、お話をひっそりとなさる。 |
ついて来た人々に |
Hito-bito ni suihan nado yau no mono kuha se, Kimi ni mo hatisu no mi nado yau no mono idasi tare ba, nare ni si atari nite, sayau no koto mo tutumi naki kokoti si te, murasame no huri-iduru ni tome rare te, monogatari simeyaka ni si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 「 言ふかひなくなりにし人よりも、 この君の御心ばへなどの、いと思ふやうなりしを、よそのものに思ひなしたるなむ、いと悲しき。など、 忘れ形見をだに留めたまはずなりにけむ」 |
「亡くなってしまった娘のことよりも、この婿君のお気持ちなどが、実に申し分なかったので、他人と思うのが、とても悲しい。どうして、せめて子供だけでもお残しにならなかったのだろう」 |
娘を失ったことよりも情のこまやかであったこの婿君を家の人でなくしてしまったことが、より以上尼君に悲痛なことであって、娘はなぜ忘れ形見でも残していかなかったか |
"Ihukahinaku nari ni si hito yori mo, kono Kimi no mi-kokorobahe nado no, ito omohu yau nari si wo, yoso no mono ni omohi-nasi taru nam, ito kanasiki. Nado, wasure-gatami wo dani todome tamaha zu nari ni kem?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | と、恋ひ偲ぶ心なりければ、たまさかにかくものしたまへるにつけても、珍しくあはれにおぼゆべかめる 問はず語りもし出でつべし。 |
と、恋い偲ぶ気持ちなので、たまたまこのようにお越しになったのにつけても、珍しくしみじみと思われるような問わず語りもしてしまいそうである。 |
とそれを歎いている心から、たまさかにこうして中将の訪問を受けるのは非常な |
to, kohi sinobu kokoro nari kere ba, tamasaka ni kaku monosi tamahe ru ni tuke te mo, medurasiku ahare ni oboyu beka' meru toha-zu-gatari mo si-ide tu besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 | 姫君は、 我は我と、思ひ出づる方多くて、眺め出だしたまへるさま、いとうつくし。白き単衣の、いと情けなくあざやぎたるに、袴も桧皮色に ならひたるにや、光も見えず黒きを着せたてまつりたれば、「 かかることどもも、見しには変はりてあやしうもあるかな」と思ひつつ、こはごはしういららぎたるものども着たまへるしも、いとをかしき姿なり。御前なる人びと、 |
姫君は、わたしはわたしと、思い出されることが多くて、外を眺めていらっしゃる様子、とても美しい。白い単衣で、とても風情もなくさっぱりとしたものに、袴も桧皮色に見倣ったのか、色艶も見えない黒いのをお着せ申していたので、「このようなことなども、昔と違って不思議なことだ」と思いながらも、ごわごわとした肌触りのよくないのを何枚も着重ねていらっしゃるのが、実に風情ある姿なのである。御前の女房たちも、 |
浮舟の姫君は昔について尼君とは異なった悲しみを多く覚え、庭のほうをながめ入っている顔が非常に美しい。同じ白といってもただ白い一方でしかない、目に情けなく見える |
Hime-Gimi ha, ware ha ware to, omohi-iduru kata ohoku te, nagame idasi tamahe ru sama, ito utukusi. Siroki hitohe no, ito nasakenaku azayagi taru ni, hakama mo hihada-iro ni narahi taru ni ya, hikari mo miye zu kuroki wo kise tatematuri tare ba, "Kakaru koto-domo mo, mi si ni ha kahari te ayasiu mo aru kana!" to omohi tutu, koha-gohasiu iraragi taru mono-domo ki tamahe ru simo, ito wokasiki sugata nari. O-mahe naru hito-bito, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.5 | 「 故姫君のおはしたる心地のみしはべりつるに、中将殿をさへ見たてまつれば、いとあはれにこそ。同じくは、昔のさまにておはしまさせばや。いとよき御あはひならむかし」 |
「亡き姫君が生き返りなさった気ばかりがしますので、中将殿までを拝見すると、とても感慨無量です。同じことなら、昔のようにおいで願いたいものですね。とてもお似合いのご夫婦でしょう」 |
「このごろはお |
"Ko-Hime-Gimi no ohasi taru kokoti nomi si haberi turu ni, Tyuuzyau-dono wo sahe mi tatemature ba, ito ahare ni koso. Onaziku ha, mukasi no sama nite ohasimasa se baya! Ito yoki ohom-ahahi nara m kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.6 | と言ひ合へるを、 |
と話し合っているのを、 |
こんなことを言っているのも浮舟の耳にはいった。 |
to ihi-ahe ru wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.7 | 「 あな、いみじや。世にありて、いかにもいかにも、 人に見えむこそ。それにつけてぞ昔のこと思ひ出でらるべき。さやうの筋は、思ひ絶えて忘れなむ」と思ふ。 |
「まあ、大変な。生き残って、どのようなことがあっても、男性と結婚するようなことは。それにつけても昔のことが思い出されよう。そのようなことは、すっかり断ち切って忘れよう」と思う。 |
思いも寄らぬことである、普通の女の生活に帰って、どんな人とにもせよ結婚をすることなどはしようと思わない、それによって自分はただ昔を思うばかりの人になるであろうから、もうそうした身の上には絶対になるまい、そして昔を忘れたいと浮舟の姫君は思った。 |
"Ana, imizi ya! Yo ni ari te, ikanimo-ikanimo, hito ni miye m koso. Sore ni tuke te zo mukasi no koto omohi-ide raru beki. Sayau no sudi ha, omohi taye te wasure na m." to omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 中将、浮舟を垣間見る |
3-3 Chujo peeps Ukifune's back figure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 尼君入りたまへる間に、 客人、雨のけしきを見わづらひて、 少将と言ひし人の 声を聞き知りて、呼び寄せたまへり。 |
尼君が奥にお入りになる間に、客人は、雨の様子に困って、少将といった女房の声を聞き知って、呼び寄せなさった。 |
尼君が内へ引っ込んだあとで、中将は降りやまぬ雨をながめることに退屈を覚え、少将といった人の声に聞き覚えがあってそばへ呼び寄せた。 |
Ama-Gimi iri tamahe ru ma ni, Marauto, ame no kesiki wo mi wadurahi te, Seusyau to ihi si hito no kowe wo kiki-siri te, yobi-yose tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 「 昔見し人びとは、皆ここにものせらるらむや、と思ひながらも、かう参り来ることも難くなりにたるを、 心浅きにや、誰れも誰れも見なしたまふらむ」 |
「昔見た女房たちは、みなここにいられようか、と思いながらも、このようにやって参ることも難しくなってしまったのを、薄情なように、皆がお思いになりましょう」 |
「昔のなじみの人たちは今も皆ここにおられるのであろうかと、思ってみる時があっても、こうした御訪問も自然できなくなってしまっている私を、薄情なようにも皆さんは思っておられるでしょう」 |
"Mukasi mi si hito-bito ha, mina koko ni monose raru ram ya, to omohi nagara mo, kau mawiri kuru koto mo kataku nari ni taru wo, kokoro-asaki ni ya, tare mo tare mo mi-nasi tamahu ram." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | などのたまふ。仕うまつり馴れにし人にて、あはれなりし昔のことどもも 思ひ出でたるついでに、 |
などとおっしゃる。親しくお世話してくれた女房なので、恋しかった当時のことが思い出される折に、 |
こんなことを中将は言った。親しく中将にも仕えていた女房であったから、昔の妻についての思い出話をしたあとで、 |
nado notamahu. Tukau-maturi nare ni si hito nite, ahare nari si mukasi no koto-domo mo omohi-ide taru tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | 「 かの廊のつま入りつるほど、風の騒がしかりつる紛れに、簾の隙より、 なべてのさまにはあるまじかりつる人の、うち垂れ髪の見えつるは、世を背きたまへるあたりに、誰れぞとなむ見おどろかれつる」 |
「あの渡廊の端の所で、風が烈しかった騷ぎに、簾の隙間から、並々の器量ではなかった人で、打ち垂れ髪が見えたのは、出家なさった家に、いったい誰なのかと驚かされました」 |
「私がさっき廊の端を通ったころに、風がひどく吹いていて、 |
"Kano rau no tuma iri turu hodo, kaze no sawagasikari turu magire ni, sudare no hima yori, nabete no sama ni ha aru mazikari turu hito no, uti-tare-gami no miye turu ha, yo wo somuki tamahe ru atari ni, tare zo to nam mi odoroka re turu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | とのたまふ。「 姫君の立ち出でたまへるうしろでを、見たまへりけるなめり」と思ひ出でて、「 ましてこまかに見せたらば、心止まりたまひなむかし。 昔人は、いとこよなう 劣りたまへりしをだに、まだ忘れがたくしたまふめるを」と、心一つに思ひて、 |
とおっしゃる。「姫君が立って出て行かれた後ろ姿を、御覧になったようだ」と思って、「これ以上に詳細に見せたら、きっとお心がお止まりになろう。故人は、とても格段に劣っていらっしゃったのさえ、今だに忘れがたく思っていらっしゃるようだから」と、独り決めにして、 |
と中将が言いだした。姫君が立って隣室へお行きになった後ろ姿を見たのであろうと少将は思い、まして細かに見せたなら多大に心の |
to notamahu. "Hime-Gimi no tati-ide tamahe ru usirode wo, mi tamahe ri keru na' meri." to omohi-ide te, "Masite komaka ni mise tara ba, kokoro tomari tamahi na m kasi. Mukasi-bito ha, ito koyonau otori tamahe ri si wo dani, mada wasure gataku si tamahu meru wo." to, kokoro hitotu ni omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 「 過ぎにし御ことを 忘れがたく、慰めかねたまふめりしほどに、 おぼえぬ人を得たてまつりたまひて、明け暮れの見物に思ひきこえたまふめるを、 うちとけたまへる御ありさまを、いかで御覧じつらむ」 |
「亡くなったお方のことを忘れがたく、慰めかねていらっしゃるようだったころ、思いがけない女性をお手に入れ申されて、明け暮れの慰めにお思い申し上げていらっしゃったようですが、寛いでいらっしゃるご様子を、どうして御覧になったのでしょうか」 |
「お |
"Sugi ni si ohom-koto wo wasure-gataku, nagusame-kane tamahu meri si hodo ni, oboye nu hito wo e tatematuri tamahi te, ake-kure no mimono ni omohi kikoye tamahu meru wo, utitoke tamahe ru ohom-arisama wo, ikade go-ran-zi tu ram?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.7 | と言ふ。「 かかることこそはありけれ」とをかしくて、「 何人ならむ。げに、いとをかしかりつ」と、ほのかなりつるを、なかなか思ひ出づ。こまかに問へど、そのままにも言はず、 |
と言う。「このようなことがあるものだ」と興味深くて、「どのような人なのだろう。なるほど、実に美しかった」と、ちらっと垣間見たのを、かえって思い出す。詳しく尋ねるが、すっかりとは答えず、 |
こう語った。そんなおもしろい事実があったのかと興味のわいてきた中将は、どうした家の娘であろう、それとなく今少将が言うとおりに美しい人らしくほのかに見ただけの人からかえって深い印象の与えられたのを中将は感じた。くわしく聞こうとするのであるが、少将は事実をそのまま告げようとはせずに、 |
to ihu. "Kakaru koto koso ha ari kere." to wokasiku te, "Nani-bito nara m? Geni, ito wokasikari tu." to, honoka nari turu wo, naka-naka omohi-idu. Komaka ni tohe do, sono mama ni mo iha zu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8 | 「 おのづから聞こし召してむ」 |
「自然とお分かりになりましょう」 |
「そのうちおわかりになるでしょう」 |
"Onodukara kikosimesi te m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.9 | とのみ言へば、うちつけに問ひ尋ねむも、さま悪しき 心地して、 |
とばかり言うので、急に詮索するのも、体裁の悪い気がして、 |
とだけ言っているのに対して、にわかに質問をしつこくするのも恥ずかしくなり、従者が、 |
to nomi ihe ba, utituke ni tohi tadune m mo, sama asiki kokoti si te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.10 | 「 雨も止みぬ。日も暮れぬべし ★」 |
「雨も止んだ。日も暮れそうだ」 |
「雨もやみました。日が暮れるでしょうから」 |
"Ame mo yami nu. Hi mo kure nu besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.11 | と言ふにそそのかされて、出でたまふ。 |
と言うのに促されて、お帰りになる。 |
と |
to ihu ni sosonokasa re te, ide tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 第四段 中将、横川の僧都と語る |
3-4 Chujo talks with Yokawa-souzu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | 前近き女郎花を折りて、「 ▼ 何匂ふらむ」と口ずさびて、独りごち立てり。 |
お庭先の女郎花を手折って、「どうしてここにいらっしゃるのだろう」と口ずさんで、独り言をいって立っていた。 |
縁側を少し離れた所に咲いた |
Mahe tikaki wominahesi wo wori te, "Nani nihohu ram?" to kuti-zusabi te, hitori-goti tate ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 | 「 人のもの言ひを、さすがに思しとがむるこそ」 |
「人の噂を、さすがに気になさるとは」 |
「人から何とか言われるのをさすがに恐れておいでになるのですね」 |
"Hito no mono-ihi wo, sasuga ni obosi togamuru koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.3 | など、古代の人どもは、ものめでをしあへり。 |
などと、古風な老人たちは、誉めあっていた。 |
などと古めかしい人らはそれをほめていた。 |
nado, kotai no hito-domo ha, mono-mede wo si ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.4 | 「 いときよげに、あらまほしくもねびまさりたまひにけるかな。同じくは、昔のやうにても見たてまつらばや」とて、 |
「とても美しげで、理想的にご成人なさったことよ。同じことなら、昔のようにお世話したいものだ」と思って、 |
「ますますきれいにおなりになってりっぱだね。できることなら昔どおりの間柄になってつきあいたい」と尼君も言っているのであった。 |
"Ito kiyoge ni, aramahosiku mo nebi masari tamahi ni keru kana! Onaziku ha, mukasi no yau nite mo mi tatematura baya!" tote, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.5 | 「 藤中納言の御あたりには、 絶えず通ひたまふやうなれど、心も止めたまはず、親の殿がちになむものしたまふ、とこそ言ふなれ」 |
「藤中納言のお所には、今も通っていらっしゃるようだが、ご執心でもなく、親の邸にいらっしゃりがちだと言っているようだが」 |
「 |
"Tou-Tyuunagon no ohom-atari ni ha, taye zu kayohi tamahu yau nare do, kokoro mo todome tamaha zu, oya no tono-gati ni nam monosi tamahu, to koso ihu nare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.6 | と、尼君ものたまひて、 |
と、尼君もおっしゃって、 |
こんな話も女房相手にしてから、浮舟へ、 |
to, Ama-Gimi mo notamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.7 | 「 心憂く、ものをのみ 思し隔てたるなむ、いとつらき。今は、なほ、 さるべきなめりと思しなして、晴れ晴れしくもてなしたまへ。 この五年、六年、時の間も忘れず、 恋しく悲しと思ひつる人の上も、 かく見たてまつりて後よりは、こよなく思ひ忘られにてはべる。 思ひきこえたまふべき人びと世におはすとも、今は世に亡きものにこそ、やうやう思しなりぬらめ。よろづのこと、さし当たりたるやうには、えしもあらぬわざになむ」 |
「情けなく、よそよそしくしてばかりいらっしゃるのが、とてもつらい。今はもう、やはり、これも宿縁だとお思いになって、気を晴れやかになさってください。この五年、六年、束の間も忘れず、恋しく悲しいと思っていた娘のことも、こうしてお目にかかって後は、すっかり悲しみも忘れております。ご心配申し上げなさる方々がいらっしゃっても、今はもう亡くなったのだと、だんだんお諦めになりましょう。どのような事でも、その当座のようには、必ずしも思わないものです」 |
「あなたはまだ私に隔て心を持っておいでになるのが恨めしくてなりませんよ。もう何事も宿命によるのだとあきらめておしまいになって、晴れ晴れしくなってくださいよ。この五、六年片時も忘れることができなくて悲しい悲しいと思っていた人のことも、あなたという方をそばで見るようになってからは忘れてしまいましたよ私は。あなたをお愛しになった方がたがこの世においでになっても、もうあなたはお |
"Kokoro-uku, mono wo nomi obosi hedate taru nam, ito turaki. Ima ha, naho, saru-beki na' meri to obosi nasi te, hare-baresiku motenasi tamahe. Kono itu-tose, mu-tose, toki no ma mo wasure zu, kohisiku kanasi to omohi turu hito no uhe mo, kaku mi tatematuri te noti yori ha, koyonaku omohi wasura re nite haberu. Omohi kikoye tamahu beki hito-bito yo ni ohasu tomo, ima ha yo ni naki mono ni koso, yau-yau obosi nari nu rame. Yorodu no koto, sasi-atari taru yau ni ha, e simo ara nu waza ni na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.8 | と 言ふにつけても、 いとど涙ぐみて、 |
と言うにつけても、ますます涙ぐんで、 |
と言うのを聞くうちにも姫君は涙ぐまれてくるのであった。 |
to ihu ni tuke te mo, itodo namida-gumi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.9 | 「 隔てきこゆる心は、はべらねど、あやしくて生き返りけるほどに、よろづのこと夢の世にたどられて。あらぬ世に生れたらむ人は、かかる心地やすらむ、とおぼえはべれば、今は、知るべき人世にあらむとも思ひ出でず。ひたみちにこそ、 睦ましく思ひきこゆれ」 |
「よそよそしくお思い申し上げる気持ちは、ございませんが、不思議に生き返ったうちに、すべての事が夢のようにはっきり分からなくなりまして。違った世界に生まれた人は、このような気がするものだろうか、と思われておりますので、今は、知っている人がこの世に生きていようとも思い出されません。ひたすらに、慕わしく存じ上げております」 |
「私は何も隔てをお置きする気などはないのですけれども、不思議な |
"Hedate kikoyuru kokoro ha, habera ne do, ayasiku te iki-kaheri keru hodo ni, yorodu no koto yume no yo ni tadorare te. Ara nu yo ni mumare tara m hito ha, kakaru kokoti ya su ram, to oboye habere ba, ima ha, siru beki hito yo ni ara m to mo omohi-ide zu. Hitamiti ni koso, mutumasiku omohi kikoyure." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.10 | とのたまふさまも、げに、何心なくうつくしく、うち笑みてぞまもりゐたまへる。 |
とおっしゃる様子も、なるほど、無心でかわいらしく、にっこりとして見つめていらっしゃった。 |
と言う |
to notamahu sama mo, geni, nani-gokoro naku utukusiku, uti-wemi te zo mamori wi tamahe ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.11 | 中将は、山におはし着きて、僧都も珍しがりて、世の中の物語したまふ。 その夜は泊りて、声尊き人に 経など読ませて、夜一夜、遊びたまふ。禅師の君、こまかなる物語などするついでに、 |
中将は、山にお着きになって、僧都も珍しく思って、世間の話をなさる。その夜は泊まって、声の尊い僧たちに読経などさせて、一晩中、管弦の遊びをなさる。禅師の君が、うちとけた話をした折に、 |
山の寺へ着いた中将を僧都も喜んで迎え、いろいろと世上の話を聞いたりした。その夜は宿泊することにして尊い声の出る僧たちに経を読ませて遊び明かした。弟の禅師とこまやかな話をしているうちに中将は、 |
Tyuuzyau ha, yama ni ohasi tuki te, Soudu mo medurasigari te, yononaka no monogatari si tamahu. Sono yo ha tomari te, kowe tahutoki hito ni kyau nado yoma se te, yo-hito-yo, asobi tamahu. Zenzi-no-Kimi, komaka naru monogatari nado suru tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.12 | 「 小野に立ち寄りて、ものあはれにもありしかな。世を捨てたれど、なほさばかりの 心ばせある人は、難うこそ」 |
「小野に立ち寄って、しみじみと感慨深いことがあったね。世を捨てているが、やはり、あれほど嗜みの深い方は、めったにいらっしゃらないものだ」 |
「小野へ寄って来たがね、身にしむ思いを味わわせられた。出家したあとまであれだけ高雅な趣味のある生活のできる人は少ないだろうね」 |
"Wono ni tati-yori te, mono ahare ni mo ari si kana! Yo wo sute tare do, naho sabakari no kokorobase aru hito ha, katau koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.13 | などあるついでに、 |
などとおっしゃるついでに、 |
こんなことを言い、続いて、 |
nado aru tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.14 | 「 風の吹き開けたりつる隙より、髪いと長くをかしげなる人こそ見えつれ。あらはなりとや思ひつらむ、立ちてあなたに入りつるうしろで、なべての人とは見えざりつ。さやうの所に、 よき女は置きたるまじきものにこそあめれ。明け暮れ見るものは法師なり。 おのづから目馴れておぼゆらむ。 不便なることぞかし」 |
「風が吹き上げた御簾の隙間から、髪がたいそう長く、美しそうな女性が見えた。人目につくと思ったのだろうか、立ってあちらに入って行く後ろ姿は、並の女性とは見えなかった。あのような所に、身分のある女性を住まわせておくべきではないでしょう。明け暮れ目にするものは法師だ。自然と見慣れてそれが普通と思われよう。不都合なことだ」 |
「風が |
"Kaze no huki ake tari turu hima yori, kami ito nagaku wokasige naru hito koso miye ture. Araha nari to ya omohi tu ram, tati te anata ni iri turu usirode, nabete no hito to ha miye zari tu. Sayau no tokoro ni, yoki womna ha oki taru maziki mono ni koso a' mere. Ake-kure miru mono ha hohusi nari. Onodukara me nare te oboyu ram. Hubin naru koto zo kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.15 | とのたまふ。禅師の君、 |
とおっしゃる。禅師の君は、 |
こんな話をした。 |
to notamahu. Zenzi-no-Kimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.16 | 「 この春、初瀬に詣でて、あやしくて見出でたる人となむ、聞きはべりし」 |
「この春、初瀬に参詣して、不思議にも発見した女性だ、と聞きました」 |
「この春 |
"Kono haru, Hatuse ni maude te, ayasiku te mi-ide taru hito to nam, kiki haberi si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.17 | とて、見ぬことなれば、こまかには言はず。 |
と言って、見てないことなので、詳しくは言わない。 |
禅師は自身の携わった事件でなく知るはずもなかったから細かには言わない。 |
tote, mi nu koto nare ba, komaka ni ha iha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.18 | 「 あはれなりけることかな。いかなる人にかあらむ。世の中を憂しとてぞ、 さる所には隠れゐけむかし。昔物語の心地もするかな」 |
「興味深い話だね。どのような人であろうか。世の中を厭って、そのような所に隠れていたのだろう。昔物語にあったような気がするね」 |
「かわいそうな人なのだね、どんな家の人だろう。世の中が悲しくなったればこそそうした寺へ来て隠れていたのだろうからね。昔の小説の中のことのようだ」 |
"Ahare nari keru koto kana! Ika naru hito ni ka ara m? Yononaka wo usi tote zo, saru tokoro ni ha kakure wi kem kasi. Mukasi-monogatari no kokoti mo suru kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.19 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
と中将は言った。 |
to notmahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 第五段 中将、帰途に浮舟に和歌を贈る |
3-5 Chujo composes and sends a waka to Ukifune at leaving |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.1 | またの日、帰りたまふにも、「 過ぎがたくなむ」とて おはしたり。 さるべき心づかひしたりければ、昔思ひ出でたる御まかなひの少将の尼なども、 袖口さま異なれども、をかし。いとどいや目に、尼君はものしたまふ。物語のついでに、 |
翌日、お帰りになる時、「素通りできにくくて」と言っていらっしゃった。しかるべき用意などしていたので、昔が思い出されるお世話の少将の尼なども、袖口の色は異なっているが、趣がある。ますます涙がちの目で、尼君はいらっしゃる。話のついでに、 |
翌日山からの帰途にもまた、「通り過ぎることができぬ気になって」こんなことを言って小野の家へ立ち寄った。ここでは迎えることを期していて食事の |
Mata-no-hi, kaheri tamahu ni mo, "Sugi gataku nam." tote ohasi tari. Saru-beki kokoro-dukahi si tari kere ba, mukasi omohi-ide taru ohom-makanahi no Seusyau-no-Ama nado mo, sode-guti sama koto nare domo, wokasi. Itodo iyame ni, Ama-Gimi ha monosi tamahu. Monogatari no tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.2 | 「 忍びたるさまにものしたまふらむは、誰れにか」 |
「こっそりと姿を隠していらっしゃるような方は、どなたですか」 |
「このお |
"Sinobi taru sama ni monosi tamahu ram ha, tare ni ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.3 | と問ひたまふ。わづらはしけれど、ほのかにも見つけてけるを、隠し顔ならむもあやしとて、 |
とお尋ねになる。厄介なことだが、ちらっと見つけたのを、隠しているようなのも変だと思って、 |
と尋ねた。めんどうになるような気はするのであったが、すでに |
to tohi tamahu. Wdurahasikere do, honoka ni mo mituke te keru wo, kakusi-gaho nara m mo ayasi tote, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.4 | 「 忘れわびはべりて、いとど罪深うのみおぼえはべりつる慰めに、この月ごろ見たまふる人になむ。いかなるにか、いともの思ひしげきさまにて、世にありと人に知られむことを、苦しげに思ひてものせらるれば、かかる 谷の底には誰れかは尋ね聞かむ、と思ひつつはべるを、いかでかは聞きあらはさせたまへらむ」 |
「忘れかねまして、ますます罪深くばかり思われましたその慰めに、ここ数か月お世話している人です。どのような理由でか、とても悲しみの深い様子で、この世に生きていると誰からも知られることを、つらいことに思っておいでなので、このような山あいの奥深くまで誰がお尋ね求めよう、と思っておりましたが、どうしてお聞きつけあそばしたのですか」 |
「昔の人のことをあまり心に持っていますのは罪の深いことになると思いまして、ここ幾月か前から娘の代わりに家へ住ませることになった人のことでしょう。どういう理由か沈んだふうでばかりいまして、自分の存在が、人に知れますことをいやがっておりますから、こんな谷底へだれがあなたを捜しに来ますかと私は慰めて隠すようにしてあげているのですが、どうしてその人のことがおわかりになったのでしょう」 |
"Wasure wabi haberi te, itodo tumi hukau nomi oboye haberi turu nagusame ni, kono tuki-goro mi tamahuru hito ni nam. Ika naru ni ka, ito mono-omohi sigeki sama nite, yo ni ari to hito ni sira re m koto wo, kurusige ni omohi te monose rarure ba, kakaru tani no soko ni ha tare kaha tadune kika m, to omohi tutu haberu wo, ikade kaha kiki arahasa se tamahe ram." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.5 | といらふ。 |
と答える。 |
to irahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.6 | 「 うちつけ心ありて参り来むにだに、山深き道のかことは聞こえつべし。まして、 思しよそふらむ方につけては、ことことに隔てたまふまじきことにこそは。いかなる筋に世を恨みたまふ人にか。慰めきこえばや」 |
「一時の物好きな心があってやって来るのでさえ、山深い道の恨み言は申し上げましょう。まして、亡き姫君の代わりとお思いなさっていることでは、まったく関係ないこととお隔てになることでしょうか。どのようなことで、この世を厭いなさる人なのでしょうか。お慰め申し上げたい」 |
「かりに突然求婚者になって現われた私としましても、遠い |
"Utituke-gokoro ari te mawiri ko m ni dani, yama hukaki miti no kakoto ha kikoye tu besi. Masite, obosi yosohu ram kata ni tuke te ha, koto-koto ni hedate tamahu maziki koto ni koso ha. Ika naru sudi ni yo wo urami tamahu hito ni ka? Nagusame kikoye baya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.7 | など、ゆかしげにのたまふ。 |
などと、関心深そうにおっしゃる。 |
好奇心の隠せぬふうで中将は言った。 |
nado, yukasige ni notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.8 | 出でたまふとて、畳紙に、 |
お帰りになるに当たって、畳紙に、 |
帰りぎわに懐紙へ、 |
Ide tamahu tote, tataugami ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.9 | 「 あだし野の風になびくな女郎花 |
「浮気な風に靡くなよ、女郎花 |
あだし野の風になびくな |
"Adasino no kaze ni nabiku na wominahesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.10 | 我しめ結はむ道遠くとも」 |
わたしのものとなっておくれ、道は遠いけれども」 |
われしめゆはん |
ware sime yuha m miti tohoku to mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.11 | と書きて、少将の尼して入れたり。尼君も見たまひて、 |
と書いて、少将の尼を介して入れた。尼君も御覧になって、 |
と書いて、少将の尼に姫君の所へ持たせてやった。尼君もそばでいっしょに読んだ。 |
to kaki te, Seusyau-no-Ama site ire tari. Ama-Gimi mo mi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.12 | 「 この御返り書かせたまへ。いと心にくきけつきたまへる人なれば、うしろめたくもあらじ」 |
「このお返事をお書きあそばせ。とても奥ゆかしいところのおありの方だから、不安なことはありますまい」 |
「返しを書いておあげなさい。紳士ですから、それがあとのめんどうを起こすことになりますまいからね」 |
"Kono ohom-kaheri kaka se tamahe. Ito kokoro-nikuki ke tuki tamahe ru hito nare ba, usirometaku mo ara zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.13 | とそそのかせば、 |
と促すと、 |
こう勧められても、 |
to sosonokase ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.14 | 「 いとあやしき手をば、いかでか」 |
「ひどく醜い筆跡を、どうして」 |
「まずい字ですから、どうしてそんなことが」 |
"Ito ayasiki te wo ba, ikade ka." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.15 | とて、さらに聞きたまはねば、 |
と言って、まったく承知なさらないので、 |
と言い、浮舟の聞き入れないのを見て、 |
tote, sarani kiki tamaha ne ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.16 | 「 はしたなきことなり」 |
「体裁の悪きことです」 |
失礼になることだから |
"Hasitanaki koto nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.17 | とて、尼君、 |
と言って、尼君が、 |
と尼君が、 |
tote, Ama-Gimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.18 | 「 聞こえさせつるやうに、世づかず、人に似ぬ人にてなむ。 |
「申し上げましたように、世間知らずで、普通の人とは違っておりますので。 |
お話しいたしましたように、世間 |
"Kikoye sase turu yau ni, yo-duka zu, hito ni ni nu hito ni te nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.19 | 移し植ゑて思ひ乱れぬ女郎花 |
ここに移し植えて困ってしまいました、女郎花です |
移し植ゑて思ひ乱れぬ女郎花 |
Utusi uwe te omohi midare nu wominahesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.20 | 憂き世を背く草の庵に」 |
嫌な世の中を逃れたこの草庵で」 |
浮き世をそむく草の |
uki yo wo somuku kusa no ihori ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.21 | とあり。「 こたみは、さもありぬべし」と、思ひ許して帰りぬ。 |
とある。「今回は、きっとそういうことだろう」と大目に見て帰った。 |
と書いて出した。はじめてのことであってはこれが普通であろうと思って中将は帰った。 |
to ari. "Kotami ha, samo ari nu besi." to, omohi yurusi te kaheri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 第六段 中将、三度山荘を訪問 |
3-6 Chujo visits to Ono villa third time |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.1 | 文などわざとやらむは、さすがにうひうひしう、ほのかに見しさまは忘れず、もの思ふらむ筋、何ごとと知らねど、あはれなれば、 八月十余日のほどに、 小鷹狩のついでにおはしたり。例の、尼呼び出でて、 |
手紙などをわざわざやるのは、何といっても不慣れな感じで、ちらっと見た様子は忘れず、何を悩んでいるのか知らないが、心を惹かれるので、八月十日過ぎに、小鷹狩のついでにいらっしゃった。いつものように、尼を呼び出して、 |
中将は小野の人に手紙を送ることもさすがに今さら若々しいことに思われてできず、しかもほのかに見た姿は忘れることができずに苦しんでいた。 |
Humi nado wazato yara m ha, sasuga ni uhi-uhisiu, honoka ni mi si sama ha wasure zu, mono omohu ram sudi, nani-goto to sira ne do, ahare nare ba, hati-gwati zihu-yo-niti no hodo ni, kotaka-gari no tuide ni ohasi tari. Rei no, Ama yobi-ide te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
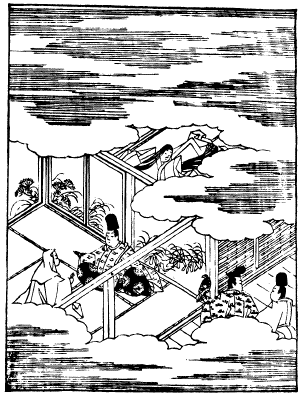 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.2 | 「 一目見しより、静心なくてなむ」 |
「先日ちらっと見てから、心が落ち着かなくて」 |
「お姿を少し隙見で知りました時から落ち着いておられなくなりました」 |
"Hito-me mi si yori, sidu-kokoro naku te nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.3 | とのたまへり。 いらへたまふべくもあらねば、尼君、 |
とおっしゃった。お答えなさるはずもないので、尼君は、 |
と取り次がせた。浮舟の姫君は返辞をしてよいことと認めず黙っていると、尼君が、 |
to notamahe ri. Irahe tamahu beku mo ara ne ba, Ama-Gimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.4 | 「 待乳の山、となむ見たまふる ★」 |
「待乳の山の、誰か他に思う人がいるように拝します」 |
「 |
"Matuti-no-yama, to nam mi tamahuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.5 | と言ひ出だしたまふ。 対面したまへるにも、 |
と中から言い出させなさる。お会いなさっても、 |
と言わせた。それから昔の |
to ihi-idasi tamahu. Taimen si tamahe ru ni mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.6 | 「 心苦しきさまにてものしたまふと聞きはべりし人の御上なむ、残りゆかしくはべりつる。何事も心にかなはぬ心地のみしはべれば、山住みもしはべらまほしき心ありながら、 許いたまふまじき人びとに思ひ障りてなむ過ぐしはべる。世に 心地よげなる人の上は、かく 屈したる人の心からにや、ふさはしからずなむ。 もの思ひたまふらむ人に、思ふことを聞こえばや」 |
「お気の毒な様子でいらっしゃると伺いました方のお身の上が、もっと詳しく知りたく存じます。何事も思った通りにならない気ばかりがしますので、出家生活をしたい考えはありながら、お許しなさるはずのない方々に妨げられて過ごしております。いかにも屈託なげな今の妻のことは、このように沈みがちな身の上のせいか、似合わないのです。悩んでいらっしゃるらしい方に、思っている気持ちを申し上げたい」 |
「気の毒な様子で暮らしておいでになるとお話しになりました方のことをくわしく承りたく思います。満足のできない生活が続くものですから、山寺へでもはいってしまいたくなるのですが、同意されるはずもない両親を思いまして、そのままにしています私は、幸福な人には自分の沈んだ心から親しんでいく気になれませんが、不幸な人には慰め合うようになりたく思われてなりません」 |
"Kokoro-gurusiki sama nite monosi tamahu to kiki haberi si hito no ohom-uhe nam, nokori yukasiku haberi turu. Nani-goto mo kokoro ni kanaha nu kokoti nomi si habere ba, yama-zumi mo si habera mahosiki kokoro ari nagara, yurui tamahu maziki hito-bito ni omohi sahari te nam sugusi haberu. Yo ni kokoti-yoge naru hito no uhe ha, kaku ku'-si taru hito no kokoro kara ni ya, husahasikara zu nam. Mono omohi tamahu ram hito ni, omohu koto wo kikoye baya." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.7 | など、いと心とどめたるさまに語らひたまふ。 |
などと、とてもご執心なさってようにお話なさる。 |
中将は熱心に言う。 |
nado, ito kokoro-todome taru sama ni katarahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.8 | 「 心地よげならぬ御願ひは、聞こえ交はしたまはむに、つきなからぬさまになむ見えはべれど、 例の人にてはあらじと、 いとうたたあるまで ★世を恨みたまふめれば。 残りすくなき齢どもだに、今はと背きはべる時は、いともの心細くおぼえはべりしものを。世をこめたる盛りには、つひにいかがとなむ、見たまへはべる」 |
「もの思わしげな方をとのご希望は、いろいろお話し合いなさるに、不似合いではないように見えますが、普通の人のようにはありたくないと、実に嫌に思われるくらい世の中を厭っていらっしゃるようなので。残り少ない寿命のわたしでさえ、今を最後と出家します時には、とても何となく心細く思われましたものを。将来の長い盛りの時では、最後まで出家生活を送れるかどうかと、心配でおります」 |
「不しあわせをお話しになろうとなさいますのには相当したお相手だと思いますけれど、あの方はこのまま俗の姿ではもういたくないということを始終言うほどにも悲観的になっています。私ら年のいった人間でさえいよいよ出家する時には心細かったのですから、春秋に富んだ人に、それが実行できますかどうかと私はあぶながっています」 |
"Kokoti-yoge nara nu ohom-negahi ha, kikoye-kahasi tamaha m ni, tuki nakara nu sama ni nam miye habere do, rei no hito nite ha ara zi to, ito utata aru made yo wo urami tamahu mere ba. Nokori sukunaki yohahi-domo dani, ima ha to somuki haberu toki ha, ito mono kokoro-bosoku oboye haberi si mono wo. Yo wo kome taru sakari ni ha, tuhini ikaga to nam, mi tamahe haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.9 | と、親がりて言ふ。入りても、 |
と、親ぶって言う。奥に入って行っても、 |
尼君は親がって言うのであった。姫君の所へ行ってはまた、 |
to, oyagari te ihu. Iri te mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.10 | 「 情けなし。なほ、いささかにても聞こえたまへ。かかる御住まひは、すずろなることも、あはれ知るこそ世の常のことなれ」 |
「思いやりのないこと。やはり、少しでもお返事申し上げなさい。このようなお暮らしは、ちょっとしたつまらないことでも、人の気持ちを汲むのは世間の常識というものです」 |
「あまり冷淡な人だと思われますよ。少しでも返辞を取り次がせておあげなさいよ。こんなわび住まいをしている人たちというものは、自尊心は陰へ隠して人情味のある交際をするものなのですよ」 |
"Nasakenasi. Naho, isasaka nite mo kikoye tamahe. Kakaru ohom-sumahi ha, suzuro naru koto mo, ahare siru koso yo no tune no koto nare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.11 | など、こしらへても言へど、 |
などと、なだめすかして言うが、 |
などと言うのであるが、 |
nado, kosirahe te mo ihe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.12 | 「 人にもの聞こゆらむ方も知らず、何事もいふかひなくのみこそ」 |
「人にものを申し上げるすべも知らず、何事もお話にならないわたしで」 |
「私は人とどんなふうにものを言うものなのか、その方法すら知らないのですもの。私は何の点でも人並みではございません」 |
"Hito ni mono kikoyu ram kata mo sira zu, nani-goto mo ihu-kahi naku nomi koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.13 | と、いとつれなくて臥したまへり。 |
と、とてもそっけなく臥せっていらっしゃった。 |
浮舟の姫君はそのまま横になってしまった。 |
to, ito turenaku te husi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.14 | 客人は、 |
客人は、 |
中将はあちらで、 |
Marauto ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.15 | 「 いづら。あな、心憂。 秋を契れるは、すかしたまふにこそありけれ」 |
「どうでしたか。何と、情けない。秋になったらとお約束したのは、おだましになったのですね」 |
「どちらへおいでになったのですか、御冷遇を受けますね。『秋を |
"Idura? Ana, kokoro-u! Aki wo tigire ru ha, sukasi tamahu ni koso ari kere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.16 | など、恨みつつ、 |
などと、恨みながら、 |
などと尼君を恨めしそうに言い、 |
nado urami tutu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.17 | 「 松虫の声を訪ねて来つれども |
「松虫の声を尋ねて来ましたが |
松虫の声をたづねて来しかども |
"Matu-musi no kowe wo tadune te ki ture domo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.18 | また萩原の露に惑ひぬ」 |
再び萩原の露に迷ってしまいました」 |
また |
mata hagi-hara no tuyu ni madohi nu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.19 | 「 あな、いとほし。これをだに」 |
「まあ、お気の毒な。せめてこのお返事だけでも」 |
と歌いかけた。「まあおかわいそうに、歌のお返しでもなさいよ」 |
"Ana, itohosi. Kore wo dani." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.20 | など責むれば、 さやうに世づいたらむこと言ひ出でむもいと心憂く、また、言ひそめては、かやうの折々に責められむも、むつかしうおぼゆれば、いらへをだにしたまはねば、あまりいふかひなく 思ひあへり。 尼君、早うは今めきたる人にぞありける 名残なるべし。 |
などと責めると、そのような色恋めいた事に返事するのもたいそう嫌で、また一方、いったん返歌をしては、このような折々に責められるのも、厄介に思われるので、返歌をさえなさらないので、あまりにいいようもなく思い合っていた。尼君は、出家前は当世風の方であった気が残っているのであろう。 |
尼夫人はこう姫君に迫るのであったが、そんな恋愛の遊戯めいたことをする気はなく、また一度歌を |
nado semure ba, sayau ni yo-dui tara m koto ihi-ide m mo ito kokoro-uku, mata, ihi-some te ha, kayau no wori-wori ni seme rare m mo, mutukasiu oboyure ba, irahe wo dani si tamaha ne ba, amari ihukahinaku omohi ahe ri. Ama-Gimi, hayau ha ima-meki taru hito ni zo ari keru nagori naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.21 | 「 秋の野の露分け来たる狩衣 |
「秋の野原の露を分けて来たため濡れた狩衣は |
「秋の野の露分け来たる狩りごろも |
"Aki no no no tuyu wake ki taru kari-goromo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.22 | 葎茂れる宿にかこつな |
葎の茂ったわが宿のせいになさいますな |
|
mugura sigere ru yado ni kakotu na |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.23 | となむ、わづらはしがりきこえたまふめる」 |
と、わずらわしがり申していらっしゃるようです」 |
迷惑がっておられます」 |
to nam, wadurahasigari kikoye tamahu meru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.24 | と言ふを、 内にも、なほ「かく心より外に世にありと知られ始むるを、 いと苦し」と思す心のうちをば知らで、 男君をも飽かず思ひ出でつつ、恋ひわたる人びとなれば、 |
と言うのを、簾中でも、やはり「このように思いの外にこの世に生きていると知られ出したのを、とてもつらい」とお思いになる心中を知らないで、男君のことをも尽きせず思い出しては、恋い慕っている人びとなので、 |
と言っているのを、浮舟は聞きながら、こうしたことからまだ自分の世の中にいることが昔の人々に知れ始めることにならないであろうかと苦しく思っていた。姫君の気持ちも知らずに、昔の姫君と同じくこの婿君をもなつかしがることの多い女房たちは、 |
to ihu wo, uti ni mo, naho "Kaku kokoro yori hoka ni yo ni ari to sira re hazimuru wo, ito kurusi." to obosu kokoro no uti wo ba sira de, Wotoko-Gimi wo mo aka zu omohi-ide tutu, kohi wataru hito-bito nare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.25 | 「 かく、はかなきついでにも、うち語らひきこえたまはむに、心より外に、よにうしろめたくは見えたまはぬものを。世の常なる筋に思しかけずとも、情けなからぬほどに、御いらへばかりは聞こえたまへかし」 |
「このような、ちょっとした機会にも、お話し合い申し上げなさるのも、お気持ちにそむいて、油断ならないことはなさらない方ですから。世間並の色恋とお思いなさらなくても、人情のわかる程度に、お返事を申し上げなさいませ」 |
「ただちょっと深い意味でもなくお立ち寄りになった方ですから、お話をなすってもよろしくない方へ進出しようなどとは大丈夫なさいませんから、御結婚問題などは別にして、好意のある程度のお返辞だけはしておあげなさいまし」 |
"Kaku, hakanaki tuide ni mo, uti katarahi kikoye tamaha m ni, kokoro yori hoka ni, yo ni usiro-metaku ha miye tamaha nu mono wo. Yo no tune naru sudi ni obosi-kake zu tomo, nasakenakara nu hodo ni, ohom-irahe bakari ha kikoye tamahe kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.26 | など、ひき動かしつべく言ふ。 |
などと、引き動かさんばかりに言う。 |
などと言い、 |
nado, hiki-ugokasi tu beku ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 第七段 尼君、中将を引き留める |
3-7 Ama-gimi who is Chujo's mother in law prevents him from leaving |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.1 | さすがに、かかる古代の心どもにはありつかず、今めきつつ、腰折れ歌好ましげに、若やぐけしきどもは、 いと うしろめたうおぼゆ。 |
そうはいっても、このような古風な気質とは不似合いに、当世風に気取っては、下手な歌を詠みたがって、はしゃいでいる様子は、とても不安に思われる。 |
さすがに年を取った女たちは尼君が柄にもなく若々しく歌らしくもない歌をいい気で |
Sasuga ni, kakaru kotai no kokoro-domo ni ha ari tuka zu, imameki tutu, kosiwore-uta konomasige ni, wakayagu kesiki-domo ha, ito usirometau oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.2 | 「 限りなく憂き身なりけり、 と見果ててし命さへ、あさましう長くて、いかなるさまにさすらふべきならむ。ひたぶるに亡き者と人に見聞き捨てられてもやみなばや」 |
「この上なく嫌な身の上であった、と見極めた命までが、あきれるくらい長くて、どのようなふうにさまよって行くのだろう。ひたすら亡くなった者として誰からもすっかり忘れられて終わりたい」 |
なんという不幸な自分であろう、捨てるのに |
"Kagiri naku uki-mi nari keri, to mi-hate te si inoti sahe, asamasiu nagaku te, ika naru sama ni sasurahu beki nara m. Hitaburu ni naki mono to mi-kiki sute rare te mo yami na baya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.3 | と思ひ臥したまへるに、中将は、 おほかたもの思はしきことのあるにや ★。いといたううち嘆き、忍びやかに笛を吹き鳴らして、 |
と思って臥せっていらっしゃるのに、中将は、およそ何か物思いの種があるのだろうか。とてもひどく嘆き、ひっそりと笛を吹き鳴らして、 |
と思い悩んで、横になったままの姿で |
to omohi husi tamahe ru ni, Tyuuzyau ha, ohokata mono omohasiki koto no aru ni ya? Ito itau uti-nageki, sinobiyaka ni hue wo huki narasi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.4 | 「 ▼ 鹿の鳴く音に」 |
「鹿の鳴く声に」 |
「 |
"Sika no naku ne ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.5 | など独りごつけはひ、 まことに心地なくはあるまじ。 |
などと独り言をいう感じは、ほんとうに弁えのない人ではなさそうである。 |
などと口ずさんでいる様子は相当な男と見えた。 |
nado hitori-gotu kehahi, makoto ni kokoti naku ha aru mazi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.6 | 「 過ぎにし方の思ひ出でらるるにも、なかなか心尽くしに、今はじめて あはれと思すべき人はた、難げなれば、 ▼ 見えぬ山路にもえ思ひなすまじうなむ」 |
「過ぎ去った昔が思い出されるにつけても、かえって心尽くしに、今初めて慕わしいと思ってくれるはずの人も、またいそうもないので、つらいことのない山奥とは思うことができません」 |
「ここへまいっては昔の思い出に心は苦しみますし、また新しく私をあわれんでくだすってよい方はその心になってくださらないし『世のうき目見えぬ山路』とも思われません」 |
"Sugi ni si kata no omohi-ide raruru ni mo, naka-naka kokoro-dukusi ni, ima hazime te ahare to obosu beki hito hata, katage nare ba, miye nu yamadi ni mo e omohi nasu maziu nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.7 | と、恨めしげにて出でなむとするに、尼君、 |
と、恨めしそうにしてお帰りになろうとする時に、尼君が、 |
と恨めしそうに言い、帰ろうとした時に、尼君が、 |
to, uramesige nite ide na m to suru ni, Ama-Gimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.8 | 「 など、あたら夜を御覧じさしつる ★」 |
「どうして、せっかくの素晴らしい夜を御覧になりませぬ」 |
「あたら夜を(あたら夜の月と花とを同じくは心知れらん人に見せばや)お帰りになるのですか」 |
"Nado, atara-yo wo go-ran-zi sasi turu?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.9 | とて、ゐざり出でたまへり。 |
と言って、膝行して出ていらっしゃった。 |
と言って、 |
tote, wizari ide tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.10 | 「 何か。遠方なる里も、試みはべれば ★」 |
「いえ。あちらのお気持ちも、分かりましたので」 |
「もうたくさんですよ。山里も悲しいものだということがわかりましたから」 |
"Nanika? Woti naru sato mo, kokoromi habere ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.11 | など言ひすさみて、「 いたう好きがましからむも、さすがに便なし。いとほのかに見えしさまの、目止まりしばかり、つれづれなる心慰めに思ひ出づるを、あまりもて離れ、奥深なるけはひも 所のさまにあはずすさまじ」と思へば、帰りなむとするを、笛の音さへ 飽かず、いとどおぼえて、 |
と軽く言って、「あまり好色めいて振る舞うのも、やはり不都合だ。ほんのちらっと見えた姿が、目にとまったほどで、所在ない心の慰めに思い出したが、あまりによそよそしくて、奥ゆかしい感じ過ぎるのも場所柄にも似合わず興醒めな感じがする」と思ので、帰ろうとするのを、笛の音まで物足りなく、ますます思われて、 |
などと中将は言い、新しい姫君へむやみに接近したいふうを見せることもしたくない、ほのかに少し見た人の印象のよかったばかりに、空虚で退屈な心の補いに恋をし始めたにすぎない相手があまりに冷淡に思い上がった態度をとっているのは場所柄にもふさわしくないことであると不快に思われる心から、帰ろうとするのであったが、尼君は笛の音に別れることすらも惜しくて、 |
nado ihi susami te, "Itau suki gamasikara m mo, sasuga ni bin-nasi. Ito honoka ni miye si sama no, me tomari si bakari, ture-dure naru kokoro-nagusame ni omohi-iduru wo, amari mote-hanare, oku-buka naru kehahi mo tokoro no sama ni aha zu susamazi." to omohe ba, kaheri na m to suru wo, hue no ne sahe aka zu, itodo oboye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.12 | 「 深き夜の月をあはれと見ぬ人や |
「夜更けの月をしみじみと御覧にならない方が |
深き夜の月を哀れと見ぬ人や |
"Hukaki yo no tuki wo ahare to mi nu hito ya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.13 | 山の端近き宿に泊らぬ」 |
山の端に近いこの宿にお泊まりになりませんか」 |
山の |
yama-no-ha tikaki yado ni tomara nu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.14 | と、なまかたはなることを、 |
と、どこか整わない歌を、 |
と奥様は仰せられますと |
to, nama kataha naru koto wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.15 | 「 かくなむ、聞こえたまふ」 |
「このように、申し上げていらっしゃいます」 |
取り次ぎで言わせたのを聞くと |
"Kaku nam, kikoye tamahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.16 | と言ふに、心ときめきして、 |
と言うと、心をときめかして、 |
またときめくものを覚えた。 |
to ihu ni, kokoro-tokimeki si te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.17 | 「 山の端に入るまで月を眺め見む |
「山の端に隠れるまで月を眺ましょう |
山の端に入るまで月をながめ見ん |
"Yama-no-ha ni iru made tuki wo nagame mi m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.18 | 閨の板間もしるしありやと」 |
その効あってお目にかかれようかと」 |
|
neya no itama mo sirusi ari ya to |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.19 | など言ふに、この 大尼君、笛の音をほのかに聞きつけたりければ、 さすがにめでて 出で来たり。 |
などと言っていると、この大尼君、笛の音をかすかに聞きつけたので、老齢ではいてもやはり心惹かれて出て来た。 |
こんな返しを伝えさせている時、この家の大尼君が、さっきから笛の音を聞いていて、心の |
nado ihu ni, kono Oho-Ama-Gimi, hue no ne wo honoka ni kikituke tari kere ba, sasuga ni mede te ide-ki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.20 | ここかしこうちしはぶき、あさましきわななき声にて、なかなか昔のことなどもかけて言はず。 誰れとも思ひ分かぬなるべし。 |
話のあちこちで咳をし、呆れるほどの震え声で、かえって昔のことなどは口にしない。誰であるかも分からないのであろう。 |
間で |
Koko-kasiko uti-sihabuki, asamasiki wananaki-gowe ni te, naka-naka mukasi no koto nado mo kake te iha zu. Tare to mo omohi waka nu naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.21 | 「 いで、その琴の琴弾きたまへ。横笛は、月にはいとをかしきものぞかし。いづら、 御達。琴とりて参れ」 |
「さあ、その琴の琴をお弾きなさい。横笛は、月にはとても趣深いものです。どこですか、そなたたち。琴を持って参れ」 |
「さあそこの琴をあなたはお |
"Ide, sono kin-no-koto hiki tamahe. Yokobue ha, tuki ni ha ito wokasiki mono zo kasi. Idura, kuso-tati Koto tori te mawire." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.22 | と言ふに、 それなめりと、推し量りに聞けど、「 いかなる所に、かかる人、いかで籠もりゐたらむ。定めなき世ぞ」、これにつけてあはれなる。 盤渉調をいとをかしう吹きて、 |
と言うので、母尼君らしい、と推察して聞くが、「どのような所に、このような老人が、どうして籠もっているのだろう。無常の世だ」と、このことにつけても感慨無量である。盤渉調をたいそう趣深く吹いて、 |
と言っている。さっきから大尼君らしいと中将は察して聞いていたのであるが、この家のどこにこうした大年寄が無事に暮らしていたのであろうと思い、 |
to ihu ni, sore na' meri to, osihakari ni kike do, "Ika naru tokoro ni, kakaru hito, ikade komori wi tara m. Sadame naki yo zo", kore ni tuke te ahare naru. Bansiki-deu wo ito wokasiu huki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.23 | 「 いづら、さらば」 |
「どうですか。さあ」 |
「さあ、それではお合わせください」 |
"Idura, sara ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.24 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
と言う。 |
to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.25 | 娘尼君、これもよきほどの好き者にて、 |
娘尼君は、この方も相当な風流人なので、 |
これも相応に風流好きな尼夫人は、 |
Musume-Ama-Gimi, kore mo yoki hodo no suki-mono ni te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.26 | 「 昔聞きはべりしよりも、こよなくおぼえはべるは、山風をのみ聞き馴れはべりにける耳からにや」とて、「 いでや、これもひがことになりてはべらむ」 |
「昔聞きましたときよりも、この上なく素晴らしく思われますのは、山風ばかりを聞き馴れていました耳のせいでしょうか」と言って、「それでは、わたしのはでたらめになっていましょう」 |
「あなたのお笛は昔聞きましたよりもずっと巧妙におなりになったように思いますのも、平生山風以外に聞くもののないせいかもしれません。私のはまちがいだらけになっているでしょう」 |
"Mukasi kiki haberi si yori mo, koyonaku oboye haberu ha, yama-kaze wo nomi kiki nare haberi ni keru mimi kara ni ya." tote, "Ideya, kore mo higa-koto ni nari te habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.27 | と言ひながら弾く。 今様は、をさをさなべての人の、今は好まずなりゆくものなれば、なかなか珍しくあはれに聞こゆ。 ▼ 松風もいとよくもてはやす。吹きて合はせたる笛の音に、月もかよひて澄める心地すれば、いよいよめでられて、 宵惑ひもせず、起き居たり。 |
と言いながら弾く。当世風では、ほとんど普通の人は、今は好まなくなって行くものなので、かえって珍しくしみじみと聞こえる。松風も実によく調和する。吹き合わせた笛の音に、月も調子を合わせて澄んでいる気がするので、ますます興趣が乗って、眠気も催さず、起きていた。 |
と言いながら琴を弾いた。現代の人はあまり琴の器楽を好まなくなって、弾き手も少なくなったためか、珍しく身にしむように思って、中将は相手の |
to ihi nagara hiku. Imayau ha, wosa-wosa nabete no hito no, ima ha konoma zu nari-yuku mono nare ba, naka-naka medurasiku ahare ni kikoyu. Matu-kaze mo ito yoku motehayasu. Huki te ahase taru hue no ne ni, tuki mo kayohi te sume ru kokoti sure ba, iyo-iyo mede rare te, yohi-madohi mo se zu, oki wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 第八段 母尼君、琴を弾く |
3-8 Ama-gimi's mother who is an old nun plays koto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.1 | 「 女は、昔は、東琴をこそは、こともなく 弾きはべりしかど、今の世には、 変はりにたるにやあらむ。この僧都の、『聞きにくし。念仏より他のあだわざなせそ』とはしたなめられしかば、何かは、とて弾きはべらぬなり。さるは、いとよく鳴る琴もはべり」 |
「お婆は、昔は、東琴を、簡単に弾きましたが、今の世では、変わったのでしょうか。息子の僧都が『聞きにくい。念仏以外のつまらないことはするな』と叱られましたので、それならと、もう弾かないのでございます。それにしても、とてもよい響きの琴もございます」 |
「昔はこの年寄りも和琴をうまく弾きこなしたものですがねえ、今は弾き方も変わっているかしれませんね。 |
"Womna ha, mukasi ha, aduma-goto wo koso ha, koto mo naku hiki haberi sika do, ima no yo ni ha, kahari ni taru ni ya ara m. Kono Soudu no, 'Kiki nikusi. Nenbutu yori hoka no ada waza na se so.' to hasitaname rare sika ba, nani-kaha, tote hiki habera nu nari. Saruha, ito yoku naru koto mo haberi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.2 | と言ひ続けて、いと 弾かまほしと思ひたれば、 いと忍びやかにうち笑ひて、 |
と言い続けて、とても弾きたく思っているので、たいそうこっそりとほほ笑んで、 |
大尼君はこんなふうに言い続けて弾きたそうに見えた。中将は忍び笑いをして、 |
to ihi tuduke te, ito hika mahosi to omohi tare ba, ito sinobiyaka ni uti-warahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.3 | 「 いとあやしきことをも制しきこえたまひける僧都かな。極楽といふなる所には、菩薩なども皆かかることをして、天人なども舞ひ遊ぶこそ 尊かなれ。行ひ紛れ、罪得べきことかは。今宵聞きはべらばや」 |
「まことに変なことをお制止申し上げなさった僧都ですね。極楽という所には、菩薩なども皆このようなことをして、天人なども舞い遊ぶのが尊いものだと言います。勤行を怠り、罪を得ることだろうか。今夜はお聞き致したい」 |
「僧都がおとめになるのはどうしたことでしょう。極楽という所では |
"Ito ayasiki koto wo mo sei-si kikoye tamahi keru Soudu kana! Gokuraku to ihu naru tokoro ni ha, Bosatu nado mo mina kakaru koto wo site, Tennin nado mo mahi asobu koso tahutoka' nare. Okonahi magire, tumi u beki koto kaha. Koyohi kiki habera baya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.4 | とすかせば、「いとよし」と思ひて、 |
とお世辞を言うと、「とても嬉しい」と思って、 |
とからかう気で言った言葉に、大尼君は満足して、 |
to sukase ba, "Ito yosi." to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.5 | 「 いで、主殿のくそ、東取りて」 |
「さあ、主殿の君さん、東琴を取って」 |
「さあ座敷がかりの童女たち、 |
"Ide, Tonomori no kuso, aduma tori te." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.6 | と言ふにも、しはぶきは絶えず。人びとは、見苦しと思へど、僧都をさへ、恨めしげにうれへて言ひ聞かすれば、いとほしくてまかせたり。 取り寄せて、ただ今の笛の音をも訪ねず、ただおのが心をやりて、 東の調べを爪さはやかに調ぶ。皆異ものは声を止めつるを、「これをのみめでたる」と思ひて、 |
と言うにも、咳は止まらない。女房たちは、見苦しいと思うが、僧都をまで、憎らしく不平を言って聞かせるので、お気の毒なのでそのままにしていた。東琴を取り寄せて、今の笛の調子もおかまいなしに、ただ自分勝手に弾いて、東の調子を爪弾きさわやかに調べる。他の楽器の演奏をみな止めてしまったので、「これにばかり聞きほれているのだ」と思って、 |
この短い言葉の間にも |
to ihu ni mo, sihabuki ha taye zu. Hito-bito ha, mi-gurusi to omohe do, Soudu wo sahe, uramesige ni urehe te ihi kika sure ba, itohosiku te makase tari. Tori-yose te, tada ima no hue no ne wo mo tadune zu, tada onoga kokoro wo yari te, aduma no sirabe wo tuma sahayaka ni sirabu. Mina koto mono ha kowe wo yame turu wo, "Kore wo nomi mede taru." to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.7 | 「 たけふ、ちちりちちり、たりたむな」 |
「たけふ、ちちりちちり、たりたんな」 |
ちりふり、ちりちり、たりたり |
"Takehu, titiri titiri, tari tam na" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.8 | など、掻き返し、はやりかに弾きたる、言葉ども、わりなく古めきたり。 |
などと、撥を掻き返し、さっそうと弾いている、その言葉などは、やたらと古めかしい。 |
などとかき返してははしゃいだ言葉もつけて言うのも古めかしいことのかぎりであった。 |
nado, kaki-kahei, hayarika ni hiki taru, kotoba-domo, warinaku hurumeki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.9 | 「 いとをかしう、今の世に聞こえぬ言葉こそは、弾きたまひけれ」 |
「実に素晴らしく、今の世には聞かれぬ歌を、お弾きになりました」 |
「おもしろいですね。ただ今では聞くことのできないような言葉がついていて」 |
"Ito wokasiu, ima no yo ni kikoye nu kotoba koso ha, hiki tamahi kere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.10 | と褒むれば、耳ほのぼのしく、かたはらなる人に問ひ聞きて、 |
と褒めると、耳も遠くなっているので、側にいる女房に尋ね聞いて、 |
などと中将がほめるのを、耳の遠い老尼はそばの者に聞き返して、 |
to homure ba, mimi hono-bonosiku, katahara naru hito ni tohi kiki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.11 | 「 今様の若き人は、かやうなることをぞ好まれざりける。ここに月ごろものしたまふめる 姫君、容貌いとけうらにものしたまふめれど、もはら、 かやうなるあだわざなどしたまはず、埋れてなむ、ものしたまふめる」 |
「今風の若い人は、このようなことをお好きでないね。ここに何か月もいらっしゃる姫君は、容貌はとても美しくいらっしゃるようだが、もっぱら、このようなつまらない遊びはなさらず、引き籠もっていらっしゃるようです」 |
「今の若い者はこんなことが好きでなさそうですよ。この |
"Imayau no wakaki hito ha, kayau naru koto wo zo konoma re zari keru. Koko ni tuki-goro monosi tamahu meru Hime-Gimi, katati ito keura ni monosi tamahu mere do, mohara, kayau naru ada-waza nado si tamaha zu, umore te nam, monosi tamahu meru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.12 | と、我かしこに うちあざ笑ひて語るを、尼君などは、かたはらいたしと思す。 |
と、得意顔に大声で笑って話すのを、尼君などは、聞き苦しいとお思いである。 |
と、 |
to, ware kasiko ni uti aza-warahi te kataru wo, Ama-Gimi nado ha, katahara-itasi to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 第九段 翌朝、中将から和歌が贈られる |
3-9 Chujo composes and sends a waka to Ukifune next morning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.1 | これに事皆醒めて、帰りたまふほども、山おろし吹きて、 聞こえ来る笛の音、いとをかしう聞こえて、起き明かしたる翌朝、 |
これによってすっかり興醒めして、お帰りになる途中も、山下ろしが吹いて、聞こえて来る笛の音も、とても素晴らしく聞こえて、起き明かしていた翌朝、 |
大老人のあずま琴で興味のしらけてしまった席から中将の帰って行く時も山おろしが吹いていた。それに混じって聞こえてくる笛の音が美しく思われて人々は寝ないで夜を明かした。翌日中将の所から、 |
Kore ni koto mina same te, kaheri tamahu hodo mo, yama-orosi huki te, kikoye kuru hue no ne, ito wokasiu kikoye te, oki-akasi taru tutomete, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.2 | 「 昨夜は、かたがた心乱れはべりしかば、急ぎまかではべりし。 |
「昨夜は、あれこれと心が乱れましたので、急いで帰りました。 |
昨日は昔と今の歎きに心が乱されてしまいまして、失礼な帰り方をしました。 |
"Yobe ha, kata-gata kokoro-midare haberi sika ba, isogi makade haberi si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.3 | 忘られぬ昔のことも笛竹の |
忘れられない昔の人のことやつれない人のことにつけ |
忘られぬ昔のことも笛竹の |
Wasura re nu mukasi no koto mo huetake no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.4 | つらきふしにも音ぞ泣かれける |
声を立てて泣いてしまいました |
継ぎし |
turaki husi ni mo ne zo naka re keru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.5 | なほ、すこし思し知るばかり教へなさせたまへ。忍ばれぬべくは、好き好きしきまでも、 何かは」 |
やはり、もう少し気持ちをご理解いただけるよう説得申し上げてください。堪えきれるものでしたら、好色がましい態度にまで、どうして出ましょうか」 |
あの方へ私の誠意を認めてくださるようにお教えください。内に忍んでいるだけで足る心でしたならこんな軽はずみ男と見られますようなことまでは決して申し上げないでしょう。 |
Naho, sukosi obosi siru bakari wosihe nasa se tamahe. Sinoba re nu beku ha, suki-zukisiki made mo, nani kaha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.6 | とあるを、 いとどわびたるは、涙とどめがたげなるけしきにて、書きたまふ。 |
とあるので、ますます困っている尼君は、涙を止めがたい様子で、お書きになる。 |
と言う消息が尼君へあった。これを見て昔の婿君をなつかしんでいる尼夫人は泣きやむことができぬふうに涙を流したあとで返事を書いた。 |
to aru wo, itodo wabi taru ha, namida todome gatage naru kesiki nite, kaki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.7 | 「 笛の音に昔のことも偲ばれて |
「笛の音に昔のことも偲ばれまして |
笛の音に昔のことも忍ばれて |
"Hue no ne ni mukasi no koto mo sinoba re te |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.8 | 帰りしほども袖ぞ濡れにし |
お帰りになった後も袖が濡れました |
帰りしほども袖ぞ |
kaheri si hodo mo sode zo nure ni si |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.9 | あやしう、もの思ひ知らぬにや、とまで見はべる ありさまは、 老い人の問はず語りに、聞こし召しけむかし」 |
不思議なことに、人の情けも知らないのではないか、と見えました様子は、年寄の問わず語りで、お聞きあそばしたでしょう」 |
不思議なほど普通の若い人と違った人のことは老人の問わず語りからも御承知のできたことと思います。 |
Ayasiu, mono-omohi sira nu ni ya, to made mi haberu arisama ha, oyi-bito no toha-zu-gatari ni, kikosi-mesi kem kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.10 | とあり。珍しからぬも 見所なき心地して、 うち置かれけむ。 |
とある。珍しくもない見栄えのしない気がして、つい読み捨てたことであろう。 |
と言うのである。恋しく思う人の字でなく、見なれた昔の |
to ari. Medurasikara nu mo mi-dokoro naki kokoti si te, uti-oka re kem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.11 | 荻の葉に劣らぬほどほどに訪れわたる ★、「 いとむつかしうもあるかな。 人の心はあながちなるものなりけり」と見知りにし折々も、やうやう思ひ出づるままに、 |
荻の葉に秋風が訪れるのに負けないくらい頻繁に便りがあるのが、「とても煩わしいことよ。男の心はむてっぽうなものだ」と分かった時々のことも、だんだん思い出すにつれて、 |
|
Wogi no ha ni otora nu hodo-hodo ni otodure wataru, "Ito mutukasiu mo aru kana! Hito no kokoro ha anagati naru mono nari keri." to mi-siri ni si wori-wori mo, yau-yau omohi-iduru mama ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.12 | 「 なほ、かかる筋のこと、人にも思ひ放たすべきさまに、疾くなしたまひてよ」 |
「やはり、このような方面のことは、相手にも諦めさせるように、早くしてくださいませ」 |
もう自分に恋愛をさせぬよう、また人からもその思いのかからぬように早くしていただきたい |
"Naho, kakaru sudi no koto, hito ni mo omohi hanatasu beki sama ni, toku nasi te yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9.13 | とて、経習ひて読みたまふ。心の内にも念じたまへり。かくよろづにつけて世の中を思ひ捨つれば、「 若き人とてをかしやかなることもことになく、結ぼほれたる本性なめり」と思ふ。容貌の見るかひあり、うつくしきに、よろづの咎見許して、明け暮れの見物にしたり。すこしうち笑ひたまふ折は、珍しくめでたきものに思へり。 |
と言って、お経を習って読んでいらっしゃる。心中でも祈っていらっしゃった。このように何かにつけて世の中を捨てているので、「若い女だといっても華やかなところも特になく、陰気な性格なのだろう」と思う。器量が見飽きず、かわいらしいので、他の欠点はすべて大目に見て、明け暮れの心の慰めにしていた。少しにっこりなさるときには、めったになく素晴らしい方だと思っていた。 |
と仏へ頼む意味で経を習って姫君は読んでいた。心の中でもそれを念じていた。こんなふうに寂しい道を選んでいる浮舟を、若い人でありながらおもしろい空気も格別作らず、うっとうしいのがその性質なのであろうと周囲の人は思った。 |
tote, kyau narahi te yomi tamahu. Kokoro no uti ni mo nen-zi tamahe ri. Kaku yorodu ni tuke te yononaka wo omohi-suture ba, "Wakaki hito tote wokasiyaka naru koto mo koto ni naku, musubohore taru honzyau na' meri." to omohu. Katati no miru kahi ari, utukusiki ni, yorodu no toga mi-yurusi te, ake-kure no mimono ni si tari. Sukosi uti-warahi tamahu wori ha, medurasiku medetaki mono ni omohe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 5/17/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 5/17/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 5/17/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/17/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経