53 手習(大島本) |
TENARAHI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十七歳三月末頃から二十八歳の夏までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March at the age of 27 to summer at the age of 28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第二章 浮舟の物語 浮舟の小野山荘での生活 |
2 Tale of Ukifune A new life of Ukifune begins at Ono |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 第一段 僧都、小野山荘へ下山 |
2-1 Souzu comes to the mountain villa in Ono |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | うちはへかく扱ふほどに、 四、五月も過ぎぬ。いとわびしうかひなきことを思ひわびて、僧都の御もとに、 |
ずっとこうしてお世話するうちに、四月、五月も過ぎた。まことに心細く看護の効のないことに困りはてて、僧都のもとに、 |
それでもはかばかしくないことに気をもんで尼君は僧都の所へ手紙を書いた。 |
Uti-hahe kaku atukahu hodo ni, Si, Go-gwati mo sugi nu. Ito wabisiu kahinaki koto wo omohi-wabi te, Soudu no ohom-moto ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 「 なほ下りたまへ。この人、助けたまへ。さすがに今日までもあるは、死ぬまじかりける人を、 憑きしみ領じたるものの、去らぬにこそあめれ。 あが仏、京に出でたまはばこそはあらめ、ここまではあへなむ」 |
「もう一度下山してください。この人を、助けてください。何といっても今日まで生きていたのは、死ぬはずのない運命の人に、取り憑いて離れない物の怪が去らないのにちがいありません。どうかあなた様、京にお出になるのは無理でしょうが、ここまでは来てください」 |
ぜひ下山してくださいまして私の病人を助けてくださいまし。重態なようでしかも今日まで死なずにいることのできた人には、何かがきっと |
"Naho ori tamahe. Kono hito, tasuke tamahe. Sasuga ni kehu made mo aru ha, sinu mazikari keru hito wo, tuki simi ryau-zi taru mono no, sara nu ni koso ame re. Aga Hotoke, kyau ni ide tamaha ba koso ha ara me, koko made ha ahe na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | など、いみじきことを書き続けて、奉りたまへれば、 |
などと、切なる気持ちを書き綴って、差し上げなさると、 |
などと、切な願いを言い続けたものであった。 |
nado, imiziki koto wo kaki tuduke te, tatematuri tamahe re ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | 「 いとあやしきことかな。かくまでもありける人の命を、やがてとり捨ててましかば。さるべき契りありてこそは、我しも見つけけめ。試みに助け果てむかし。それに止まらずは、業尽きにけりと思はむ」 |
「まことに不思議なことだな。こんなにまで生きている人の命を、そのまま見捨ててしまったら。そうなるはずの縁があって、わたしが見つけたのであろう。ためしに最後まで助けてやろう。それでだめなら、命数が尽きたのだと思おう」 |
不思議なことである、今までまだ死なずにおられた人を、あの時うちやっておけばむろん死んだに違いない、前生の因縁があったからこそ、自分が見つけることにもなったのであろう、試みにどこまでも助けることに骨を折ってみよう、それでとめられない命であったなら、その人の業が尽きたのだとあきらめてしまおう |
"Ito ayasiki koto kana! Kaku made mo ari keru hito no inoti wo, yagate tori sute te masika ba. Saru-beki tigiri ari te koso ha, ware simo mituke keme. Kokoromi ni tasuke hate m kasi. Sore ni todomara zu ha, gou tuki ni keri to omoha m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | とて、下りたまひけり。 |
と思って、下山なさった。 |
と僧都は思って山をおりた。 |
tote, ori tamahi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | よろこび拝みて、月ごろのありさまを語る。 |
喜んで拝して、いく月日の間の様子を話す。 |
うれしく思った尼君は僧都を拝みながら今までの経過を話した。 |
Yorokobi wogami te, tuki-goro no arisama wo kataru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7 | 「 かく久しうわづらふ人は、 むつかしきこと、おのづからあるべきを、いささか衰へず、いときよげに、ねぢけたるところなくのみものしたまひて、限りと見えながらも、かくて生きたるわざなりけり」 |
「このように長い間患っている人は、見苦しい感じが、自然と出て来るものですが、少しも衰弱せず、とても美しげで、ひねくれたところもなくいらっしゃって、最期と見えながらも、こうして生きていることです」 |
「こんなに長わずらいをする人というものはどこかしら病人らしい気味悪さが自然にでてくるものですが、そんなことはないのでございますよ。少しも衰えたふうはなくて、きれいで清らかなのですよ。そうした人ですから危篤にも見えながら生きられるのでしょうね」 |
"Kaku hisasiu wadurahu hito ha, mutukasiki koto, onodukara aru beki wo, isasaka otorohe zu, ito kiyoge ni, nedike taru tokoro naku nomi monosi tamahi te, kagiri to miye nagara mo, kaku te iki taru waza nari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8 | など、おほなおほな泣く泣くのたまへば、 |
などと、本気になって泣きながらおっしゃるので、 |
尼君は真心から病人を愛して泣く泣く言うのであった。 |
nado, ohona-ohona naku-naku notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.9 | 「 見つけしより、珍かなる人のみありさまかな。いで」 |
「見つけた時から、めったにいないご様子の方であったな。さあ」 |
「はじめ見た時から珍しい |
"Mituke si yori, meduraka naru hito no mi-arisama kana! Ide." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.10 | とて、さしのぞきて見たまひて、 |
と言って、さし覗いて御覧になって、 |
と言い、僧都は病室をのぞいた。 |
tote, sasi-nozoki te mi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.11 | 「 げに、いと警策なりける人の御容面かな。功徳の報いにこそ、かかる容貌にも生ひ出でたまひけめ。 いかなる違ひめにて、そこなはれたまひけむ。もし、さにや、と聞き合はせらるることもなしや」 |
「なるほど、まことに優れたご容貌の方であるなあ。功徳の報恩で、このような器量にお生まれになったのであろう。どのような行き違いで、ひどいことにおなりになったのであろう。もしや、それか、と思い当たるような噂を聞いたことはありませんか」 |
「実際この人はすぐれた麗人だね。前生での |
"Geni, ito kyauzaku nari keru hito no ohom-youmei kana! Kudoku no mukuyi ni koso, kakaru katati ni mo ohi-ide tamahi keme. Ika naru tagahime nite, sokonahare tamahi kem. Mosi, sa ni ya, to kiki-ahase raruru koto mo nasi ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.12 | と問ひたまふ。 |
と尋ねなさる。 |
to tohi tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.13 | 「 さらに聞こゆることもなし。何か、初瀬の観音の賜へる人なり」 |
「まったく聞いたことありません。何の、初瀬の観音が授けてくださった人です」 |
「少しもございません。そんなことを考える必要はないと思います。私へ |
"Sarani kikoyuru koto mo nasi. Nanika, Hatuse no Kwanon no tamahe ru hito nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.14 | とのたまへば、 |
とおっしゃるので、 |
と尼君は言う。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.15 | 「 何か。それ縁に従ひてこそ導きたまはめ。種なきことは いかでか」 |
「いや何。宿縁によってお導きくださったものでしょう。因縁のないことはどうして起ころうか」 |
「それにはそれの順序がありますよ。虚無から人の出てくるものではないからね」 |
"Nanika. Sore en ni sitagahi te koso mitibiki tamaha me. Tane naki koto ha ikadeka." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.16 | など、のたまふが、あやしがりたまひて、修法始めたり。 |
などと、おっしゃるのが、不思議がりなさって、修法を始めた。 |
などと |
nado, notamahu ga, ayasigari tamahi te, syuhohu hazime tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 第二段 もののけ出現 |
2-2 An evil spirit appears from the young woman |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 「 朝廷の召しにだに従はず、深く籠もりたる山を出でたまひて、すぞろにかかる人のためになむ行ひ騷ぎたまふと、ものの聞こえあらむ、いと聞きにくかるべし」と思し、弟子どもも言ひて、「人に聞かせじ」と隠す。僧都、 |
「朝廷のお召しでさえお受けせず、深く籠もっている山をお出になって、わけもなくこのような人のために修法をなさっていると、噂が聞こえた時には、まことに聞きにくいことであろう」とお思いになり、弟子どももそう意見して、「人に聞かせまい」と隠す。僧都、 |
宮中からのお召しさえ辞退して山にこもっている自分が、だれとも知らぬ女のために自身で |
"Ohoyake no mesi ni dani sitagaha zu, hukaku komori taru yama wo ide tamahi te, suzoro ni kakaru hito no tame ni nam okonahi sawagi tamahu to, mono no kikoye ara m, ito kiki-nikukaru besi." to obosi, desi-domo mo ihi te, "Hito ni kikase zi." to kakusu. Soudu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 「 いで、あなかま。大徳たち。われ無慚の法師にて、忌むことの中に、破る戒は多からめど、女の筋につけて、まだ誹りとらず、過つことなし。六十に余りて、今さらに人のもどき負はむは、さるべきにこそはあらめ」 |
「まあ、お静かに。大徳たち。わたしは破戒無慚の法師で、戒律の中で、破った戒律は多かろうが、女の方面ではまだ非難されたことなく、過ったこともない。年齢も六十を過ぎて、今さら人の非難を受けるのは、前世の因縁なのであろう」 |
「静かにするがよい。自分は |
"Ide, anakama! Daitoko-tati. Ware muzan no hohusi nite, imu koto no naka ni, yaburu kai ha ohokara me do, womna no sudi ni tuke te, mada sosiri tora zu, ayamatu koto nasi. Roku-zihu ni amari te, imasara ni hito no modoki oha m ha, saru beki ni koso ha ara me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
と言った。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | 「 よからぬ人の、ものを便なく言ひなしはべる時には、 仏法の瑕となりはべることなり」 |
「口さがない連中が、何か不都合な事にとりなして言いました時には、仏法の恥となりますことです」 |
「悪口好きな人たちに悪く解釈され、評判が立ちますればそれが根本の仏法の |
"Yokara nu hito no, mono wo bin-naku ihi-nasi haberu toki ni ha, Buppohu no kizu to nari haberu koto nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | と、心よからず思ひて言ふ。 |
と、不機嫌に思って言う。 |
快く思っていない弟子はこんな答えをした。 |
to, kokoro-yokara zu omohi te ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6 | 「 この修法のほどにしるし見えずは」 |
「この修法によって効験が現れなかったら」 |
自分のする修法の間に効験のない場合には |
"Kono suhohu no hodo ni sirusi miye zu ha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.7 | と、いみじきことどもを誓ひたまひて、夜一夜加持したまへる暁に、 人に駆り移して、「 何やうのもの、かく人を惑はしたるぞ」と、ありさまばかり言はせまほしうて、弟子の阿闍梨、とりどりに加持したまふ。月ごろ、いささかも現はれざりつるもののけ、調ぜられて、 |
と、非常な決意をなさって、夜一晩中、加持なさった翌早朝に、人に乗り移らせて、「どのような物の怪がこのように人を惑わしていたのであろう」と、様子だけでも言わせたくて、弟子の阿闍梨が、交替で加持なさる。何か月もの間、少しも現れなかった物の怪が、調伏されて、 |
と非常な決心までもして夜明けまで続けた加持のあとで、他の人に |
to, imiziki koto-domo wo tikahi tamahi te, yo-hito-yo kadi si tamahe ru akatuki ni, hito ni kari-utusi te, "Nani-yau no mono, kaku hito wo madohasi taru zo?" to, arisama bakari iha se mahosiu te, desi no Azyari, tori-dori ni kadi si tamahu. Tuki-goro, isasaka mo arahare zari turu mononoke, teu-ze rare te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.8 | 「 おのれは、ここまで参うで来て、かく調ぜられたてまつるべき身にもあらず。 昔は行ひせし法師の、いささかなる世に 恨みをとどめて、漂ひありきしほどに、 よき女のあまた住みたまひし所に住みつきて、 かたへは失ひてしに、 この人は、心と世を恨みたまひて、我いかで死なむ、と言ふことを、夜昼のたまひしに たよりを得て、いと暗き夜、独りものしたまひしを取りてしなり。されど、 観音とざまかうざまにはぐくみたまひければ、この僧都に負けたてまつりぬ。今は、まかりなむ」 |
「自分は、ここまで参って、このように調伏され申すべき身ではない。生前は、修業に励んだ法師で、わずかにこの世に恨みを残して、中有にさまよっていたときに、よい女が大勢住んでいられた辺りに住み着いて、一人は失わせたが、この人は、自分から世を恨みなさって、自分は何とかして死にたい、ということを、昼夜おっしゃっていたのを手がかりと得て、まことに暗い夜に、一人でいらした時に奪ったのである。けれども、観音があれやこれやと加護なさったので、この僧都にお負け申してしまった。今は、立ち去ろう」 |
「自分はここへまで来て、こんなに懲らされるはずの者ではない。生きている時にはよく仏の勤めをした僧であったが、少しの |
"Onore ha, koko made maude ki te, kaku teu-ze rare tatematuru beki mi ni mo ara zu. Mukasi ha okonahi se si hohusi no, isasaka naru yo ni urami wo todome te, tadayohi ariki si hodo ni, yoki womna no amata sumi tamahi si tokoro ni sumi-tuki te, katahe ha usinahi te si ni, kono hito ha, kokoro to yo wo urami tamahi te, ware ikade sina m, to ihu koto wo, yoru-hiru notamahi si ni tayori wo e te, ito kuraki yo, hitori monosi tamahi si wo tori te si nari. Saredo, Kwanon tozama-kauzama ni hagukumi tamahi kere ba, kono Soudu ni make tatematuri nu. Ima ha, makari na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.9 | とののしる。 |
と声を立てる。 |
叫ぶようにこれは言われたのである。 |
to nonosiru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.10 | 「 かく言ふは、何ぞ」 |
「こう言うのは、何者だ」 |
「そう言う者はだれか」 |
"Kaku ihu ha, nani zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.11 | と問へば、憑きたる人、ものはかなきけにや、はかばかしうも言はず。 |
と問うが、乗り移らせた人が、力のないせいか、はっきりとも言わない。 |
と問うたが、移してあった人が単純な者でわきまえの少なかったせいか、それをつまびらかに言うことをなしえなかった。 |
to tohe ba, tuki taru hito, mono-hakanaki ke ni ya, haka-bakasiu mo iha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 第三段 浮舟、意識を回復 |
2-3 Ukifune returns to herself |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 正身の心地はさはやかに、いささかものおぼえて 見回したれば、一人見し人の顔はなくて、皆、老法師、ゆがみ衰へたる者のみ多かれば、 知らぬ国に来にける心地して、いと悲し。 |
ご本人の気分はさわやかになって、少し意識がはっきりして見回すと、一人も見たことのある顔はなくて、皆、老法師か腰の曲がった者ばかり多いので、知らない国に来たような気がして、実に悲しい。 |
|
Syauzimi no kokoti ha sahayaka ni, isasaka mono oboye te mi-mahasi tare ba, hitori mi si hito no kaho ha naku te, mina, oyi-hohusi, yugami otorohe taru mono nomi ohokare ba, sira nu kuni ni ki ni keru kokoti si te, ito kanasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | ありし世のこと思ひ出づれど、住みけむ所、 誰れと言ひし人とだに、たしかにはかばかしうもおぼえず。ただ、 |
以前のことを思い出すが、住んでいた所、何という名前であったかさえ、確かにはっきりとも思い出せない。ただ、 |
以前のことを思い出そうとするが、どこに住んでいたとも、何という人で自分があったかということすらしかと記憶から呼び出すことができないのであった。ただ |
Arisi yo no koto omohi-idure do, sumi kem tokoro, tare to ihi si hito to dani, tasika ni haka-bakasiu mo oboye zu. Tada, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | 「 我は、限りとて身を投げし人ぞかし。いづくに来にたるにか」とせめて思ひ出づれば、 |
「自分は、最期と思って身を投げた者である。どこに来たのか」と無理に思い出すと、 |
自分は |
"Ware ha, kagiri tote mi wo nage si hito zo kasi. Iduku ni ki ni taru ni ka?" to seme te omohi-idure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 「 いといみじと、ものを思ひ嘆きて、皆人の寝たりしに、妻戸を放ちて出でたりしに、風は烈しう、川波も荒う聞こえしを、独りもの恐ろしかりしかば、来し方行く先もおぼえで、簀子の端に 足をさし下ろしながら、行くべき方も惑はれて、 帰り入らむも中空にて、心強くこの世に亡せなむと思ひ立ちしを、『をこがましうて人に見つけられむよりは、鬼も何も食ひ失へ』と言ひつつ、 つくづくと居たりしを、いときよげなる男の寄り来て、『いざ、たまへ。おのがもとへ』と言ひて、 抱く心地のせしを、宮と聞こえし人のしたまふ、とおぼえしほどより、心地惑ひにけるなめり。 知らぬ所に据ゑ置きて、この男は消え失せぬ、と見しを、つひにかく 本意のこともせずなりぬる、と思ひつつ、 いみじう泣く、と思ひしほどに、その後のことは絶えて、いかにもいかにもおぼえず。 |
「とてもつらいことよと、悲しい思いを抱いて、皆が寝静まったときに、妻戸を開けて外に出たが、風が烈しく、川波も荒々しく聞こえたが、独りぼっちで恐かったので、過去や将来も分からず、簀子の端に足をさし下ろしながら、行くはずの所も迷って、引き返すのも中途半端で、気強くこの世から消えようと決心したが、『馬鹿らしく人に見つけられるよりは鬼でも何でも喰って亡くしてくれよ』と言いながら、つくづくと座っていたが、とても美しそうな男が近寄って来て、『さあ、いらっしゃい。わたしの所へ』と言って、抱く気がしたが、宮様と申し上げた方がなさる、と思われた時から、意識がはっきりしなくなったようだ。知らない所に置いて、この男は消えてしまった、と見えたが、とうとうこのように目的も果たせずになってしまった、と思いながら、ひどく泣いている、と思ったときから、その後のことはまったく、何もかも覚えていない。 |
生きていることがもう堪えがたく悲しいことに思われて、家の人の寝たあとで妻戸をあけて外へ出てみると、風が強く吹いていて川波の音響も荒かったため、一人であることが恐ろしくなり、前後も考えて見ず縁側から足を下へおろしたが、どちらへ向いて行ってよいかもわからず、今さら家の中へ帰って行くこともできず、気強く自殺を思い立ちながら、人に見つけられるような恥にあうよりは鬼でも何でも自分を食べて死なせてほしいと口で言いながらそのままじっと縁側によりかかっていた所へ、きれいな男が出て来て、「さあおいでなさい私の所へ」と言い、抱いて行く気のしたのを、宮様と申した方がされることと自分は思ったが、そのまま失心したもののようであった。知らぬ所へ自分をすわらせてその男は消えてしまったのを見て、自分はこんなことになって、目的とした自殺も遂げられなかったと思い、ひどく泣いていたと思うがそれからのことは何も記憶にない。 |
"Ito imizi to, mono wo omohi-nageki te, mina-hito no ne tari si ni, tumado wo hanati te ide tari si ni, kaze ha hagesiu, kaha-nami mo arau kikoye si wo, hitori mono-osorosikari sika ba, kisikata-yukusaki mo oboye de, sunoko no hasi ni asi wo sasi-orosi nagara, yuku beki kata mo madoha re te, kaheri ira m mo naka-zora nite, kokoro-duyoku konoyo ni use na m to omohi-tati si wo, 'Wokogamasiu te hito ni mituke rare m yori ha, oni mo nani mo kuhi usinahe.' to ihi tutu, tuku-duku to wi tari si wo, ito kiyoge naru wotoko no yori-ki te, 'Iza, tamahe. Onoga moto he.' to ihi te, idaku kokoti no se si wo, Miya to kikoye si hito no si tamahu, to oboye si hodo yori, kokoti-madohi ni keru na' meri. Sira nu tokoro ni suwe-oki te, kono wotoko ha kiye-use nu, to mi si wo, tuhi ni kaku ho'i no koto mo se zu nari nuru, to omohi tutu, imiziu naku, to omohi si hodo ni, sono noti no koto ha taye te, ikanimo-ikanimo oboye zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | 人の言ふを聞けば、 多くの日ごろも経にけり。 いかに憂きさまを、知らぬ人に扱はれ見えつらむ、と恥づかしう、 つひにかくて生き返りぬるか」 |
人が言うのを聞くと、たくさんの日数を経てしまった。どのように嫌な様子を、知らない人にお世話されたのであろう、と恥ずかしく、とうとうこうして生き返ってしまったのか」 |
今人々の語っているのを聞くとそれから多くの日がたったようである。どんなに醜態を人の前にさらした自分で、どんなに知らぬ人の |
Hito no ihu wo kike ba, ohoku no higoro mo he ni keri. Ikani uki sama wo, sira nu hito ni atukaha re miye tu ram, to hadukasiu, tuhini kaku te iki-kaheri nuru ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6 | と思ふも口惜しければ、いみじうおぼえて、なかなか、沈みたまひつる日ごろは、うつし心もなきさまにて、ものいささか参る事もありつるを、つゆばかりの湯をだに参らず。 |
と思うのも残念なので、ひどく悲しく思われて、かえって、沈んでいらした日ごろは、正気もない様子で、何か食物も少し召し上がることもあったが、露ほどの薬湯でさえお飲みにならない。 |
と思われるのが残念で、かえって失心状態であった今日までは意識してではなくものもときどきは食べてきた浮舟の姫君であったが、今は少しの湯さえ飲もうとしない。 |
to omohu mo kutiwosikere ba, imiziu oboye te, naka-naka, sidumi tamahi turu higoro ha, utusi-gokoro naki sama nite, mono isasaka mawiru koto mo ari turu wo, tuyu bakari no yu wo dani mawira zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 第四段 浮舟、五戒を受く |
2-4 Ukifune is given a Buddhist five admonition |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | 「 いかなれば、かく ★頼もしげなくのみはおはするぞ。うちはへぬるみなどしたまへることは冷めたまひて、さはやかに見えたまへば、うれしう思ひきこゆるを」 |
「どうして、このように頼りなさそうにばかりいらっしゃるのですか。ずっと熱がおありだったのは下がりなさって、さわやかにお見えになるので、嬉しくお思い申し上げていましたのに」 |
「どうしてそんなにたよりないふうをばかりお見せになりますか。もうずっと発熱することもなくなって、病苦はあなたから去ったように見えるのを私は喜んでいますのに」 |
"Ika nare ba, kaku tanomosige naku nomi ha ohasuru zo. Utihahe nurumi nado si tamahe ru koto ha same tamahi te, sahayaka ni miye tamahe ba, uresiu omohi kikoyuru wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 | と、泣く泣く、たゆむ折なく添ひゐて扱ひきこえたまふ。 ある人びとも、あたらしき御さま容貌を見れば、心を尽くしてぞ惜しみまもりける。 心には、「なほいかで死なむ」とぞ 思ひわたりたまへど、 さばかりにて、生き止まりたる人の命なれば、 いと執念くて、やうやう頭もたげたまへば、もの参りなどしたまふにぞ、 なかなか面痩せもていく。 いつしかとうれしう思ひきこゆるに、 |
と、泣きながら、気を緩めることなく付き添ってお世話申し上げなさる。仕える女房たちも、惜しいお姿や容貌を見ると、誠心誠意惜しんで看病したのであった。内心では、「やはり何とかして死にたい」と思い続けていらしたが、あれほどの状態で、生き返った人の命なので、とてもねばり強くて、だんだんと頭もお上げになったので、食物を召し上がりなさるが、かえって容貌もひきしまって行く。はやく好くなってほしいと嬉しくお思い申し上げていたところ、 |
こう言って、尼夫人という緊張した看病人がそばを離れず世話をしていた。他の女房たちも惜しい |
to, naku-naku, tayumu wori naku sohi wi te atukahi kikoye tamahu. Aru hito-bito mo, atarasiki ohom-sama katati wo mire ba, kokoro wo tukusi te zo, wosimi mamori keru. Kokoro ni ha, "Naho ikade sina m." to zo omohi watari tamahe do, sabakari nite, iki tomari taru hito no inoti nare ba, ito sihuneku te, yau-yau kasira motage tamahe ba, mono mawiri nado si tamahu ni zo, naka-naka omo-yase mote-iku. Itusika to uresiu omohi kikoyuru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3 | 「 尼になしたまひてよ。さてのみなむ生くやうもあるべき」 |
「尼にしてください。そうしたら生きて行くようもありましょう」 |
「尼にしてくださいませ、そうなってしまえば生きてもよいという気になれるでしょうから」 |
"Ama ni nasi tamahi te yo. Sate nomi nam iku yau mo aru beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.4 | とのたまへば、 |
とおっしゃるので、 |
と言い、浮舟は出家を望んだ。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.5 | 「 いとほしげなる御さまを。いかでか、さはなしたてまつらむ」 |
「あたら惜しいお身を。どうして、そのように致せましょう」 |
「いたいたしいあなたをどうしてそんなことにされますか」 |
"Itohosige naru ohom-sama wo. Ikade ka, saha nasi tatematura m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.6 | とて、 ただ頂ばかりを削ぎ、五戒ばかりを受けさせたてまつる。心もとなけれど、 もとよりおれおれしき人の心にて、えさかしく強ひてものたまはず。僧都は、 |
と言って、ただ頂の髪だけを削いで、五戒だけを受けさせ申し上げる。不安であるが、もともとはきはきしない性分で、さし出て強くもおっしゃらない。僧都は、 |
と尼君は言い、頭の頂の髪少しを切り、五戒だけを受けさせた。それだけで安心はできないのであるが、 |
tote, tada itadaki bakari wo sogi, go-kai bakari wo uke sase tatematuru. Kokoro-motonakere do, motoyori ore-oresiki hito no kokoro nite, e sakasiku sihite mo notamaha zu. Soudu ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7 | 「 今は、かばかりにて、いたはり止めたてまつりたまへ」 |
「今はもう、このくらいにしておいて、看病して差し上げなさい」 |
「もう大丈夫です。このくらいのところで快癒を御仏におすがりすることはやめたらいいでしょう」 |
"Ima ha, kabakari nite, itahari yame tatematuri tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8 | と言ひ置きて、登りたまひぬ。 |
と言い置いて、山へ登っておしまいになった。 |
と言い残して寺へ帰った。 |
to ihi-oki te, nobori tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 第五段 浮舟、素性を隠す |
2-5 Ukifune hides her identity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 | 「 夢のやうなる人を見たてまつるかな」と尼君は喜びて、せめて起こし据ゑつつ、御髪手づから削りたまふ。 さばかりあさましう、ひき結ひてうちやりたりつれど、いたうも乱れず、解き果てたれば、つやつやとけうらなり。 ▼ 一年足らぬ九十九髪多かる所にて、目もあやに、いみじき天人の天降れるを見たらむやうに思ふも、危ふき心地すれど、 |
「夢に見たような人をお世話申し上げることだわ」と尼君は喜んで、無理に起こして座らせながら、お髪をご自身でお梳かしになる。あのように驚きあきれ、結んでおいたが、ひどくは乱れず、解き放ってみると、つやつやとして美しい。白髪の人の多い所なので、目もあざやかに、美しい天人が地上に下りたのを見たように思うのも、不安な気がするが、 |
予期もせぬ夢のような人が現われたものであるというように尼君は恢復期の浮舟を喜んで、しいて勧めて起こし、髪を自身で |
"Yume no yau naru hito wo mi tatematuru kana!" to Ama-Gimi ha yorokobi te, semete okosi suwe tutu, mi-gusi tedukara keduri tamahu. Sabakari asamasiu, hiki-yuhi te uti-yari tari ture do, itau mo midare zu, toki-hate tare ba, tuya-tuya to keura nari. Hito-tose tara nu tukumo-gami ohokaru tokoro nite, me mo aya ni, imiziki tennin no ama kudare ru wo mi tara m yau ni omohu mo, ayahuki kokoti sure do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2 | 「 などか、いと心憂く、かばかりいみじく思ひきこゆるに、御心を立てては見えたまふ。 いづくに誰れと聞こえし人の、さる所にはいかでおはせしぞ」 |
「どうして、とても情けなく、こんなにたいそうお世話申し上げていますのに、強情をはっていらっしゃるのですか。どこの誰と申し上げた方が、そのような所にどうしておいでになったのですか」 |
「なぜあなたに人情がわからないのでしょう。私がどんなにあなたを愛しているかしれないのに、物隠しをしてばかりおいでになりますね。どこの何という家の方で、なぜ宇治というような所へ来ておいでになりましたの」 |
"Nadoka, ito kokoro-uku, kabakari imiziku omohi kikoyuru ni, mi-kokoro wo tate te ha miye tamahu. Idukuni tare to kikoye si hito no, saru tokoro ni ha ikade ohase si zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3 | と、せめて問ふを、いと恥づかしと思ひて、 |
と、しいて尋ねるのを、とても恥ずかしいと思って、 |
尼君から熱心に聞かれて浮舟の姫君は恥ずかしく思った。 |
to, semete tohu wo, ito hadukasi to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4 | 「 あやしかりしほどに、皆忘れたるにやあらむ、ありけむさまなどもさらにおぼえはべらず。 ただ、ほのかに思ひ出づることとては、ただ、いかでこの世にあらじと思ひつつ、夕暮ごとに端近くて眺めしほどに、前近く大きなる木のありし下より、人の出で来て、率て行く心地なむせし。それより他のことは、 我ながら、誰れともえ思ひ出でられはべらず」 |
「意識を失っている間に、すっかり忘れてしまったのでしょうか、以前の様子などもまったく覚えておりません。ただ、かすかに思い出すこととしては、ただ、何とかしてこの世から消えたいと思いながら、夕暮になると端近くで物思いをしていたときに、前の近くにある大きな木があった下から、人が出て来て、連れて行く気がしました。それ以外のことは、自分自身でも、誰とも思い出すことができません」 |
「重くわずらっておりましたうちに皆忘れてしまったのでしょうか、どんなふうにどこにいたかを少しも覚えていないのですよ。ただね、私は夕方ごとに庭へ近い所に出て寂しい |
"Ayasikari si hodo ni, mina wasure taru ni ya ara m, ari kem sama nado mo sarani oboye habera zu. Tada, honoka ni omohi-iduru koto tote ha, tada, ikade konoyo ni ara zi to omohi tutu, yuhugure goto ni hasi tikaku te nagame si hodo ni, mahe tikaku ohoki naru ki no ari si sita yori, hito no ide-ki te, wi te iku kokoti nam se si. Sore yori hoka no koto ha, ware nagara, tare to mo e omohi-ide rare habera zu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5 | と、 いとらうたげに言ひなして、 |
と、とてもかわいらしげに言って、 |
と姫君は |
to, ito rautage ni ihi-nasi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.6 | 「 世の中に、なほありけりと、いかで人に知られじ。聞きつくる人もあらば、いといみじくこそ」 |
「この世に、やはり生きていたと、何とか人に知られたくない。聞きつける人がいたら、とても悲しい」 |
「私がまだ生きているということをだれにも知られたくないと思います。それを人が知ってしまっては悲しゅうございます」 |
"Yononaka ni, naho ari keri to, ikade hito ni sira re zi. Kiki-tukuru hito mo ara ba, ito imiziku koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.7 | とて泣いたまふ。あまり問ふをば、苦しと思したれば、え問はず。 かぐや姫を見つけたりけむ竹取の翁よりも、珍しき心地するに、「いかなるものの隙に消え失せむとすらむ」と、静心なくぞ思しける。 |
と言ってお泣きになる。あまり尋ねるのを、つらいとお思いなので、尋ねることもできない。かぐや姫を見つけた竹取の翁よりも、珍しい気がするので、「どのような何かの機会に姿が消え失せてしまうのか」と、落ち着かない気持ちでいた。 |
と告げて泣いた。あまり聞かれるのが苦しいふうであったから尼君はそれ以上を尋ねようとしなかった。かぐや姫を竹の中に見つけた |
tote nai tamahu. Amari tohu wo ba, kurusi to obosi tare ba, e toha zu. Kaguya-Hime wo mituke tari kem Taketori-no-Okina yori mo, medurasiki kokoti suru ni, "Ika naru mono no hima ni kiye-use m to su ram." to, sidu-kokoro naku zo obosi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 第六段 小野山荘の風情 |
2-6 A landscape and feeling of Ono villa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 | この主人もあてなる人なりけり。 娘の尼君は、上達部の北の方にてありけるが、その人亡くなりたまひてのち、娘ただ一人をいみじくかしづきて、よき君達を婿にして思ひ扱ひけるを、その娘の君の亡くなりにければ、心憂し、いみじ、と思ひ入りて、形をも変へ、かかる山里には住み始めたりけるなり。 |
ここの主人も高貴な方であった。娘の尼君は、上達部の北の方であったが、その方がお亡くなりになって後、娘をただ一人大切にお世話して、立派な公達を婿に迎えて大切にしていたが、その娘が亡くなってしまったので、情けない、悲しい、と思いつめて、尼姿になって、このような山里に住み始めたのであった。 |
この家の人も貴族であった。若いほうの尼君は高級官吏の妻であったが、 |
Kono aruzi mo ate naru hito nari keri. Musume no Ama-Gimi ha, kamdatime no kitanokata nite ari keru ga, sono hito nakunari tamahi te noti, musume tada hitori wo imiziku kasiduki te, yoki kim-dati wo muko ni si te omohi atukahi keru wo, sono Musume-no-Kimi no nakunari ni kere ba, kokoro-usi, imizi, to omohi-iri te, katati wo mo kahe, kakaru yama-zato ni ha sumi hazime tari keru nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2 | 「 世とともに 恋ひわたる人の形見にも、思ひよそへつべからむ人をだに見出でてしがな」、つれづれも心細きままに思ひ嘆きけるを、かく、 おぼえぬ人の、容貌けはひも まさりざまなるを得たれば、うつつのことともおぼえず、あやしき心地しながら、うれしと思ふ。 ねびにたれど、いときよげによしありて、ありさまもあてはかなり。 |
「歳月とともに恋い慕っていた娘の形見にでも、せめて思いよそえられるような人を見つけたい」と、所在ない心細い思いで嘆いていたところ、このように、思いがけない人で、器量や感じも優っているような人を得たので、現実のこととも思われず、不思議な気がしながらも、嬉しいと思う。年は召しているが、とても美しそうで嗜みがあり、態度も上品である。 |
忘れる時もなく恋しい娘の形見とも思うことのできる人を見つけたいとつれづれなあまりに願っていた人が、意外な、 |
"Yo to tomoni kohi wataru hito no katami ni mo, omohi yosohe tu bekara m hito wo dani mi-ide te si gana!", ture-dure mo kokoro-bosoki mama ni omohi-nageki keru wo, kaku, oboye nu hito no, katati kehahi mo masari zama naru wo e tare ba, ututu no koto to mo oboye zu, ayasiki kokoti nagara, uresi to omohu. Nebi ni tare do, ito kiyoge ni yosi ari te, arisama mo atehaka nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
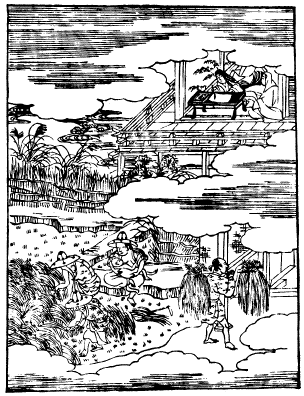 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.3 | 昔の山里よりは、 水の音もなごやかなり。造りざま、ゆゑある所、木立おもしろく、前栽もをかしく、ゆゑを尽くしたり。 秋になりゆけば、空のけしきもあはれなり。門田の稲刈るとて、所につけたる ものまねびしつつ、 若き女どもは、歌うたひ興じあへり。引板ひき鳴らす音もをかしく、 見し東路のことなども思ひ出でられて。 |
昔の山里よりは、川の音も物やわらかである。家の造りは、風流な所の、木立も趣があり、前栽なども興趣あり、風流をし尽くしている。秋になって行くと、空の様子もしみじみとしている。門田の稲を刈ろうとして、その土地の者の真似をしては、若い女房たちが、民謡を謡いながらおもしろがっていた。引板を鳴らす音もおもしろく、かつて見た東国のことなども思い出されて。 |
ここは浮舟のいた宇治の山荘よりは水の音も静かで優しかった。庭の作りも雅味があって、木の姿が皆よく、前の植え込みの |
Mukasi no yamazato yori ha, midu no oto mo nagoyaka nari. Tukuri-zama, yuwe aru tokoro, kodati omosiroku, sensai mo wokasiku, yuwe wo tukusi tari. Aki ni nari-yuke ba, sora no kesiki mo ahare nari. Kado-ta no ine karu tote, tokoro ni tuke taru mono manebi si tutu, wakaki womna-domo ha, uta utahi kyou-zi ahe ri. Hita hiki-narasu oto mo wokasiku, mi si Adumadi no koto nado mo omohi-ide rare te. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.4 | かの夕霧の御息所のおはせし山里よりは、今すこし入りて、山に片かけたる家なれば、 松蔭茂く、風の音もいと心細きに、つれづれに行ひをのみしつつ、いつとなくしめやかなり。 |
あの夕霧の御息所がおいでになった山里よりは、もう少し奥に入って、山の斜面に建ててある家なので、松の木蔭が鬱蒼として、風の音もまことに心細いので、することもなく勤行ばかりして、いつとなくひっそりとしている。 |
同じ小野ではあるが夕霧の |
Kano Yuhugiri no Miyasumdokoro no ohase si yamazato yori ha, ima-sukosi iri te, yama ni kata-kake taru ihe nare ba, matu-kage sigeku, kaze no oto mo ito kokoro-bosoki ni, ture-dure ni okonahi wo nomi si tutu, itu to naku simeyaka nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 第七段 浮舟、手習して述懐 |
2-7 Ukifune composes wala with thinking her life |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1 | 尼君ぞ、月など明き夜は、琴など弾きたまふ。少将の尼君などいふ人は、琵琶弾きなどしつつ遊ぶ。 |
尼君は、月などの明るい夜は、琴などをお弾きになる。少将の尼君などという女房は、琵琶を弾いたりして遊ぶ。 |
尼君は月の明るい夜などに琴を |
Ama-Gimi zo, tuki nado akaki yo ha, kin nado hiki tamahu. Seusyau-no-Amagimi nado ihu hito ha, biha hiki nado si tutu asobu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2 | 「 かかるわざはしたまふや。つれづれなるに」 |
「このようなことはなさいますか。何もすることがないので」 |
「音楽をなさいますか。でなくては退屈でしょう」 |
"Kakaru waza ha si tamahu ya? Ture-dure naru ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3 | など言ふ。 昔も、あやしかりける身にて、心のどかに、「さやうのことすべきほどもなかりしかば、いささかをかしきさまならずも生ひ出でにけるかな」と、かくさだ過ぎにける人の、心をやるめる折々につけては、思ひ出づるを、「 あさましくものはかなかりける」と、我ながら口惜しければ、手習に、 |
などと言う。昔も、賤しかった身の上で、のんびりと、「そのようなことをする境遇でもなかったので、少しも風流なところもなく成長したことよ」と、このように盛りを過ぎた人が、心を晴らしているような時々につけては、思い出すが、「何とも言いようのない身の上であった」と、自分ながら残念なので、手習いに、 |
と尼君は姫君に言っていた。昔も母の行く国々へつれまわられていて、静かにそうしたものの |
nado ihu. Mukasi mo, ayasikari keru mi nite, kokoro nodoka ni, "Sayau no koto su beki hodo mo nakari sika ba, isasaka wokasiki sama nara zu mo ohi-ide ni keru kana!" to, kaku sada sugi ni keru hito no, kokoro wo yaru meru wori-wori ni tuke te ha, omohi-iduru wo, "Asamasiku mono hakanakari keru." to, ware nagara kutiwosikere ba, tenarahi ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4 | 「 身を投げし涙の川の早き瀬を |
「涙ながらに身を投げたあの川の早い流れを |
身を投げし涙の川の早き瀬に |
"Mi wo nage si namida no kaha no hayaki se wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.5 | しがらみかけて誰れか止めし」 |
堰き止めて誰がわたしを救い上げたのでしょう」 |
しがらみかけてたれかとどめし |
sigarami kake te tareka todome si |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.6 | 思ひの外に心憂ければ、行く末もうしろめたく、疎ましきまで思ひやらる。 |
思いがけないことに情けないので、将来も不安で、疎ましいまでに思われる。 |
こんな歌を書いていた。よいことの拾い出せない過去から思えば将来も同じ薄命道を続けて歩んで行くだけであろうと自身がうとましくさえなった。 |
Omohi no hoka ni kokoro-ukere ba, yuku-suwe mo usirometaku, utomasiki made omohi-yara ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.7 | 月の明かき夜な夜な、 老い人どもは艶に歌詠み、いにしへ思ひ出でつつ、さまざま物語などするに、いらふべきかたもなければ、つくづくとうち眺めて、 |
月の明るい夜毎に、老人たちは優雅に和歌を詠み、昔を思い出しながら、いろいろな話などをするが、答えることもできないので、つくづくと物思いに沈んで、 |
月の明るい夜ごとに老いた女たちは気どった歌を |
Tuki no akaki yona-yona, oyibito-domo ha en ni uta yomi, inisihe omohi-ide tutu, sama-zama monogatari nado suru ni, irahu beki kata mo nakere ba, tuku-duku to uti-nagame te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.8 | 「 我かくて憂き世の中にめぐるとも |
「わたしがこのように嫌なこの世に生きているとも |
われかくて浮き世の中にめぐるとも |
"Ware kaku te uki yononaka ni meguru tomo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.9 | 誰れかは知らむ月の都に」 |
誰が知ろうか、あの月が照らしている都の人で」 |
たれかは知らん月の都に |
tare-kaha sira m tuki no miyako ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.10 | 今は限りと思ひしほどは、恋しき人多かりしかど、こと人びとはさしも思ひ出でられず、ただ、 |
今を最期と思い切ったときは、恋しい人が多かったが、その他の人びとはそれほども思い出されず、ただ、 |
こんな歌も詠まれた。自殺を決意した時には、もう一度逢いたく思った人も多かったが、他の人々のことはそう思い出されもしない。 |
Ima ha kagiri to omohi si hodo ha, kohisiki hito ohokari sika do, koto hito-bito ha sasimo omohi-ide rare zu, tada, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.11 | 「 親いかに惑ひたまひけむ。乳母、よろづに、いかで人なみなみになさむと思ひ焦られしを、いかにあへなき心地しけむ。いづくにあらむ。我、世にあるものとは いかでか知らむ」 |
「母親がどんなにお嘆きになったろう。乳母が、いろいろと、何とか一人前にしようと一生懸命であったが、どんなにがっかりしたろう。どこにいるのだろう。わたしが、生きていようとはどうして知ろう」 |
母がどんなに悲しんだことであろう。 |
"Oya ikani madohi tamahi kem? Menoto, yorodu ni, ikade hito nami-nami ni nasa m to omohi-ira re si wo, ikani ahe-naki kokoti si kem. Iduku ni ara m? Ware, yo ni aru mono to ha ikadeka sira m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.12 | 同じ心なる人もなかりしままに、よろづ隔つることなく語らひ見馴れたりし 右近なども、折々は思ひ出でらる。 |
同じ気持ちの人もいなかったが、何事も隠すことなく相談し親しくしていた右近なども、時々は思い出される。 |
気の合った人もないままに、主従とはいえ隔てのない友情を持ち合ったあの |
Onazi kokoro naru hito mo nakari si mama ni, yorodu hedaturu koto naku katarahi mi-nare tari si Ukon nado mo, wori-wori ha omohi-ide raru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 第八段 浮舟の日常生活 |
2-8 Ukifune's daily life at Ono villa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.1 | 若き人の、かかる 山里に、今はと思ひ絶え籠もるは、難きわざなりければ、ただいたく年経にける尼、七、八人ぞ、常の人にてはありける。それらが娘孫やうの者ども、京に宮仕へするも、 異ざまにてあるも、時々ぞ来通ひける。 |
若い女で、このような山里に、もうこれまでと思いを断ち切って籠もるのは、難しいことなので、ただひどく年をとった尼、七、八人が、いつも仕えていた人であった。その人たちの娘や孫のような者たちで、京で宮仕えするものや、結婚している者が、時々行き来するのであった。 |
若い女がこうした山の家に世の中をあきらめて暮らすことは不可能なことであったから、そうした女房はいず、長く使われている尼姿の七、八人だけが常の女房であった。その人たちの娘とか孫とかいう人らで、京で宮仕えをしているのも、また普通の家庭にいるのも時々出て来ることがあった。 |
Wakaki hito no, kakaru yamazato ni, ima ha to omohi-taye komoru ha, kataki waza nari kere ba, tada itaku tosi he ni keru ama, siti, hati-nin zo, tune no hito nite ha ari keru. Sorera ga musume mago yau no mono-domo, kyau ni miya-dukahe suru mo, koto-zama nite aru mo, toki-doki zo ki kayohi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2 | 「 かやうの人につけて、見しわたりに行き通ひ、おのづから、世にありけりと 誰れにも誰れにも聞かれたてまつらむこと、いみじく恥づかしかるべし。いかなるさまにてさすらへけむ」 |
「このような人がいることにつけて、以前見た近辺に出入りして、自然と、生きていたとどちら様にも聞かれ申すことは、ひどく恥ずかしいことであろう。どのような様子でさすらっていていたのだろう」 |
そうした人が宇治時代の関係者の所へ出入りすることもあって、自分の生きていることが宮にも大将にも知れることになったならきわめて恥ずかしいことである、 |
"Kayau no hito ni tuke te, mi si watari ni iki-kayohi, onodukara, yo ni ari keri to tare ni mo tare ni mo kika re tatematura m koto, imiziku hadukasikaru besi. Ika naru sama nite sasurahe kem?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.3 | など、 思ひやり世づかずあやしかるべきを思へば、かかる人びとに、かけても見えず。ただ 侍従、こもきとて、尼君のわが人にしたりける二人をのみぞ、 この御方に言ひ分けたりける。 みめも心ざまも、 昔見し都鳥に ★似たるはなし。何事につけても、「 世の中にあらぬ所はこれにやあらむ ★」とぞ、かつは思ひなされける。 |
などと、想像されて並外れたみすぼらしい有様を思うにちがいないのを思うと、このような人びとに、少しも姿を見せない。ただ、侍従と、こもきといって、尼君が私的に使っている二人だけを、この御方に特別に言って分けておいたのだった。容貌も気立ても、昔見た都人に似た者はいない。何事につけても、「世の中で身を隠す所はここであろうか」と、一方では思われるのであった。 |
ここへ来た経路についてどんな悪い想像をされるかもしれぬ、過去において正しく踏みえた人の道ではなかったのであるからと思う |
nado, omohi-yari yoduka zu ayasikaru beki wo omohe ba, kakaru hito-bito ni, kakete mo miye zu. Tada Zizyuu, Komoki tote, Ama-Gimi no waga hito ni si tari keru hutari wo nomi zo, kono Ohom-Kata ni ihi-wake tari keru. Mime mo kokoro-zama mo, mukasi mi si miyako-dori ni ni taru ha nasi. Nani-goto ni tuke te mo, "Yononaka ni ara nu tokoro ha kore ni ya ara m?" to zo, katu ha omohi-nasa re keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.4 | かくのみ、人に知られじと忍びたまへば、「 まことにわづらはしかるべきゆゑある人にもものしたまふらむ」とて、詳しきこと、ある人びとにも知らせず。 |
こうしてばかり、人には知られまいと隠れていらっしゃるので、「ほんとうに厄介な理由のある人でいらっしゃるのだろう」と思って、詳しいことは、仕えている女房にも知らせない。 |
こんなふうに人にかくれてばかりいる浮舟を、この人の言うとおりにめんどうなつながりを世間に持っていて、それからのがれたい |
Kaku nomi, hito ni sira re zi to sinobi tamahe ba, "Makoto ni wadurahasikaru beki yuwe aru hito ni mo monosi tamahu ram." tote, kuhasiki koto, aru hito-bito ni mo sira se zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 5/17/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 5/17/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 5/17/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/17/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経