52 蜻蛉(大島本) |
KAGEROHU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十七歳三月末頃から秋頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March to fall at the age of 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第五章 薫の物語 明石中宮の女宮たち |
5 Tale of Kaoru Akashi-Empress' daughters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 第一段 薫と小宰相の君の関係 |
5-1 Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1 | 后の宮の、御軽服のほどは、なほかくておはしますに、 二の宮なむ式部卿になりたまひにける。 重々しうて、常にしも参りたまはず。 この宮は、さうざうしくものあはれなるままに、 一品の宮の御方を慰め所にしたまふ。 よき人の容貌をも、えまほに見たまはぬ、残り多かり。 |
后の宮が、御軽服の間は、やはり里下がりしていらっしゃるうちに、二の宮が式部卿におなりになった。重々しくなって、常には参上なさらない。この宮は、もの寂しくて何となく悲しい気分のまま、一品の宮のお側を慰め所としていらっしゃる。器量の良い女房の顔で、まだよく御覧にならない者が、多く残っていた。 |
|
Kisaki-no-Miya no, ohom-kyaubuku no hodo ha, naho kakute ohasimasu ni, Ni-no-Miya nam Sikibukyau ni nari tamahi ni keru. Omo-omosiu te, tune ni simo mawiri tamaha zu. Kono Miya ha, sau-zausiku mono ahare naru mama ni, Ippon-no-Miya no Ohom-Kata wo nagusame-dokoro ni si tamahu. Yoki hito no katati wo mo, e maho ni mi tamaha nu, nokori ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2 | 大将殿の、からうして、いと忍びて語らはせたまふ 小宰相の君といふ人の、容貌などもきよげなり、心ばせある方の人と思されたり。同じ琴を掻きならす、爪音、撥音も、人にはまさり、文を書き、ものうち言ひたるも、よしあるふしをなむ添へたりける。 |
大将殿が、やっとのことで、たいそうこっそりと親しくなさっている小宰相の君という女房で、器量なども美しげで、気立ての良い人とお思いであった。同じ琴をかき鳴らす、その爪音や、撥の音が、誰にもまさって、手紙を書き、何か言うのも、風流な事が加わっているのだった。 |
右大将が多数の女房の中で深い交際をしている |
Daisyau-dono no, karausite, ito sinobi te kataraha se tamahu Ko-Zaisyau-no-Kimi to ihu hito no, katati nado mo kiyoge nari, kokoro-base aru kata no hito to obosa re tari. Onazi koto wo kaki-narasu, tuma-oto, bati-oto mo, hito ni ha masari, humi wo kaki, mono uti-ihi taru mo, yosi aru husi wo nam sohe tari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.3 | この宮も、年ごろ、いといたきものにしたまひて、例の、 言ひ破りたまへど、「 などか、さしもめづらしげなくはあらむ」と、 心強くねたきさまなるを、 まめ人は、「 すこし人よりことなり」と思すになむありける。かくもの思したるも 見知りければ、忍びあまりて聞こえたり。 |
この宮も、長年、とても関心を寄せていらっしゃって、いつものように、悪口おっしゃるが、「どうして、そのようにありふれた女でいようか」と、気強くて従わないのを、真面目人間は、「少しは他の女と違っている」とお思いなのであった。このように物思いに沈んでいらっしゃるのを知っていたので、思い余って差し上げた。 |
兵部卿の宮も長くこの人に恋を持っておいでになるのであって、例の |
Kono Miya mo, tosi-goro, ito itaki mono ni si tamahi te, rei no, ihi-yaburi tamahe do, "Nadoka, sasimo medurasige naku ha ara m." to, kokoro-duyoku netaki sama naru wo, mame-bito ha, "Sukosi hito yori koto nari." to obosu ni nam ari keru. Kaku mono obosi taru mo mi-siri kere ba, sinobi amari te kikoye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.4 | 「 あはれ知る心は人におくれねど |
「お悲しみを知る心は誰にも負けませんが |
哀れ知る心は人におくれねど |
"Ahare siru kokoro ha hito ni okure ne do |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.5 | 数ならぬ身に消えつつぞ経る |
一人前でもない身では遠慮して消え入らんばかりに過ごしております |
数ならぬ身に消えつつぞ |
kazu nara nu mi ni kiye tutu zo huru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.6 | 代へたらば」 |
亡くなった方と入れ替れるものでたら」 |
私が代わって死んでおあげすればよかったように思われます。 |
Kahe tara ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.7 | と、ゆゑある紙に書きたり。ものあはれなる夕暮、しめやかなるほどを、いとよく推し量りて言ひたるも、憎からず。 |
と、由緒ある紙に書いてあった。何となくしみじみとした夕暮で、しんみりした時に、まことによく推察して言って来たのも、気が利いている。 |
と感じのよい色の紙に書かれてあった。身にしむような夕方時のしめっぽい気持ちをよく察して |
to, yuwe aru kami ni kaki tari. Mono ahare naru yuhugure, simeyaka naru hodo wo, ito yoku osihakari te ihi taru mo, nikukara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.8 | 「 常なしとここら世を見る憂き身だに |
「無常の世を長年見続けて来たわが身でさえ |
つれなしとここら世を見るうき身だに |
"Tune nasi to kokora yo wo miru uki mi dani |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.9 | 人の知るまで嘆きやはする |
人が見咎めるまで嘆いてはいないつもりでしたが |
人の知るまで歎きやはする |
hito no siru made nageki ya ha suru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.10 | このよろこび、あはれなりし折からも、いとどなむ」 |
このお見舞いのお礼には、悲しい折柄、ひとしお嬉しかった」 |
これを返歌にした。答礼のつもりで、「寂しい時の御慰問のお手紙はことにありがたく思われました」 |
Kono yorokobi, ahare nari si wori kara mo, itodo nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.11 | など言ひに立ち寄りたまへり。いと恥づかしげにものものしげにて、なべてかやうになどもならしたまはぬ、人柄もやむごとなきに、 いとものはかなき住まひなりかし。局などいひて、狭くほどなき遣戸口に寄りゐたまへる、 かたはらいたくおぼゆれど、さすがにあまり卑下してもあらで、いとよきほどにものなども聞こゆ。 |
などと言いに立ち寄りなさった。たいそう気恥ずかしくなるほど堂々として、普段はこのようにはお立ち寄りなさらず、人柄もご立派なのに、たいそうささやかな住まいである。局などと言って、狭く何程もない遣戸口に寄っていらっしゃるのは、体裁悪く思われるが、そうは言ってもむやみに卑下することもなく、とても良い具合にお話など申し上げる。 |
と言いに小宰相の家を薫は |
nado ihi ni tati-yori tamahe ri. Ito hadukasige ni mono-monosige nite, nabete kayau ni nado mo narasi tamaha nu, hitogara mo yamgotonaki ni, ito mono-hakanaki sumahi nari kasi. Tubone nado ihi te, sebaku hodo naki yarido-guti ni yori wi tamahe ru, kataharaitaku oboyure do, sasuga ni amari hige si te mo ara de, ito yoki hodo ni mono nado mo kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.12 | 「 見し人よりも ★、これは心にくきけ添ひてもあるかな。などて、 かく出で立ちけむ。 さるものにて、我も置いたらましものを」 |
「亡き人よりも、この人は奥ゆかしい感じが加わっているな。どうして、このように出仕したのだろう。そのような人として、わたしも側に置いたらよかったものを」 |
失った人よりもこの人のほうに才識のひらめきがあるではないか、なぜ女房などに出たのであろう、自分の妻の一人として持っていてもよかった人であったのに |
"Mi si hito yori mo, kore ha kokoro-nikuki ke sohi te mo aru kana! Nadote, kaku ide tati kem. Saru mono nite, ware mo oi tara masi mono wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.13 | と思す。 人知れぬ筋は、かけても見せたまはず。 |
とお思いになる。密やかな心の内は、少しもお見せにならない。 |
と薫は思っていた。しかしながら友情以上に進んでいこうとするふうを少しも薫は見せていなかった。 |
to obosu. Hito sire nu sudi ha, kake te mo mise tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 第二段 六条院の法華八講 |
5-2 A Buddhist servisce is held for Hikaru-Genji amd Murasaki at Rokujo-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1 | 蓮の花の盛りに、 御八講せらる。六条の院の御ため、紫の上など、皆思し分けつつ、御経仏など供養ぜさせたまひて、いかめしく、尊くなむありける。 五巻の日などは、いみじき見物なりければ、こなたかなた、 女房につきて参りて、物見る人多かりけり。 |
蓮の花の盛りに、法華八講が催される。六条院の御ため、紫の上のなどと、皆それぞれに日をお分けになって、お経や仏などを供養あそばして、荘厳に、立派に催された。五巻目の日などは、大変な見物だったので、あちらこちら、女房の縁故をたどって、見物に来る人が多かった。 |
|
Hatisu no hana no sakari ni, mi-hakkau se raru. Rokudeu-no-Win no ohom-tame, Murasaki-no-Uhe nado, mina obosi wake tutu, ohom-kyau Hotoke nado kuyau-ze sase tamahi te, ikamesiku, tahutoku nam ari keru. Go-kwan no hi nado ha, imiziki mi-mono nari kere ba, konata-kanata, nyoubau ni tuki te mawiri te, mono miru hito ohokari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.2 | 五日といふ朝座に果てて、 御堂の飾り取りさけ、御しつらひ改むるに、北の廂も、障子ども放ちたりしかば、皆入り立ちてつくろふほど、西の渡殿に 姫宮おはしましけり。 もの聞き極じて、女房もおのおの局にありつつ、 御前はいと人少ななる夕暮に、大将殿、直衣着替へて、今日まかづる 僧の中に、かならずのたまふべきことあるにより、釣殿の方におはしたるに、 皆まかでぬれば、池の方に涼みたまひて、人少ななるに、 かくいふ宰相の君など、かりそめに几帳などばかり立てて、うちやすむ上局にしたり。 |
五日という朝座で終わって、御堂の飾りを取り外し、お部屋の飾りつけを改めるので、北の廂も、襖障子なども外してあったので、皆が入り込んで整えている間、西の渡殿に姫宮はいらっしゃった。お経を聞き疲れて、女房たちもそれぞれの局にいて、御前はたいそう人少なな夕暮に、大将殿は、直衣に着替えて、今日退出する僧の中に、是非にお話なさらなければならない事があったので、釣殿の方にいらっしゃったが、皆が退出してしまったので、池の方で涼みなさって、人も少ないので、さきほどの小宰相の君などが、仮に几帳などを立てて、ちょっと休むための上局にしていた。 |
五日めの朝の講座が終わって仏前の飾りが取り払われ、室内の装飾を改めるために、北側の座敷などへも皆人がはいって、旧態にかえそうとする騒ぎのために、西の廊の座敷のほうへ一品の姫宮は行っておいでになった。日々の多くの講義に聞き疲れて女房たちも皆 |
Itu-ka to ihu asaza ni hate te, mi-dau no kazari tori-sake, ohom-siturahi aratamuru ni, kita no hisasi mo, syauzi-domo hanati tari sika ba, mina iri tati te tukurohu hodo, nisi no wata-dono ni Hime-Miya ohasimasi keri. Mono kiki gou-zi te, nyoubau mo ono-ono tubone ni ari tutu, o-mahe ha ito hito-zukuna naru yuhugure ni, Daisyau-dono, nahosi ki-gahe te, kehu makaduru sou no naka ni, kanarazu notamahu beki koto aru ni yori, turidono no kata ni ohasi taru ni, mina makade nure ba, ike no kata ni suzumi tamahi te, hito-zukuna naru ni, kaku ihu Saisyau-no-Kimi nado, karisome ni kityau nado bakari tate te, uti-yasumu uhe-tubone ni si tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.3 | 「 ここにやあらむ、人の衣の音す」と思して、馬道の方の障子の細く開きたるより、やをら見たまへば、例さやうの人のゐたるけはひには似ず、晴れ晴れしくしつらひたれば、なかなか、几帳どもの立て違へたるあはひより見通されて、あらはなり。 |
「ここであろうか、衣ずれの音がする」とお思いになって、馬道の方の襖障子が細く開いているところから、そっと御覧になると、いつもそのような女房がいる感じと違って、広々と整頓されているので、かえって、几帳などがいくつもはすに立ててあって見通されて、丸見えである。 |
人の |
"Koko ni ya ara m, hito no kinu no oto su." to obosi te, medau no kata no syauzi no hosoku aki taru yori, yawora mi tamahe ba, rei sayau no hito no wi taru kehahi ni ha ni zu, hare-baresiku siturahi tare ba, naka-naka, kityau-domo no tate-tigahe taru ahahi yori mi-tohosa re te, araha nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
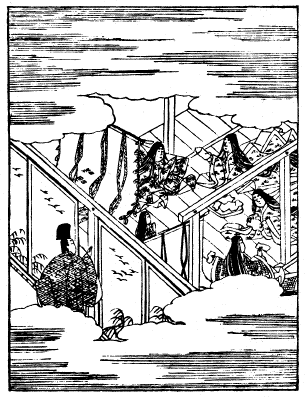 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.4 | 氷をものの蓋に置きて割るとて、もて騒ぐ人びと、大人三人ばかり、童と居たり。唐衣も汗衫も着ず、皆うちとけたれば、御前とは見たまはぬに、白き薄物の御衣 着替へたまへる人 ★の、手に氷を持ちながら、かく争ふを、すこし笑みたまへる御顔、言はむ方なくうつくしげなり。 |
氷を何かの蓋の上に置いて割ろうとして、騒いでいる女房たち、大人三人ほどと、童女とがいた。唐衣も汗衫も着ず、みな打ち解けていたので、御前とはお思いでないが、白い薄物のお召物を着ていらっしゃる人で、手に氷を持ちながら、このように騒いでいるのを、少しほほ笑んでいらっしゃるお顔、何とも言いようもなくかわいらしげである。 |
氷を何かの |
Hi wo mono no huta ni oki te waru tote, mote-sawagu hito-bito, otona mi-tari bakari, waraha to wi tari. Karaginu mo kazami mo ki zu, mina utitoke tare ba, o-mahe to ha mi tamaha nu ni, siroki usumono no ohom-zo kigahe tamahe ru hito no, te ni hi wo moti nagara, kaku arasohu wo, sukosi wemi tamahe ru ohom-kaho, iham-kata-naku utukusige nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.5 | いと暑さの堪へがたき日なれば、こちたき御髪の、 苦しう思さるるにやあらむ、すこしこなたに靡かして引かれたるほど、たとへむものなし。「 ここらよき人を見集むれど、似るべくもあらざりけり」とおぼゆ。御前なる人は、まことに 土などの心地ぞするを、思ひ静めて見れば、黄なる生絹の単衣、薄色なる裳着たる人の、扇うち使ひたるなど、「 用意あらむはや」と、ふと見えて、 |
ひどく暑さの堪えがたい日なので、うるさい御髪が、暑苦しくお思いなされるのであろうか、少しこちら側に靡かして引いている様子、何物にも譬えようがない。「大勢美しい女性を見て来たが、似ている人は誰もいないなあ」と思われる。御前の女房は、まこと土人形のような気がするのを、冷静になって見ていると、黄色い生絹の単衣に薄紫色の裳を着ている女で、扇をちょっと使っているところなど、「いかにも嗜みがあるなあ」と、ふと見えて、 |
非常に暑い日であったから、多いお |
Ito atusa no tahe-gataki hi nare ba, kotitaki mi-gusi no, kurusiu obosa ruru ni ya ara m, sukosi konata ni nabikasi te hika re taru hodo, tatohe m mono nasi. "Kokora yoki hito wo mi atumure do, niru beku mo ara zari keri." to oboyu. O-mahe naru hito ha, makoto ni tuti nado no kokoti zo suru wo, omohi-sidume te mire ba, ki naru suzusi no hitohe, usuiro naru mo ki taru hito no, ahugi uti-tukahi taru nado, "Youi ara m haya!" to, huto miye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.6 | 「 なかなか、もの扱ひに、いと苦しげなり。 ただ、さながら見たまへかし」 |
「かえって、氷を扱うのに、とても暑苦しそうです。ただ、そのままで御覧なさい」 |
そうした人にとって氷は取り扱いにくそうに見えた。「そのままにして、御覧だけなさいましよ」 |
"Naka-naka, mono-atukahi ni, ito kurusige nari. Tada, sanagara mi tamahe kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.7 | とて、笑ひたるまみ、愛敬づきたり。声聞くにぞ、 この心ざしの人とは知りぬる。 |
と言って、にっこりしている目もと、愛嬌がある。声を聞くと、この目指している女と分かった。 |
と |
tote, warahi taru mami, aigyau-duki tari. Kowe kiku ni zo, kono kokorozasi no hito to ha siri nuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 第三段 小宰相の君、氷を弄ぶ |
5-3 Ko-Zaisho plays with a piece of ice at hot day |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.1 | 心強く割りて、手ごとに持たり。頭にうち置き、胸にさし当てなど、 さま悪しうする人もあるべし。異人は、紙につつみて、御前にもかくて参らせたれど、 いとうつくしき御手をさしやりたまひて、 拭はせたまふ。 |
無理して割って、それぞれの手に持っていた。頭の上に置いたり、胸に当てたりなど、体裁の悪い恰好をする女もいるのであろう。他の人は、紙に包んで、御前にもこのようにして差し上げたが、とてもかわいらしいお手を差し出しなさって、拭わせなさる。 |
とどめた人のあったにもかかわらず氷を割ってしまった人々は、手ごとに一つずつの |
Kokoro-duyoku wari te, te-goto ni mo' tari. Kasira ni uti-oki, mune ni sasi-ate nado, sama asiu suru hito mo aru besi. Koto-bito ha, kami ni tutumi te, o-mahe ni mo kaku te mawira se tare do, ito utukusiki mi-te wo sasi-yari tamahi te, nogoha se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.2 | 「 いな、持たらじ。雫むつかし」 |
「いえ、持てません。雫が嫌です」 |
「もう私は持たない、 |
"Ina, mo' tara zi. Siduku mutukasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.3 | とのたまふ御声、いとほのかに聞くも、 限りもなくうれし。「 まだいと小さくおはしまししほどに、我も、ものの心も知らで見たてまつりし時、めでたの稚児の御さまや、と見たてまつりし。その後、たえてこの御けはひをだに聞かざりつるものを、 いかなる神仏の、かかる折見せたまへるならむ。 例の、やすからずもの思はせむとするにやあらむ」 |
とおっしゃるお声、とてもかすかに聞くのも、この上なく嬉しい。「まだとても幼くいらしたときに、わたしも、何も分からず拝見したとき、何とかわいらしい姫宮か、と拝見した。その後は、まったく姫宮のご様子をさえ聞かなかったが、どのような神仏が、このような機会をお見せになったのであろうか。いつもの、心安からず物思いをさせようとするのであろうか」 |
と、お言いになる声をほのかに聞くことのできたのが薫のかぎりもない喜びになった。まだごくお小さい時に、自分も無心にお見上げして、美しい幼女でおありになると思った。それ以後は絶対にこの宮を拝見する機会を持たなかったのであるが、なんという神か仏かがこんなところを自分の目に見せてくれたのであろうと思い、また過去の経験にあるように、こうした |
to notamahu ohom-kowe, ito honoka ni kiku mo, kagiri mo naku uresi. "Mada ito tihisaku ohasimasi si hodo ni, ware mo, mono no kokoro mo sira de mi tatematuri si toki, medeta no tigo no ohom-sama ya, to mi tatematuri si. Sono noti, taye te kono ohom-kehahi wo dani kika zari turu mono wo, ika naru Kami Hotoke no, kakaru wori mise tamahe ru nara m. Rei no, yasukara zu mono omoha se m to suru ni ya ara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.4 | と、かつは静心なくて、まもり立ちたるほどに、 こなたの対の北面に住みける下臈女房の、この 障子は、とみのことにて、開けながら下りにけるを思ひ出でて、「 人もこそ見つけて騒がるれ」と思ひければ、惑ひ入る。 |
と、一方では落ち着かず、じっと見つめて佇んでいると、こちらの対の北面に住んでいた下臈の女房が、この襖障子は、急ぎの用事で、開けたままで下りて来たのを思い出して、「人が見つけて騒いだら大変だ」と思ったので、あわてて入って来る。 |
とも思われて、落ち着かぬ心で見つめていた。ここの対の北側の座敷に涼んでいた下級の女房の一人が、この |
to, katuha sidu-kokoro naku te, mamori tati taru hodo ni, konata no tai no kita-omote ni sumi keru gerahu nyoubau no, kono syauzi ha, tomi no koto nite, ake nagara ori ni keru wo omohi-ide te, "Hito mo koso mi-tuke te sawaga rure." to omohi kere ba, madohi iru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.5 | この直衣姿を見つくるに、「誰ならむ」と心騷ぎて、おのがさま見えむことも知らず、簀子よりただ 来に来れば、 ふと立ち去りて、「 誰れとも見えじ。好き好きしきやうなり」と思ひて隠れたまひぬ。 |
この直衣姿を見つけて、「誰だろう」とびっくりして、自分の姿を見られることも構わず、簀子からずんずんやって来たので、ふと立ち去って、「誰とも知られまい。好色なようだ」と思って隠れなさった。 |
襖子に寄り添った |
Kono nahosi-sugata wo mi-tukuru ni, "Tare nara m?" to kokoro-sawagi te, onoga sama miye m koto mo sira zu, sunoko yori tada ki ni kure ba, huto tati-sari te, "Tare to mo miye zi. Suki-zukisiki yau nari." to omohi te kakure tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.6 | この御許は、 |
この女房は、 |
その女房は |
Kono omoto ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.7 | 「 いみじきわざかな。御几帳をさへあらはに引きなしてけるよ。 右の大殿の君たちならむ。疎き人、はた、ここまで来べきにもあらず。 ものの聞こえあらば、誰れか 障子は開けたりしと、かならず 出で来なむ。 単衣も袴も、生絹なめりと見えつる人の御姿なれば、え人も 聞きつけたまはぬならむかし」 |
「大変なことだわ。御几帳までを丸見えにしていたことだわ。右の大殿の公達であろうかしら。疎遠な方は、また、ここまでは来るはずがない。何かの噂が立ったら、誰が襖障子を開けていたのだろうかと、きっと出て来るだろう。単衣も袴も、生絹のように見えた方のお姿なので、誰もお気づきになることができなかっただろう」 |
たいへんなことになった、自分はお |
"Imiziki waza kana! Mi-kityau wo sahe araha ni hiki-nasi te keru yo. Migi-no-Ohotono no Kimi-tati nara m. Utoki hito, hata, koko made ku beki ni mo ara zu. Mono no kikoye ara ba, tareka syauzi ha ake tari si to, kanarazu ide-ki na m. Hitohe mo hakama mo, suzusi na' meri to miye turu hito no ohom-sugata nare ba, e hito mo kiki-tuke tamaha nu nara m kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.8 | と思ひ極じてをり。 |
と困りきっていた。 |
と苦しんでいた。 |
to omohi-gou-zi te wori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.9 | かの人は、「 やうやう聖になりし心を、 ひとふし違へそめて、さまざまなるもの思ふ人ともなるかな。そのかみ世を 背きなましかば、今は深き山に住み果てて、かく心 乱れましや」など思し続くるも、やすからず。「 などて、年ごろ、 見たてまつらばやと思ひつらむ。なかなか苦しう、かひなかるべきわざにこそ」と思ふ。 |
あの方は、「だんだんと聖になって来た心を、一度踏み外して、さまざまに物思いを重ねる人となってしまったなあ。その昔に出家遁世してしまったら、今は深い山奥に住みついて、このような心を乱すことはないものを」などとお思い続けるにつけても、落ち着かない。「どうして、長年、お顔を拝見したものだと思っていたのであろう。かえって苦しいだけで、何にもならないことであるのに」と思う。 |
薫は漸く僧に近い心になりかかった時に、宇治の宮の姫君たちによって |
Kano hito ha, "Yau-yau hiziri ni nari ni si kokoro wo, hito-husi tagahe-some te, sama-zama naru mono omohu hito to mo naru kana! Sono-kami yo wo somuki na masika ba, ima ha hukaki yama ni sumi-hate te, kaku kokoro-midare masi ya!" nado obosi tudukuru mo, yasukara zu. "Nadote, tosi-goro, mi tatematura baya to omohi tu ram. Naka-naka kurusiu, kahinakaru beki waza ni koso." to omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | 第四段 薫と女二宮との夫婦仲 |
5-4 The marital relationship between Kaoru and Ni-no-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.1 | つとめて、起きたまへる 女宮の御容貌、「 いとをかしげなめるは、これよりかならずまさるべきことかは」と見えながら、「 さらに似たまはずこそありけれ。あさましきまであてに、えも言はざりし 御さまかな。かたへは思ひなしか、折からか」と思して、 |
翌朝、起きなさった女宮の御器量が、「とても美しくいらっしゃるようなのは、この宮よりもきっとまさっていらっしゃるだろうか」と思いながらも、「まったく似ていらっしゃらない。驚くほど上品で、何とも言えないほどのご様子だなあ。一つには気のせいか、時節柄か」とお思いになって、 |
翌朝起きた薫は夫人の女二の宮の美しいお姿をながめて、必ずしもこれ以上の御 |
Tutomete, oki tamahe ru Womna-Miya no ohom-katati, "Ito wokasige na' meru ha, kore yori kanarazu masaru beki koto kaha." to miye nagara, "Sarani ni tamaha zu koso ari kere. Asamasiki made ate ni, e mo iha zari si ohom-sama kana! Katahe ha omohi sika, wori kara ka." to obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.2 | 「 いと暑しや。これより薄き御衣奉れ。女は、例ならぬ物着たるこそ、時々につけてをかしけれ」とて、「 あなたに参りて、 大弐に、薄物の単衣の御衣、縫ひて参れと言へ」 |
「ひどく暑いね。これより薄いお召し物になさいませ。女性は、変わった物を着ているのが、その時々につけ趣があるものです」と言って、「あちらに参上して、大弍に、薄物の単衣のお召し物を、縫って差し上げよと申せ」 |
「非常に暑い。もっと薄いお召し物を宮様にお着せ申せ。女は平生と違った服装をしていることなどのあるのが美しい感じを与えるものだからね。あちらへ行って |
"Ito atusi ya! Kore yori usuki ohom-zo tatemature. Womna ha, rei nara nu mono ki-taru koso, toki-doki ni tuke te wokasikere." tote, "Anata ni mawiri te, Daini ni, usumono no hiothe no ohom-zo nuhi te mawire to ihe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.3 | とのたまふ。 御前なる人は、「この御容貌のいみじき盛りにおはしますを、もてはやしきこえたまふ」とをかしう思へり。 |
とおっしゃる。御前の女房は、「宮のご器量がたいそう女盛りでいらっしゃるのを、さらに引き立てようとなさる」とおもしろく思っていた。 |
と言いだした。侍している女房たちは宮のお美しさにより多く異彩の添うのを楽しんでの言葉ととって喜んでいた。 |
to notamahu. O-mahe naru hito ha, "Kono ohom-katati no imiziki sakari ni ohasimasu wo, motehayasi kikoye tamahu." to wokasiu omohe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.4 | 例の、念誦したまふわが御方におはしましなどして、昼つ方 渡りたまへれば、のたまひつる御衣、御几帳にうち掛けたり。 |
いつものように、念誦をなさるご自分のお部屋にいらっしゃったりなどして、昼頃にお渡りになると、お命じになっていたお召し物が、御几帳に懸けてあった。 |
いつものように一人で |
Rei no, nenzyu si tamahu waga ohom-kata ni ohasimasi nado si te, hiru tu kata watari tamahe re ba, notamahi turu ohom-zo, mi-kityau ni uti-kake tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.5 | 「 なぞ、こは奉らぬ。人多く見る時なむ、透きたる物着るは、ばうぞくにおぼゆる。ただ今はあへはべりなむ」 |
「どうして、これをお召しにならないのか。人が大勢見る時に、透けた物を着るのは、はしたなく思われる。今は構わないでしょう」 |
「どうしてこれをお着にならぬのですか、人がたくさん見ている時に |
"Nazo, koha tatematura nu? Hito ohoku miru toki nam, suki taru mono kiru ha, bauzoku ni oboyuru. Tadaima ha ahe haberi na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.6 | とて、手づから着せ奉りたまふ。御袴も昨日の同じ紅なり。御髪の多さ、裾などは 劣りたまはねど、なほ さまざまなるにや、似るべくもあらず。氷召して、人びとに割らせたまふ。取りて一つ奉りなどしたまふ、心のうちもをかし。 |
と言って、ご自身でお着せなさる。御袴も昨日のと同じ紅色である。御髪の多さや、裾などは負けないが、やはりそれぞれの美しさなのか、似るはずもない。氷を召して、女房たちに割らせなさる。取って一つ差し上げなどなさる、心の中もおもしろい。 |
と薫は言って、手ずからお着せしていた。宮のお |
tote, tedukara kise tatematuri tamahu. Ohom-hakama mo kinohu no onazi kurenawi nari. Mi-gusi no ohosa, suso nado ha otori tamaha ne do, naho sama-zama naru ni ya, niru beku mo ara zu. Hi mesi te, hito-bito ni wara se tamahu. Tori te hitotu tatematuri nado si tamahu, kokoro no uti mo wokasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.7 | 「 絵に描きて、恋しき人見る人は、なくやはありける。ましてこれは、慰めむに 似げなからぬ御ほどぞかし と思へど、昨日かやうにて、 我混じりゐ、心にまかせて見たてまつらましかば」とおぼゆるに、心にもあらずうち嘆かれぬ。 |
「絵に描いて、恋しい人を見る人は、いないだろうか。ましてこの宮は、気持ちを慰めるのに似つかわしからぬご姉妹であると思うが、昨日あのようにして、自分があの中に混じっていて、心ゆくまで拝することができたなら」と思うと、われ知らずのうちに溜息が漏れてしまった。 |
絵に |
"We ni kaki te, kohisiki hito miru hito ha, naku yaha ari keru. Masite kore ha, nagusame m ni nigenakara nu ohom-hodo zo kasi to omohe do, kinohu kayau nite, ware maziri wi, kokoro ni makase te mi tatematura masika ba." to oboyuru ni, kokoro ni mo ara zu uti-nageka re nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.8 | 「 一品の宮に、御文は奉りたまふや」 |
「一品の宮に、お手紙は差し上げなさいましたか」 |
「一品の宮さんへお手紙をおあげになることがありますか」 |
"Ippon-no-Miya ni, ohom-humi ha tatematuri tamahu ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.9 | と聞こえたまへば、 |
とお尋ね申し上げなさると、 |
to kikoye tamahe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.10 | 「 内裏にありし時、主上の、 さのたまひしかば聞こえしかど、久しうさもあらず」 |
「内裏にいたとき、主上が、そのようにおっしゃったので差し上げましたが、長いことそういたしてません」 |
「御所にいましたころ、お |
"Uti ni ari si toki, Uhe no, sa notamahi sika ba kikoye sika do, hisasiu samo ara zu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.11 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
to notamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.12 | 「 ただ人にならせたまひにたりとて、かれよりも聞こえさせたまはぬにこそは、心憂かなれ。今、大宮の御前にて、 恨みきこえさせたまふ、と啓せむ」 |
「臣下におなりあそばしたといって、あちらからお便りを下さらないのは、情けないことです。今、大宮の御前に、お恨み申されています、と申し上げよう」 |
「人臣の妻におなりになったからといって、あちらからお手紙をくださらなくなったのでしょうが、悲観させられますね。そのうち私から中宮へあなたが恨んでおいでになると申し上げよう」 |
"Tadaudo ni nara se tamahi ni tari tote, kare yori mo kikoye sase tamaha nu ni koso ha, kokoro-uka' nare. Ima, Oho-Miya no o-mahe nite, urami kikoye sase tamahu, to kei-se m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.13 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
と薫は言う。 |
to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.14 | 「 いかが恨みきこえむ。うたて」 |
「どうしてお恨み申していましょう。嫌ですわ」 |
「そんなこと、お恨みなど私はしているものでございますか。いやでございます」 |
"Ikaga urami kikoye m. Utate." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.15 | とのたまへば、 |
とおっしゃるので、 |
to notamahe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.16 | 「 下衆になりにたりとて、思し落とすなめり、と見れば、 おどろかしきこえぬ、とこそは聞こえめ」 |
「身分が低くなったからといって、軽んじていらっしゃるようだ、と思われるので、お便りも差し上げないのです、と申し上げましょう」 |
「身分が悪くなったからといって |
"Gesu ni nari ni tari tote, obosi-otosu na' meri, to mire ba, odorokasi kikoye nu, to koso ha kikoye me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.17 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
to notamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 第五段 薫、明石中宮に対面 |
5-5 Kaoru meets Akashi-Empress who is his wife's mother |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.1 | その日は暮らして、またの朝に大宮に参りたまふ。例の、 宮もおはしけり。 丁子に深く染めたる薄物の単衣を、こまやかなる直衣に着たまへる、いとこのましげなる 女の御身なりのめでたかりしにも劣らず、白くきよらにて、なほありしよりは面痩せたまへる、いと見るかひあり。 |
その日は過ごして、翌朝に大宮に参上なさる。いつものように、宮もいらっしゃった。丁子色に深く染めた薄物の単衣を、濃い縹色の直衣の下に召していらっしゃったのは、たいそう好感がもてる女宮のお姿が素晴らしかったのにも負けず、白く清らかで、やはり以前よりは面痩せなさっているのは、とても見栄えがする。 |
こんなことを言ってその日は暮らし、翌日になって大将は中宮の御殿へまいった。例の |
Sono hi ha kurasi te, mata no asita ni Oho-Miya ni mawiri tamahu. Rei no, Miya mo ohasi keri. Tyauzi ni hukaku some taru usumono no hitohe wo, komayaka naru nahosi ni ki tamahe ru, ito konomasige naru Womna no ohom-minari no medetakari si ni mo otora zu, siroku kiyora nite, naho arisi yori ha omo-yase tamahe ru, ito miru kahi ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.2 | おぼえたまへりと見るにも、 まづ恋しきを、いとあるまじきこと、と静むるぞ、 ただなりしよりは苦しき。 絵をいと多く持たせて参りたまへりける、女房して、 あなたに参らせたまひて、渡らせたまひぬ。 |
似ていらっしゃると見るにつけても、まっさきに恋しいのを、まことにけしからぬこと、と抑えるのは、拝見しなかった時よりもつらい。絵をとてもたくさん持たせて参上なさったが、女房を介して、あちらに差し上げなさって、ご自分もお渡りになった。 |
女宮によく似ておいでになるということから、またおさえている恋しさがわき上がるのを、あるまじいことであると思い、静めようとするのもあの日の前には知らぬ苦しみであった。兵部卿の宮は絵をたくさんに持って来ておいでになったが、そのうちの幾つかを女房に姫宮のほうへ持たせておあげになり、御自身もあちらへおいでになった。 |
Oboye tamahe ri to miru ni mo, madu kohisiki wo, ito aru maziki koto, to sidumuru zo, tada nari si yori ha kurusiki. We wo ito ohoku mota se te mawiri tamahe ri keru, nyoubau site, anata ni mawirase tamahi te, watara se tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.3 | 大将も近く参り寄りたまひて、御八講の尊くはべりしこと、いにしへの御こと、すこし聞こえつつ、残りたる絵見たまふついでに、 |
大将も近くに参り寄りなさって、御八講が立派であったことや、昔の御事を少し申し上げながら、残っている絵を御覧になる折に、 |
薫は后の宮のお近くへ寄って行き、御八講の尊かったことを言い、六条院のことも少しお話し申し上げながら、残った絵を拝見している時に、 |
Daisyau mo tikaku mawiri yori tamahi te, mi-ha'kau no tahutoku haberi si koto, inisihe no ohom-koto, sukosi kikoye tutu, nokori taru we mi tamahu tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.4 | 「 この里にものしたまふ皇女の、雲の上離れて、思ひ屈したまへるこそ、いとほしう見たまふれ。 姫宮の御方より、御消息もはべらぬを、かく品定まりたまへるに、思し捨てさせたまへるやうに思ひて、心ゆかぬけしきのみはべるを、 かやうのもの、時々 ものせさせたまはなむ。 なにがしがおろして持てまからむ。はた、見るかひもはべらじかし」 |
「わたしの里にいらっしゃるこ皇女が、宮中から離れて、思い沈んでいらっしゃるのが、お気の毒に拝されます。姫宮の御方から、お便りもございませんのを、このように身分が決定なさったので、お見捨てあそばされたように思って、気の晴れない様子ばかりしておりますが、こうした物を、時々お見せ下さいませ。わたしが直接持って参りますのも、また、張り合いのないものです」 |
「私の所に来ておいでになります宮さんが、宮廷から離れて屈託した気持ちになっておられますのをお気の毒だと見ております。一品の宮様のお消息などをいただけませんことを人妻に |
"Kono sato ni monosi tamahu Miko no, kumo no uhe hanare te, omohi-kut'-si tamahe ru koso, itohosiu mi tamahure. Hime-Miya no ohom-kata yori, ohom-seusoko mo habera nu wo, kaku sina sadamari tamahe ru ni, obosi-sute sase tamahe ru yau ni omohi te, kokoro-yuka nu kesiki nomi haberu wo, kayau no mono, toki-doki monose sase tamaha nam. Nanigasi ga orosi te mo'te makara m. Hata, miru kahi mo habera zi kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.5 | とのたまへば、 |
と申し上げなさると、 |
と中宮へ申し上げると、 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.6 | 「 あやしく。などてか捨てきこえたまはむ。内裏にては、近かりしにつきて、時々も聞こえたまふめりしを、所々になりたまひし折に、とだえたまへるにこそあらめ。今、そそのかしきこえむ。 それよりもなどかは」 |
「変なこと。どうしてお見捨て申し上げなさいましょう。内裏では、近かったことにつけて、時々手紙のやりとりをなさったようですが、別々におなりになった時から、滞りがちになったのでしょう。これから、お促し申し上げましょう。そちらからもどうして差し上げなさらないのですか」 |
「まあそんなことで御交際をおやめになるものですか。同じ御所の中におられたころは、近いものですからときどき手紙が通ったのでしょうが、遠く離れ離れにおなりになった時からお手紙が途絶え始めて、そのままになったことなのでしょう。そのうち私からお勧めしてお書きになるようにしますよ。そちらからだってお手紙をお送りになればいいのにね」 |
"Ayasiku. Nadoteka sute kikoye tamaha m. Uti nite ha, tikakari si ni tuki te, toki-doki mo kikoye tamahu meri si wo, tokoro-dokoro ni nari tamahi si wori ni, todaye tamahe ru ni koso ara me. Ima, sosonokasi kikoye m. Sore yori mo nado-kaha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.7 | と聞こえたまふ。 |
と申し上げなさる。 |
と、宮は仰せられた。 |
to kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.8 | 「 かれよりは、いかでかは。もとより 数まへさせたまはざらむをも、かく親しくてさぶらふべきゆかりに寄せて、思し召し数まへさせたまはむをこそ、うれしくははべるべけれ。まして、さも聞こえ馴れたまひにけむを、今捨てさせたまはむは、からきことにはべり」 |
「あちらからは、どうしてできましょうか。もともとお心に懸けていただけなかったとしても、こうして親しく伺候します縁にことよせて、お心を懸けてくださいましたら、嬉しいことでございます。それ以上に、そのように親しくなさっていたのを、今お見捨てになるのは、つらいことでございます」 |
「そちらからは出過ぎたように思われておできにならないのでしょう。初めから御交渉のなかった方にいたしましても、私と宮様がたとの縁の続きに愛しておあげくださることになるのがうれしい成り行きなのですが、まして以前から御交際のあった間柄でおありになるのですから、私の所へ来られましたあとでお捨てになるのは、あの宮さんにとっておかわいそうなことです」 |
"Kare yori ha, ikade-kaha. Motoyori kazumahe sase tamaha zara m wo mo, kaku sitasiku te saburahu beki yukari ni yose te, obosi-mesi kazumahe sase tamaha m wo koso, uresiku ha haberu bekere. Masite, samo kikoye nare tamahi ni kem wo, ima sute sase tamaha m ha, karaki koto ni haberi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.9 | と啓せさせたまふを、「 好きばみたるけしきあるか」とは思しかけざりけり。 |
と申し上げなさるのを、「好色心があるのか」とは思いよりなさらなかった。 |
などと申しているのを、恋が言わせることと中宮はお悟りにならなかった。 |
to kei-se sase tamahu wo, "Sukibami taru kesiki aru ka?" to ha obosi-kake zari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.10 | 立ち出でて、「 一夜の心ざしの人に会はむ。ありし渡殿も慰めに見むかし」と思して、御前を歩み渡りて、西ざまにおはするを、御簾の内の人は心ことに用意す。 げに、いと様よく限りなきもてなしにて、渡殿の方は、左の大殿の君たちなど居て、物言ふけはひすれば、妻戸の前に居たまひて、 |
お立ちになって、「先夜のお目当ての女に会おう。先日の渡殿も慰めに見よう」とお思いになって、御前を渡って、西の方角にいらっしゃるのを、御簾の内側の女房は特に緊張する。なるほど、たいそう風采よく、この上ない身のこなしで、渡殿の方では、左の大殿の公達などが座っていて、何か言っている様子がするので、妻戸の前にお座りになって、 |
薫は中宮のお居間を辞して、先夜の好意のある女友人にも逢おう、あの思い出の廊の座敷を心の慰めに見て行こうと思い、縁側伝いに西に向いて歩いて行った。 |
Tati-ide te, "Hito-yo no kokorozasi no hito ni aha m. Arisi watadono mo nagusame ni mi m kasi." to obosi te, o-mahe wo ayumi watari te, nisi-zama ni ohasuru wo, mi-su no uti no hito ha kokoro-koto ni youi su. Geni, ito sama yoku kagiri naki motenasi nite, watadono no kata ha, Hidari-no-Ohotono no Kimi-tati nado wi te, mono ihu kehahi sure ba, tumado no mahe ni wi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.11 | 「 おほかたには参りながら、 この御方の見参に入ることの、難くはべれば、いとおぼえなく、翁び果てにたる心地しはべるを、今よりは、と思ひ起こしはべりてなむ。ありつかず、若き人どもぞ思ふらむかし」 |
「よく参上はいたしますが、こちらの御方にはお目にかかることも、めったにございませんので、いつのまにか、老人めいた気持ちでございますが、今からは、と気を奮い起こしまして。不似合いな振る舞いだと、若い人たちは思うでしょう」 |
「始終この院へはまいっている私ですが、こちらの宮様の御殿へ伺うことができないでいますと、自然老人めいた気持ちになるようになったのですが、これからはそうしていまいと決心してまいったのですよ。 |
"Ohokata ni ha mawiri nagara, kono Ohom-Kata no genzan ni iru koto no, kataku habere ba, ito oboye naku, okinabi hate ni taru kokoti si haberu wo, ima yori ha, to omohi-okosi haberi te nam. Arituka zu, wakaki hito-domo zo omohu ram kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.12 | と、 ▼ 甥の君たちの方を見やりたまふ。 |
と、甥の公達の方を御覧になる。 |
|
to, wohi no Kimi-tati no kata wo mi-yari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.13 | 「 今よりならはせたまふこそ、げに若くならせたまふならめ」 |
「今からお馴染みになられたら、なるほど若返りなされるでしょう」 |
「ただ今からお習いになりましたなら新鮮なお若さが拝見されることでしょう」 |
"Ima yori naraha se tamahu koso, geni wakaku nara se tamahu nara me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.14 | など、はかなきことを言ふ人びとのけはひも、あやしうみやびかに、をかしき御方のありさまにぞある。そのこととなけれど、世の中の物語などしつつ、しめやかに、例よりは居たまへり。 |
などと、とりとめもないことを言う女房たちの様子も、不思議と優雅で、風情のあるこちらの御方のご様子である。特に用事ということはないが、世間話などをしながら、しんみりと、いつもよりは長居なさった。 |
などと戯れて言う女房らからも怪しいまでの高雅な感じの受け取られるのであった。何をおもな話題にするというのでもなく、世間話を平生よりもしんみりと話し込んで |
nado, hakanaki koto wo ihu hito-bito no kehahi mo, ayasiu miyabika ni, wokasiki ohom-kata no arisama ni zo aru. Sono koto to nakere do, yononaka no monogatari nado si tutu, simeyaka ni, rei yori ha wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | 第六段 明石中宮、薫と小宰相の君の関係を聞く |
5-6 Akashi-Empress hears the relationship between Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.1 | 姫宮は、 あなたに渡らせたまひにけり。大宮、 |
姫宮は、あちらにお渡りあそばした。大宮が、 |
姫宮は |
Hime-Miya ha, anata ni watara se tamahi ni keri. Oho-Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.2 | 「 大将のそなたに参りつるは」 |
「大将がそちらに参ったが」 |
「大将があちらへ行きましたか」 |
"Daisyau no sonata ni mawiri turu ha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.3 | と問ひたまふ。御供に参りたる 大納言の君、 |
とお尋ねになる。お供して参った大納言の君が、 |
とお尋ねになると、一品の宮のお供をしてこちらへ来た大納言の君が、 |
to tohi tamahu. Ohom-tomo ni mawiri taru Dainagon-no-Kimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.4 | 「 小宰相の君に、もののたまはむとにこそは、はべめりつれ」 |
「小宰相の君に、何かおっしゃろうとのことで、ございましょう」 |
「小宰相に話があると言っていらっしゃいました」 |
"Ko-Zaisyau-no-Kimi ni, mono notamaha m to ni koso ha, habe' meri ture." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.5 | と聞こゆるに、 |
と申し上げると、 |
と申した。 |
to kikoyuru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.6 | 「例、 まめ人の、さすがに人に心とどめて物語する こそ、心地おくれたらむ人は苦しけれ。心のほども見ゆらむかし。 小宰相などは、いとうしろやすし」 |
「いつもの、真面目人間が、やはり女性に心を止めて話をするのは、気のきかない人でしたら困ります。心の底も見透かされるでしょう。小宰相などは、とても安心です」 |
「まじめな人であって、さすがに女の友だちにも心の |
"Rei, mame-bito no, sasuga ni hito ni kokoro-todome te monogatari suru koso, kokoti okure tara m hito ha kurusikere. Kokoro no hodo mo miyu ram kasi. Ko-Zaisyau nado ha, ito usiroyasusi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.7 | とのたまひて、 御姉弟なれど、この君をば、なほ恥づかしく、「 人も用意なくて見えざらむかし」と思いたり。 |
とおっしゃって、ご姉弟であるが、この君を、やはり恥ずかしく思い、「女房たちも不注意に応対しないでほしい」とお思いになっていた。 |
こんなことをお言いになる宮は、御弟なのであるが、薫に周囲を観察されることを恥ずかしく思召し、女房らも飽き足らず思われるところを見せぬようにしてほしいと思召すのである。 |
to notamahi te, ohom-harakara nare do, kono Kimi wo ba, naho hadukasiku, "Hito mo youi naku te miye zara m kasi." to oboi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.8 | 「 人よりは 心寄せたまひて、局などに立ち寄りたまふべし。物語こまやかにしたまひて、夜更けて出でたまふ折々もはべれど、例の目馴れたる筋にははべらぬにや。 宮をこそ、いと情けなくおはしますと 思ひて、御いらへをだに聞こえずはべるめれ。かたじけなきこと」 |
「どの女房よりも心をお寄せになって、局などにお立ち寄りなさるのでしょう。お話を親密になさって、夜が更けてお帰りになる時々もございましたが、普通のありふれた色恋沙汰ではないのでしょうか。宮を、とても情けないお方と思って、お返事さえ差し上げないようでございます。恐れ多いこと」 |
「あの人をだれよりも御ひいきになさいまして、部屋のほうへも寄ってお行きになることがよくあるようでございます。しんみりとお話をしておいでになることもございまして夜がふけてお帰りになることはありましても恋愛関係と申すようなことはなさそうに思われます。あの人兵部卿の宮様の御性情には反感を持っておりまして、お返辞すらよくいたさないようでございますのはもったいないことでございます」 |
"Hito yori ha kokoro-yose tamahi te, tubone nado ni tati-yori tamahu besi. Monogatari komayaka ni si tamahi te, yo huke te ide tamahu wori-wori mo habere do, rei no me-nare taru sudi ni ha habera nu ni ya? Miya wo koso, ito nasakenaku ohasimasu to omohi te, ohom-irahe wo dani kikoye zu haberu mere. Katazikenaki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.9 | と言ひて笑へば、宮も笑はせたまひて、 |
と言って笑うと、宮もにっこりあそばして、 |
と言い、大納言の君が笑うと、中宮もお笑いになって、 |
to ihi te warahe ba, Miya mo waraha se tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.10 | 「 いと見苦しき御さまを、思ひ知るこそをかしけれ。いかで、かかる御癖やめたてまつらむ。恥づかしや、この人びとも」 |
「ひどく見苦しいご様子を、知っているのがおもしろい。何とかして、あのようなお癖を止めさせ申したいものです。恥ずかしいね、そなたたちの手前も」 |
「あの宮の多情な本質が直感できるのだからいいね。どうしてあの方の悪癖を直させたらいいだろう、恥ずかしいと私は思う。だれも皆そう思っているだろうね」 |
"Ito mi-gurusiki ohom-sama wo, omohi-siru koso wokasikere. Ikade, kakaru ohom-kuse yame tatematura m. Hadukasi ya, kono hito-bito mo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.11 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
こうお語りになった。 |
to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7 | 第七段 明石中宮、薫の三角関係を知る |
5-7 Akashi-Empress knew a love triangle between Kaoru, Niou-no-miya and Ukifune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.1 | 「 いとあやしきことをこそ聞きはべりしか。この大将の 亡くなしたまひてし人は、宮の御二条の北の方の御おとうとなりけり。異腹なるべし。 常陸の前の守なにがしが妻は、 叔母とも母とも言ひはべるなるは、いかなるにか。その女君に、宮こそ、いと忍びておはしましけれ。 |
「とても不思議な事を聞きました。この大将殿が亡くしなさった人は、宮の二条の北の方のお妹君でした。異腹なのでしょう。常陸の前の介の何某の妻は、叔母とも母とも言っていますのは、どういうものでしょうか。その女君に、宮が、まことにこっそりとお通いになりました。 |
「妙な話を私は聞いたのでございます。あの大将さんのお |
"Ito ayasiki koto wo koso kiki haberi sika. Kono Daisyau no nakunasi tamahi te si hito ha, Miya no ohom-Nideu-no-Kitanokata no ohom-otouto nari keri. Koto-bara naru besi. Hitati-no-saki-no-kami nanigasi ga me ha, woba to mo haha to mo ihi haberu naru ha, ika naru ni ka? Sono Womna-Gimi ni, Miya koso, ito sinobi te ohasimasi kere. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.2 | 大将殿や聞きつけたまひたりけむ。にはかに迎へたまはむとて、守り目添へなど、ことことしくしたまひけるほどに、宮も、いと忍びておはしましながら、え入らせたまはず、あやしきさまに、御馬ながら立たせたまひつつぞ、帰らせたまひける。 |
大将殿がお聞きつけになったのでしょうか。急遽お迎えなさろうとして、番人を増やしなどして、厳重になさっているところに、宮も、とてもこっそりとお通いになりながら、お入りになることができず、粗末な姿で、お馬に乗って立ったまま、お帰りになりました。 |
その大将の愛人の所へそっと兵部卿の宮様も通ってお行きになったということでございまして、大将さんがそれをお聞きになりましたのか、にわかに宇治から京へ迎えようとなすって、監視の人などをきびしくお付けになりましたころに、宮様はまたおいでになったのでございますが、家の中へおはいりになることができませんで、危険なことでございますが、お馬のままで外に立っておいでになり、それなり帰っておしまいになったということでございまして、 |
Daisyau-dono ya kiki-tuke tamahi tari kem. Nihaka ni mukahe tamaha m tote, mamori-me sohe nado, koto-kotosiku si tamahi keru hodo ni, Miya mo, ito sinobi te ohasimasi nagara, e ira se tamaha zu, ayasiki sama ni, ohom-muma nagara tata se tamahi tutu zo, kahera se tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.3 | 女も、宮を思ひきこえさせけるにや、にはかに消え失せにけるを、身投げたるなめりとてこそ、乳母などやうの人どもは、泣き惑ひはべりけれ」 |
女も、宮をお慕い申し上げていたのでしょうか、急に消えてしまいましたが、身投げしたようだと言って、乳母などの女房は、泣き暮れておりました」 |
女も宮様をお慕いしていたのでしょうか、にわかに行くえがわからなくなりましたのを、川へ身を投げたのであろうと、 |
Womna mo, Miya wo omohi kikoye sase keru ni ya, nihaka ni kiye-use ni keru wo, mi nage taru na' meri tote koso, Menoto nado yau no hito-domo ha, naki madohi haberi kere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.4 | と聞こゆ。宮も、「いとあさまし」と思して、 |
と申し上げる。大宮も、「まことに呆れたことだ」とお思いになって、 |
大納言の君はこんな話を申し上げた。中宮がお驚きになったことは言うまでもない。 |
to kikoyu. Miya mo, "Ito asamasi." to obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.5 | 「 誰れか、さることは言ふとよ。いとほしく心憂きことかな。さばかりめづらかならむことは、おのづから聞こえありぬべきを。大将もさやうには言はで、世の中のはかなくいみじきこと、かく宇治の宮の族の、命短かりけることをこそ、いみじう悲しと思ひて のたまひしか」 |
「誰が、そのようなことを言うのですか。お気の毒な情けないことですね。それほど珍しい事は、自然と噂になろうものを。大将もそのようには言わないで、世の中のはかなく無常なこと、このような宇治の宮の一族の短命であったことを、ひどく悲しんでおっしゃっていたが」 |
「だれがまあそんな |
"Tare ka, saru koto ha ihu to yo. Itohosiku kokoro-uki koto kana! Sabakari meduraka nara m koto ha, onodukara kikoye ari nu beki wo! Daisyau mo sayau ni ha iha de, yononaka no hakanaku imiziki koto, kaku Udi-no-Miya no zou no, inoti mizikakari keru koto wo koso, imiziu kanasi to omohi te notamahi sika." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.6 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
to notamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.7 | 「 いさや、下衆は、たしかならぬことをも言ひはべるものを、と思ひはべれど、 かしこにはべりける下童の、ただこのころ、宰相が里に出でまうできて、たしかなるやうにこそ言ひはべりけれ。かくあやしうて亡せたまへること、人に聞かせじ。おどろおどろしく、おぞきやうなりとて、いみじく隠しけることどもとて。さて、詳しくは 聞かせたてまつらぬにやありけむ」 |
「さあ、下衆は、確かでないことも申すものを、と思いますが、あちらに仕えておりました下童が、つい最近、小宰相の君の実家に出て参って、確かなことのように言いました。このように不思議に亡くなったことは、誰にも聞かせまい。大げさで、気味の悪い話だからといって、ひどく隠していたこととか。そうして、詳しくはお聞かせ申し上げなかったのでしょう」 |
「ほんとうでございますか、どうでございますか、しもざまの者は確かでないこともほんとうらしく話にいたすものですが、その宇治の山荘におりました |
"Isaya, gesu ha, tasika nara nu koto wo mo ihi haberu mono wo, to omohi habere do, kasiko ni haberi keru simo-waraha no, tada kono-koro, Saisyau ga sato ni ide maude-ki te, tasika naru yau ni zo ihi haberi kere. Kaku ayasiu te use tamahe ru koto, hito ni kika se zi. Odoro-odorosiku, ozoki yau nari tote, imiziku kakusi keru koto-domo tote. Sate, kuhasiku ha kika se tatematura nu ni ya ari kem?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.8 | と聞こゆれば、 |
と申し上げると、 |
to kikoyure ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.9 | 「 さらに、かかること、またまねぶな、と言はせよ。かかる筋に、御身をももてそこなひ、人に軽く心づきなきものに思はれぬべきなめり」 |
「まったく、このような話は、二度と他人には話さないように、と言わせなさい。このような色恋沙汰で、お身の上を過ち、世人に軽々しく顰蹙をおかいになることになりましょう」 |
「その話をまたほかへ行ってするなと宰相からお言わせよ。そうした問題で宮は自身をだいなしにしておしまいになることにもなり、世間からも |
"Sarani, kakaru koto, mata manebu na, to iha se yo. Kakaru sudi ni, ohom-mi wo mo motesokonahi, hito ni karuku kokorodukinaki mono ni omoha re nu beki na' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.10 | といみじう思いたり。 |
とたいそうご心配になった。 |
こうお言いになって、中宮は非常に御心配をあそばす御様子であった。 |
to imiziu oboi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 5/6/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 5/6/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 5/6/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/13/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経