52 蜻蛉(大島本) |
KAGEROHU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十七歳三月末頃から秋頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March to fall at the age of 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 匂宮の物語 匂宮、侍従を迎えて語り合う |
3 Tale of Niou-no-miya Niou-no-miya invites and talks with Jiju |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 四月、薫と匂宮、和歌を贈答 |
3-1 Kaoru and Niou-no-miya compose and exchange waka in April |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 月たちて、「 今日ぞ渡らまし」と思し出でたまふ日の夕暮、いとものあはれなり。 御前近き橘の香のなつかしきに、ほととぎすの二声ばかり鳴きて渡る。「 ▼ 宿に通はば」と 独りごちたまふも飽かねば、 北の宮に、ここに 渡りたまふ日なりければ、橘を折らせて聞こえたまふ。 |
月が変わって、「今日が引き取る日であったのに」と思い出しなさった夕暮、まことにもの悲しい。御前近くの橘の香がやさしい感じのところに、ほととぎすが二声ほど鳴いて飛んで行く。「亡くなった人の所に行くなら」と独り言をおっしゃっても物足りないので、北の宮邸に、そこにお渡りになる日であったので、橘を折らせて申し上げなさる。 |
月が変わって、今日は宇治へ行ってみようと薫の思う日の夕方の気持ちはまた寂しく、 |
Tuki tati te, "Kehu zo watara masi." to obosi-ide tamahu hi no yuhugure, ito mono-ahare nari. O-mahe tikaki tatibana no kano natukasiki ni, hototogisu no huta-kowe bakari naki te wataru. "Yado ni kayoha ba." to hitori-goti tamahu mo aka ne ba, Kita no Miya ni, koko ni watari tamahu hi nari kere ba, tatibana wo wora se te kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
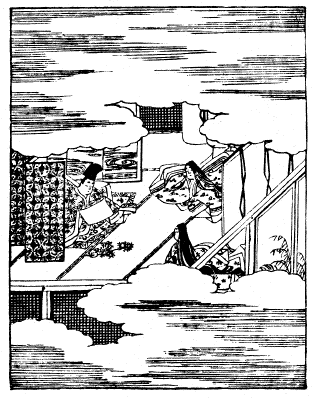 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 「 忍び音や君も泣くらむかひもなき |
「忍び音にほととぎすが鳴いていますが、あなた様も泣いていらっしゃいましょうか |
忍び |
"Sinobi ne ya Kimi mo naku ram kahi mo naki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | 死出の田長に心通はば」 |
いくら泣いても効のない方にお心寄せならば」 |
しでのたをさに心通はば |
side-no-tawosa ni kokoro kayoha ba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | 宮は、女君の御さまのいとよく似たるを、あはれと思して、 二所 眺めたまふ折なりけり。「 けしきある文かな」と見たまひて、 |
宮は、女君のご様子がとてもよく似ているのを、しみじみとお思いになって、お二方で物思いに耽っていらっしゃるところであった。「意味のありそうな手紙だ」と御覧になって、 |
宮は中の君の顔の浮舟によく似たのに心を慰めて、二人で庭をながめておいでになる時であった。言外に意味のあるような歌であると宮は御覧になり、 |
Miya ha, Womna-Gimi no ohom-sama no ito yoku ni taru wo, ahare to obosi te, huta-tokoro nagame tamahu wori nari keri. "Kesiki aru humi kana!" to mi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | 「 橘の薫るあたりはほととぎす |
「橘が薫っているところは、ほととぎすよ |
橘の |
"Tatibana no kaworu atari ha hototogisu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | 心してこそ鳴くべかりけれ |
気をつけて鳴くものですよ |
心してこそ鳴くべかりけれ |
kokoro-si te koso naku bekari kere |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.7 | わづらはし」 |
迷惑なことを」 |
なんだかかかりあいのあるようなことが言われますね。 |
Wadurahasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.8 | と書きたまふ。 |
とお書きになる。 |
とお返事をあそばした。 |
to kaki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.9 | 女君、 このことのけしきは、皆見知りたまひてけり。「 あはれにあさましきはかなさの、さまざまにつけて心深きなかに、 我一人もの思ひ知らねば、今までながらふるにや。それもいつまで」と心細く思す。宮も、隠れなきものから、隔てたまふもいと心苦しければ、ありしさまなど、すこしはとり直しつつ語りきこえたまふ。 |
女君は、この事件の経緯は、みなご存知なのであった。「しみじみと言いようもないほどあっけなかった、あれこれにつけて感慨深い中で、自分一人が物思いを知らないので、今まで生き永らえていたのであろうか。それもいつまで続くやら」と心細くお思いになる。宮も、隠すことのできないものから、分け隔てなさるのもとてもお気の毒なので、生前の様子などを、少し取り繕いながらお話し申し上げなさる。 |
宮と浮舟の姫君の関係もまたその人の死も何に基因するかも今は皆わかってしまった中の君は、姉の |
Womna-Gimi, kono koto no kesiki ha, mina mi-siri tamahi te keri. "Ahare ni asamasiki hakanasa no, sama-zama ni tuke te kokoro-hukaki naka ni, ware hitori mono-omohi sira ne ba, ima made nagarahuru ni ya? Sore mo itu made." to kokoro-bosoku obosu. Miya mo, kakure naki mono kara, hedate tamahu mo ito kokoro-gurusikere ba, ari si sama nado, sukosi ha tori-nahosi tutu katari kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.10 | 「 隠したまひしがつらかりし」 |
「隠していらっしゃったのがつらかった」 |
「だれであるのかをあなたがどこまでも隠そうとしたのが恨めしかったために |
"Kakusi tamahi si ga turakari si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.11 | など、泣きみ笑ひみ聞こえたまふにも、 異人よりは睦ましくあはれなり。 ことことしくうるはしくて、 例ならぬ御ことのさまも、 おどろき惑ひたまふ所にては、御訪らひの人しげく、 父大臣、兄の君たち隙なきも、いとうるさきに、 ここはいと心やすくて、なつかしくぞ思されける。 |
などと、泣いたり笑ったりしながら申し上げなさるにつけても、他の人よりは親しみを感じ胸を打つ。大げさに格式ばって、ご病気の件でも、大騒ぎをなさる所では、お見舞い客が多くて、父大臣や、兄の公達がひっきりなしなのも、とてもうるさいが、ここはたいそう気楽で、慕わしい感じにお思いなさるのであった。 |
など、泣きも笑いもしながらお語りになる相手が、恋人の姉であることにお慰みになるところも多かった。形式が簡単でなく、ちょっとお |
nado, naki-mi warahi-mi kikoye tamahu ni mo, koto-bito yori ha mutumasiku ahare nari. Koto-kotosiku uruhasiku te, rei nara nu ohom-koto no sama mo, odoroki madohi tamahu tokoro nite ha, ohom-toburahi no hito sigeku, titi-Otodo, Seuto-no-Kimi-tati hima naki mo, ito urusaki ni, koko ha ito kokoro-yasuku te, natukasiku zo obosa re keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 匂宮、右近を迎えに時方派遣 |
3-2 Niou-no-miya sends Tokikata to invite Jiju to Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | いと夢のやうにのみ、なほ、「いかで、いとにはかなりけることにかは」とのみいぶせければ、例の人びと召して、 右近を迎へに遣はす。 母君も、さらにこの水の音けはひを聞くに、我もまろび入りぬべく、悲しく心憂きことのどまるべくもあらねば、いとわびしうて帰りたまひにけり。 |
まことに夢のようにばかり、やはり、「どうして、とても急なことであったのか」とばかり気が晴れないので、いつもの人びとを召して、右近を迎えにやる。母君も、まったくこの川の音や感じを聞くと、自分もころがり込んでしまいそうで、悲しく嫌なことが休まる間もないので、とても侘しくてお帰りになったのであった。 |
浮舟の死んだことはまだ夢のようにばかりお思われになり、どうして急にそうなったかという不審がお解けにならぬため、例の内記たちをお召しになり、右近を呼びにおつかわしになった。母の常陸夫人も宇治川の音を聞くと自身も引き入れられるような悲しみが続くために困って京へ帰って行った。 |
Ito yume no yau ni nomi, naho, "Ikade, ito nihaka nari keru koto ni kaha." to nomi ibusekere ba, rei no hito-bito mesi te, Ukon wo mukahe ni tukahasu. Haha-Gimi mo, sarani kono midu no oto kehahi wo kiku ni, ware mo marobi-iri nu beku, kanasiku kokoro-uki koto nodomaru beku mo ara ne ba, ito wabisiu te kaheri tamahi ni keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 念仏の僧どもを 頼もしき者にて、いとかすかなるに 入り来たれば、ことことしく、にはかに立ちめぐりし宿直人どもも、見とがめず。「 あやにくに、限りのたびしも入れたてまつらずなりにしよ」と、思ひ出づるもいとほし。 |
念仏の僧どもを頼りとする人として、たいそうひっそりとしているところにやって来たので、厳重に、急に警戒していた宿直人どもも、見咎めない。「皮肉にも、最期の折にお入れ申し上げることができずに終わってしまったことよ」と、思い出すのもおいたわしい。 |
念仏の役を勤める僧だけが頼もしい人のようなかすかな家と見えたが、内記がはいって行っても、人が来るとすぐに外を見まわりに来るような |
Nenbutu no sou-domo wo tanomosiki mono nite, ito kasuka naru ni iri ki tare ba, koto-kotosiku, nihaka ni tati-meguri si tonowi-bito-domo mo, mi-togame zu. "Ayaniku ni, kagiri no tabi simo ire tatematura zu nari ni si yo." to, omohi-iduru mo itohosi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | 「 さるまじきことを思ほし焦がるること」と、見苦しく見たてまつれど、ここに来ては、 おはしましし夜な夜なのありさま、 抱かれたてまつりたまひて、舟に乗りたまひしけはひの、あてにうつくしかりしことなどを思ひ出づるに、 心強き人なくあはれなり。右近会ひて、いみじう泣くもことわりなり。 |
「とんでもないことをご執着なさったことよ」と、見苦しく拝見したが、こちらに来ては、お越しになった夜々の有様や、お抱かれなさって、舟にお乗りになった感じが、上品でかわいらしかったことなどを思い出すと、気丈な人などもなくしみじみとなる。右近が会って、ひどく泣くのも道理である。 |
それほどまでに悲しみにお |
"Saru maziki koto wo omohosi kogaruru koto." to, mi-gurusiku mi tatemature do, koko ni ki te ha, ohasimasi si yona-yona no arisama, idaka re tatematuri tamahi te, hune ni nori tamahi si kehahi no, ate ni utukusikari si koto nado wo omohi-iduru ni, kokoro-duyoki hito naku ahare nari. Ukon ahi te, imiziu naku mo kotowari nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 | 「 かくのたまはせて、御使になむ参り来つる」 |
「このようにおっしゃるので、お使いに来ました」 |
宮がこういう思召しで迎えのために自分らをおつかわしになった |
"Kaku notamahase te, ohom-tukahi ni nam mawiri ki turu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.5 | と言へば、 |
と言うと、 |
ということを語ると、 |
to ihe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.6 | 「 今さらに、人もあやしと言ひ思はむも慎ましく、参りても、はかばかしく 聞こし召し明らむばかり、もの聞こえさすべき心地もしはべらず。この御忌果てて、 あからさまにもなむ、と人に言ひなさむも、すこし似つかはしかりぬべきほどになしてこそ、心より外の命はべらば、いささか思ひ静まらむ折になむ、仰せ言なくとも参りて、 げにいと夢のやうなりしことどもも、語りきこえまほしき」 |
「今さら、皆が変だと言い思うのも気がひけまして、参上しても、はきはきとご納得の行くようには、何か申し上げられそうな気がしません。このご忌中が終わって、ちょっとどこそこにと人に言っても、少しふさわしいころになってから、思いの他に生きていましたら、少し気持ちが静まったような時に、ご命令がなくても参上して、おっしゃるようにとても夢のようだった事柄を、お話し申し上げとう存じます」 |
今になって他の女房たちからも怪しいことと言われ、思われするであろうことが苦しく考えられて、「まいりましてもよくおわかりいただきますほどな細かなお話がまだできます自信がございません。お四十九日が済みましたあとで、ちょっと外へまいると申すような体裁を作りましても不自然でないころになりました時、私はもう生きても居られない気はいたしますものの、まだ生き延びておられましたなら、お召しがございませんでも伺いまして、ほんとうに夢のようでございました悲しいお話も申し上げたいと思います」 |
"Imasara ni, hito mo ayasi to ihi omoha m mo tutumasiku, mawiri te mo, haka-bakasiku kikosimesi akiramu bakari, mono kikoye sasu beki kokoti mo si habera zu. Kono ohom-imi hate te, akarasama ni mo nam, to hito ni ihi-nasa m mo, sukosi nitukahasi kari nu beki hodo ni nasi te koso, kokoro yori hoka no inoti habera ba, isasaka omohi sidumara m wori ni nam, ohose-goto naku to mo mawiri te, geni ito yume no yau nari si koto-domo mo, katari kikoye mahosiki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.7 | と言ひて、今日は動くべくもあらず。 |
と言って、今日は動きそうにもない。 |
と言い、今は動きそうにもない。 |
to ihi te, kehu ha ugoku beku mo ara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 時方、侍従と語る |
3-3 Tokikata talks with Jiju at Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 大夫も泣きて、 |
大夫も泣いて、 |
内記も泣いて、 |
Taihu mo naki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 「 さらに、この御仲のこと、こまかに知りきこえさせはべらず。物の心知りはべらずながら、たぐひなき御心ざしを見たてまつりはべりしかば、 君たちをも、何かは急ぎてしも聞こえ承らむ。つひには仕うまつるべきあたりにこそ、と思ひたまへしを、 言ふかひなく悲しき御ことの後は、 私の御心ざしも、なかなか深さまさりてなむ」 |
「まったく、お二方の事は、詳しくは存じ上げません。物の道理もわきまえていませんが、無類のご寵愛を拝見しましたので、あなた方を、どうして急いでお近づき申し上げよう。いずれはお仕えなさるはずの方だ、と存じていましたが、何とも言いようもなく悲しいお事の後は、わたし個人としても、かえって悲しみの深さがまさりまして」 |
「私は何も細かい御関係のことまでは知らないのですし、事情もわかりませんが、宮様がどんなに深い愛をお持ちになりましたかということだけは存じ上げていたものですから、あなたがたとも急いで御懇意にならずとも、しまいには御主人としてお仕えする方についておいでになる方と思いまして |
"Sarani, kono ohom-naka no koto, komaka ni siri kikoye sase habera zu. Mono no kokoro siri habera zu nagara, taguhi naki mi-kokorozasi wo mi tatematuri haberi sika ba, Kimi-tati wo mo, nanikaha isogi te simo kikoye uke tamahara m. Tuhini ha tukau-maturu beki atari ni koso, to omohi tamahe si wo, ihukahinaku kanasiki ohom-koto no noti ha, watakusi no mi-kokorozasi mo, naka-naka hukasa masari te nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | と語らふ。 |
と懇切に言う。 |
などと言っていた。 |
to katarahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | 「 わざと御車など 思しめぐらして、奉れたまへるを、空しくては、いといとほしうなむ。 今一所にても参りたまへ」 |
「わざわざお車などをお考えめぐらされて、差し向けなさったのを、空っぽで帰るのは、まことにお気の毒です。もうお一方でも参上なさい」 |
「車も宮御自身でお |
"Wazato mi-kuruma nado obosi megurasi te, tatemature tamahe ru wo, munasiku te ha, ito itohosiu nam. Ima hito-tokoro nite mo mawiri tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | と言へば、侍従の君呼び出でて、 |
と言うので、侍従の君を呼び出して、 |
と内記が言うので、右近は侍従を呼び、 |
to ihe ba, Zizyuu-no-Kimi yobi-ide te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 「 さは、参りたまへ」 |
「それでは、参上なさい」 |
「あなたが伺ってください、私の代わりに」 |
"Saha, mawiri tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.7 | と言へば、 |
と言うと、 |
と言った。 |
to ihe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8 | 「 まして何事をかは聞こえさせむ。さても、なほ、この御忌のほどにはいかでか。忌ませ たまはぬか」 |
「あなた以上に何を申し上げることができましょう。それにしても、やはり、このご忌中の間にはどうして。お厭いあそばさないのでしょうか」 |
「あなたでさえもお話を申し上げる自信が持てないのに、私にどうしてそれができましょう。それにしましても忌中の者がお |
"Masite nani-goto wo kaha kikoyesase m. Satemo, naho, kono ohom-imi no hodo ni ha ikade ka. Ima se tamaha nu ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.9 | と言へば、 |
と言うと、 |
to ihe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.10 | 「 悩ませたまふ御響きに、さまざまの御慎みどもはべめれど、忌みあへさせたまふまじき御けしきになむ。また、かく深き御契りにては、籠もらせたまひてもこそおはしまさめ。 残りの日いくばくならず。なほ一所参りたまへ」 |
「ご病気で大騒ぎをして、いろいろなお慎みがございますようですが、忌明けをお待ち切れになれないようなご様子です。また、このように深いご宿縁では、忌籠もりあそばすのでいらっしゃいましょう。忌明けまでの日も幾日でもない。やはりお一方参上なさい」 |
「御病気のためにいろいろなふうに御謹慎をなさらねばならなくなっていらっしゃいますが、そんなこともかまっておいでになれない御様子なのです。また考えてみますと、あれほどお愛しになった方のためには宮様御自身が忌におこもりになってもよろしいわけなのですからね、もう忌の残りが幾日もあるのではないのですから、ぜひお一人だけは来てください」 |
"Nayama se tamahu ohom-hibiki ni, sama-zama no ohom-tutusimi-domo habe' mere do, imi ahe sase tamahu maziki mi-kesiki ni nam. Mata, kaku hukaki ohom-tigiri nite ha, komora se tamahi te mo koso ohasimasa me. Nokori no hi ikubaku nara zu. Naho hito-tokoro mawiri tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.11 | と責むれば、侍従ぞ、 ありし御さまもいと恋しう思ひきこゆるに、「 いかならむ世にかは見たてまつらむ、かかる折に」と思ひなして参りける。 |
と責めるので、侍従が、以前のご様子もとても恋しく思い出し申し上げるので、「いつの世にかお目にかかることができようか、この機会に」と思って参上するのであった。 |
内記がこう責めるので、侍従も宮の御様子をおなつかしく思い出している心から、もう一度お目にかかりうる機会などというものはありえないことであるから、こうした時にでもと願うようになり、まいることにした。 |
to semure ba, Zizyuu zo, arisi ohom-sama mo ito kohisiu omohi kikoyuru ni, "Ika nara m yo ni kaha mi tatematura m, kakaru wori ni." to omohi-nasi te mawiri keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 第四段 侍従、京の匂宮邸へ |
3-4 Jiju goes to Kyoto to meet Niou-no-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | 黒き衣ども着て、引きつくろひたる容貌もいときよげなり。 裳は、ただ今我より上なる人なきにうちたゆみて ★、色も変へざりければ、 薄色なるを持たせて参る。 |
黒い衣装類を着て、化粧をした容貌もとても美しそうである。裳は、今後は自分より目上の人はいないとうっかりして、色も染め変えなかったので、薄い紫色のを持たせて参上する。 |
黒い服ながら引き繕って着た姿はきれいであった。 |
Kuroki kinu-domo ki te, hiki-tukurohi taru katati mo ito kiyoge nari. Mo ha, tadaima ware yori uhe naru hito naki ni uti-tayumi te, iro mo kahe zari kere ba, usu-iro naru wo mota se te mawiru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 | 「 おはせましかば、この道にぞ 忍びて出でたまはまし。 人知れず心寄せきこえしものを」など思ふにもあはれなり。道すがら泣く泣くなむ来ける。 |
「生きていらっしゃったら、この道を人目を忍んでお出になるはずだったのに。人知れずお心寄せ申し上げていたのに」などと思うにつけ悲しい。道中泣きながらやって来た。 |
姫君がおいでになったなら、宮にこうして迎えられておいでになったであろう、自分はその時にお付きして行こうと心にきめていたのであったがと思い出すのは悲しかった。途中をずっと泣きながら侍従は二条の院へまいった。 |
"Ohase masika ba, kono miti ni zo sinobi te ide tamaha masi. Hito-sire-zu kokoro-yose kikoye si mono wo." nado omohu ni mo ahare nari. Mitisugara naku-naku nam ki keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.3 | 宮は、この人参れり、と聞こし召すもあはれなり。 女君には、あまりうたてあれば、聞こえたまはず。 寝殿におはしまして、渡殿に降ろしたまへり。ありけむさまなど詳しう問はせたまふに、日ごろ思し嘆きしさま、その夜泣きたまひしさま、 |
宮は、この人が参った、とお耳にあそばすにつけてもお胸が迫る。女君には、あまりに憚れるので、申し上げなさらない。寝殿にお出でになって、渡殿に降ろさせなさった。生前の様子などを詳しくお尋ねあそばすと、日頃お嘆きになっていた様子や、その夜にお泣きになった様子を、 |
兵部卿の宮は侍従の来たしらせをお受けになっても身にしむようにお思われになった。夫人へは恥ずかしくてお話しにはならなかったのである。宮は寝殿のほうへおいでになり、そこの廊のほうへ車を着けさせて侍従を |
Miya ha, kono hito mawire ri, to kikosi-mesu mo ahare nari. Womna-Gimi ni ha, amari utate are ba, kikoye tamaha zu. Sinden ni ohasimasi te, watadono ni orosi tamahe ri. Ari kem sama nado kuhasiu toha se tamahu ni, higoro obosi nageki si sama, sono yo naki tamahi si sama, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.4 | 「 あやしきまで言少なに、おぼおぼとのみものしたまひて、いみじと思すことをも、人にうち出でたまふことは難く、ものづつみをのみしたまひしけにや、のたまひ置くこともはべらず。夢にも、 かく心強きさまに思しかくらむとは、思ひたまへずなむはべりし」 |
「不思議なまでに言葉少なく、ぼんやりとばかりしていらっしゃって、大変だとお思いになることも、他人にお話しになることはめったになく、遠慮ばかりなさったせいでしょうか、言い残しなさることもございません。夢にも、このような心強いことをお覚悟だったとは、存じませんでした」 |
「怪しいほどお口数の少ない方で、内気でいらっしゃいましたから、遺言らしいことは何もなさいませんでした。夢にも自殺などという強いことのおできになるとは思われませんでした」 |
"Ayasiki made koto-zukuna ni, obo-obo to nomi monosi tamahi te, imizi to obosu koto wo mo, hito ni uti-ide tamahu koto ha kataku, mono-dutumi wo nomi si tamahi si ke ni ya, notamahi-oku koto mo habera zu. Yume ni mo, kaku kokoro-duyoki sama ni obosi-kaku ram to ha, omohi tamahe zu nam haberi si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.5 | など、詳しう聞こゆれば、ましていといみじう、「 さるべきにても、ともかくもあらましよりも、いかばかりものを思ひ立ちて、さる水に溺れけむ」と思しやるに、「 これを見つけて堰きとめたらましかば」と、湧きかへる心地したまへど、かひなし。 |
などと、詳しく申し上げると、ひとしお実に悲しく思われて、「前世からの因縁で、病死などすることなどよりも、どんなに覚悟なさって、そのような川の中に溺死したのだろう」とお思いやりなさると、「その場を見つけてお止めできたら」と、煮えかえる気持ちがなさるが、どうしようもない。 |
などと侍従が話すことによって、宮はいっそうお悲しみが深くなり、命数が尽きて死んだということよりも、どんなに物思いを多くして恐ろしい川へなど身を投げたのであろうと御想像あそばすのが苦しく、その時に見つけることができてとどめえたならばと、沸きかえるような心持ちにおなりになるのであるが、今ではすべてむなしいことであった。 |
nado, kuhasiu kikoyure ba, masite ito imiziu, "Saru beki ni te mo, tomo-kakumo aramasi yori mo, ikabakari mono wo omohi-tati te, saru midu ni obore kem." to obosi-yaru ni, "Kore wo mituke te seki tome tara masika ba." to waki-kaheru kokoti si tamahe do, kahinasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.6 | 「 御文を焼き失ひたまひしなどに、などて目を立てはべらざりけむ」 |
「お手紙をお焼き捨てになったことなどに、どうして不審に思わなかったのでございましょう」 |
「あのお手紙を始末してお焼きになりました時に、なぜ私らの頭が働かなかったのでございましょう」 |
"Ohom-humi wo yaki usinahi tamahi si nado ni, nadote me wo tate habera zari kem." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.7 | など、夜一夜語らひたまふに、聞こえ明かす。 かの巻数に書きつけたまへりし、母君の返り事などを聞こゆ。 |
などと、一晩中お聞きなさるので、お話し申し上げて夜が明ける。あの巻数にお書きつけになった、母君の返事などを申し上げる。 |
と侍従は言ったりして、夜の明けるまで語っても語り足りないというふうであった。寺からもらった経巻へ書いて母君の返事にした歌のことなどもお話しした。 |
nado, yo hito-yo katarahi tamahu ni, kikoye akasu. Kano kwanzyu ni kaki-tuke tamahe ri si, Haha-Gimi no kaheri-goto nado wo kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 第五段 侍従、宇治へ帰る |
3-5 Jiju went back to Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.1 | 何ばかりのものとも 御覧ぜざりし人も、睦ましくあはれに思さるれば、 |
何程の者ともお考えでなかった侍従も、親しくしみじみと思われなさるので、 |
侍従などは何とも宮の思っておいでにならなかった女であったが、哀れに思召すために、 |
Nani-bakari no mono to mo go-ran-ze zari si hito mo, mutumasiku ahare ni obosa rure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.2 | 「 わがもとにあれかし。 あなたももて離るべくやは」 |
「わたしの側にいなさい。あちらにも縁がないではない」 |
「自分の所にいるがよい。あちらにいる奥さんもあの人には他人でなかったのだから」 |
"Waga moto ni are kasi. Anata mo mote-hanaru beku ya ha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.3 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
と仰せられたが、 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.4 | 「 さて、さぶらはむにつけても、もののみ悲しからむを思ひたまへれば、今 この御果てなど過ぐして」 |
「そのようにして、お仕えしますにつけても、何となく悲しく存じられますので、もう暫くこの御忌みなどを済ませましてから」 |
「そうしてお仕えさせていただきましては何も何も悲しいことになりましょう。ともかくもお忌を済ませましてから、どうとも身の振り方を考えます」 |
"Sate, saburaha m ni tuke te mo, mono nomi kanasikara m wo omohi tamahe re ba, ima kono ohom-hate nado sugusi te." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.5 | と聞こゆ。「 またも参れ」など、この人をさへ、飽かず思す。 |
と申し上げる。「再び参るように」などと、この人までも、別れがたくお思いになる。 |
侍従はこう申し上げた。「また来るがいい」こんな人とすらも別れるのを悲しく宮は思召した。 |
to kikoyu. "Mata mo mawire." nado, kono hito wo sahe, akazu obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.6 | 暁帰るに、 かの御料にとてまうけさせたまひける櫛の筥一具、衣筥一具、 贈物にせさせたまふ。 さまざまにせさせたまふことは多かりけれど、おどろおどろしかりぬべければ、ただこの人に仰せたるほどなりけり。 |
早朝に帰る時に、あの方の御料にと思って準備なさっていた櫛の箱一具、衣箱一具を、贈物にお遣わしになる。いろいろとお整えさせになったことは多かったが、仰々しくなってしまいそうなので、ただ、この人に与えるのに相応な程度であった。 |
浮舟のために作らせておありになった |
Akatuki kaheru ni, kano go-reu ni tote mauke sase tamahi keru kusi no hako hito-yorohi, koromo-bako hito-yorohi, okurimono ni se sase tamahu. Sama-zama ni se sase tamahu koto ha ohokari kere do, odoro-odorosikari nu bekere ba, tada kono hito ni ohose taru hodo nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.7 | 「 なに心もなく参りて、かかることどものあるを、人はいかが見む。すずろにむつかしきわざかな」 |
「何も考えなく参上して、このようなことがあったのを、女房はどのように見るだろうか。何となく厄介なことだわ」 |
突然山荘を出て来て、こうした |
"Nani-gokoro mo naku mawiri te, kakaru koto-domo no aru wo, hito ha ikaga mi m. Suzuro ni mutukasiki waza kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.8 | と思ひわぶれど、いかがは聞こえ返さむ。 |
と困るが、どうして辞退申し上げられよう。 |
少し困ったことであると侍従は思ったのであるが、御辞退のできることでもなかった。 |
to omohi-wabure do, ikagaha kikoye kahesa m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.9 | 右近と二人、忍びて見つつ、つれづれなるままに、こまかに今めかしうし集めたることどもを見ても、いみじう泣く。装束もいとうるはしうし集めたるものどもなれば、 |
右近と二人で、こっそりと見ながら、所在ないままに、精巧で今風に仕立ててあるのを見ても、ひどく泣く。装束もたいそう立派に仕立て上げられたものばかりなので、 |
宇治へ帰った侍従は右近と二人でひそかに櫛の箱と衣箱の衣裳をつれづれなままにこまごまと見た。はなやかな |
Ukon to hutari, sinobi te mi tutu, ture-dure naru mama ni, komaka ni imamekasiu si atume taru koto-domo wo mi te mo, imiziu naku. Syauzoku mo ito uruhaiu si atume taru mono-domo nare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.10 | 「 かかる御服に、これをばいかでか隠さむ」 |
「このような服喪期間中なので、これをどう隠したものか」 |
喪にこもっている自分たちはこれをどう隠しておればいいかということにも苦心を要した。 |
"Kakaru ohom-buku ni, kore wo ba ikadeka kakusa m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.11 | など、もてわづらひける。 |
などと、困るのであった。 |
薫も思い余って宇治へ行くことにした。 |
nado, mote-wadurahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 5/6/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 5/6/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 5/6/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/13/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経