52 蜻蛉(大島本) |
KAGEROHU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十七歳三月末頃から秋頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March to fall at the age of 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 浮舟の物語 浮舟失踪後の人びとの動転 |
1 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, the others' perplexity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 宇治の浮舟失踪 |
1-1 Ukifune's disapperarance at Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | かしこには、人びと、おはせぬを求め騒げど、かひなし。 物語の姫君の、人に盗まれたらむ明日の やうなれば、 詳しくも言ひ続けず。 京より、ありし使の帰らずなりにしかば、おぼつかなしとて、 また人おこせたり。 |
あちらでは、女房たちが、いらっしゃらないのを探して大騷ぎするが、その効がない。物語の姫君が、誰かに盗まれたような朝のようなので、詳しくは話し続けない。京から、先日の使者が帰れなくなってしまったので、気がかりに思って、再び使者をよこした。 |
宇治の山荘では |
Kasiko ni ha, hito-bito, ohase nu wo motome sawage do, kahinasi. Monogatari no hime-gimi no, hito ni nusuma re tara m asita no yau nare ba, kuhasiku mo ihi tuduke zu. Kyau yori, arisi tukahi no kahera zu nari ni sika ba, obotukanasi tote, mata hito okose tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 「 まだ、鶏の鳴くになむ、出だし立てさせたまへる」 |
「まだ、鶏が鳴く時刻に、出立させなさった」 |
まだ鶏の鳴いているころに出立たせた |
"Mada, tori no naku ni nam, idasi tate sase tamahe ru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | と使の言ふに、いかに聞こえむと、乳母よりはじめて、あわて惑ふこと限りなし。思ひやる方なくて、ただ騷ぎ合へるを、 かの心知れるどちなむ、いみじくものを思ひたまへりしさまを思ひ出づるに、「 身を投げたまへるか」とは思ひ寄りける。 |
と使者が言うと、どのように申し上げようと、乳母をはじめとして、あわてふためることこの上ない。推量しても見当がつかず、ただ大騷ぎし合っているのを、あの事情を知っている者どうしは、ひどく物思いなさっていた様子を思い出すと、「身を投げなさったのか」と思い寄るのであった。 |
と言っている使いにどうこの始末を書いて帰したものであろうと、 |
to tukahi no ihu ni, ikani kikoye m to, Menoto yori hazime te, awate madohu koto kagiri nasi. Omohi-yaru kata naku te, tada sawagi-ahe ru wo, kano kokorosire-ru-doti nam, imiziku mono wo omohi tamahe ri si sama wo omohi-iduru ni, "Mi wo nage tamahe ru ka?" to ha omohi-yori keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 泣く泣くこの文を開けたれば、 |
泣きながらこの手紙を開くと、 |
泣く泣く夫人の送ってきた手紙をあけて見ると、 |
Naku-naku kono humi wo ake tare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | 「 いとおぼつかなさに、まどろまれはべらぬけにや、今宵は夢にだにうちとけても見えず。物に襲はれつつ、心地も例ならずうたてはべるを。 なほいと恐ろしく、 ものへ渡らせたまはむことは近くなれど、 そのほど、ここに迎へたてまつりてむ。今日は雨降りはべりぬべければ」 |
「とても気がかりなので、眠れませんでしたせいでしょうか、今夜は夢でさえゆっくりと見えません。悪夢にうなされうなされして、気分も普段と違って悪うございますよ。やはりとても恐ろしく、あちらにお移りになる日は近くなったが、その前後に、こちらにお迎え申しましょう。今日は雨が降りそうでございますので」 |
あまりにあなたが心配で安眠のできないせいでしょうか、今夜は夢の中であなたを見ることすらよくできないのです。眠ったかと思うと何かに襲われて苦しむのです。そんなことで気分もよろしくなくて困ります。移転される日の近くなったことは知っていますが、それまでの間をこの家へあなたを来させていたく思います。今日は雨になりそうですからだめでしょうが。 |
"Ito obotukanasa ni, madoroma re habera nu ke ni ya, koyohi ha yume ni dani utitoke te mo miye zu. Mono ni osoha re tutu, kokoti mo rei nara zu utate haberu wo! Naho ito osorosiku, mono he watara se tamaha m koto ha tikaku nare do, sono hodo, koko ni mukahe tatematuri te m. Kehu ha ame huri haberi nu bekere ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | などあり。 昨夜の御返りをも開けて見て、右近いみじう泣く。 |
などとある。昨夜のお返事を開いて見て、右近はひどく泣く。 |
と書かれてあった。昨夜浮舟の書いた返事もあけて読みながら右近は非常に泣いた。 |
nado ari. Yobe no ohom-kaheri wo mo ake te mi te, Ukon imiziu naku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | 「 さればよ。心細きことは 聞こえたまひけり。我に、などかいささかのたまふことのなかりけむ。 幼かりしほどより、つゆ心置かれたてまつることなく、塵ばかり隔てなくてならひたるに、今は限りの道にしも、我を後らかし、けしきをだに見せたまはざりけるがつらきこと」 |
「そうであったか。心細いことを申し上げなさっていたのだ。わたしに、どうして少しもおしゃってくださらなかったのだろう。幼かった時から、少しも分け隔て申し上げることもなく、塵ほども隠しだてすることなくやって来たのに、最期の別れ路の時に、わたしを後に残して、そのそぶりさえお見せにならなかったのがつらいことだ」 |
こんな覚悟をしておいでになったので心細いようなことをお言いになったのである、小さい時から少しの隔てもなく親しみ合った主従ではないか、隠し事は |
"Sarebayo! Kokoro-bosoki koto ha kikoye tamahi keri. Ware ni, nadoka isasaka notamahu koto no nakari kem? Wosanakari si hodo yori, tuyu kokoro-oka re tatematuru koto naku, tiri bakari hedate naku te narahi taru ni, ima ha kagiri no miti ni simo, ware wo okurakasi, kesiki wo dani mise tamaha zari keru ga turaki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8 | と思ふに、 足摺りといふことをして泣くさま、若き子どものやうなり。 いみじく思したる御けしきは、見たてまつりわたれど、かけても、かくなべてならずおどろおどろしきこと、思し寄らむものとは見えざりつる人の御心ざまを、「なほ、いかにしつることにか」とおぼつかなくいみじ。 |
と思うと、足摺りということをして泣く有様は、若い子供のようである。ひどくお悩みのご様子は、ずっと拝見して来たが、まったく、このように普通の人と違って大それたこと、お思いつくとは見えなかった方のお気持ちを、「やはり、どうなさったことか」と分からず悲しい。 |
と思うと、泣いても泣いても足らず |
to omohu ni, asi-zuri to ihu koto wo si te naku sama, wakaki kodomo no yau nari. Imiziku obosi taru mi-kesiki ha, mi tatematuri watare do, kaketemo, kaku nabete nara zu odoro-odorosiki koto, obosi-yora m mono to ha miye zari turu hito no mi-kokoro-zama wo, "Naho, ikani si turu koto ni ka?" to obotukanaku imizi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9 | 乳母は、なかなかものもおぼえで、ただ、「いかさまにせむ。いかさまにせむ」とぞ 言はれける。 |
乳母は、かえって何も分からなくなって、ただ、「どうしよう。どうしよう」と言うだけであった。 |
乳母はかえってはげしい驚きのために放心して、「どうすればいいだろう、どうすれば」とばかり言っているのである。 |
Menoto ha, naka-naka mono mo oboye de, tada, "Ika sama ni se m? Ika sama ni se m?" to zo iha re keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 匂宮から宇治へ使者派遣 |
1-2 Niou-no-miya sends a messenger to Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 宮にも、いと 例ならぬけしきありし御返り、「 いかに思ふならむ。我を、さすがにあひ思ひたるさまながら、あだなる心なりとのみ、深く疑ひたれば、他へ行き隠れむとにやあらむ」と思し騷ぎ、御使あり。 |
宮にも、まことにいつもと違った様子であったお返事に、「どのように思っているのだろう。わたしを、そうはいっても愛している様子でいながら、浮気な心だとばかり、深く疑っていたので、他へ身を隠したのであろうか」とお慌てになって、お使者がある。 |
|
Miya ni mo, ito rei nara nu kesiki ari si ohom-kaheri, "Ika ni omohu nara m? Ware wo, sasuga ni ahi-omohi taru sama nagara, ada naru kokoro nari to nomi, hukaku utagahi tare ba, hoka he iki kakure m to ni ya ara m?" to obosi sawagi, ohom-tukahi ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | ある限り泣き惑ふほどに来て、御文もえたてまつらず。 |
居合わせた者たちが泣き騒いでいるところに来て、お手紙も差し上げられない。 |
使いが来てみると家の中は女の泣き叫ぶ声に満ちていてお手紙を受け取ろうとする者もない。 |
Aru kagiri naki madohu hodo ni ki te, ohom-humi mo e tatematura zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 「 いかなるぞ」 |
「どうしたことか」 |
どうしたことか |
"Ika naru zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | と下衆女に問へば、 |
と下衆女に尋ねると、 |
と |
to gesu-womna ni tohe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 「 上の、今宵、にはかに亡せたまひにければ、 ものもおぼえたまはず。 頼もしき人もおはしまさぬ折なれば、 さぶらひたまふ人びとは、ただものに当たりてなむ 惑ひたまふ」 |
「ご主人様が、今夜、急にお亡くなりになったので、何もかも分からなくいらっしゃいます。頼りになる方もいらっしゃらない時なので、お仕えなさっている方々は、ただ物に突き当たっておろおろなさっています」 |
「姫君が昨晩にわかにお |
"Uhe no, koyohi, nihaka ni use tamahi ni kere ba, mono mo oboye tamaha zu. Tanomosiki hito mo ohasimasa nu wori nare ba, saburahi tamahu hito-bito ha, tada mono ni atari te nam madohi tamahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | と言ふ。心も深く知らぬ男にて、詳しう問はで参りぬ。 |
と言う。事情を深く知らない男なので、詳しくは尋ねないで帰参した。 |
と言った。何の事情も知らぬ男であったから、くわしく聞くこともせずに帰ってまいった。 |
to ihu. Kokoro mo hukaku sira nu wonoko nite, kuhasiu toha de mawiri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 「 かくなむ」と申させたるに、 夢とおぼえて、 |
「こうこうでした」と申し上げさせたところ、夢のように思われて、 |
そして山荘の出来事を取り次ぎによっておしらせしたのであった。宮は夢とよりお思われにならない。 |
"Kaku nam." to mausa se taru ni, yume to oboye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | 「 いとあやし。いたくわづらふとも聞かず。日ごろ、悩ましとのみありしかど、昨日の返り事はさりげもなくて、常よりもをかしげなりしものを」 |
「まことに変だ。ひどく患っていたとも聞いてない。日頃、気分が悪いとばかりあったが、昨日の返事は変わったこともなくて、いつものよりも興趣があったものを」 |
ひどく病をしているというふうでもなく、いつも気分がすぐれぬとは書いてあったが、 |
"Ito ayasi. Itaku wadurahu to mo kika zu. Higoro, nayamasi to nomi ari sika do, kinohu no kaheri-goto ha sarige-mo-naku te, tune yori mo wokasige nari si mono wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | と、思しやる方なければ、 |
と、ご想像もおつきにならないので、 |
to, obosi-yaru kata nakere ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 「 時方、行きてけしき見、たしかなること問ひ聞け」 |
「時方、行って様子を見て、はっきりとしたことを尋ね出せ」 |
|
"Tokikata, iki te kesiki mi, tasika naru koto tohi kike." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
お命じになった。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 「 かの大将殿、いかなることか、聞きたまふことはべりけむ、宿直する者おろかなり、など戒め仰せらるるとて、 下人のまかり出づるをも、 見とがめ問ひはべるなれば、ことづくることなくて、 時方まかりたらむを、ものの聞こえはべらば、 思し合はすることなどやはべらむ。さて、にはかに人の亡せたまへらむ所は、論なう騒がしう、人しげくはべらむを」と聞こゆ。 |
「あの大将殿は、どのようなことか、お聞きになっていることがございましたのでしょう、宿直をする者が怠慢である、などと訓戒なさったと言って、下人が退出するのさえ、注意して調べると言いますので、口実もなくて、時方が参ったのを、事が漏れたりしましたら、お気づきになることがございましょう。そうして、急に人のお亡くなりになった所は、言うまでもなく騒がしく、人目が多くございましょうから」と申し上げる。 |
「あの大将のお耳にどんなことがはいったのですか、 |
"Kano Daisyau-dono, ika naru koto ka, kiki tamahu koto haberi kem, tonowi suru mono oroka nari, nado imasime ohose raruru tote, simo-bito no makari-iduru wo mo, mi-togame tohi haberu nare ba, koto-dukuru koto naku te, Tokikata makari tara m wo, mono no kikoye habera ba, obosi-ahasuru koto nado ya habera m? Sate, nihaka ni hito no use tamahe ra m tokoro ha, ron-nau sawagasiu, hito sigeku habera m wo." to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | 「 さりとては、いとおぼつかなくてやあらむ。なほ、とかくさるべきさまに構へて、例の、心知れる侍従などに会ひて、いかなることをかく言ふぞ、と案内せよ。下衆はひがことも言ふなり」 |
「そうかといって、まことに気がかりなままでいられようか。やはり、何か適当に計らって、いつものように、事情を知っている侍従などに会って、どうしたわけでこのように言うのか、と尋ねよ。下衆も間違ったことを言うものだ」 |
「だからといって、訳のわからぬままにしておけるものではない。何とか口実を作って行って、こちらの味方になっている侍従などに |
"Saritote ha, ito obotukanaku te ya ara m? Naho, tokaku saru-beki sama ni kamahe te, rei no, kokoro-sire ru Ziziu nado ni ahi te, ika naru koto wo kaku ihu zo, to anai se yo. Gesu ha higa-koto mo ihu nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.14 | とのたまへば、いとほしき御けしきもかたじけなくて、夕つ方行く。 |
とおっしゃるので、お気の毒なご様子も恐れ多くて、夕方に行く。 |
こう仰せられる宮の御様子においたましいところの見えるのももったいなくて時方はその夕方から宇治へ出かけた。 |
to notamahe ba, itohosiki mi-kesiki mo katazikenaku te, yuhu-tu-kata yuku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 時方、宇治に到着 |
1-3 Tokikata arrived at Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | かやすき人は、疾く行き着きぬ。雨少し降り止みたれど、わりなき道にやつれて、下衆のさまにて来たれば、人多く立ち騷ぎて、 |
身分の軽い者は、すぐに行き着いた。雨が少し降り止んだが、難儀な山道を身を簡略にして、下衆の恰好で来たところ、人が大勢立ち騒いで、 |
この人たちが急いで行けば早く行き着くこともできるのであった。少し降っていた雨はやんだが |
Kayasuki hito ha, toku iki-tuki nu. Ame sukosi huri yami tare do, warinaki miti ni yature te, gesu no sama nite ki tare ba, hito ohoku tati-sawagi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 「 今宵、やがてをさめたてまつるなり」 |
「今夜、このままご葬送申し上げるのです」 |
今夜のうちにお葬儀をしてしまうのである |
"Koyohi, yagate wosame tatematuru nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | など言ふを聞く心地も、あさましくおぼゆ。右近に消息したれども、え会はず、 |
などと言うのを聞く気分も、驚き呆れて思われる。右近に案内を乞うたが、会うことはできない。 |
などと皆の言っているのを聞いて時方はひどく驚かされた。右近に面会を求めたが逢えない。 |
nado ihu wo kiku kokoti mo, asamasiku oboyu. Ukon ni seusoko si tare domo, e aha zu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 「 ただ今、ものおぼえず。起き上がらむ心地もせでなむ。さるは、 今宵ばかりこそ、かくも立ち寄りたまはめ ★、え聞こえぬこと」 |
「ただ今は、何も分かりません。起き上がる気持ちもしません。それにしても、今夜を最後に、このようにお立ち寄りになるのでしょうが、お話しできませんことが」 |
「何が何やらわからぬふうになっていまして、起き上がる力もないのです。夜分おそくにでもなりましたらおいでくださいませ。お目にかかれませんのは残念でございます」 |
"Tadaima, mono oboye zu. Oki-agara m kokoti mo se de nam. Saruha, koyohi bakari koso, kaku mo tati-yori tamaha me, e kikoye nu koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | と言はせたり。 |
と言わせた。 |
と取り次ぎをもって言わせた。 |
to ihase tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 「 さりとて、かくおぼつかなくては、いかが帰り参りはべらむ。今一所だに」 |
「そうは言っても、このようにはっきり分かりませんでは、どうして帰参できましょう。せめてもうお一方にでも」 |
「そうではありましょうが、こちらの御事情がわからぬままでは帰りようがありません。もう一人の方にでも逢わせてください」 |
"Saritote, kaku obotukanaku te ha, ikaga kaheri mawiri habera m. Ima hito-tokoro dani." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | と切に言ひたれば、侍従ぞ会ひたりける。 |
と切に言ったので、侍従が会ったのであった。 |
時方がせつに言ったために侍従が出て来た。 |
to seti ni ihi tare ba, Zizyuu zo ahi tari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.8 | 「 いとあさまし。 思しもあへぬさまにて亡せたまひにたれば、いみじと言ふにも飽かず、夢のやうにて、誰も誰も惑ひはべるよしを 申させたまへ。すこしも心地のどめはべりてなむ、日ごろも、もの思したりつるさま、一夜、 いと心苦しと思ひきこえさせたまへりしありさまなども、聞こえさせはべるべき。 この穢らひなど、人の忌みはべるほど過ぐして、今一度立ち寄りたまへ」 |
「まことに呆れたことです。ご自身も思いがけない様子でお亡くなりになったので、悲しいと言っても言い足りず、夢のようで、誰も彼もが途方に暮れています旨を申し上げてくださいませ。少しでも気分が落ち着きましたら、日頃、物思いなさっていた様子や、先夜、ほんとうに申し訳なくお思い申し上げていらした有様などを、お聞かせ申し上げましょう。この穢など、世間の人が忌む期間が過ぎてから、もう一度お立ち寄りくださいませ」 |
「とんだことになりまして、だれも想像のできませんようなふうでお |
"Ito asamasi. Obosi mo ahe nu sama ni te use tamahi ni tare ba, imizi to ihu ni mo aka zu, yume no yau nite, tare mo tare mo madohi haberu yosi wo mausa se tamahe. Sukosi mo kokoti nodome haberi te nam, higoro mo, mono obosi tari turu sama, hito-yo, ito kokoro-gurusi to omohi kikoye sase tamahe ri si arisama nado mo, kikoye sase haberu beki. Kono kegarahi nado, hito no imi haberu hodo sugusi te, ima hito-tabi tati-yori tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.9 | と言ひて、泣くこといといみじ。 |
と言って、泣く様子はまことに大変である。 |
と言って侍従ははげしく泣く。 |
to ihi te, naku koto ito imizi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 乳母、悲嘆に暮れる |
1-4 The wet nurse suffered grief at the loss of Ukifune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 内にも泣く声々のみして、 乳母なるべし、 |
内側でも泣く声ばかりがして、乳母であろう、 |
奥のほうにも泣き声が幾いろにも聞こえて、乳母らしく思われる声で、 |
Uti ni mo naku kowe-gowe nomi si te, Menoto naru besi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 「 あが君や、いづ方にかおはしましぬる。帰りたまへ。むなしき骸をだに見たてまつらぬが、かひなく悲しくもあるかな。明け暮れ見たてまつりても飽かず おぼえたまひ、いつしかかひある御さまを見たてまつらむと、朝夕に 頼みきこえつるにこそ、命も延びはべりつれ。うち捨てたまひて、かく行方も知らせたまはぬこと。 |
「わが姫君は、どこに行かれてしまったのか。お帰りください。むなしい亡骸をさえ拝見しないのが、効なく悲しいことよ。毎日拝見しても物足りなくお思い申し、早く立派なご様子を拝見しようと、朝夕にお頼み申し上げていたので、寿命も延びました。お見捨てになって、このように行く方もお知らせにならないこと。 |
「お姫様どこへいらっしゃいました。帰っておいでくださいませ。御 |
"Aga-Kimi ya, idu-kata ni ka ohasimasi nuru? Kaheri tamahe. Munasiki kara wo dani mi tatematura nu ga, kahinaku kanasiku mo aru kana! Ake-kure mi tatematuri te mo aka zu oboye tamahi, itusika kahi aru ohom-sama wo mi tatematura m to, asita yuhube ni tanomi kikoye turu ni koso, inoti mo nobi haberi ture. Uti-sute tamahi te, kaku yukuhe mo sira se tamaha nu koto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | 鬼神も、あが君をばえ領じたてまつらじ。人のいみじく惜しむ人をば、 帝釈も返したまふなり。あが君を取りたてまつりたらむ、人にまれ鬼にまれ、返したてまつれ。亡き御骸をも見たてまつらむ」 |
鬼神も、わが姫君をお取り申すことはできまい。皆がたいそう惜しむ人を、帝釈天もお返しになるという。姫君をお取り申し上げたのは、人であれ鬼であれ、お返し申し上げてください。御亡骸を拝見したい」 |
鬼神でもあなた様を取り込めてしまうことはできないはずです。人が非常に惜しむ人は |
Oni-Gami mo aga-Kimi wo ba e ryau-zi tatematura zi. Hito no imiziku wosimu hito wo ba, Taisyaku mo kahesi tamahu nari. Aga-Kimi wo tori tatematura m, hito ni mare oni ni mare, kahesi tatemature. Naki ohom-kara wo mo mi tatematura m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | と言ひ続くるが、心得ぬことども混じるを、あやしと思ひて、 |
と言い続けるが、合点の行かないことがあるのを、変だと思って、 |
こう叫んでいるうちに不審な点のあるのに気のついた時方は、 |
to ihi-tudukuru ga, kokoro-e nu koto-domo maziru wo, ayasi to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | 「 なほ、のたまへ。もし、人の隠しきこえたまへるか。たしかに 聞こし召さむと、御身の代はりに出だし立てさせたまへる 御使なり。今は、とてもかくてもかひなきことなれど、後にも 聞こし召し合はすることのはべらむに、違ふこと混じらば、参りたらむ御使の罪なるべし。 |
「やはり、おっしゃってください。もしや、誰かがお隠し申し上げなさったのか。確かな事をお聞きなさろうとして、ご自身の代わりに出立させなさったお使いです。今は、何にしても効のないことですが、後にお聞き合わせになることがございましょうが、違ったことがございましたら、聞いて参ったお使いの落度になるでしょう。 |
「真相を知らせてください。だれかがお隠しになったのですか。確かに知りたく思召して、御自身の代わりにおよこしになった私は使いです。今ははっきりしないままでも事は済むでしょうがあとでほんとうのことがお耳にはいった節、御報告が違っていたものでしたら使いの罪になります。 |
"Naho, notamahe. Mosi, hito no kakusi kikoye tamahe ru ka? Tasika ni kikosimesa m to, ohom-mi no kahari ni idasi-tate sase tamahe ru ohom-tukahi nari. Ima ha, tote-mo kakute-mo kahinaki koto nare do, noti ni mo kikosimesi aha suru koto no habera m ni, tagahu koto mazira ba, mawiri tara m ohom-tukahi no tumi naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | また、さりともと頼ませたまひて、『 君たちに対面せよ』と仰せられつる御心ばへも、かたじけなしとは思されずや。女の道に惑ひたまふことは、 人の朝廷にも、古き例どもありけれど、またかかること、この世にはあらじ、となむ見たてまつる」 |
また、そのようなことはあるまいとご信頼あそばして、『あなた方にお会いせよ』と仰せになったお気持ちを、もったいないとはお思いになりませんか。女の道に迷いなさることは、異国の朝廷にも、古い幾つもの例があったが、またこのようなことは、この世にない、と拝見しています」 |
まただれだれに逢えと、御好意を持つものと思召して御名ざしになったのに対しても相済まぬこととお思いになりませんか。一人の女性に傾倒される方は外国の歴史などにもありますが、宮様のあの方への御熱愛ほどのものはこの世にもう一つとはないと私は拝見しているのです」 |
Mata, saritomo to tanoma se tamahi te, 'Kimi-tati ni taimen se yo.' to ohose rare turu mi-kokoro-bahe mo, katazikenasi to ha obosa re zu ya? Womna no miti ni madohi tamahu koto ha, hito no mikado ni mo huruki tamesi-domo ari kere do, mata kakaru koto, konoyo ni ha ara zi, to nam mi tatematuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | と言ふに、「 げに、いとあはれなる御使にこそあれ。隠すとすとも、かくて 例ならぬことのさま、おのづから聞こえなむ」と思ひて、 |
と言うので、「おっしゃるとおり、まことに恐れ多いお使いだ。隠そうとしても、こうして珍しい事件の様子は、自然とお耳に入ろう」と思って、 |
と言った。道理なことで、この場合の宮の御感情はさもこそと恐察される、隠しても姫君の普通の死でない |
to ihu ni, "Geni, ito ahare naru ohom-tukahi ni koso are. Kakusu to su to mo, kakute rei nara nu koto no sama, onodukara kikoye na m." to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | 「 などか、いささかにても、人や隠いたてまつりたまふらむ、と思ひ寄るべきことあらむには、かくしもある限り惑ひはべらむ。日ごろ、いといみじくものを思し入るめりしかば、 かの殿の、わづらはしげに、ほのめかし聞こえたまふことなどもありき。 |
「どうして、少しでも、誰かがお隠し申し上げなさったのだろう、と思い寄るようなことがあったら、こんなにも皆が泣き騒ぐことがございましょうか。日頃、とてもひどく物を思いつめているようでしたので、あの殿が、厄介なことに、ちらっとおっしゃってくることなどもありました。 |
「だれかがお隠ししたかという疑いも起こることでしたなら、こんなふうに家じゅうの人が悲しみにおぼれることもないでしょう。お悲しみになってめいったふうになっていらっしゃいましたころに、殿様のほうから少しめんどうなふうの仰せがあったのです。 |
"Nado ka, isasaka ni te mo, hito ya kakui tatematuri tamahu ram, to omohi-yoru beki koto ara m ni ha, kaku si mo aru kagiri madohi habera m. Higoro, ito imiziku mono wo obosi-iru meri sika ba, kano Tono no, wadurahasige ni, honomekasi kikoye tamahu koto nado mo ari ki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | 御母にものしたまふ人も、かくののしる乳母なども、 初めより知りそめたりし方に渡りたまはむ、となむいそぎ立ちて、 この御ことをば、人知れぬさまにのみ、かたじけなくあはれと 思ひきこえさせたまへりしに、 御心乱れけるなるべし。 あさましう、心と身を亡くなしたまへるやうなれば、 かく心の惑ひに、ひがひがしく言ひ続けらるる なめり」 |
お母上でいらっしゃる方も、このように大騷ぎする乳母なども、初めから知り合った方のほうにお引っ越しなさろう、と準備し出して、宮とのご関係を、誰にも知られない状態にばかり、恐れ多くもったいないとお思い申し上げていらっしゃいましたので、お気持ちも乱れたのでしょう。驚き呆れますが、ご自分から身をお亡くしになったようなので、このように心の迷いに、愚痴っぽく言い続けてしまうのでしょう」 |
お母様である方も、あのわめいております乳母なども初めからの方へ迎えられておいでになりますことの用意に夢中でしたし、宮様のお志に感激しておいでになりました姫君の思召しはまた別でしたから、それでお |
Ohom-haha ni monosi tamahu hito mo, kaku nonosiru Menoto nado mo, hazime yori siri-some tari si kata ni watari tamaha m, to nam isogi-tati te, kono ohom-koto wo ba, hito-sire-nu sama ni nomi, katazikenaku ahare to omohi kikoyesase tamahe ri si ni, mi-kokoro midare keru naru besi. Asamasiu, kokoro to mi wo naku-nasi tamahe ru yau nare ba, kaku kokoro no madohi ni, higa-higasiku ihi-tuduke raruru na' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
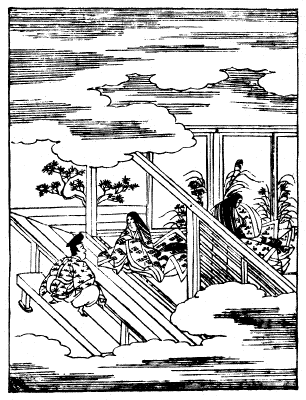 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | と、さすがに、まほならずほのめかす。心得がたくおぼえて、 |
と、そうはいっても、ありのままにではなく暗示する。合点が行かず思われて、 |
さすがに正面から言おうとはせずにほのめかしていることのあるのを内記も知った。 |
to, sauga ni, maho nara zu honomekasu. Kokoro-e gataku oboye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | 「 さらば、のどかに参らむ。立ちながらはべるも、いとことそぎたるやうなり。今、 御みづからもおはしましなむ」 |
「それでは、落ち着いてから参りましょう。立ちながら話しますのも、まことに簡略なようです。いずれ、宮ご自身でもお出でになりましょう」 |
「それではまたお静かになってから改めて伺いましょう。立ちながらの話にしてはあまりに失礼なことになります。そのうち宮様御自身でもおいでになることになりましょう」 |
"Saraba, nodoka ni mawira m. Tati-nagara haberu mo, ito koto-sogi taru yau nari. Ima, ohom-midukara mo ohasimasi na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.12 | と言へば、 |
と言うと、 |
to ihe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.13 | 「 あな、かたじけな。今さら、人の知りきこえさせむも、亡き御ためは、なかなかめでたき御宿世見ゆべきことなれど、忍びたまひしことなれば、また漏らさせたまはで、止ませたまはむなむ、御心ざしにはべるべき」 |
「まあ、恐れ多い。今さら、人がお知り申すのも、亡きお方のためには、かえって名誉なご運勢と見えることですが、お隠しになっていた事なので、またお漏らしあそばさないで、終わりなさることが、お気持ちに従うことでしょう」 |
「もったいない、それはいけません。今になりましていっさいの秘密の暴露してしまいますことは、お |
"Ana, katazikena! Ima-sara, hito no siri kikoye sase m mo, naki ohom-tame ha, naka-naka medetaki ohom-sukuse miyu beki koto nare do, sinobi tamahi si koto nare ba, mata mora sase tamaha de, yama se tamaha m nam, mi-kokorozasi ni haberu beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.14 | ここには、かく 世づかず亡せたまへるよしを、人に聞かせじと、よろづに紛らはすを、「自然にことどものけしきもこそ見ゆれ」と思へば、かくそそのかしやりつ。 |
こちらでは、このように異常な形でお亡くなりになった旨を、人に聞かせまいと、いろいろと紛らわしているが、「自然と事件の子細も分かってしまうのでは」と思うと、このように勧めて帰らせた。 |
などと侍従は言い、姫君の最後が普通の死でないことをほかへ |
Koko ni ha, kaku yo-duka zu use tamahe ru yosi wo, hito ni kika se zi to, yorodu ni magirahasu wo, "Zinen ni koto-domo no kesiki mo koso miyure." to omohe ba, kaku sosonokasi-yari tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 浮舟の母、宇治に到着 |
1-5 Ukifune's mother arrived at Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 雨のいみじかりつる紛れに、母君も渡りたまへり。さらに言はむ方もなく、 |
雨がひどく降ったのに隠れて、母君もお越しになった。まったく何とも言いようなく、 |
雨の降る最中に |
Ame no imizikari turu magire ni, Haha-Gimi mo watari tamahe ri. Sarani iham-kata mo naku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 「 目の前に亡くなしたらむ悲しさは、いみじうとも、世の常にて、たぐひあることなり。これは、いかにしつることぞ」 |
「目の前で亡くなった悲しさは、どんなに悲しくあっても、世の中の常で、いくらでもあることだ。これは、いったいどうしたことか」 |
遺骸があっての死は悲しいといっても無常の世にいては、どれほど愛していた人でもある時は甘んじて受けなければならぬのが人生の |
"Me no mahe ni naku-nasi tara m kanasisa ha, imiziu to mo, yo no tune nite, taguhi aru koto nari. Kore ha, ikani si turu koto zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | と惑ふ。かかることどもの紛れありて、いみじうもの思ひたまふらむとも知らねば、身を投げたまへらむとも思ひも寄らず、 |
とうろうろする。このような込み入った事件があって、ひどく物思いなさっていたとは知らないので、身を投げなさったとは思いも寄らず、 |
と悲しがった。苦しい恋の結末をそうしてつけたことなどは想像のできぬことで、身を投げたなどとは思い寄ることもできず、 |
to madohu. Kakaru koto-domo no magire ari te, imiziu mono omohi tamahu ram to mo sira ne ba, mi wo nage tamahe ra m to mo omohi-yora zu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 「 鬼や食ひつらむ。狐めくものや取りもて去ぬらむ。いと昔物語のあやしきもののことのたとひにか、さやうなることも言ふなりし」 |
「鬼が喰ったのか。狐のような魔物が連れさらったのか。まことに昔物語の妙な事件の例にか、そのような事も言っていた」 |
鬼が食ってしまったか、 |
"Oni ya kuhi tu ram? Kitune meku mono ya tori mote inu ram? Ito mukasi-monogatari no ayasiki mono no koto no tatohi ni ka, sayau naru koto mo ihu nari si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | と思ひ出づ。 |
と思い出す。 |
と夫人は思うのであった。 |
to omohi-idu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | 「 さては、 かの恐ろしと思ひきこゆるあたりに、心など悪しき御乳母やうの者や、 かう迎へたまふべしと聞きて、めざましがりて、 たばかりたる人もやあらむ」 |
「それとも、あの恐ろしいとお思い申し上げる方の所で、意地悪な乳母のような者が、このようにお迎えになる予定と聞いて、目障りに思って、誘拐を企んだ人でもあろうか」 |
また常に恐れている大将の正妻の宮の周囲に性質の悪い乳母というような者がいて、 |
"Sateha, kano osorosi to omohi kikoyuru atari ni, kokoro nado asiki ohom-menoto yau no mono ya, kau mukahe tamahu besi to kiki te, mezamasi-gari te, tabakari taru hito mo ya ara m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | と、下衆などを疑ひ、 |
と、下衆などを疑って、 |
と、召使いに疑いをかけて、 |
to, gesu nado wo utagahi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.8 | 「 今参りの、心知らぬやある」 |
「新参者で、気心の知れない者はいないか」 |
「近ごろ来た女房で気心の知れなかったのがいましたか」 |
"Ima-mawiri no, kokoro-sira nu ya aru?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.9 | と問へば、 |
と尋ねるが、 |
と問うた。 |
to tohe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10 | 「 いと世離れたりとて、ありならはぬ人は、ここにてはかなきこともえせず、 今とく参らむ、と言ひてなむ、皆、そのいそぐべきものどもなど取り具しつつ、 帰り出ではべりにし」 |
「とても世間離れした所だといって、住み馴れない新参者は、こちらではちょっとしたこともできず、又すぐに参上しましょう、と言っては、皆、その引っ越しの準備の物などを持っては、京に帰ってしまいました」 |
「そんなのはあまりにこちらが寂しいと申していやがりまして、 |
"Ito yo-banare tari tote, ari naraha nu hito ha, koko nite hakanaki koto mo e se zu, ima toku mawira m, to ihi te nam, mina, sono isogu beki mono-domo nado tori-gusi tutu, kaheri-ide haberi ni si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.11 | とて、もとよりある人だに、片へはなくて、いと人少ななる折になむありける。 |
と言って、元からいる女房でさえ、半分はいなくなって、まことに人数少ないときであった。 |
答えはこうであった。もとからいた女房も実家へ行っていたりして人数は少ない時だったのである。 |
tote, moto yori aru hito dani, katahe ha naku te, ito hito-zukuna naru wori ni nam ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 第六段 侍従ら浮舟の葬儀を営む |
1-6 Jiju and the others hold a funeral for Ukifune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1 | 侍従などこそ、日ごろの御けしき思ひ出で、「 身を失ひてばや」など、泣き入りたまひし折々のありさま、書き置きたまへる文をも見るに、「 亡き影に」と書きすさびたまへるものの、硯の下にありけるを見つけて、川の方を見やりつつ、響きののしる水の音を聞くにも、 疎ましく悲しと思ひつつ、 |
侍従などは、日頃のご様子を思い出して、「死んでしまいたい」などと、泣き入っていらした時々の様子、書き置きなさった手紙を見ると、「亡くなった後形に」と書き散らしていらっしゃったものが、硯の下にあったのを見つけて、川の方角を見やりながら、ごうごうと轟いて流れている川の音を聞くにつけても、気味悪く悲しいと思いながら、 |
侍従などはそれまでの姫君の煩悶を知っていて、死んでしまいたいと言って泣き入っていたことを思い、書いておいたものを読んで「なきかげに」という歌も |
Zizyuu nado koso, higoro no mi-kesiki omohi-ide, "Mi wo usinahi te baya!" nado, naki-iri tamahi si wori-wori no arisama, kaki-oki tamahe ru humi wo mo miru ni, "Naki kage ni." to kaki susabi tamahe ru mono no, suzuri no sita ni ari keru wo mi-tuke te, kaha no kata wo mi-yari tutu, hibiki nonosiru midu no oto wo kiku ni mo, utomasiku kanasi to omohi tutu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | 「 さて、亡せたまひけむ人を、とかく言ひ騷ぎて、いづくにもいづくにも、いかなる方になりたまひにけむ、と思し疑はむも、いとほしきこと」 |
「こうして、お亡くなりになった方を、あれこれと噂し合って、どなたもどなたも、どのようなふうにお亡くなりになったのか、とお疑いになるのも、お気の毒なこと」 |
ともかくも死んでおしまいになった人が、どこへだれに |
"Sate, use tamahi kem hito wo, tokaku ihi-sawagi te, iduku ni mo iduku ni mo, ika naru kata ni nari tamahi kem, to obosi utagaha m mo, itohosiki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | と 言ひ合はせて、 |
と相談し合って、 |
と右近と話し合い、 |
to ihi-sahase te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.4 | 「 忍びたる事とても、御心より起こりてありしことならず。親にて、亡き後に聞きたまへりとも、 いとやさしきほどならぬを、ありのままに 聞こえて、 かくいみじくおぼつかなきことどもをさへ、 かたがた思ひ惑ひたまふさまは、すこし明らめさせたてまつらむ。亡くなりたまへる人とても、 骸を置きてもて扱ふこそ、世の常なれ、世づかぬけしきにて日ごろも経ば、さらに隠れあらじ。なほ、 聞こえて、今は世の聞こえをだにつくろはむ」 |
「秘密の事とは言っても、ご自身から引き起こした事ではない。母親の身として、後に聞き合わせなさったとしても、別に恥ずかしい相手ではないのを、ありのままに申し上げて、このようにひどく気がかりなことまで加わって、あれこれ思い迷っていらっしゃる様子は、少しは合点の行くようにして上げよう。お亡くなりになった方としても、亡骸を安置し弔うのが、世間一般であるが、世間の例と変わった様子で幾日もたったら、まったく隠しおおせないだろう。やはり、申し上げて、今は世間の噂だけでも取り繕いましょう」 |
あの秘密の関係も自発的に招いた過失ではないのであるから、親である人に死後に知られても姫君として多く恥じるところもないのであると言い、ありのままに話して、五里霧中に迷っているような心境をだけでも救いたいと夫人を思い、また故人も遺骸を始末するのが世の常の営みなのであるから、そのまま空で悲しんでばかりいることをしていては日が重なるにしたがい秘密は早く世の中へ知られてしまうことでもある、その体裁も相談して作るほうがよい、 |
"Sinobi taru koto tote mo, mi-kokoro yori okori te ari si koto nara zu. Oya nite, naki noti ni kiki tamahe ri tomo, ito yasasiki hodo nara nu wo, ari no mama ni kikoye te, kaku imiziku obotukanaki koto-domo wo sahe, kata-gata omohi madohi tamahu sama ha, sukosi akirame sase tatematura m. Naku-nari tamahe ru hito tote mo, kara wo oki te mote-atukahu koso, yo no tune nare, yo-duka nu kesiki nite higoro mo he ba, sarani kakure ara zi. Naho, kikoye te, ima ha yo no kikoye wo dani tukuroha m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.5 | と語らひて、忍びてありしさまを聞こゆるに、言ふ人も消え入り、え言ひやらず、聞く心地も惑ひつつ、「 さは、このいと荒ましと思ふ川に、流れ亡せたまひにけり」と思ふに、いとど我も落ち入りぬべき心地して、 |
と相談し合って、こっそりと生前の状態を申し上げると、言う人も正気を失って、言葉も続かず、聞く気持ちも乱れて、「それでは、このとても荒々しい川に、身を投じて亡くなったのだ」と思うと、ますます自分も落ち込んでしまいそうな気がして、 |
どうしても真実を母夫人に知らす必要があるとして、ひそかに兵部卿の宮との関係、そののち大将に秘密を悟られて姫君が煩悶した話をするのであったが、語る人も魂が消えるようになり、聞く人もさらに予期せぬ悲哀の落ち重なってきたふためきをどうすることもできないふうであった。それではこの荒い川へ身を投げて死んだのかと思うと、母の夫人は自身もそこへはいってしまいたい気を覚えた。 |
to katarahi te, sinobi te ari-si sama wo kikoyuru ni, ihu hito mo kiye-iri, e ihi-yara zu, kiku kokoti mo madohi tutu, "Saha, kono ito aramasi to omohu kaha ni, nagare use tamahi ni keri." to omohu ni, itodo ware mo oti-iri nu beki kokoti si te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.6 | 「 おはしましにけむ方を尋ねて、骸をだにはかばかしくをさめむ」 |
「流れて行かれた方角を探して、せめて亡骸だけでもちゃんと葬儀したい」 |
流れて行ったほうを捜させて遺骸だけでも丁寧に納めたい |
"Ohasimasi ni kem kata wo tadune te, kara wo dani haka-bakasiku wosame m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.7 | とのたまへど、 |
とおっしゃるが、 |
と夫人は言いだしたが、 |
to notamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.8 | 「 さらに何のかひはべらじ。行方も知らぬ大海の原にこそおはしましにけめ。さるものから、人の言ひ伝へむことは、いと聞きにくし」 |
「全然何の効もありません。行く方も知れない大海原にいらっしゃったでしょう。それなのに、人が言い伝えることは、とても聞きにくい」 |
もう大海へ押し流されたに違いない、効果は収めることができずに人の噂だけが高くなることははばからなければならぬことを二人は忠告した。 |
"Sarani nani no kahi habera zi. Yukuhe mo sira nu oho-umi no hara ni koso ohasimasi ni keme. Saru mono kara, hito no ihi-tutahe m koto ha, ito kiki nikusi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.9 | と聞こゆれば、 とざまかくざまに思ふに、胸のせきのぼる心地して、いかにもいかにもすべき方もおぼえたまはぬを、 この人びと二人して、 車寄せさせて、御座ども、気近う使ひたまひし御調度ども、皆ながら脱ぎ置きたまへる御衾などやうのものを取り入れて、 乳母子の大徳、 それが叔父の阿闍梨、その弟子の睦ましきなど、もとより知りたる老法師など、 御忌に籠もるべき限りして、人の亡くなりたるけはひにまねびて、 出だし立つるを、乳母、母君は、 いといみじくゆゆしと臥しまろぶ。 |
と申し上げるので、あれやこれやと思うと、胸がこみ上げてくる気がして、どうにもこうにもなすすべもなく思われなさるが、この女房たち二人で、車を寄せさせて、ご座所や、身近にお使いになったご調度類など、みなそのままそっくり脱いで置かれた御衾などのようなものを詰めこんで、乳母子の大徳や、その叔父の阿闍梨、その弟子の親しい者など、昔から知っていた老法師など、御忌中に籠もる者だけで、人が亡くなった時の例にまねて、出立させたのを、乳母や、母君は、まことにひどく不吉だと倒れ転ぶ。 |
どうすればよいかと思うと胸がせき上がってくる気のする常陸夫人は、どうと定めることもできずに |
to kikoyure ba, to-zama kaku-zama ni omohu ni, mune no seki noboru kokoti si te, ikanimo-ikanimo su beki kata mo oboye tamaha nu wo, kono hito-bito hutari si te, kuruma yose sase te, o-masi-domo, ke-dikau tukahi tamahi si mi-teudo-domo, mina nagara nugi-oki tamahe ru ohom-husuma nado yau no mono wo tori-ire te, Menotogo no Daitoku, sore ga wodi no Azari, sono desi no mutumasiki nado, moto yori siri taru oyi-hohusi nado, ohom-imi ni komoru beki kagiri site, hito no naku-nari taru kehahi ni manebi te, idasi-taturu wo, Menoto, Haha-Gimi ha, ito imiziku yuyusi to husi-marobu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 第七段 侍従ら真相を隠す |
1-7 Jiju and the others suppress the truth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.1 | 大夫、内舎人など、脅しきこえし者どもも参りて、 |
大夫や、内舎人など、脅迫申し上げた者どもが参って、 |
宇治の五位、その |
Taihu, Udoneri nado, odosi kikoye si mono-domo mo mawiri te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.2 | 「 御葬送の事は、殿に事のよしも申させたまひて、日定められ、いかめしうこそ仕うまつらめ」 |
「ご葬送の事は、殿に事情を申し上げさせなさって、日程を決められて、厳かにお勤め申し上げるのがよいでしょう」 |
「お葬式のことは殿様と御相談なすってから、日どりもきめてりっぱになさるのがよろしいでしょう」 |
"Ohom-sausou no koto ha, Tono ni koto no yosi mo mausa se tamahi te, hi sadame rare, ikamesiu koso tukau-matura me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.3 | など言ひけれど、 |
などと言ったが、 |
などと言っていたが、 |
nado ihi kere do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.4 | 「 ことさら、今宵過ぐすまじ。いと忍びてと 思ふやうあればなむ」 |
「特別に、今夜のうちに行いたいのです。たいそうこっそりにと思っているところがありますので」 |
「どうしても今夜のうちにしたい |
"Kotosara, koyohi sugusu mazi. Ito sinobi te to omohu yau are ba nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.5 | とて、この車を、向かひの山の前なる原にやりて、人も近うも寄せず、この案内知りたる法師の限りして焼かす。いとはかなくて、煙は果てぬ。 田舎人どもは、なかなか、かかることをことことしくしなし、言忌みなど深くするものなりければ、 |
と言って、この車を、向かいの山の前の野原に行かせて、人も近くに寄せず、この事情を知っている法師たちだけで火葬させる。まことにあっけなくて、煙は消えた。田舎者どもは、かえって、このようなことを仰々しくして、言忌などを深くするものだったので、 |
と言い、その車を川向かいの山の前の原へやり、人も近くは寄せずに、真実のことを知らせてある僧たちだけを立ち合わせて焼いてしまった。火は長くも燃えていなかった。 |
tote, kono kuruma wo, mukahi no yama no mahe naru hara ni yari te, hito mo tikau mo yose zu, kono anai siri taru hohusi no kagiri site yaka su. Ito hakanaku te, keburi ha hate nu. Winaka-bito-domo ha, naka-naka, kakaru koto wo koto-kotosiku si-nasi, koto-imi nado hukaku suru mono nari kere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.6 | 「 いとあやしう。 例の作法など、あることども知らず、下衆下衆しく、あへなくてせられぬることかな」 |
「まことに変なこと。きまりの作法などが、あることもなさらずに、いかにも下衆のように、あっけなくなさったことよ」 |
大家の夫人の葬儀とも思われぬ貧弱な式であったと |
"Ito ayasiu. Rei no sahohu nado, aru koto-domo sira zu, gesu-gesusiku, ahe-naku te se rare nuru koto kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.7 | と 誹りければ、 |
と非難すると、 |
to sosiri kere ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.8 | 「 片へおはする人は、ことさらにかくなむ、京の人はしたまふ」 |
「兄弟などのいらっしゃる方は、わざとこのように、京の方はなさる」 |
また側室であった人の場合はこんなふうにして済まされるのが京の風俗であるなど |
"Katahe ohasuru hito ha, kotosara ni kaku nam, kyau no hito ha si tamahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.9 | などぞ、さまざまになむやすからず言ひける。 |
などと、いろいろと感心しないことを言うのであった。 |
と言ったり、いずれにもせようれしくない取り |
nado zo, sama-zama ni nam yasukara zu ihi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.10 | 「 かかる人どもの言ひ思ふことだに慎ましきを、まして、ものの聞こえ隠れなき世の中に、大将殿わたりに、骸もなく亡せたまひにけり、と聞かせたまはば、かならず思ほし疑ふこともあらむを、宮はた、 同じ御仲らひにて、さる人のおはしおはせず、しばしこそ忍ぶとも思さめ、つひには隠れあらじ。 |
「このような者どもが言ったり思ったりするだけでも憚れるのに、それ以上に、噂が漏れて広がる世の中では、大将殿あたりで、亡骸もなくお亡くなりになった、とお聞きになったら、きっとお疑いになることがあろうが、宮もまた、親しいお間柄であるから、そのような人がいらっしゃるかいらっしゃらないかは、しばらくの間は隠していると疑っても、いつかは明らかになるであろう。 |
そうした階級の人がどう思ったかということさえもつつましいこの場合に、大将が遺骸も残さず死んだと聞いては必ずどこかへ |
"Kakaru hito-domo no ihi omohu koto dani tutumasiki wo, masite, mono no kikoye kakure naki yononaka ni, Daisyau-dono watari ni, kara mo naku use tamahi ni keri, to kika se tamaha ba, kanarazu omohosi utagahu koto mo ara m wo, Miya hata, onazi ohom-nakarahi nite, saru hito no ohasi ohase zu, sibasi koso sinobu to mo obosa me, tuhini ha kakure ara zi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.11 | また、定めて宮をしも疑ひきこえたまはじ。いかなる人か率て隠しけむなどぞ、思し寄せむかし。生きたまひての御宿世は、 いと気高くおはせし人の、 げに亡き影に、いみじきことをや疑はれたまはむ」 |
また一方、きっと宮だけをお疑い申し上げることはなさらないだろう。どのような人が連れて行って隠したのだろうなどと、お考え寄りになるだろう。生きていらした間のご運勢は、とても高くいらした方が、なるほど亡くなって後は、たいへんな疑いをお受けになるのだろうか」 |
その時に宮がお隠しになったと大将は思うまい、どんな人が隠しているかと思い想像もされるに違いない、生きていた間は高い貴人たちに愛される運命を持った人が、死後に醜い疑いをかけられるのはもってのほかである |
Mata, sadame te Miya wo simo utagahi kikoye tamaha zi. Ika naru hito ka wi te kakusi kem nado zo, obosi yose m kasi. Iki tamahi te no ohom-sukuse ha, ito ke-dakaku ohase si hito no, geni naki kage ni, imiziki koto wo ya utagaha re tamaha m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.12 | と思へば、ここの内なる下人どもにも、今朝のあわたたしかりつる惑ひに、「 けしきも見聞きつるには口かため、案内知らぬには聞かせじ」などぞたばかりける。 |
と思うと、この家にいる下人どもにも、今朝の慌ただしかった騒動に、「その様子を見たり聞いたりした者には口止めをし、事情を知らない者には聞かせまい」などとごまかしたのであった。 |
と女房らは思い、山荘の中の下人たちにも |
to omohe ba, koko no uti naru simo-bito-domo ni mo, kesa no awatatasikari turu madohi ni, "Kesiki mo mi kiki turu ni ha kuti-katame, a'nai sira nu ni ha kikase zi." nado zo tabakari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.13 | 「 ながらへては、誰にも、静やかに、ありしさまをも聞こえてむ。ただ今は、 悲しさ覚めぬべきこと、ふと人伝てに聞こし召さむは、なほいといとほしかるべきことなるべし」 |
「年月が経ったら、どちらにも、静かに、生前のご様子を申し上げよう。ただ今は、悲しみも覚めるようなことを、ふと人伝てにお聞きなさると、やはりとてもお気の毒なことになるであろう」 |
時間がたったのちには浮舟の姫君が死を決意するまでの経過を宮へも大将へもお話しすることができようが、今は興ざめさせるような死に方を人の口から次へ次へと聞こえることは故人のために気の毒である |
"Nagarahe te ha, tare ni mo, siduyaka ni, arisi sama wo mo kikoye te m. Tada-ima ha, kanasisa same nu beki koto, huto hito-dute ni kikosimesa m ha, naho ito itohosikaru beki koto naru besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.14 | と、 この人二人ぞ、深く心の鬼添ひたれば、もて隠しける。 |
と、この人ら二人は、深く良心が咎めるので、隠すのであった。 |
と思い、この二人が自身らの責任を感じる心から深く隠すことに努めた。 |
to, kono hito hutari zo, hukaku kokoro-no-oni sohi tare ba, mote-kakusi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 5/6/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 5/6/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 5/6/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/13/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経