51 浮舟(明融臨模本) |
UKIHUNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十六歳十二月から二十七歳の春雨の降り続く三月頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from December at the age of 26 to rainy days in March at the age of 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第七章 浮舟の物語 浮舟、匂宮にも逢わず、母へ告別の和歌を詠み残す |
7 Tale of Ukifune Ukifune does not meet Niou-no-miya and leaves farewell waka to her mother |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | 第一段 内舎人、薫の伝言を右近に伝える |
7-1 Udoneri telles Kaoru's message to Ukon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1 | 殿よりは、かのありし返り事をだにのたまはで、日ごろ経ぬ。 この脅しし内舎人といふ者ぞ来たる。げに、いと荒々しく、ふつつかなるさましたる翁の、声かれ、さすがにけしきある、 |
殿からは、あの先日の返事をさえおっしゃらずに、幾日も過ぎた。この恐ろしがらせた内舎人という者が来た。なるほど、たいそう荒々しく不格好に太った様子をした老人で、声も嗄れ、何といっても凄そうなのが、 |
大将からはあの返した手紙に対して言ってくることもなくそのまま幾日かたった。右近が姫君をおどすために話した内舎人という者が山荘へ現われて来た。 |
Tono yori ha, kano ari si kaheri-goto wo dani notamaha de, higoro he nu. Kono odosi si Udoneri to ihu mono zo ki taru. Geni, ito ara-arasiku, hututuka naru sama si taru okina no, kowe kare, sasuga ni kesiki aru, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.2 | 「 女房に、ものとり申さむ」 |
「女房に、お話申し上げたい」 |
「もののわかる女房衆にお話がしたい」 |
"Nyoubau ni, mono tori-mausa m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.3 | と言はせたれば、右近しも会ひたり。 |
と言わせたので、右近が会った。 |
と取り次がせたために、右近が出て行った。 |
to iha se tare ba, Ukon simo ahi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.4 | 「 殿に召しはべりしかば、今朝参りはべりて、ただ今なむ、まかり帰りはんべりつる。雑事ども仰せられつるついでに、かくておはしますほどに、夜中、暁のことも、なにがしらかくて さぶらふ、と思ほして、宿直人 わざとさしたてまつらせたまふこともなきを、このころ 聞こしめせば、 |
「殿からお呼び出しがございましたので、今朝参上しまして、たった今、帰って参りました。雑事などをお命じになった折に、こうしてここにいらっしゃる間は、夜中、早朝の間も、わたくしどもがこうしてお勤め申している、とお思いになって、宿直人を特にお差し向け申し上げることもなかったが、最近お耳になさるには、 |
「殿様からお召しがありましたので、今朝から京へまいって今が帰りです。いろいろと御用を仰せつけられましたついでに、こうしてここに奥様をお置きになっていらっしゃって、夜中でも夜明けでも御用には私らが宇治にいるのであるからと思召して、京のお邸から宿直の侍などはおよこしにならなかったところが、このごろになって、 |
"Tono ni mesi haberi sika ba, kesa mawiri haberi te, tada-ima nam, makari kaheri hanberi turu. Zahuzi-domo ohose rare turu tuide ni, kaku te ohasimasu hodo ni, yonaka, akatuki no koto mo, nanigasira kaku te saburahu, to omohosi te, tonowi-bito waza to sasi-tatematura se tamahu koto mo naki wo, kono koro kikosimese ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.5 | 『 女房の御もとに、知らぬ所の人通ふやうになむ 聞こし召すことある。たいだいしきことなり。宿直にさぶらふ者どもは、その案内聞きたらむ。知らでは、いかがさぶらふべき』 |
『女房のもとに、素性の知れない者供が通っているようにお聞きになったことがある。不届きなことである。宿直に仕える者供は、その事情を聞いていよう。知らないでは、どうしていられよう』 |
こちらの女房衆の所へよその人が通って来る話を聞いた、不届きだ、宿直に行っている者は出入りの人の名を聞いたはずだ、知らないで門を通すはずはないではないか、 |
'Nyoubau no ohom-moto ni, sira nu tokoro no hito kayohu yau ni nam kikosimesu koto aru. Tai-daisiki koto nari. Tonowi ni saburahu mono-domo ha, sono a'nai kiki tara m. Sira de ha, ikaga saburahu beki.' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.6 | と問はせたまひつるに、承らぬことなれば、 |
とお尋ねあそばしたのが、全然知らないことなので、 |
何という人が来たのかとこうお尋ねになったのですが、私は何も承知しないことですから、 |
to toha se tamahi turu ni, uketamahara nu koto nare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.7 | 『 なにがしは身の病重くはべりて、宿直仕うまつることは、月ごろおこたりてはべれば、案内もえ知りはんべらず。さるべき男どもは、解怠なく催しさぶらはせはべるを、さのごとき非常のことのさぶらはむをば、いかでか承らぬやうははべらむ』 |
『わたくしは病気が重くございまして、宿直いたしますことは幾月も致しておりませんので、事情を知ることができません。しかるべき男どもは、怠けることなく警護させておりますのに、そのようなもってのほかのことがございますのを、どうして知らないでいられましょう』 |
私は重い病気をしておりまして、そんなことのありましたのも、来た人はだれかということも存じません。ただしお役にたつような男はかわるがわる差し上げてあるのですから、ただ今お話のようなとんでもない事件がありますれば私の耳にはいっていぬはずはございません |
'Nanigasi ha mi no yamahi omoku haberi te, tonowi tukau-maturu koto ha, tuki-goro okotari te habere ba, a'nai mo e siri hanbera zu. Saru beki wonoko-domo ha, ketai naku moyohosi saburahase haberu wo, sa no gotoki hizyau no koto no saburaha m wo ba, ikadeka uketamahara nu yau ha habera m.' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.8 | となむ 申させはべりつる。用意してさぶらへ。便なきこともあらば、重く勘当せしめたまふべきよしなむ、仰せ言はべりつれば、 いかなる仰せ言にかと、恐れ申しはんべる」 |
と申し上げさせました。気をつけてお仕えなさい。不都合なことがあったら、厳重に処罰なさる旨のご命令がございますので、どのようなお考えなのかと、恐ろしく存じております」 |
とお取り次ぎをもって申していただいて来ました。気をつけて別荘を守れ、悪いことが起これば重い罰を加えるからという仰せがあったので、どんな罰にあうのかと恐れていますよ」 |
to nam mausa se haberi turu. Youi si te saburahe, bin naki koto mo ara ba, omoku kandau-se sime tamahu beki yosi nam, ohose-goto haberi ture ba, ika naru ohose-goto ni ka to, osore mausi hanberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.9 | と言ふを聞くに、梟の鳴かむよりも、いともの恐ろし。いらへもやらで、 |
と言うのを聞くと、梟が鳴くのよりも、とても恐ろしい。返事もしないで、 |
これを聞いていて右近は、 |
to ihu wo kiku ni, hukurohu no naka m yori mo, ito mono osorosi. Irahe mo yara de, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.10 | 「 さりや。 聞こえさせしに違はぬことどもを聞こしめせ。 もののけしき御覧じたるなめり。御消息もはべらぬよ」 |
「そうか。申し上げたことに違わないことをお聞きあそばせ。事の真相をお察しになったようです。お手紙もございませんよ」 |
「とうとうこんなことになりました。私が申していたとおりのことをお聞きになることになりました。大将様はあの秘密を皆お知りになったのですよ。お手紙もあれからまいりませんね」 |
"Sari ya! Kikoye sase si ni tagaha nu koto-domo wo kikosimese. Mono no kesiki go-ran-zi taru na' meri. Ohom-seusoko mo habera nu yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.11 | と嘆く。乳母は、ほのうち聞きて、 |
と嘆く。乳母は、ちらっと聞いて、 |
などと姫君に言って歎息をした。乳母は内舎人の話を少し聞いていて、 |
to nageku. Menoto ha, hono-uti-kiki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.12 | 「 いとうれしく仰せられたり。盗人多かんなるわたりに、宿直人も初めのやうにもあらず。皆、身の代はりぞと言ひつつ、あやしき下衆をのみ参らすれば、夜行をだにえせぬに」と喜ぶ。 |
「とても嬉しいことをおっしゃった。盗賊が多いという所で、宿直人も最初のころのようではありません。みな、代理だと言っては、変な下衆ばかりを差し向けていたので、夜回りさえできなかったが」と喜ぶ。 |
「よく御注意をしてくださいましたわね。 |
"Ito uresiku ohose rare tari. Nusu-bito ohokan naru watari ni, tonowi-bito mo hazime no yau ni mo ara zu. Mina, mi no kahari zo to ihi tutu, ayasiki gesu wo nomi mawira sure ba, yagyau wo dani e se nu ni." to yorokobu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 第二段 浮舟、死を決意して、文を処分す |
7-2 Ukifune determines to kill herself and disposes of their letters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.1 | 君は、「 げに、ただ今いと悪しくなりぬべき身なめり」と思すに、宮よりは、 |
女君は、「なるほど、今はまことに悪くなってしまった身の上のようだ」とお思いになっているところに、宮からは、 |
浮舟はこうして寂しい運命のきわまっていくことを感じている時、宮から決心ができたはずであるとお言いになり、 |
Kimi ha, "Geni, tada-ima ito asiku nari nu beki mi na' meri." to obosu ni, Miya yori ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.2 | 「いかに、いかに」 |
「いかがですか、いかがですか」 |
"Ikani, ikani?" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.3 | と、 苔の乱るるわりなさを ★のたまふ、いとわづらはしくてなむ。 |
と、苔が乱れるような無理なことをおっしゃるのが、とても厄介である。 |
「君に逢はんその日はいつぞ松の木の |
to, koke no midaruru wari-nasa wo notamahu, ito wadurahasiku te nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.4 | 「 とてもかくても、一方一方につけて、いとうたてあることは出で来なむ。わが身一つの亡くなりなむのみこそめやすからめ。 昔は、懸想する人のありさまの、いづれとなきに思ひわづらひてだにこそ、身を投ぐるためしもありけれ。ながらへば、かならず憂きこと見えぬべき身の、亡くならむは、なにか惜しかるべき。親もしばしこそ嘆き惑ひたまはめ、あまたの子ども扱ひに、おのづから 忘草摘みてむ ★。ありながらもてそこなひ、 人笑へなるさまにてさすらへむは、まさるもの思ひなるべし」 |
「どちらにしても、それぞれの方につけて、とても嫌なことが出て来よう。自分一人がいなくなるのが最もよいようだ。昔は、懸想する男の気持ちが、どちらとも決められないのに思いわずらって、それだけで身を投げた例もあった。生き永らえたら、きっと嫌な目に遭ってしまいそうな身で、死ぬのに、どうして惜しい身であろう。親も少しの間は嘆きなさろうが、大勢の子供の世話で、自然と忘れよう。生きながら間違いを犯し、物笑いな様子でうろうろしては、それ以上の物思いになろう」 |
どちらへ行っても残る一人に |
"Totemo-kakutemo, hito-kata hito-kata ni tuke te, ito utate aru koto ha ide-ki na m. Waga mi hitotu no naku nari na m nomi koso meyasukara me. Mukasi ha, kesau suru hito no arisama no, idure to naki ni omohi wadurahi te dani koso, mi wo naguru tamesi mo ari kere. Nagarahe ba, kanarazu uki koto miye nu beki mi no, naku nara m ha, nani ka wosikaru beki. Oya mo sibasi koso nageki madohi tamaha me, amata no kodomo atukahi ni, onodukara wasure-gusa tumi te m. Ari nagra motesokonahi, hito-warahe naru sama ni te saurahe m ha, masaru mono-omohi naru besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.5 | など思ひなる。児めきおほどかに、たをたをと見ゆれど、気高う世のありさまをも知る方すくなくて、思し立てたる 人にしあれば、すこし おずかるべきことを、思ひ寄るなりけむかし。 |
などと思うようになる。子供っぽくおっとりとして、たおやかに見えるが、気品高く貴族社会の様子を知ることも少なくて育った人なので、少し乱暴なことを、考えついたのであろう。 |
子供らしくおおようで、なよなよと柔らかな姫君と見えるが、人生の意義というものを悟るだけの学識も与えられずに成長した人であるから自殺というような思いきったこともする気になったらしい。 |
nado omohi naru. Ko-meki ohodoka ni, tawo-tawo to miyure do, kedakau yo no arisama wo mo siru kata sukunaku te, obosi-tate taru hito ni si are ba, sukosi ozukaru beki koto wo, omohi-yoru nari kem kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.6 | むつかしき反故など破りて、おどろおどろしく一度にもしたためず、灯台の火に焼き、水に投げ入れさせなど、やうやう失ふ。心知らぬ御達は、「 ものへ渡りたまふべければ、つれづれなる月日を経て、はかなくし集めたまへる手習などを、破りたまふなめり」と思ふ。侍従などぞ、見つくる時は、 |
厄介な反故などを破って、大げさになるような一度には始末せず、灯台の火で焼いたり、川に投げ入れさせたりなど、だんだん少なくして行く。事情を知らない御達は、「京へお引っ越しになるので、退屈な日々を送るうちに、いつしか書き集めなさった手習などを、お破り捨てになるのだろう」と思う。侍従などは、見つけた時には、 |
あとで人の迷惑になりそうな |
Mutukasiki hogu nado yari te, odoro-odorosiku hito-tabi ni mo sitatame zu, toudai no hi ni yaki, midu ni nage-ire sase nado, yau-yau usinahu. Kokoro-sira nu go-tati ha, "Mono he watari tamahu bekere ba, ture-dure naru tuki-hi wo he te, hakanaku si atume tamahe ru tenarahi nado wo, yari tamahu na' meri." to omohu. Zizyuu nado, mi-tukuru toki ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.7 | 「 など、かくはせさせたまふ。あはれなる御仲に、心とどめて書き交はしたまへる文は、 人にこそ見せさせたまはざらめ、ものの底に置かせたまひて御覧ずるなむ、ほどほどにつけては、いとあはれにはべる。さばかりめでたき御紙使ひ、かたじけなき御言の葉を尽くさせたまへるを、かくのみ破らせたまふ、情けなきこと」 |
「どうして、このようなことをあそばします。愛し合っていらっしゃるお間柄で、心をこめてお書き交わしなさった手紙は、他人にはお見せあそばさなくても、何かの箱底におしまいあそばして御覧になるのが、身分相応に、とても感慨深いものでございます。あれほど立派な紙を使い、恐れ多いお言葉のあらん限りをお尽くしになったのを、あのようにばかりお破りあそばすのは、情けないこと」 |
「なぜそんなことをなさいますか。思い合った中でお取りかわしになったお手紙は、人にはお見せになるものではありませんでも、箱の底へでもしまってお置きになりまして、時々出して御覧になりますのが、どの女性にも共通した楽しいことになっておりますよ。この上もないお紙をお使いになりまして、美しい御文章でおしたためになったものを、そんなに皆お破りになりますのは情けないことではございませんか」 |
"Nado, kaku ha se sase tamahu? Ahare naru ohom-naka ni, kokoro todome te kaki-kahasi tamahe ru humi ha, hito ni koso mise sase tamaha zara me, mono no soko ni oka se tamahi te go-ran-zuru nam, hodo-hodo ni tuke te ha, ito ahare ni haberu. Sabakari medetaki ohom-kami tukahi, katazikenaki ohom-kotonoha wo tukusa se tamahe ru wo, kaku nomi yara se tamahu, nasake naki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.8 | と言ふ。 |
と言う。 |
こんなふうに言ってとめる。 |
to ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.9 | 「 何か。むつかしく。長かるまじき身にこそあめれ。落ちとどまりて、人の御ためもいとほしからむ。さかしらにこれを取りおきけるよなど、漏り聞きたまはむこそ、恥づかしけれ」 |
「いいえどうして。厄介な。長生きできそうにない身の上のようです。落ちぶれ残って、相手の方にとってもお気の毒でしょう。利口ぶってお手紙を残しておいたものよなどと、漏れ聞きなされたら、恥ずかしい」 |
「いいのよ。私にはもう長い命はないようだからね。あとへ残ってはお書きになった方の迷惑にもなって気の毒よ。悪い趣味だ、愛人の手紙などをしまっておくなどとまたお思いになる方があっても恥ずかしいしね」 |
"Nani ka? Mutukasiku. Nagakaru maziki mi ni koso a' mere. Oti-todomari te, hito no ohom-tame mo itohosikara m. Sakasira ni kore wo tori-oki keru yo nado, mori-kiki tamaha m koso, hadukasikere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.10 | などのたまふ。心細きことを思ひもてゆくには、またえ思ひ立つまじきわざなりけり。 親をおきて亡くなる人は、いと罪深かなるものをなど、 さすがに、ほの聞きたることをも思ふ。 |
などとおしゃる。心細いことを思い続けていくと、再び決心ができなくなるのであった。親を残して先立つ人は、とても罪障深いと言うものをなどと、やはり、かすかに聞いたことを思う。 |
などと浮舟は言うのであった。死というものの心細い本質を思ってはまだ自殺の決行はできないらしいのももっともである。親よりも先に死んで行く人は罪が深くなるそうであるがなどとさすがに仏教の教理も聞いていて思いもするのである。 |
nado notamahu. Kokoro-bosoki koto wo omohi mote-yuku ni ha, mata e omohi-tatu maziki waza nari keri. Oya wo oki te naku naru hito ha, ito tumi hukaka' naru mono wo nado, sasuga ni, hono-kiki taru koto wo mo omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 第三段 三月二十日過ぎ、浮舟、匂宮を思い泣く |
7-3 Ukifune sobs as recalling Niou-no-miya at March 20 past |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.1 | 二十日あまりにもなりぬ。かの家主、二十八日に下るべし。宮は、 |
二十日過ぎにもなった。あの家の主人が、二十八日に下向する予定である。宮は、 |
二十日過ぎにもなった。宮が交渉しておありになった家の住み主が二十八日に家をあけて立つことになっていて、 |
Hatu-ka amari ni mo nari nu. Kano ihe-aruzi, nizihu-hati-niti ni kudaru besi. Miya ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.2 | 「 その夜かならず迎へむ。下人などに、よくけしき見ゆまじき心づかひしたまへ。こなたざまよりは、ゆめにも聞こえあるまじ。疑ひたまふな」 |
「その夜にきっと迎えよう。下人などに、様子を気づかれないように注意なさい。こちらの方からは、絶対漏れることはない。疑いなさるな」 |
その二十八日の夜に必ず迎えに行きます。下人などに出かけるのを悟らせぬように気をおつけなさい。自分のほうから秘密のもれるようなことは絶対にありません。疑いを持たずにいてください。 |
"Sono yo kanarazu mukahe m. Simo-bito nado ni, yoku kesiki miyu maziki kokoro-dukahi si tamahe. Konata-zama yori ha, yume ni mo kikoye aru mazi. Utagahi tamahu na." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.3 | などのたまふ。「 さて、あるまじきさまにておはしたらむに、今一度ものをもえ聞こえず、おぼつかなくて返したてまつらむことよ。また、時の間にても、いかでかここには寄せたてまつらむとする。かひなく怨みて帰りたまはむ」さまなどを思ひやるに、例の、面影離れず、堪えず悲しくて、この御文を顔におし当てて、しばしはつつめども、いといみじく泣きたまふ。 |
などとおっしゃる。「そうして、無理をしておいでになったとしても、もう一度何も申し上げることができず、お目にかかれぬままお帰し申し上げることよ。また、束の間でも、どうしてここにお近づけ申し上げることができよう。効なく恨んでお帰りになろう」その様子を想像すると、いつものように、面影が離れず、始終悲しくて、このお手紙を顔に押し当てて、しばらくの間は我慢していたが、とてもひどくお泣きになる。 |
というようなお手紙が来た。そうした無理な工作をしておいでになっても、もう一度お話をすることすら不可能でそのままお帰しすることになるのは悲しい。またどんな短時間でもこの家へお入れすることはできるものでないと思う |
nado notamahu. "Sate, arumaziki sama nite ohasi tara m ni, ima hito-tabi mono wo mo e kikoye zu, obotukanaku te kahesi tatematura m koto yo. Mata, toki no ma nite mo, ikadeka koko ni ha yose tatematura m to suru. Kahinaku urami te kaheri tamaha m." sama nado wo omohi-yaru ni, rei no, omokage hanare zu, tahe zu kanasiku te, kono ohom-humi wo kaho ni osi-ate te, sibasi ha tutume domo, ito imiziku naki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.4 | 右近、 |
右近は、 |
右近が、 |
Ukon, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.5 | 「 あが君、かかる御けしき、つひに人見たてまつりつべし。やうやう、あやしなど思ふ人はべるべかめり。かうかかづらひ思ほさで、さるべきさまに聞こえさせたまひてよ。右近はべらば、おほけなきこともたばかり出だしはべらば、かばかり小さき御身一つは、空より率てたてまつらせたまひなむ」 |
「姫君様、このようなご様子に、終いには周囲の人もお気づき申そう。だんだんと、変だなどと思う女房がございますようです。このようにくよくよなさらずに、適当にご返事申し上げなさいませ。右近がおります限りは、大それたこともうまく処理いたしましたら、これほどお小さい身体一つぐらいは、空からお連れ申し上げなさいましょう」 |
「お姫様はこんなふうにしていらっしゃいますと人が皆悟ってしまいます。近ごろは不審を起こしかけた人たちもあるようでございます。こんなに一つのことを断ち切れない御心配になさいませんで、宮様へは御同意なさいましたことを書いておあげなさいましよ。私がおります以上、どんな大それたことでございましても取り繕いまして、こんなお小さいお |
"Aga Kimi, kakaru mi-kesiki, tuhi ni hito mi tatematuri tu besi. Yau-yau, ayasi nado omohu hito haberu beka' meri. Kau kakadurahi omohosa de, saru-beki sama ni kikoye sase tamahi te yo. Ukon habera ba, ohokenaki koto mo tabakari idasi habera ba, kabakari tihisaki ohom-mi hitotu ha, sora yori wi te tatematura se tamahi na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.6 | と言ふ。とばかりためらひて、 |
と言う。しばし躊躇して、 |
と言うのを聞いて、 |
to ihu. Tobakari tamerahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.7 | 「 かくのみ言ふこそ、いと心憂けれ。 さもありぬべきこと、と思ひかけば こそあらめ、あるまじきこと、と皆思ひとるに、わりなく、かくのみ 頼みたるやうにのたまへば、いかなることをし出でたまはむとするにかなど、思ふにつけて、身のいと心憂きなり」 |
「このようにばかり言うのが、とても情けない。たしかにそうなってもよいこと、と思っているならともかくも、とんでもないことだ、とすっかり分かっているのに、無理に、このようにばかり期待しているようにおっしゃるので、どのようなことをし出かしなさろうとするのかなどと、思うにつけても、身がとてもつらいのです」 |
「そんなふうに私の心を解釈されるのが苦しい。そうしたいと私が望んでいるのならそれでいいけれど、してはならないことだと、どんなことも皆私は否定しているのに、このお手紙のように信じていらっしゃるのかと思うと、あの方はこれからのちにまたどんなことをあそばすだろうと不安でならなくて、私は今運命を悲しんでいるのよ」 |
"Kaku nomi ihu koso, ito kokoro-ukere. Samo ari nu beki koto, to omohi-kake ba koso ara me, arumaziki koto, to mina omohi-toru ni, warinaku, kaku nomi tanomi taru yau ni notamahe ba, ika naru koto wo si-ide tamaha m to suru ni ka nado, omohu ni tuke te, mi no ito kokoro-uki nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.8 | とて、返り事も聞こえたまはずなりぬ。 |
と言って、お返事も差し上げないでしまわれた。 |
と浮舟は言い、お返事は書かなかった。 |
tote, kaheri-goto mo kikoye tamaha zu nari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | 第四段 匂宮、宇治へ行く |
7-4 Niou-no-miya goes to Uji to meet Ukifune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.1 | 宮、「 かくのみ、なほ受け引くけしきもなくて、返り事さへ絶え絶えになるは、 かの人の、あるべきさまに言ひしたためて、すこし心やすかるべき方に思ひ定まりぬるなめり。ことわり」と 思すものから、いと口惜しくねたく、 |
宮は、「こうしてばかり、依然として承知する様子もなくて、返事までが途絶えがちになるのは、あの人が、適当に言い含めて、少し安心な方に心が落ち着いたのだろう。もっともなことだ」とはお思いになるが、たいそう残念で悔しく、 |
|
Miya, "Kaku nomi, naho uke-hiku kesiki mo naku te, kahesi-goto sahe taye-daye ni naru ha, kano hito no, aru beki sama ni ihi sitatame te, sukosi kokoro-yasukaru beki kata ni omohi sadamari nuru na' meri. Kotowari." to obosu mono kara, ito kutiwosiku netaku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.2 | 「 さりとも、我をばあはれと思ひたりしものを。あひ見ぬとだえに、人びとの言ひ知らする方に寄るならむかし」 |
「それにしても、わたしを慕っていたものを。逢わない間に、女房が説き聞かせた方に傾いたのであろう」 |
今の態度はこうであっても、確かに自分をあの人は愛していたのだ、逢わないうちに周囲の者からよけいな忠告をされて、そのほうへ心が傾いたのであろう |
"Saritomo, ware wo ba ahare to omohi tari si mono wo. Ahi-mi nu todaye ni, hito-bito no ihi sira suru kata ni yoru nara m kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.3 | など眺めたまふに、 行く方しらず、 むなしき空に満ちぬる心地したまへば、例の、いみじく思し立ちておはしましぬ。 |
などと物思いなさると、恋しさは晴らしようもなく、むなしい空にいっぱい満ちあふれた気がなさるので、いつものように、大変なご決意でおいでになった。 |
と物思いをしておいでになると、「わが恋はむなしき空に満ちぬらし思ひやれども行き方のなき」というふうにもなっていくため、例の無理をあそばして宇治へおいでになった。 |
nado nagame tamahu ni, yuku-kata sira zu, munasiki sora ni miti nuru kokoti si tamahe ba, rei no, imiziku obosi-tati te ohasi masi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.4 | 葦垣の方を見るに、例ならず、 |
葦垣の方を見ると、いつもと違って、 |
|
Asigaki no kata wo miru ni, rei nara zu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.5 | 「 あれは、誰そ」 |
「あれは、誰だ」 |
「そこへ来るのはだれだ」 |
"Are ha, taso?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.6 | と言ふ声々、いざとげなり。立ち退きて、心知りの男を入れたれば、それをさへ問ふ。前々のけはひにも似ず。わづらはしくて、 |
と言う声々が、目ざとげである。いったん退いて、事情を知っている男を入れたが、その男までを尋問する。以前の様子と違っている。やっかいになって、 |
と緊張した声でとがめる者が幾人もあった。そこからやや遠ざかっておいでになり、行きなれた侍だけをおやりになったが、それをさえ |
to ihu kowe-gowe, izatoge nari. Tati-noki te, kokoro-siri no wonoko wo ire tare ba, sore wo sahe tohu. Saki-zaki no kehahi ni mo ni zu. Wadurahasiku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.7 | 「 京よりとみの御文あるなり」 |
「京から急のお手紙です」 |
「京から急用のお手紙を持って来たのです」 |
"Kyau yori tomi no ohom-humi aru nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.8 | と言ふ。右近は徒者の名を呼びて会ひたり。いとわづらはしく、いとどおぼゆ。 |
と言う。右近は従者の名を呼んで会った。とても煩わしく、ますますやっかいに思う。 |
と侍は言った。右近の使っている侍の名を言って呼んでもらった。右近はこの上にもまた難儀なことが起こってくると思った。 |
to ihu. Ukon ha zyusya no na wo yobi te ahi tari. Ito wadurahasiku, itodo oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.9 | 「 さらに、今宵は不用なり。いみじくかたじけなきこと」 |
「全然、今夜はだめです。まことに恐れ多いことで」 |
「どうしても今夜はだめでございます。非常に恐縮しておりますが」 |
"Sarani, koyohi ha huyou nari. Imiziku katazikenaki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.10 | と言はせたり。宮、「 など、かくもて離るらむ」と思すに、わりなくて、 |
と言わせた。宮は、「どうして、こんなによそよそしくするのだろう」とお思いになると、たまらなくなって、 |
と宮へ申し上げさせた。宮はどうしてこんな冷淡な取り扱いをするのであろうと、途方にくれたように思召して、 |
to iha se tari. Miya, "Nado, kaku mote hanaru ram?" to obosu ni, warinaku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.11 | 「 まづ、時方入りて、侍従に会ひて、さるべきさまにたばかれ」 |
「まず、時方が入って、侍従に会って、しかるべくはからえ」 |
「ともかくも |
"Madu, Tokikata iri te, Zizyuu ni ahi te, saru-beki sama ni tabakare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.12 | とて遣はす。かどかどしき人にて、とかく言ひ構へて、訪ねて会ひたり。 |
と言って遣わす。才覚ある人で、あれこれ言い繕って、探し出して会った。 |
とお言いになり、内記をまたおやりになった。時方は才子であったから上手に宇治侍を |
to tukahasu. Kado-kadosiki hito nite, tokaku ihi kamahe te, tadune te ahi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.13 | 「 いかなるにかあらむ。かの殿ののたまはすることありとて、宿直にある者どもの、さかしがりだちたるころにて、いとわりなきなり。御前にも、ものをのみいみじく思しためるは、かかる御ことのかたじけなきを、思し乱るるにこそ、と心苦しくなむ見たてまつる。 さらに、今宵は。人けしき見はべりなば、なかなかにいと悪しかりなむ。やがて、 さも御心づかひせさせたまひつべからむ夜、 ここにも人知れず思ひ構へてなむ、聞こえさすべかめる」 |
「どうしたわけでありましょう。あの殿がおっしゃることがあると言って、宿直にいる者どもが、出しゃばっているところで、まことに困っているのです。御前におかれても、深く思い嘆いていらっしゃるらしいのは、このようなご訪問のもったいなさを、悩んでいらっしゃるのだ、とお気の毒に拝しております。全然、今晩はだめです。誰かが様子に気づきましたら、かえってまことに悪いことになりましょう。そのまま、そのようにお考えあそばしている夜には、こちらでも誰にも知られず計画しまして、ご案内申し上げましょう」 |
「どうしたのでしょうか、大将様から仰せがあったのだと言いまして、 |
"Ika naru ni ka ara m? Kano Tono no notamahasuru koto ari tote, tonowi ni aru mono-domo no, sakasi-gari-dati taru koro nite, ito warinaki nari. O-mahe ni mo, mono wo nomi imiziku obosi ta' meru ha, kakaru ohom-koto no katazikenaki wo, obosi midaruru ni koso, to kokoro-gurusiku nam mi tatematuru. Sarani, koyohi ha. Hito kesiki mi haberi na ba, naka-naka ni ito asikari na m. Yagate, samo mi-kokoro-dukahi se sase tamahi tu bekara m yo, koko ni mo hito-sire-zu omohi kamahe te nam, kikoye sasu beka' meru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.14 | 乳母のいざときことなども語る。大夫、 |
乳母が目ざといことなども話す。大夫、 |
と侍従は言い、 |
Menoto no izatoki koto nado mo kataru. Taihu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.15 | 「 おはします道のおぼろけならず、あながちなる御けしきに、あへなく聞こえさせむなむ、たいだいしき。さらば、 いざ、たまへ。ともに詳しく聞こえさせたまへ」といざなふ。 |
「おいでになった道中が大変なことで、ぜひにもというお気持ちなので、はりあいもなくお返事申し上げるのは、具合が悪い。それでは、さあ、いらっしゃい。一緒に詳しく申し上げましょう」と誘う。 |
「並みたいていの道をおいでになったのではありませんからね、よくよくお逢いになりたい御様子なんですから、失望をおさせいたすようなお返辞はもったいなくて私からできません。それではあなたがそこまで来てくだすって、私も言葉を添えますが、あなたからお断わりを申し上げるようにしてください」と言って、誘い出そうとした。 |
"Ohasimasu miti no oboroke nara zu, anagati naru mi-kesiki ni, ahe-naku kikoye sase m nam, tai-daisiki. Saraba, iza, tamahe. Tomoni kuhasiku kikoye sase tamahe." to izanahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.16 | 「 いとわりなからむ」 |
「とても無理です」 |
それは無理である、 |
"Ito warinakara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.17 | と言ひしろふほどに、夜もいたく更けゆく。 |
と言い合いをしているうちに、夜もたいそう更けて行く。 |
ぜひそうしてと言い合っているうちにも夜もずっとふけてきた。 |
to ihi-sirohu hodo ni, yo mo itaku huke yuku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 第五段 匂宮、浮舟に逢えず帰京す |
7-5 Niou-no-miya tried in vain to meet Ukifune and came back to Kyoto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.1 | 宮は、御馬にてすこし遠く立ちたまへるに、里びたる声したる 犬どもの出で来てののしるも、いと恐ろしく、 人少なに、いとあやしき御ありきなれば、「 すずろならむものの走り出で来たらむも、いかさまに」と、さぶらふ限り心をぞ惑はしける。 |
宮は、御馬で少し遠くに立っていらっしゃったが、里めいた声をした犬どもが出て来て吠え立てるのも、たいそう恐ろしく、供回りが少ないうえに、たいそう簡略なお忍び歩きなので、「おかしな者どもが襲いかかって来たら、どうしよう」と、お供申している者たちはみな心配していたのであった。 |
馬上の宮は少し遠くへ立っておいでになるのであったが、 |
Miya ha, ohom-muma nite sukosi tohoku tati tamahe ru ni, satobi taru kowe si taru inu-domo no ide-ki te nonosiru mo, ito osorosiku, hito-zukuna ni, ito ayasiki ohom-ariki nare ba, "Suzuro nara m mono no hasiri ide-ki tara m mo, ika-sama ni?" to, saburahu kagiri kokoro wo zo madohasi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
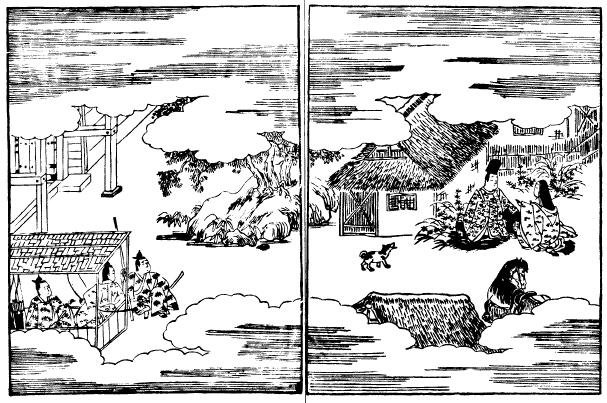 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.2 | 「 なほ、とくとく参りなむ」 |
「もっと、早く早く参ろう」 |
「どうしても来てくださることですよ。早く、早く」 |
"Naho, toku-toku mawiri na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.3 | と言ひ騒がして、この侍従を率て参る。髪脇より 掻い越して、様体いとをかしき人なり。馬に乗せむとすれど、さらに聞かねば、 衣の裾をとりて、立ち添ひて行く。 わが沓を履かせて、みづからは、供なる人のあやしき物を履きたり。 |
とうるさく言って、この侍従を連れて上がる。髪は、脇の下から前に出して、姿がとても美しい人である。馬に乗せようとしたが、どうしても聞かないので、衣の裾を持って、歩いて付いて来る。自分の沓を履かせて、自分は供人の粗末なのを履いた。 |
とせきたてて時方は侍従をつれて来るのであった。髪を右の |
to ihi sawagasi te, kono Zizyuu wo wi te mawiru. Kami waki yori kai-kosi te, yaudai ito wokasiki hito nari. Muma ni nose m to sure do, sarani kika ne ba, kinu no suso wo tori te, tati sohi te yuku. Waga kutu wo haka se te, midukara ha, tomo naru hito no ayasiki mono wo haki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.4 | 参りて、「かくなむ」と聞こゆれば、 語らひたまふべきやうだになければ、山賤の垣根のおどろ葎の蔭に、障泥といふものを敷きて 降ろしたてまつる。わが御心地にも、「 あやしきありさまかな。かかる道にそこなはれて、はかばかしくは、えあるまじき身なめり」と、思し続くるに、 泣きたまふこと限りなし。 |
参上して、「これこれです」と申し上げると、相談しようにも適当な場所がないので、山家の垣根の茂った葎のもとに、障泥という物を敷いて、お下ろし申し上げる。ご自身のお気持ちにも、「変な恰好だな。このような道につまずいて、これといった、将来とても期待できそうにない身の上のようだ」と、お思い続けると、お泣きになることこの上ない。 |
自身の |
Mawiri te, "Kaku nam." to kikoyure ba, katarahi tamahu beki yau dani nakere ba, yamagatu no kakine no odoro mugura no kage ni, ahuri to ihu mono wo siki te orosi tatematuru. Waga mi-kokoti ni mo, "Ayasiki arisama kana! Kakaru miti ni sokonaha re te, haka-bakasiku ha, e aru maziki mi na' meri." to, obosi tudukuru ni, naki tamahu koto kagiri nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.5 | 心弱き人は、ましていといみじく悲しと見たてまつる。 いみじき仇を鬼につくりたりとも、おろかに見捨つまじき人の御ありさまなり。 ためらひたまひて、 |
気弱な女は、それ以上にほんとうに悲しいと拝見する。大変な敵を鬼にしたとしても、いいかげんには見捨てることのできないご様子の人である。躊躇なさって、 |
心の弱い者はましてきわめて悲しいことであるとお見上げしていた。どんな |
Kokoro-yowaki hito ha, masite ito imiziku kanasi to mi tatematuru. Imiziki ata wo oni ni tukuri tari to mo, oroka ni mi-sutu maziki hito no ohom-arisama nari. Tamerahi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.6 | 「 ただ一言もえ聞こえさすまじきか。いかなれば、今さらにかかるぞ。なほ、人びとの言ひなしたるやうあるべし」 |
「たった一言でも申し上げることはできないのか。どうして、今さらこうなのだ。やはり、女房らが申し上げたことがあるのだろう」 |
「ちょっとひと言だけ話をすることもできないのだろうか。どうして今になってそんなに厳重に見張るのだろう。そばの者がどんなことを言ってあの方の自由意志を曲げさせたのか」 |
"Tada hito-koto mo e kikoye sasu maziki ka. Ika nare ba, ima-sara ni kakaru zo? Naho, hito-bito no ihi-nasi taru yau aru besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.7 | とのたまふ。ありさま詳しく聞こえて、 |
とおっしゃる。事情を詳しく申し上げて、 |
と侍従へ仰せられた。山荘内のことをくわしく申し上げて、 |
to notamahu. Arisama kuhasiku kikoye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.8 | 「 やがて、さ思し召さむ日を、かねては散るまじきさまに、たばからせたまへ。かくかたじけなきことどもを見たてまつりはべれば、身を捨てても思うたまへたばかりはべらむ」 |
「いずれ、そのようにお考えになっている日を、事前に漏れないように、計らいなさいませ。このように恐れ多いことを拝見いたしておりますと、身を捨ててでもお取り計らい申し上げましょう」 |
「またおいでの思召しのございます前からおっしゃってくださいまして、私どもにできますことをさせてくださいませ。こんなもったいない御様子を拝見いたします以上、私は自分を喜んで犠牲にもいたしまして、よろしい計らいをいたします」 |
"Yagate, sa obosimesa m hi wo, kanete ha tiru maziki sama ni, tabakara se tamahe. Kaku katazikenaki koto-domo wo mi tatematuri habere ba, mi wo sute te mo omou tamahe tabakari habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.9 | と聞こゆ。 我も人目をいみじく思せば、一方に怨みたまはむやうもなし。 |
と申し上げる。ご自身も人目をひどくお気になさっているので、一方的にお恨みになることもできない。 |
と侍従は申した。御自身も人目をはばかっておいでになるのであるから、恋人をだけお恨みになることもおできにならなかった。 |
to kikoyu. Ware mo hitome wo imiziku obose ba, hito-kata ni urami tamaha m yau mo nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.10 | 夜はいたく更けゆくに、このもの咎めする犬の声絶えず、 人びと追ひさけなどするに、弓引き鳴らし、あやしき男どもの声どもして、 |
夜はたいそう更けて行くが、この怪しんで吠える犬の声が止まず、供人たちが追い払いなどするために、弓を引き鳴らし、賤しい男どもの声がして、 |
夜はふけにふけてゆく。初めから吠えかかった犬はそれなりも声も休めずに騒がしく |
Yo ha itaku huke yuku ni, kono mono-togame suru inu no kowe taye zu, hito-bito ohi-sake nado suru ni, humi hiki-narasi, ayasiki wonoko-domo no kowe-domo si te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.11 | 「 火危ふし」 |
「火の用心」 |
「火の用心」 |
"Hi ayahusi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.12 | など言ふも、いと心あわたたしければ、帰りたまふほど、言へばさらなり。 |
などと言うのも、たいそう気が気でないので、お帰りになる時のお気持ちは、言葉では言い尽くせない。 |
などと呼ぶ。落ち着かぬお心から帰ろうとあそばしながらも、宮のお心は非常に悲しかった。 |
nado ihu mo, ito kokoro-awatatasikere ba, kaheri tamahu hodo, ihe ba sara nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.13 | 「 いづくにか身をば捨てむと白雲の |
「どこに身を捨てようかと捨て場も知らない、白雲が |
「いづくにか身をば捨てんとしら雲の |
"Iduku ni ka mi wo ba sute m to sira-kumo no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.14 | かからぬ山も泣く泣くぞ行く |
かからない山とてない山道を泣く泣く帰って行くことよ |
かからぬ山もなく泣くぞ行く |
kakara nu yama mo naku-naku zo yuku |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.15 | さらば、はや」 |
それでは、早く」 |
ではもう別れて行こう」 |
Sara ba, haya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.16 | とて、この人を帰したまふ。御けしきなまめかしくあはれに、夜深き露にしめりたる 御香の香うばしさなど、たとへむ方なし。 泣く泣くぞ帰り来たる。 |
と言って、この人をお帰しになる。ご様子が優雅で胸を打ち、夜深い露にしめったお香の匂いなどは、他にたとえようもない。泣く泣く帰って来た。 |
とお言いになり、侍従をお帰しになった。宮の御様子は |
tote, kono hito wo kahesi tamahu. Mi-kesiki namamekasiku ahare ni, yo-bukaki tuyu ni simeri taru ohom-ka no kaubasisa nado, tatohe m kata nasi. Naku naku zo kaheri ki taru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 第六段 浮舟の今生の思い |
7-6 Ukifune thinks about last life at her dying hour |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.1 | 右近は、言ひ切りつるよし言ひゐたるに、 君は、いよいよ思ひ乱るること多くて臥したまへるに、 入り来て、ありつるさま語るに、 いらへもせねど、 枕のやうやう浮きぬるを、かつはいかに見るらむ、とつつまし。明朝も、あやしからむまみを思へば、無期に臥したり。ものはかなげに 帯などして経読む。「 親に先だちなむ罪失ひたまへ」とのみ思ふ。 |
右近が、きっぱり断った旨を言っていると、君は、ますます思い乱れることが多くて臥せっていらっしゃるが、入って来て、先程の様子を話すので、返事もしないが、だんだんと泣けてしまったのを、一方ではどのように見るだろう、と気がひける。翌朝も、みっともない目もとを思うと、いつまでも臥していた。頼りなさそうに掛け帯などかけて経を読む。「親に先立つ罪障を無くしてください」とばかり思う。 |
右近が宮のおいでをお断わり申し上げたことを言ってから浮舟はいよいよ煩悶を深くして寝ていたが、侍従のはいって来て、外での様子を話すのに対して返辞はしないながら |
Ukon ha, ihi-kiri turu yosi ihi-wi taru ni, Kimi ha, iyo-iyo omohi midaruru koto ohoku te husi tamahe ru ni, iri-ki te, ari-turu sama kataru ni, irahe mo se ne do, makura no yau-yau uki nuru wo, katu ha ikani miru ram, to tutumasi. Tutomete mo, ayasikara m mami wo omohe ba, mugo ni husi tari. Mono-hakanage ni obi nado si te kyau yomu. "Oya ni saki-dati na m tumi usinahi tamahe." to nomi omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.2 | ありし絵を取り出でて見て、描きたまひし手つき、顔の匂ひなどの、向かひきこえたらむやうにおぼゆれば、昨夜、一言をだに聞こえずなりにしは、なほ今ひとへまさりて、いみじと思ふ。「 かの、心のどかなるさまにて見む、と行く末遠かるべきことを のたまひわたる人も、いかが思さむ」といとほし。 |
先日の絵を取り出して見て、お描きになった手つき、お顔の美しさなどが、向かい合っているように思い出されるので、昨夜、一言も申し上げずじまいになったことは、やはりもう一段とまさって、悲しく思われる。「あの、のんびりとした邸で逢おう、と末長い約束をおっしゃり続けていた方も、どのようにお思いになるだろう」とお気の毒である。 |
宮のお |
Arisi we wo tori-ide te mi te, kaki tamahi si tetuki, kaho no nihohi nado no, mukahi kikoye tara m yau ni oboyure ba, yobe, hito-koto wo dani kikoye zu nari ni si ha, naho ima hitohe masari te, imizi to omohu. "Kano, kokoro-nodoka naru sama nite mi m, to yuku-suwe tohokaru beki koto wo notamahi wataru hito mo, ikaga obosa m?" to itohosi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.3 | 憂きさまに言ひなす人もあらむこそ、思ひやり恥づかしけれど、「心浅く、けしからず人笑へならむを、聞かれたてまつらむよりは」など思ひ続けて、 |
嫌なことに噂する人もあるだろうことを、想像すると恥ずかしいが、「浅薄で、けしからぬ女だと物笑いになるのを、お聞かれ申すよりは」などと思い続けて、 |
初めから同じように永久愛して変わるまいと言っていた大将も、自分が死んだあとではどんなに歎くことであろうと思い、その人への恋を忘れて心の変わったために死んだと自殺後に言う人もあろうことの想像されるのも恥ずかしかったが、軽薄な女と思われ、宮のほうへ |
Uki sama ni ihi-nasu hito mo ara m koso, omohi-yari hadukasikere do, "Kokoro-asaku, kesikara zu hito-warahe nara m wo, kika re tatematura m yori ha." nado omohi-tuduke te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.4 | 「 嘆きわび身をば捨つとも亡き影に |
「嘆き嘆いて身を捨てても亡くなった後に |
歎きわび身をば捨つとも |
"Nageki wabi mi wo ba sutu tomo naki kage ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.5 | 憂き名流さむことをこそ思へ」 |
嫌な噂を流すのが気にかかる」 |
浮き名流さんことをこそ思へ |
ukina nagasa m koto wo koso omohe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.6 | 親もいと恋しく、例は、ことに思ひ出でぬ 弟妹の醜やかなるも、恋し。宮の上を思ひ出できこゆるにも、すべて今一度ゆかしき人多かり。人は皆、おのおの物染めいぞぎ、何やかやと言へど、耳にも入らず、夜となれば、人に見つけられず、出でて行くべき方を思ひまうけつつ、寝られぬままに、心地も悪しく、 皆違ひにたり。明けたてば、川の方を見やりつつ、 羊の歩みよりも ★ほどなき心地す。 |
親もとても恋しく、いつもは、特に思い出さない姉妹の醜いのも、恋しい。宮の上をお思い出し申し上げるにつけても、何から何までもう一度お会いしたい人が多かった。女房は皆、それぞれの衣類の染物に精を出し、何やかやと言っているが、耳にも入らず、夜となると、誰にも見つけられず、出て行く方法を考えながら、眠れないままに、気分も悪く、すっかり人が変わったようである。夜が明けると、川の方を見やりながら、羊の足取りよりも死に近い感じがする。 |
と |
Oya mo ito kohisiku, rei ha, koto ni omohi-ide nu harakara no minikuyaka naru mo, kohisi. Miya-no-Uhe wo omohi-ide kikoyuru ni mo, subete ima hito-tabi yukasiki hito ohokari. Hito ha mina, ono-ono mono-zome isogi, naniya-kaya to ihe do, mimi ni mo ira zu, yoru to nare ba, hito ni mi-tuke rare zu, ide te yuku beki kata wo omohi mauke tutu, ne rare nu mama ni, kokoti mo asiku, mina tagahi ni tari. Ake tate ba, kaha no kata wo mi-yari tutu, hituzi no ayumi yori mo hodo naki kokoti su. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 第七段 京から母の手紙が届く |
7-7 A mail comes to Ukifune from her mother in Kyoto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.1 | 宮は、いみじきことどもをのたまへり。今さらに、人や見むと思へば、この御返り事をだに、思ふままにも書かず。 |
宮は、たいそうな恨み言をおっしゃっていた。今さらに、誰が見ようかと思うと、このお返事をさえ、気持ちのままに書かない。 |
宮からは悲しかった夜のことをお言いになり激情にあふれたお手紙を贈られた。死期に人の見るかもしれぬものであるからと思うと、このお返事にも浮舟は思うだけのことを書かなかった。 |
Miya ha, imiziki koto-domo wo notamahe ri. Imasara ni, hito ya mi m to omohe ba, kono ohom-kaheri-goto wo dani, omohu mama ni mo kaka zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.2 | 「 ▼ からをだに憂き世の中にとどめずは |
「亡骸をさえ嫌なこの世に残さなかったら |
からをだにうき世の中にとどめずば |
"Kara wo dani uki yononaka ni todome zu ha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.3 | いづこをはかと君も恨みむ」 |
どこを目当てにと、あなた様もお恨みになりましょう」 |
いづくをはかと君も恨みん |
iduko wo haka to Kimi mo urami m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.4 | とのみ書きて出だしつ。「 かの殿にも、今はのけしき見せたてまつらまほしけれど、所々に書きおきて、 離れぬ御仲なれば、つひに聞きあはせたまはむこと、いと憂かるべし。すべて、いかになりけむと、 誰れにもおぼつかなくてやみなむ」と思ひ返す。 |
とだけ書いて出した。「あちらの殿にも、最後の様子をお見せ申し上げたいが、お二方に書き残しては、親しいお間柄なので、いつかは聞き合わせなさろうことは、とても困ることだどう。まるきり、どうなったのかと、誰からも分からないようにして死んでしまおう」と思い返す。 |
とだけ書いて出した。姫君は大将へも遺書としてのものを書いておきたく思ったが、あちらへもそちらへも書いておいて、親友でおありになる人たちの話に上ることがあれば、情操のないことと思われるかもしれぬ、 |
to nomi kaki te idasi tu. "Kano Tono ni mo, ima ha no kesiki mise tatematura mahosikere do, tokoro-dokoro ni kaki-oki te, hanare nu ohom-naka nare ba, tuhini kiki ahase tamaha m koto, ito ukaru besi. Subete, ikani nari kem to, tare ni mo obotukanaku te yami na m." to omohi-kahesu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.5 | 京より、母の御文持て来たり。 |
京から、母親のお手紙を持って来た。 |
京の使いが母の手紙を持って来た。 |
Kyau yori, Haha no ohom-humi mote ki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.6 | 「 寝ぬる夜の夢に ★、いと騒がしくて見たまひつれば、誦経所々せさせなどしはべるを、やがて、その夢の後、寝られざりつるけにや、ただ今、昼寝してはべる夢に、人の忌むといふことなむ、見えたまひつれば、驚きながらたてまつる。よく慎ませたまへ。 |
「昨晩の夢に、とても物騒がしくお見えになったので、誦経をあちこちの寺にさせたりなどしましたが、そのまま、その夢の後で、眠れなかったせいか、たった今、昼寝をして見ました夢に、世間で不吉とするようなことが、お現れになったので、目を覚ますなり差し上げました。十分に慎みなさい。 |
昨夜の悪夢の中であなたを見たものですから、ほうぼうの寺へ |
"Ne nuru yo no yume ni, ito sawagasiku te mi tamahi ture ba, zukyau tokoro-dokoro se sase nado si haberu wo, yagate, sono yume no noti, ne rare zari turu ke ni ya, tada-ima, hiru-ne si te haberu yume ni, hito no imu to ihu koto nam, miye tamahi ture ba, odoroki nagara tatematuru. Yoku tutusima se tamahe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.7 | 人離れたる御住まひにて、 時々立ち寄らせたまふ人の御ゆかりもいと恐ろしく、悩ましげにものせさせたまふ折しも、夢のかかるを、よろづになむ思うたまふる。 |
人里離れたお住まいで、時々お立ち寄りになる方のご正室のお恨みがとても恐ろしく、気分悪くいらっしゃるときに、夢がこのようなのを、いろいろと案じております。 |
寂しいそのお |
Hito hanare taru ohom-sumahi ni te, toki-doki tati-yora se tamahu hito no ohom-yukari mo ito osorosiku, nayamasige ni monose sase tamahu wori simo, yume no kakaru wo, yorodu ni nam omou tamahuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.8 | 参り来まほしきを、 少将の方の、なほ、いと心もとなげに、もののけだちて悩みはべれば、片時も立ち去ること、と いみじく言はれはべりてなむ。その近き寺にも御誦経せさせたまへ」 |
参上したいが、少将の北の方が、やはり、とても心配で、物の怪めいて患っていますので、少しの間も離れることは、いけないときつく言われていますので。そちらの近くの寺にも御誦経をさせなさい」 |
私が行きたいのだけれど、少将の妻の産前の容体が不安で、 |
Mawiri-ko mahosiki wo, Seusyau no kata no, naho, ito kokoro-motonage ni, mononoke-dati te nayami habere ba, kata-toki mo tati saru koto, to imiziku iha re haberi te nam. Sono tikaki tera ni mo mi-zyukyau se sase tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.9 | とて、その料の物、文など書き添へて、持て来たり。限りと思ふ命のほどを知らで、かく言ひ続けたまへるも、いと悲しと思ふ。 |
とあって、そのお布施の物や、手紙などを書き添えて、持って来た。最期と思っている命のことも知らないで、このように書き綴ってお寄越しになったのも、とても悲しいと思う。 |
と書いて、寺へ納めるべき物、寺への依頼状も添えて持たせて来たのであった。もう死ぬ覚悟をしている自分とも知らずに、こんなに心をつかっているかと |
tote, sono reu no mono, humi nado kaki-sohe te, mote ki tari. Kagiri to omohu inoti no hodo wo sira de, kaku ihi-tuduke tamahe ru mo, ito kanasi to omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8 | 第八段 浮舟、母への告別の和歌を詠み残す |
7-8 Ukifune composes and leaves waka to her mother |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.1 | 寺へ人遣りたるほど、 返り事書く。言はまほしきこと多かれど、つつましくて、ただ、 |
寺へ使者をやった間に、返事を書く。言いたいことはたくさんあるが、気がひけて、ただ、 |
寺へその使いをやった間に、母への返事を姫君は書くのであった。言いたいことは多かったが気恥ずかしくて、ただ、 |
Tera he hito yari taru hodo, kaheri-goto kaku. Iha mahosiki koto ohokare do, tutumasiku te, tada, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.2 | 「 後にまたあひ見むことを思はなむ |
「来世で再びお会いすることを思いましょう |
のちにまた逢ひ見んことを思はなん |
"Noti ni mata ahi-mi m koto wo omoha nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.3 | この世の夢に心惑はで」 |
この世の夢に迷わないで」 |
このよの夢に心まどはで |
kono yo no yume ni kokoro-madoha de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.4 | 誦経の鐘の風につけて聞こえ来るを、つくづくと聞き臥したまふ。 |
誦経の鐘の音が風に乗って聞こえて来るのを、つくづくと聞き臥していらっしゃる。 |
とだけ書いた。誦経の初めの鐘の音が川風に混じって聞こえてくるのをつくづくと聞いて浮舟は寝ていた。 |
Zyukyau no kane no kaze ni tuke te kikoye kuru wo, tuku-duku to kiki husi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.5 | 「 鐘の音の絶ゆる響きに音を添へて |
「鐘の音が絶えて行く響きに、泣き声を添えて |
鐘の |
"Kane no oto no tayuru hibiki ni ne wo sohe te |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.6 | わが世尽きぬと君に伝へよ」 |
わたしの命も終わったと母上に伝えてください」 |
わが世尽きぬと君に伝へよ |
waga yo tuki nu to Kimi ni tutahe yo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.7 | 巻数持て来たるに書きつけて、 |
僧の所から持って来た手紙に書き加えて、 |
これは寺から使いがもらって来た経巻へ書きつけた歌であるが、 |
Kwanzu mote ki taru ni kaki-tuke te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.8 | 「 今宵は、え帰るまじ」 |
「今夜は、帰ることはできまい」 |
使いは朝になってから帰る |
"Koyohi ha, e kaheru mazi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.9 | と言へば、 物の枝に結ひつけて置きつ。乳母、 |
と言うので、何かの枝に結び付けておいた。乳母が、 |
というために木の枝へ結びつけて渡すようにしておいた。 |
to ihe ba, mono no yeda ni yuhi-tuke te oki tu. Menoto, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.10 | 「 あやしく、心ばしりのするかな。夢も騒がし、と のたまはせたりつ。宿直人、よくさぶらへ」 |
「妙に、胸騷ぎのすることだわ。夢見が悪い、とおっしゃった。宿直人、十分注意するように」 |
「何だか胸騒ぎがしてならない。奥様も悪夢をたくさん見ると書いておよこしになったのだから、 |
"Ayasiku, kokoro-basiri no suru kana! Yume mo sawagasi, to notamahase tari tu. Tonowi-bito, yoku saburahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.11 | と言はするを、苦しと聞き臥したまへり。 |
などと言わせるのを、苦しいと聞きながら臥していらっしゃった。 |
と言っているのを、今夜脱出して川へ行こうとする浮舟は迷惑に思って聞いていた。 |
to iha suru wo, kurusi to kiki husi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.12 | 「 物聞こし召さぬ、いと あやし。御湯漬け」 |
「何もお召し上がりにならないのは、とてもいけません。お湯漬けを」 |
「お食事の進みませんのはどうしたことでしょう。お |
"Mono kikosimesa nu, ito ayasi. Ohom-yuduke." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.13 | などよろづに言ふを、「 さかしがるめれど、いと醜く老いなりて、我なくは、いづくにかあらむ」と思ひやりたまふも、いとあはれなり。「 世の中にえあり果つまじきさまを、ほのめかして言はむ」など思すに、 まづ驚かされて先だつ涙を、つつみたまひて、ものも言はれず。右近、ほど近く臥すとて、 |
などといろいろと言うのを、「よけいなおせっかいのようだが、とても醜く年とって、わたしが死んだら、どうするのだろう」とご想像なさるのも、とても不憫である。「この世には生きていられないことを、ちらっと言おう」などとお思いになるが、何より先に涙が溢れてくるのを、隠しなさって、何もおっしゃれない。右近は、お側近くに横になろうとして、 |
などと世話をやくのを、 |
nado yorodu ni ihu wo, "Sakasi-garu mere do, ito minikuku oyi-nari te, ware naku ha, iduku ni ka ara m?" to omohi-yari tamahu mo, ito ahare nari. "Yononaka ni e ari-hatu maziki sama wo, honomekasi te iha m." nado obosu ni, madu odoroka sare te saki-datu namida wo, tutumi tamahi te, mono mo iha re zu. Ukon, hodo tikaku husu tote, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.14 | 「 かくのみものを思ほせば、 もの思ふ人の魂は、あくがるなるものなれば、夢も騒がしきならむかし。 いづ方と思し定まりて、いかにもいかにも、おはしまさなむ」 |
「このようにばかり物思いをなさると、物思う人の魂は、抜け出るものと言いますから、夢見も悪いのでしょう。どちらの方かとお決めになって、どうなるにもこうなるにも、思う通りになさってください」 |
「あんまり物思いをあそばすと、物思いする魂は |
"Kaku nomi mono wo omohose ba, mono omohu hito no tamasihi ha, akugaru naru mono nare ba, yume mo sawagasiki nara m kasi. Idu-kata to obosi sadamari te, ikani-mo ikani-mo, ohasimasa nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.15 | とうち嘆く。萎えたる衣を 顔におしあてて、 臥したまへり、となむ。 |
と溜息をつく。柔らかくなった衣を顔に押し当てて、臥せっていらっしゃった、とか。 |
と歎息もしつつ告げた。柔らかい着物を顔に押し当てるようにして浮舟の姫君は寝たそうである。 |
to uti-nageku. Naye taru kinu wo kaho ni osi-ate te, husi tamahe ri, to nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 4/30/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 4/30/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 4/30/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/9/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経