51 浮舟(明融臨模本) |
UKIHUNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十六歳十二月から二十七歳の春雨の降り続く三月頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from December at the age of 26 to rainy days in March at the age of 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 浮舟と薫の物語 薫と浮舟、宇治橋の和歌を詠み交す |
3 Tale of Ukifune and Kaoru Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 匂宮、二条院に帰邸し、中君を責める |
3-1 Niou-no-miya comes back to Nijo-in and comforts Naka-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 二条の院におはしまし着きて、女君のいと心憂かりし御もの隠しもつらければ、 心やすき方に大殿籠もりぬるに、寝られたまはず、いと寂しきに、もの思ひまされば、心弱く 対に渡りたまひぬ。 |
二条の院にお着きになって、女君がたいそう水臭くお隠しになっていたことが情けないので、気楽な方の部屋でお寝みになったが、眠ることがおできになれず、とても寂しく物思いがまさるので、心弱く対の屋にお渡りになった。 |
二条の院へお帰りになった |
Nideu-no-win ni ohasimasi tuki te, Womna-Gimi no ito kokoro-ukari si ohom-mono-kakusi mo turakere ba, kokoro-yasuki kata ni ohotono-gomori nuru ni, ne rare tamaha zu, ito sabisiki ni, mono-omohi masare ba, kokoro-yowaku tai ni watari tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 何心もなく、いときよげにておはす。「 めづらしくをかしと見たまひし人よりも、またこれはなほありがたきさまはしたまへりかし」と見たまふものから、いとよく似たるを思ひ出でたまふも、胸塞がれば、いたくもの思したるさまにて、御帳に入りて大殿籠もる。女君も率て入りきこえたまひて、 |
何があったとも知らずに、とても美しそうにしていらっしゃる。「又となく魅力的だと御覧になった人よりも、またこの人はやはり類稀な様子をしていらっしゃった」と御覧になる一方で、とてもよく似ているのを思い出しなさるにも、胸が塞がる思いがして、ひどく物思いをなさっている様子で、御帳台に入ってお寝みになる。女君もお連れ申してお入りになって、 |
何も知らぬふうで中の君はきれいな顔をしていた。まれな美女であると御覧になった人よりもこれはまた一段まさった容姿であるとお認めになりながら、夫人の顔からよく似ていた恋人がお思い出されになった |
Nani-gokoro mo naku, ito kiyoge nite ohasu. "Medurasiku wokasi to mi tamahi si hito yori mo, mata kore ha naho arigataki sama ha si tamahe ri kasi." to mi tamahu monokara, ito yoku ni taru wo omohi-ide tamahu mo, mune hutagare ba, itaku mono obosi taru sama nite, mi-tyau ni iri te ohotono-gomoru. Womna-Gimi mo wi te iri kikoye tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | 「 心地こそいと悪しけれ。いかならむとするにかと、心細くなむある。まろは、 いみじくあはれと見置いたてまつるとも、 御ありさまはいととく変はりなむかし。人の本意は、かならずかなふなれば」 |
「気分がとても悪い。どうなるのだろうかと、心細い気がする。わたしは、どんなにも深く愛していても先立ってしまったら、お身の上はまことすぐに変わってしまうでしょうね。人の思いは、きっと通るものですからね」 |
「私は |
"Kokoti koso ito asikere. Ika nara m to suru ni ka to, kokoro-bosoku nam aru. Maro ha, imiziku ahare to mi-oi tatematuru tomo, ohom-arisama ha ito toku kahari na m kasi. Hito no ho'i ha, kanarazu kanahu nare ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | とのたまふ。「 けしからぬことをも、まめやかにさへのたまふかな」と思ひて、 |
とおっしゃる。「ひどいことを、真面目になっておっしゃるわ」と思って、 |
とお言いになった。こんな奇怪なことを至極まじめにお言いになるではないかと中の君は思い、 |
to notamahu. "Kesikara nu koto wo mo, mameyaka ni sahe notamahu kana!" to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | 「 かう聞きにくきことの 漏りて聞こえたらば、いかやうに聞こえなしたるにかと、 人も思ひ寄りたまはむこそ、あさましけれ。心憂き身には、すずろなることもいと苦しく」 |
「このように聞きずらいことが漏れ聞こえたら、どのように申し上げたのかと、あちらもお考えになりましょうことが、たまりません。不運の身には、いい加減な冗談もとてもつらいので」 |
「こうした醜い疑いを持っておいでになることを大将がお聞きになれば、何か中傷をしたかと私の思われますのがあさましゅうございます。薄幸な私はただいじめるために言っていらっしゃることでも重大なことのように苦しみます」 |
"Kau kiki nikuki koto no mori te kikoye tara ba, ika yau ni kikoye-nasi taru ni ka to, hito mo omohi-yori tamaha m koso, asamasikere. Kokoro-uki mi ni ha, suzuro naru koto mo ito kurusiku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | とて、背きたまへり。宮も、まめだちたまひて、 |
と言って、横をお向きになった。宮も、真面目になって、 |
と言って、夫人はあちらへ顔を向けた。宮も真剣なふうにおなりになって、 |
tote, somuki tamahe ri. Miya mo, mame-dati tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.7 | 「 まことにつらしと思ひきこゆることもあらむは、いかが思さるべき。まろは、御ために おろかなる人かは。 人も、ありがたしなど、とがむるまでこそあれ。 人にはこよなう思ひ落としたまふべかめり。誰れもさべきにこそはと、ことわらるるを、隔てたまふ御心の深きなむ、いと心憂き」 |
「ほんとうにつらいとお思い申し上げることがあるのは、どのようにお思いになるでしょう。わたしは、あなたにとっていい加減な人でしょうか。誰もが、めったにいない人だなどと、言い立てるくらいです。誰かに比べてこの上なく見下しなさるようだ。誰もそのような運命なのだろうと、自然と理解されるが、隔てなさるお気持ちの強いのが、とても情けない」 |
「いじめるためなどでなく、真底からあなたを恨んでいることが私にあったらどうしますか。私はあなたのために決して薄情な |
"Makoto ni turasi to omohi kikoyuru koto mo ara m ha, ikaga obosa ru beki? Maro ha, ohom-tame ni oroka naru hito kaha. Hito mo, arigatasi nado, togamuru made koso are. Hito ni ha koyonau omohi-otosi tamahu beka' meri. Tare mo sa' beki ni koso ha to, kotowaruru wo, hedate tamahu mi-kokoro no hukaki nam, ito kokoro-uki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.8 | とのたまふにも、「 宿世のおろかならで、尋ね寄りたるぞかし」と思し出づるに、涙ぐまれぬ。まめやかなるを、「いとほしう、 いかやうなることを聞きたまへるならむ」と驚かるるに、いらへきこえたまはむ言もなし。 |
とおっしゃるにつけても、「宿世が並々でなく、探し出したのだ」と思い出されると、自然と涙ぐまれた。真剣なお姿を、「お気の毒で、どのようなことをお聞きになったのだろう」とはっとさせられるが、お答え申し上げなさる言葉もない。 |
と言っておいでになりながら、その宿縁が並み並みでなかったから思う人に再会することができたとお思われになることで涙ぐまれたもう宮であった。いつものように |
to notamahu ni mo, "Sukuse no oroka nara de, tadune-yori taru zo kasi." to obosi-iduru ni, namida-guma re nu. Mameyaka naru wo, "Itohosiu, ika yau naru koto wo kiki tamahe ru nara m." to odoroka ruru ni, irahe kikoye tamaha m koto mo nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.9 | 「 ものはかなきさまにて見そめたまひしに、何ごとをも軽らかに推し量りたまふにこそはあらめ。すずろなる人をしるべにて、その心寄せを思ひ知り始めなどしたる過ちばかりに、おぼえ劣る身にこそ」と 思し続くるも、よろづ悲しくて、いとどらうたげなる御けはひなり。 |
「ちょっとした関係で結婚なさったので、どんなことも軽い気持ちで推量なさるのであろう。縁故もない人を頼みにして、その好意を受け入れたりしたのが過ちで、軽く扱われる身なのだ」とお思い続けるのも、何かと悲しくて、ますます可憐なご様子である。 |
初めがあんなことであった自分は |
"Mono-hakanaki sama nite mi-some tamahi si ni, nani-goto wo mo karoraka ni osihakari tamahu ni koso ha ara me. Suzuro naru hito wo sirube nite, sono kokoro-yose wo omohi siri hazime nado si taru ayamati bakari ni, oboye otoru mi ni koso." to obosi tudukuru mo, yorodu kanasiku te, itodo rautage naru ohom-kehahi nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.10 | 「 かの人見つけたることは、しばし知らせたてまつらじ」と 思せば、「 異ざまに思はせて怨みたまふを、 ただこの大将の御ことをまめまめしくのたまふ」と思すに、「人や虚言をたしかなるやうに聞こえたらむ」など思す。ありやなしやを聞かぬ間は、見えたてまつらむも恥づかし。 |
「あの人を見つけたことは、しばらくの間はお知らせ申すまい」とお思いなので、「他の事に思わせて恨みなさるのを、ひたすらこの大将の事を真剣になっておっしゃる」とお思いになると、「誰かが嘘を真実のように申し上げたのだろう」などとお思いになる。事実か否かを確かめない間は、お会い申すのも恥ずかしい。 |
あの恋人を発見したとはなおしばらくの間知らせずにおこうとお思いになるために、ほかのことに思わせて宮は |
"Kano hito mi-tuke taru koto ha, sibasi sirase tatematura zi." to obose ba, "Koto-zama ni omoha se te urami tamahu wo, tada kono Daisyau no ohom-koto wo mame-mamesiku notamahu." to obosu ni, "Hito ya sora-goto wo tasika naru yau ni kikoye tara m." nado obosu. Ari-ya nasi-ya wo kika nu ma ha, miye tatematura m mo hadukasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 明石中宮からと薫の見舞い |
3-2 A visitor from Akashi-Empress and Kaoru comes to Niou-no-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 内裏より大宮の御文あるに、驚きたまひて、 なほ心解けぬ御けしきにて、 あなたに渡りたまひぬ。 |
内裏から大宮のお手紙が来たので、驚きなさって、やはり釈然としないご様子で、あちらにお渡りになった。 |
御所から中宮のお手紙の使いがまいったと申し上げられた時に、驚いてお起きになった宮は、まだ解けないお気持ちのままで御自身の室のほうへ行っておしまいになった。 |
Uti yori Oho-Miya no ohom-humi aru ni, odoroki tamahi te, naho kokoro-toke nu mi-kesiki nite, anata ni watari tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 「 昨日のおぼつかなさを。悩ましく思されたなる、よろしくは参りたまへ。久しうもなりにけるを」 |
「昨日の心配したことよ。ご気分悪くいらっしゃったそうですが、悪くないようでしたら参内なさい。久しく見えませんこと」 |
お手紙の内容は昨日お逢いになれなかったことで御心配をあそばしたことが言われてあるのであった。気分がよろしければおいでなさい。久しくお逢いしないでいるのですから。 |
"Kinohu no obotukanasa wo. Nayamasiku obosa re ta' naru, yorosiku ha mawiri tamahe. Hisasiu mo nari ni keru wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | などやうに聞こえたまへれば、騒がれたてまつらむも苦しけれど、まことに御心地も違ひたるやうにて、その日は参りたまはず。上達部など、あまた 参りたまへど、御簾の内にて暮らしたまふ。 |
などというように申し上げなさったので、大げさに心配していただくのもつらいけれど、ほんとうにご気分も正気でないようで、その日は参内なさらない。上達部などが、大勢参上なさったが、御簾の中でその日はお過ごしになる。 |
などと言うものであったから、御心配をおさせ申すのは苦しいと思召しながら、実際病気らしい御気分であったためその日は参内されなかった。高官たちが幾人も伺候したが皆 |
nado yau ni kikoye tamahe re ba, sawaga re tatematura m mo kurusikere do, makoto ni mi-kokoti mo tagahi taru yau nite, sono hi ha mawiri tamaha zu. Kamdatime nado, amata mawiri tamahe do, mi-su no uti nite kurasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 | 夕つ方、右大将参りたまへり。 |
夕方、右大将が参上なさった。 |
夕方に源大将が出て来た。 |
Yuhu-tu-kata, U-Daisyau mawiri tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.5 | 「 こなたにを」 |
「こちらに」 |
こちらへ |
"Konata ni wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.6 | とて、うちとけながら対面したまへり。 |
と言って、寛いだ恰好でお会いなさった。 |
とお言いになって、御自身のそばへこの時はお迎えになった。 |
tote, uti-toke nagara taimen si tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.7 | 「 悩ましげにおはします、とはべりつれば、宮にもいとおぼつかなく思し召してなむ。いかやうなる御悩みにか」 |
「ご気分がお悪い、ということでございましたので、宮におかれましてもとてもご心配あそばされています。どのようなご病気すか」 |
「御病気でいらせられますそうで、中宮様もお逢いあそばせないのを寂しく思召すふうでございました。どんな御症状ですか」 |
"Nayamasige ni ohasimasu, to haberi ture ba, Miya ni mo ito obotukanaku obosimesi te nam. Ika yau naru ohom-nayami ni ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.8 | と聞こえたまふ。見るからに、御心騷ぎのいとどまされば、言少なにて、「 聖だつと言ひながら、こよなかりける山伏心かな。さばかり あはれなる人を、さて置きて、心のどかに月日を待ちわびさすらむよ」と思す。 |
とお尋ね申し上げなさる。お会いしただけで、お胸がどきどき高まってくるので、言葉少なくて、「聖めいているというが、途方もない山伏心だな。あれほどかわいい女を、そのままにして置いて、何日も何日も待ちわびさせているとは」とお思いになる。 |
と薫はお尋ねした。顔を御覧になった時から胸騒ぎのひどくなったため、言葉少なに宮は相手をしておいでになった。僧がかった人とはいいながらも、人間的な感情を人の学びがたいまでにも殺している男ではないか。あれほど可憐な人に寂しい山荘住まいをさせ、日々待ち暮らさせているようなこともこの人にはできるのであるなどと宮はお思いになり、平生はそんな話でない時にさえ、まじめ男であることを薫は |
to kikoye tamahu. Miru kara ni, mi-kokoro-sawagi no itodo masare ba, koto-zukuna nite, "Hiziri-datu to ihi nagara, koyonakari keru yamabusi-gokoro kana! Sabakari ahare naru hito wo, sate oki te, kokoro-nodoka ni tuki-hi wo mati-wabi sasu ram yo!" to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.9 | 例は、さしもあらぬことのついでにだに、 我はまめ人ともてなし名のりたまふを、 ねたがりたまひて、よろづにのたまひ破るを、かかること見表はいたるを、 いかにのたまはまし。されど、さやうの戯れ事もかけたまはず、いと苦しげに見えたまへば、 |
いつもは、ほんの些細な機会でさえ、自分はまじめ人間だと振る舞い自称していらっしゃるのを、悔しがりなさって、何かと文句をおつけになるのを、このような事を発見したのを、どうしておっしゃっらないだろうか。けれども、そのような冗談もおっしゃらず、とてもつらそうにお見えになるので、 |
こんなことがあるではないかなどと微細なことまでもあげてお責めになる宮でおありになったから、宇治の人を発見された以上は、どんなにそれでおからかいになるかもしれないのに、今日は |
Rei ha, sasimo ara nu koto no tuide ni dani, ware ha mame-bito to motenasi nanori tamahu wo, netagari tamahi te, yorodu ni notamahi yaburu wo, kakaru koto mi-arahai taru wo, ikani notamaha masi. Saredo, sayau no tahabure-goto mo kake tamaha zu, ito kurusige ni miye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.10 | 「 不便なるわざかな。おどろおどろしからぬ御心地の、さすがに日数経るは、いと悪しきわざにはべり。御風邪よくつくろはせたまへ」 |
「お気の毒なことです。大したご病気ではなくても、やはり何日も続くのは、とてもよくないことでございます。お風邪を充分ご養生なさいませ」 |
「困ったことでございますね。たいしてお悪いのではなくて、しかも同じような容体の続きますのは悪い兆候でございます。 |
"Hu-bin naru waza kana! Odoro-odorosikara nu mi-kokoti no, sasuga ni hi-kazu huru ha, ito asiki waza ni haberi. Ohom-kaze yoku tukuroha se tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.11 | など、まめやかに聞こえおきて出でたまひぬ。「 恥づかしげなる人なりかし。わがありさまを、 いかに思ひ比べけむ」など、さまざまなることにつけつつも、ただ この人を、時の間忘れず思し出づ。 |
などと、心からお見舞い申し述べてお出になった。「気のひけるほど立派な人である。わたしの態度を、どのように比較しただろう」などと、いろいろな事柄につけて、ひたすらあの女を、束の間も忘れずお思い出しになる。 |
などとまじめに見舞いを言いおいて薫は帰った。上品な男である、あの人と自分をどんなふうにあの恋人は比較して見ることだろうなどと、何事も宇治の人を離れては思うことのおできにならない心に宮はなっておいでになった。 |
nado, mameyaka ni kikoye-oki te ide tamahi nu. "Hadukasige naru hito nari kasi. Wa ga arisama wo, ikani omohi kurabe kem." nado, sama-zama naru koto ni tuke tutu mo, tada kono hito wo, toki no ma wasure zu obosi-idu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.12 | かしこには、石山も停まりて、いとつれづれなり。御文には、いといみじきことを書き集めたまひて遣はす。それだに心やすからず、「時方」と召しし大夫の従者の、心も知らぬしてなむやりける。 |
あちらでは、石山詣でも中止になって、まことに何もすることない。お手紙には、とてもつらい思いをたくさんお書きになってお遣りになる。それでさえ気が落ち着かず、「時方」と言って召し出した大夫の従者で、事情を知らない者をして遣わしたのであった。 |
宇治の山荘の人たちは石山 |
Kasiko ni ha, Isiyama mo tomari te, ito ture-dure nari. Ohom-humi ni ha, ito imiziki koto wo kaki atume tamahi te tukahasu. Sore dani kokoro-yasukara zu, "Tokikata" to mesi si Taihu no zyusya no, kokoro mo sira nu site nam yari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.13 | 「 右近が古く知れりける人の、殿の御供にて尋ね出でたる、さらがへりてねむごろがる」 |
「私め右近が古くから知っていた人で、殿のお供で訪ねて来まして、昔に縒りを戻して懇意になろうとするのです」 |
右近を以前知っていた人が大将の供をして行って、話などをした時から、またしきりに好意を運んでくるのである |
"Ukon ga huruku sire ri keru hito no, Tono no ohom-tomo nite tadune-ide taru, saragaheri te nemgoro-garu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.14 | と、友達には言ひ聞かせたり。 よろづ右近ぞ、虚言しならひける。 |
と、女房仲間には言い聞かせていた。何かと右近は、嘘をつくことになったのであった。 |
と右近は他の |
to, tomodati ni ha ihi kikase tari. Yorodu Ukon zo, sora-goto si narahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 二月上旬、薫、宇治へ行く |
3-3 Kaoru goes to Uji at the begining of February |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 月もたちぬ。かう思し知らるれど、おはしますことはいとわりなし。「 かうのみものを思はば、さらにえながらふまじき身なめり」と、心細さを添へて嘆きたまふ。 |
月が替わった。このようにお分かりになるが、お出かけになることはとても無理である。「こうして物思いばかりしていたら、生きてもいられないようなわが身だ」と、心細さが加わってお嘆きになる。 |
二月になった。逢いたいとこがれ続けておいでになる宮でおありになるが宇治へお出かけになることは困難であった。こう |
Tuki mo tati nu. Kau obosi sira rure do, ohasimasu koto ha ito warinasi. "Kau nomi mono wo omoha ba, sarani e nagarahu maziki na' meri." to, kokoro-bososa wo sohe te nageki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 大将殿、すこしのどかになりぬるころ、例の、忍びておはしたり。寺に仏など拝みたまふ。御誦経せさせたまふ僧に、物賜ひなどして、夕つ方、 ここには忍びたれど、 これはわりなくもやつしたまはず。烏帽子直衣の姿、いとあらまほしくきよげにて、歩み入りたまふより、恥づかしげに、用意ことなり。 |
大将殿は、少しのんびりしたころ、いつものように、人目を忍んでお出でになった。寺で仏などを拝みなさる。御誦経をおさせになる僧に、お布施を与えたりして、夕方に、こちらには人目を忍んでだが、この人はひどく身を簡略になさるでもない。烏帽子に直衣姿が、たいそう理想的で美しそうで、歩んでお入りになるなり、こちらが恥ずかしくなりそうで、心づかいが格別である。 |
薫は公務の少しひまになったころ例のように微行で宇治へ出かけた。寺へ行き仏に謁し、 |
Daisyau-dono, sukosi nodoka ni nari nuru koro, rei no, sinobi te ohasi tari. Tera ni Hotoke nado ogami tamahu. Mi-zyukyau se sase tamahu sou ni, mono tamahi nado si te, yuhu-tu-kata, koko ni ha sinobi tare do, kore ha warinaku mo yatusi tamaha zu. Ebousi nahosi no sugata, ito aramahosiku kiyoge nite, ayumi-iri tamahu yori, hadukasige ni, youi koto nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | 女、 いかで見えたてまつらむとすらむと、空さへ恥づかしく恐ろしきに、 あながちなりし人の御ありさま、うち思ひ出でらるるに、また、この人に見えたてまつらむを思ひやるなむ、いみじう心憂き。 |
女は、どうしてお会いできようかと、空にまで目があって恐ろしく思われるので、激しく一途であった方のご様子が、自然と思い出されると、一方で、この方にお会いすることを想像すると、ひどくつらい。 |
姫君は罪を犯した身で薫を迎えることが苦しく天地に恥じられて恐ろしいにもかかわらず、不条理な恋を持って接近しておいでになった人のことが忘れられない心もあって、またこの人に貞操な女らしくして逢うことが非常に情けなかった。 |
Womna, ikade miye tatematura m to su ram to, sora sahe hadukasiku osorosiki ni, anagati nari si hito no ohom-arisama, uti-omohi-ide raruru ni, mata, kono hito ni miye tatematura m wo omohi-yaru nam, imiziu kokoro-uki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | 「『 われは年ごろ見る人をも、皆思ひ変はりぬべき心地なむする』とのたまひしを、 げに、そののち御心地苦しとて、 いづくにもいづくにも、例の御ありさまならで、御修法など騒ぐなるを聞くに、また、 いかに聞きて思さむ」と思ふもいと苦し。 |
「『私は今まで何年も会っていた女の思いが、皆あなたに移ってしまいそうだ』とおっしゃったのを、なるほど、その後はご気分が悪いと言って、どの方にもどの方にも、いつものようなご様子ではなく、御修法などと言って騒いでいるというのを聞くと、また、どのようにお聞きになってどのようにお思いになるだろうか」と、思うにつけてまことにつらい。 |
自分は今まで愛していた人への情けも皆捨てるほかはない気がすると宮はお語りになったのであったが、そのお言葉どおりに御病気に託してどちらの夫人の所へもおいでになることはなくて、おそばで始終修法ばかりを行なわせておいでになるというそうであるのに、自分が大将と夫婦らしくしていたということをお聞きになればどんなふうにお憎みになるであろうと思われるのも苦しかった。 |
"'Ware ha tosi-goro miru hito wo mo, mina omohi kahari nu beki kokoti nam suru.' to notamahi si wo, geni, sono noti mi-kokoti kurusi tote, iduku ni mo iduku ni mo, rei no ohom-arisama nara de, mi-syuhohu nado sawagu naru wo kiku ni, mata, ikani kiki te obosa m." to omohu mo ito kurusi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | この人はた、いとけはひことに、心深く、なまめかしきさまして、久しかりつるほどのおこたりなどのたまふも、言多からず、恋し愛しとおり立たねど、常にあひ見ぬ恋の苦しさを、さまよきほどにうちのたまへる、いみじく ▼ 言ふにはまさりて、いとあはれと 人の思ひぬべきさまをしめたまへる人柄なり。 艶なる方はさるものにて、行く末長く人の頼みぬべき心ばへなど、こよなく まさりたまへり。 |
この方はこの方で、たいそう感じが格別で、愛情深く、優美な態度で、久しく会わなかったご無沙汰のお詫びをおっしゃるのも、言葉数多くなく、恋しい愛しいと直接には言わないが、いつも一緒にいられない恋の苦しい気持ちを、体裁よくおっしゃるのが、ひどく言葉を尽くして言うよりもまさって、たいそうしみじみと誰もが思うにちがいないような感じを身につけていらっしゃる人柄である。やさしく美しい方面は無論のこと、将来末長く信頼できる性格などが、この上なくまさっていらっしゃった。 |
薫はまた別箇の存在と見えて優美なふうで、ながく来られなかった言いわけなどをするにも多くの言葉は用いない。恋しい悲しいとひたひたと迫って言うことはないが、常に逢いがたい人に持つ恋の苦しさを品よく言う効果は、誇張された多くの言葉がもたらすそれにまさって、心を |
Kono hito hata, ito kehahi koto ni, kokoro-hukaku, namamekasiki sama si te, hisasikari turu hodo no okotari nado notamahu mo, koto ohokara zu, kohisi kanasi to ori-tata ne do, tune ni ahi-mi nu kohi no kurusisa wo, sama yoki hodo ni uti-notamahe ru, imiziku ihu ni masari te, ito ahare to hito no omohi nu beki sama wo sime tamahe ru hitogara nari. En-naru kata ha saru mono nite, yuku-suwe nagaku hito no tanomi nu beki kokorobahe nado, koyonaku masari tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 「 思はずなるさまの心ばへなど、漏り聞かせたらむ時も、なのめならずいみじくこそあべけれ。あやしううつし心もなう 思し焦らるる人を、あはれと思ふも、それはいとあるまじく軽きことぞかし。この人に憂しと思はれて、忘れたまひなむ」心細さは、いと深うしみにければ、思ひ乱れたるけしきを、「 月ごろに、こよなうものの心知り、ねびまさりにけり。つれづれなる住み処のほどに、思ひ残すことはあらじかし」と見たまふも、心苦しければ、常よりも心とどめて語らひたまふ。 |
「心外なと思われる様子の気持ちなどが、漏れてお耳に入った時は、とても大変なことになるであろう。不思議なほど正気もなく恋い焦がれている方を、恋しいと思うのも、それはとてもとんでもなく軽率なことだわ。この方に嫌だと思われて、お忘れになるってしまう」心細さは、とても深くしみこんでいたので、思い乱れている様子を、「途絶えていたこの幾月間に、すっかり男女の情理をわきまえ、成長したものだ。何もすることのない住処にいる間に、あらゆる物思いの限りを尽くしたのだろうよ」と御覧になるにつけても、気の毒なので、いつもより心をこめてお語らいになる。 |
自分が意外な恋をしていることをこの人が知れば、真心からどんなに歎くことであろう、狂おしいようにも自分を熱愛する人に自分も愛は覚えるが、それはまじめな人間の心とは言えない、 |
"Omoha zu naru sama no kokorobahe nado, mori-kika se tara m toki mo, nanome nara zu imiziku koso a' bekere. Ayasiu utusi-gokoro mo nau obosi-ira ruru hito wo, ahare to omohu mo, sore ha ito arumaziku karoki koto zo kasi. Kono hito ni usi to omoha re te, wasure tamahi na m." kokoro-bososa ha, ito hukau simi ni kere ba, omohi-midare taru kesiki wo, "Tuki-goro ni, koyonau mono no kokoro-siri, nebi-masari ni keri. Ture-dure naru sumika no hodo ni, omohi-nokosu koto ha ara zi kasi." to mi tamahu mo, kokoro-gurusikere ba, tune yori mo kokoro todome te katarahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 第四段 薫と浮舟、それぞれの思い |
3-4 Kaoru and Ukifune have separate thoughts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | 「 造らする所、やうやうよろしうしなしてけり。一日なむ、見しかば、ここよりは気近き水に、花も見たまひつべし。 三条の宮も近きほどなり。明け暮れおぼつかなき隔ても、おのづからあるまじきを、この春のほどに、さりぬべくは渡してむ」 |
「造らせている所は、だんだんと出来上がって来た。先日、見に行ったが、ここよりはやさしい感じの川があって、花も御覧になれましょう。三条宮邸も近い所です。毎日会わないでいる不安も、自然と消えましょうから、この春のころに、差し支えなければお連れしよう」 |
「新築させている家がどうやら形にはなりましたよ。この間見に行ったのですが、ここよりは水のある場所に近くて、桜なども相当にあります。三条の宮とも距離は遠くないのです。そこへ来れば毎日でも逢えないことはないのですから、この春のうちに都合さえよければあなたを移そうと思う」 |
"Tukura suru tokoro, yau-yau yorosiu si-nasi te keri. Hito-hi nam, mi sika ba, koko yori ha ke-dikaki midu ni, hana mo mi tamahi tu besi. Samdeu-no-miya mo tikaki hodo nari. Ake-kure obotukanaki hedate mo, onodukara aru maziki wo, kono haru no hodo ni, sa'ri-nu-beku ha watasi te m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 | と思ひてのたまふも、「 かの人の、のどかなるべき所思ひまうけたりと、 昨日ものたまへりしを、かかることも知らで、さ思すらむよ」と、あはれながらも、「 そなたになびくべきにはあらずかし」 と思ふからに、 ありし御さまの、面影におぼゆれば、「 我ながらも、うたて心憂の身や」と、思ひ続けて泣きぬ。 |
と思っておっしゃるのにつけても、「あの方が、のんびりとした所を考えついたと、昨日もおっしゃっていたが、このようなことをご存知なくて、そのようにお考えになっていることよ」と、心が痛みながらも、「そちらに靡くべきではないのだ」と思うその一方で、先日のお姿が、面影に現れるので、「自分ながらも嫌な情けない身の上だわ」と、思い続けて泣いた。 |
と薫の言うのを聞いていて、隠れてのどかに住む家の用意をさせているとは |
to omohi te notamahu mo, "Kano hito no, nodoka naru beki tokoro omohi mauke tari to, kinohu mo notamahe ri si wo, kakaru koto mo sira de, sa obosu ram yo." to, ahare nagara mo, "Sonata ni nabiku beki ni ha ara zu kasi." to omohu kara ni, ari si ohom-sama no, omokage ni oboyure ba, "Ware nagara mo, utate kokoro-u no mi ya!" to, omohi-tuduke te naki nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.3 | 「 御心ばへの、かからでおいらかなりしこそ、のどかにうれしかりしか。人のいかに聞こえ知らせたることかある。すこしもおろかならむ心ざしにては、かうまで参り来べき身のほど、道のありさまにもあらぬを」 |
「お気持ちが、このようでなくおっとりとしていたのが、のんびりと嬉しかった。誰かが何か言い聞かせたことがあるのですか。少しでも並々の愛情であったら、こうしてわざわざやって来ることができる身分ではないし、道中でもないのですよ」 |
「あなたがこんなふうでなくおおようだったら、私も心配がなくておられたのですよ。だれか中傷をした者でもあったのですか、少しでもあなたをおろそかに思っていれば、こんなにして逢いに来られる私の身分でも |
"Mi-kokorobahe no, kakara de oyiraka nari si koso, nodoka ni uresikari sika. Hito no ikani kikoye sirase taru koto ka aru. Sukosi mo oroka nara m kokoro-zasi nite ha, kau made mawiri ku beki mi no hodo, miti no arisama ni mo ara nu wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.4 | など、 朔日ごろの夕月夜に、すこし端近く臥して眺め出だしたまへり。 男は、過ぎにし方のあはれをも思し出で、女は、今より添ひたる身の憂さを嘆き加へて、かたみにもの思はし。 |
などと言って、初旬ころの夕月夜に、少し端に近い所に臥して外を眺めていらっしゃった。男は、亡くなった姫君のことを思い出しなさって、女は、今から加わった身のつらさを嘆いて、お互いに物思いする。 |
などと薫は言い、月初めの夕月夜に少し縁へ近い所へ出て横になりながら二人は外を見ていた。薫は昔の人を思い、女は新しい物思いになった恋に苦しみ、双方とも離れ離れのことを考えていた。 |
nado, tuitati-goro no yuhu-duku-yo ni, sukosi hasi tikaku husi te nagame idasi tamahe ri. Wotoko ha, sugi ni si kata no ahare wo mo obosi-ide, Womna ha, ima yori sohi taru mi no usa wo nageki kuhahe te, katamini mono omohasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 第五段 薫と浮舟、宇治橋の和歌を詠み交す |
3-5 Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.1 | 山の方は霞隔てて、 寒き洲崎に立てる鵲の姿も、所からはいとをかしう見ゆるに、宇治橋のはるばると見わたさるるに、柴積み舟の所々に行きちがひたるなど、他にて目馴れぬことどものみとり集めたる所なれば、見たまふたびごとに、なほ そのかみのことのただ今の心地して、 いとかからぬ人を見交はしたらむだに、めづらしき仲のあはれ多かるべきほどなり。 |
山の方は霞が隔てて、寒い洲崎に立っている鵲の姿も、場所柄かとても興趣深く見えるが、宇治橋がはるばると見渡されるところに、柴積み舟があちこちで行き交っているのなどが、他の場所では見慣れないことばかりがあれやこれやある所なので、御覧になる度ごとに、やはりその当時のことがまるで今のような気がして、ほんとにそうでもない女を相手にする時でさえ、めったにない逢瀬の情が多いにちがいないところである。 |
山のほうは霞がぼんやりと隠していて、寒い |
Yama no kata ha kasumi hedate te, samuki susaki ni tate ru kasasagi no sugata mo, tokoro kara ha ito wokasiu miyuru ni, Udi-basi no haru-baru to mi-watasa ruru ni, siba-tumi-bune no tokoro-dokoro ni yuki-tigahi taru nado, hoka nite me-nare nu koto-domo nomi tori-atume taru tokoro nare ba, mi tamahu tabi goto ni, naho sono kami no koto no tada-ima no kokoti si te, ito kakara nu hito wo mi-kahasi tara m dani, medurasiki naka no ahare ohokaru beki hodo nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
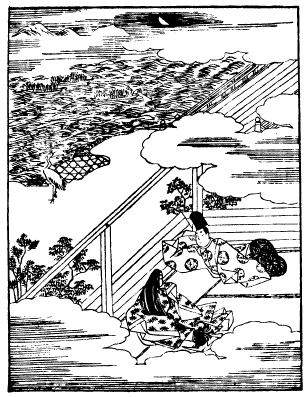 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.2 | まいて、 ▼ 恋しき人によそへられたるもこよなからず、やうやうものの心知り、都馴れゆくありさまのをかしきも、こよなく見まさりしたる心地したまふに、女は、かき集めたる心のうちに、催さるる涙、ともすれば出でたつを、慰めかねたまひつつ、 |
それ以上に、恋しい女に似ているのもこの上なく、だんだんと男女の情理を知り、都の女らしくなってゆく様子がかわいらしいのも、すっかり良くなった感じがなさるが、女は、あれこれ物思いする心中に、いつの間にかこみ上げてくる涙、ややもすれば流れ出すのを、慰めかねなさって、 |
まして恋しい人に似たところが多く、かわりとして見てもそう格段な価値の相違もない人が、ようやく思想も成熟してき、都なれていく様子の美しさも時とともに加わる人であるからと薫は満足感に似たものを覚えて相手を見ていたが、女はいろいろな煩悶のために、ともすれば涙のこぼれる様子であるのを大将はなだめかねていた。 |
Maite, kohisiki hito ni yosohe rare taru mo koyonakara zu, yau-yau mono no kokoro-siri, miyako nare yuku arisama no wokasiki mo, koyonaku mi masari si taru kokoti si tamahu ni, Womna ha, kaki-atume taru kokoro no uti ni, moyohosa ruru namida, tomo-sure-ba, ide-tatu wo, nagusame kane tamahi tutu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.3 | 「 宇治橋の長き契りは朽ちせじを |
「宇治橋のように末長い約束は朽ちないから |
「宇治橋の長き契りは朽ちせじを |
"Udi-basi no nagaki tigiri ha kuti se zi wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.4 | 危ぶむ方に心騒ぐな |
不安に思って心配なさるな |
あやぶむ方に心騒ぐな |
ayabumu kata ni kokoro sawagu na |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.5 | 今見たまひてむ」 |
やがてお分かりになりましょう」 |
そのうち私の愛を理解できますよ」 |
Ima mi tamahi te m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.6 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
と言った。 |
to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.7 | 「 絶え間のみ世には危ふき宇治橋を |
「絶え間ばかりが気がかりでございます宇治橋なのに |
絶え間のみ世には危ふき宇治橋を |
"Tayema nomi yo ni ha ayahuki Udi-basi wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.8 | 朽ちせぬものとなほ頼めとや」 |
朽ちないものと依然頼りにしなさいとおっしゃるのですか」 |
朽ちせぬものとなほたのめとや |
kuti se nu mono to naho tanome to ya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.9 | さきざきよりもいと見捨てがたく、しばしも立ちとまらまほしく思さるれど、人のもの言ひのやすからぬに、「 今さらなり。心やすきさまにてこそ」など思しなして、暁に帰りたまひぬ。「 いとようもおとなびたりつるかな」と、心苦しく思し出づること、 ありしにまさりけり。 |
以前よりもまことに見捨てがたく、暫くの間も逗留していたくお思いになるが、世間の噂がうるさいので、「今さら長居をすべきでもない。気楽に会える時になったら」などとお考えになって、早朝にお帰りになった。「とても素晴らしく成長なさったな」と、おいたわしくお思い出しになること、今まで以上であった。 |
と女は言う。今まで来て逢っていた時よりも別れて行くのがつらく、少しの時間でも多くそばにいたい気のする薫であったが、世間はいろいろな批評をしたがるものであるから、今まで事もなく隠すことのできた愛人との間のことが、今になって暴露することになってはまずい、よい時節に公表もできるのを待とうと思い夜明けに帰った。感情の豊かに備わった女になったと薫は宇治の人のことを思い、哀れに思い出されることは以前に倍した。 |
Saki-zaki yori mo ito mi-sute gataku, sibasi mo tati-tomara mahosiku obosa rure do, hito no mono-ihi yasukara nu ni, "Ima-sara nari. Kokoro-yasuki sama nite koso." nado obosi-nasi te, akatuki ni kaheri tamahi nu. "Ito you mo otonabi tari turu kana!" to, kokoro-gurusiku obosi-iduru koto, arisi ni masari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 4/30/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 4/30/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 4/30/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/9/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経