51 浮舟(明融臨模本) |
UKIHUNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十六歳十二月から二十七歳の春雨の降り続く三月頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from December at the age of 26 to rainy days in March at the age of 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 匂宮の物語 匂宮、大内記から薫と浮舟の関係を聞き知る |
1 Tale of Niou-no-miya Niou-no-miya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 匂宮、浮舟を追想し、中君を恨む |
1-1 Niou-no-miya recalls Ukifune and complains to his wife Naka-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 宮、なほ、かのほのかなりし夕べを思し忘るる世なし。「 ことことしきほどにはあるまじげなりしを、人柄のまめやかにをかしうもありしかな」と、いとあだなる御心は、「口惜しくてやみにしこと」と、ねたう思さるるままに、 女君をも、 |
宮は、今もなお、あのちらっと御覧になった夕方をお忘れになる時とてない。「たいした身分ではけっしてなさそうであったが、人柄が誠実で魅力的であったなあ」と、とても浮気なご性分にとっては、「残念なところで終わってしまったことだ」と、悔しく思われなさるままに、女君に対しても、 |
|
Miya, naho, kano honoka nari si yuhube wo obosi wasururu yo nasi. "Koto-kotosiki hodo ni ha arumazige nari si wo, hitogara no mameyaka ni wokasiu mo ari si kana!" to, ito ada naru mi-kokoro ha, "Kutiwosiku te yami ni si koto." to, netau obosa ruru mama ni, Womna-Gimi wo mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 「 かう、はかなきことゆゑ、あながちに、かかる筋のもの憎みしたまひけり。思はずに心憂し」 |
「あのように、ちょっとしたことぐらいで、むやみに、このような方面の嫉妬をなさるなあ。思いがけなく情けない」 |
「何でもない恋の遊戯をしようとするくらいのことにもあなたはよく |
"Kau, hakanaki koto yuwe, anagati ni, kakaru sudi no mono-nikumi si tamahi keri. Omoha zu ni kokoro-usi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | と、恥づかしめ怨みきこえたまふ折々は、 いと苦しうて、「 ありのままにや聞こえてまし」と思せど、 |
と、悪口言って恨み申し上げなさる時々は、とてもつらくて、「ありのままに申し上げてしまおうかしら」とお思いになるが、 |
こんなふうにお言いになり、 |
to, hadukasime urami kikoye tamahu wori-wori ha, ito kurusiu te, "Ari no mama ni ya kikoye te masi." to obose do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 「 やむごとなきさまには もてなしたまはざなれど、浅はかならぬ方に、心とどめて 人の隠し置きたまへる人を、物言ひさがなく聞こえ出でたらむにも、さて 聞き過ぐしたまふべき御心ざまにもあらざめり。 |
「重々しい様子にはお扱いなさらないようだが、いいかげんでない扱いに、心とめて人が隠していらっしゃる女を、おしゃべりに申し上げてしまうようなのも、そのまま聞き流しなさるようなご性分の方ではいらっしゃらないようだ。 |
妻の一人としての待遇はしていないにもせよ軽々しい情人とは思わずに愛して、世間の目にはつかぬようにと宇治へ隠してある妹の姫君のことを、お話ししても宮の御性情ではそのままにしてお置きにはなれまい、 |
"Yamgotonaki sama ni ha motenasi tamaha za' nare do, asahaka nara nu kata ni, kokoro todome te hito no kakusi-oki tamahe ru hito wo, monoihi saga-naku kikoye-ide tara m ni mo, sate kiki-sugusi tamahu beki mi-kokoro-zama ni mo ara za' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | さぶらふ人の中にも、はかなうものをものたまひ触れむと思し立ちぬる限りは、 あるまじき里まで尋ねさせたまふ御さまよからぬ 御本性なるに、 さばかり月日を経て、思ししむめるあたりは、 ましてかならず 見苦しきこと取り出でたまひてむ。 他より伝へ聞きたまはむはいかがはせむ。 |
仕えている女房の中でも、ちょっと何かおっしゃり関係を持とうとお思いになった者にはすべて、身分柄あってはならない実家までお尋ねあそばすご体裁の良くないご性分なので、あれほど月日を経ても、お思い込んでいらっしゃるあたりの女は、女房の場合以上にきっと見苦しいことを引き起こしなさるだろう。他から伝え聞きなさるのはどうすることもできない。 |
女房にでもそうした関係を結びたくおなりになった人の所へは無反省にそうした人の実家へまでもお出かけになるような多情さがおありになるのであるから、これはまして相当に月日もたつ今になっても思い込んでお忘れになれない相手であっては、必ず醜い事件をお起こしになるであろう、ほかから聞いておしまいになればそれはしかたがない、 |
Saburahu hito no naka ni mo, hakanau mono wo mo notamahi hure m to obosi-tati nuru kagiri ha, arumaziki sato made tadune sase tamahu ohom-sama yokara nu go-honzyau naru ni, sabakari tukihi wo he te, obosi-simu meru atari ha, masite kanarazu mi-gurusiki koto tori-ide tamahi te m. Hoka yori tutahe kiki tamaha m ha ikagaha se m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | いづ方ざまにもいとほしくこそはありとも、 防ぐべき人の御心ありさまならねば、 よその人よりは聞きにくくなどばかりぞおぼゆべき。とてもかくても、わがおこたりにてはもてそこなはじ」 |
どちらにとってもお気の毒ではあっても、それを防げる方のご性分でないので、他人の場合よりは聞きにくいなどとばかりに思われるだろう。どうなるにせよ、自分からの過失にはするまい」 |
大将のためにも姫君のためにも不幸になるのを知っておいでになっても、それに遠慮のおできになる方ではないから、そうした場合に姫君が他人でない点で、自分は多く恥を覚えることであろう、何にもせよ自分のあやまりから悪いほうへ運命の進む動機は作るまい |
Idu-kata-zama ni mo itohosiku koso ha ari tomo, husegu beki hito no mi-kokoro arisama nara ne ba, yoso no hito yori ha kiki nikuku nado bakari zo oboyu beki. Totemo-kakutemo, waga okotari nite ha motesokonaha zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | と思ひ返したまひつつ、いとほしながらえ聞こえ出でたまはず、 異ざまにつきづきしくは、え言ひなしたまはねば、おしこめてもの怨じしたる、世の常の人になりてぞおはしける。 |
と思い返しなさっては、お気の毒には思うが申し上げなさらず、嘘をついてもっともらしく言いつくろうことは、おできになれないので、黙りとおして嫉妬する、世の常の女になっていらっしゃった。 |
と反省して、宮の恋に同情はしながらも姫君の現在の境遇を語ろうとしなかった。 |
to omohi-kahesi tamahi tutu, itohosi nagara e kikoye-ide tamaha zu, koto-zama ni tuki-dukisiku ha, e ihi-nasi tamaha ne ba, osi-kome te mono-wen-zi si taru, yo no tune no hito ni nari te zo ohasi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 薫、浮舟を宇治に放置 |
1-2 Kaoru leaves Ukifune alone in Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | かの人は、たとしへなくのどかに思しおきてて、「 待ち遠なりと思ふらむ」と、心苦しうのみ思ひやりたまひながら、所狭き身のほどを、さるべきついでなくて、かやしく通ひたまふべき道ならねば、 神のいさむるよりもわりなし ★。されど、 |
あの方は、たとえようもなくのんびりと構えていらっしゃって、「待ち遠しいと思っているだろう」と、お気の毒にはお思いやりになりながら、窮屈な身の上を、適当な機会がなくては、たやすくお通いになれる道ではないので、神が禁じている以上に困っている。けれども、 |
|
Kano hito ha, tatosihe naku nodoka ni obosi-okite te, "Mati-doho nari to omohu ram." to, kokoro-gurusiu nomi omohi-yari tamahi nagara, tokoroseki mi no hodo wo, saru-beki tuide naku te, kayasiku kayohi tamahu beki miti nara ne ba, Kami no isamuru yori mo warinasi. Saredo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 「 今いとよくもてなさむ、とす。山里の慰めと思ひおきてし心あるを、すこし 日数も経ぬべきことども作り出でて、のどやかに行きても見む。さて、しばしは人の知るまじき住み所して、やうやうさる方に、 かの心をものどめおき、わがためにも、人のもどきあるまじく、なのめにてこそよからめ。 |
「いずれはたいそうよく扱ってやろう、と思う。山里の慰めと思っていた考えがあるが、少し日数のかかりそうな事柄を作り出して、のんびりと出かけて行って逢おう。そうして、しばらくの間は誰も知らない住処で、だんだんとそのようなことで、あの女の気持ちも馴れさせて、自分にとっても、他人から非難されないように、目立たぬようにするのがよいだろう。 |
そのうちに自分は十分にその人をいたわる方法を考えている、宇治へ行って見る時に覚える |
"Ima ito yoku motenasa m, to su. Yamazato no nagusame to omohi-oki te si kokoro aru wo, sukosi hi-kazu mo he nu beki koto-domo tukuri-ide te, nodoyaka ni yuki te mo mi m. Sate, sibasi ha hito no siru maziki sumi-dokoro si te, yau-yau saru kata ni, kano kokoro wo mo nodome-oki, waga tame ni mo, hito no modoki arumaziku, nanome nite koso yokara me. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | にはかに、何人ぞ、いつより、など聞きとがめられむも、もの騒がしく、 初めの心に違ふべし。また、 宮の御方の聞き思さむことも、 もとの所を際々しう率て離れ、昔を忘れ顔ならむ、いと本意なし」 |
急に迎えて、誰だろう、いつからだろう、などと取り沙汰されるのも、何となく煩わしく、当初の考えと違ってこよう。また、宮の御方がお聞きになってご心配になることも、もとの場所をきっぱりと離れて連れ出し、昔を忘れてしまったような顔なのも、まことに不本意だ」 |
にわかにだれの娘か、いつからというようなことを私議されるのも煩わしく初めの精神と違ってくる、また二条の院の |
Nihaka ni, nani-bito zo, itu yori, nado kiki togame rare m mo, mono-sawagasiku, hazime no kokoro ni tagahu besi. Mata, Miya no ohom-kata no kiki obosa m koto mo, moto no tokoro wo kiha-gihasiu wi te hanare, mukasi wo wasure-gaho nara m, ito ho'i nasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | など思し静むるも、 例の、のどけさ過ぎたる心からなるべし ★。 渡すべきところ思しまうけて、忍びてぞ造らせたまひける。 |
などと冷静に考えなさるのも、例によって、のんびりと構え過ぎた性分からであろう。引っ越しさせる所をお考えおいて、こっそりと造らせなさるのであった。 |
と思い、恋しい心をおさえているのも、例の恋に |
nado, obosi-sidumuru mo, rei no, nodokesa sugi taru kokoro kara naru besi. Watasu beki tokoro obosi-mauke te, sinobi te zo tukura se tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 薫と中君の仲 |
1-3 A relationship between Kaoru and Naka-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | すこしいとまなきやうにもなりたまひにたれど、宮の御方には、なほたゆみなく心寄せ仕うまつりたまふこと同じやうなり。見たてまつる人もあやしきまで思へれど、 世の中をやうやう思し知り、人のありさまを見聞きたまふままに、「これこそはまことに昔を忘れぬ心長さの、名残さへ浅からぬためしなめれ」と、あはれも少なからず。 |
少し暇がないようにおなりになったが、宮の御方に対しては、やはりたゆまずお心寄せ申し上げなさることは以前と同じようである。拝見する女房も不思議なまでに思っているが、世の中をだんだんとお分かりになってきて、他人の様子を見たり聞いたりなさるにつけて、「この人こそは本当に昔を忘れない心長さが、引き続いて浅くない例のようだ」と、感慨も少なくない。 |
少し心の暇が少なくなったようであるがなお二条の院の夫人に尽くすことは怠らなかった。これを知っている女房などは不思議にも思うのであったが、世の中というものがようやくわかってきた中の君にはこうした薫の誠意が認識できるようになり、これこそ恋した人を死後までも長く忘れない深い愛の例にもすべき志であると哀れを覚えさせられることも少なくないのであった。 |
Sukosi itoma naki yau ni mo nari tamahi ni tare do, Miya-no-Ohomkata ni ha, naho tayumi naku kokoro-yose tukau-maturi tamahu koto onazi yau nari. Mi tatematuru hito mo ayasiki made omohe re do, yononaka wo yau-yau obosi-siri, hito no arisama wo mi kiki tamahu mama ni, "Kore koso ha makoto ni mukasi wo wasure nu kokoro-nagasa no, nagori sahe asakara nu tamesi na' mere." to, ahare mo sukunakara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | ねびまさりたまふままに、人柄もおぼえも、さま殊にものしたまへば、宮の御心のあまり頼もしげなき時々は、 |
成人なさっていくにつれて、人柄も評判も、格別でいらっしゃるので、宮のお気持ちがあまりに頼りなさそうな時には、 |
世の信望を得ていることも多くて、官位の昇進の目ざましい薫であったから、宮があまりにも真心のない態度をお見せになったりする時には、 |
Nebi masari tamahu mama ni, hitogara mo oboye mo, sama koto ni monosi tamahe ba, Miya no mi-kokoro no amari tanomosige naki toki-doki ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 「 思はずなりける宿世かな。 故姫君の思しおきてしままにもあらで、 かくもの思はしかるべき方にしもかかりそめけむよ」 |
「思いもかけなかった運命であったわ。亡き姉君がお考えおいたとおりでもなく、このように悩みの多い結婚をしてしまったことよ」 |
不運な自分である、姉君の心にきめたままにはなっていないで、陰で多くの |
"Omoha zu nari keru sukuse kana! Ko-Hime-Gimi no obosi-oki te si mama ni mo ara de, kaku mono-omohasikaru beki kata ni simo kakari some kem yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | と 思す折々多くなむ。されど、 対面したまふことは難し。 |
とお思いになる時々も多かった。けれども、お会いなさることは難しい。 |
と、こんなことも思われた。けれども逢って話などをすることはもうあまりできないようになっていた。 |
to obosu wori-wori ohoku nam. Saredo, taimen si tamahu koto ha katasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | 年月もあまり昔を隔てゆき、 うちうちの御心を深う知らぬ人は、 なほなほしきただ人こそ、さばかりのゆかり尋ねたる睦びをも忘れぬに、つきづきしけれ、 なかなか、かう限りあるほどに、例に違ひたるありさまも、つつましければ、宮の絶えず思し疑ひたるも、いよいよ苦しう 思し憚りたまひつつ、 おのづから疎きさまになりゆくを、さりとても絶えず、 同じ心の変はりたまはぬなりけり。 |
年月もあまりに昔から遠ざかってきて、内々のご事情を深く知らない女房は、普通の身分の人なら、これくらいの縁者を求めて親交を忘れないのも、ふさわしいが、かえって、このように高い身分では、一般と違った交際も、気がひけるので、宮が絶えずお疑いになっているのも、ますますつらくご遠慮なさりながら、自然と疎遠になってゆくのを、それでも絶えず、同じ気持ちがお変わりにならないのであった。 |
宇治時代と今とはあまりにも年月が隔たり過ぎ、どんな |
Tosi-tuki mo amari mukasi wo hedate yuki, uti-uti no mi-kokoro wo hukau sira nu hito ha, naho-nahosiki tadaudo koso, sabakari no yukari tadune taru mutubi wo mo wasure nu ni, tuki-dukisikere, naka-naka, kau kagiri aru hodo ni, rei ni tagahi taru arisama mo, tutumasikere ba, Miya no tayezu obosi utagahi taru mo, iyo-iyo kurusiu obosi habakari tamahi tutu, onodukara utoki sama ni nari yuku wo, saritote mo tayezu, onazi kokoro no kahari tamaha nu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 宮も、あだなる御本性こそ、見まうきふしも混じれ、若君のいとうつくしうおよすけたまふままに、「 他にはかかる人も出で来まじきにや」と、やむごとなきものに思して、うちとけなつかしき方には、 人にまさりてもてなしたまへば、ありしよりはすこしもの思ひ静まりて過ぐしたまふ。 |
宮も、浮気っぽいご性質は、厭わしいところも混じっているが、若君がとてもかわいらしく成長なさってゆくにつれて、「他にはこのような子も生まれないのではないかしら」と、格別大事にお思いになって、気のおけぬ親しい夫人としては、正室にまさってご待遇なさるので、以前よりは少し悩み事も落ち着いて過ごしていらっしゃる。 |
宮も多情な御性質がわざわいして情けなく夫人をお思わせになるようなことも時々はまじるが若君がかわいく成長してくるのを御覧になっては、他の人から自分の子は生まれないかもしれぬと思召し、夫人を尊重あそばすようになり、隔てのない妻としてはだれよりもお愛しになるため、以前よりは少し物思いをすることの少ない日を中の君は送っていた。 |
Miya mo, ada naru go-honzyau koso, mi-mauki husi mo mazire, Waka-Gimi no ito utukusiu oyosuke tamahu mama ni, "Hoka ni ha kakaru hito mo ide-ku maziki ni ya?" to, yamgotonaki mono ni obosi te, utitoke natukasiki kata ni ha, hito masari te motenasi tamahe ba, arisi yori ha sukosi mono-omohi sidumari te sugusi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 正月、宇治から京の中君への文 |
1-4 At early of January, Ukifune sends a mail to Naka-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 睦月の朔日過ぎたるころ 渡りたまひて、 若君の年まさりたまへるを、もて遊びうつくしみたまふ昼つ方、小さき童、 緑の薄様なる包み文の大きやかなるに、小さき鬚籠を小松につけたる、また、 すくすくしき立文とり添へて、奥なく走り参る。 女君にたてまつれば、宮、 |
正月の上旬が過ぎたころにお越しになって、若君が一つ年齢をおとりになったのを、相手にしてかわいがっていらっしゃる昼ころ、小さい童女が、緑の薄様の包紙で大きいのに、小さい鬚籠を小松に結びつけてあるのや、また、きちんとした立文とを持って、無邪気に走って参る。女君に差し上げると、宮は、 |
正月の元日の過ぎたあとで宮は二条の院へ来ておいでになって、 |
Mutuki no tuitati sugi taru koro watari tamahi te, Waka-Gimi no tosi masari tamahe ru wo, mote-asobi utukusimi tamahu hiru-tu-kata, tihisaki waraha, midori no usuyau naru tutumi-bumi no ohokiyaka naru ni, tihisaki higeko wo komatu ni tuke taru, mata, suku-sukusiki tate-bumi tori-sohe te, aunaku hasiri mawiru. Womna-Gimi ni tatemature ba, Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 「 それは、いづくよりぞ」 |
「それは、どこからのですか」 |
「それはどこからよこしたのか」 |
"Sore ha, iduku yori zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
とお言いになった。 |
to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 「 宇治より大輔のおとどにとて、 もてわづらひはべりつるを、 例の、御前にてぞ御覧ぜむとて、取りはべりぬる」 |
「宇治から大輔のおとどにと言ったが、いないので困っていましたのを、いつものように、御前様が御覧になるだろうと思って、受け取りました」 |
「宇治から |
"Udi yori Taihu-no-Otodo ni tote, mote-wadurahi haberi turu wo, rei no, o-mahe nite zo go-ran-ze m tote, tori haberi nuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | と言ふも、いとあわたたしきけしきにて、 |
と言うのも、とても落ち着きのないふうなので、 |
せかせかと早口で申した。 |
to ihu mo, ito awatatasiki kesiki nite, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 「 この籠は、金を作りて色どりたる籠なりけり。松もいとよう似て作りたる枝ぞとよ」 |
「この籠は、金属で作って色を付けた籠でしたのだわ。松もとてもよく本物に似せて作ってある枝ですよ」 |
「この籠は金の |
"Kono ko ha, kane wo tukuri te iro-dori taru ko nari keri. Matu mo ito you ni te tukuri taru yeda zo to yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | と、笑みて言ひ続くれば、宮も笑ひたまひて、 |
と、笑顔で言い続けるので、宮もにっこりなさって、 |
うれしそうな顔で言うのを御覧になって、宮もお笑いになり、 |
to, wemi te ihi tydukure ba, Miya mo warahi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | 「 いで、我ももてはやしてむ」 |
「それでは、わたしも鑑賞しようかね」 |
「では私もどんなによくできているかを見よう」 |
"Ide, ware mo motehayasi te m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | と召すを、女君、いとかたはらいたく思して、 |
とお取り寄せになると、女君は、とても見ていられない気持ちがなさって、 |
と言い、受け取ろうとあそばされたのを、夫人は困ったことと思い、 |
to mesu wo, Womna-Gimi, ito kataharaitaku obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | 「 文は、大輔がりやれ」 |
「手紙は、大輔のもとにやりなさい」 |
「手紙だけは大輔の所へ持ってお行き」 |
"Humi ha, Taihu-gari yare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | とのたまふ。御顔の赤みたれば、宮、「 大将のさりげなくしなしたる文にや、宇治の名のりもつきづきし」と思し寄りて、この文を取りたまひつ。 |
とおっしゃる。お顔が赤くなっているので、宮は、「大将がさりげなくよこした手紙であろうか、宇治からと名乗るのもいかにもらしい」とお思いつきになって、この手紙をお取りになった。 |
こういう顔が少し赤くなっていたのを宮はお見とがめになり、大将がさりげなくして送って来た |
to notamahu. Ohom-kaho no akami tare ba, Miya, "Daisyau no sarigenaku si nasi taru humi ni ya, Udi no nanori mo tuki-dukisi." to obosi-yori te, kono humi wo tori tamahi tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.12 | さすがに、「 それならむ時に」と思すに、いとまばゆければ、 |
とはいえ、「もし本当にそれであったら」とお思いになると、たいそう気がひけて、 |
さすがにそれであったならどんなことになろう、夫人はどんなに恥じて苦しがるであろうとお思いになると |
Sasuga ni, "Sore nara m toki ni." to obosu ni, ito mabayukere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.13 | 「 開けて見むよ。怨じやしたまはむとする」 |
「開けてみますよ。お恨みになりますか」 |
「あけて私が読みますよ。恨みますか、あなたは」 |
"Ake te mi m yo! Wen-zi ya si tamaha m to suru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.14 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
とお言いになると、 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.15 | 「 見苦しう。何かは、その女どちのなかに書き通はしたらむうちとけ文をば、御覧ぜむ」 |
「みっともありません。どうして、女房どうしの間でやりとりしている気を許した手紙を、御覧になるのでしょう」 |
「そんなもの、女房どうしで書き合っています平凡な手紙などを御覧になってもおもしろくも何ともないでしょう」 |
"Migurusiu. Nani-kaha, sono womna-doti no naka ni kaki kayohasi tara m utitoke-bumi wo ba, go-ran-ze m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.16 | とのたまふが、 騒がぬけしきなれば、 |
とおしゃるが、あわてない様子なので、 |
夫人は騒がぬふうであった。 |
to notamahu ga, sawaga nu kesiki nare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.17 | 「 さは、見むよ。女の文書きは、いかがある」 |
「それでは、見ますよ。女性の手紙とは、どんなものかな」 |
「じゃあ見よう。女仲間の手紙にはどんなことが書かれてあるものだろう」 |
"Saha, mi m yo. Womna no humi-gaki ha, ikaga aru?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.18 | とて開けたまへれば、 いと若やかなる手にて、 |
と言ってお開けになると、とても若々しい筆跡で、 |
とお言いになり、あけてお見になると、若々しい字で、 |
tote ake tamahe re ba, ito wakayaka naru te nite, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.19 | 「 おぼつかなくて、年も暮れはべりにける。 山里のいぶせさこそ、峰の霞も絶え間なくて」 |
「ご無沙汰のまま、年も暮れてしまいました。山里の憂鬱さは、峰の霞も絶え間がなくて」 |
その後お目にかかることもできませんままで年も暮れたのでございました。山里は寂しゅうございます。峰から |
"Obotukanaku te, tosi mo kure haberi ni keru. Yamazato no ibusesa koso, mine no kasumi mo tayema naku te." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.20 | とて、端に、 |
とあって、端の方に、 |
などとある奥に、 |
tote, hasi ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.21 | 「 これも若宮の御前に。あやしうはべるめれど」 |
「これも若宮様の御前に。不出来でございますが」 |
これを若君に差し上げます。つまらぬものでございますが。 |
"Kore mo Waka-Miya no go-zen ni. Ayasiu haberu mere do." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.22 | と書きたり。 |
と書いてある。 |
と書いてある。 |
to kaki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 匂宮、手紙の主を浮舟と察知す |
1-5 Niou-no-miya recognizes that the mail was written by Ukifune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | ことにらうらうじきふしも見えねど、おぼえなき、御目立てて、 この立文を見たまへば、げに女の手にて、 |
特に才気があるようには見えないが、心当たりがないので、お目を凝らして、この立文を御覧になると、なるほど女性の筆跡で、 |
ことに貴女らしいふうも見えぬ手紙ではあるが、心当たりのおありにならぬために、また立文のほうを御覧になると、いかにも女房らしい字で、 |
Koto ni rau-rauziki husi mo miye ne do, oboye naki, ohom-me tate te, kono tate-bumi wo mi tamahe ba, geni womna no te nite, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 「 年改まりて、何ごとかさぶらふ。 御私にも、いかにたのしき御よろこび多くはべらむ。 |
「年が改まりましたが、いかがお過しでしょうか。あなた様ご自身におかれましても、どんなに楽しくお喜びが多いことでございましょう。 |
新年になりまして、そちら様はいかがでいらっしゃいますか。御主人様、また皆様がたにもお喜びの多い春かと存じ上げます。 |
"Tosi aratamari te, nani-goto ka saburahu? Ohom-watakusi ni mo, ikani tanosiki ohom-yorokobi ohoku habera m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | ここには、いとめでたき御住まひの心深さを、 なほ、ふさはしからず見たてまつる。かくてのみ、つくづくと 眺めさせたまふよりは、 時々は渡り参らせたまひて、御心も慰めさせたまへ、と思ひはべるに、つつましく恐ろしきものに 思しとりてなむ、もの憂きことに嘆かせたまふめる。 |
こちらでは、とても結構なお住まいで行き届いておりますが、やはり、不似合いに存じております。こうしてばかり、つくづくと物思いにお耽りあそばすより他には、時々そちらにお伺いなさって、お気持ちをお慰めあそばしませ、と存じておりますが、気がねして恐ろしい所とお思いになって、嫌なこととお嘆きになっているようです。 |
ここはごりっぱな風流なお |
Koko ni ha, ito medetaki ohom-sumahi no kokoro-hukasa wo, naho, husahasikara zu mi tatematuru. Kaku-te nomi, tuku-duku to nagame sase tamahu yori ha, toki-doki ha watari mawirase tamahi te, mi-kokoro mo nagusame sase tamahe, to omohi haberu ni, tutumasiku osorosiki mono ni obosi tori te nam, mono-uki koto ni nageka se tamahu meru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
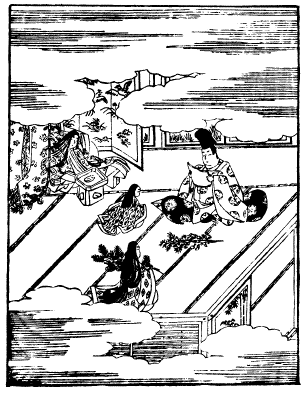 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 若宮の御前にとて、卯槌まゐらせたまふ。 大き御前の御覧ぜざらむほどに、御覧ぜさせたまへ、とてなむ」 |
若宮の御前にと思って、卯槌をお贈り申し上げなさいます。ご主人様が御覧にならない時に御覧下さいませ、とのことでございます」 |
若君様へこちらから |
Waka-Miya no o-mahe ni tote, uduti mawirase tamahu. Ohoki o-mahe no go-ran-ze zara m hodo ni, go-ran-ze sase tamahe, tote nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | と、こまごまと 言忌もえしあへず、もの嘆かしげなるさまのかたくなしげなるも、うち返しうち返し、あやしと御覧じて、 |
と、こまごまと言忌もできずに、もの悲しい様子が見苦しいのにつけても、繰り返し繰り返し、変だと御覧になって、 |
こまごまと、年の初めの縁起も忘れて、主人のことを哀訴している、かたくならしい心も見える手紙を、宮は何度となく読んで御覧になり、怪しく思召して、 |
to, koma-goma to koto-imi mo e si-ahe zu, mono-nagekasige naru sama no katakunasige naru mo, uti-kahesi uti-kahesi, ayasi to go-ran-zi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | 「 今は、のたまへかし。誰がぞ」 |
「今はもう、おっしゃいなさい。誰からのですか」 |
「もう言ってもいいでしょう、だれの手紙ですか」 |
"Ima ha, notamahe kasi. Taga zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | とのたまへば、 |
とお尋ねになると、 |
と夫人へお言いになった。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.8 | 「 昔、かの山里にありける人の娘の、さるやうありて、このころかしこにあるとなむ聞きはべりし」 |
「昔、あの山里に仕えておりました女の娘が、ある事情があって、最近あちらにいると聞きました」 |
「以前あの山荘にいました人の娘が、訳があってこのごろあそこにいるということを聞いていました。それでしょう」 |
"Mukasi, kano yamazato ni ari keru hito no musume no, saru yau ari te, kono-koro kasiko ni aru to nam kiki haberi si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.9 | と聞こえたまへば、おしなべて仕うまつるとは見えぬ文書きを心得たまふに、 かのわづらはしきことあるに思し合はせつ。 |
と申し上げなさると、普通にお仕えする女とは見えない書き方を心得ていらっしゃるので、あの厄介なことがあると書いてあったのでお察しになった。 |
この答えをお聞きになった宮は、普通の二人の女房が同じ階級の者として一人のことの言われてある文章でもないし、めんどうが起こったと書いてあるのは、あの時のことをさして言うに違いないとお悟りになった。 |
to kikoye tamahe ba, osinabete tukau-maturu to ha miye nu humi-gaki wo kokoro-e tamahu ni, kano wadurahasiki koto aru ni obosi ahase tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10 | 卯槌をかしう、つれづれなりける人のしわざと見えたり。またぶりに、山橘作りて、貫き添へたる枝に、 |
卯槌が見事な出来で、所在ない人が作った物だと見えた。松の二股になったところに、山橘を作って、それを貫き通した枝に、 |
卯槌が美しい細工で作られてあるのは、 |
Uduti wokasiu, ture-dure nari keru hito no siwaza to miye tari. Mataburi ni, yama-tatibana tukuri te, turanuki sohe taru yeda ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.11 | 「 まだ古りぬ物にはあれど君がため |
「まだ古木にはなっておりませんが、若君様のご成長を |
まだふりぬものにはあれど君がため |
"Mada huri nu mono ni ha are do Kimi ga tame |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.12 | 深き心に待つと知らなむ」 |
心から深くご期待申し上げております」 |
深き心にまつとしらなん |
hukaki kokoro ni matu to sira nam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.13 | と、ことなることなきを、「 かの思ひわたる人のにや」と思し寄りぬるに、御目とまりて、 |
と、特にたいした歌でないなので、「あのずっと思い続けている女のか」とお思いになると、お目が止まって、 |
こんな平凡な歌であったが、常に心にかかっている人の作であるかもしれぬということで興味をお覚えになった。 |
to, koto naru koto naki wo, "Kano omohi wataru hito no ni ya?" to obosi-yori nuru ni, ohom-me tomari te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.14 | 「 返り事したまへ。情けなし。隠いたまふべき文にもあらざめるを。など、御けしきの悪しき。 まかりなむよ」 |
「お返事をなさい。返事しなくては情愛がない。隠さなければならない手紙でもあるまいに。どうして、ご機嫌が悪いのですか。去りましょうよ」 |
「返事を書いてあげなさい。無情じゃありませんか。隠す必要もない手紙を私が見ただけだのに、なぜ |
"Kaheri-goto si tamahe. Nasakenasi. Kakui tamahu beki humi ni mo ara za' meru wo. Nado, mi-kesiki no asiki? Makari na m yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.15 | とて、立ちたまひぬ。女君、 少将などして、 |
と言って、お立ちになった。女君は、少将などに向かって、 |
こんな言葉を残して宮は夫人の居間から出てお行きになった。中の君は少将などに、 |
tote, tati tamahi nu. Womna-Gimi, Seusyau nado site, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.16 | 「 いとほしくもありつるかな。幼き人の取りつらむを、 人はいかで見ざりつるぞ」 |
「お気の毒なことになってしまいましたね。幼い童女が受け取ったのを、他の女房はどうして気づかなかったのでしょう」 |
「宮様に見られてしまって、あの人がかわいそうだったね。小さい子が使いから受け取ったのだろうけれど、だれも気がつかなかったのかねえ」 |
"Itohosiku mo ari turu kana! Wosanaki hito no tori tu ram wo, hito ha ikade mi zari turu zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.17 | など、忍びてのたまふ。 |
などと、小声でおっしゃる。 |
ひそかにこんなことを言っていた。 |
nado, sinobi te notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.18 | 「 見たまへましかば、いかでかは、参らせまし。すべて、この子は心地なうさし過ぐしてはべり。生ひ先見えて、 人は、おほどかなるこそをかしけれ」 |
「拝見しましたら、どうして、こちらへお届けしたりしましょうか。ぜんたい、この子は思慮が浅く出過ぎています。将来性がうかがえて、女の子は、おっとりとしているのが好ましいものです」 |
「私どもが気がついておりましたなら、どうして持たせて差し上げなどするものでございますか、全体この子はあさはかに出過ぎる子でございます。将来のことは子供の時を見てよく想像されるものですが、おっとりとしています子には見込みがございますけれど」 |
"Mi tamahe masika ba, ikade kaha, mawira se masi. Subete, kono ko ha kokotinau sasi-sugusi te haberi. Ohi-saki miye te, hito ha, ohodoka naru koso wokasikere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.19 | など憎めば、 |
などと叱るので、 |
などと憎むのを見て、 |
nado nikume ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.20 | 「 あなかま。幼き人、な腹立てそ」 |
「お静かに。幼い子を、叱りなさいますな」 |
「まあそんなに言わないでね。子供に腹をたてるものではない」 |
"Anakama! Wosanaki hito, na hara-tate so." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.21 | とのたまふ。 去年の冬、人の参らせたる童の、顔はいとうつくしかりければ、宮もいとらうたくしたまふなりけり。 |
とおっしゃる。去年の冬、ある人が奉公させた童女で、顔がとてもかわいらしかったので、宮もとてもかわいがっていらっしゃるのだった。 |
と夫人は制した。去年の冬にある人から童女として奉公させた子であるが、顔のきれいなために宮もかわいがっておいでになった。 |
to notamahu. Kozo no huyu, hito no mawirase taru waraha no, kaho ha ito utukusikari kere ba, Miya mo ito rautaku si tamahu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 第六段 匂宮、大内記から薫と浮舟の関係を知る |
1-6 Niou-no-miya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1 | わが御方におはしまして、 |
ご自分のお部屋にお帰りになって、 |
御自身の居間のほうへおいでになった宮は、 |
Waga ohom-kata ni ohasimasi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | 「 あやしうもあるかな。宇治に大将の通ひたまふことは、年ごろ絶えずと聞くなかにも、 忍びて夜泊りたまふ時もあり、と人の言ひしを、いとあまりなる 人の形見とて、さるまじき所に旅寝したまふらむこと、と思ひつるは、かやうの人隠し置きたまへるなるべし」 |
「不思議なことであったな。宇治に大将がお通いになることは、何年も続いていると聞いていた中でも、こっそりと夜お泊まりになる時もある、と人が言ったが、実にあまりな故人の思い出の土地だからとて、とんでもない所に旅寝なさるのだろうこと、と思ったのは、あのような女を隠して置きなさったからなのだろう」 |
不思議なことでないか、あれからのちも宇治へ行くことを大将はやめないと聞いていたが、そっと泊まる夜もあると人が言った時に、深い恋をした人の面影の残る山荘だからといっても、ああした所に宿泊までするのかと思ったのは、こうした新しい情人を隠していたためなのであろう |
"Ayasiu mo aru kana! Udi ni Daisyau no kayohi tamahu koto ha, tosi-goro taye zu to kiku naka ni mo, sinobi te yoru tomari tamahu toki mo ari, to hito no ihi si wo, ito amari naru hito no katami tote, sarumaziki tokoro ni tabine si tamahu ram koto, to omohi turu ha, kayau no hito kakusi-oki tamahe ru naru besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | と思し得ることもありて、 御書のことにつけて使ひたまふ大内記なる人の、 かの殿に親しき たよりあるを思し出でて、御前に召す。参れり。 |
と合点なさることもあって、ご学問のことでお使いになる大内記である者で、あちらの邸に親しい縁者がいる者を思い出しなさって、御前にお召しになる。参上した。 | と、思い合わされることもおありになって、学問のほうの用で自邸でもお使いになる大内記が、薫の家の人によるべのあることをお思い出しになり、居間へお呼びになった。 |
to obosi-uru koto mo ari te, ohom-humi no koto ni tuke te tukahi tamahu Dainaiki naru hito no, kano Tono ni sitasiki tayori aru wo obosi-ide te, o-mahe ni mesu. Mawire ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.4 | 「 韻塞すべきに ★、集ども選り出でて、こなたなる厨子に積むべきこと」 |
「韻塞をしたいのだが、詩集などを選び出して、こちらにある厨子に積むように」 |
|
"Win-hutagi subeki ni, sihu-domo eri-ide te, konata naru dusi ni tumu beki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.5 | などのたまはせて、 |
などとお命じになって、 |
などをお命じになったあとで、 |
nado notamahase te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.6 | 「 右大将の宇治へいますること、なほ絶え果てずや。寺をこそ、いとかしこく造りたなれ。いかでか見るべき」 |
「右大将が宇治へ行かれることは、相変わらず続いていますか。寺を、とても立派に造ったと言うね。何とか見られないかね」 |
「右大将が宇治へ行かれることは今でも同じかね。寺をりっぱに作ったそうだね。一度見たいものだ」 |
"U-Daisyau no Udi he imasuru koto, naho taye-hate zu ya? Tera wo koso, ito kasikoku tukuri ta' nare. Ikadeka miru beki?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.7 | とのたまへば、 |
とおっしゃると、 |
こんな話をおしかけになった。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.8 | 「 寺いとかしこく、いかめしく造られて、不断の三昧堂など、いと尊くおきてられたり、 となむ聞きたまふる。通ひたまふことは、去年の秋ごろよりは、ありしよりも、しばしばものしたまふなり。 |
「寺をたいそう立派に、荘厳にお造りになって、不断の三昧堂など、大変に尊くお命じになった、と聞いております。お通いになることは、去年の秋ごろからは、以前よりも、頻繁に行かれると言います。 |
「たいへんなものでございます。不断の |
"Tera ito kasikoku, ikamesiku tukurare te, hu-dan no sammai-dau nado, ito tahutoku okite rare tari, to nam kiki tamahuru. Kayohi tamahu koto ha, kozo no aki-goro yori ha, ari-si yori mo, siba-siba monosi tamahu nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.9 | 下の人びとの忍びて申ししは、『女をなむ隠し据ゑさせたまへる、けしうはあらず思す人なるべし。あのわたりに領じたまふ所々の人、皆仰せにて参り仕うまつる。宿直にさし当てなどしつつ、京よりもいと忍びて、さるべきことなど問はせたまふ。いかなる幸ひ人の、さすがに心細くてゐたまへるならむ』となむ、ただこの師走のころほひ申す、と聞きたまへし」 |
下々の人びとがこっそりと申した話では、『女を隠し据えていらっしゃり、憎からずお思いになっている女なのでしょう。あの近辺に所領なさる所々の人が、皆ご命令に従ってお仕えしております。宿直を担当させたりしては、京からもたいそうこっそりと、しかるべき事などお尋ねになります。どのような幸い人で、幸せながらも心細くおいでなのでしょう』と、ちょうどこの十二月のころに申していた、とお聞き致しました」 |
下の者のそっと申しておりますのを聞きますと、愛人を隠しておいておありになるようでございます。かなり大事にしていられる人らしゅうございます。大将のあのへんのあちらこちらの荘園の者が皆仰せで山荘の御用を勤めております。代る代る |
Simo no hito-bito no sinobi te mausi si ha, 'Womna wo nam kakusi suwe sase tamahe ru, kesiu ha ara zu obosu hito naru besi. Ano watari ni ryau-zi tamahu tokoro-dokoro no hito, mina ohose nite mawiri tukau-maturu. Tonowi ni sasi-ate nado si tutu, kyau yori mo ito sinobi te, saru-beki koto nado tohase tamahu. Ika naru saihahi-bito no, sasuga ni kokoro-bosoku te wi tamahe ru nara m?' to nam, tada kono Sihasu no korohohi mausu, to kiki tamahe si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.10 | と聞こゆ。 |
と申し上げる。 |
と大内記は言った。 |
to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 第七段 匂宮、薫の噂を聞き知り喜ぶ |
1-7 Niou-no-miya is glad of hearing the information about Kaoru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.1 | 「 いとうれしくも聞きつるかな」と思ほして、 |
「とても嬉しいことを聞いたなあ」とお思いになって、 |
すべてがこれで明らかになったと宮はお喜びになった。 |
"Ito uretaku mo kiki turu kana!" to omohosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.2 | 「 たしかにその人とは、言はずや。かしこにもとよりある尼ぞ、訪らひたまふと聞きし」 |
「はっきりと名前を、言わなかったか。あちらに以前から住んでいた尼を、お訪ねになると聞いていたが」 |
「どういう人と言っていなかったかね、あの山荘にもとからいる尼のめんどうを大将は見てやっていると聞いたが、そのまちがいではないだろうね」 |
"Tasika ni sono hito to ha, iha zu ya? Kasiko ni motoyori aru Ama zo, toburahi tamahu to kiki si." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.3 | 「 尼は、廊になむ住みはべるなる。 この人は、今建てられたるになむ、きたなげなき女房などもあまたして、口惜しからぬけはひにてゐてはべる」 |
「尼は、渡廊に住んでおりますと言います。この女は、今度建てられた所に、こぎれいな女房なども大勢して、結構な具合で住んでおります」 |
「尼さんは廊の座敷に住んでおります。その方は今度建ちました御殿のほうに、きれいな女房などもたくさん使って、品よく住んでおいでになるようでございます」 |
"Ama ha, rau ni nam sumi haberu naru. Kono hito ha, ima tate rare taru ni nam, kitanage naki nyoubau nado mo amata site, kutiwosikara nu kehahi nite wi te haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.4 | と聞こゆ。 |
と申し上げる。 |
to kikoyu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.5 | 「 をかしきことかな。何心ありて、いかなる人をかは、さて据ゑたまひつらむ。なほ、いとけしきありて、なべての人に似ぬ御心なりや。 |
「興味深いことだね。どのような考えがあって、どのような女を、そのように据えていらしゃるのだろうか。やはり、とても好色なところがあって、普通の人と似ていないお心なのだろうか。 |
「おもしろい話だね、どういうつもりで、どこの婦人をそうして隠しているのだろう。なんといってもあの人のすることは特色があるね、 |
"Wokasiki koto kana! Nani-gokoro ari te, ika naru hito wo kaha, sate suwe tamahi tu ram? Naho, ito kesiki ari te, nabete no hito ni ni nu mi-kokoro nari ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.6 | 右の大臣など、『 この人のあまりに道心に進みて、山寺に、夜さへともすれば泊りたまふなる、軽々し』ともどきたまふと聞きしを、げに、などかさしも仏の道には忍びありくらむ。なほ、かの故里に心をとどめたると聞きし、かかること こそはありけれ。 |
右大臣などが、『この人があまりに仏道に進んで、山寺に、夜までややもすればお泊まりになるというが、軽々しい行為だ』と非難なさると聞いたが、なるほど、どうしてそんなにも仏道にこっそり行かれるのだろう。やはり、あの思い出の地に心を惹かれていると聞いたが、このようなわけがあったのだ。 |
左大臣などはあの人があまりに宗教に傾き過ぎて、山の寺などに夜さえも泊まることをするのは、身分柄軽率な |
Migi-no-Otodo nado, 'Kono hito no amari ni dausin ni susumi te, yama-dera ni, yoru sahe tomo-sure-ba tomari tamahu naru, karo-garosi.' to modoki tamahu to kiki si wo, geni, nadoka sasimo Hotoke no miti ni ha sinobi-ariku ram? Naho, kano hurusato ni kokoro wo todome taru to kiki si, kakaru koto koso ha ari kere. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.7 | いづら、人よりはまめなるとさかしがる人しも、ことに人の思ひいたるまじき隈ある構へよ」 |
どうだ、誰よりも真面目だと分別顔をする人の方がかえって、ことさら誰も考えつかないようなところがあるものだよ」 |
だれよりも自分はまじめな人間であると |
Idura, hito yori ha mame naru to sakasigaru hito simo, koto ni hito no omohi-itaru maziki kuma aru kamahe yo!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.8 | とのたまひて、いとをかしと思いたり。この人は、かの殿にいと睦ましく仕うまつる家司の婿になむありければ、 隠したまふことも 聞くなるべし。 |
とおっしゃって、たいそうおもしろいとお思いになった。この人は、あちらの邸でたいそう親しくお仕えしている家司の婿であったので、隠していらっしゃることも聞いたのであろう。 |
と宮はおかしそうにお言いになった。大内記は右大将の家に古くから使っている |
to notamahi te, ito wokasi to oboi tari. Kono hito ha, kano Tono ni ito mutumasiku tukau-maturu keisi no muko ni nam ari kere ba, kakusi tamahu koto mo kiku naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.9 | 御心の内には、「 いかにして、この人を、見し人かとも見定めむ。 かの君の、さばかりにて据ゑたるは、なべてのよろし人にはあらじ。 このわたりには、いかで疎からぬにかはあらむ。 心を交はして隠したまへりけるも、いとねたう」おぼゆ。 |
ご心中では、「何とかして、この女を、前に会ったことのある女かどうか確かめたい。あの君が、あのように据えているのは、平凡で普通の女ではあるまい。こちらでは、どうして親しくしているのだろう。しめし合わせて隠していらっしゃったというのも、とても悔しい」と思われる。 |
宮のお心の中では、どんな策を用いてその |
Mi-kokoro no uti ni ha, "Ikani si te, kono hito wo, mi si hito ka to mo mi sadame m. Kano Kimi no, sa-bakari nite suwe taru ha, nabete no yorosi-bito ni ha ara zi. Kono watari ni ha, ikade utokara nu ni kaha ara m. Kokoro wo kahasi te kakusi tamahe ri keru mo, ito netau" oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 4/30/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 4/30/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 4/30/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/9/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経