50 東屋(大島本) |
ADUMAYA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の大納言時代 二十六歳秋八月から九月までの物語 |
Tale of Kaoru's Dainagon era, from August to September at the age of 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第二章 浮舟の物語 京に上り、匂宮夫妻と左近少将を見比べる |
2 Tale of Ukifune Ukifune's mother compares Niou-no-miya with Sakon-shosho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 第一段 浮舟の母と乳母の嘆き |
2-1 Ukifune's mother and her wet nurse are disappointed in cancellation of marriage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | こなたに渡りて見るに、いとらうたげにをかしげにて居 たまへるに、「さりとも、人には劣りたまはじ」とは思ひ慰む。乳母と二人、 |
こちらに来てみると、たいそうかわいらしい様子で座っていらっしゃるので、「不縁になったとはいっても、誰にもお負けになるまい」と気持ちを慰める。乳母と二人で、 |
姫君の所へ行ってみると、 |
Konata ni watari te miru ni, ito rautage ni wokasige nite wi tamahe ru ni, "Sari-tomo, hito ni ha otori tamaha zi." to ha omohi nagusamu. Menoto to hutari, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 「 心憂きものは人の心なりけり。 おのれは、 同じごと思ひ扱ふとも、 この君のゆかりと思はむ人のためには、命をも譲りつべくこそ思へ、親なしと聞きあなづりて、まだ幼くなりあはぬ人を、 さし越えて、かくは 言ひなるべしや。 |
「いやなものは人の心ですこと。わたくしは、同じようにお世話していても、この姫君が婿殿と思うお方のためには、命に代えてもと思っても、父親がいないと聞いて馬鹿にし、まだ十分に成人していない妹を、姉をさしおいて、このように言うものでしょうか。 |
「いやなものは人の心だね。私は同じようにだれも娘と思って世話をしているものの、この方と縁を結ぶ人には命までも譲りたい気でいるのだのに、父親がないと聞いて、 |
"Kokoro-uki mono ha hito no kokoro nari keri. Onore ha, onazi goto omohi atukahu tomo, kono Kimi no yukari to omoha m hito no tame ni ha, inoti wo mo yuduri tu beku koso omohe, oya nasi to kiki anaduri te, mada wosanaku nari aha nu hito wo, sasi-koye te, kaku ha ihi naru besi ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | かく心憂く、 近きあたりに見じ聞かじと思ひぬれど、守のかくおもだたしきことに思ひて、受け取り騒ぐめれば、 あひあひにたる世の人のありさまを、すべてかかることに口入れじと思ふ。いかでここならぬ所に、しばしありにしがな」 |
こんなに情けない、同じ家の中で見まい聞くまいと思っていたが、介がこのように面目がましいことと思って、承知して騒いでいるようなので、どちらもお似合いの様子なので、いっさいこの話には口を入れまいと思います。何とかここではない所で、しばらく暮らしたいものだ」 |
そんな人をまた婿にすることなどは絶対にもう私はいやだけれど、守が名誉に思って大騒ぎしているのを見ると、それがちょうど似合いの |
Kaku kokoro-uku, tikaki atari ni mi zi kika zi to omohi nure do, Kami no kaku omodatasiki koto ni omohi te, uketori sawagu mere ba, ahi ahi ni taru yo no hito no arisama wo, subete kakaru koto ni kuti ire zi to omohu. Ikade koko nara nu tokoro ni, sibasi ari ni si gana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | とうち嘆きつつ言ふ。乳母もいと腹立たしく、「 わが君をかく落としむること」と思ふに、 |
と泣きながら言う。乳母もひどく腹が立って、「自分の主人をこのように見下していること」と思うと、 |
こう歎きながら言うのであった。乳母も腹がたってならない。姫君が軽蔑されたと思うからである。 |
to uti-nageki tutu ihu. Menoto mo ito hara-datasiku, "Waga Kimi wo kaku otosimuru koto." to omohu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | 「 何か、これも御幸ひにて違ふこととも知らず。かく心口惜しくいましける 君なれば、あたら御さまをも見知らざらまし。 わが君をば、心ばせあり、もの思ひ知りたらむ人にこそ、見せたてまつらまほしけれ。 |
「なあに、これもご幸運なことで破談になったのかも知れません。あのように情けない方でいらっしゃるのだから、もったいない姫君の美しいご様子をご存知ないのでしょう。大事な姫君は、思慮もあり、道理の分かる方にこそ、差し上げたいものです。 |
「いいのですよ奥様。これも結局お姫様の御運が強かったから、あの人と結婚をなさらないで済むことになったのですよ。そんな人にはこの方の |
"Nanika, kore mo ohom-saihahi nite tagahu koto to mo sira zu. Kaku kokoro kutiwosiku imasi keru Kimi nare ba, atara ohom-sama wo mo mi-sira zara masi. Waga Kimi wo ba, kokorobase ari, mono omohi siri tara m hito ni koso, mise tatematura mahosikere. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | 大将殿の御さま容貌の、ほのかに見たてまつりしに、さも命延ぶる心地のしはべりしかな。 あはれにはた聞こえたまふなり。御宿世にまかせて、思し寄りねかし」 |
大将殿のお姿や器量を、ちらっと拝見しましたが、ほんとうに寿命が延びるような気持ちしましたね。嬉しいことにお世話申し上げたいとおっしゃっています。ご運勢にまかせて、そのようにお決めなさいまし」 |
源右大将様の御 |
Daisyau-dono no ohom-sama katati no, honoka ni mi tatematuri si ni, samo inoti noburu kokoti no si haberi si kana! Ahare ni hata kikoye tamahu nari. Ohom-sukuse ni makase te, obosi-yori ne kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7 | と言へば、 |
と言うと、 |
to ihe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8 | 「 あな、恐ろしや。 人の言ふを聞けば、年ごろ、 おぼろけならむ人をば見じとのたまひて、 右の大殿、 按察使大納言、 式部卿宮などの、いとねむごろに ほのめかしたまひけれど、聞き過ぐして、 帝の御かしづき女を得たまへる君は、 いかばかりの ★人かまめやかには 思さむ。 |
「まあ、恐ろしいこと。人の言うことを聞くと、長年、並大抵の女とは結婚しまいとおっしゃって、右の大殿や按察使大納言、式部卿宮などが、とても熱心にお申し込みなさったが、聞き流して、帝が大切にしている姫宮を得なさった君は、どれほどの人を熱心にお思いになりましょうか。 |
「まあ恐ろしい。人の話に聞くと、長い間すぐれた女性とでなければ結婚をしないとお言いになって、左大臣、 |
"Ana, osorosi ya! Hito no ihu wo kike ba, tosi-goro, oboroke nara m hito wo ba mi zi to notamahi te, Migi-no-Ohotono, Azeti-no-Dainagon, Sikibukyau-no-Miya nado no, ito nemgoro ni honomekasi tamahi kere do, kiki-sugusi te, Mikado no ohom-kasiduki musume wo e tamahe ru Kimi ha, ika-bakari no hito ka mameyaka ni ha obosa m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.9 | かの母宮などの御方にあらせて、時々も見むとは思しもしなむ、 それはた、げにめでたき御あたりなれども、いと 胸痛かるべきことなり。 宮の上の、かく幸ひ人と申すなれど、 もの思はしげに思したるを見れば、いかにもいかにも、二心なからむ人のみこそ、めやすく頼もしきことにはあらめ。 わが身にても知りにき。 |
あの母宮などのお側におかせて、時々は会おうとはお思いになろうが、それもまた、なるほど結構なお所ですが、とても胸の痛いことです。宮の上が、このように幸い人と申し上げるようだが、物思いがちにいらっしゃるのを見ると、いかにもいかにも、二心のない人だけが、安心で信頼できることでしょう。自分の体験でも分かりました。 |
あのお母様の尼宮の女房にして時々は愛してやろうとは思ってくださるだろうがね。それはごりっぱな所だけれど、そんな関係に置かれているのは苦しいものだからね。二条の院の奥様を幸福な方だと人は申しているけれど、やはり物思いのやむ間もないふうでおありになるのを見ると、どんな人でもいいから唯一の妻として愛してくださる |
Kano Haha-Miya nado no ohom-kata ni ara se te, toki-doki mo mi m to ha obosi mo si na m, sore hata, geni medetaki ohom-atari nare domo, ito mune itakaru beki koto nari. Miya-no-Uhe no, kaku saihahi-bito to mausu nare do, mono-omohasige ni obosi taru wo mire ba, ikani-mo-ikani-mo, huta-gokoro nakara m hito nomi koso, meyasuku tanomosiki koto ni ha ara me. Waga mi nite mo siri ni ki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.10 | 故宮の御ありさまは ★、いと情け情けしく、めでたくをかしくおはせしかど、 人数にも思さざりしかば、いかばかりかは心憂くつらかりし。 このいと言ふかひなく、情けなく、さま悪しき人なれど、ひたおもむきに二心なきを見れば、心やすくて年ごろをも過ぐしつるなり。 |
故宮のご様子は、とても情愛があって、素晴らしく好感が持てるお方でしたが、人並みにもお思いくださらなかったので、どんなにかつらい思いをしたことか。この介はまことに取るに足らない、情けない、不恰好な人ですが、一途で二心のないのを見ると、気を揉むこともなく何年も過ごしてきたのです。 |
お |
Ko-Miya no ohom-arisama ha, ito nasake-nasakesiku, medetaku wokasiku ohase sika do, hito-kazu ni mo obosa zari sika ba, ika-bakari kaha kokoro-uku turakari si. Kono ito ihukahinaku, nasakenaku, sama asiki hito nare do, hita-omomuki ni huta-gokoro naki wo mire ba, kokoro-yasuku te tosi-goro wo mo sugusi turu nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.11 | をりふしの心ばへの、かやうに愛敬なく用意なきこと こそ憎けれ、嘆かしく恨めしきこともなく、かたみにうちいさかひても、心にあはぬことをばあきらめつ。上達部、親王たちにて、みやびかに心恥づかしき人の御あたりといふとも、わが数ならでは甲斐あらじ。 |
折々の仕打ちが、あのように癪な思いやりのないのが憎らしいが、嘆かわしく恨めしいこともなく、お互いに言い合っても、納得できないことははっきりさせました。上達部や、親王方で、優雅で心恥ずかしい方の所といっても、わたしのように一人前でない身分では詮のないことでしょう。 |
何かの時に今度のような、ぶしつけな、 |
Wori-husi no kokorobahe no, kayau ni aigyau naku youi naki koto koso nikukere, nagekasiku uramesiki koto mo naku, katami ni uti-isakahi te mo, kokoro ni aha nu koto wo ba akirame tu. Kamdatime, Miko-tati nite, miyabika ni kokoro-hadukasiki hito no ohom-atari to ihu tomo, waga kazu nara de ha kahi ara zi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.12 | よろづのこと、わが身からなりけりと思へば、よろづに悲しうこそ 見たてまつれ。いかにして、人笑へならずしたてたてまつらむ」 |
万事が、わが身分からであった思うと、何もかも悲しく拝見される。何とかして、物笑いにならないようにして差し上げよう」 |
すべてのことは自身の世間的価値によって |
Yorodu no koto, waga mi kara nari keri to omohe ba, yorodu ni kanasiu koso mi tatemature. Ikani si te, hito-warahe nara zu sitate tatematura m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.13 | と語らふ。 |
と相談する。 |
二人は姫君の将来のことをいろいろと相談し合った。 |
to katarahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 第二段 継父常陸介、実娘の結婚の準備 |
2-2 Hitachi-no-suke prepares his daughter's marriage with Sakon-shosho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 守は急ぎたちて、 |
介は急いで準備して、 |
|
Kami ha isogi-tati te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 「 女房など、 こなたにめやすきあまたあなるを、 このほどは、あらせたまへ。 やがて、帳なども新しく仕立てられためる方を、事にはかになりにためれば、取り渡し、 とかく改むまじ」 |
「女房など、こちらに無難な者が大勢いるので、当座の間、回してください。そのまま、帳台なども新調されたようなのをも、事情が急に変わったようなので、引っ越したり、あれこれ模様変えもしないことにしよう」 |
「女房などはこちらにいいのがたくさんあるようだから、当分あちらの娘付きにさせておくがいい。帳台の |
"Nyoubau nado, konata ni meyasuki amata a' naru wo, kono-hodo ha, ara se tamahe. Yagate, tyau nado mo atarasiku sitate rare ta' meru kata wo, koto nihaka ni nari ni ta' mere ba, tori watasi, tokaku aratamu mazi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | とて、 西の方に来て、立ち居、とかくしつらひ騒ぐ。めやすきさまにさはらかに、あたりあたりあるべき限りしたる所を、さかしらに屏風ども持て来て、いぶせきまで立て集めて、 厨子二階など、あやしきまでし加へて、心をやりて急げば、北の方見苦しく見れど、口入れじと言ひてしかば、ただに見聞く。 御方は、北面に居たり。 |
と言って、西の対に来て、立ったり座ったりして、あれこれと準備に騒いでいる。体裁のよい様子にさっぱりとさせ、あちらこちらに必要な準備をすべて整えてあるところに、利口ぶって屏風類を持って来て、狭苦しいまでに立て並べて、厨子や二階棚など、妙なまで増やして、得意になって準備するので、北の方は見苦しいと思うが、口出しすまいと言ったので、ただ見聞きしている。御方は、北面に座っていた。 |
西座敷のほうへもそんなことを言いに来て、大騒ぎに騒いでいた。夫人が感じよくさっぱりと装飾しておいた姫君の座敷へ、よけいに幾つもの |
tote, nisi no kata ni ki te, tati wi, tokaku siturahi sawagu. Meyasuki sama ni saharaka ni, atari atari aru beki kagiri si taru tokoro wo, sakasira ni byaubu-domo mote ki te, ibuseki made tate atume te, dusi ni-kai nado, ayasiki made si kuhahe te, kokoro wo yari te isoge ba, Kitanokata migurusiku mire do, kuti ire zi to ihi te sika ba, tada ni mi kiku. Ohom-kata ha, kita-omote ni wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
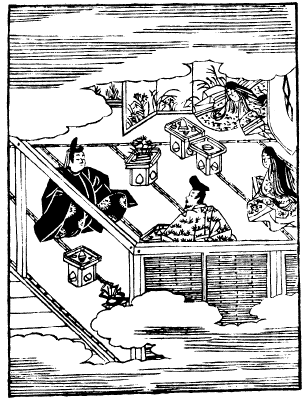 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | 「 人の御心は、見知り果てぬ。ただ同じ子なれば、さりとも、いとかくは思ひ放ちたまはじとこそ思ひつれ。 さはれ、世に母なき子は、なくやはある」 |
「あなたのお気持ちは、すっかり分かりました。全く同じ娘なのだから、そうは言っても、まるでこんなには放っておかれまいと思っていました。まあよい、世間に母親のない子は、いないのだから」 |
「あなたの心は皆わかってしまった。同じあなたの子なのだから、どんなに愛に厚薄はあっても、今度のような場合に打ちやりにしておけるものでないだろうと思っていたのはまちがいだった。もういいよ。世間には母親のある子ばかりではないのだから」 |
"Hito no mi-kokoro ha, mi-siri hate nu. Tada onazi ko nare ba, saritomo, ito kaku ha omohi hanati tamaha zi to koso omohi ture. Sahare, yo ni haha naki ko ha, naku yaha aru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | とて、 娘を、昼より 乳母と二人、撫でつくろひ立てたれば、憎げにもあらず、 十五、六のほどにて、 いと小さやかにふくらかなる人の、髪うつくしげにて小袿のほどなり、裾いとふさやかなり。 これをいとめでたしと思ひて、撫でつくろふ。 |
と言って、娘を、昼から乳母と二人で、念入りに装い立てたので、憎らしいところもなく、十五、六歳の年齢で、たいそう小柄でふっくらとした人で、髪は美しく小袿の長さで、裾はとてもふさやかである。この娘を実に素晴らしいと思って、念入りに装っている。 |
と守は言い、愛嬢を昼から |
tote, musume wo, hiru yori Menoto to hutari, nade tukurohi tate tare ba, nikuge ni mo ara zu, zihu-go, roku no hodo nite, ito tihisa-yaka ni hukuraka naru hito no, kami utukusige nite ko-utiki no hodo nari, suso ito husayaka nari. Kore wo ito medetasi to omohi te, nade tukurohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6 | 「 何か、人の異ざまに 思ひ構へられける人をしも、と思へど、 人柄のあたらしく、警策にものしたまふ君なれば、我も我もと、婿に取らまほしくする人の多かなるに、取られなむも口惜しくてなむ」 |
「何も、北の方があちらにと思っていた人をよりによって横取りしなくても、と思うが、少将の人柄がもったいなく、すぐれていらっしゃる公達なので、われもわれもと、婿に迎えたい人が多いらしいので、人に取られるのも残念である」 |
「家内がほかの計画を立てていた人をわざわざ実子の婿にせずともいいとは思ったが、あまりに人物がりっぱなもので、われもわれもと婿に取りたがるというのを聞いて、よそへ取られてしまうのは残念だったから」 |
"Nanika, hito no koto-zama ni omohi kamahe rare keru hito wo simo, to omohe do, hito-gara no atarasiku, keuzaku ni monosi tamahu Kimi nare ba, ware mo ware mo to, muko ni tora mahosiku suru hito no ohoka' naru ni, tora re na m mo kutiwosiku te nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.7 | と、 かの仲人にはかられて言ふもいとをこなり ★。 男君も、「このほどのいかめしく思ふやうなること」と、 よろづの罪あるまじう思ひて、 その夜も替へず来そめぬ。 |
と、あの仲人にだまされて言うのもほんとうに愚かである。男君も、「今般の待遇が豪勢で申し分ないこと」と、何の支障もないように思って、その夜も改めず通い始めた。 |
と、あの |
to, kano nakaudo ni hakara re te ihu mo ito woko nari. Wotoko-Gimi mo, "Kono hodo no ikamesiku omohu yau naru koto." to, yorodu no tumi aru maziu omohi te, sono yo mo kahe zu ki-some nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 第三段 浮舟の母、京の中君に手紙を贈る |
2-3 Ukifune's mother sends a letter to Naka-no-kimi in Kyoto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 母君、御方の乳母、いとあさましく思ふ。ひがひがしきやうなれば、 とかく見扱ふも心づきなければ、 宮の北の方の御もとに、御文たてまつる。 |
母君や、御方の乳母は、たいそうあきれて思う。ひがんでいるようなので、あれこれと婿の世話をするのも気にいらないので、宮の北の方の御もとに、お手紙を差し上げる。 |
守の妻と姫君の乳母はあさましくこれをながめていたのであった。ひがんだようには見られまいと夫人は世話に手を貸そうとも思っていたが、それをするのも気が進まないままに、二条の院の中の君へまず手紙を送ることにした。 |
Haha-Gimi, Ohom-Kata no Menoto, ito asamasiku omohu. Higa-higasiki yau nare ba, tokaku mi atukahu mo kokoro-duki-nakere ba, Miya no Kitanokata no ohom-moto ni, ohom-humi tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | 「 そのこととはべらでは、なれなれしくやとかしこまりて、え思ひたまふるままにも聞こえさせぬを、 つつしむべきことはべりて、しばし所変へさせむと思うたまふるに、いと忍びてさぶらひぬべき隠れの方さぶらはば、いともいともうれしくなむ。数ならぬ身一つの蔭に隠れもあへず、あはれなることのみ多くはべる世なれば、 頼もしき方にはまづなむ」 |
「特別のご用事がございませんでは、ご無礼かとご遠慮申しまして、思うままにはお便り差し上げませんでしたが、慎まねばならないことがございまして、暫く場所を変えさせたいと存じていましたが、とても人目につかないでいられる所がございましたら、とてもとても嬉しく存じます。人数にも入らないわが身一つでは庇護することもできず、気の毒なことばかりが多い世の中ですので、頼りになるお方にまずお願い申し上げました」 |
用事がございませんで手紙を差し上げますのもなれなれしくいたしすぎることになり、失礼かと存じまして、 |
"Sono koto to habera de ha, nare-naresiku ya to kasikomari te, e omohi tamahuru mama ni mo kikoyesase nu wo, tutusimu beki koto haberi te, sibasi tokoro kahe sase m to omou tamahuru ni, ito sinobi te saburahi nu beki kakure no kata saburaha ba, itomo-itomo uresiku nam. Kazu nara nu mi hitotu no kage ni kakure mo ahe zu, ahare naru koto nomi ohoku haberu yo nare ba, tanomosiki kata ni ha madu nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | と、うち泣きつつ書きたる文を、 あはれとは見たまひけれど、「 故宮の、さばかり許したまはで やみにし人を、我一人残りて、知り語らはむもいとつつましく、また 見苦しきさまにて世にあぶれむも、知らず顔にて 聞かむこそ心苦しかるべけれ。ことなることなくて かたみに散りぼはむも、 亡き人の御ために見苦しかるべきわざ」を 思しわづらふ。 |
と、泣きながら書いた手紙を、しみじみと御覧になったが、「亡き父宮が、あれほどお許しにならずに終わった人を、自分一人が生き残って、親しく世話するのもたいそう気がひけるし、またみっともない恰好で世の中に落ちぶれているのを知らない顔をしているのも、いたわしいことだろう。特別なこともなくて、互いに散り散りになっているようなのも、亡き父宮のためにもみっともない事だ」と思案に暮れなさる。 |
泣きながら書かれたものであるこの手紙を、中の君は哀れと思ったが、父宮が、あくまで子とあそばさなかった人を、父や姉の異議の聞きようのない世になって、自分が |
to, uti-naki tutu kaki taru humi wo, ahare to ha mi tamahi kere do, "Ko-Miya no, sabakari yurusi tamaha de yami ni si hito wo, ware hitori nokori te, siri kataraha m mo ito tutumasiku, mata migurusiki sama nite yo ni abure m mo, sira-zu-gaho nite kika m koso kokoro-gurusikaru bekere. Koto naru koto naku te katamini tiri-boha m mo, naki hito no ohom-tame ni migurusikaru beki waza." wo obosi wadurahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 大輔がもとにも、いと心苦しげに言ひやりたりければ、 |
大輔のもとにも、とても気がかりそうに書いてやったので、 |
|
Taihu ga moto ni mo, ito kokoro-gurusige ni ihi-yari tari kere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | 「 さるやうこそははべらめ。人憎くはしたなくも、 なのたまはせそ。 かかる劣りの者の、人の御中に交じりたまふも、世の常のことなり」 |
「何か事情がございますのでしょう。人を恨んで体裁悪く、おっしゃいますな。このような母親の卑しい人が、ご姉妹の中にいらっしゃるということも、世間にはよくあることです」 |
「何かわけがあることでございましょう。冷淡に断わっておしまいになってはいけません。ああした劣った人から生まれた方が |
"Saru yau koso ha habera me. Hito nikuku hasitanaku mo, na notamahase so. Kakaru otori no mono no, hito no ohom-naka ni maziri tamahu mo, yo no tune no koto nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6 | など聞こえて、 |
などと申し上げて、 |
などと夫人に取りなして、 |
nado kikoye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7 | 「 さらば、かの西の方に、隠ろへたる所し出でて、いとむつかしげなめれど、さても過ぐいたまひつべくは、しばしのほど」 |
「それでは、あの西の対に、人目につかない所を用意して、とてもむさ苦しいようですが、そうしてお過ごしになってはいかがですか、暫くの間を」 |
それではお居間から西のほうに目だたぬ場所をこしらえましたから、いいお座敷ではありませんがごしんぼうをなさいますならしばらくお預かりになろうとおっしゃいます。 |
"Saraba, kano nisi no kata ni, kakurohe taru tokoro si-ide te, ito mutukasige na' mere do, satemo sugui tamahi tu beku ha, sibasi no hodo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8 | と言ひつかはしつ。 いとうれしと思ほして、人知れず出で立つ。 御方も、かの御あたりをば、睦びきこえまほしと思ふ心なれば、 なかなか、かかることどもの出で来たるを、うれしと思ふ。 |
と言い送った。とても嬉しく思って、人に知られないようにして出発する。御方も、あの方と親しく交際申したいと思う考えなので、かえって、このようなことが出て来たのを、嬉しく思う。 |
と昔の |
to ihi tukahasi tu. Ito uresi to omohosi te, hito-sire-zu ide tatu. Ohomkata mo, kano ohom-atari wo ba, mutubi kikoye mahosi to omohu kokoro nare ba, naka-naka, kakaru koto-domo no ide-ki taru wo, uresi to omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 第四段 母、浮舟を匂宮邸に連れ出す |
2-4 Ukifune's mother takes her out Hitachi-no-suke's home |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | 守、少将の扱ひを、いかばかりめでたきことをせむと思ふに、そのきらきらしかるべきことも知らぬ心には、ただ、あららかなる東絹どもを、 押しまろがして投げ出でつ。食ひ物も、所狭きまでなむ運び出でてののしりける。 |
常陸介は、少将の新婚のもてなしを、どんなにか立派なふうにしようと思うが、その豪華にする方法も知らないので、ただ、粗末な東絹類を、おし丸めて投げ出した。食べ物も、あたり狭しと運び出して大騒ぎした。 |
常陸守は婿の少将の三日の夜の儀式をどんなふうに |
Kami, Seusyau no atukahi wo, ika-bakari medetaki koto wo se m to omohu ni, sono kira-kirasikaru beki koto mo sira nu kokoro ni ha, tada, araraka naru Aduma-ginu-domo wo, osi marogasi te nage ide tu. Kuhi-mono mo, tokoro-seki made nam hakobi ide te nonosiri keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 | 下衆などは、それをいとかしこき情けに思ひければ、 君も、「いとあらまほしく、心かしこく取り寄りにけり」と思ひけり。 北の方、「このほどを見捨てて知らざらむもひがみたらむ」と思ひ念じて、 ただするままにまかせて見ゐたり。 |
下衆などは、それをたいそうありがたいお心づかいだと思ったので、君も、「とても理想的な、賢明な縁組をしたものだ」と思うのだった。北の方は、「この間の事を見捨てて知らないふうをするのもひねくれているようだろう」と思い堪えて、ただするままに任せて見ていた。 |
卑しい従者らは大恩恵に |
Gesu nado ha, sore wo ito kasikoki nasake ni omohi kere ba, Kimi mo, "Ito aramahosiku, kokoro-kasikoku tori yori ni keri." to omohi keri. Kitanokata, "Kono hodo wo mi-sute te sira zara m mo higami tara m." to omohi nen-zi te, tada suru mama ni makase te mi wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3 | 客人の御出居、侍ひとしつらひ騒げば、家は広けれど、 源少納言、東の対には住む、 男子などの多かるに、所もなし。 この御方に客人住みつきぬれば、 廊などほとりばみたらむに住ませたてまつらむも、飽かずいとほしくおぼえて ★、とかく思ひめぐらすほど、 宮にとは思ふなりけり。 |
お客人のお座敷や、お供の部屋と準備に騒ぐので、家は広いけれど、源少納言が、東の対に住み、男の子などが多いので、場所もない。こちらのお部屋にお客人が住みつくようになると、渡廊などの端の方にお住まわせ申すのも、どんなにかお気の毒に思われて、あれこれと思案するうちに、宮の邸にと思うのであった。 |
婿君の昼の座敷、侍の詰め所というような |
Marauto no ohom-dewi, saburahi to siturahi sawage ba, ihe ha hirokere do, Gen-Seunagon, himgasi-no-tai ni ha sumu, wonoko-go nado no ohokaru ni, tokoro mo nasi. Kono ohom-kata ni marauto sumi-tuki nure ba, rau nado hotori-bami tara m ni suma se tatematura m mo, akazu itohosiku oboye te, tokaku omohi megurasu hodo, Miya ni to ha omohu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.4 | 「 この御方ざまに、数まへたまふ人のなきを、あなづるなめり」と思へば、 ことに許いたまはざりしあたりを、あながちに参らず。乳母、若き人びと、二、三人ばかりして、 西の廂の北に寄りて、人げ遠き方に局したり。 |
「この御方には、人並みに扱ってくださる人がいないので、馬鹿にしているのだろう」と思うと、特に認めていただけなかった所だが、無理に参上させる。乳母や、若い女房二、三人ほどして、西の廂の北側寄りで、人気の遠い所に部屋を用意した。 |
だれもが八の宮の三女として姫君を見ないところから、私生児として |
"Kono ohom-Kata-zama ni, kazumahe tamahu hito no naki wo, anaduru na' meri." to omohe ba, koto ni yurui tamaha zari si atari wo, anagati ni mawira zu. Menoto, wakaki hito-bito, hu-tari, mi-tari bakari si te, nisi no hisasi no kita ni yori te, hitoge tohoki kata ni tubone si tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.5 | 年ごろ、かくはかなかりつれど、 疎く思すまじき人なれば、参る時は 恥ぢたまはず、いとあらまほしく、 けはひことにて、 若君の御扱ひをしておはする御ありさま、 うらやましくおぼゆるもあはれなり。 |
長年、このように頼りなく過ごして来たが、よそよそしくお思いになれない方なので、参上した時には姿を隠したりなさらず、とても理想的に、感じがまるで違って、若君のお世話をしていらっしゃるご様子を、羨ましく思われるのも感慨無量である。 |
長い間遠く離れていた間柄ではあるが、母方の血縁のある常陸夫人であったから、来た時には中の君も他人扱いにはせず、顔を見せずに隠れて話すようなこともせず、親王夫人らしい気品を持って、若君の世話などをする様子も近く見せられるのを、わが娘に比べて常陸夫人がうらやましく思うのも哀れである。 |
Tosi-goro, kaku hakanakari ture do, utoku obosu maziki hito nare ba, mawiru toki ha hadi tamaha zu, ito ara-mahosiku, kehahi koto nite, Waka-Gimi no ohom-atukahi wo si te ohasuru ohom-arisama, urayamasiku oboyuru mo ahare nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.6 | 「 我も、故北の方には、離れたてまつるべき人かは。 仕うまつるといひしばかりに、 数まへられたてまつらず、口惜しくて、かく人にはあなづらるる」 |
「自分も、亡くなった北の方とは、縁のない人ではない。女房としてお仕えしたために、人並みに扱ってもらえず、残念なことに、このように人から馬鹿にされるのだ」 |
自分も八の宮夫人と家柄の懸隔のあるわけではない、 |
"Ware mo, ko-Kitanokta ni ha, hanare tatematuru beki hito kaha. Tukau-maturu to ihi si bakari ni, kazumahe rare tatematura zu, kutiwosiku te, kaku hito ni ha anadura ruru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7 | と思ふには、 かくしひて睦びきこゆるもあぢきなし。 ここには、御物忌と言ひてければ、人も通はず。二、三日ばかり母君もゐたり。 こたみは、心のどかにこの御ありさまを見る。 |
と思うと、このように無理してお親しみ申すのもつまらない。こちらには、御物忌と言ったので、誰も来ない。二、三日ほど母君もいた。今度は、のんびりとこちらのご様子を見る。 |
と思う心から、こんなふうにしいて親しみ寄ろうとするのも悲しい心である。その一室には |
to omohu ni ha, kaku sihite mutubi kikoyuru mo adikinasi. Koko ni ha, ohom-monoimi to ihi te kere ba, hito mo kayoha zu. Hutu-ka, mi-ka bakari Haha-Gimi mo wi tari. Kotami ha, kokoro-nodoka ni kono mi-arisama wo miru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 第五段 浮舟の母、匂宮と中君夫妻を垣間見る |
2-5 Ukifune's mother peeps Niou-no-miya and his wife Naka-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 | 宮渡りたまふ。ゆかしくてもののはさまより見れば、いときよらに、桜を折りたるさましたまひて、 わが頼もし人に思ひて、恨めしけれど、心には違はじと思ふ常陸守より、さま容貌も人のほども、こよなく見ゆる五位四位ども、 あひひざまづきさぶらひて、このことかのことと、あたりあたりのことども、家司どもなど申す。 |
宮がお越しになる。見たくて物の間から見ると、たいそう美しく、桜を手折ったような姿をして、自分が頼りにする人と思い、恨めしいけれど、気持ちには背くまいと思っている常陸介よりも、容姿や器量も人品も、この上なく見える五位や四位の人が、一斉にひざまずいて控えて、あれやこれやと、あれこれの事務を、家司連中が申し上げる。 |
|
Miya watari tamahu. Yukasiku te mono no hasama yori mire ba, ito kiyora ni, sakura wo wori taru sama si tamahi te, waga tanomosi-bito ni omohi te, uramesikere do, kokoro ni ha tagaha zi to omohu Hitati-no-Kami yori, sama katati mo hito no hodo mo, koyonaku miyuru go-wi si-wi-domo, ahi-hizamaduki saburahi te, kono koto kano koto to, atari atari no koto-domo, keisi-domo nado mausu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2 | また若やかなる五位ども、顔も知らぬどもも多かり。 わが継子の式部丞にて蔵人なる、内裏の御使にて参れり。 御あたりにもえ近く参らず。こよなき人の御けはひを、 |
また若々しい五位の人で、顔も知らない人たちも多かった。自分の継子の式部丞で蔵人なのが、帝のお使いとして参上したが、お側近くにも参ることができない。この上なく高貴なご様子を、 |
また年若な五位などで、この夫人にはだれとも顔のわからぬお供も多かった。自身の継子の |
Mata wakayaka naru go-wi-domo, kaho mo sira nu domo mo ohokari. Waga mama-ko no Sikibu-no-Zou nite Kuraudo naru, Uti no ohom-tukahi nite mawire ri. Ohom-atari ni mo e tikaku mawira zu. Koyonaki hito no ohom-kehahi wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3 | 「 あはれ、こは何人ぞ。かかる御あたりにおはする めでたさよ。よそに思ふ時は、めでたき人びとと聞こゆとも、つらき目見せたまはばと、もの憂く推し量りきこえさせつらむあさましさよ。 この御ありさま容貌を見れば、七夕ばかりにても、かやうに見たてまつり通はむは、いといみじかるべきわざかな」 |
「まあ、この方はいったいどのようなお方か。このようなお方の所にいらっしゃる幸運なことよ。遠くで考えている時は、素晴らしい方々と申し上げても、つらい思いをさせなさったらと、嫌なお方とお思い申し上げていたのはあさはかな考えであったことよ。この方のご様子や器量を見ると、七夕のように年に一度の逢瀬でも、このようにお目にかかれてお通いいただけるのは、とてもありがたいことだわ」 |
これは人間世界のほかから |
"Ahare, ko ha nani-bito zo. Kakaru ohom-atari ni ohasuru medetasa yo. Yoso ni omohu toki ha, medetaki hito-bito to kikoyu tomo, turaki me mise tamaha ba to, mono-uku osihakari kikoye sase tu ram asamasisa yo! Kono ohom-arisama katati wo mire ba, tanabata bakari nite mo, kayau ni mi tatematuri kayoha m ha, ito imizikaru beki waza kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4 | と思ふに、若君抱きてうつくしみおはす。 女君、 短き几帳を隔てておはするを、 押しやりて、ものなど聞こえたまふ 御容貌ども、いときよらに似合ひたり。 故宮の寂しくおはせし御ありさまを ★ 思ひ比ぶるに、「 宮たちと聞こゆれど、いとこよなきわざにこそありけれ」とおぼゆ。 |
と思うと、若君を抱いてかわいがっていらっしゃる。女君は、短い几帳を隔てておいでになるが、押しやって、お話し申し上げなさる。そのお二方のご器量は、実に美しく似合っている。亡き父宮が寂しくいらっしゃった時のご様子を思い比べると、「宮様と申し上げても、とてもこの上なくいらっしゃるのだ」と思われる。 |
などと思っている時、宮は若君を抱いてあやしておいでになった。夫人は短い |
to omohu ni, Waka-Gimi idaki te utukusimi ohasu. Womna-Gimi, mizikaki kityau wo hedate te ohasuru wo, osi-yari te, mono nado kikoye tamahu ohom-katati-domo, ito kiyora ni niahi tari. Ko-Miya no sabisiku ohase si ohom-arisama wo omohi kuraburu ni, "Miya-tati to kikoyure do, ito koyonaki waza ni koso ari kere." to oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5 | 几帳の内に入りたまひぬれば、若君は、若き人、乳母などもてあそびきこゆ。 人びと参り集まれど、 悩ましとて、大殿籠もり暮らしつ。御台こなたに参る。よろづのこと気高く、心ことに見ゆれば、 わがいみじきことを尽くすと見思へど、「なほなほしき人のあたりは、口惜しかりけり」と思ひなりぬれば、「 わが娘も、かやうにてさし並べたらむには、かたはならじかし。勢ひを頼みて、 父ぬしの、后にもなしてむと思ひたる人びと、同じわが子ながら、けはひこよなきを思ふも、なほ今よりのちも、 心は高くつかふべかりけり」と、夜一夜あらまし語り思ひ続けらる。 |
几帳の中にお入りになったので、若君は、若い女房や、乳母などがお相手申し上げる。官人たちが参集したが、気分が悪いと言って、お休みになって一日中を過ごされた。食膳をこちらで差し上げる。万事が気高くて、格別に見えるので、自分がどんなに善美を尽くしたと思っても、「普通の身分のすることは、たかが知れている」と悟ったので、「自分の娘も、このような立派な方の側に並べて見ても、不体裁ではあるまい。財力を頼んで、父親が、后にもしようと思っている娘たちは、同じわが子ながらも、感じがまるで違うのを思うと、やはり今後は理想は高く持つべきであるわ」と、一晩中将来の事を思い続けられる。 |
几帳の中へおはいりになったあとでは |
Kityau no uti ni iri tamahi nure ba, Waka-Gimi ha, wakaki hito, Menoto nado mote-asobi kikoyu. Hito-bito mawiri atumare do, nayamasi tote, ohoto-gomori kurasi tu. Mi-dai konata ni mawiru. Yorodu no koto kedakaku, kokoro koto ni miyure ba, waga imiziki koto wo tukusu to mi omohe do, "Naho-nahosiki hito no atari ha, kutiwosikari keri." to omohi nari nure ba, "Waga musume mo, kayau nite sasi-narabe tara m ni ha, kataha nara zi kasi. Ikihohi wo tanomi te, Titi-nusi no, Kisaki ni mo nasi te m to omohi taru hito-bito, onazi waga ko nagara, kehahi koyonaki wo omohu mo, naho ima yori noti mo, kokoro ha takaku tukahu bekari keri." to, yo hito-yo aramasi gatari omohi tuduke raru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 第六段 浮舟の母、左近少将を垣間見て失望 |
2-6 Ukifune's mother peeps Sakon-shosho and is disappointed with him |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 | 宮、日たけて起きたまひて、 |
宮は、日が高くなってからお起きになって、 |
朝おそくなってから宮はお起きになり、 |
Miya, hi take te oki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
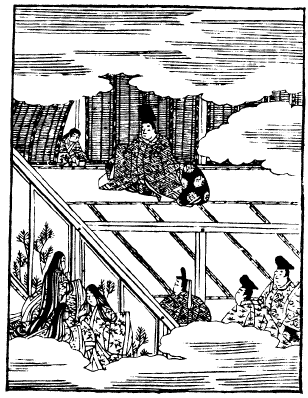 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2 | 「 后の宮、例の、悩ましくしたまへば、参るべし」 |
「后の宮が、相変わらず、お具合が悪くいらっしゃるので、参内しよう」 |
病身になっておいでになる |
"Kisai-no-Miya, rei no, nayamasiku si tamahe ba, mawiru besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.3 | とて、御装束などしたまひておはす。 ゆかしうおぼえて覗けば、うるはしくひきつくろひたまへる、はた、似るものなく気高く愛敬づききよらにて、若君をえ見捨てたまはで遊びおはす。御粥、強飯など参りてぞ、 こなたより出でたまふ。 |
と言って、ご装束などをお召しになっていらっしゃる。興味をもって覗くと、きちんと身づくろいなさったのが、また、似る者がいないほど気高く魅力的で美しくて、若君をお放しになることができず遊んでいらっしゃる。お粥や、強飯などを召し上がって、こちらからお出かけになる。 |
とされ、衣服を改めなどしておいでになった。心が |
tote, ohom-syauzoku nado si tamahi te ohasu. Yukasiu oboye te nozoke ba, uruhasiku hikitukurohi tamahe ru, hata, niru mono naku kedakaku aigyau-duki kiyora nite, Waka-Gimi wo e mi-sute tamaha de asobi ohasu. Ohom-kayu, koha-ihi nado mawiri te zo, konata yori ide tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.4 | 今朝より参りて、さぶらひの方にやすらひける人びと、今ぞ参りてものなど聞こゆる中に、 きよげだちて、なでふことなき人のすさまじき顔したる、直衣着て太刀佩きたるあり。 御前にて何とも見えぬを、 |
今朝方から参上して、侍所の方に控えていた供人たちは、今しも御前に参上して何か申し上げている中で、めかしこんで、何ということもない人でつまらない顔をして、直衣を着て太刀を佩いている人がいる。御前では何とも見えないが、 |
|
Kesa yori mawiri te, saburahi no kata ni yasurahi keru hito-bito, ima zo mawiri te mono nado kikoyuru naka ni, kiyoge-dati te, nadehu koto naki hito no susamaziki kaho si taru, nahosi ki te tati haki taru ari. O-mahe nite nanitomo miye nu wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.5 | 「 かれぞ、この常陸守の婿の少将な。初めは御方にと定めけるを、守の娘を得てこそいたはられめ、など言ひて、かしけたる女の童を持たるななり」 |
「あの人が、この常陸介の婿の少将ですよ。初めはこの御方にと決めていたが、介の実の娘を得てこそ大切にされたい、などと言って、痩せっぽっちの女の子を得たと言います」 |
「あれがあの常陸守の婿の少将じゃありませんか。初めはあの姫君の婿にと定められていたのに、 |
"Kare zo, kono Hitati-no-Kami no muko no Seusyau na! Hazime ha Ohom-kata ni to sadame keru wo, Kami no musume wo e te koso itahara re me, nado ihi te, kasike taru me-no-waraha wo mo' taru na' nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.6 | 「いさ、 この御あたりの人はかけても言はず。 かの君の方より、よく聞くたよりのあるぞ」 |
「いえ、こちらの女房たちはそんな噂は全然しません。あの君の方からは、よく聞く話ですよ」 |
そんなことをこちらなどで |
"Isa, kono ohom-atari no hito ha kakete mo iha zu. Kano Kimi no kata yori, yoku kiku tayori no aru zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.7 | など、おのがどち言ふ。 聞くらむとも知らで、人のかく言ふにつけても、胸つぶれて、少将をめやすきほどと思ひける心も口惜しく、「 げに、ことなることなかるべかりけり」と思ひて、いとどしく あなづらはしく思ひなりぬ。 |
などと、めいめい言っている。聞いているとも知らないで、女房がこのように言っているのにつけても、胸がどきりとして、少将を無難だと思っていた考えも残念で、「なるほど、格別なことはなかったのだ」と思って、ますます馬鹿らしく思った。 |
とほかの一人にささやいている女房があった。常陸の妻が聞いているとは知らずにこんなことの言われているのにもその人ははっとして、少将を相当な |
nado, onoga-doti ihu. Kiku ram to mo sira de, hito no kaku ihu ni tuke te mo, mune tubure te, Seusyau wo meyasuki hodo to omohi keru kokoro mo kutiwosiku, "Geni, koto naru koto nakaru bekari keri." to omohi te, itodosiku anadurahasiku omohi nari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.8 | 若君のはひ出でて、御簾のつまよりのぞきたまへるを、 うち見たまひて、立ち返り寄りおはしたり。 |
若君が這いだして来て、御簾の端から顔を出していらっしゃるのを、ちょっと御覧になって、後戻りなさった。 |
若君が |
Waka-Gimi no hahi-ide te, mi-su no tuma yori nozoki tamahe ru wo, uti-mi tamahi te, tati-kaheri yori ohasi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.9 | 「 御心地よろしく見えたまはば、やがてまかでなむ。なほ苦しくしたまはば、今宵は 宿直にぞ。今は、 一夜を隔つるもおぼつかなきこそ苦しけれ」 |
「ご気分がよくお見えでしたら、そのまま帰って来ましょう。やはりお悪いようでいらしたら、今夜は宿直します。今は、一晩でも会わないのは気がかりでつらいことだ」 |
「中宮様の御気分がよろしいようだったら早く退出して来よう。まだお苦しいふうな御容体だったら今夜は |
"Mi-kokoti yorosiku miye tamaha ba, yagate makade na m. Naho kurusiku si tamaha ba, koyohi ha tonowi ni zo. Ima ha, hito-yo wo hedaturu mo obotukanaki koso kurusikere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.10 | とて、しばし慰め遊ばして、出でたまひぬるさまの、 返す返す見るとも見るとも、飽くまじく、匂ひやかにをかしければ、出でたまひぬる名残、 さうざうしくぞ眺めらるる。 |
と言って、暫くご機嫌をおとりになって、お出かけになった様子が、繰り返し見ても、どこまでも満ち足りていて、華やかにお美しいので、お出かけになった後の気持ちが、物足りなく物思いに沈んでしまう。 |
こう女房へお言いになりながらしばらく若君をお慰めになってから出てお行きになる宮の御様子は見ても見ても飽くことのないほどお美しかったのが、行っておしまいになったあとに物足りなさと寂しさを常陸夫人は感じた。 |
tote, sibasi nagusame asobasi te, ide tamahi nuru sama no, kahesu-gahesu miru to mo miru to mo, aku maziku, nihohiyaka ni wokasikere ba, ide tamahi nuru nagori, sau-zausiku zo nagame raruru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 4/24/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 4/24/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 4/24/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/5/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経