49 宿木(大島本) |
YADORIGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の中、大納言時代 二十四歳夏から二十六歳夏四月頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Chunagon and Dainagon era, from summer at the age of 24 to April at the age of 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 第八章 薫の物語 女二の宮、薫の三条宮邸に降嫁 |
8 Tale of Kaoru Onna-ni-no-miya gets married to Kaoru and moves into Samjo residence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 第一段 新年、薫権大納言兼右大将に昇進 |
8-1 Kaoru is promoted to Gon-Dainagon and U-Daisho in new year |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.1 | 正月晦日方より、 例ならぬさまに悩みたまふを、宮、まだ御覧じ知らぬことにて、いかならむと、思し嘆きて、御修法など、所々にてあまたせさせたまふに、またまた始め添へさせたまふ。いといたくわづらひたまへば、后の宮よりも御訪らひあり。 |
正月晦日方から、ふだんと違ってお苦しみになるのを、宮は、まだご経験のないことなので、どうなることだろうと、お嘆きになって、御修法などを、あちこちの寺にたくさんおさせになるが、またまたお加え始めさせなさる。たいそうひどく患いなさるので、后の宮からもお見舞いがある。 |
一月の終わりから普通でない身体の苦痛を夫人は感じだしたのを、宮もまだ産をする婦人の悩みをお見になった御経験はなかったので、どうなるのかと御心配をあそばして、今まで |
Syaugwati tugomori-gata yori, rei nara nu sama ni nayami tamahu wo, Miya, mada go-ran-zi sira nu koto nite, ika nara m to, obosi-nageki te, mi-syuhohu nado, tokoro-dokoro nite amata se sase tamahu ni, mata-mata hazime sase tamahu. Ito itaku wadurahi tamahe ba, Kisai-no-Miya yori mo ohom-toburahi ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.2 | かくて三年になりぬれど、 一所の御心ざしこそおろかならね、 おほかたの世には、ものものしくももてなしきこえたまはざりつるを ★、この折ぞ、いづこにもいづこにも 聞こしめしおどろきて、御訪ぶらひども聞こえたまひける。 |
結婚して三年になったが、お一方のお気持ちは並々でないが、世間一般に対しては、重々しくおもてなし申し上げなさらなかったので、この時に、どこもかしこもお聞きになって驚いて、お見舞い申し上げになるのであった。 |
中の君が二条の院へ迎えられてから足かけ三年になるが、御 |
Kakute mi-tose ni nari nure do, hito-tokoro no mi-kokorozasi koso oroka nara ne, ohokata no yo ni ha, mono-monosiku motenasi kikoye tamaha zari turu wo, kono wori zo, iduko ni mo iduko ni mo kikosimesi odoroki te, ohom-toburahi-domo kikoye tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.3 | 中納言の君は、宮の思し騒ぐに劣らず、 いかにおはせむと嘆きて、心苦しくうしろめたく思さるれど、限りある御訪らひばかりこそあれ、あまりもえ 参うでたまはで、忍びてぞ御祈りなどもせさせたまひける。 |
中納言の君は、宮がお騷ぎになるのに負けず、どうおなりになることだろうかとご心配になって、お気の毒に気がかりにお思いになるが、一通りのお見舞いはするが、あまり参上することはできないので、こっそりとご祈祷などをおさせになるのだった。 |
源中納言は宮の御心配しておいでになるのにも劣らぬ不安を覚えて、気づかわしくてならないのであっても、表面的な見舞いに行くほかは近づいて尋ねることもできずに、ひそかに祈祷などをさせていた。 |
Tyuunagon-no-Kimi ha, Miya no obosi-sawagu ni otora zu, ikani ohase m to nageki te, kokoro-gurusiku usirometaku obosa rure do, kagiri aru ohom-toburahi bakari koso are, amari mo e maude tamaha de, sinobi te zo ohom-inori nado mo se sase tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.4 | さるは、 女二の宮の御裳着、ただこのころになりて、世の中響きいとなみののしる。よろづのこと、帝の御心一つなるやうに思し急げば、御後見なきしもぞ、なかなかめでたげに見えける。 |
その一方では、女二の宮の御裳着が、ちょうどこのころとなって、世間で大評判となっている。万事が、帝のお心一つみたいに御準備なさるので、御後見がいないのも、かえって立派に見えるのであった。 |
この人の婚約者の |
Saruha, Womna-Ni-no-Miya no ohom-mogi, tada kono-koro ni nari te, yononaka hibiki itonami nonosiru. Yorodu no koto, Mikado no mi-kokoro hitotu naru yau ni obosi-isoge ba, ohom-usiromi naki simo zo, naka-naka medetage ni miye keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.5 | 女御のしおきたまへることをばさるものにて、作物所、さるべき受領どもなど、とりどりに仕うまつることども、いと限りなしや。 |
女御が生前に準備しておかれたことはいうまでもなく、作物所や、しかるべき受領連中などが、それぞれにお仕え申し上げることは、とても際限がない。 |
|
Nyougo no si-oki tamahe ru koto wo ba saru mono nite, tukumo-dokoro, saru-beki Zuryau-domo nado, tori-dori ni tukau-maturu koto-domo, ito kagirinasi ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.6 | やがてそのほどに、参りそめたまふべきやうにありければ、 男方も心づかひしたまふころなれど、例のことなれば、そなたざまには心も入らで、 この御事のみいとほしく嘆かる。 |
そのままその時から、通い始めさせなさることになっていたので、男の方も気をおつかいになるころであるが、例の性格なので、その方面には気が進まず、このご懐妊のことばかりお気の毒に嘆かずにいられない。 |
その式の済んだあとで通い始めるようにとの御内意が薫へ伝達されている時であったから、婿方でも平常と違う緊張をしているはずであるが、なおいままでどおりにそちらのことはどうでもいいと思われ、中の君の産の重いことばかりを哀れに思って歎息を続ける薫であった。 |
Yagate sono hodo ni, mawiri some tamahu beki yau ni ari kere ba, Wotoko-gata mo kokoro-dukahi si tamahu koro nare do, rei no koto nare ba, sonata-zama ni ha kokoro mo ira de, kono ohom-koto nomi itohosiku nageka ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.7 | 如月の朔日ごろに、直物とかいふことに、権大納言になりたまひて、右大将かけたまひつ。 右の大殿、左にておはしけるが、辞したまへる所なりけり。 |
二月の初めころに、直物とかいうことで、権大納言におなりになって、右大将を兼官なさった。右の大殿が、左大将でいらっしゃったが、お辞めになったものであった。 |
二月の |
Kisaragi no tuitati-goro ni, nahosi-mono to ka ihu koto ni, Gon-Dainagon ni nari tamahi te, U-Daisyau kake tamahi tu. Migi-no-Ohoidono, Hidari ni te ohasi keru ga, zi-si tamahe ru tokoro nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.8 | 喜びに所々ありきたまひて、この宮にも参りたまへり。 いと苦しくしたまへば、 こなたにおはしますほどなりければ、 やがて参りたまへり。 僧などさぶらひて便なき方に、とおどろきたまひて、あざやかなる御直衣、御下襲などたてまつり、 ひきつくろひたまひて、 下りて答の拝したまふ御さまどもとりどりにいとめでたく、 |
お礼言上に諸所をお回りになって、こちらの宮にも参上なさった。たいそう苦しそうでいらっしゃるので、こちらにいらっしゃるときであったので、そのまま参上なさった。僧などが伺候していて不都合なところで、と驚きなさって、派手なお直衣に、御下襲などをお召し替えになって、身づくろいなさって、下りて拝舞の礼をなさるお二方のお姿は、それぞれに立派で、 |
新任の |
Yorokobi ni tokoro-dokoro ariki tamahi te, kono Miya ni mo mawiri tamahe ri. Ito kurusiku si tamahe ba, konata ni ohasimasu hodo nari kere ba, yagate mawiri tamahe ri. Sou nado saburahi te bin naki kata ni, to odoroki tamahi te, azayaka naru ohom-nahosi, ohom-sita-gasane nado tatematuri, hiki-tukurohi tamahi te, ori te tahu-no-hai si tamahu ohom-sama-domo tori-dori ni ito medetaku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.9 | 「 やがて、官の禄賜ふ饗の所に」 |
「このまま今晩、近衛府の人に禄を与える宴会の所にどうぞ」 |
この日は |
"Yagate, tukasa no roku tamahu aruzi no tokoro ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.10 | と、請じたてまつりたまふを、悩みたまふ人によりてぞ、 思したゆたひたまふめる。右大臣殿のしたまひけるままにとて、六条の院にてなむありける。 |
と、お招き申し上げなさるが、お具合の悪い人のために、躊躇なさっているようである。右大臣殿がなさった例に従ってと、六条院で催されるのであった。 |
自邸でとは言っていたが、近くに中の君の悩んでいる二条の院があることで少し |
to, syau-zi tatematuri tamahu wo, nayami tamahu hito ni yori te zo, obosi-tayutahi tamahu meru. U-Daizin-dono no si tamahi keru mama ni tote, Rokudeu-no-win nite nam ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.11 | 垣下の親王たち上達部、 大饗に劣らず、あまり騒がしきまでなむ集ひたまひける。この宮も渡りたまひて、静心なければ、まだ事果てぬに急ぎ帰りたまひぬるを、 大殿の御方には、 |
お相伴の親王方や上達部たちは、大饗に負けないほど、あまり騒がし過ぎるほど参集なさった。この宮もお渡りになって、落ち着いていられないので、まだ宴会が終わらないうちに急いでお帰りになったのを、大殿の御方では、 |
皇子がたも相伴の客として宴にお |
Wenga no Miko-tati Kamdatime, daikyau ni otora zu, amari sawagasiki made nam tudohi tamahi keru. Kono Miya mo watari tamahi te, sidu-kokoro nakere ba, mada koto hate nu ni isogi kaheri tamahi nuru wo, Ohotono-no-Ohomkata ni ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.12 | 「 いと飽かずめざまし」 |
「とても物足りなく癪にさわる」 |
ねたましがった。 |
"Ito akazu mezamasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.13 | とのたまふ。 劣るべくもあらぬ御ほどなるを、ただ今のおぼえのはなやかさに思しおごりて、おしたちもてなしたまへるなめりかし。 |
とおっしゃる。負けるほどでもないご身分なのを、ただ今の威勢が立派なのにおごって、いばっていらっしゃるのであろうよ。 |
同じほどに愛されているのであるが権家の娘であることに |
to notamahu. Otoru beku mo ara nu ohom-hodo naru wo, tada ima no oboye no hanayaka ni obosi-ogori te, ositati motenasi tamahe ru na' meri kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | 第二段 中君に男子誕生 |
8-2 A baby boy is born to the couple of Naka-no-kimi and Nio-no-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.1 | からうして、その暁、 男にて生まれたまへるを、宮もいとかひありてうれしく思したり。大将殿も、喜びに添へて、うれしく思す。昨夜おはしましたりしかしこまりに、やがて、この御喜びもうち添へて、 立ちながら参りたまへり。 かく籠もりおはしませば、参りたまはぬ人なし。 |
やっとのこと、その早朝に、男の子でお生まれになったのを、宮もたいそうその効あって嬉しくお思いになった。大将殿も、昇進の喜びに加えて、嬉しくお思いになる。昨夜おいでになったお礼言上に、そのまま、このお祝いを合わせて、立ったままで参上なさった。こうして籠もっていらっしゃるので、お祝いに参上しない人はいない。 |
ようやくその夜明けに二条の院の夫人は男児を生んだ。宮も非常にお喜びになった。右大将も昇任の |
Karausite, sono akatuki, wotoko nite mumare tamahe ru wo, Miya mo ito kahi ari te uresiku obosi tari. Daisyau-dono mo, yorokobi ni sohe te, uresiku obosu. Yobe ohasimasi tari si kasikomari ni, yagate, kono ohom-yorokobi mo uti-sohe te, tati nagara mawiri tamahe ri. Kaku komori ohasimase ba, mawiri tamaha nu hito nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.2 | 御産養、三日は、例のただ宮の御私事にて、 五日の夜、大将殿より屯食五十具、碁手の銭、椀飯などは、世の常のやうにて、子持ちの御前の衝重三十、稚児の御衣五重襲にて、御襁褓などぞ、ことことしからず、忍びやかにしなしたまへれど、こまかに見れば、わざと目馴れぬ心ばへなど見えける。 |
御産養は、三日は、例によってただ宮の私的祝い事として、五日の夜は、大将殿から屯食五十具、碁手の銭、椀飯などは、普通通りにして、子持ちの御前の衝重三十、稚児の御産着五重襲に、御襁褓などは、仰々しくないようにこっそりとなさったが、詳細に見ると、特別に珍しい趣向が凝らしてあったのであった。 |
|
Ohom-ubuyasinahi, mi-ka ha, rei no tada Miya no ohom-watakusi-goto nite, itu-ka no yo, Daisyau-dono yori tonziki gozihu-gu, gote no zeni, wauban nado ha, yo no tune no yau nite, Komoti-no-Omahe no tui-gasane sam-zihu, Tigo no ohom-zo itu-he-gasane nite, ohom-mutuki nado zo, koto-kotosikara zu, sinobi-yaka ni si-nasi tamahe re do, komaka ni mire ba, wazato me-nare nu kokorobahe nado miye keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
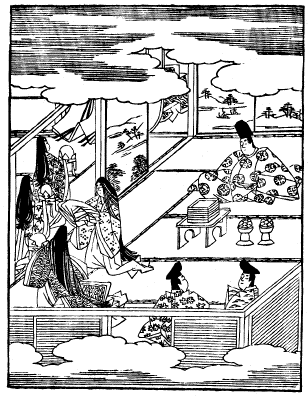 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.3 | 宮の御前にも浅香の折敷、高坏どもにて、粉熟参らせたまへり。女房の御前には、衝重をばさるものにて、桧破籠三十、さまざまし尽くしたることどもあり。人目にことことしくは、ことさらにしなしたまはず。 |
宮の御前にも浅香の折敷や、高坏類に、粉熟を差し上げなさった。女房の御前には、衝重はもちろんのこと、桧破子三十、いろいろと手を尽くしたご馳走類がある。人目につくような大げさには、わざとなさらない。 |
父宮へも浅香木の |
Miya no o-mahe ni mo sankau no wosiki, takatuki-domo ni te, huzuku mawira se tamahe ri. Nyoubau no o-mahe ni ha, tui-gasane wo ba saru mono nite, hiwarigo sam-zihu, sama-zama si tukusi taru koto-domo ari. Hitome ni koto-kotosiku ha, kotosara ni si-nasi tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.4 | 七日の夜は、后の宮の御産養なれば、参りたまふ人びといと多かり。宮の大夫をはじめて、殿上人、上達部、数知らず参りたまへり。内裏にも聞こし召して、 |
七日の夜は、后の宮の御産養なので、参上なさる人びとが多い。中宮大夫をはじめとして、殿上人、上達部が、数知れず参上なさった。主上におかれてもお耳にあそばして、 |
七日の夜は中宮からのお産養であったから、席に |
Siti-niti no yo ha, Kisai-no-Miya no ohom-ubuyasinahi nare ba, mawiri tamahu hito-bito ito ohokari. Miya-no-Daibu wo hazime te, Tenzyau-bito, Kamdatime, kazu sira zu mawiri tamahe ri. Uti ni mo kikosimesi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.5 | 「 宮のはじめて大人びたまふなるには、いかでか」 |
「宮がはじめて一人前におなりになったというのに、どうして放っておけようか」 |
兵部卿の宮がはじめて父になった喜びのしるしをぜひとも贈るべきである |
"Miya no hazimete otona-bi tamahu naru ni ha, ikadeka." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.6 | とのたまはせて、御佩刀奉らせたまへり。 |
と仰せになって、御佩刀を差し上げなさった。 |
と仰せになり、 |
to notamahase te, mi-hakasi tatematura se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.7 | 九日も、大殿より仕うまつらせたまへり。よろしからず思すあたりなれど、 宮の思さむところあれば、御子の公達など参りたまひて、すべていと思ふことなげにめでたければ、 御みづからも、月ごろもの思はしく心地の悩ましきにつけても、心細く思したりつるに、かくおもただしく今めかしきことどもの多かれば、 すこし慰みもやしたまふらむ。 |
九日も、大殿からお世話申し上げなさった。おもしろくなくお思いになるところだが、宮がお思いになることもあるので、ご子息の公達が参上なさって、万事につけたいそう心配事もなさそうにおめでたいので、ご自身でも、ここ幾月も物思いによって気分が悪いのにつけても、心細くお思い続けていたが、このように面目がましいはなやかな事が多いので、少し慰みなさったことであろうか。 |
九日も左大臣からの産養があった。愛嬢の競争者の夫人を喜ばないのであるが、宮の思召しをはばかって、当夜は子息たちを何人も送り、接客の用を果たさせもした。夫人もこの幾月間物思いをし続けると同時に、身体の苦しさも並み並みでなく、心細くばかり思っていたのであったが、こうしたはなやかな空気に包まれる日が来て少し慰んだかもしれない。 |
Kokonu-ka mo, Ohoi-dono yori tukau-matura se tamahe ri. Yorosikara zu obosu atari nare do, Miya no obosa m tokoro are ba, mi-ko no Kimdati nado mawiri tamahi te, subete ito omohu koto nage ni medetakere ba, ohom-midukara mo, tuki-goro mono-omohasiku kokoti no nayamasiki ni tuke te mo, kokoro-bosoku obosi tari turu ni, kaku omodatasiku imamekasiki koto-domo no ohokare ba, sukosi nayami mo ya si tamahu ram. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.8 | 大将殿は、「 かくさへ大人び果てたまふめれば、いとどわが方ざまは気遠くやならむ。また、宮の御心ざしもいとおろかならじ」と思ふは口惜しけれど、また、初めよりの心おきてを思ふには、いとうれしくもあり。 |
大将殿は、「このようにすっかり大人になってしまわれたので、ますます自分のほうには縁遠くなってしまうだろう。また、宮のお気持ちもけっして並々ではあるまい」と思うのは残念であるが、また、初めからの心づもりを考えてみると、たいそう嬉しくもある。 |
右大将はこんなふうに動揺されぬ位置が中の君にできてしまい、王子の母君となってしまっては、自分の恋に対して冷淡さが加わるばかりであろうし、宮の愛はこの夫人に多く傾くばかりであろうと思われるのはくちおしい気のすることであったが、最初から願っていた中の君の幸福というものがこれで確実になったとする点ではうれしく思わないではいられなかった。 |
Daisyau-dono ha, "Kaku sahe otonabi hate tamahu mere ba, itodo waga kata-zama ha ke-dohoku ya nara m. Mata, Miya no mi-kokorozasi mo ito oroka nara zi." to omohu ha kutiwosikere do, mata, hazime yori no kokoro-okite wo omohu ni ha, ito uresiku mo ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 第三段 二月二十日過ぎ、女二の宮、薫に降嫁す |
8-3 Onna-ni-no-miya gets married to Kaoru and moves into his home at 20 past on February |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.1 | かくて、 その月の二十日あまりにぞ、藤壺の宮の御裳着の事ありて、またの日なむ、大将参りたまひける。夜のことは忍びたるさまなり。天の下響きていつくしう見えつる御かしづきに、ただ人の具したてまつりたまふぞ、なほ飽かず心苦しく見ゆる。 |
こうして、その月の二十日過ぎに、藤壷の宮の御裳着の儀式があって、翌日、大将が参上なさった。その夜のことは内々のことである。世間に評判なほど大切にかしずかれた姫宮なのに、臣下がご結婚申し上げなさるのは、やはり物足りなくお気の毒に見える。 |
その月の二十幾日に女二の宮の裳着の式が行なわれ、翌夜に右大将は |
Kakute, sono tuki no hatu-ka amari ni zo, Huditubo-no-Miya no ohom-mogi no koto ari te, mata no hi nam, Daisyau mawiri tamahi keru. Yo no koto ha sinobi taru sama nari. Ame-no-sita hibiki te itukusiu miye turu ohom-kasiduki ni, tadaudo no gu-si tatematuri tamahu zo, naho akazu kokoro-gurusiku miyuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.2 | 「 さる御許しはありながらも、ただ今、かく急がせたまふまじきことぞかし」 |
「そのようなお許しはあったとしても、ただ今、このようにお急ぎあそばすことでもあるまい」 |
婚約はお許しになっておいても、結婚をそう急いでおさせにならないでもよいではないか |
"Saru ohom-yurusi ha ari nagara mo, tada ima, kaku isoga se tamahu maziki koto zo kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.3 | と、そしらはしげに思ひのたまふ人もありけれど、思し立ちぬること、すがすがしくおはします御心にて、来し方ためしなきまで、同じくはもてなさむと、 思しおきつるなめり。 帝の御婿になる人は、昔も今も多かれど、かく盛りの御世に、ただ人のやうに、婿取り急がせたまへるたぐひは、すくなくやありけむ。 右の大臣も、 |
と、非難がましく思いおっしゃる人もいるのだったが、ご決意なさったことを、すらすらとなさるご性格なので、過去に例がないほど同じことならお扱いなさろうと、お考えおいたようである。帝の御婿になる人は、昔も今も多いが、このように全盛の御世に、臣下のように、婿を急いでお迎えなさる例は少なかったのではなかろうか。右大臣も、 |
と非難らしいことを申す者もあったが、お思い立ちになったことはすぐ実行にお移しになる |
to, sosirahasige ni omohi notamahu hito mo ari kere do, obosi-tati nuru koto, suga-sugasiku ohasimasu mi-kokoro nite, kisi-kata tamesi naki made, onaziku ha motenasa m to, obosi-oki turu na' meri. Mikado no ohom-muko ni naru hito ha, mukasi mo ima mo ohokare do, kaku sakari no mi-yo ni, tadaudo no yau ni, muko-dori isoga se tamahe ru taguhi ha, sukunaku ya ari kem. Migi-no-Otodo mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.4 | 「 めづらしかりける人の御おぼえ、宿世なり。故院だに、朱雀院の御末にならせたまひて、今はとやつしたまひし際にこそ、 かの母宮を得たてまつりたまひしか。我はまして、 人も許さぬものを拾ひたりしや」 |
「珍しいご信任、運勢だ。故院でさえ、朱雀院の晩年におなりあそばして、今は出家されようとなさった時に、あの母宮を頂戴なさったのだ。自分はまして、誰も許さなかったのを拾ったものだ」 |
「右大将はすばらしい運命を持った男ですね。六条院すら |
"Medurasikari keru hito no ohom-oboye, sukuse nari. Ko-Win dani, Suzaku-Win no ohom-suwe ni narase tamahi te, imaha to yatusi tamahi si kiha ni koso, kano Haha-Miya wo e tatematuri tamahi sika. Ware ha masite, hito mo yurusa nu mono wo hirohi tari si ya." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.5 | とのたまひ出づれば、宮は、げにと思すに、恥づかしくて御いらへもえしたまはず。 |
とおっしゃり出すので、宮は、その通りとお思いになると、恥ずかしくてお返事もおできになれない。 |
こんなことを言った。夫人の宮はそのとおりであったことがお恥ずかしくて返辞をあそばすこともできなかった。 |
to notamahi-idure ba, Miya ha, geni to obosu ni, hadukasiku te ohom-irahe mo si tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.6 | 三日の夜は、大蔵卿よりはじめて、 かの御方の心寄せになさせたまへる人びと、家司に仰せ言賜ひて、忍びやかなれど、かの御前、随身、車副、舎人まで禄賜はす。そのほどの事どもは、 私事のやうにぞありける。 |
三日の夜は、大蔵卿をはじめとして、あの御方のお世話役をなさっていた人びとや、家司にご命令なさって、人目に立たないようにではあるが、婿殿の御前駆や随身、車副、舎人まで禄をお与えになる。その時の事柄は、私事のようであった。 |
三日目の夜は |
Mi-ka no yo ha, Ohokura-kyau yori hazime te, kano Ohom-kata no kokoro-yose ni nasa se tamahe ru hito-bito, Keisi ni ohose-goto tamahi te, sinobiyaka nare do, kano go-zen, zuizin, kuruma-zohi, Toneri made roku tamaha su. Sono hodo no koto-domo ha, watakusi-goto no yau ni zo ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.7 | かくて後は、忍び忍びに参りたまふ。心の内には、 なほ忘れがたきいにしへざまのみおぼえて、昼は里に起き臥し眺め暮らして、暮るれば心より外に急ぎ参りたまふをも、ならはぬ心地に、いともの憂く苦しくて、「 まかでさせたてまつらむ」とぞ思しおきてける。 |
こうして後は、忍び忍びに参上なさる。心の中では、やはり忘れることのできない故人のことばかりが思われて、昼は実邸に起き臥し物思いの生活をして、暮れると気の進まないままに急いで参内なさるのを、なれない気持ちには億劫で苦しくて、「ご退出させ申し上げよう」とお考えになったのであった。 |
それからのちは忍び忍びに藤壺へ薫は通って行った。心の中では昔のこと、昔にゆかりのある人のことばかりが思われて、昼はひねもす物思いに暮らして、夜になるとわが意志でもなく女二の宮をお訪ねに行くのも、そうした習慣のなかった人であるからおっくうで苦しく思われる薫は、御所から自邸へ宮をお迎えしようと考えついた。 |
Kakute noti ha, sinobi-sinobi ni mawiri tamahu. Kokoro no uti ni ha, naho wasure gataki inisihe-zama nomi oboye te, hiru ha sato ni oki-husi nagame kurasi te, kurure ba kokoro yori hoka ni isogi mawiri tamahu wo mo, naraha nu kokoti ni, ito mono-uku kurusiku te, "Makade sase tatematura m." to zo obosi-oki te keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.8 | 母宮は、いとうれしきことに思したり。おはします寝殿譲りきこゆべくのたまへど、 |
母宮は、とても嬉しいこととお思いになっていらっしゃった。お住まいになっている寝殿をお譲り申し上げようとおっしゃるが、 |
そのことを尼宮はうれしく |
Haha-Miya ha, ito uresiki koto ni obosi tari. Ohasimasu sinden yuduri kikoyu beku notamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.9 | 「 いとかたじけなからむ」 |
「まことに恐れ多いことです」 |
それはもったいないことである |
"Ito katazikenakara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.10 | とて、御念誦堂のあはひに、廊を続けて造らせたまふ。 西面に移ろひたまふべきなめり。東の対どもなども、焼けて後、うるはしく新しくあらまほしきを、いよいよ磨き添へつつ、こまかにしつらはせたまふ。 |
と言って、御念誦堂との間に、渡廊を続けてお造らせになる。西面にお移りになるようである。東の対なども、焼失して後は、立派に新しく理想的なのを、ますます磨き加え加えして、こまごまとしつらわせなさる。 |
と薫は言って、自身の |
tote, ohom-nenzyu-dau no ahahi ni, rau wo tuduke te tukura se tamahu. Nisi-omote ni uturohi tamahu beki na' meri. Himgasi-no-tai-domo nado mo, yake te noti, uruhasiku atarasiku aramahosiki wo, iyo-iyo migaki sohe tutu, komaka ni situraha se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.11 | かかる御心づかひを、内裏にも聞かせたまひて、 ほどなくうちとけ移ろひたまはむを、いかがと思したり。帝と聞こゆれど、 ▼ 心の闇は同じごとなむおはしましける。 |
このようなお心づかいを、帝におかせられてもお耳にあそばして、月日も経ずに気安く引き取られなさるのを、どんなものかとお思いであった。帝と申し上げても、子を思う心の闇は同じことでおありだった。 |
薫のそうした用意をしていることが帝のお耳にはいり、結婚してすぐに |
Kakaru mi-kokoro-dukahi wo, uti ni mo kika se tamahi te, hodo naku utitoke uturohi tamaha m wo, ikaga to obosi tari. Mikado to kikoyure do, kokoro-no-yami ha onazi-goto nam ohasimasi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.12 | 母宮の御もとに、 御使ありける御文にも、ただこのことをなむ聞こえさせたまひける。 故朱雀院の、取り分きて、この尼宮の御事をば聞こえ置かせたまひしかば、かく世を背きたまへれど、衰へず、何事も元のままにて、 奏せさせたまふことなどは、かならず聞こしめし入れ、御用意 深かりけり。 |
母宮の御もとに、お使いがあったお手紙にも、ただこのことばかりを申し上げなさった。故朱雀院が、特別に、この尼宮の御事をお頼み申し上げていたので、このように出家なさっているが、衰えず、何事も昔通りで、奏上させなさることなどは、必ずお聞き入れなさって、お心配りが深いのであった。 |
尼宮の所へ勅使がまいり、お手紙のあった中にも、ただ女二の宮のことばかりが書かれてあった。お |
Haha-Miya no ohom-moto ni, ohom-tukahi ari keru ohom-humi ni mo, tada kono koto wo nam kikoye sase tamahi keru. Ko-Syuzaku-Win no, tori-waki te, ko no Ama-Miya no ohom-koto wo ba kikoye oka se tamahi sika ba, kaku yo wo somuki tamahe re do, otorohe zu, nani-goto mo moto no mama nite, sou-se sase tamahu koto nado ha, kanarazu kikosimesi ire, ohom-youi hukakari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.13 | かく、 やむごとなき御心どもに、かたみに限りもなくもてかしづき騒がれたまふおもだたしさも、いかなるにかあらむ、 心の内にはことにうれしくもおぼえず、なほ、ともすればうち眺めつつ、宇治の寺造ることを急がせたまふ。 |
このように、重々しいお二方に、互いにこの上なく大切にされていらっしゃる面目も、どのようなものであろうか、心中では特に嬉しくも思われず、やはり、ともすれば物思いに耽りながら、宇治の寺の造営を急がせなさる。 |
こうした最高の方を |
Kaku, yamgotonaki mi-kokoro-domo ni, katami ni kagiri mo naku mote-kasiduki sawagare tamahu omodatasisa mo, ika naru ni ka ara m, kokoro no uti ni ha koto ni uresiku mo oboye zu, naho, tomo-sure ba uti-nagame tutu, Udi no tera tukuru koto wo isoga se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 第四段 中君の男御子、五十日の祝い |
8-4 A celebration of the baby's 50th day born |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.1 | 宮の若君の五十日になりたまふ日数へ取りて、その餅の急ぎを心に入れて、籠物、桧破籠などまで見入れたまひつつ、世の常のなべてにはあらずと思し心ざして、沈、紫檀、銀、黄金など、道々の細工どもいと多く召しさぶらはせたまへば、 我劣らじと、さまざまのことどもを し出づめり。 |
宮の若君が五十日におなりになる日を数えて、その餅の準備を熱心にして、籠物や桧破子などまで御覧になりながら、世間一般の平凡なものにはしまいとお考え向きになって、沈、紫檀、銀、黄金など、それぞれの専門の工匠をたいそう大勢呼び集めさせなさるので、自分こそは負けまいと、いろいろのものを作り出すようである。 |
兵部卿の宮の若君の五十日になる日を数えていて、その式用の祝いの |
Miya-no-Waka-Gimi no i-ka ni nari tamahu hi kazohe tori te, sono motihi no isogi wo kokoro ni ire te, ko-mono, hiwarigo nado made, mi-ire tamahi tutu, yo no tune no nabete ni ha ara zu to obosi kokorozasi te, din, sitan, sirokane, kogane nado, miti-miti no saiku-domo ito ohoku mesi saburaha se tamahe ba, ware otora zi to, sama-zama no koto-domo wo si-idu meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.2 | みづからも、例の、宮のおはしまさぬ隙におはしたり。 心のなしにやあらむ、今すこし重々しくやむごとなげなるけしきさへ添ひにけりと見ゆ。「 今は、さりとも、むつかしかりしすずろごとなどは紛れたまひにたらむ」と思ふに、心やすくて、対面したまへり。されど、ありしながらのけしきに、まづ涙ぐみて、 |
ご自身も、いつものように、宮がいらっしゃらない間においでになった。気のせいであろうか、もう一段と重々しく立派な感じが加わったと見える。「今は、そうはいっても、わずらわしかった懸想事などは忘れなさったろう」と思うと、安心なので、お会いなさった。けれど、以前のままの様子で、まっさきに涙ぐんで、 |
薫はまた宮のおいでにならぬひまに二条の院の夫人を訪れた。思いなしか重々しさと高貴さが添ったように中の君を薫は思った。もう薫は結婚もしたのであるから、自分の迷惑になるような気持ちは皆紛れてしまっているであろうと安心して夫人は出て来たのであったが、やはり同じように寂しい表情をし、涙ぐんでいて、 |
Midukara mo, rei no, Miya no ohasimasa nu hima ni ohasi tari. Kokoro no nasi ni ya ara m, ima sukosi omo-omosiku yamgotonage naru kesiki sahe sohi ni keri to miyu. "Ima ha, saritomo, mutukasikari si suzuro-goto nado ha magire tamahi ni tara m." to omohu ni, kokoro-yasuku te, taimen si tamahe ri. Saredo, ari si nagara no kesiki ni, madu namida-gumi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.3 | 「 心にもあらぬまじらひ、いと思ひの外なるものにこそと、世を思ひたまへ乱るることなむ、まさりにたる」 |
「気の進まない結婚は、たいそう心外なものだと、世の中を思い悩みますことは、今まで以上です」 |
「自分の意志でない結婚をした苦痛というものはまた予想外に堪えられないものだとわかりまして、 |
"Kokoro ni mo ara nu mazirahi, ito omohi no hoka naru mono ni koso to, yo wo omohi tamahe midaruru koto nam, masari ni taru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.4 | と、あいだちなくぞ愁へたまふ。 |
と、何の遠慮もなく訴えなさる。 |
と、新婦の宮に同情の欠けたようなことを |
to, aidati naku zo urehe tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.5 | 「 いとあさましき御ことかな。人もこそおのづからほのかにも 漏り聞きはべれ」 |
「まあ何というお事を。他人が自然と漏れ聞いたら大変ですよ」 |
「とんだことをおっしゃいます。そういうことをいつの間にか人が聞くようになってはたいへんですよ」 |
"Ito asamasiki ohom-koto kana! Hito mo koso onodukara honoka ni mo mori kiki habere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.6 | などはのたまへど、 かばかりめでたげなることどもにも慰まず、「忘れがたく思ひたまふらむ心深さよ」とあはれに思ひきこえたまふに、おろかにもあらず思ひ知られたまふ。「 おはせましかば」と、口惜しく思ひ出できこえたまへど、「 それも、わがありさまのやうに、うらやみなく身を恨むべかりけるかし。何事も数ならでは、世の人めかしきこともあるまじかりけり」とおぼゆるにぞ、いとど、 かの、うちとけ果てでやみなむと思ひたまへりし心おきては、なほ、いと重々しく思ひ出でられたまふ。 |
などとおっしゃるが、これほどめでたい幾つものことにも心が晴れず、「忘れがたく思っていらっしゃるのだろう愛情の深さは」としみじみお察し申し上げなさると、並々でない愛情だとお分かりになる。「生きていらっしゃったら」と、残念にお思い出し申し上げなさるが、「そうしても、自分と同じようになって、姉妹で恨みっこなしに恨むのがおちであろう。何事も、落ちぶれた身の上では、一人前らしいこともありえないのだ」と思われると、ますます、姉君の結婚しないで通そうと思っていらっしゃった考えは、やはり、とても重々しく思い出されなさる。 |
こう中の君は言いながらも、だれが見ても光栄の人になっていて、それにも慰められずまだ故人が忘れられないように言うこの人の愛の純粋さをうれしく思っていた。姉君が生きていたらとも思うのであったが、しかしそれも自分と同じように勝ち味のない競争者を持って薄運を歎くにとどまることになったであろう、富のない自分らは世の中から何につけても尊重されていくものではないらしいとまた思うことによって姉君がどこまでも情に負けず結婚はせまいとした心持ちのえらさが思われた。 |
nado ha notamahe do, kabakari medetage naru koto-domo ni mo nagusama zu, "Wasure gataku omohi tamhu ram kokoro-hukasa yo." to ahare ni omohi kikoye tamahu ni, oroka ni mo ara zu omohi-sira re tamahu. "Ohase masika ba." to, kutiwosiku omohi-ide kikoye tamahe do, "Sore mo, wa ga arisama no yau ni, urayami naku mi wo uramu bekari keru kasi. Nani-goto mo kazu nara de ha, yo no hito mekasiki koto mo aru mazikari keri." to oboyuru ni zo, itodo, kano, utitoke hate de yami na m to omohi tamahe ri si kokoro-okite ha, naho, ito omo-omosiku omohi-ide rare tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 第五段 薫、中君の若君を見る |
8-5 Kaoru sees Naka-no-kimi's baby |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.1 | 若君を切にゆかしがりきこえたまへば、恥づかしけれど、「 何かは隔て顔にもあらむ、わりなきこと一つにつけて恨みらるるよりほかには、いかでこの人の御心に違はじ」と思へば、みづからはともかくもいらへきこえたまはで、 乳母してさし出でさせたまへり。 |
若君を切に拝見したがりなさるので、恥ずかしいけれど、「どうしてよそよそしくしていられよう、無理なこと一つで恨まれるより以外には、何とかこの人のお心に背くまい」と思うので、ご自身はあれこれお答え申し上げなさらないで、乳母を介して差し出させなさった。 |
薫が若君をぜひ見せてほしいと言っているのを聞いて、恥ずかしくは思いながら、この人に隔て心を持つようには取られたくない、無理な恋を受け入れぬと恨まれる以外のことで、この人の感情は害したくないと中の君は思い、自身では何とも返辞をせずに、 |
Waka-Gimi wo seti ni yukasi-gari kikoye tamahe ba, hadukasikere do, "Nani-kaha hedate-gaho ni mo ara m, warinaki koto hitotu ni tuke te urami raruru yori hoka ni ha, ikade kono hito no mi-kokoro ni tagaha zi." to omohe ba, midukara ha tomo-kaku-mo irahe kikoye tamaha de, menoto si te sasi-ide sase tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.2 | さらなることなれば、憎げならむやは。ゆゆしきまで白くうつくしくて、たかやかに物語し、うち笑ひなどしたまふ顔を見るに、わがものにて見まほしくうらやましきも、世の思ひ離れがたくなりぬるにやあらむ。されど、「 言ふかひなくなりたまひにし人の、世の常のありさまにて、かやうならむ人をもとどめ置きたまへらましかば」とのみおぼえて、 このころおもだたしげなる御あたりに、いつしかなどは思ひ寄られぬこそ、あまりすべなき君の御心なめれ。かく女々しくねぢけて、まねびなすこそいとほしけれ。 |
当然のことながら、どうして憎らしいところがあろう。不吉なまでに白くかわいらしくて、大きい声で何か言っており、にっこりなどなさる顔を見ると、自分の子として見ていたく羨ましいのも、この世を離れにくくなったのであろうか。けれど、「亡くなってしまった方が、普通に結婚して、このようなお子を残しておいて下さったら」とばかり思われて、最近面目をほどこすあたりには、はやく子ができないかなどとは考えもつかないのは、あまり仕方のないこの君のお心のようだ。このように女々しくひねくれて、語り伝えるのもお気の毒である。 |
いうまでもなく醜い子であるはずはない。驚くほど色が白く、美しくて、高い声を立てて |
Sara naru koto nare ba, nikuge nara m yaha. Yuyusiki made siroku utukusiku te, takayaka ni monogatari si, uti-warahi nado si tamahu kaho wo miru ni, waga mono nite mi mahosiku urayamasiki mo, yo no omohi hanare-gataku nari nuru ni ya ara m. Saredo, "Ihukahinaku nari tamahi ni si hito no, yo no tune no arisama nite, kayau nara m hito wo mo todome-oki tamahe ra masika ba." to nomi oboye te, kono koro omodatasige naru atari ni, itusika nado ha omohi-yora re nu koso, amari subenaki Kimi no mi-kokoro na' mere. Kaku me-mesiku nedike te, manebi nasu koso itohosikere. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.3 | しか悪ろびかたほならむ人を、帝の取り分き切に近づけて、睦びたまふべきにもあらじものを、「まことしき方ざまの御心おきてなどこそは、めやすくものしたまひけめ」とぞ推し量るべき。 |
そんなによくない方を、帝が特別お側にお置きになって、親しみなさることもあるまいに、「生活面でのご思慮などは、無難でいらっしゃったのだろう」と推量すべきであろう。 |
こんな変人を帝が特にお愛しになって、婿にまではあそばされるはずはないのである。公人としての才能が完全なものであったのであろうと見ておくよりしかたがない。 |
Sika warobi kataho nara m hito wo, Mikado no tori-waki seti ni tikaduke te, mutubi tamahu beki ni mo ara zi mono wo, "Makoto-siki kata-zama no mi-kokoro okite nado koso ha, meyasuku monosi tamahi keme." to zo osihakaru beki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.4 | げに、いとかく幼きほどを 見せたまへるもあはれなれば、例よりは物語などこまやかに聞こえたまふほどに、暮れぬれば、心やすく夜をだに更かすまじきを、苦しうおぼゆれば、嘆く嘆く 出でたまひぬ。 |
なるほど、まことにこのように幼い子をお見せなさるのもありがたいことなので、いつもよりはお話などをこまやかに申し上げなさるうちに、日も暮れたので、気楽に夜を更かすわけにもゆかないのを、つらく思われるので、嘆息しながらお出になった。 |
これほどの幼い人をはばからず見せてくれた夫人の好意もうれしくて、平生以上にこまやかに話をしているうちに日が暮れたため、他で夜の刻をふかしてはならぬ境遇になったことも苦しく思い、薫は歎息を |
Geni, ito kaku wosanaki hodo wo mise tamahe ru mo ahare nare ba, rei yori ha monogatari nado komayaka ni kikoye tamahu hodo ni, kure nure ba, kokoro-yasuku yoru wo dani hukasu maziki wo, kurusiu oboyure ba, nageku nageku ide tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.5 | 「 をかしの人の御匂ひや。 折りつれば、とか ★や言ふやうに、 鴬も尋ね来ぬべかめり」 |
「結構なお匂いの方ですこと。梅を折ったなら、とか言うように、鴬も求めて来ましょうね」 |
「なんというよいにおいでしょう。『折りつれば |
"Wokasi no hito no ohom-nihohi ya! Wori ture ba, to kaya ihu yau ni, uguhisu mo tadune ki nu beka' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.6 | など、わづらはしがる若き人もあり。 |
などと、やっかいがる若い女房もいる。 |
などと騒いでいる女房もあった。 |
nado, wadurahasigaru wakaki hito mo ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6 | 第六段 藤壺にて藤の花の宴催される |
8-6 A banquet is held by Mikado under the wistera blossoms |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.1 | 「 夏にならば、三条の宮塞がる方になりぬべし」と定めて、四月朔日ごろ、節分とかいふこと、まだしき先に渡したてまつりたまふ。 |
「夏になったら、三条宮邸は宮中から塞がった方角になろう」と判定して、四月初めころの、節分とかいうことは、まだのうちにお移し申し上げなさる。 |
夏になると御所から三条の宮は方角 |
"Natu ni nara ba, Samdeu-no-miya hutagaru kata ni nari nu besi." to sadame te, Uduki tuitati-goro, setibun to ka ihu koto, madasiki saki ni watasi tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.2 | 明日とての日藤壺に主上渡らせたまひて、 藤の花の宴せさせたまふ。南の廂の御簾上げて、椅子立てたり。公わざにて、主人の 宮の仕うまつりたまふにはあらず。上達部、殿上人の饗など、内蔵寮より仕うまつれり。 |
明日引っ越しという日に、藤壷に主上がお渡りあそばして、藤の花の宴をお催しあそばす。南の廂の御簾を上げて、椅子を立ててある。公の催事で、主人の宮がお催しなさることではない。上達部や、殿上人の饗応などは、内蔵寮からご奉仕した。 |
その前日に帝は |
Asu tote no hi, Hudi-tubo ni Uhe watara se tamahi te, hudi-no-hana-no-en se sase tamahu. Minami no hisasi no mi-su age te, isi tate tari. Ohoyake-waza nite, aruzi no Miya no tukau-maturi tamahu ni ha arazu. Kamdatime, Tenzyau-bito no kyau nado, Kura-dukasa yori tukau-mature ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.3 | 右の大臣、 按察使大納言、 藤中納言、 左兵衛督。親王たちは、 三の宮、 常陸宮などさぶらひたまふ。南の庭の藤の花のもとに、殿上人の座はしたり。後涼殿の東に、楽所の人びと召して、暮れ行くほどに、双調に吹きて、上の御遊びに、 宮の御方より、御琴ども笛など出ださせたまへば、大臣をはじめたてまつりて、御前に取りつつ参りたまふ。 |
右大臣や、按察大納言、藤中納言、左兵衛督。親王方では、三の宮、常陸宮などが伺候なさる。南の庭の藤の花の下に、殿上人の座席は設けた。後涼殿の東に、楽所の人びとを召して、暮れ行くころに、双調に吹いて、主上の御遊に、宮の御方から、絃楽器や管楽器などをお出させなさったので、大臣をおはじめ申して、御前に取り次いで差し上げなさる。 |
左大臣、 |
Migi-no-Otodo, Azeti-no-Dainagon, Tou-Tyuunagon, Sa-Hyauwe-no-Kami. Miko-tati ha, Sam-no-Miya, Hitati-no-Miya nado saburahi tamahu. Minami no niha no hudi no hana no moto ni, Tenzyau-bito no za ha si tari. Kourau-den no himgasi ni, gakuso no hito-bito mesi te, kure-yuku hodo ni, soudeu ni huki te, uhe no ohom-asobi ni, Miya-no-Ohomkata yori, ohom-koto-domo hue nado idasa se tamahe ba, Otodo wo hazime tatematuri te, o-mahe ni tori tutu mawiri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.4 | 故六条の院の御手づから書きたまひて、入道の宮にたてまつらせたまひし琴の譜二巻、五葉の枝に付けたるを、大臣取りたまひて奏したまふ。 |
故六条院がご自身でお書きになって、入道の宮に差し上げなさった琴の譜二巻、五葉の枝に付けたのを、大臣がお取りになって奏上なさる。 |
六条院が自筆でおしたためになり、三条の尼宮へお与えになった琴の譜二巻を五葉の枝につけて左大臣は持って出、由来を御 |
Ko-Rokudeu-no-Win no ohom-te-dukara kaki tamahi te, Nihudau-no-Miya ni tatematura se tamahi si kin no hu huta-maki, goehu no yeda ni tuke taru wo, Otodo tori tamahi te sou-si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.5 | 次々に、箏の御琴、琵琶、和琴など、 朱雀院の物どもなりけり。 笛は、かの夢に伝へし いにしへの形見のを、「 またなき物の音なり」と賞でさせたまひければ、「 この折のきよらより、またはいつかは映え映えしきついでのあらむ」と思して、取う出で たまへるなめり。 |
次々に、箏のお琴、琵琶、和琴など、朱雀院の物であった。笛は、あの夢で伝えた故人の形見のを、「二つとない素晴らしい音色だ」とお誉めあそばしたので、「今回の善美を尽くした宴の他に、再びいつ名誉なことがあろうか」とお思いになって、取り出しなさったようだ。 |
次々に十三 |
Tugi-tugi ni, syau-no-ohom-koto, biwa, wagon nado, Syuzyaku-win no mono-domo nari keri. Hue ha, kano yume ni tutahe si inisihe no katami no wo, "Matanaki mono no ne nari." to mede sase tamahi kere ba, "Kono wori no kiyora yori, mata ituka ha haye-bayesiki tuide no ara m." to obosi te, tou-ide tamahe ru na' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.6 | 大臣和琴、三の宮琵琶など、とりどりに賜ふ。大将の御笛は、今日ぞ、世になき音の限りは吹き立てたまひける。殿上人の中にも、唱歌につきなからぬどもは、召し出でて、おもしろく遊ぶ。 |
大臣に和琴、三の宮に琵琶など、それぞれにお与えになる。大将のお笛は、今日は、またとない音色の限りをお立てになったのだった。殿上人の中にも、唱歌に堪能な人たちは、召し出して、風雅に合奏する。 |
大臣に和琴、兵部卿の宮に琵琶の役を仰せつけになった。笛の右大将はこの日比類もなく妙音を吹き立てた。殿上役人の中にも唱歌の役にふさわしい人は呼び出され、おもしろい合奏の夜になった。 |
Otodo wagon, Sam-no-Miya biwa nado, tori-dori ni tamahu. Daisyau no ohom-hue ha, kehu zo, yo ni naki ne no kagiri ha huki tate tamahi keru. Tenzyau-bito no naka ni mo, syauga ni tuki nakara nu domo ha, mesi-ide te, omosiroku asobu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.7 | 宮の御方より、粉熟参らせたまへり。沈の折敷四つ、紫檀の高坏、藤の村濃の打敷に、 折枝縫ひたり。銀の様器、瑠璃の御盃、瓶子は紺瑠璃なり。兵衛督、御まかなひ仕うまつりたまふ。 |
宮の御方から、粉熟を差し上げなさった。沈の折敷四つ、紫檀の高坏、藤の村濃の打敷に、折枝を縫ってある。銀の容器、瑠璃のお盃、瓶子は紺瑠璃である。兵衛督が、お給仕をお勤めなさる。 |
御前へ |
Miya-no-Ohomkata yori, huzuku mawira se tamahe ri. Din no wosiki yo-tu, sitan no takatuki, hudi no murago no utisiki ni, woriyeda nuhi tari. Sirokane no yauki, ruri no ohom-sakaduki, heisi ha kon-ruri nari. Hyauwe-no-Kami, ohom-makanahi tukau-maturi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.8 | 御盃参りたまふに、大臣、 しきりては便なかるべし、宮たちの御中にはた、さるべきもおはせねば、大将に譲りきこえたまふを、憚り申したまへど、 御けしきもいかがありけむ、 御盃ささげて、「をし」とのたまへる声づかひもてなしさへ、例の公事なれど、人に似ず見ゆるも、今日はいとど 見なしさへ添ふにやあらむ。 さし返し賜はりて、 下りて舞踏したまへるほど、いとたぐひなし。 |
お盃をいただきなさる時に、大臣は、自分だけしきりにいただくのは不都合であろう、宮様方の中には、またそのような方もいらっしゃらないので、大将にお譲り申し上げなさるのを、遠慮してご辞退申し上げなさるが、帝の御意向もどうあったのだろうか、お盃を捧げて、「おし」とおっしゃる声や態度までが、いつもの公事であるが、他の人と違って見えるのも、今日はますます帝の婿君と思って見るせいであろうか。さし返しの盃にいただいて、庭に下りて拝舞なさるところは、実にまたとない。 |
お杯を奉る時に、大臣は自分がたびたび出るのはよろしくないし、その役にしかるべき宮がたもおいでにならぬからと言い、右大将にこの晴れの役を譲った。薫は遠慮をして辞退をしていたが、帝もその御希望がおありになるようであったから、お杯をささげて「おし」という声の出し方、身のとりなしなども、御前ではだれもする役であるが比べるものもないりっぱさに見えるのも、今日は婿君としての思いなしが添うからであるかもしれぬ。返しのお杯を賜わって、階下へ下り舞踏の礼をした姿などは輝くようであった。 |
Ohom-sakaduki mawiri tamahu ni, Otodo, sikiri te ha bin nakaru besi, Miya-tati no ohom-naka ni hata, saru-beki mo ohase ne ba, Daisyau ni yuduri kikoye tamahu wo, habakari mausi tamahe do, mi-kesiki mo ikaga ari kem, ohom-sakaduki sasage te, "Wosi!" to notamahe ru kowa-dukahi motenasi sahe, rei no ohoyake-goto nare do, hito ni ni zu miyuru mo, kehu ha itodo mi nasi sahe sohu ni ya ara m. Sasi-kahesi tamahari te, ori te butahu si tamahe ru hodo, ito taguhi nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6.9 | 上臈の親王たち、大臣などの賜はりたまふだにめでたきことなるを、これはまして御婿にてもてはやされたてまつりたまへる、御おぼえ、おろかならずめづらしきに、限りあれば、下りたる座に帰り着きたまへるほど、 心苦しきまでぞ見えける。 |
上席の親王方や、大臣などが戴きなさるのでさえめでたいことなのに、これはそれ以上に帝の婿君としてもてはやされ申されていらっしゃる、その御信任が、並々でなく例のないことだが、身分に限度があるので、下の座席にお帰りになってお座りになるところは、お気の毒なまでに見えた。 |
皇子がた、大臣などがお杯を賜わるのさえきわめて光栄なことであるのに、これはまして御婿として御歓待あそばす |
Zyaurahu no Miko-tati, Daizin nado no tamahari tamahu dani medetaki koto naru wo, kore ha masite ohom-muko nite motehayasa re tatematuri tamahe ru, ohom-oboye, oroka nara zu medurasiki ni, kagiri are ba, kudari taru za ni kaheri tuki tamahe ru hodo, kokoro-gurusiki made zo miye keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7 | 第七段 女二の宮、三条宮邸に渡御す |
8-7 Onna-ni-no-miya moves into Kaoru's Samjo residence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.1 | 按察使大納言は、「 我こそかかる目も見むと思ひしか、ねたのわざや」と思ひたまへり。 この宮の御母女御をぞ、昔、心かけきこえたまへりけるを、参りたまひて後も、なほ思ひ離れぬさまに聞こえ通ひたまひて、果ては 宮を得たてまつらむの心つきたりければ、御後見望むけしきも漏らし申しけれど、 聞こし召しだに伝へずなりにければ、いと心やましと思ひて、 |
按察使大納言は、「自分こそはこのような目に会いたい思ったが、妬ましいことだ」と思っていらっしゃった。この宮の御母女御を、昔、思いをお懸け申し上げていらっしゃったが、入内なさった後も、やはり思いが離れないふうにお手紙を差し上げたりなさって、終いには宮を得たいとの考えがあったので、ご後見を希望する様子をお漏らし申し上げたが、お聞き入れさえなさらなかったので、たいそう悔しく思って、 |
按察使大納言は自分こそこの光栄に浴そうとした者ではないか、うらやましいことであると心で思っていた。昔この宮の母君の |
Azeti-no-Dainagon ha, "Ware koso kakaru me mo mi m to omohi sika, neta no waza ya!" to omohi tamahe ri. Kono Miya no ohom-haha-Nyougo wo zo, mukasi, kokoro-kake kikoye tamahe ri keru wo, mawiri tamahi te noti mo, naho omohi hanare nu sama ni kikoye kayohi tamahi te, hate ha Miya wo e tatematura m no kokoro tuki tari kere ba, ohom-usiromi nozomu kesiki mo morasi mausi kere do, kikosimesi dani tutahe zu nari ni kere ba, ito kokoro-yamasi to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.2 | 「 人柄は、げに契りことなめれど、なぞ、時の帝のことことしきまで婿かしづきたまふべき。またあらじかし。九重のうちに、 おはします殿近きほどにて、ただ人のうちとけ訪らひて、果ては宴や何やともて騒がるることは」 |
「人柄は、なるほど前世の因縁による格別の生まれであろうが、どうして、時の帝が大仰なまでに婿を大切になさることだろう。他に例はないだろう。宮中の内で、お常御殿に近い所に、臣下が寛いで出入りして、最後は宴や何やとちやほやされることよ」 |
右大将は天才に生まれて来ているとしても、現在の帝がこうした婿かしずきをあそばすべきでない、禁廷の中のお居間に近い殿舎で一臣下が新婚の夢を結び、果ては宴会とか何とか |
"Hitogara ha, geni tigiri koto na' mere do, nazo, toki no Mikado no koto-kotosiki made muko kasiduki tamahu beki. Mata ara zi kasi. Kokonohe no uti ni, ohasimasu tono tikaki hodo nite, tadaudo no utitoke toburahi te, hate ha en ya nani ya to mote-sawaga ruru koto ha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.3 | など、いみじく誹りつぶやき申したまひけれど、さすがゆかしければ、参りて、心の内にぞ腹立ちゐたまへりける。 |
などと、ひどく悪口をぶつぶつ申し上げなさったが、やはり盛儀を見たかったので、参内して、心中では腹を立てていらっしゃるのだった。 |
などとお |
nado, imiziku sosiri tubuyaki mausi tamahi kere do, sasuga yukasi kere ba, mawiri te, kokoro no uti ni zo, hara-dati wi tamahe ri keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
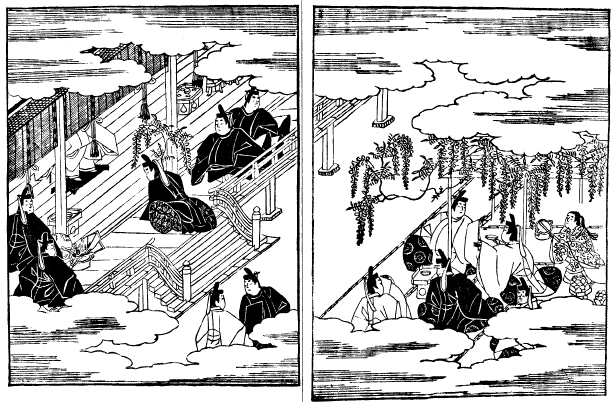 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.4 | 紙燭さして歌どもたてまつる。 文台のもとに寄りつつ置くほどのけしきは、おのおのしたり顔なりけれど、 例の、「いかにあやしげに古めきたりけむ」と 思ひやれば、あながちに皆もたづね書かず。 上の町も、上臈とて、御口つきどもは、異なること見えざめれど、しるしばかりとて、一つ、二つぞ問ひ聞きたりし。これは、大将の君の、下りて御かざし折りて参りたまへりけるとか。 |
紙燭を灯して何首もの和歌を献上する。文台のもとに寄りながら置く時の態度は、それぞれ得意顔であったが、例によって、「どんなにかおかしげで古めかしかったろう」と想像されるので、むやみに全部は探して書かない。上等の部も、身分が高いからといって、詠みぶりは、格別なことは見えないようだが、しるしばかりにと思って、一、二首聞いておいた。この歌は、大将の君が、庭に下りて帝の冠に挿す藤の花を折って参上なさった時のものとか。 |
燭を手にして歌を文台の所へ置きに来る人は皆得意顔に見えたが、こんな場合の歌は型にはまった古くさいものが多いに違いないのであるから、わざわざ調べて書こうと筆者はしなかった。上流の人とても佳作が成るわけではないが、しるしだけに一、二を聞いて書いておく。次のは右大将が庭へ |
Sisoku sasi te uta-domo tatematuru. Bundai no moto ni yori tutu oku hodo no kesiki ha, ono-ono sitari-gaho nari kere do, rei no, "Ikani ayasige ni hurumeki tari kem." to omohi-yare ba, anagati ni mina mo tadune kaka zu. Kami no mati mo, zyaurahu tote, ohom-kutituki-domo ha, koto naru koto miye za' mere do, sirusi bakari tote, hitotu, hutatu zo tohi kiki tari si. Kore ha, Daisyau-no-Kimi no, ori te ohom-kazasi wori te mawiri tamahe ri keru to ka. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.5 | 「 すべらきのかざしに折ると藤の花 |
「帝の插頭に折ろうとして藤の花を |
すべらぎのかざしに折ると藤の花 |
"Suberaki no kazasi ni woru to hudi no hana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.6 | 及ばぬ枝に袖かけてけり」 |
わたしの及ばない袖にかけてしまいました」 |
及ばぬ枝に袖かけてけり |
oyoba nu yeda ni sode kake te keri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.7 | うけばりたるぞ、憎きや。 |
いい気になっているのが、憎らしいこと。 |
したり顔なのに少々反感が起こるではないか。 |
Ukebari taru zo, nikuki ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.8 | 「 よろづ世をかけて匂はむ花なれば |
「万世を変わらず咲き匂う花であるから |
よろづ代をかけてにほはん花なれば |
"Yorodu-yo wo kake te nihoha m hana nare ba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.9 | 今日をも飽かぬ色とこそ見れ」 |
今日も見飽きない花の色として見ます」 |
これは御製である。まただれかの作、 |
kehu wo mo aka nu iro to koso mire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.10 | 「君がため折れるかざしは 紫の |
「主君のため折った插頭の花は |
君がため折れるかざしは紫の |
"kimi ga tame wore ru kazasi ha murasaki no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.11 | 雲に劣らぬ花のけしきか」 |
紫の雲にも劣らない花の様子です」 |
雲に劣らぬ花のけしきか |
kumo ni otora nu hana no kesiki ka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.12 | 「 世の常の色とも見えず雲居まで |
「世間一般の花の色とも見えません |
世の常の色とも見えず雲井まで |
"Yo no tune no iro to mo miye zu kumowi made |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.13 | たち昇りたる藤波の花」 |
宮中まで立ち上った藤の花は」 |
立ちのぼりける藤波の花 |
tati-nobori taru hudinami no hana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.14 | 「 これやこの腹立つ大納言のなりけむ」と見ゆれ。かたへは、ひがことにもやありけむ。かやうに、ことなるをかしきふしもなくのみぞあなりし。 |
「これがこの腹を立てた大納言のであった」と見える。一部は、聞き違いであったかも知れない。このように、格別に風雅な点もない歌ばかりであった。 |
あとのは腹をたてていた大納言の歌らしく思われる。どの歌にも筆者の聞きそこねがあってまちがったところがあるかもしれない。だいたいこんなふうの歌で、感激させられるところの少ないもののようであった。 |
"Kore ya kono hara-datu Dainagon no nari kem." to miyure. Katahe ha, higa-koto ni mo ya ari kem. Kayau ni, koto naru wokasiki husi mo naku nomi zo a' nari si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.15 | 夜更くるままに、御遊びいともしろし。大将の君、「 安名尊」謡ひたまへる声ぞ、限りなくめでたかりける。按察使も、昔すぐれたまへりし御声の名残なれば、今もいとものものしくて、うち合はせたまへり。 右の大殿の御七郎、童にて笙の笛吹く。いとうつくしかりければ、 御衣賜はす。大臣下りて舞踏したまふ。 |
夜の更けるにしたがって、管弦の御遊はたいそう興趣深い。大将の君が、「安名尊」を謡いなさった声は、この上なく素晴しかった。按察使大納言も、若い時にすぐれていらっしゃったお声が残っていて、今でもたいそう堂々としていて、合唱なさった。右の大殿の七郎君が、子供で笙の笛を吹く。たいそうかわいらしかったので、御衣を御下賜になる。大臣が庭に下りて拝舞なさる。 |
夜がふけるにしたがって音楽は佳境にはいっていった。薫が「あなたふと」を歌った声が限りもなくよかった。按察使も昔はすぐれた声を持った人であったから、今もりっぱに合わせて歌った。左大臣の七男が |
Yo-hukuru mama ni, ohom-asobi ito omosirosi. Daisyau-no-kimi, Ana tahuto utahi tamahe ru kowe zo, kagirinaku medetakari keru. Azeti mo, mukasi sugure tamahe ri si ohom-kowe no nagori nare ba, ima mo ito mono-monosiku te, uti-ahase tamahe ri. Migi-no-Ohotono no ohom-Sitirou, waraha nite syau-no-hue huku. Ito utukusikari kere ba, ohom-zo tamaha su. Otodo ori te butahu si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.16 | 暁近うなりてぞ帰らせたまひける。禄ども、上達部、親王たちには、主上より賜はす。殿上人、楽所の人びとには、宮の御方より品々に賜ひけり。 |
暁が近くなってお帰りあそばした。禄などを、上達部や、親王方には、主上から御下賜になる。殿上人や、楽所の人びとには、宮の御方から身分に応じてお与えになった。 |
もう夜明け近くなってから帝は常の御殿へお帰りになった。 |
Akatuki tikau nari te zo kahera se tamahi keru. Roku-domo, Kamdatime, Miko-tati ni ha, Uhe yori tamahasu. Tenzyau-bito, gakuso no hito-bito ni ha, Miya-no-Ohomkata yori sina-zina ni tamahi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.17 | その夜ふさりなむ、宮まかでさせたてまつりたまひける。儀式いと心ことなり。主上の女房さながら御送り仕うまつらせたまひける。庇の御車にて、庇なき糸毛三つ、黄金づくり六つ、ただの檳榔毛二十、網代二つ、童、下仕へ八人づつさぶらふに、また御迎への出車どもに、本所の人びと乗せてなむありける。御送りの上達部、殿上人、六位など、言ふ限りなききよらを尽くさせたまへり。 |
その夜に、宮をご退出させなさった。その儀式はまことに格別である。主上つきの女房全員にお供をおさせになった。廂のお車で、廂のない糸毛車三台、黄金造りの車六台、普通の檳榔毛の車二十台、網代車二台、童女と、下仕人を八人ずつ伺候させたが、一方お迎えの出車に、本邸の女房たちを乗せてあった。お送りの上達部、殿上人、六位など、何ともいいようなく善美を尽くさせていらっしゃった。 |
その翌晩薫は姫宮を自邸へお迎えして行ったのであった。儀式は |
Sono yohusari nam, Miya makade sase tatematuri tamahi keru. Gisiki ito kokoro koto nari. Uhe no nyoubau sanagara ohom-okuri tukau-matura se tamahi keru. Hisasi no ohom-kuruma nite, hisasi naki itoge mi-tu, kogane-dukuri mu-tu, tada no birauge ni-zihu, aziro huta-tu, waraha, simo-dukahe hati-nin dutu saburahu ni, mata ohom-mukahe no idasi-guruma-domo ni, honzyo no hito-bito nose te nam ari keru. Ohom-okuri no Kamdatime, Tenzyau-bito, roku-wi nado, ihu kagiri naki kiyora wo tukusa se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.18 | かくて、心やすくうちとけて 見たてまつりたまふに、いとをかしげにおはす。ささやかにしめやかにて、ここはと見ゆるところなくおはすれば、「 宿世のほど口惜しからざりけり」と、心おごりせらるるものから、 過ぎにし方の忘らればこそはあらめ、なほ紛るる折なく、もののみ恋しくおぼゆれば、 |
こうして、寛いで拝見なさると、まことに立派でいらっしゃる。小柄で上品でしっとりとして、ここがいけないと見えるところもなくいらっしゃるので、「運命も悪くはなかった」と、心中得意にならずにいらないが、亡くなった姫君が忘れられればよいのだが、やはり気持ちの紛れる時なく、そればかりが恋しく思い出されるので、 |
こうしてお迎えした女二の宮を、薫は妻として心安く観察するようになったが、宮はお美しかった。小柄で上品に落ち着いて、どこという欠点もお持ちにならないのを知って、自分の宿命というものも悪くはないようであると喜んだとはいうものの、それで過去の悲しい恋の傷がいやされたのでは少しもなかった。今もどんな時にも紛れる方もなく昔ばかりが恋しく思われる薫であったから、 |
Kakute, kokoro-yasuku utitoke te mi tatematuri tamahu ni, ito wokasige ni ohasu. Sasayaka ni sime-yaka nite, koko ha to miyuru tokoro naku ohasure ba, "Sukuse no hodo kutiwosikara zari keri." to, kokoro-ogori se raruru monokara, sugi ni si kata no wasura re ba koso ara me, naho magiruru wori naku, mono nomi kohisiku oboyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.19 | 「 この世にては慰めかねつべきわざなめり。 仏になりてこそは、あやしくつらかりける契りのほどを、何の報いと諦めて思ひ離れめ」 |
「この世では慰めきれないことのようである。仏の悟りを得てこそ、不思議でつらかった二人の運命を、何の報いであったのかとはっきり知って諦めよう」 |
自分としては生きているうちにそれに対する慰めは得られないに違いない、仏になってはじめて、恨めしい因縁は何の報いであるということが判然することにより忘られることにもなろう |
"Kono yo nite ha nagusame kane tu beki waza na' meri. Hotoke ni nari te koso ha, ayasiku turakari keru tigiri no hodo wo, nani no mukuyi to akirame te omohi hanare me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7.20 | と思ひつつ、寺の急ぎにのみ心を入れたまへり。 |
と思いながら、寺の造営にばかり心を注いでいらっしゃった。 |
と思い、寺の建築のことにばかり心が行くのであった。 |
to omohi tutu, tera no isogi ni nomi kokoro wo ire tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 4/15/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 4/15/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 4/15/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/2/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経