49 宿木(大島本) |
YADORIGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の中、大納言時代 二十四歳夏から二十六歳夏四月頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Chunagon and Dainagon era, from summer at the age of 24 to April at the age of 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第四章 薫の物語 中君に同情しながら恋慕の情高まる |
4 Tale of Kaoru Kaoru's sympathy and love to Naka-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 第一段 薫、匂宮の結婚につけわが身を顧みる |
4-1 Kaoru considers himself as Nio-no-miya gets married to Roku-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | 中納言殿の御前の中に、なまおぼえあざやかならぬや、暗き紛れに立ちまじりたりけむ、帰りてうち嘆きて、 |
中納言殿の御前駆の中に、あまり待遇がよくなかったのか、暗い物蔭に立ち交じっていたのだろうか、帰って来て嘆いて、 |
源中納言の従者の中に、あまり |
Tyuunagon-dono no go-zen no naka ni, nama-oboye azayaka nara nu ya, kuraki magire ni tati-maziri tari kem, kaheri te uti-nageki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | 「 わが殿の、などかおいらかに、 この殿の御婿にうちならせたまふまじき。あぢきなき御独り住みなりや」 |
「わが殿は、どうしておとなしくて、この殿の婿におなりあそばさないのだろう。つまらない独身生活だよ」 |
「うちの殿様はなぜいざこざをお言いにならないでこちらの殿様の婿におなりにならなかったろう、つまらぬ御独身生活だ」 |
"Waga Tono no, nadoka oyiraka ni, kono Tono no ohom-muko ni uti-nara se tamahu maziki. Adikinaki ohom-hitori-zumi nari ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3 | と、中門のもとにてつぶやきけるを 聞きつけたまひて、をかしとなむ思しける。 夜の更けてねぶたきに、かのもてかしづかれつる人びとは、心地よげに酔ひ乱れて寄り臥しぬらむかしと、うらやましきなめりかし。 |
と、中門の側でぶつぶつ言っていたのをお聞きつけになって、おかしくお思いになるのであった。夜が更けて眠たいのに、あの歓待されている人びとは、気持ちよさそうに酔い乱れて寄り臥せってしまったのだろうと、羨ましいようである。 |
と中門の所でつぶやいているのが耳にはいって中納言はおかしく思った。自身たちは夜ふけまで待たされていて、ただつまらぬ眠さを覚えさせられているだけであるのと、婿君の従者が美酒に酔わされて快くどこかの座敷で身を横たえているらしく思われるのとを比較してみてうらやましかったのであろう。 |
to, tyuumon no moto nite tubuyaki keru wo kiki-tuke tamahi te, wokasi to nam obosi keru. Yo no huke te nebutaki ni, kano mote-kasiduka re turu hito-bito ha, kokoti-yoge ni wehi midare te yori-husi nu ram kasi to, urayamasiki na' meri kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.4 | 君は、入りて臥したまひて、 |
君は、部屋に入ってお臥せりになって、 |
薫は家に入り寝室で横になりながら、 |
Kimi ha, iri te husi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.5 | 「 はしたなげなるわざかな。ことことしげなるさましたる親の出でゐて、 離れぬなからひなれど、これかれ、火明くかかげて、勧めきこゆる盃などを、いとめやすくもてなしたまふめりつるかな」 |
「きまりの悪いことだなあ。仰々しい父親が出て来て座って、縁遠くはない仲だが、あちこちに、火を明るく掲げて、お勧め申した盃事などを、とても体裁よくお振る舞いになったな」 |
新しい婿として式に臨むことはきまりの悪そうなことである、たいそうな |
"Hasitanage naru waza kana! Koto-kotosige naru sama si taru oya no ide wi te, hanare nu nakara hi nare do, kore kare, hi akaku kakage te, susume kikoyuru sakaduki nado wo, ito meyasuku motenasi tamahu meri turu kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.6 | と、宮の御ありさまを、めやすく思ひ出でたてまつりたまふ。 |
と、宮のお振舞を、無難であったとお思い出し申し上げなさる。 |
のはごりっぱなものであったなどと思い出していた。 |
to, Miya no ohom-arisama wo, meyasuku omohi-ide tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.7 | 「 げに、我にても、よしと思ふ 女子持たらましかば、この 宮をおきたてまつりて、内裏にだにえ参らせざらまし」と思ふに、「 誰れも誰れも、宮にたてまつらむと心ざしたまへる女は、なほ 源中納言にこそと、とりどりに 言ひならふなるこそ、わがおぼえの口惜しくはあらぬなめりな。さるは、 いとあまり世づかず、古めきたるものを」など、心おごりせらる。 |
「なるほど、自分でも、良いと思う女の子を持っていたら、この宮をお措き申しては、宮中にさえ入内させないだろう」と思うと、「誰も彼もが、宮に差し上げたいと志していらっしゃる娘は、やはり源中納言にこそと、それぞれ言っているらしいことは、自分の評判がつまらないものではないのだな。実のところは、あまり結婚に関心もなく、ぱっとしないのに」などと、大きな気持ちにおなりになる。 |
それは実際自分でもすぐれた娘というようなものを持っていれば、この宮以外には御所へでもお上げする気にはなれなかったであろうと思われた薫は、どこの家でも |
"Geni, ware nite mo, yosi to omohu womna-go mo' tara masika ba, kono Miya wo oki tatematuri te, Uti ni dani e mawira se zara masi." to omohu ni, "Tare mo tare mo, Miya ni tatematura m to kokorozasi tamahe ru musume ha, naho Gen-Tyuunagon ni koso to, tori-dori ni ihi narahu naru koso, wa ga oboye no kutiwosiku ha ara nu na' meri na. Saruha, ito amari yo-duka zu, hurumeki taru mono wo." nado, kokoro-ogori se raru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.8 | 「 内裏の御けしきあること、まことに 思したたむに、かくのみもの憂くおぼえば、いかがすべからむ。おもだたしきことにはありとも、いかがはあらむ。いかにぞ、 故君にいとよく似たまへらむ時に、うれしからむかし」と思ひ寄らるるは、 さすがにもて離るまじき心なめりかし。 |
「帝の御内意のあることが、本当に御決意なさったら、このようにばかり何となく億劫にばかり思っていたら、どうしたものだろう。面目がましいことではあるが、どんなものだろうか。どうかな、亡くなった姫君にとてもよく似ていらっしゃったら、嬉しいことだろう」と自然と思い寄るのは、やはりまったく関心がないではないのであろうよ。 |
内親王を賜わるという帝の |
"Uti no mi-kesiki aru koto, makoto ni obosi tata m ni, kaku nomi mono-uku oboye ba, ikaga su bekara m? Omodatasiki koto ni ha ari tomo, ikagaha ara m? Ikani zo, ko-Kimi ni ito yoku ni tamahe ra m toki ni, uresikara m kasi." to omohi yora ruru ha, sasuga ni mote hanaru maziki na' meri kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 第二段 薫と按察使の君、匂宮と六の君 |
4-2 Kaoru and his girlfriend Azechi-no-kimi, Nio-no-miya and Roku-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | 例の、寝覚がちなるつれづれなれば、 按察使の君とて、人よりはすこし思ひましたまへるが局におはして、その夜は明かしたまひつ。明け過ぎたらむを、人の咎むべきにもあらぬに、苦しげに急ぎ起きたまふを、 ただならず思ふべかめり。 |
いつものように、寝覚めがちな何もすることのないころなので、按察使の君といって、他の女房よりは少し気に入っていらっしゃる者の部屋にいらして、その夜は明かしなさった。夜の明け過ぎても、誰も非難するはずもないのに、つらそうに急いで起きなさるので、平気ではいられないようである。 |
例のような目のさめがちな |
Rei no, nezame-gati naru ture-dure nare ba, Azeti-no-Kimi tote, hito yori ha sukosi omohi-masi tamahe ru ga tubone ni ohasi te, sono yo ha akasi tamahi tu. Ake sugi tara m wo, hito no togamu beki ni mo ara nu ni, kurusige ni isogi oki tamahu wo, tada nara zu omohu beka' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | 「 うち渡し世に許しなき関川を |
「いったいに世間から認められない仲なのに |
うち渡し世に許しなき関川を |
"Uti-watasi yo ni yurusi naki Seki-kaha wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.3 | みなれそめけむ名こそ惜しけれ」 |
お逢いし続けているという評判が立つのが辛うございます」 |
みなれそめけん名こそ惜しけれ |
minare some kem na koso wosikere |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.4 | いとほしければ、 |
気の毒なので、 |
と按察使は言った。哀れに思われて、 |
Itohosikere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.5 | 「 深からず上は見ゆれど関川の |
「深くないように表面は見えますが |
深からず上は見ゆれど関川の |
"Hukakara zu uhe ha miyure do Seki-kaha no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.6 | 下の通ひは絶ゆるものかは」 |
心の底では愛情の絶えることはありません」 |
しもの通ひは絶ゆるものかは |
sita no kayohi ha tayuru mono kaha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
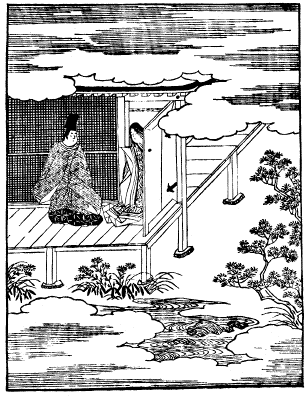 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.7 | 深しと、のたまはむにてだに頼もしげなきを、 この上の浅さは、いとど心やましくおぼゆらむかし。妻戸押し開けて、 |
深いと、おっしゃるだけでも頼りないのを、これ以上の浅さは、ますますつらく嫌に思われるであろうよ。妻戸を押し開けて、 |
薫はこう言った。恋の心は深いと言われてさえ頼みにならぬものであるのに、上は浅いと認めて言われるのに女は苦痛を覚えなかったはずはない。妻戸を薫はあけて、 |
Hukasi to, notamaha m nite dani tanomosige naki wo, kono uhe no asasa ha, itodo kokoro-yamasiku oboyura m kasi. Tumado osi-ake te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.8 | 「 まことは、この空見たまへ。いかでかこれを知らず顔にては明かさむとよ。艶なる人まねにてはあらで、いとど明かしがたくなり行く、夜な夜なの寝覚には、この世 かの世までなむ思ひやられて、あはれなる」 |
「ほんとうは、この空を御覧なさい。どうしてこれを知らない顔で夜を明かそうかよ。風流人を気取るのではないが、ますます明かしがたくなってゆく、夜々の寝覚めには、この世やあの世まで思い馳せられて、しんみりする」 |
「この夜明けの空のよさを思って早く出て見たかったのだ。こんな深い趣を味わおうとしない人の気が知れないね、風流がる男ではないが、夜長を苦しんで明かしたのちの秋の |
"Makoto ha, kono sora mi tamahe. Ikadeka kore wo sira-zu-gaho nite ha akasa m to yo! En naru hito-mane nite ha ara de, itodo akasi gataku nari yuku, yo-na yo-na no ne-zame ni ha, konoyo ka-no-yo made nam omohi-yara re te, ahare naru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.9 | など、言ひ紛らはしてぞ出でたまふ。ことにをかしきことの数を尽くさねど、 さまのなまめかしき見なしにやあらむ ★、情けなくなどは人に思はれたまはず。 かりそめの戯れ言をも言ひそめたまへる人の、気近くて見たてまつらばや、とのみ思ひきこゆるにや、あながちに、 世を背きたまへる宮の御方に、 縁を尋ねつつ参り集まりてさぶらふも、あはれなること、ほどほどにつけつつ多かるべし。 |
などと、言い紛らわしてお出になる。特に趣きのある言葉の数々は尽くさないが、態度が優美に見えるせいであろうか、情けのない人のようには誰からも思われなさらない。ちょっとした冗談を言いかけなさった女房で、お側近くに拝見したい、とばかりお思い申しているのか、強引に、出家なさった宮の御方に、縁故を頼っては頼って参集して仕えているのも、気の毒なことが、身分に応じて多いのであろう。 |
こんなことを紛らして言いながら薫は出て行った。女を喜ばそうとして |
nado, ihi-magirahasi te zo ide tamahu. Koto ni wokasiki koto no kazu wo tukusa ne do, sama no namamekasiki mi-nasi ni ya ara m, nasakenaku nado ha hito ni omoha re tamaha zu. Karisome no tahabure-goto wo mo ihi some tamahe ru hito no, ke-dikaku te mi tatematura baya, to nomi omohi kikoyuru ni ya, anagati ni, yo wo somuki tamahe ru Miya-no-Ohomkata ni, en wo tadune tutu mawiri atumari te saburahu mo, ahare naru koto, hodo-hodo ni tuke tutu ohokaru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.10 | 宮は、女君の御ありさま、昼見きこえたまふに、いとど御心ざしまさりけり。おほきさよきほどなる人の、様体いときよげにて、髪のさがりば、頭つきなどぞ、ものよりことに、あなめでた、と見えたまひける。 色あひあまりなるまで匂ひて、ものものしく気高き顔の、まみいと恥づかしげにらうらうじく、すべて何ごとも足らひて、容貌よき人と言はむに、飽かぬところなし。 |
宮は、女君のご様子、昼間に拝見なさると、ますますお気持ちが深くなるのであった。背恰好も程よい人で、姿態はたいそう美しくて、髪のさがり具合、頭の恰好などは、人より格別にすぐれて、まあ素晴らしい、とお見えになるのであった。色艶があまりにもつやつやとして、堂々とした気品のある顔で、目もとがとてもこちらが恥ずかしくなるほど美しくかわいらしく、何から何まで揃っていて、器量のよい人というのに、足りないところがない。 |
兵部卿の宮は式のあったのちの日に新夫人を昼間御覧になることによって、いっそう深い愛をお覚えになった。中くらいな |
Miya ha, Womna-Gimi no ohom-arisama, hiru mi kikoye tamahu ni, itodo mi-kokorozasi masari keri. Ohokisa yoki hodo naru hito no, yaudai ito kiyoge nite, kami no sagariba, kasira-tuki nado zo, mono yori koto ni, ana medeta, to miye tamahi keru. Iro-ahi amari naru made nihohi te, mono-monosiku kedakaki kaho no, mami ito hadukasige ni rau-rauziku, subete nani-goto mo tarahi te, katati yoki hito to iha m ni, aka nu tokoro nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.11 | 二十に一つ二つぞ余りたまへりける。いはけなきほどならねば、片なりに飽かぬところなく、あざやかに、盛りの花と見えたまへり。限りなくもてかしづきたまへるに、かたほならず。 げに、親にては、心も惑はしたまひつべかりけり ★。 |
二十歳を一、二歳越えていらっしゃった。幼い年ではないので、不十分で足りないところはなく、華やかで、花盛りのようにお見えになっていた。この上なく大事にお世話なさっていたので、不十分なところがない。なるほど、親としては、夢中になるのも無理からぬことであった。 |
二十一、二であった。少女ではないから完成されぬところもなくて |
Ni-zihu ni hito-tu huta-tu zo amari tamahe ri keru. Ihakenaki hodo nara ne ba, kata-nari ni aka nu tokoro naku, azayaka ni, sakari no hana to miye tamahe ri. Kagiri naku mote-kasiduki tamahe ru ni, kataho nara zu. Geni, oya nite ha, kokoro mo madohasi tamahi tu bekari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.12 | ただ、やはらかに愛敬づきらうたきことぞ、かの対の御方はまづ思ほし出でられける。 もののたまふいらへなども、恥ぢらひたれど、また、あまりおぼつかなくはあらず、すべていと見所多く、かどかどしげなり。 |
ただ、もの柔らかで魅力的でかわいらしい点では、あの対の御方がまっさきにお心に浮かぶのであった。何かおっしゃるお返事なども、恥じらっていらっしゃるが、また、あまりにはっきりしないことはなく、総じて実にとりえが多くて、才気がありそうである。 |
ただ柔らかで |
Tada, yaharaka ni aigyau-duki rautaki koto zo, kano Tai-no-Ohomkata ha madu omohosi-ide rare keru. Mono notamahu irahe nado mo, hadirahi tare do, mata, amari obotukanaku ha ara zu, subete ito mi-dokoro ohoku, kado-kadosige nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.13 | よき若人ども三十人ばかり、童六人、かたほなるなく、装束なども、例のうるはしきことは、目馴れて思さるべかめれば、引き違へ、心得ぬまでぞ好みそしたまへる。 三条殿腹の大君を、春宮に参らせたまへるよりも、この御ことをば、ことに思ひおきてきこえたまへるも、宮の御おぼえありさまからなめり。 |
器量のよい若い女房連中を三十人ほど、童女を六人、整っていないのはなく、装束なども、例によって格式ばったことは、目馴れてお思いになるだろうから、変わって、いかがと思われるまで趣向をお凝らしになっていた。三条殿腹の大君を、東宮に参内させなさった時よりも、この儀式を、特別にお考えおきなさっていたのも、宮のご評判や様子からのようである。 |
きれいな若い女房が三十人ほど、童女六人が姫君付きで、そうした人の服装なども、きらきらしいものは飽くほど見ておいでになる |
Yoki wakaudo-domo sam-zihu-nin bakari, waraha roku-nin, kataho naru naku, syauzoku nado mo, rei no uruhasiki koto ha, me-nare te obosa ru beka' mere ba, hiki-tagahe, kokoro-e nu made zo konomi sosi tamahe ru. Samdeu-dono-bara no Ohoi-Kimi wo, Touguu ni mawira se tamahe ru yori mo, kono ohom-koto wo ba, koto ni omohi oki te kikoye tamahe ru mo, Miya no ohom-oboye arisama kara na' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 第三段 中君と薫、手紙を書き交す |
4-3 Naka-no-kimi and Kaoru send a letter each other |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | かくて後、二条院に、え心やすく渡りたまはず。軽らかなる御身ならねば、思すままに、昼のほどなどもえ出でたまはねば、 やがて同じ南の町に、年ごろありしやうにおはしまして、暮るれば、また、 え引き避きても渡りたまはずなどして、待ち遠なる折々あるを、 |
こうして後は、二条院に、気安くお渡りになれない。軽々しいご身分でないので、お考えのままに、昼間の時間もお出になることができないので、そのまま同じ六条院の南の町に、以前に住んでいたようにおいでになって、暮れると、再び、この君を避けてあちらへお渡りになることもできないなどして、待ち遠しい時々があるが、 |
それからのちの宮は二条の院へ気安くおいでになることもおできにならなかった。軽い御身分でなかったから、昼間をそちらへ行っておいでになるということもむずかしくて、六条院の中の南の御殿に以前ずっとおいでになったようにしてお住みになり、日が暮れると東御殿を |
Kakute noti, Nideu-no-win ni, e kokoro-yasuku watari tamaha zu. Karuraka naru ohom-mi nara ne ba, obosu mama ni, hiru no hodo nado mo e ide tamaha ne ba, yagate onazi minami-no-mati ni, tosi-goro ari si yau ni ohasimasi te, kurure ba, mata, e hiki-yoki te mo watari tamaha zu nado si te, mati-doho naru wori-wori aru wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.2 | 「 かからむとすることとは思ひしかど、さしあたりては、いとかくやは名残なかるべき。 げに、心あらむ人は、数ならぬ身を知らで、交じらふべき世にもあらざりけり」 |
「このようなことになるとは思っていたが、当面すると、まるっきり変わってしまうものであろうか。なるほど、思慮深い人は、物の数にも入らない身分で、結婚すべきではなかった」 |
すぐにも露骨に冷淡なお扱いを受けることになったではないか、賢い人であれば自分の無価値さをよく知って京へまでは出て来なかったはずであったと、 |
"Kakara m to suru koto to ha omohi sika do, sasi-atari te ha, ito kaku ya ha nagori nakaru beki. Geni, kokoro ara m hito ha, kazu nara nu mi wo sira de, mazirahu beki yo ni mo ara zari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.3 | と、返す返すも山路分け出でけむほど、うつつともおぼえず悔しく悲しければ、 |
と、繰り返し山里を出て来た当座のことを、現実とも思われず悔しく悲しいので、 |
今になっては返す返す宇治を離れて来たことが正気をもってしたこととは思えなくて悲しい中の君は、 |
to, kahesu-gahesu mo yamadi wake-ide kem hodo, ututu to mo oboye zu kuyasiku kanasikere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.4 | 「 なほ、いかで忍びて 渡りなむ。むげに背くさまにはあらずとも、しばし心をも慰めばや。憎げにもてなしなどせばこそ、うたてもあらめ」 |
「やはり、何とかしてこっそりと帰りたい。まるっきり縁が切れるというのでなくとも、暫く気を休めたいものだ。憎らしそうに振る舞ったら、嫌なことであろう」 |
やはりどうともして宇治へ行くことにしたい、ここを捨てて行くふうではなくて、あちらでしばらくでも心を休めたい、反抗的に行なえば人聞きも悪いであろうが、それならばいいはずである、 |
"Naho, ikade sinobi te watari na m. Muge ni somuku sama ni ha ara zu tomo, sibasi kokoro wo mo nagusame baya! Nikuge ni motenasi nado se ba koso, utate mo ara me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.5 | など、心一つに思ひあまりて、恥づかしけれど、中納言殿に文たてまつれたまふ。 |
などと、胸一つに思いあまって、恥ずかしいが、中納言殿に手紙を差し上げなさる。 |
とこの |
nado, kokoro hito-tu ni omohi amari te, hadukasikere do, Tyuunagon-dono ni humi tatemature tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.6 | 「 一日の御ことをば、阿闍梨の伝へたりしに、詳しく聞きはべりにき。 かかる御心の名残なからましかば、いかに いとほしくと思ひたまへらるるにも、おろかならずのみなむ。 さりぬべくは、みづからも ★」 |
「先日の御事は、阿闍梨が伝えてくれたので、詳しくお聞きしました。このようなご親切がなかったら、どんなにかおいたわしいことかと存じられますにつけても、深く感謝申し上げております。できますことなら、親しくお礼を」 |
父君の仏事の日のことは |
"Hito-hi no ohom-koto wo ba, Azyari no tutahe tari si ni, kuhasiku kiki haberi ni ki. Kakaru mi-kokoro no nagori nakara masika ba, ikani itohosiku to omohi tamahe raruru ni mo, oroka nara zu nomi nam. Sari nu beku ha, midukara mo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.7 | と聞こえたまへり。 |
と申し上げなさった。 |
という |
to kikoye tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.8 | 陸奥紙に、ひきつくろはずまめだち書きたまへるしも、いとをかしげなり。宮の御忌日に、例のことどもいと尊くせさせたまへりけるを、喜びたまへるさまの、おどろおどろしくはあらねど、 げに、思ひ知りたまへるなめりかし。例は、これよりたてまつる御返りをだに、つつましげに思ほして、はかばかしくも続けたまはぬを、「みづから」とさへのたまへるが、めづらしくうれしきに、 心ときめきもしぬべし。 |
陸奥紙に、しゃれないできちんとお書きになっているのが、実に美しい。宮のご命日に、例の法事をとても尊くおさせになったのを、喜んでいらっしゃる様子が、仰々しくはないが、なるほど、お分かりになったようである。いつもは、こちらから差し上げるお返事でさえ、遠慮深そうにお思いになって、てきぱきともお書きにならないのに、「親しくお礼を」とまでおっしゃったのが、珍しく嬉しいので、心ときめきするにちがいない。 |
檀紙の上の字も |
Mitinokuni-gami ni, hiki-tukuroha zu mame-dati kaki tamahe ru simo, ito wokasige nari. Miya no ohom-ki-niti ni, rei no koto-domo ito tahutoku se sase tamahe ri keru wo, yorokobi tamahe ru sama no, odoro-odorosiku ha ara ne do, geni, omohi siri tamahe ru na' meri kasi. Rei ha, kore yori tatematuru ohom-kaheri wo dani, tutumasige ni omohosi te, haka-bakasiku mo tuduke tamaha nu wo, "Midukara" to sahe notamahe ru ga, medurasiku uresiki ni, kokoro-tokimeki mo si nu besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.9 | 宮の今めかしく好みたちたまへるほどにて、 思しおこたりけるも、げに心苦しく推し量らるれば、いとあはれにて、をかしやかなることもなき御文を、うちも置かず、ひき返しひき返し見ゐたまへり。御返りは、 |
宮が新しい女性に関心を寄せていらっしゃる時なので、疎かにお扱いになっていたのも、なるほどおいたわしく推察されるので、たいそう気の毒になって、風流なこともないお手紙を、下にも置かず、繰り返し繰り返し御覧になっていた。お返事は、 |
宮がお得になったはなやかな生活に心が多くお引かれになって、二条の院へはよくもおいでにならないことについての中の君の |
Miya no imamekasiku konomi tati tamahe ru hodo nite, obosi okotari keru mo, geni kokoro-gurusiku osihakara rure ba, ito ahare ni te, wokasiyaka naru koto mo naki ohom-humi wo, uti mo oka zu, hiki-kahesi hiki-kahesi mi wi tamahe ri. Ohom-kaheri ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.10 | 「 承りぬ。一日は、聖だちたるさまにて、ことさらに忍びはべしも、さ思ひたまふるやうはべるころほひにてなむ。名残とのたまはせたるこそ、 すこし浅くなりにたるやうにと、恨めしく思うたまへらるれ。よろづはさぶらひてなむ。 あなかしこ」 |
「承知いたしました。先日は、修行者のような恰好で、わざとこっそり参りましたが、そのように考えますような事情がございましたときですので。引き続いてとおっしゃってくださるのは、わたしの気持ちが少し薄くなったようだからかと、恨めしく存じられます。何もかも伺いましてから。恐惶謹言」 |
承りました。先日は僧のようなことを多く申して、昔のことばかりを歎いた私でしたが、それは追想にとらわれざるをえない時節だったからです。名残とお書きになりましたことで、私が故人の宮様にお持ちする感情を少し浅く御覧になっていらっしゃるのではないかと恨めしくなります。何も皆近く参上してお話しいたしましょう。 |
"Uketamahari nu. Hito-hi ha, hiziri-dati taru sama nite, kotosara ni sinobi habe si mo, sa omohi tamahuru yau haberu korohohi nite nam. Nagori to notamaha se taru koso, sukosi asaku nari ni taru yau ni to, uramesiku omou tamahe rarure. Yorodu ha saburahi te nam. Ana kasiko." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.11 | と、すくよかに、白き色紙のこはごはしきにてあり。 |
と、きまじめに、白い色紙でごわごわとしたのに書いてある。 |
と、きまじめな文章が、白い厚い色紙に書いて送られた。 |
to, sukuyoka ni, siroki sikisi no koha-gohasiki ni te ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 第四段 薫、中君を訪問して慰める |
4-4 Kaoru visits and comforts Naka-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.1 | さて、またの日の夕つ方ぞ渡りたまへる。人知れず思ふ心し添ひたれば、あいなく心づかひいたくせられて、なよよかなる御衣どもを、いとど匂はし添へたまへるは、あまりおどろおどろしきまであるに、丁子染の扇の、もてならしたまへる移り香などさへ、喩へむ方なくめでたし。 |
そうして、翌日の夕方にお渡りになった。人知れず思う気持ちがあるので、無性に気づかいがされて、柔らかなお召し物類を、ますます匂わしなさっているのは、あまりに大げさなまでにあるので、丁子染の扇の、お持ちつけになっている移り香などまでが、譬えようもなく素晴らしい。 |
|
Sate, mata no hi no yuhu-tu-kata zo watari tamahe ru. Hito-sire-zu omohu kokoro si sohi tare ba, ainaku kokoro-dukahi itaku se rare te, nayoyoka naru ohom-zo-domo wo, itodo nihohasi sohe tamahe ru ha, amari odoro-odorosiki made aru ni, tyauzi-zome no ahugi no, mote-narasi tamahe ru uturiga nado sahe, tatohe m kata naku medetasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.2 | 女君も、 あやしかりし夜のことなど、思ひ出でたまふ折々なきにしもあらねば、まめやかにあはれなる御心ばへの、人に似ずものしたまふを見るにつけても、「 さてあらましを」とばかりは思ひやしたまふらむ。 |
女君も、不思議な事であった夜のことなどを、お思い出しになる折々がないではないので、誠実で情け深いお気持ちが、誰とも違っていらっしゃるのを見るにつけても、「この人と一緒になればよかった」とお思いになるのだろう。 |
中の君も昔のあの夜のことが思い出されることもないのではなかったから、父宮と姉君への愛の深さが認識されるにつけても、運命が姉の意志のままになっていたのであったらと心の動揺を覚えたかもしれない。 |
Womna-Gimi mo, ayasikari si yo no koto nado, omohi-ide tamahu wori-wori naki ni simo ara ne ba, mameyaka ni ahare naru mi-kokorobahe no, hito ni ni zu monosi tamahu wo miru ni tuke te mo, "Sate ara masi mono wo." to bakari ha omohi ya si tamahu ram. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.3 | いはけなきほどにしおはせねば、恨めしき人の御ありさまを思ひ比ぶるには、何事もいとどこよなく 思ひ知られたまふにや、常に隔て多かるもいとほしく、「 もの思ひ知らぬさまに思ひたまふらむ」など思ひたまひて、今日は、御簾の内に入れたてまつりたまひて、母屋の簾に几帳添へて、我はすこしひき入りて対面したまへり。 |
幼いお年でもいらっしゃらないので、恨めしい方のご様子を比較すると、何事もますますこの上なく思い知られなさるのか、いつも隔てが多いのもお気の毒で、「物の道理を弁えないとお思いなさるだろう」などとお思いになって、今日は、御簾の内側にお入れ申し上げなさって、母屋の御簾に几帳を添えて、自分は少し奥に入ってお会いなさった。 |
少女ではないのであるから、恨めしい方の心と比べてみて、何につけてもりっぱな薫がわかったのか、平生あまりに遠々しくもてなしていて気の毒であった、人情にうとい女だとこの人が思うかもしれぬと思い、今日は前の室の |
Ihakenaki hodo ni si ohase ne ba, uramesiki hito no ohom-arisama wo omohi kuraburu ni ha, nani-goto mo itodo koyonaku omohi-sira re tamahu ni ya, tune ni hedate ohokaru mo itohosiku, "Mono omohi sira nu sama ni omohi tamahu ram." nado omohi tamahi te, kehu ha, mi-su no uti ni ire tatematuri tamahi te, moya no sudare ni kityau sohe te, ware ha sukosi hiki-iri te taimen si tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.4 | 「 わざと召しとはべらざりしかど、例ならず許させたまへりし喜びに、すなはちも参らまほしくはべりしを、宮渡らせたまふと承りしかば、折悪しくやはとて、今日になしはべりにける。さるは、年ごろの心のしるしもやうやうあらはれはべるにや、隔てすこし薄らぎはべりにける御簾の内よ。めづらしくはべるわざかな」 |
「特にお呼びということではございませんでしたが、いつもと違ってお許しあそばしたお礼に、すぐにも参上したく思いましたが、宮がお渡りあそばすとお聞きいたしましたので、折が悪くてはと思って、今日にいたしました。一方では、長年の誠意もだんだん分かっていただけましたのか、隔てが少し薄らぎました御簾の内ですね。珍しいことですね」 |
「お招きくだすったのではありませんが、来てもよろしいとのお許しが珍しくいただけましたお礼に、すぐにもまいりたかったのですが、宮様が来ておいでになると承ったものですから、御都合がお悪いかもしれぬと御遠慮を申して今日にいたしました。これは長い間の私の誠意がようやく認められてまいったのでしょうか。遠さの少し減った御簾の中へお席をいただくことにもなりました。珍しいですね」 |
"Wazato mesi to habera zari sika do, rei nara zu yurusa se tamahe ri si yorokobi ni, sunahati mo mawira mahosiku haberi si wo, Miya watara se tamahu to uketamahari sika ba, wori asiku yaha tote, kehu ni nasi haberi ni keru. Saruha, tosi-goro no kokoro no sirusi mo yau-yau arahare haberu ni ya, hedate sukosi usuragi haberi ni keru mi-su no uti yo. Medurasiku haberu waza kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.5 | とのたまふに、 なほいと恥づかしく、言ひ出でむ言葉もなき心地すれど、 |
とおっしゃるが、やはりとても恥ずかしくて、言い出す言葉もない気がするが、 |
と薫の言うのを聞いて、中の君はさすがにまた恥ずかしくなり、言葉が出ないように思うのであったが、 |
to notamahu ni, naho ito hadukasiku, ihi-ide m kotoba mo naki kokoti sure do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.6 | 「 一日、うれしく聞きはべりし心の内を、例の、ただ結ぼほれながら過ぐしはべりなば、思ひ知る片端をだに、いかでかはと、口惜しさに」 |
「先日、嬉しく聞きました心の中を、いつものように、ただ仕舞い込んだまま過ごしてしまったら、感謝の気持ちの一部分だけでも、何とかして知ってもらえようかと、口惜しいので」 |
「この間の御親切なお計らいを聞きまして、感激いたしました心を、いつものようによく申し上げもいたしませんでは、どんなに私がありがたく存じておりますかしれませんような気持ちの一端をさえおわかりになりますまいと残念だったものですから」 |
"Hito-hi, uresiku kiki haberi si kokoro no uti wo, rei no, tada musubohore nagara sugusi haberi na ba, omohi-siru katahasi wo dani, ikadekaha to, kutiwosisa ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.7 | と、いとつつましげにのたまふが、 いたくしぞきて、絶え絶えほのかに聞こゆれば、心もとなくて、 |
と、いかにも慎ましそうにおっしゃるのが、たいそう奥の方に身を引いて、途切れ途切れにかすかに申し上げるので、もどかしく思って、 |
と |
to, ito tutumasige ni notamahu ga, itaku sizoki te, taye-daye honoka ni kikoyure ba, kokoro-motonaku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.8 | 「 いと遠くもはべるかな。まめやかに聞こえさせ、承らまほしき世の御物語もはべるものを」 |
「とても遠くでございますね。心からお話し申し上げ、またお聞き致したい世間話もございますので」 |
「たいへん遠いではありませんか。細かなお話もし、あなたからも承りたい昔のお話もあるのですから」 |
"Ito tohoku mo haberu kana! Mameyaka ni kokoye sase, uketamahara mahosiki yo no ohom-monogatari mo haberu mono wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.9 | とのたまへば、 げに、と思して、すこしみじろき寄りたまふけはひを聞きたまふにも、ふと胸うちつぶるれど、さりげなくいとど静めたるさまして、宮の 御心ばへ、思はずに 浅う おはしけりとおぼしく、かつは 言ひも疎め、また慰めも、かたがたにしづしづと聞こえたまひつつおはす。 |
とおっしゃると、なるほど、とお思いになって、少しいざり出てお近寄りになる様子をお聞きなさるにつけても、胸がどきりとするが、平静を装いますます冷静な態度をして、宮のご愛情が、意外にも浅くおいでであったとお思いで、一方では批判したり、また一方では慰めたりして、それぞれについて落ち着いて申し上げていらっしゃる。 |
こう言われて中の君は道理に思い、少し身じろぎをして几帳のほうへ寄って来たかすかな音にさえ、衝動を感じる薫であったが、さりげなくいっそう冷静な様子を作りながら、宮の御誠意が案外浅いものであったとお |
to notamahe ba, geni, to obosi te, sukosi miziroki yori tamahu kehahi wo kiki tamahu ni mo, huto mune uti-tuburure do, sarige-naku itodo sidume taru sama si te, Miya no mi-kokorobahe, omoha zu ni asau ohasi keri to obosi ku, katu ha ihi mo utome, mata nagusame mo, kata-gata ni sidu-sidu to kikoye tamahi tutu ohasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 第五段 中君、薫に宇治への同行を願う |
4-5 Naka-no-kimi asks Kaoru to take her with him to Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.1 | 女君は、人の御恨めしさなどは、うち出で語らひきこえたまふべきことにもあらねば、 ただ、世やは憂きなどやうに思はせて ★、言少なに紛らはしつつ、山里にあからさまに渡したまへとおぼしく、いとねむごろに思ひてのたふ。 |
女君は、宮の恨めしさなどは、口に出して申し上げなさるようなことでもないので、ただ、自分だけがつらいように思わせて、言葉少なに紛らわしては、山里にこっそりとお連れくださいとのお思いで、たいそう熱心に申し上げなさる。 |
中の君としては宮をお恨めしく思う心などは表へ出してよいことではないのであるから、ただ人生を悲しく恨めしく思っているというふうに紛らして、言葉少なに |
Womna-Gimi ha, hito no ohom-uramesisa nado ha, uti-ide katarahi kikoye tamahu beki koto ni mo ara ne ba, tada, yo yaha uki nado yau ni omohase te, koto-zukuna ni magirahasi tutu, yama-zato ni akarasama ni watasi tamahe to obosiku, ito nemgoro no omohi te notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.2 | 「 それはしも、心一つにまかせては、え仕うまつるまじきことにはべり。なほ、宮にただ心うつくしく 聞こえさせたまひて、かの御けしきに従ひてなむよくはべるべき。さらずは、すこしも違ひ目ありて、心軽くもなど思しものせむに、いと悪しくはべりなむ。さだにあるまじくは、道のほども御送り迎へも、おりたちて仕うまつらむに、何の憚りかははべらむ。うしろやすく人に似ぬ心のほどは、宮も皆知らせたまへり」 |
「そのことは、わたしの一存では、お世話できないことです。やはり、宮にただ素直にお話し申し上げなさって、あの方のご様子に従うのがよいことです。そうでなかったら、少しでも行き違いが生じて、軽率だなどとお考えになるだろうから、大変悪いことになりましょう。そういう心配さえなければ、道中のお送りや迎えも、自らお世話申しても、何の遠慮がございましょう。安心で人と違った性分は、宮もみなご存知でいらっしゃいました」 |
「その問題だけは私の一存でお受け合いすることができかねます。宮様へ |
"Sore ha simo, kokoro hitotu ni makase te ha, e tukau-maturu maziki koto ni haberi. Naho, Miya ni tada kokoro utukusiku kikoye sase tamahi te, kano mi-kesiki ni sitagahi te nam yoku haberu beki. Sara zu ha, sukosi mo tagahi-me ari te, kokoro karoku mo nado obosi monose m ni, ito asiku haberi na m. Sa dani arumaziku ha, miti no hodo mo ohom-okuri mukahe mo, oritati te tukau-matura m ni, nani no habakari kaha habera m. Usiroyasuku hito ni ni nu kokoro no hodo ha, Miya mo mina sirase tamaeh ri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.3 | などは言ひながら、折々は、過ぎにし方の悔しさを忘るる折なく、 ものにもがなやと、取り返さまほしき ★と、ほのめかしつつ、やうやう暗くなりゆくまでおはするに、いとうるさくおぼえて、 |
などと言いながら、時々は、過ぎ去った昔の悔しさが忘れる折もなく、できることなら昔を今に取り戻したいと、ほのめかしながら、だんだん暗くなって行くまでおいでになるので、とてもわずらわしくなって、 |
こんなことを言いながらも、話の中に自分は過去にしそこねた結婚について後悔する念に支配ばかりされていて、もう一度昔を今にする |
nado ha ihi nagara, wori-wori ha, sugi ni si kata no kuyasisa wo wasururu wori naku, mono ni mo gana ya to, torikahesa mahosiki to, honomekasi tutu, yau-yau kuraku nari-yuku made ohasuru ni, ito urusaku oboye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.4 | 「 さらば、心地も悩ましくのみはべるを、また、よろしく思ひたまへられむほどに、何事も」 |
「それでは、気分も悪くなるばかりですので、また、よおろしくなった折に、どのような事でも」 |
「それではまた、私は |
"Saraba, kokoti mo nayamasiku nomi haberu wo, mata, yorosiku omohi tamahe rare m hodo ni, nani-goto mo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.5 | とて、入りたまひぬるけしきなるが、いと口惜しければ、 |
と言って、お入りになってしまった様子なのが、とても残念なので、 |
と言い、引っ込んで行ってしまいそうになったのが残念に思われて、薫は、 |
tote, iri tamahi nuru kesiki naru ga, ito kutiwosikere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.6 | 「 さても、いつばかり思し立つべきにか。いとしげくはべし道の草も、すこしうち払はせはべらむかし」 |
「それでは、いつごろにお立ちになるつもりですか。たいそう茂っていた道の草も、少し刈り払わせましょう」 |
「それにしてもいつごろ宇治へおいでになろうとお思いになるのですか。伸びてひどくなっていました庭の草なども少しきれいにさせておきたいと思います」 |
"Satemo, itu bakari obosi-tatu beki ni ka. Ito sigeku habe' si miti no kusa mo, sukosi uti-haraha se habera m kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.7 | と、心とりに聞こえたまへば、しばし入りさして、 |
と機嫌を取って申し上げなさると、少し奥に入りかけて、 |
と、 |
to, kokoro tori ni kikoye tamahe ba, sibasi iri sasi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.8 | 「 この月は過ぎぬめれば、 朔日のほどにも、とこそは思ひはべれ。ただ、いと忍びてこそよからめ。何か、 世の許しなどことことしく」 |
「今月は終わってしまいそうなので、来月の朔日頃にも、と思っております。ただ、とても人目に立たないのがよいでしょう。どうして、夫の許可など仰々しく必要でしょう」 |
「もう今月はすぐ終わるでしょうから、来月の初めでもと思います。それは忍んですればいいでしょう。皆の同意を得たりしますようなたいそうなことにいたしませんでも」 |
"Kono tuki ha sugi nu mere ba, tuitati no hodo ni mo, to koso ha omohi habere. Tada, ito sinobi te koso yokara me. Nanika, yo no yurusi nado koto-kotosiku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.9 | とのたまふ声の、「いみじくらうたげなるかな」と、常よりも 昔思ひ出でらるるに、えつつみあへで、寄りゐたまへる 柱もとの簾の下より、やをらおよびて、御袖をとらへつ。 |
とおっしゃる声が、「何ともかわいらしいな」と、いつもより亡き大君が思い出されるので、堪えきれないで、寄り掛かっていらっしゃった柱の側の簾の下から、そっと手を伸ばして、お袖を捉えた。 |
と答えた。その声が非常に |
to notamahu kowe no, "Imiziku rautage naru kana!" to, tune yori mo mukasi omohi-ide raruru ni, e tutumi ahe de, yori-wi tamahe ru hasira moto no sudare no sita yori, yawora oyobi te, ohom-sode wo torahe tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | 第六段 薫、中君に迫る |
4-6 Kaoru presses Naka-no-kimi for his love |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.1 | 女、「さりや、あな心憂」と思ふに、何事かは言はれむ、ものも言はで、いとど引き入りたまへば、それにつきていと馴れ顔に、 半らは内に入りて添ひ臥したまへり。 |
女は、「やはり、そうだった、ああ嫌な」と思うが、何を言うことができようか、何も言わないで、ますます奥にお入りになるので、その後についてとても物馴れた態度で、半分は御簾の内に入って添い臥せりなさった。 |
中の君はこんなことの起こりそうな予感がさっきから自分にあって恐れていたのであると思うと、とがめる言葉も出すことができず、いっそう奥のほうへいざって行こうとした時、持った袖について、親しい男女の間のように、薫は御簾から半身を内に入れて中の君に寄り添って横になった。 |
Womna, "Sariya, ana kokoro-u!" to omohu ni, nani-goto kaha iha re m, mono mo iha de, itodo hiki-iri tamahe ba, sore ni tuki te ito nare-gaho ni, nakara ha uti ni iri te sohi-husi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.2 | 「 あらずや。忍びてはよかるべく思すこともありけるがうれしきは、ひが耳か、聞こえさせむとぞ。疎々しく思すべきにもあらぬを、心憂のけしきや」 |
「そうではありません。人目に立たないようにとはよいことをお考えになったことが嬉しく思えたのは、聞き違いでしょうか、それを伺おうと思いまして。よそよそしくお思いになるべき問題でもないのでに、情けない待遇ですね」 |
「私が間違っていますか、忍んでするのがいいとお言いになったのをうれしいことと取りましたのは聞きそこねだったのでしょうかと、それをもう一度お聞きしようと思っただけです。他人らしくお取り扱いにならないでもよいはずですが、無情なふうをなさるではありませんか」 |
"Ara zu ya? Sinobi te ha yokaru beku obosu koto mo ari keru ga uresiki ha, higa-mimi ka, kikoyesase m to zo. Uto-utosiku obosu beki ni mo ara nu wo, kokoro-u no kesiki ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.3 | と怨みたまへば、いらへすべき心地もせず、思はずに憎く思ひなりぬるを、せめて思ひしづめて、 |
とお恨みになると、お返事できる気もなくて、意外にも憎く思う気になるのを、無理に落ち着いて、 |
こう薫に恨まれても夫人は返辞をする気にもならないで、思わず憎みの心の起こるのをしいておさえながら、 |
to urami tamahe ba, irahe su beki kokoti mo se zu, omoha zu ni nikuku omohi nari nuru wo, semete omohi sidume te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.4 | 「 思ひの外なりける御心のほどかな。 人の思ふらむことよ。あさまし」 |
「意外なお気持ちですね。女房たちがどう思いましょう。あきれたこと」 |
なんというお心でしょう、こんな方とは想像もできませんようなことをなさいます。人がどう思うでしょう、あさましい」 |
"Omohi no hoka nari keru mi-kokoro no hodo kana! Hito no omohu ram koto yo! Asamasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.5 | とあはめて、泣きぬべきけしきなる、すこしはことわりなれば、いとほしけれど、 |
と軽蔑して、泣いてしまいそうな様子なのは、少しは無理もないことなので、お気の毒とは思うが、 |
とたしなめて、泣かんばかりになっているのにも少し道理はあるとかわいそうに思われる薫が、 |
to ahame te, naki nu beki kesiki naru, sukosi ha kotowari nare ba, itohosikere do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.6 | 「 これは咎あるばかりのことかは。かばかりの対面は、いにしへをも思し出でよかし。 過ぎにし人の御許しもありしものを。いとこよなく思しけるこそ、なかなかうたてあれ。好き好きしくめざましき心はあらじと、心やすく思ほせ」 |
「これは非難されるほどのことでしょうか。この程度の面会は、昔を思い出してくださいな。亡くなった姉君のお許しもあったのに。とても疎々しくお思いになっていらっしゃるとは、かえって嫌な気がします。好色がましい目障りな気持ちはないと、安心してください」 |
「これくらいのことは道徳に触れたことでも何でもありませんよ。これほどにしてお話をした昔を思い出してください。 |
"Kore ha toga aru bakari no koto kaha. Kabakari no taimen ha, inisihe wo mo obosi-ide yo kasi. Sugi ni si hito no ohom-yurusi mo ari si mono wo. Ito koyonaku obosi keru koso, naka-naka utate are. Suki-zukisiku mezamasiki kokoro ha ara zi to, kokoro-yasuku omohose." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.7 | とて、いとのどやかにはもてなしたまへれど、月ごろ 悔しと思ひわたる心のうちの、苦しきまでなりゆくさまを、つくづくと言ひ続けたまひて、 許すべきけしきにもあらぬに、 せむかたなく、 いみじとも世の常なり。なかなか、むげに心知らざらむ人よりも、恥づかしく心づきなくて、泣きたまひぬるを、 |
と言って、たいそう穏やかに振る舞っていらっしゃるが、幾月もずっと後悔していた心中が、堪え難く苦しいまでになって行く様子を、つくづくと話し続けなさって、袖を放しそうな様子もないので、どうしようもなく、大変だと言ったのでは月並な表現である。かえって、まったく気持ちを知らない人よりも、恥ずかしく気にくわなくて、泣いてしまわれたのを、 |
と言い、激情は見せずゆるやかなふうにして、もう幾月か後悔の日ばかりが続き、苦しいまでになっていく恋の悩みを、初めからこまごまと述べ続け、反省して去ろうとする様子も見せないため、中の君はどうしてよいかもわからず、悲しいという言葉では全部が現わせないほど悲しんでいた。知らない他人よりもかえって恥ずかしく、いとわしくて、泣き出したのを見て、薫は、 |
tote, ito nodoyaka ni ha motenasi tamahe re do, tuki-goro kuyasi to omohi wataru kokoro no uti no, kurusiki made nari-yuku sama wo, tuku-duku to ihi-tuduke tamahi te, yurusu beki kesiki ni mo ara nu ni, semkatanaku, imizi to mo yo no tune nari. Naka-naka, muge ni kokoro sira zara m hito yori mo, hadukasiku kokoro-dukinaku te, naki tamahi nuru wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.8 | 「 こは、なぞ。あな、若々し」 |
「これは、どうしましたか。何とも、幼げない」 |
「どうしたのですか、あなたは、少女らしい」 |
"Ko ha, na-zo? Ana, waka-wakasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.9 | とは言ひながら、言ひ知らずらうたげに、心苦しきものから、用意深く恥づかしげなるけはひなどの、 見しほどよりも、こよなくねびまさりたまひにけるなどを見るに、「 心からよそ人にしなして、 かくやすからずものを思ふこと」と悔しきにも、また げに音は泣かれけり。 |
とは言いながらも、何とも言えずかわいらしく、お気の毒に思う一方で、心配りが深くこちらが恥ずかしくなるような態度などが、以前に一夜を共にした当時よりも、すっかり成人なさったのを見ると、「自分から他人に譲って、このようにつらい思いをすることよ」と悔しいのにつけても、また自然泣かれるのであった。 |
こう非難をしながらも、非常に |
to ha ihi nagara, ihi-sira-zu rautage ni, kokoro-gurusiki monokara, youi hukaku hadukasige naru kehahi nado no, mi si hodo yori mo, koyonaku nebi masari tamahi ni keru nado wo miru ni, "Kokoro kara yoso-bito ni nasi te, kaku yasukara zu mono wo omohu koto." to kuyasiki ni mo, mata geni ne ha naka re keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | 第七段 薫、自制して退出する |
4-7 Kaoru leaves Naka-no-kimi keeping his mind control |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.1 | 近くさぶらふ女房二人ばかりあれど、すずろなる男のうち入り来たるならばこそは、こはいかなることぞとも、参り寄らめ、疎からず聞こえ交はしたまふ御仲らひなめれば、 さるやうこそはあらめと思ふに、 かたはらいたければ、知らず顔にてやをらしぞきぬるに、 いとほしきや。 |
近くに伺候している女房が二人ほどいるが、何の関係のない男が入って来たのならば、これはどうしたことかと、近寄り集まろうが、親しくご相談し合っている仲のようなので、何か子細があるのだろうと思うと、側にいずらいので、知らない顔をしてそっと離れて行ったのは、お気の毒なことだ。 |
夫人のそばには二人ほどの女房が侍していたのであるが、知らぬ男の |
Tikaku saburahu nyoubau hutari bakari are do, suzuro naru wotoko no uti-iri ki taru nara ba koso ha, ko ha ika naru koto zo to mo, mawiri yora me, utokara zu kikoye-kahasi tamahu ohom-nakarahi na' mere ba, saru yau koso ha ara me to omohu ni, kataharaitakere ba, sira-zu-gaho nite yawora sizoki nuru ni, itohosiki ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.2 | 男君は、いにしへを悔ゆる心の忍びがたさなども、いと静めがたかりぬべかめれど、 昔だにありがたかりし心の用意なれば、なほいと思ひのままにももてなしきこえたまはざりけり。 かやうの筋は、こまかにもえなむまねび続けざりける。かひなきものから、人目のあいなきを思へば、よろづに思ひ返して出でたまひぬ。 |
男君は、昔を後悔する心の堪えがたさなども、とても静め難いようであるが、昔でさえめったになかったお心配りなので、やはりとても思いのままにも無体な振る舞いはなさらないのだった。このような場面は、詳細に語り続けることはできないのであった。不本意ながら、人目の悪いことを思うと、あれやこれやと思い返してお出になった。 |
中納言は昔の後悔が立ちのぼる情炎ともなって、おさえがたいのであったであろうが、夫人の処女時代にさえ、どの男性もするような強制的な結合は遂げようとしなかった人であるから、ほしいままな行為はしなかった。こうしたことを細述することはむずかしいと見えて筆者へ話した人はよくも言ってくれなかった。どんな時を費やしても |
Wotoko-Gimi ha, inisihe wo kuyuru kokoro no sinobi gatasa nado mo, ito sidume gatakari nu beka' mere do, mukasi dani arigatakari si kokoro no youi nare ba, naho ito omohi no mama ni mo motenasi kikoye tamaha zari keri. Kayau no sudi ha, komaka ni mo e nam manebi tuduke zari keru. Kahinaki monokara, hitome no ainaki wo omohe ba, yorodu ni omohi-kahesi te ide tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.3 | まだ宵と思ひつれど、暁近うなりにけるを、見とがむる人もやあらむと、わづらはしきも、 女の御ためのいとほしきぞかし。 |
まだ宵とは思っていたが、暁近くになったのを、見咎める人もあろうかと、厄介なのも、女方の御ためにはお気の毒である。 |
まだ |
Mada yohi to omohi ture do, akatuki tikau nari ni keru wo, mi togamuru hito mo ya ara m to, wadurahasiki mo, womna no ohom-tame no itohosiki zo kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.4 | 「 悩ましげに聞きわたる御心地は、 ことわりなりけり。いと恥づかしと思したりつる 腰のしるしに、 多くは心苦しくおぼえてやみぬるかな。例のをこがましの心や」と思へど、「 情けなからむことは、なほいと本意なかるべし。また、たちまちのわが心の乱れにまかせて、あながちなる心をつかひて後、 心やすくしもはあらざらむものから、わりなく 忍びありかむほども心尽くしに、 女のかたがた思し乱れむことよ」 |
「身体が悪そうだと聞いていたご気分は、もっともなことであった。とても恥ずかしいとお思いでいらした腰の帯を見て、大部分はお気の毒に思われてやめてしまったなあ。いつもの馬鹿らしい心だ」と思うが、「情けのない振る舞いは、やはり不本意なことだろう。また、一時の自分の心の乱れにまかせて、むやみな考えをしでかして後、気安くなくなってしまうものの、無理をして忍びを重ねるのも苦労が多いし、女方があれこれ思い悩まれることであろう」 |
妊娠のために身体の調子を悪くしているという |
"Nayamasige ni kiki wataru mi-kokoti ha, kotowari nari keri. Ito hadukasi to obosi tari turu kosi no sirusi ni, ohoku ha kokoro-gurusiku oboye te yami nuru kana! Rei no wokogamasi no kokoro ya!" to omohe do, "Nasake nakara m koto ha, naho ito ho'i nakaru besi. Mata, tatimati no waga kokoro no midare ni makase te, anagati naru kokoro wo tukahi te noti, kokoro-yasuku simo ara zara m mono kara, wari naku sinobi arika m hodo mo kokoro-dukusi ni, Womna no kata-gata obosi midare m koto yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.5 | など、さかしく思ふにせかれず、 今の間も恋しきぞわりなかりける ★。 さらに見ではえあるまじくおぼえたまふも、 返す返すあやにくなる心なりや。 |
などと、冷静に考えても抑えきれず、今の間も恋しいのは困ったことであった。ぜひとも会わなくては生きていられないように思われなさるのも、重ね重ねどうにもならない恋心であるよ。 |
などとまた賢い反省はしてみても、それでおさえきれる恋の火ではなく、別れて出て来てすでにもう逢いたく恋しい心はどうしようもなかった。どうしてもこの恋を成立させないでは生きておられないようにさえ思うのも、返す返すあやにくな薫の心というべきである。 |
nado, sakasiku omohu ni seka re zu, ima no ma mo kohisiki zo wari nakari keru. Sarani mi de ha e aru maziku oboye tamahu mo, kahesu-gahesu ayaniku naru kokoro nari ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 4/15/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 4/15/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 4/15/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/2/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経