49 宿木(大島本) |
YADORIGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の中、大納言時代 二十四歳夏から二十六歳夏四月頃までの物語 |
Tale of Kaoru's Chunagon and Dainagon era, from summer at the age of 24 to April at the age of 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 薫と匂宮の物語 女二の宮や六の君との結婚話 |
1 Tale of Kaoru and Nio-no-miya Topics for Onna-ni-no-miya and Roku-no-kimi's marriages |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 藤壺女御と女二の宮 |
1-1 About Fujitsubo and her daughter Onna-ni-no-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | そのころ、藤壺と聞こゆるは、故左大臣殿の女御になむおはしける。まだ春宮と聞こえさせし時、人より先に参りたまひにしかば、睦ましくあはれなる方の御思ひは、ことに ものしたまふめれど、 そのしるしと見ゆるふしもなくて年経たまふに、中宮には、宮たちさへあまた、ここら 大人びたまふめるに、さやうのこともすくなくて、ただ 女宮一所をぞ持ちたてまつりたまへりける。 |
その当時、藤壷と申し上げた方は、故左大臣殿の女御でいらっしゃった。が、まだ東宮と申し上げあそばしたとき、誰よりも先に入内なさっていたので、親しく情け深い御愛情は、格別でいらっしゃったらしいが、その甲斐があったと見えることもなくて長年お過ぎになるうちに、中宮におかれては、宮たちまでが大勢、成長なさっているらしいのに、そのようなことも少なくて、ただ女宮をお一方お持ち申し上げていらっしゃるのだった。 |
そのころ |
Sono-koro, Huditubo to kikoyuru ha, ko-Sa-Daizin-dono no Nyougo ni nam ohasi keru. Mada Touguu to kikoye sase si toki, hito yori saki ni mawiri tamahi ni sika ba, mutumasiku ahare naru kata no ohom-omohi ha, koto ni monosi tamahu mere do, sono sirusi to miyuru husi mo naku te tosi he tamahu ni, Tyuuguu ni ha, Miya-tati sahe amata, kokora otona-bi tamahu meru ni, sayau no koto mo sukunaku te, tada Womna-Miya hito-tokoro wo zo moti tatematuri tamahe ri keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | わがいと口惜しく、人におされたてまつりぬる宿世、嘆かしくおぼゆる代はりに、「この宮をだに、いかで行く末の心も慰むばかりにて見たてまつらむ」と、かしづききこえたまふことおろかならず。御容貌もいとをかしくおはすれば、帝もらうたきものに思ひきこえさせたまへり。 |
自分の実に無念に、他人に圧倒され申した運命、嘆かしく思っている代わりに、「せめてこの宮だけでも、何とか将来に心も慰められるようにして差し上げたい」と、大切にお世話申し上げること並々でない。ご器量もとても美しくおいでなので、帝もかわいいとお思い申し上げあそばしていらした。 |
自分が後宮の競争に失敗する悲しい運命を見たかわりに、この宮を長い将来にかけて唯一の慰安にするまでも完全な幸福のある方にしたいと女御は大事にかしずいていた。御 |
Waga ito kutiwosiku, hito ni osa re tatematuri nuru sukuse, nagekasiku oboyuru kahari ni, "Kono Miya wo dani, ikade yuku-suwe no kokoro mo nagusamu bakari nite mi tatematura m." to, kasiduki kikoye tamahu koto oroka nara zu. Ohom-katati mo ito wokasiku ohasure ba, Mikado mo rautaki mono ni omohi kikoye sase tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 女一の宮を、世にたぐひなきものにかしづききこえさせたまふに、おほかたの世のおぼえ こそ及ぶべうもあらね、うちうちの御ありさまは、をさをさ劣らず。父大臣の御勢ひ、厳しかりし名残、いたく衰へねば、ことに心もとなきことなどなくて、さぶらふ人びとのなり姿よりはじめ、たゆみなく、時々につけつつ、調へ好み、今めかしくゆゑゆゑしきさまにもてなしたまへり。 |
女一の宮を、世に類のないほど大切にお世話申し上げあそばすので、世間一般の評判こそ及ぶべくもないが、内々の御待遇は、少しも劣らない。父大臣のご威勢が、盛んであったころの名残が、たいして衰えてはいないので、特に心細いことなどはなくて、伺候する女房たちの服装や姿をはじめとして、気を抜くことなく、季節季節に応じて、仕立て好み、はなやかで趣味豊かにお暮らしになっていた。 |
中宮からお生まれになった |
Womna-Iti-no-Miya wo, yo ni taguhi naki mono ni kasiduki kikoye sase tamahu ni, ohokata no yo no oboye koso oyobu beu mo ara ne, uti-uti no ohom-arisama ha, wosa-wosa otora zu. Titi Otodo no ohom-ikihohi, ikamesikari si nagori, itaku otorohe ne ba, koto ni kokoro-motonaki koto nado naku te, saburahu hito-bito no nari sugata yori hazime, tayumi naku, toki-doki ni tuke tutu, totonohe konomi, imamekasiku yuwe-yuwesiki sama ni motenasi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 藤壺女御の死去と女二の宮の将来 |
1-2 Fujitsubo's death and her daughter's future |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 十四になりたまふ年、御裳着せたてまつりたまはむとて、春よりうち始めて、異事なく思し急ぎて、何事もなべてならぬさまにと思しまうく。 |
十四歳におなりになる年、御裳着の式をして差し上げようとして、春から準備して、余念なく御準備して、何事も普通でない様子にとお考えになる。 |
宮の十四におなりになる年に |
Zihu-si ni nari tamahu tosi, ohom-mo kise tatematuri tamaha m tote, haru yori uti-hazime te, koto-koto naku obosi isogi te, nani-goto mo nabete nara nu sama ni to obosi mauku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | いにしへより伝はりたりける宝物ども、この折にこそはと、探し出でつつ、いみじく営みたまふに、女御、 夏ごろ、もののけにわづらひたまひて、いとはかなく亡せたまひぬ。言ふかひなく口惜しきことを、内裏にも思し嘆く。 |
昔から伝わっていた宝物類、この機会にと、探し出しては探し出しては、大変な準備をなさっていらっしゃったが、女御が、夏頃に、物の怪に患いなさって、まことにあっけなくお亡くなりになってしまった。言いようもなく残念なことと、帝におかせられてもお嘆きになる。 |
自家の祖先から伝わった宝物類も晴れの式に役だてようと捜し出させて、非常に熱心になっていた女御が、夏ごろから |
Inisihe yori tutahari tari keru takaramono-domo, kono wori ni koso ha to, sagasi-ide tutu, imiziku itonami tamahu ni, Nyougo, natu-goro, mononoke ni wadurahi tamahi te, ito hakanaku use tamahi nu. Ihukahinaku kutiwosiki koto wo, Uti ni mo obosi nageku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 心ばへ情け情けしく、なつかしきところおはしつる御方なれば、殿上人どもも、「 こよなくさうざうしかるべきわざかな」と、惜しみきこゆ。おほかたさるまじき際の女官などまで、しのびきこえぬはなし。 |
お心も情け深く、やさしいところがおありだった御方なので、殿上人たちも、「この上なく寂しくなってしまうことだなあ」と、惜しみ申し上げる。一般の特に関係ない身分の女官などまでが、お偲び申し上げない者はいない。 |
優しい人であったため、殿上役人なども御所の内が寂しくなったように言って惜しんだ。直接の関係のなかった女官たちなども |
Kokoro-bahe nasake-nasakesiku, natukasiki tokoro ohasi turu ohom-kata nare ba, Tenzyau-bito-domo mo, "Koyonaku sau-zausikaru beki waza kana!" to, wosimi kikoyu. Ohokata sarumaziki kiha no Nyoukwan nado made, sinobi kikoye nu ha nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | 宮は、まして若き御心地に、心細く悲しく思し入りたるを、 聞こし召して、心苦しくあはれに思し召さるれば、 御四十九日過ぐるままに、忍びて参らせ たてまつらせたまへり。 日々に、渡らせたまひつつ見たてまつらせたまふ。 |
宮は、それ以上に若いお気持ちとて、心細く悲しみに沈んでいらっしゃるのを、お耳にあそばして、おいたわしくかわいそうにお思いあそばすので、御四十九日忌が過ぎると、早速に人目につかぬよう参内させなさった。毎日、お渡りあそばしてお会い申し上げなさる。 |
女二の宮はまして若い |
Miya ha, masite wakaki mi-kokoti ni, kokoro-bosoku kanasiku obosi-iri taru wo, kikosimesi te, kokoro-gurusiku ahare ni obosimesa rure ba, ohom-sizihu-ku niti suguru mama ni, sinobi te mawira se tatematura se tamahe ri. Hi-bi ni, watara se tamahi tutu mi tatematura se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 黒き御衣にやつれておはするさま、いとどらうたげにあてなるけしき まさりたまへり。心ざまもいとよく大人びたまひて、母女御よりも今すこしづしやかに、重りかなるところはまさりたまへるを、うしろやすくは見たてまつらせたまへど、まことには、御母方とても、後見と頼ませたまふべき、 叔父などやうのはかばかしき人もなし。わづかに 大蔵卿、修理大夫などいふは、女御にも異腹なりける。 |
黒い御喪服で質素にしていらっしゃる様子は、ますますかわいらしく上品な感じがまさっていらっしゃった。お考えもすっかり一人前におなりになって、母女御よりも少し落ち着いて、重々しいところはまさっていらっしゃるのを、危なげのないお方だと御拝見あそばすが、実質的方面では、御母方といっても、後見役をお頼みなさるはずの叔父などといったようなしっかりとした人がいない。わずかに大蔵卿、修理大夫などという人びとは、女御にとっても異母兄弟なのであった。 |
黒い喪服姿になっておいでになる宮は、いっそう |
Kuroki ohom-zo ni yature te ohasuru sama, itodo rautage ni ate naru kesiki masari tamahe ri. Kokoro-zama mo ito yoku otona-bi tamahi te, haha-Nyougo yori mo ima sukosi dusiyaka ni, omorika naru tokoro ha masari tamahe ru wo, usiro-yasuku ha mi tatematura se tamahe do, makoto ni ha, ohom-haha-kata tote mo, usiro-mi to tanoma se tamahu beki, wodi nado yau no haka-bakasiki hito mo nasi. Waduka ni Ohokura-Kyau, Syuri-no-Kami nado ihu ha, Nyougo ni mo koto-bara nari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | ことに世のおぼえ重りかにもあらず、やむごとなからぬ人びとを 頼もし人にておはせむに、「 女は心苦しきこと多かりぬべきこそいとほしけれ」など、 御心一つなるやうに思し扱ふも、やすからざりけり。 |
特に世間の声望も重くなく、高貴な身分でもない人びとを後見人にしていらっしゃるので、「女性はつらいことが多くあるだろうことがお気の毒である」などと、お一人で御心配なさっているのも、大変なことであった。 |
格別世間から重んぜられてもいず地位の高くもない人を背景にしていることは女の身にとって不利な場合が多いであろうことが哀れであると、帝はただ一人の親となってこの宮のことに全責任のある気のあそばすのもお苦しかった。 |
Koto ni yo no oboye omorika ni mo ara zu, yamgotonakara nu hito-bito wo tanomosi-bito nite ohase m ni, "Womna ha kokoro-gurusiki koto ohokari nu beki koso itohosikere." nado, mi-kokoro hitotu naru yau ni obosi atukahu mo, yasukara zari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 帝、女二の宮を薫に降嫁させようと考える |
1-3 Mikado considers and gives her daughter in marriage to Kaoru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 御前の菊移ろひ果てて盛りなるころ、空のけしきのあはれにうちしぐるるにも、まづこの御方に渡らせたまひて、昔のことなど聞こえさせたまふに、御いらへなども、おほどかなるものから、いはけなからずうち聞こえさせたまふを、うつくしく思ひきこえさせたまふ。 |
お庭先の菊がすっかり変色して盛んなころ、空模様が胸打つようにちょっと時雨するにつけても、まずこの御方にお渡りあそばして、故人のことなどをお話し申し上げあそばすと、お返事なども、おっとりしたものの、幼くはなく少しお答え申し上げるなさるのを、かわいらしいとお思い申し上げあそばす。 |
お庭の菊の花がまだ終わりがたにもならず盛りなころ、空模様も |
O-mahe no kiku uturohi-hate te sakari naru koro, sora no kesiki no ahare ni uti-sigururu ni mo, madu kono ohom-kata ni watara se tamahi te, mukasi no koto nado kikoye sase tamahu ni, ohom-irahe nado mo, ohodoka naru monokara, ihakenakara zu uti-kikoye sase tamahu wo, utukusiku omohi kikoye sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | かやうなる御さまを見知りぬべからむ人の、もてはやしきこえむも、などかはあらむ、 朱雀院の姫宮を、六条の院に譲りきこえたまひし折の定めどもなど、思し召し出づるに、 |
このようなご様子が分かるような人が、慈しみ申し上げるというのも、何の不都合があろうかと、朱雀院の姫宮を、六条院にお譲り申し上げなさった時の御評定などをお思い出しあそばすと、 |
こうした人の価値を認めて愛する |
Kayau naru ohom-sama wo mi-siri nu bekara m hito no, motehayasi kikoye m mo, nado kaha ara m, Syuzaku-Win no Hime-Miya wo, Rokudeu-no-Win ni yuduri kikoye tamahi si wori no sadame-domo nado, obosimesi iduru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 「 しばしは、いでや、飽かずもあるかな。 さらでもおはしなまし、と聞こゆることどもありしかど、 源中納言の、人よりことなるありさまにて、かくよろづを 後見たてまつるにこそ、そのかみの御おぼえ衰へず、やむごとなきさまにてはながらへたまふめれ。さらずは、御心より外なる事どもも出で来て、おのづから人に軽められたまふ こともやあらまし」 |
「暫くの間は、どんなものかしら、物足りないことだ。降嫁などなさらなくてもよかったろうに、と申し上げる意見もあったが、源中納言が、誰よりも孝養ある様子で、いろいろとご後見申し上げているから、その当時のご威勢も衰えず、高貴な身分の生活でいらっしゃるのだ。そうでなかったら、ご心外なことがらが出てきて、自然と人から軽んじられなさることもあったろうに」 |
あの当時は飽き足らぬことである、皇女は一人でおいでになるほうが神聖でいいとも世間で言ったものであるが、源中納言のようなすぐれた子をお持ちになり、それがついているために昔と変わらぬ世の尊敬も女三の宮が受けておいでになる事実もあるではないか、そうでなく独身でおいでになれば、弱い女性の身には、自発的のことでなく過失に |
"Sibasi ha, ide ya, akazu mo aru kana! Sarade mo ohasi na masi, to kikoyuru koto-domo ari sika do, Gen-Tyuunagon no, hito yori koto naru arisama nite, kaku yorodu wo usiromi tatematuru ni koso, sono-kami no ohom-oboye otorohe zu, yamgotonaki sama nite ha nagarahe tamahu mere. Sarazuha, mi-kokoro yori hoka naru koto-domo mo ide-ki te, onodukara hito ni karume rare tamahu koto mo ya ara masi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | など思し続けて、「 ともかくも、御覧ずる世にや思ひ定めまし」と思し寄るには、やがて、 そのついでのままに、この中納言より他に、よろしかるべき人、またなかりけり。 |
などと、お思い続けて、「いずれにせよ、在位中に決定しようかしら」とお考えになると、そのまま、順序に従って、この中納言より他に、適当な人は、またいないのであった。 |
と、こんなことを帝はお思い続けになって、ともかくも自分の位にいるうちに婿をきめておきたい、だれが好配偶者とするに足る人物であろうとお思いになると、その女三の宮の御子の源中納言以外に適当な婿はないということへ帝のお考えは帰着した。 |
nado obosi tuduke te, "Tomo-kakumo, go-ran-zuru yo ni ya omohi sadame masi." to obosi-yoru ni ha, yagate, sono tuide no mama ni, kono Tyuunagon yori hoka ni, yorosikaru beki hito, mata nakari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | 「 宮たちの御かたはらにさし並べたらむに、何事もめざましくはあらじを。もとより思ふ人持たりて、聞きにくきことうちまずまじくはた、あめるを、 つひにはさやうのことなくてしもえあらじ。さらぬ先に、さもやほのめかしてまし」 |
「宮たちの伴侶となったとして、何につけても目障りなことはあるまいよ。もともと心寄せる人があっても、聞き苦しい噂は聞くこともなさそうだし、また、もしいても、結局は結婚しないこともあるまい。本妻を持つ前に、それとなく当たってみよう」 |
内親王の |
"Miya-tati no ohom-katahara ni sasi-narabe tara m ni, nani-goto mo mezamasiku ha ara zi wo. Moto yori omohu hito mo' tari te, kiki-nikuki koto uti-mazu maziku hata, a' meru wo, tuhini ha sayau no koto naku te simo e ara zi. Sara nu saki ni, samoya honomekasi te masi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | など、折々思し召しけり。 |
などと、時々お考えになっているのであった。 |
とこんなことを帝は時々思召した。 |
nado, wori-wori obosimesi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 帝、女二の宮や薫と碁を打つ |
1-4 Mikado plays go with his daughter and Kaoru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 御碁など打たせたまふ。暮れゆくままに、時雨をかしきほどに、花の色も夕映えしたるを御覧じて、 人召して、 |
御碁などをお打ちあそばす。暮れて行くにしたがって、時雨が趣きあって、花の色も夕日に映えて美しいのを御覧になって、人を召して、 |
ある日帝は碁を打っておいでになった。暮れがたになり |
Ohom-go nado uta se tamahu. Kure-yuku mama ni, sigure wokasiki hodo ni hana no iro mo yuhu-baye si taru wo go-ran-zi te, hito mesi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 「 ただ今、殿上には誰れ誰れか」 |
「ただ今、殿上間には誰々がいるか」 |
「今殿上の室にはだれとだれがいるか」 |
"Tada-ima, Tenzyau ni ha tare-tare ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | と問はせたまふに、 |
とお問いあそばすと、 |
と、お尋ねになった。 |
to toha se tamahu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 「 中務親王、上野親王、中納言源朝臣さぶらふ」 |
「中務親王、上野親王、中納言源朝臣が伺候しております」 |
「 |
"Nakatukasa-no-Miko, Kamduke-no-Miko, Tyuunagon Minamoto-no-Asom saburahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | と奏す。 |
と奏上する。 |
to sou-su. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 「 中納言朝臣こなたへ」 |
「中納言の朝臣こちらへ」 |
「中納言の朝臣をこちらへ」 |
"Tyuunagon-no-Asom konata he." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | と仰せ言ありて参りたまへり。 げに、かく取り分きて召し出づるもかひありて、遠くより薫れる匂ひよりはじめ、人に異なるさましたまへり。 |
と仰せ言があって参上なさった。なるほど、このように特別に召し出すかいもあって、遠くから薫ってくる匂いをはじめとして、人と違った様子をしていらっしゃった。 |
と、仰せがあって |
to ohose-goto ari te mawiri tamahe ri. Geni, kaku tori-waki te mesi-iduru mo kahi ari te, tohoku yori kawore ru nihohi yori hazime, hito ni koto naru sama si tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | 「 今日の時雨、常よりことにのどかなるを、 遊びなどすさまじき方にて、いとつれづれなるを、 いたづらに日を送る戯れにて ★、これなむよかるべき」 |
「今日の時雨は、いつもより格別にのんびりとしているが、音楽などは具合が悪い所なので、まことに所在ないが、何となく日を送る遊び事として、これがよいだろう」 |
「今日の |
"Kehu no sigure, tune yori koto ni nodoka naru wo, asobi nado susamaziki kata nite, ito ture-dure naru wo, itadura ni hi wo okuru tahabure ni te, kore nam yokaru beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | とて、碁盤召し出でて、御碁の敵に召し寄す。いつもかやうに、気近くならしまつはしたまふにならひにたれば、「さにこそは」と思ふに、 |
と仰せになって、碁盤を召し出して、御碁の相手に召し寄せる。いつもこのように、お身近に親しくお召しになるのが習慣になっているので、「今日もそうだろう」と思うと、 |
と帝はお言いになって、碁盤をそばへお取り寄せになり、薫へ相手をお命じになった。いつもこんなふうに親しくおそばへお呼びになる習慣から、格別何でもなく薫が思っていると、 |
tote, goban mesi-ide te, ohom-go no kataki ni mesi-yosu. Itumo kayau ni, ke-dikaku narasi matuhasi tamahu ni narahi ni tare ba, "Sa ni koso ha." to omohu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | 「 好き賭物はありぬべけれど、軽々しくはえ渡すまじきを、何をかは」 |
「ちょうどよい賭物はありそうだが、軽々しくは与えることができないので、何がよかろう」 |
「よい |
"Yoki nori-mono ha ari nu bekere do, karu-garusiku ha e watasu maziki wo, nani kaha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | などのたまはする御けしき、 いかが見ゆらむ、いとど心づかひしてさぶらひたまふ。 |
などと仰せになるご様子は、どのように見えたのであろう、ますます緊張して控えていらっしゃる。 |
という仰せがあった。お心持ちを悟ったのか薫は平生よりも緊張したふうになっていた。 |
nado notamahasuru mi-kesiki, ikaga miyu ram, itodo kokoro-dukahi si te saburahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.12 | さて、打たせたまふに、三番に 数一つ負けさせたまひぬ。 |
そうして、お打ちあそばすうちに、三番勝負に一つお負け越しあそばした。 |
碁の勝負で三番のうち二番を帝はお負けになった。 |
Sate, uta se tamahu ni, sam-ban ni kazu hitotu make sase tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.13 | 「 ねたきわざかな」とて、「 まづ、今日は、この花一枝許す ★」 |
「悔しいことだ」とおっしゃって、「まず、今日は、この花一枝を許す」 |
「くやしいことだ。まあ今日はこの庭の菊一枝を許す」 |
"Netaki waza kana!" tote, "Madu, kehu ha, ko no hana hito-yeda yurusu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
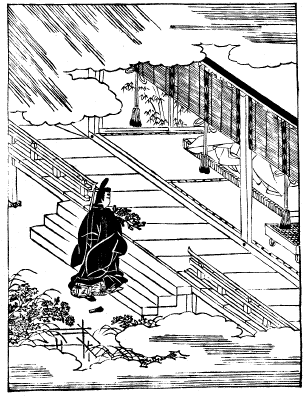 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.14 | とのたまはすれば、御いらへ聞こえさせで、下りて おもしろき枝を折りて参りたまへり。 |
と仰せになったので、お返事を申し上げずに、降りて美しい枝を手折って持って昇がった。 |
このお言葉にお答えはせずに薫は |
to notamahasure ba, ohom-irahe kikoye sase de, ori te omosiroki yeda wo wori te mawiri tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.15 | 「 世の常の垣根に匂ふ花ならば |
「世間一般の家の垣根に咲いている花ならば |
世の常の |
"Yo no tune no kakine ni nihohu hana nara ba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.16 | 心のままに折りて見ましを」 |
思いのままに手折って賞美すことができましょうものを」 |
心のままに折りて見ましを |
kokoro no mama ni wori te mi masi wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.17 | と奏したまへる、用意あさからず見ゆ。 |
と奏上なさる、心づかいは浅くなく見える。 |
この歌を奏したのは思召しに添ったことであった。 |
to sou-si tamahe ru, youi asakara zu miyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.18 | 「 霜にあへず枯れにし園の菊なれど |
「霜に堪えかねて枯れてしまった園の菊であるが |
霜にあへず枯れにし園の菊なれど |
"Simo ni ahe zu kare ni si sono no kiku nare do |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.19 | 残りの色はあせずもあるかな」 |
残りの色は褪せていないな」 |
残りの色はあせずもあるかな |
nokori no iro ha ase zu mo aru kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.20 | とのたまはす。 |
と仰せになる。 |
と帝は仰せられた。 |
to notamahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.21 | かやうに、折々ほのめかさせたまふ御けしきを、人伝てならず承りながら、 例の心の癖なれば、急がしくしもおぼえず。 |
このように、ときどき結婚をおほのめかしあそばす御様子を、人伝てでなく承りながら、例の性癖なので、急ごうとは思わない。 |
こんなふうにおりおりおほのめかしになるのを、直接薫は伺いながらも、この人の性質であるから、すぐに進んで出ようとも思わなかった。 |
Kayau ni, wori-wori honomekasa se tamahu mi-kesiki wo, hito-dute nara zu uketamahari nagara, rei no kokoro no kuse nare ba, isogasiku mo oboye zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.22 | 「 いでや、本意にもあらず。 さまざまにいとほしき人びとの御ことどもをも、よく聞き過ぐしつつ年経ぬるを、 今さらに聖のものの、世に帰り出でむ心地すべきこと」 |
「いや、本意ではない。いろいろと心苦しい人びとのご縁談を、うまく聞き流して年を過ごしてきたのに、今さら出家僧が、還俗したような気がするだろう」 |
結婚をするのは自分の本意でない、今までもいろいろな縁談があって、その人々に対して気の毒な感情もありながら、断わり続けてきたのに、今になって妻を持っては、俗人と違うことを |
"Ide ya, ho'i ni mo ara zu. Sama-zama ni itohosiki hito-bito no ohom-koto-domo wo mo, yoku kiki-sugusi tutu tosi he nuru wo, imasara ni hiziri no mono no, yo ni kaheri ide m kokoti su beki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.23 | と思ふも、 かつはあやしや。 |
と思うのも、また妙なものだ。 |
妙なものであろう。 |
to omohu mo, katu ha ayasi ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.24 | 「ことさらに心を尽くす人だにこそあなれ」とは思ひながら、「 后腹におはせばしも」とおぼゆる心の内ぞ、あまりおほけなかりける ★。 |
「特別に恋い焦がれている人さえあるというのに」とは思う一方で、「后腹の姫宮でいらっしゃったら」と思う心の中は、あまりに大それた考えであった。 |
恋しくてならぬ人ででもあればともかくもであるがと否定のされる心でまた、これが |
"Kotosara ni kokoro wo tukusu hito dani koso a' nare." to ha omohi nagara, "Kisaki-bara ni ohase ba simo." to oboyuru kokoro no uti zo, amari ohokenakari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 夕霧、匂宮を六の君の婿にと願う |
1-5 Yugiri desires Nio-no-miya to get married to his daughter Roku-no-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | かかることを、 右の大殿ほの聞きたまひて、 |
このようなことを、右大殿がちらっとお聞きになって、 |
この話を左大臣は聞いて、 |
Kakaru koto wo, Migi-no-Ohoidono hono-kiki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 「 六の君は、さりとも この君にこそは。しぶしぶなりとも、まめやかに恨み寄らば、つひには、えいなび果てじ」 |
「六の君は、そうはいってもこの君にこそ縁づけたいものだ。しぶしぶであっても、一生懸命に頼みこめば、結局は、断ることはできまい」 |
六の君との縁組みに |
"Roku-no-Kimi ha, saritomo kono Kimi ni koso ha. Sibu-sibu nari tomo, mameyaka ni urami yora ba, tuhini ha, e inabi-hate zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | と思しつるを、「 思ひの外のこと出で来ぬべかなり」と、ねたく思されければ、兵部卿宮はた、わざとにはあらねど、折々につけつつ、をかしきさまに聞こえたまふことなど絶えざりければ、 |
とお思いになったが、「意外なことが出てきたようだ」と、悔しくお思いになったので、兵部卿宮が、わざわざではないが、何かの時にそれに応じて、風流なお手紙を差し上げなさることが続いているので、 |
と楽観していたのに、意外なことが起こってきそうであると思い、兵部卿の宮は正面からの話にはお乗りにはならないでいて、何かと六の君に交渉を求めて手紙をよくおよこしになるのであるから、 |
to obosi turu wo, "Omohi no hoka no koto ide-ki nu beka' nari." to, netaku obosa re kere ba, Hyaubukyau-no-Miya hata, wazato ni ha ara ne do, wori-wori ni tuke tutu, wokasiki sama ni kikoye tamahu koto nado taye zari kere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 「 さはれ、なほざりの好きにはありとも、さるべきにて、御心とまるやうもなどかなからむ。 水漏るまじく思ひ定めむとても ★、なほなほしき際に下らむはた、いと人悪ろく、飽かぬ心地すべし」 |
「ままよ、いい加減な浮気心であっても、何かの縁で、お心が止まるようなことがどうしてないことがあろうか。水も漏らさない男性を思い定めていても、並の身分の男に縁づけるのは、また体裁が悪く、不満な気がするだろう」 |
それは真実性の少ないものであっても、妻にされれば御愛情の生じないはずもない、どんなに忠実な |
"Sahare, nahozari no suki ni ha ari tomo, saru-beki ni te, mi-kokoro tomaru yau mo nado ka nakara m. Midu moru maziku omohi-sadame m tote mo, naho-nahosiki kiha ni kudara m hata, ito hito-waroku, aka nu kokoti su besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | など思しなりにたり。 |
などとお考えになっていた。 |
と思って、やはり兵部卿の宮を目標として進むことに定めた。 |
nado obosi nari ni tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | 「 女子うしろめたげなる世の末にて、帝だに婿求めたまふ世に、まして、ただ人の盛り過ぎむもあいなし」 |
「女の子が心配に思われる末世なので、帝でさえ婿をお探しになる世で、まして、臣下の娘が盛りを過ぎては困ったものだ」 |
女の子によい婿のあることの困難な世の中になり、 |
"Womna-go usirometage naru yo no suwe nite, Mikado dani muko motome tamahu yo ni, masite, tadaudo no sakari sugi m mo aimasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | など、 誹らはしげにのたまひて、中宮をもまめやかに恨み申したまふこと、たび重なれば、 聞こし召しわづらひて、 |
などと、陰口を申すようにおっしゃって、中宮をも本気になってお恨み申し上げなさることが、度重なったので、お聞きあそばしになり困って、 |
などと、帝のお考えに多少の非難めいたことも左大臣は言い、中宮へ兵部卿の宮との縁組みの実現されるように訴えることがたびたびになったため、后の宮はお困りになり、宮へ、 |
nado, sosirahasige ni notamahi te, Tyuuguu wo mo mameyaka ni urami mausi tamahu koto, tabi-kasanare ba, kikosimesi wadurahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.8 | 「 いとほしく、かくおほなおほな 思ひ心ざして年経たまひぬるを、あやにくに逃れきこえたまはむも、情けなきやうならむ。 親王たちは、御後見からこそ、ともかくもあれ。 |
「お気の毒にも、このように一生懸命にお思いなさってから何年にもおなりになったので、不義理なまでにお断り申し上げなさるのも、薄情なようでしょう。親王たちは、ご後見によって、ともかくもなるものです。 |
「気の毒なように長くそれを望んで大臣は待ち暮らしていたのだのに、口実を作っていつまでもお応じにならないのも無情なことですよ。親王というものは後援者次第で光りもし、光らなくも見えるものなのですよ。 |
"Itohosiku, kaku ohona-ohona omohi kokorozasi te tosi he tamahi nuru wo, ayaniku ni nogare kikoye tamaha m mo, nasakenaki yau nara m. Miko-tati ha, ohom-usiromi kara koso, tomo-kakumo are. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.9 | 主上の、御代も末になり行くとのみ思しのたまふめるを、ただ人こそ、ひと事に定まりぬれば、また心を分けむことも難げなめれ。それだに、かの大臣のまめだちながら、 こなたかなた羨みなくもてなしてものしたまはずやはある。 まして、これは、思ひおきてきこゆることも叶はば、あまたもさぶらはむに などかあらむ」 |
主上が、御在位も終わりに近いとばかりお思いになりおっしゃっていますようなので、臣下の者は、本妻がお決まりになると、他に心を分けることは難しいようです。それでさえ、あの大臣が誠実に、こちらの本妻とあちらの宮とに恨まれないように待遇していらっしゃるではありませんか。まして、あなたは、お考え申していることが叶ったら、大勢伺候させても構わないのですよ」 |
お |
Uhe no, mi-yo mo suwe ni nari yuku to nomi obosi notamahu meru wo, tadaudo koso, hito-koto ni sadamari nure ba, mata kokoro wo wake m koto mo katage na' mere. Sore dani, kano Otodo no mame-dati nagara, konata kanata urayami naku motenasi te monosi tamaha zu ya ha aru. Masite, kore ha, omohi-oki te kikoyuru koto mo kanaha ba, amata mo saburaha m ni nado ka ara m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10 | など、 例ならず言続けて、あるべかしく聞こえさせたまふを、 |
などと、いつもと違って言葉数多く話して、道理をお説き申し上げなさるのを、 |
と、平生にまして長々御教訓をあそばすのを承って、 |
nado, rei nara zu koto tuduke te, aru bekasiku kikoye sase tamahu wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.11 | 「 わが御心にも、もとよりもて離れて、はた、思さぬことなれば、あながちには、などてかはあるまじきさまにも聞こえさせたまはむ。ただ、いとことうるはしげなるあたりにとり籠められて、心やすくならひたまへるありさまの所狭からむことを、なま苦しく思すにもの憂きなれど、げに、この大臣に、あまり怨ぜられ果てむもあいなからむ」 |
「ご自身でも、もともとまったく嫌とは、お思いにならないことなので、無理やりに、どうしてとんでもないこととお思い申し上げなさろう。ただ、万事格式ばった邸に閉じ籠められて、自由気ままになさっていらした状態が窮屈になることを、何となく苦しくお思いになるのが嫌なのだが、なるほど、この大臣から、あまり恨まれてしまうのも困ったことだろう」 |
兵部卿の宮御自身も無関心では決しておいでにならない女性のことであったから、それをしいてお |
"Waga mi-kokoro ni mo, motoyori mote-hanare te, hata, obosa nu koto nare ba, anagati ni ha, nadoteka ha arumaziki sama ni mo kikoye sase tamaha m. Tada, ito koto uruhasige naru atari ni tori-kome rare te, kokoro-yasuku narahi tamahe ru arisama no tokoro-sekara m koto wo, nama-kurusiku obosu ni mono-uki nare do, geni, kono Otodo ni, amari wen-ze rare hate m mo ainakara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.12 | など、やうやう思し弱りにたるべし。あだなる御心なれば、 かの按察使大納言の、紅梅の御方をも、なほ思し絶えず、花紅葉につけてもののたまひわたりつつ、 いづれをもゆかしくは思しけり。されど、その年は変はりぬ。 |
などと、だんだんお弱りになったのであろう。浮気なお心癖なので、あの按察大納言の、紅梅の御方をも、依然としてお思い捨てにならず、花や紅葉につけてはお歌をお贈りなさって、どちらの方にもご関心がおありであった。けれども、その年は過ぎた。 |
今になっては抵抗力も少なくおなりになった。多情な御性質であるから、あの |
nado, yau-yau obosi yowari ni taru besi. Ada naru mi-kokoro nare ba, kano Azeti-no-Dainagon no, Koubai-no-Ohomkata wo mo, naho obosi taye zu, hana momidi ni tuke te mono notamahi watari tutu, idure wo mo yukasiku ha obosi keri. Saredo, sono tosi ha kahari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 4/15/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 4/15/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 4/15/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/2/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経