47 総角(大島本) |
AGEMAKI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の中納言時代 二十四歳秋から歳末までの物語 |
Tale of Kaoru's Chunagon era, from fall to the end of the year at the age of 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第七章 大君の物語 大君の死と薫の悲嘆 |
7 Tale of Ohoi-kimi Ohoi-kimi's death and Kaoru's grief |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | 第一段 大君、もの隠れゆくように死す |
7-1 Ohoi-kimi dies as if she disapears her figure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1 | 「 つひにうち捨てたまひなば、世にしばしもとまるべきにもあらず。 命もし限りありてとまるべうとも、 深き山にさすらへなむとす。ただ、いと心苦しうて、とまりたまはむ御ことをなむ思ひきこゆる」 |
「とうとう捨てて逝っておしまいになったら、この世に少しも生きている気がしない。寿命がもし決まっていて生き永らえたとしても、深い山に分け入るつもりです。ただ、とてもお気の毒に、お残りになる方の御事を心配いたします」 |
「あなたがいよいよ私を捨ててお行きになることになったら、私も生きていませんよ。けれど、人の命は思うようになるものでなく、生きていねばならぬことになりましたら、私は深い山へはいってしまおうと思います。ただその際にお妹様を心細い状態であとへお残しするだけが苦痛に思われます」 |
"Tuhini uti-sute tamahi na ba, yo ni sibasi mo tomaru beki ni mo ara zu. Inoti mosi kagiri ari te tomaru beu tomo, hukaki yama ni sasurahe na m to su. Tada, ito kokoro-gurusiu te, tomari tamaha m ohom-koto wo nam omohi kikoyuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.2 | と、 いらへさせたてまつらむとて、 かの御ことをかけたまへば、顔隠したまへる御袖を少しひき直して、 |
と、答えさせていただこうと思って、あの方の御事におふれになると、顔を隠していらっしゃったお袖を少し離して、 |
中納言は少しでもものを言わせたいために、病者が最も関心を持つはずの人のことを言ってみると、姫君は顔を隠していた |
to, irahe sase tatematura m tote, kano ohom-koto wo kake tamahe ba, kaho kakusi tamahe ru ohom-sode wo sukosi hiki-nahosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.3 | 「 かく、はかなかりけるものを、 思ひ隈なきやうに思されたりつるもかひなければ、 このとまりたまはむ人を、 同じこと思ひきこえたまへと、ほのめかしきこえしに、 違へたまはざらましかば、うしろやすからましと、これのみなむ恨めしきふしにて、 とまりぬべうおぼえはべる」 |
「このように、はかなかったものを、思いやりがないようにお思いなさったのも効がないので、このお残りになる人を、同じようにお思い申し上げてくださいと、それとなく申し上げましたが、その通りにしてくださったら、どんなに安心して死ねたろうにと、この点だけが恨めしいことで、執着が残りそうに思われます」 |
「私はこうして短命で終わる予感があったものですから、あなたの御好意を解しないように思われますのが苦しくて、残っていく人を私の代わりと思ってくださるようにとそう願っていたのですが、あなたがそのとおりにしてくださいましたら、どんなに安心だったかと思いましてね、それだけが心残りで死なれない気もいたします」 |
"Kaku, hakanakari keru mono wo, omohi kumanaki yau ni obosa re tari turu mo kahinakere ba, kono tomari tamaha m hito wo, onazi koto omohi kikoye tamahe to, honomekasi kikoye ni si, tagahe tamaha zara masika ba, usiroyasukara masi to, kore nomi nam uramesiki husi nite, tomari nu beu oboye haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.4 | とのたまへば、 |
とおっしゃるので、 |
と言った。 |
to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.5 | 「 かくいみじう、もの思ふべき身にやありけむ。いかにも、いかにも、 異ざまにこの世を思ひかかづらふ方のはべらざりつれば、 御おもむけに従ひきこえずなりにし。 今なむ、悔しく心苦しうもおぼゆる。されども、 うしろめたくな思ひきこえたまひそ」 |
「このようにひどく、物思いをする身の上なのでしょうか。何としても、かんとしても、他の人には執着することがございませんでしたので、ご意向にお従い申し上げずになってしまいました。今になって、悔しくいたわしく思われます。けれども、ご心配申し上げなさいますな」 |
「こんなふうに悲しい思いばかりをしなければならないのが私の宿命だったのでしょう。私はあなた以外のだれとも夫婦になる気は持ってなかったものですから、あなたの好意にもそむいたわけなのです。今さら残念であの方がお気の毒でなりません。しかし御心配をなさることはありませんよ。あの方のことは」 |
"Kaku imiziu, mono omohu beki mi ni ya ari kem. Ikani mo, ikani mo, koto-zama ni konoyo wo omohi kakadurahu kata no habera zari ture ba, ohom-omomuke ni sitagahi kikoye zu nari ni si. Ima nam, kuyasiku kokoro-gurusiu mo oboyuru. Saredomo, usirometaku na omohi kikoye tamahi so." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.6 | などこしらへて、 いと苦しげにしたまへば、修法の阿闍梨ども 召し入れさせ、さまざまに験ある限りして、 加持参らせさせたまふ。 我も仏を念ぜさせたまふこと、限りなし。 |
などと慰めて、たいそう苦しそうでいらっしゃるので、修法の阿闍梨たちを召し入れさせて、いろいろな効験のある僧全員して、加持して差し上げさせなさる。ご自分でも仏にお祈りあそばすこと、この上ない。 |
などともなだめていた薫は、姫君が苦しそうなふうであるのを見て、修法の僧などを近くへ呼び入れさせ、効験をよく現わす人々に加持をさせた。そして自身でも念じ入っていた。 | nado kosirahe te, ito kurusige ni si tamahe ba, suhohu no Azyari-domo mesi-ire sase, sama-zama ni gen aru kagiri si te, kadi mawirase sase tamahu. Ware mo Hotoke wo nen-ze sase tamahu koto, kagiri nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.7 | 「 世の中をことさらに厭ひ離れね、と勧めたまふ仏などの、いとかくいみじきものは思はせたまふにやあらむ。 見るままにもの隠れゆくやうにて消え果てたまひぬるは、いみじきわざかな」 |
「世の中を特に厭い離れなさい、とお勧めになる仏などが、とてもこのようにひどい目にお遭わせになるのだろうか。見ている前で物が隠れてゆくようにして、お亡くなりになったのは、何と悲しいことであろうか」 |
人生をことさらいとわしくなっている薫でないために、道へ深く入れようとされる仏などが、今こうした大きな悲しみをさせるのではなかろうか。見ているうちに何かの植物が枯れていくように |
"Yononaka wo kotosara ni itohi hanare ne, to susume tamahu Hotoke nado no, ito kaku imiziki mono ha omoha se tamahu ni ya ara m. Miru mama ni mono kakure yuku yau ni te kiye-hate tamahi nuru ha, imiziki waza kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.8 | 引きとどむべき方なく、足摺りもしつべく、人のかたくなしと見むこともおぼえず。限りと見たてまつりたまひて、中の宮の、後れじと 思ひ惑ひたまふさまもことわりなり。 あるにもあらず見えたまふを、例の、さかしき女ばら、「 今は、いとゆゆしきこと」と、引き避けたてまつる。 |
引き止める方法もなく、足摺りもしそうに、人が馬鹿だと見ることも気にしない。ご臨終と拝しなさって、中の宮が、後れまいと嘆き悲しみなさる様子ももっともなことである。正気を失ったようにお見えになるのを、いつもの、利口ぶった女房連中が、「今は、まことに不吉なこと」と、お引き離し申し上げる。 |
引きとめることもできず、 |
Hiki-todomu beki kata naku, asi-zuri mo si tu beku, hito no katakunasi to mi m koto mo oboye zu. Kagiri to mi tatematuri tamahi te, Naka-no-Miya no, okure zi to omohi madohi tamahu sama mo kotowari nari. Aru ni mo ara zu miye tamahu wo, rei no, sakasiki womna-bara, "Ima ha, ito yuyusiki koto." to, hiki-sake tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 第二段 大君の火葬と薫の忌籠もり |
7-2 Kaoru goes into mourning after a cremation of Ohoi-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.1 | 中納言の君は、 さりとも、いとかかることあらじ、夢か、と思して、 大殿油を近うかかげて見たてまつりたまふに、 隠したまふ顔も、ただ寝たまへるやうにて、変はりたまへるところもなく、うつくしげにてうち臥したまへるを、「 かくながら、 虫の骸のやうにても見るわざならましかば」と、思ひ惑はる。 |
中納言の君は、そうはいっても、まさかこんなことにはなるまい、夢か、とお思いになって、大殿油を近くに芯をかき立てて拝見なさると、お隠しになっている顔も、まるで寝ていらっしゃるように、変わっておいでになるところもなく、かわいらしげに臥せっていらっしゃるのを、「このままで、虫の脱殻のようにずっと見続けることができるものならば」と、悲しみにくれる。 |
源中納言は死んだのを見ていても、これは事実でないであろう、夢ではないかと思って、台の |
Tyuunagon-no-Kimi ha, saritomo, ito kakaru koto ara zi, yume ka, to obosi te, ohotonabura wo tikau kakage te mi tatematuri tamahu ni, kakusi tamahu kaho mo, tada ne tamahe ru yau nite, kahari tamahe ru tokoro naku, utukusige nite uti-husi tamahe ru wo, "Kaku nagara, musi no kara no yau nite mo miru waza nara masika ba." to, omohi madoha ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
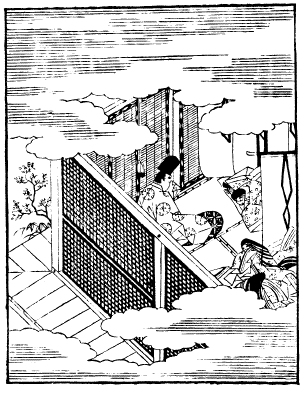 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.2 | 今はの事どもするに、 御髪をかきやるに、さとうち匂ひたる、ただありしながらの匂ひに、なつかしう香ばしきも、 |
ご臨終の作法をする時に、お髪をかきやると、さっと匂うのが、まるで生きていた時の匂いそのままで、懐かしく香ばしいのも、 |
Ima ha no koto-domo suru ni, mi-gusi wo kaki-yaru ni, sato uti-nihohi taru, tada arisi-nagara no nihohi ni, natukasiu kaubasiki mo, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.3 | 「 ありがたう、何ごとにてこの人を、すこしもなのめなりしと思ひさまさむ。 まことに世の中を思ひ捨て果つるしるべならば、恐ろしげに憂きことの、悲しさも冷めぬべきふしをだに見つけさせたまへ」 |
「世に比類なく、どうしてこの人を、少しでも普通の女性であったと思い諦められようか。ほんとうに世の中を思い捨て去る道しるべならば、恐ろしそうな醜いことで、悲しさも冷めてしまいそうなところだけでも見つけさせてください」 |
どの点でこの人に欠点があるとしてのけにくい執着を除けばいいのであろう、あまりにも完全な女性であった。この人の死が自分を信仰へ導こうとする仏の方便であるならば、恐怖もされるような、悲しみも忘れられるほど変相を見せられたい | "Arigatau, nani-goto nite kono hito wo, sukosi mo nanome nari si to omohi samasa m. Makoto ni yononaka wo omohi sute-haturu sirube nara ba, osorosige ni uki koto no, kanasisa mo same nu beki husi wo dani mituke sase tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.4 | と仏を念じたまへど、いとど思ひのどめむ方なくのみあれば、言ふかひなくて、「 ひたぶるに煙にだになし果ててむ」と思ほして、 とかく例の作法どもするぞ、あさましかりける。 |
と仏にお祈りになるが、ますます悲しみを慰めようもなくなるばかりなので、どうしようもなくて、「ひと思いにせめて火葬にしてしまおう」とお思いになって、あれこれ例の葬式をするのが、何ともいいようのないことであった。 |
と仏を念じているのであるが、悲しみはますます深まるばかりであったから、せめて早く煙にすることをしようと思い、葬送の儀式のことなどを命じてさせるのもまた苦しいことであった。 | to Hotoke wo nen-zi tamahe do, itodo omohi-nodome m kata naku nomi are ba, ihukahinaku te, "Hitaburu ni keburi ni dani nasi hate te m." to omohosi te, tokaku rei no sahohu-domo suru zo, asamasikari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.5 | 空を歩むやうにただよひつつ、 限りのありさまさへはかなげにて、煙も多くむすぼほれたまはずなりぬるもあへなしと、あきれて帰りたまひぬ。 |
宙を歩くようにふらふらとして、最後に空に上る様子さえ頼りなさそうで、煙も多くはお立ちにならなかったのもあっけなかったことと、茫然としてお帰りになった。 |
空を歩くような気持ちを覚えて薫は葬場へ行ったのであるが、火葬の煙さえも多くは立たなかったのにはかなさをさらに感じて山荘へ帰った。 |
Sora wo ayumu yau ni tadayohi tutu, kagiri no arisama sahe hakanage nite, keburi mo ohoku musubohore tamaha zu nari nuru mo ahenasi to, akire te kaheri tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.6 | 御忌に籠もれる人数多くて、 心細さはすこし紛れぬべけれど、中の宮は、 人の見思はむことも恥づかしき身の心憂さを思ひ沈みたまひて、また亡き人に見えたまふ。 |
御忌中に籠もっている人の数が多くて、心細さは少し紛れそうだが、中の宮は、人の目や思惑も恥ずかしい身の情けなさを悲観なさって、同じく死んだ人のようにお見えになる。 |
|
Ohom-imi ni komore ru hito-kazu ohoku te, kokoro-bososa ha sukosi magire nu bekere do, Naka-no-Miya ha, hito no mi omoha m koto mo hadukasiki mi no kokoro-usa wo omohi sidumi tamahi te, matanaki hito ni miye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.7 | 宮よりも御弔らひいとしげくたてまつれたまふ。思はずにつくづくと思ひきこえたまへりしけしきも、思し直らでやみぬるを思すに、 いと憂き人の御ゆかりなり。 |
宮からもご弔問をたいそう頻繁に差し上げなさる。意外でつくづくとお思い申し上げていらっしゃったお気持ちも、お直りにならずに亡くなってしまったことをお思いになると、まことにつらいご縁の方である。 |
Miya yori mo ohom-toburahi ito sigeku tatemature tamahu. Omoha zu ni tuku-duku to omohi kikoye tamahe ri si kesiki mo, obosi nahora de yami nuru wo obosu ni, ito uki hito no ohom-yukari nari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.8 | 中納言、かく世のいと心憂くおぼゆるついでに、本意遂げむと思さるれど、 三条の宮の思されむことに憚り、 この君の御ことの心苦しさとに思ひ乱れて、 |
中納言は、このようにこの世がまことにつらく思われる機会に、出家の本願を遂げようとお思いになるが、三条宮がお悲しみになることに気がねし、この姫君の御事のおいたわしさに思い乱れて、 |
中納言は人生の悲しみを切実に味わった今度のことを機会に、出家したいと思う心はあるのであるが、三条の母宮の思召しもはばかられ、それとこの中の君の境遇の心細さは見捨てられないものに思われて |
Tyuunagon, kaku yo no ito kokoro-uku oboyuru tuide ni, ho'i toge m to obosa rure do, Samdeu-no-Miya no obosa re m koto ni habakari, kono Kimi no ohom-koto no kokoro-gurusisa to ni omohi-midare te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.9 | 「 かののたまひしやうにて、形見にも見るべかりけるものを。下の心は、身を分けたまへりとも、移ろふべくもおぼえざりしを、 かうもの思はせたてまつるよりは、ただうち語らひて、 尽きせぬ慰めにも見たてまつり通はましものを」 |
「あの方がおっしゃったようにして、形見としてでも結婚すべきであったよ。心の底では、身を分けた姉妹でいらしても、気を移せるようには思えなかったが、このようにお悲しみ申し上げさせるよりは、いっそ深い仲になって、尽きない慰めとしてずっとお世話申し上げてゆくべきであったのに」 |
故 |
"Kano notamahi si yau nite, katamini mo miru bekari keru mono wo. Sita no kokoro ha, mi wo wake tamahe ri tomo, uturohu beku mo oboye zari si wo, kau mono omoha se tatematuru yori ha, tada uti-katarahi te, tuki se nu nagusame ni mo mi tatematuri kayoha masi mono wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.10 | など思す。 |
などとお思いになる。 |
とも思った。 | nado obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.11 | かりそめに京にも出でたまはず、かき絶え、慰む方なくて 籠もりおはするを、世人も、おろかならず思ひたまへること、と見聞きて、内裏よりはじめたてまつりて、御弔ひ多かり。 |
ちょっとも京にお出にならず、ふっつりと、慰めようもなく籠もっておいでになるのを、世の人も、並々ならず悲しんでいらっしゃる、と見聞きして、帝をはじめ申して、ご弔問が多かった。 |
かりそめにも京へ出ることをせず、物思いをしてこもっていることを知って、世間の人も故人を薫が深く愛していたことを知り、宮中をはじめとして諸方面からの慰問の使いが山荘を多く |
Karisome ni Kyau ni mo ide tamaha zu, kaki taye, nagusamu kata naku te komori ohasuru wo, yohito mo, oroka nara zu omohi tamahe ru koto, to mi kiki te, Uti yori hazime tatematuri te, ohom-toburahi ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 第三段 七日毎の法事と薫の悲嘆 |
7-3 Kaoru grieves evry seven days of Buddhist service for the dead |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.1 | はかなくて日ごろは過ぎゆく。 七日七日の事ども、いと尊くせさせたまひつつ、おろかならず孝じたまへど、 限りあれば、御衣の色の変らぬを、かの御方の心寄せわきたりし人びとの、いと黒く着替へたるを、ほの見たまふも、 |
とりとめもなく幾日も過ぎてゆく。七日毎の法事も、たいそう尊くおさせになっては、心をこめて供養なさるが、規則があるので、お召し物の色の変わらないのを、あの御方を特に慕っていた女房たちが、たいそう黒く着替えているのを、ちらっと御覧になるにつけても、 |
女王の |
Hakanaku te higoro ha sugi-yuku. Nanu-ka nanu-ka no koto-domo, ito tahutoku se sase tamahi tutu, oroka nara zu keu-zi tamahe do, kagiri are ba, ohom-zo no iro no kahara nu wo, kano ohom-kata no kokoro-yose waki tari si hito-bito no, ito kuroku ki-kahe taru wo, hono-mi tamahu mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.2 | 「 くれなゐに落つる涙もかひなきは |
「紅色に落ちる涙が何にもならないのは |
「くれなゐに落つる涙もかひなきは | "Kurenawi ni oturu namida mo kahinaki ha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.3 | 形見の色を染めぬなりけり」 |
形見の喪服の色を染めないことだ」 |
かたみの色を染めぬなりけり」 |
katami no iro wo some nu nari keri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.4 | 聴し色の氷解けぬかと見ゆるを、いとど濡らし添へつつ眺めたまふさま、 いとなまめかしくきよげなり。人びと覗きつつ見たてまつりて、 |
許し色の氷が解けないかと見えるのを、ますます濡らし加えながら物思いに沈んでいらっしゃるお姿は、たいそう艶っぽく美しい。女房たちが覗きながら拝見して、 |
こんなことがつぶやかれ、浅い |
Yurusi-iro no kohori toke nu ka to miyuru wo, itodo nurasi sohe tutu nagame tamahu sama, ito namamekasiku kiyoge nari. Hito-bito nozoki tutu mi tatematuri te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.5 | 「 言ふかひなき御ことをばさるものにて、この殿のかくならひたてまつりて、 今はとよそに思ひきこえむこそ、あたらしく口惜しけれ」 |
「亡くなってしまったお方のことはしかたないとして、この殿がこのようにお親しみ申されて、これからは他人とお思い申し上げるのは、惜しく残念なことだわ」 |
「姫君のお |
"Ihukahinaki ohom-koto wo ba saru mono nite, kono Tono no kaku narahi tatematuri te, ima ha to yoso ni omohi kikoye m koso, atarasiku kutiwosikere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.6 | 「思ひの外なる御宿世にもおはしかるかな。かく深き御心のほどを、 かたがたに背かせたまへるよ」 |
「意外なご運勢でいらっしゃったわ。こんなに深いお志を、どちらもお添いになれなかったとは」 |
なんという宿命でしょう。こんなに真心の深い方をお二方とも御冷淡になすって、御縁をお結びにならなかったとはね」 |
"Omohi no hoka naru ohom-sukuse ni mo ohasi keru kana! Kaku hukaki mi-kokoro no hodo wo, kata-gata ni somuka se tamahe ru yo!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.7 | と泣きあへり。 |
と言って、泣きあっている。 |
とも言って泣き合っていた。 |
to naki-ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.8 | この御方には、 |
この御方には、 |
「こちらの姫君を | Kono Ohom-kata ni ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.9 | 「 昔の御形見に、今は何ごとも聞こえ、承らむとなむ思ひたまふる。疎々しく思し隔つな」 |
「亡くなった方のお形見として、今は何でも申し上げ、承りたいと存じております。よそよそしくお思いなさいませんように」 |
あの方のお形見とみなして、今後はいろいろ昔の話を申し上げ、また承りもしたいと思うのです。他人のように思召さないでください」 |
"Mukasi no ohom-katami ni, ima ha nani-goto mo kikoye, uketamahara m to nam omohi tamahuru. Uto-utosiku obosi hedatu na." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.10 | と聞こえたまへど、「 よろづのこと憂き身なりけり」と、もののみつつましくて、まだ対面してものなど聞こえたまはず。 |
と申し上げなさるが、「万事が嫌な身の上だ」と、何もかも気後れして、まだお会いしてお話など申し上げなさらない。 |
と薫は中の君へ言わせたが、すべての点で自分は薄命な女であると思う心から恥じられて、中の君はまだ話し合おうとはしなかった。 | to kikoye tamahe do, "Yorodu no koto uki mi nari keri." to, mono nomi tutumasiku te, mada taimen si te mono nado kikoye tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.11 | 「 この君は、けざやかなるかたに、いますこし子めき、気高くおはするものから、 なつかしく匂ひある心ざまぞ、劣りたまへりける」 |
「この姫君は、はきはきとした方で、もう少し子供っぽく、気高くいらっしゃる一方で、親しみがありうるおいのある人柄という点では劣っていらっしゃる」 |
この女王のほうはあざやかな美人で、娘らしいところと、 |
"Kono Kimi ha, kezayaka naru kata ni, ima sukosi ko-meki, ke-dakaku ohasuru monokara, natukasiku nihohi aru kokoro-zama zo, otori tamahe ri keru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.12 | と、事に触れておぼゆ。 |
と、何かにつけて思われる。 |
と事に触れて薫は思った。 |
to, koto ni hure te oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | 第四段 雪の降る日、薫、大君を思う |
7-4 In a snow day, Kaoru recollects the late Ohoi-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.1 | 雪のかきくらし降る日、終日にながめ暮らして、 世の人のすさまじきことに言ふなる師走の月夜の、曇りなくさし出でたるを、 簾巻き上げて見たまへば、向かひの寺の鐘の声、枕をそばたてて、今日も暮れぬと ★ ★、かすかなる響を聞きて、 |
雪が烈しく降る日、一日中物思いに沈んで、世間の人が殺風景な物という十二月の月夜の、曇りなく照りだしているのを、簾を巻き上げて御覧になると、向かい側の寺の鐘の音を、枕をそばだてて、今日も暮れたと、かすかな音を聞いて、 |
雪の暗く降り暮らした日、終日物思いをしていた薫は、世人が愛しにくいものに言う十二月の月の |
Yuki no kaki-kurasi huru hi, hinemosu ni nagame kurasi te, yo no hito no susamaziki koto ni ihu naru sihasu no tukiyo no, kumori naku sasi-ide taru wo, sudare maki-age te mi tamahe ba, mukahi no tera no kane no kowe, makura wo soba-date te, kehu mo kure nu to, kasuka naru hibiki wo kiki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.2 | 「 おくれじと空ゆく月を慕ふかな |
「後れまいと空を行く月が慕われる |
「おくれじと空行く月を慕ふかな | "Okure zi to sora yuku tuki wo sitahu kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.3 | つひに住むべきこの世ならねば」 |
いつまでも住んでいられないこの世なので」 |
|
tuhi ni sumu beki konoyo nara ne ba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
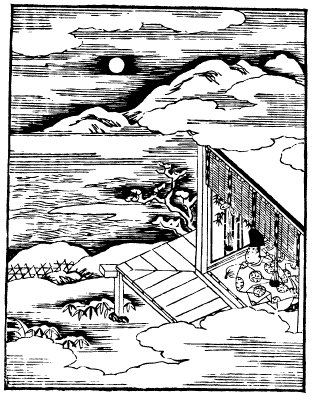 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.4 | 風のいと烈しければ、蔀下ろさせたまふに、 四方の山の鏡と見ゆる汀の氷、月影にいとおもしろし。「 京の家の限りなくと磨くも、えかうは あらぬはや」とおぼゆ。「 わづかに生き出でてものしたまはましかば、もろともに聞こえまし」と思ひつづくるぞ、胸よりあまる心地する。 |
風がたいそう烈しいので、蔀を下ろさせなさると、四方の山の鏡に見える汀の氷が、月の光に実に美しい。「京の邸をこの上なく磨いても、こんなにまではできまい」と思われる。「かろうじて少しでも生き返りなさったら、一緒に語りあえたものを」と思い続けると、胸がいっぱいになる。 |
風がはげしくなったので、揚げ戸を皆おろさせるのであったが、四辺の山影をうつした宇治川の |
Kaze no ito hagesikere ba, sitomi orosa se tamahu ni, yomo no yama no kagami to miyuru migiha no kohori, tuki-kage ni ito omosirosi. "Kyau no ihe no kagirinaku to migaku mo, e kau ha ara nu haya!" to oboyu. "Waduka ni iki-ide te monosi tamaha masika ba, morotomoni kikoye masi." to omohi tudukuru zo, mune yori amaru kokoti suru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.5 | 「 恋ひわびて死ぬる薬のゆかしきに |
「恋いわびて死ぬ薬が欲しいゆえに |
「恋ひわびて死ぬる薬のゆかしきに | "Kohi wabi te sinuru kusuri no yukasiki ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.6 | 雪の山にや跡を消なまし」 |
雪の山に分け入って跡を晦ましてしまいたい」 |
雪の山には跡を |
yuki no yama ni ya ato wo kena masi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.7 | 「 半ばなる偈教へむ鬼もがな、ことつけて身も投げむ」 と思すぞ、心ぎたなき聖心なりける。 |
「半偈を教えたという鬼でもいてくれたら、かこつけて身を投げたい」とお考えになるのは、未練がましい道心であるよ。 |
死を求める |
"Nakaba naru ge wosihe m oni mo gana, kototuke te mi mo nage m." to obosu zo, kokoro-gitanaki hiziri-gokoro nari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.8 | 人びと近く呼び出でたまひて、物語など せさせたまふけはひなどの、いとあらまほしくのどやかに心深きを、見たてまつる人びと、若きは、心にしめてめでたしと思ひたてまつる。老いたるは、ただ口惜しくいみじきことを、いとど思ふ。 |
女房たちを近くに呼び出しなさって、話などをおさせになる様子などが、まことに理想的でゆったりとして情愛深いのを、拝する女房たち、若い者は、心にしみて立派だとお思い申し上げる。年とった者は、ただ口惜しく残念なことを、ますます思う。 |
中納言は女房たちを皆そばへ呼び集めて、話などをさせて聞いていた。様子のりっぱであることと、親切な性情を知っている女たちであるから、その中の若い人らは身にしむほどの思いで好意を持った。老いた人たちは薫を見ることによっても故人が惜しまれてならなかった。 |
Hito-bito tikaku yobi-ide tamahi te, monogatari nado se sase tamahu kehahi nado no, ito aramahosiku nodoyaka ni kokoro-hukaki wo, mi tatematuru hito-bito, wakaki ha, kokoro ni sime te medetasi to omohi tatematuru. Oyi taru ha, tada kutiwosiku imiziki koto wo, itodo omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.9 | 「 御心地の重くならせたまひしことも、 ただこの宮の御ことを、思はずに見たてまつりたまひて、人笑へにいみじと思すめりしを、さすがに かの御方には、 かく思ふと知られたてまつらじと、ただ御心一つに世を恨みたまふめりしほどに、はかなき御くだものをも聞こしめし触れず、ただ弱りになむ弱らせたまふめりし。 |
「ご病気が重態におなりあそばしたことも、ただあの宮の御事を思いもかけずお迎えなさって、物笑いで辛いとお思いのようであったが、何といってもあの御方には、こう心配していると知られ申すまいと、ただお胸の内で二人の仲を嘆いていらっしゃるうちに、ちょっとした果物もお口におふれにならず、すっかりお弱りあそばしたようでした。 |
「御病気の重くなりましたのも、 |
"Mi-kokoti no omoku nara se tamahi si koto mo, tada kono Miya no ohom-koto wo, omoha zu ni mi tatematuri tamahi te, hito-warahe ni imizi to obosu meri si wo, sasuga ni kano ohom-kata ni ha, kaku omohu to sira re tatematura zi to, tada mi-kokoro hitotu ni yo wo urami tamahu meri si hodo ni, hakanaki ohom-kudamono wo mo kikosimesi hure zu, tada yowari ni nam yowara se tamahu meri si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.10 | 上べには、何ばかりことことしくもの深げにももてなさせたまはで、下の御心の限りなく、何事も思すめりしに、 故宮の御戒めにさへ違ひぬることと、あいなう人の御上を思し悩みそめしなり」 |
表面では何ほども大げさに心配しているようにはお振る舞いあそばさず、お心の底ではこの上なく、何事もご心配のようでして、故宮のご遺戒にまで背いてしまったことと、ひとごとながら妹君のお身の上をお悩み続けたのでした」 |
表面には物思いをあそばすふうをお見せにならずに、深く胸の中で悩んでいらっしったのでございます。それに中の君様に結婚をおさせになりましたことは父宮様の御遺戒にもそむいたことであったと、いつもそれをお心の苦になさいましたのでございますよ」 |
Uhabe ni ha, nani bakari koto-kotosiku mono-hukage ni mo motenasa se tamaha de, sita no mi-kokoro no kagirinaku, nani-goto mo obosu meri si ni, ko-Miya no ohom-imasime ni sahe tagahi nuru koto to, ainau hito no ohom-uhe wo obosi-nayami some si nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.11 | と聞こえて、折々のたまひしことなど語り出でつつ、誰も誰も泣き惑ふこと尽きせず。 |
と申し上げて、時々おっしゃったことなどを話し出しては、誰も彼もいつまでも泣きくれている。 |
こんなことを言って、いつの時、いつかこうお言いになったことがあるなどと大姫君のことを語って、だれもだれも際限なく泣いた。 | to kikoye te, wori-wori notamahi si koto nado katari-ide tutu, tare mo tare mo naki madohu koto tuki se zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 第五段 匂宮、雪の中、宇治へ弔問 |
7-5 Nio-no-miya visits to make a call to express his condolence in a snow day |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.1 | 「 わが心から、あぢきなきことを思はせたてまつりけむこと」と ▼ 取り返さまほしく、なべての世もつらきに、 念誦をいとどあはれにしたまひて、まどろむほどなく明かしたまふに、 まだ夜深きほどの雪のけはひ、いと寒げなるに、人びと声あまたして、馬の音聞こゆ。 |
「自分のせいで、つまらない心配をおかけ申したこと」と元に戻したく、すべての世の中がつらいので、念誦をますますしみじみとなさって、うとうととする間もなく夜を明かしなさると、まだ夜明け前の雪の様子が、たいそう寒そうな中を、人びとの声がたくさんして、馬の声が聞こえる。 |
自分の計らいが原因して苦しい物思いを故人にさせたと、あやまちを取り返しうるものなら取り返したく思って薫は聞いたのであって、恋人の死そのものだけでなく、すべての人生が恨めしく、 この早朝の雪の |
"Waga kokoro-kara, adikinaki koto wo omoha se tatematuri kem koto." to torikahesa mahosiku, nabete no yo mo turaki ni, nenzyu wo itodo ahare ni si tamahi te, madoromu hodo naku akasi tamahu ni, mada yo-bukaki hodo no yuki no kehahi, ito samuge naru ni, hito-bito kowe amata si te, muma no oto kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.2 | 「 何人かは、かかるさ夜中に雪を分くべき」 |
「誰がいったいこのような夜中に雪の中を来きたのだろうか」 |
こうした未明に雪を分けてだれも山荘へ近づくはずがない | "Nani-bito kaha, kakaru sa-yonaka ni yuki wo waku beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.3 | と、大徳たちも驚き思へはべるに、宮、狩の御衣にいたうやつれて、濡れ濡れ入りたまへるなりけり。うちたたきたまふさま、 さななり、と聞きたまひて、中納言は、隠ろへたる方に入りたまひて、忍びておはす。御忌は日数残りたりけれど、 心もとなく思しわびて、夜一夜、雪に惑はされてぞおはしましける。 |
と、大徳たちも目を覚まして思っていると、宮が、狩のお召物でひどく身をやつして、濡れながらお入りなって来るのであった。戸を叩きなさる様子が、そうである、とお聞きになって、中納言は、奥のほうにお入りになって、隠れていらっしゃる。御忌中の日数は残っていたが、ご心配でたまらなくなって、一晩中雪に難儀されながらおいでになったのであった。 |
と僧たちもそれを聞いて思っていると、それは目だたぬ |
to, Daitoko-tati mo odoroki omohe haberu ni, Miya, kari no ohom-zo ni itau yature te, nure-nure iri tamahe ru nari keri. Uti-tataki tamahu sama, sa na' nari, to kiki tamahi te, Tyuunagon ha, kakurohe taru kata ni iri tamahi te, sinobi te ohasu. Ohom-imi ha hikazu nokori tari kere do, kokoro-motonaku obosi-wabi te, yo hito-yo, yuki ni madohasa re te zo ohasimasi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.4 | 日ごろのつらさも紛れぬべきほどなれど、対面したまふべき心地もせず、 思し嘆きたるさまの恥づかしかりしを、 やがて見直されたまはずなりにしも、 今より後の御心改まらむは、かひなかるべく思ひしみてものしたまへば、誰も誰もいみじうことわりを聞こえ知らせつつ、 物越にてぞ、 日ごろのおこたり尽きせずのたまふを、つくづくと聞きゐたまへる。 |
今までのつらさも紛れてしまいそうなことだけれど、お会いなさる気もせず、お嘆きになっていた様子が恥ずかしかったが、そのまま見直していただけなかったことを、今から以後にお心が改まったところで、何の効もないようにすっかり思い込んでいらっしゃるので、誰も彼もが、強く道理を説いて申し上げ申し上げしては、物越しに、これまでのご無沙汰の詫びを言葉を尽くしておっしゃるのを、つくづくと聞いていらっしゃった。 |
こんな悪天候をものともあそばさなかった御訪問であったから、恨めしさも紛らされていってもいいのであろうが、中の君は |
Higoro no turasa mo magire nu beki hodo nare do, taimen si tamahu beki kokoti mo se zu, obosi-nageki taru sama no hadukasikari si wo, yagate mi-nahosa re tamaha zu nari ni si mo, ima yori noti no mi-kokoro aratamara m ha, kahinakaru beku omohi simi te monosi tamahe ba, tare mo tare mo imiziu kotowari wo kikoye sirase tutu, mono-gosi nite zo, higoro no okotari tuki se zu notamahu wo, tuku-duku to kiki-wi tamahe ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.5 | これも いとあるかなきかにて、「後れたまふまじきにや」と聞こゆる御けはひの心苦しさを、「 うしろめたういみじ」と、宮も思したり。 |
この君もまことに生きているのかいないのかの様子で、「後をお追いなさるのではないか」と感じられるご様子のおいたわしさを、「心配でたまらない」と、宮もお思いになっていた。 |
この人さえも、あるかないかのような心細い命の人と思われ、続いてどうかなるのではあるまいかと思われる |
Kore mo ito aru ka naki ka nite, "Okure tamahu maziki ni ya?" to kikoyuru ohom-kehahi no kokoro-gurusisa wo, "Usirometau imizi." to, Miya mo obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.6 | 今日は、御身を捨てて、泊りたまひぬ。「 物越ならで」といたくわびたまへど、 |
今日は、わが身がどうなろうともと、お泊まりになった。「物を隔ててでなく」としきりにおせがみになるが、 |
今日は何事も犠牲にしてよいという気におなりになりお帰りにならないことになった。物越しなどでなく、直接に逢いたいと宮はいろいろお訴えになるのであったが、 |
Kehu ha, ohom-mi wo sute te, tomari tamahi nu. "Mono-gosi nara de." to itaku wabi tamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.7 | 「 今すこしものおぼゆるほどまではべらば」 |
「もう少し気持ちがすっきりしましてから」 |
「もう少し人ごこちがするようになっているのでしたら」 |
"Ima sukosi mono oboyuru hodo made habera ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.8 | とのみ聞こえたまひて、つれなきを、中納言もけしき聞きたまひて、さるべき人召し出でて、 |
とばかり申し上げなさって、冷たいのを、中納言もその様子をお聞きになって、しかるべき女房を召し出して、 |
と言い、女王はいなみ続けていた。 このことを薫も聞いて、中の君へ取り次がすのに都合のよい女房を呼んで、 |
to nomi kikoye tamahi te, turenaki wo, Tyuunagon mo kesiki kiki tamahi te, saru-beki hito mesi-ide te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.9 | 「 御ありさまに違ひて、心浅きやうなる御もてなしの、 昔も今も心憂かりける 月ごろの罪は、さも思ひきこえたまひぬべきことなれど、憎からぬさまにこそ、勘へたてまつりたまはめ。 かやうなること、まだ見知らぬ御心にて、苦しう思すらむ」 |
「お気持ちに反して、薄情なようなお振る舞いで、以前も今も情けなかった一月余りのご無沙汰の罪は、きっとそうもお思い申し上げなさるのも当然なことですが、憎らしくない程度に、お懲らしめ申し上げなさいませ。このようなことは、まだご経験のないことなので、困っておいででしょう」 |
「こちらの真心に対してあさはかにも見える態度を、初めもその後もおとりになった宮を不快にお思いになるのはもっともですが、今少し情状を |
"Ohom-arisama ni tagahi te, kokoro-asaki yau naru ohom-motenasi no, mukasi mo ima mo kokoro-ukari keru tuki-goro no tumi ha, samo omohi kikoye tamahi nu beki koto nare do, nikukara nu sama ni koso, kamgahe tatematuri tamaha me. Kayau naru koto, mada mi sira nu mi-kokoro nite, kurusiu obosu ram." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.10 | など、忍びて 賢しがりたまへば、いよいよこの君の御心も恥づかしくて、 え聞こえたまはず。 |
などと、こっそりとおせっかいなさるので、ますますこの君のお気持ちが恥ずかしくて、お答え申し上げることがおできになれない。 |
などと忠告をさせた。それを聞いた中の君は薫の思うことも恥ずかしくて、いよいよ宮のお話にお答えを申し上げる気になれなくなった。 |
nado, sinobi te sakasigari tamahe ba, iyo-iyo kono Kimi no mi-kokoro mo hadukasiku te, e kikoye tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.11 | 「 あさましく心憂くおはしけり。聞こえしさまをも、むげに忘れたまひけること」 |
「あきれるくらい情けなくいらっしゃるよ。お約束申し上げたことを、すっかりお忘れになったようだ」 |
「あなたはどうしてこんなに気が強いのでしょう。前にあんなに私の心持ちも、周囲の事情もお話ししておいたではありませんか。それを皆お忘れになったのですか」 |
"Asamasiku kokoro-uku ohasi keri. Kikoye si sama wo mo, muge ni wasure tamahi keru koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.12 | と、おろかならず 嘆き暮らしたまへり。 |
と、並々ならず嘆いて日をお送りになった。 |
とお言いになり、宮は一日をお歎き暮らしになった。 | to, oroka nara zu nageki kurasi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 第六段 匂宮と中の君、和歌を詠み交す |
7-6 Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchangewaka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.1 | 夜のけしき、いとど険しき風の音に、 人やりならず嘆き臥したまへるも、さすがにて、例の、もの隔てて 聞こえたまふ。 千々の社をひきかけて、行く先長きことを契りきこえたまふも、「 いかでかく口馴れたまひけむ」と、心憂けれど、よそにてつれなきほどの疎ましさよりはあはれに、人の心もたをやぎぬべき御さまを、一方にもえ疎み果つまじかりけり。ただ、つくづくと聞きて、 |
夜の様子は、ますます烈しい風の音に、自分のせいで嘆き臥していらっしゃるのも、さすがに気の毒で、例によって、物を隔てて申し上げなさる。数々の神の名をあげて、将来長くお約束申し上げなさるのも、「どうしてこんなに口馴れていらっしゃるのだろう」と、嫌な気がするが、離れていて薄情な時のつらさよりは胸にしみて、女君の気持ちも柔らかくなってしまいそうなご様子を、一方的にも嫌ってばかりいられない。ただ、じっと耳を傾けていて、 |
夜になるといっそう天気が悪くなり、ますます吹きつのる風の音を聞きながら、寂しい旅寝の床に歎き続けておいでになるのもさすがにおいたましく思われて、女王はまた物越しでお話を聞くことにした。無数の神を |
Yoru no kesiki, itodo kehasiki kaze no oto ni, hito-yari-nara-zu nageki husi tamahe ru mo, sasuga ni te, rei no, mono hedate te kikoye tamahu. Ti-di no yasiro wo hiki-kake te, yuku-saki nagaki koto wo tigiri kikoye tamahu mo, "Ikade kaku kuti-nare tamahi kem." to, kokoro-ukere do, yoso nite turenaki hodo no utomasisa yori ha ahare ni, hito no kokoro mo tawoyagi nu beki ohom-sama wo, hito-kata ni mo e utomi-hatu mazikari keri. Tada, tuku-duku to kiki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.2 | 「 来し方を思ひ出づるもはかなきを |
「過ぎ去ったことを思い出しても頼りないのに |
「きしかたを思ひいづるもはかなきを | "Kisi-kata wo omohi-iduru mo hakanaki wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.3 | 行く末かけてなに頼むらむ」 |
将来までどうして当てになりましょう」 |
行く末かけて何頼むらん」 |
yuku-suwe kake te nani tanomu ram |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.4 | と、ほのかにのたまふ。 なかなかいぶせう、心もとなし。 |
と、かすかにおっしゃる。かえって気がふさぎ、気が気でない。 |
と、はじめてほのかな声で言った。なお飽き足らず思召す宮であった。 |
to, honoka ni notamahu. Naka-naka ibuseu, kokoro-motonasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.5 | 「 行く末を短きものと思ひなば |
「将来が短いものと思ったら |
「「行く末を短きものと思ひなば | "Yuku-suwe wo mizikaki mono to omohi na ba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.6 | 目の前にだに背かざらなむ |
せめてわたしの前だけでも背かないでほしい |
目の前にだにそむかざらなん」 |
me no mahe ni dani somuka zara nam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.7 | 何事も いとかう見るほどなき世を、罪深くな思しないそ」 |
何事もまことにこのように瞬く間に変わる世の中を、罪深くお思いなさるな」 |
すべてはかない人生にいて、人をお憎みになるような罪はお作りにならないがいいでしょう」 |
Nani-goto mo ito kau miru hodo naki yo wo, tumi hukaku na obosi-nai so." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.8 | と、よろづにこしらへたまへど、 |
と、いろいろと宥めなさるが、 |
ともお言いになり、いろいろとおなだめになったが、 |
to, yorodu ni kosirahe tamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.9 | 「 心地も悩ましくなむ」 |
「気分が悪くて」 |
「私は気分もよろしくないのでございますから」 |
"Kokoti mo nayamasiku nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.10 | とて入りたまひにけり。 人の見るらむもいと人悪ろくて、嘆き明かしたまふ。 恨みむもことわりなるほどなれど、 あまりに人憎くもと、つらき涙の落つれば、「 ましていかに思ひつらむ」と、さまざまあはれに思し知らる。 |
と言ってお入りになってしまった。女房が見ているのもとても体裁が悪くて、嘆きながら夜を明かしなさる。恨むのも無理もない際であるが、あまりにも無愛想なのではと、つらい涙が落ちるので、「まして私以上にどんなにおつらいであろう」と、いろいろとお気の毒に思わずにはいらっしゃれない。 |
中の君はこう言って奥へはいってしまった。人目も恥ずかしいように思召し、そのまま歎息を続けて宮は夜をお明かしになった。女の恨むのも道理なほどの途絶えを作ったのは自分であるが、あまりに無情な扱い方であると恨めしい涙の落ちてきた時に、ましてそのころの彼女はどれほどに |
tote iri tamahi ni keri. Hito no miru ram mo ito hito-waroku te, nageki akasi tamahu. Urami m mo kotowari naru hodo nare do, amari ni hito nikuku mo to, turaki namida no oture ba, "Masite ikani omohi tu ram?" to, sama-zama ahare ni obosi sira ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.11 | 中納言の、 主人方に住み馴れて、人びとやすらかに呼び使ひ、人もあまたしてもの参らせなどしたまふを、 あはれにもをかしうも御覧ず。 いといたう痩せ青みて、ほれぼれしきまでものを思ひたれば、 心苦しと見たまひて、まめやかに訪らひたまふ。 |
中納言が、主人方に住みついて、人びとをやすやすと召し使い、人も大勢して食事を差し上げなどさせたりなさるのを、感慨深くもおもしろくも御覧になる。たいそうひどく痩せ青ざめて、茫然と物思いしているので、気の毒にと御覧になって、心をこめてお見舞い申し上げなさる。 |
中納言が主人がたの座敷に住んでいて、どの女房をも気安いふうに呼び使い、みずから |
Tyuunagon no, aruzi-gata ni sumi nare te, hito-bito yasuraka ni yobi tukahi, hito mo amata site mono mawirase nado si tamahu wo, ahare ni mo wokasiu mo go-ran-zu. Ito itau yase awomi te, hore-boresiki made mono wo omohi tare ba, kokoro-gurusi to mi tamahi te, mameyaka ni toburahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.12 | 「 ありしさまなど、かひなきことなれど、この宮にこそは聞こえめ」と思へど、うち出でむにつけても、 いと心弱く、かたくなしく見えたてまつらむに憚りて、言少ななり。音をのみ泣きて、日数経にければ、顔変はりのしたるも、 見苦しくはあらで、いよいよものきよげになまめいたるを、「 女ならば、かならず心移りなむ」と、 おのがけしからぬ御心ならひに思しよるも、なまうしろめたかりければ、「 いかで人のそしりも 恨みをもはぶきて、京に移ろはしてむ」と思す。 |
「生前のことなど、言っても始まらないことだが、この宮だけには申し上げよう」と思うが、口に出すにつけても、まことに意気地がなく、愚かしく見られ申すのに気が引けて、言葉少なである。声を上げて泣きながら、日数が過ぎたので、顔が変わったのも、見苦しくはなく、ますます美しく艶やかなのを、「女であったら、きっと心移りがしよう」と、自分の良くない性癖をお思いつきになると、何となく不安になったので、「何とか世間の非難や恨みを取り除いて、京に引越させよう」とお考えになる。 |
恋人の死の前後の悲しい心の動揺を今さら言いだしても |
"Arisi sama nado, kahinaki koto nare do, kono Miya ni koso ha kikoye me." to omohe do, uti-ide m ni tuke te mo, ito kokoro-yowaku, katakunasiku miye tatematura m ni habakari te, koto-zukuna nari. Ne wo nomi naki te, hikazu he ni kere ba, kaho kahari no si taru mo, mi-gurusiku ha ara de, iyo-iyo mono-kiyoge ni namamei taru wo, "Womna nara ba, kanarazu kokoro uturi na m." to, onoga kesikara nu mi-kokoro narahi ni obosi-yoru mo, nama usirometakari kere ba, "Ikade hito no sosiri mo urami wo mo habuki te, Kyau ni uturohasi te m." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.13 | かくつれなきものから、 内裏わたりにも聞こし召して、いと悪しかるべきに思しわびて、今日は 帰らせたまひぬ。おろかならず言の葉を尽くしたまへど、 ▼ つれなきは苦しきものをと、一節を 思し知らせまほしくて、心とけずなりぬ。 |
このように打ち解けないけれども、帝にもお耳にあそばして、まことに具合の悪いことになるにちがいないとお困りになって、今日はお帰りあそばした。並々ならずお言葉を尽くしなさるが、相手にされないとはつらいものだと、それだけを知っていただきたくて、ついに気をお許しにらなかった。 |
こんなふうに恋人の心は容易に打ち解けるとは見えないし、今一日をここにいることは御所でも悪く 真心を尽くして恋人の心を動かそうと宮はお努めになったのであるが、相手の冷淡であることは苦しいものであると、この一点をお思い知らせようとして、この朝も何の言葉も送らずに中の君は宮をお帰ししたのであった。 |
Kaku turenaki monokara, uti watari ni mo kikosimesi te, ito asikaru beki ni obosi-wabi te, kehu ha kahera se tamahi nu. Oroka nara zu koto-no-ha wo tukusi tamahe do, turenaki ha kurusiki mono wo to, hito-husi wo obosi-sira se mahosiku te, kokoro-toke zu nari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 第七段 歳暮に薫、宇治から帰京 |
7-7 Kaoru comes back to Kyoto from Uji at the end of the year |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.1 | 年暮れ方には、かからぬ所だに、空のけしき例には似ぬを、荒れぬ日なく降り積む雪に、 うち眺めつつ明かし暮らしたまふ心地、尽きせず夢のやうなり。 |
年の暮方では、こんな山里でなくても、空の模様がいつもとちがうのに、荒れない日はなく降り積む雪に、物思いに沈みながら日をお送りになる気持ちは、尽きせず夢のようである。 |
年末になればこうした山里でなくても晴れる日は少ないのであるから、まして宇治は荒れ |
Tosi kure-kata ni ha, kakara nu tokoro dani, sora no kesiki rei ni ha ni nu wo, are nu hi naku huri tumu yuki ni, uti nagame tutu akasi-kurasi tamahu kokoti, tuki se zu yume no yau nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.2 | 宮よりも、御誦経など、こちたきまで訪らひきこえたまふ。 かくてのみやは、新しき年さへ嘆き過ぐさむ。ここかしこにも、おぼつかなくて閉ぢ籠もりたまへることを 聞こえたまへば、今はとて帰りたまはむ心地も、たとへむ方なし。 |
宮からも、御誦経などをうるさいまでにお見舞い申し上げなさる。こうしてばかりいては、新年まで嘆き過すことになろう。あちらこちらと、音沙汰なく籠もっていらっしゃることを申し上げられるので、今はもうお帰りになる気持ちも、何にもたとえようがない。 |
このまま新年までも閉じこもっていることはできぬ、御母宮を初めとして自分を長くお待ちになっている所々があるのであるからと思い、いよいよ引き上げようとする薫はまた新たな深い悲しみを覚えた。 |
Miya yori mo, mi-zyukyau nado, kotitaki made toburahi kikoye tamahu. Kaku te nomi yaha, atarasiki tosi sahe nageki sugusa m. Koko-kasiko ni mo, obotukanaku te todi-komori tamahe ru koto wo kikoye tamahe ba, ima ha tote kaheri tamaha m kokoti mo, tatohe m kata nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.3 | かくおはしならひて、人しげかりつる名残なくならむを、思ひわぶる人びと、 いみじかりし折のさしあたりて悲しかりし騷ぎよりも、うち静まりていみじくおぼゆ。 |
このようにお住みつきなさって、人が多かったのがすっかりいなくなるのを、悲しむ女房たちは、大変であった時の当面の悲しかった騷ぎよりも、ひっそりとしてひどく悲しく思われる。 |
ずっとこの人が来て住んでいたために、出入りする人の多かった忌中に続いた生活が跡かたもなく消えていくことを寂しがる人々は、姫君の死の当時にもまさって悲しがった。 | Kaku ohasi-narahi te, hito sigekari turu nagori naku nara m wo, omohi waburu hito-bito, imizikari si wori no sasiatari te kanasikari si sawagi yori mo, uti-sidumari te imiziku oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.4 | 「 時々、折ふし、をかしやかなるほどに 聞こえ交はしたまひし年ごろよりも、かくのどやかにて過ぐしたまへる日ごろの御ありさまけはひの、なつかしく情け深う、 はかなきことにもまめなる方にも、思ひやり多かる御心ばへを、今は限りに見たてまつりさしつること」 |
「時々、折節に、風流な感じにお話し交わしなさった年月よりも、こうしてのんびりと過ごしていらした今までの、ご様子がやさしく情け深くて、風流事にも実際面にも、よく行き届いたお人柄を、今を限りに拝見できなくなったこと」 |
以前間をおいて |
"Toki-doki, wori-husi, wokasiyaka naru hodo ni kikoye-kahasi tamahi si tosi-goro yori mo, kaku nodoyaka nite sugusi tamahe ru higoro no ohom-arisama kehahi no, natukasiku nasake hukau, hakanaki koto ni mo mame naru kata ni mo, omohi-yari ohokaru mi-kokoro-bahe wo, ima ha kagiri ni mi tatematuri sasi turu koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.5 | と、おぼほれあへり。 |
と、一同涙に暮れていた。 |
と女房たちは歎きにおぼれていた。 |
to, obohore-ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.6 | かの宮よりは、 |
あの宮からは、 |
兵部卿の宮からは、 |
Kano Miya yori ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.7 | 「 なほ、かう参り来ることもいと難きを思ひわびて、近う渡いたてまつるべきことをなむ、たばかり出でたる」 |
「やはり、このように参ることがとても難しいのに困って、近くにお引越し申し上げることを、考え出した」 |
お話ししたように、そちらへ出向くことにいろいろ困難なことがあるため、私は心を苦しめておりましたが、ようやくあなたを近日京へ迎える方法が見つかりました。 |
"Naho, kau mawiri kuru koto mo ito kataki wo omohi-wabi te, tikau watai tatematuru beki koto wo nam, tabakari-ide taru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.8 | と聞こえたまへり。 后の宮、聞こし召しつけて、 |
と申し上げなさった。后の宮がお耳にあそばして、 |
というお手紙が中の君へあった。 |
to kikoye tamahe ri. Kisai-no-Miya, kikosimesi tuke te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.9 | 「 中納言もかくおろかならず思ひほれてゐたなるは、げに、おしなべて思ひがたうこそは、誰も 思さるらめ」と、心苦しがりたまひて、「 二条院の西の対に渡いたまて、時々も通ひたまふべく、忍びて聞こえたまひけるは、 女一の宮の御方にことよせて思しなるにや」 |
「中納言もこのように並々ならず悲しみに茫然としていたのは、なるほど、普通の扱いはできない方と、どなたもお思いなのではあろう」と、お気の毒になって、「二条院の西の対に迎えなさって、時々お通いになるよう、内々に申し上げなさったのは、女一の宮の御方の女房にとお考えになっているのではないか」 |
その姉君であった恋人を失った中納言もあれほどの悲しみを見せていることを思うと、並み並みの情人としてはだれも思われないすぐれた女性なのであろうと、兵部卿の宮のお心持ちに御同情をあそばして、二条の院の西の対へ迎えて時々通うようにとそっと仰せがあったのである。 |
"Tyuunagon mo kaku orokanara zu omohi-hore te wi ta' naru ha, geni, osinabete omohi gatau koso ha, tare mo obosa ru rame." to, kokoro-kurusigari tamahi te, "Nideu-no-win no nisi-no-tai ni watai tama' te, toki-doki mo kayohi tamahu beku, sinobi te kikoye tamahi keru ha, Womna-Iti-no-Miya no ohom-kata ni koto-yose te obosi naru ni ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.10 | と思しながら、おぼつかなかるまじきはうれしくて、のたまふなりけり。 |
とお疑いになりながらも、会えないことがないのは嬉しくて、おっしゃって来られたのであった。 |
と兵部卿の宮はお思いになりながらも、近くへその人を置いて、常にお逢いになることのできるのはうれしいことであると思召して、 | to obosi nagara, obotukanakaru maziki ha uresiku te, notamahu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.11 | 「 さななり」と、中納言も聞きたまひて、 |
「そういうことになったらしい」と、中納言もお聞きになって、 |
この話を薫にもあそばされた。 | "Sa na' nari." to, Tyuunagon mo kiki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.12 | 「 三条宮も造り果てて、 渡いたてまつらむことを思ひしものを。かの御代りになずらへて見るべかりけるを」 |
「三条宮邸も完成して、お迎え申し上げることを考えていたが。あのお方の代わりとしてお世話すべきであった」 |
三条の宮を落成させて大姫君を迎えようとしていた自分であるが、その人の形見にせめてわが家の人にしておきたかった中の君であった | "Samdeu-no-miya mo tukuri-hate te, watai tatematura m koto wo omohi si mono wo. Kano ohom-kahari ni nazurahe te miru bekari keru wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.13 | など、 ひき返し心細し。 宮の思し寄るめりし筋は、いと似げなきことに思ひ離れて、「 おほかたの御後見は、我ならでは、また誰かは」と、 思すとや。 |
などと、昔のことを思って心細い。宮がお疑いになっていたらしい方面は、まことに似つかわしくないことと思い離れていて、「一般的なご後見は、自分以外に、誰ができようか」と、お思いになっていたとか。 |
と、このことでまた心細くなる気もする薫であった。宮の疑っておいでになるような感情はまったく捨てて、その人の保護者は自分のほかにないと、兄めいた義務感を持っているのであった。 |
nado, hiki-kahesi kokoro-bososi. Miya no obosi-yoru meri si sudi ha, ito nigenaki koto ni omohi hanare te, "Ohokata no ohom-usiromi ha, ware nara de he, mata tare kaha." to, obosu to ya. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 3/28/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 3/28/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 3/28/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 10/26/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経