47 総角(大島本) |
AGEMAKI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の中納言時代 二十四歳秋から歳末までの物語 |
Tale of Kaoru's Chunagon era, from fall to the end of the year at the age of 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第四章 中の君の物語 匂宮と中の君、朝ぼらけの宇治川を見る |
4 Tale of Naka-no-kiki Nio-no-miya and Naka-no-kimi look at Uji River in dawn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 第一段 明石中宮、匂宮の外出を諌める |
4-1 Akashi-chugu advice Nio-no-miya not to go out |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | 宮は、 その夜、内裏に参りたまひて、えまかでたまふまじげなるを、人知れず御心も空にて思し嘆きたるに、 中宮、 |
宮は、その夜、内裏に参りなさって、退出しがたそうなのを、ひそかにお心も上の空でお嘆きになっていたが、中宮が、 |
兵部卿の宮はその夜宮中へおいでになったのであるが、新婦の宇治へ行くことが非常な難事にお思われになって、人知れず心を苦しめておいでになる時に、 |
Miya ha, sono yo, uti ni mawiri tamahi te, e makade tamahu mazige naru wo, hito-sire-zu mi-kokoro mo sora ni te obosi nageki taru ni, Tyuuguu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | 「 なほ、かく独りおはしまして、世の中に、好いたまへる御名のやうやう聞こゆる、なほ、いと悪しきことなり。 何事ももの好ましく、立てたる御心なつかひたまひそ ★。 上もうしろめたげに思しのたまふ」 |
「依然として、このように独身でいらして、世間に、好色でいらっしゃるご評判がだんだんと聞こえてくるのは、やはり、とてもよくないことです。何事にも風流が過ぎて、評判を立てるようなことをなさいますな。主上も不安にお思いおっしゃっています」 |
「どんなに言ってもあなたはいつまでも一人でおいでになるものだから、このごろは私の耳にもあなたの浮いた話が少しずつはいってくるようになりましたよ。それはよくないことですよ。風流好きとか、何々趣味の人とか人に違った評判は立てられないほうがいいのですよ。お |
"Naho, kaku hitori ohasimasi te, yononaka ni, sui tamahe ru ohom-na no yau-yau kikoyuru, naho, ito asiki koto nari. Nani-goto mo mono konomasiku, tate taru mi-kokoro na tukahi tamahi so. Uhe mo usirometage ni obosi notamahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3 | と、 里住みがちにおはしますを諌めきこえたまへば、いと苦しと思して、御宿直所に出でたまひて、 御文書きてたてまつれたまへる名残も、いたくうち眺めておはしますに、 中納言の君参りたまへり。 |
と、里住みがちでいらっしゃるのをお諌め申し上げなさると、まことに辛いとお思いになって、御宿直所にお出になって、お手紙を書いて差し上げなさったその後も、ひどく物思いに耽っていらっしゃるところに、中納言の君が参上なさった。 |
と仰せになって、私邸に行っておいでがちな点で御忠告をあそばしたために、 |
to, sato-zumi-gati ni ohasimasu wo isame kikoye tamahe ba, ito kurusi to obosi te, ohom-tonowi-dokoro ni ide tamahi te, ohom-humi kaki te tatemature tamahe ru nagori mo, itaku uti-nagame te ohasimasu ni, Tyuunagon-no-Kimi mawiri tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.4 | そなたの心寄せと思せば、例よりもうれしくて、 |
あの姫君のお味方とお思いになると、いつもより嬉しくて、 |
宇治がたの人とお思いになるとうれしくて、 |
Sonata no kokoro-yose to obose ba, rei yori mo uresiku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.5 | 「 いかがすべき。いとかく暗くなりぬめるを、心も乱れてなむ」 |
「どうしよう。とてもこのように暗くなってしまったようだが、気がいらいらして」 |
「どうしたらいいだろう。こんなに暗くなってしまったのに、出られないので |
"Ikaga su beki. Ito kaku kuraku nari nu meru wo, kokoro mo midare te nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.6 | と、嘆かしげに思したり。「 よく御けしきを見たてまつらむ」と思して、 |
と、嘆かしくお思いになっていた。「よくご本心をお確かめ申したい」とお思いになって、 |
こうお言いになり、歎かわしそうなふうをお見せになったが、なおよく宮の新婦に対する真心の深さをきわめたく思った |
to, nagekasige ni obosi tari. "Yoku mi-kesiki wo mi tatematura m." to obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.7 | 「 日ごろ経て、かく 参りたまへるを、今宵さぶらはせたまはで、急ぎまかでたまひなむ、いとどよろしからぬことにや 思しきこえさせたまはむ。台盤所の方にて承りつれば、 人知れず、わづらはしき宮仕へのしるしに、あいなき勘当にやはべらむと、顔の色違ひはべりつる」 |
「久しぶりに、こうして参内なさったのに、今夜伺候あそばさないで、急いで退出なさるのは、ますますけしからぬこととお思いあそばしましょう。台盤所の方で伺ったところ、ひそかに、厄介なご用をお勤め申したために、受けなくてもよいお叱りもございましょうかと、顔が青くなりました」 |
「しばらくぶりで御所へおいでになりましたあなた様が、今夜 |
"Hi-goro he te, kaku mawiri tamahe ru wo, koyohi saburaha se tamaha de, isogi makade tamahi na m, itodo yorosikara nu koto ni ya obosi kikoye sase tamaha m. Daiban-dokoro no kata nite uketamahari ture ba, hito-sire-zu, wadurahasiki miya-dukahe no sirusi ni, ainaki kandau ni ya habera m to, kaho no iro tagahi haberi turu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.8 | と申したまへば、 |
と申し上げなさると、 |
と申して見た。 |
to mausi tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.9 | 「 いと聞きにくくぞ思しのたまふや。多くは人のとりなすことなるべし。世に咎めあるばかりの心は、何事にかは、つかふらむ。所狭き身のほどこそ、 なかなかなるわざなりけれ」 |
「まことに聞き憎いことをおっしゃいますね。多くは誰かが中傷するのでしょう。世間から非難を受けるような料簡は、どうして、起こそうか。窮屈なご身分など、かえってないほうがましだ」 |
「私がひどく悪いようにおっしゃるではないか。たいていのことは人がいいかげんなことを申し上げているからなのだろう。世間から非難をされるようなことは何もしていないではないか。何にせよ窮窟な身の上であることがいけないね。こんな身分でなければと思う」 |
"Ito kiki nikuku zo obosi notamahu ya! Ohoku ha hito no tori-nasu koto naru besi. Yo ni togame aru bakari no kokoro ha, nani-goto ni kaha, tukahu ram. Tokoro-seki mi no hodo koso, naka-naka naru waza nari kere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.10 | とて、まことに厭はしくさへ思したり。 |
とおっしゃって、ほんとうに厭わしくさえお思いであった。 |
心の底からそう思召すふうで仰せられるのを見て、 | tote, makoto ni itohasiku sahe obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.11 | いとほしく見たてまつりたまひて、 |
お気の毒に拝しなさって、 |
お気の毒になった薫は、 |
Itohosiku mi tatematuri tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.12 | 「 同じ御騒がれにこそはおはすなれ。今宵の罪には代はりきこえさせて、身をもいたづらになしはべりなむかし。 木幡の山に馬はいかがはべるべき ★。 いとどものの聞こえや障り所なからむ」 |
「同じご不興でいらっしゃいましょう。今夜のお咎めは代わり申し上げて、我が身をも滅ぼしましょう。木幡の山に馬はいかがでございましょう。ますます世間の噂が避けようもないでしょう」 |
「どうせ同じことでございますから、今晩のあなた様の罪は私が |
"Onazi ohom-sahagare ni koso ha ohasu nare. Koyohi no tumi ni ha kahari kikoye sase te, mi wo mo itadura ni nasi haberi na m kasi. Kohata-no-yama ni muma ha ikaga haberu beki. Itodo mono no kikoye ya sahari-dokoro nakara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.13 | と聞こえたまへば、ただ暮れに暮れて更けにける夜なれば、思しわびて、御馬にて出でたまひぬ。 |
と申し上げなさるので、ただもうすっかり暮れて更けてしまった夜なので、お困りになって、お馬でお出かけになった。 |
こう申し上げた。夜はますます暗くなっていくばかりであったから、忍びかねて宮は馬でお出かけになることになった。 |
to kikoye tamahe ba, tada kure ni kure te huke ni keru yo nare ba, obosi-wabi te, ohom-muma nite ide tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.14 | 「 御供には、なかなか仕うまつらじ。御後見を」 |
「お供は、かえっていたしますまい。後始末をしよう」 |
「お供にはかえって私のまいらぬほうがよろしゅうございましょう。私は |
"Ohom-tomo ni ha, naka-naka tukau-matura zi. Ohom-usiromi wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.15 | とて、この君は内裏にさぶらひたまふ。 |
と言って、この君は内裏にお残りになる。 |
と言って、薫は残ることにした。 |
tote, kono Kimi ha uti ni saburahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 第二段 薫、明石中宮に対面 |
4-2 Kaoru meets Akashi-chugu at the Court of Mikado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | 中宮の御方に参りたまひつれば、 |
中宮の御方に参上なさると、 |
薫が中宮の御殿へまいると、 |
Tyuuguu-no-Ohomkata ni mawiri tamahi ture ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | 「 宮は出でたまひぬなり。あさましくいとほしき御さまかな。いかに人見たてまつるらむ。上聞こし召しては、 諌めきこえぬが言ふかひなき、と思しのたまふこそわりなけれ」 |
「宮はお出かけになったそうな。あきれて困ったお方ですこと。どのように世間の人はお思い申すことでしょう。主上がお耳にあそばしたら、ご注意申し上げないのがいけないのだ、とお考えになり仰せになるのが耐えられません」 |
「兵部卿の宮さんはお出かけになったらしい。困った御行跡ね。お |
"Miya ha ide tamahi nu nari. Asamasiku itohosiki ohom-sama kana! Ikani hito mi tatematuru ram? Uhe kikosimesi te ha, isame kikoye nu ga ihukahinaki, to obosi notamahu koso wari nakere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.3 | とのたまふ。 あまた宮たちの、かくおとなび整ひたまへど、 大宮は、いよいよ若くをかしきけはひなむ、まさりたまひける。 |
と仰せになる。大勢の宮たちが、このようにご成人なさったが、大宮は、ますます若く美しい感じが、優っていらっしゃるのであった。 |
こうお |
to notamahu. Amata Miya-tati no, kaku otonabi totonohi tamahe do, Oho-Miya ha, iyo-iyo wakaku wokasiki kehahi nam, masari tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.4 | 「 女一の宮も、かくぞおはしますべかめる。いかならむ折に、かばかりにてももの近く、御声をだに聞きたてまつらむ」と、あはれとおぼゆ。「 好いたる人の、おぼゆまじき心つかふらむも、 かうやうなる御仲らひの、さすがに気遠からず入り立ちて、心にかなはぬ折のことならむかし。 |
「女一の宮も、このように美しくいらっしゃるようである。どのような機会に、この程度にお側近く、お声だけでもお聞きいたしたい」と、しみじみと思われる。「好色な男が、けしからぬ料簡を起こすのも、このようなお間柄で、そうはいっても他人行儀でなく出入りして、思いどおりにできないときのことなのだろう。 |
"Womna-Iti-no-Miya mo, kaku zo ohasimasu beka' meru. Ika nara m wori ni, kabakari nite mo mono-tikaku, ohom-kowe wo dani kiki tatematura m." to, ahare to oboyu. "Sui taru hito no, oboyu maziki kokoro tukahu ram mo, kau yau naru ohom-nakarahi no, sasuga ni kedohokara zu iri-tati te, kokoro ni kanaha nu wori no koto nara m kasi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.5 | わが心のやうに、ひがひがしき心のたぐひ やは、また世にあんべかめる。それに、なほ 動きそめぬるあたりは、えこそ思ひ絶えね」 |
自分のように、偏屈な性分は、他に世にいるだろうか。なのに、やはり心動かされた女は、思い切ることができないのだ」 |
自分のように異性への関心の淡いものはないのであるが、それでさえもなお動き始めた心はおさえがたいものなのであるから、 | Waga kokoro no yau ni, higa-higasiki kokoro no taguhi ya ha, mata yo ni an beka' meru. Sore ni, naho ugoki some nuru atari ha, e koso omohi taye ne." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.6 | など思ひゐたまへる。さぶらふ限りの女房の容貌心ざま、いづれとなく悪ろびたるなく、めやすくとりどりにをかしきなかに、あてにすぐれて目にとまるあれど、 さらにさらに乱れそめじの心にて、いときすくにもてなしたまへり。ことさらに 見えしらがふ人もあり。 |
などと思っていらっしゃった。お仕えしているすべての女房の器量や気立ては、どの人となく悪い者はなく、無難でそれぞれに美しい中に、上品で優れて目にとまるのもいるが、全然乱れまいとの気持ちで、まことに生真面目に振る舞っていらっしゃった。わざと気を引いてみる女房もいる。 |
などと薫は思っていた。侍女たちは |
nado omohi wi tamahe ru. Saburahu kagiri no nyoubau no katati kokoro-zama, idure to naku warobi taru naku, meyasuku tori-dori ni wokasiki naka ni, ate ni sugure te me ni tomaru are do, sarani sarani midare some zi no kokoro nite, ito kisuku ni motenasi tamahe ri. Kotosara ni miye siragahu hito mo ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.7 | おほかた恥づかしげに、もてしづめたまへるあたりなれば、 上べこそ心ばかり もてしづめたれ、 心々なる世の中なりければ ★、色めかしげにすすみたる下の心漏りて見ゆるもあるを、「さまざまにをかしくも、あはれにもあるかな」と、 立ちてもゐても、ただ常なきありさまを思ひありきたまふ。 |
だいたいが気後れするような、沈着に振る舞っていらっしゃる所なので、表面はしとやかにしているが、人の心はさまざまなので、色っぽい性分の本心をちらちらと見せるのもいるが、「人それぞれにおもしろくもあり、いとおしくもあるなあ」と、立っても座っても、ただ世の無常を思い続けていらっしゃる。 |
気品を傷つけないようにと上下とも慎み深く暮らす女房たちにも、個性はそれぞれ違ったものであるから、美しい薫への好奇心が、おさえられつつも外へ現われて見える人などに、薫は |
Ohokata hadukasige ni, mote-sidume tamahe ru atari nare ba, uhabe koso kokoro bakari mote-sidume tare, kokoro-gokoro naru yononaka nari kere ba, iro-mekasige ni susumi taru sita no kokoro mori te miyuru mo aru wo, "Sama-zama ni wokasiku mo, ahare ni mo aru kana!" to, tati te mo wi te mo, tada tune naki arisama wo omohi ariki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 第三段 女房たちと大君の思い |
4-3 The thinking of Ohoi-kimi and her maids |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | かしこには、中納言殿のことことしげに言ひなしたまへりつるを、 夜更くるまでおはしまさで、御文のあるを、「 さればよ」と胸つぶれておはするに、夜中近くなりて、荒ましき風のきほひに、いともなまめかしくきよらにて匂ひおはしたるも、 いかがおろかにおぼえたまはむ。 |
あちらでは、中納言殿が仰々しくおっしゃったのを、夜の更けるまでいらっしゃらず、お手紙のあるのを、「やはりそうであったか」と胸をつぶしておいでになると、夜半近くなって、荒々しい風に競うようにして、たいそう優雅で美しく匂っていらっしゃったのも、どうしていい加減に思われなさろう。 |
宇治では薫から |
Kasiko ni ha, Tyuunagon-dono no koto-kotosige ni ihi-nasi tamahe ri turu wo, yo hukuru made ohasimasa de, ohom-humi no aru wo, "Sarebayo!" to mune tubure te ohasuru ni, yonaka tikaku nari te, aramasiki kaze no kihohi ni, ito mo namamekasiku kiyora nite nihohi ohasi taru mo, ikaga oroka ni oboye tamaha m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.2 | 正身も、いささか うちなびきて、 思ひ知りたまふことあるべし。 いみじくをかしげに盛りと見えて、引きつくろひたまへるさまは、「 ましてたぐひあらじはや」とおぼゆ。 |
ご本人も、わずかにうちとけて、お分かりになることがきっとあるにちがいない。たいそう美しく女盛りと見えて、ひきつくろっていらっしゃる様子は、「この方以上の方があろうか」と思われる。 |
新夫人の中の君も前に似ぬ好意をお持ちしたことと思われる。中の君は非常に美しい盛りの |
Syauzimi mo, isasaka uti-nabiki te, omohi-siri tamahu koto aru besi. Imiziku wokasige ni sakari to miye te, hiki-tukurohi tamahe ru sama ha, "Masite taguhi ara zi ha ya." to oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.3 | さばかりよき人を多く見たまふ御目にだに、けしうはあらずと、容貌よりはじめて、多く近まさりしたりと思さるれば、山里の老い人どもは、まして口つき憎げにうち笑みつつ、 |
あれほど美しい人を数多く御覧になっているお目にさえ、悪くはないと、器量をはじめとして、多く近勝りして思われなさるので、山里の老女連中は、まして慎みなく相好を崩して微笑しながら、 |
多くの美女を知っておいでになる宮の御目にも欠点をお見いだしになることはなくて、姿も心も接近してますますすぐれたことの明らかになった恋人であると思召すばかりであったから、山荘の老いた女房などは満足したか自身の表情がどんなに醜いかも知らずに、ゆがんだ |
Sabakari yoki hito wo ohoku mi tamahu ohom-me ni dani, kesiu ha ara zu to, katati yori hazime te, ohoku tika-masari si tari to obosa rure ba, yamazato no Oyi-bito-domo ha, masite kuti-tuki nikuge ni uti-wemi tutu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.4 | 「 かくあたらしき御ありさまを、なのめなる際の人の 見たてまつりたまはましかば、いかに口惜しからまし。思ふやうなる御宿世」 |
「このように惜しいご様子を、並の身分の男性がお世話申し上げなさるようになったら、どんなに口惜しいことでしょう。思いどおりのご運勢を」 |
これほどにもりっぱな方が凡人の妻におなりになったとしたらどんなに残念に思われるであろう、御運よく理想的な |
"Kaku atarasiki ohom-arisama wo, nanome naru kiha no hito no mi tatematuri tamaha masika ba, ikani kutiwosikara masi. Omohu yau naru ohom-sukuse." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.5 | と聞こえつつ、 姫宮の御心を、あやしく ひがひがしくもてなしたまふを、もどき口ひそみきこゆ。 |
と申し上げながら、姫宮のご性格を、妙な偏屈者のようにお振る舞いなさるのを、悪しざまに口をとがらせてご非難申し上げる。 |
と言い合い、大姫君が薫の熱心な求婚に応じようとしないのをひそかに非難していた。 | to kikoye tutu, Hime-Miya no mi-kokoro wo, ayasiku higa-higasiku motenasi tamahu wo, modoki kuti hisomi kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.6 | 盛り過ぎたるさまどもに、あざやかなる花の色々、似つかはしからぬをさし縫ひつつ、 ありつかずとりつくろひたる姿どもの、罪許されたるもなきを見わたされたまひて、姫宮、 |
盛りを過ぎた身なのに、派手な花の色とりどりや、似つかわしくないのを縫いながら、身にもつかずめかしこんでいる女房連中の姿が、見られた者もいないのを見渡しなさって、姫宮は、 |
こうした中年になった人たちが薫から贈られた美しいいろいろな絹で衣装を縫って、それぞれ似合いもせぬ盛装をしている中に一人でも感じのよいと思われる女房はなかった。 |
Sakari sugi taru sama-domo ni, azayaka naru hana no iro-iro, nitukahasikara nu wo sasi-nuhi tutu, arituka zu toritukurohi taru sugata-domo no, tumi yurusa re taru mo naki wo mi-watasa re tamahi te, Hime-Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.7 | 「 我もやうやう盛り過ぎぬる身ぞかし。鏡を見れば、痩せ痩せになりもてゆく。おのがじしは、この人どもも、 我悪しとやは思へる。うしろでは知らず顔に、額髪をひきかけつつ、色どりたる顔づくりをよくしてうち振る舞ふめり。わが身にては、まだいとあれがほどにはあらず。目も鼻も直しとおぼゆるは、心のなしにやあらむ」 |
「わたしもだんだん盛りを過ぎた身だわ。鏡を見ると、痩せ痩せになってゆく。めいめいは、この女房連中も、自分自身を醜いと思っていようか。後ろ姿は知らない顔で、額髪をかき上げながら、化粧した顔づくろいをよくして振る舞っているようだ。自分の身としては、まだあの女房ほどは醜くはない。目鼻だちも尋常だと思われるのは、うぬぼれであろうか」 |
自分も盛りの過ぎた女である、このごろ鏡を見ると顔は |
"Ware mo yau-yau sakari sugi nuru mi zo kasi. Kagami wo mire ba, yase-yase ni nari mote yuku. Onogazisi ha, kono Hito-domo mo, ware asi to yaha omohe ru? Usirode ha sira-zu-gaho ni, hitahi-gami wo hiki-kake tutu, iro-dori taru kaho dukuri wo yoku si te uti-hurumahu meri. Waga mi nite ha, mada ito are ga hodo ni ha ara zu. Me mo hana mo nahosi to oboyuru ha, kokoro no nasi ni ya ara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.8 | とうしろめたくて、見出だして臥したまへり。「 恥づかしげならむ人に見えむことは、いよいよかたはらいたく、今一二年あらば、衰へまさりなむ。 はかなげなる身のありさまを」と、御手つきの細やかにか弱く、あはれなるをさし出でても、 世の中を思ひ続けたまふ。 |
と不安で、外を眺めながら臥せっていらっしゃった。「気後れするような方と結婚することは、ますますみっともなく、もう一、二年したらいっそう衰えよう。頼りない身の上を」と、お腕が細っそりとして弱々しく、痛々しいのをさし出してみても、世の中を思い続けなさる。 |
と気恥ずかしいような思いをしながら |
to usirometaku te, mi-idasi te husi tamahe ri. "Hadukasige nara m hito ni miye m koto ha, iyo-iyo kataharaitaku, ima hito-tose huta-tose ara ba, otorohe masari na m. Hakanage naru mi no arisama wo." to, ohom-tetuki no komayaka ni kayowaku, ahare naru wo sasi-ide te mo, yononaka wo omohi tuduke tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 第四段 匂宮と中の君、朝ぼらけの宇治川を見る |
4-4 Nio-no-miya and Naka-no-kimi look at Uji River in dawn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.1 | 宮は、ありがたかりつる御暇のほどを思しめぐらすに、「 なほ、心やすかるまじきことにこそは」と、胸ふたがりておぼえたまひけり。 大宮の聞こえたまひしさまなど語りきこえたまひて、 |
匂宮は、めったにないお暇のほどをお考えになると、「やはり、気軽にできそうにないことだ」と、胸が塞がって思われなさるのであった。大宮がご注意申し上げなさったことなどをお話し申し上げなさって、 |
兵部卿の宮は今夜のお出かけにくかったことをお考えになると、将来も不安におなりになって、今さえそれでお胸がふさがれてしまうようになるのであった。中宮の仰せられた話などをされて、 |
Miya ha, arigatakari turu ohom-itoma no hodo wo obosi-megurasu ni, "Naho, kokoro-yasukaru maziki koto ni koso ha." to, mune hutagari te oboye tamahi keri. Oho-Miya no kikoye tamahi si sama nado katari kikoye tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.2 | 「 思ひながらとだえあらむを、いかなるにか、と思すな。夢にてもおろかならむに、かくまでも参り来まじきを。心のほどやいかがと疑ひて、思ひ乱れたまはむが心苦しさに、 身を捨ててなむ。常にかくは え惑ひありかじ。さるべきさまにて、近く渡したてまつらむ」 |
「愛していながら途絶えがあろうが、どうしたことなのか、とお案じなさるな。かりそめにも疎かに思ったら、このようには参りません。心の中をどうかしらと疑って、お悩みになるのがお気の毒で、身を捨てて参ったのです。いつもこのようには抜け出すことはできないでしょう。しかるべき用意をして、近くにお移し申しましょう」 |
「変わりない愛を持っていながら来られない日が続いても疑いは持たないでください。仮にもおろそかにあなたを思っているのだったら、こんな苦心を払って今夜なども出て来られるはずはありません。それだのに私の愛を信じることがおできにならないで、 |
"Omohi nagara todaye ara m wo, ika naru ni ka, to obosu na. Yume nite mo oroka nara m ni, kaku made mo mawiri ku maziki wo. Kokoro no hodo ya ikaga to utagahi te, omohi midare tamaha m ga kokoro-gurusisa ni, mi wo sute te nam. Tune ni kaku ha e madohi arika zi. Saru-beki sama ni te, tikaku watasi tatematura m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.3 | と、いと深く聞こえたまへど、「 絶え間あるべく思さるらむは、音に聞きし御心のほどしるべきにや」と心おかれて、わが御ありさまから、さまざまもの嘆かしくてなむありける。 |
と、とても心をこめて申し上げなさるが、「絶え間がきっとあるように思われなさるのは、噂に聞いたお心のほどが現れたのかしら」と疑われて、ご自身の頼りない様子を思うと、いろいろと悲しいのであった。 |
宮はこれを真心からお言いになるのであったが、間の途絶えるであろうことを今からお言いになるのは、名高い多情な生活から、恨ませまいための予防の線をお張りになるのであろうと、心細さに |
to, ito hukaku kikoye tamahe do, "Taye-ma aru beku obosaru ram ha, oto ni kiki si mi-kokoro no hodo siru beki ni ya?" to kokoro-oka re te, waga ohom-arisama kara, sama-zama mono-nagekasiku te nam ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
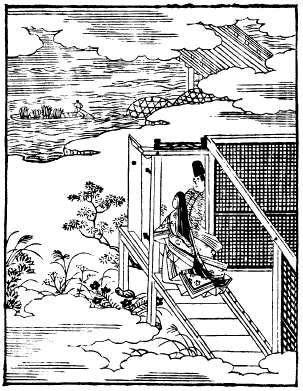 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.4 | 明け行くほどの空に、妻戸押し開けたまひて、 もろともに誘ひ出でて見たまへば、霧りわたれるさま、 所からのあはれ多く添ひて、 例の、柴積む舟のかすかに行き交ふ跡の白波 ★、「 目馴れずもある住まひのさまかな」と、 色なる御心には、をかしく思しなさる。 |
明けてゆく空に、妻戸を押し開けなさって、一緒に誘って出て御覧になると、霧の立ちこめた様子、場所柄の情趣が多く加わって、例の、柴積み舟がかすかに行き来する跡の白波、「見慣れない住まいの様子だなあ」と、物事に感じやすいお心には、おもしろく思われなさる。 |
夜明けに近い空模様を、横の妻戸を押しあけて宮は女王も誘って出ておながめになるのであった。霧が深く立って特色のある宇治の寂しい |
Ake-yuku hodo no sora ni, tumado osi-ake tamahi te, morotomo ni izanahi ide te mi tamahe ba, kiri watare ru sama, tokoro-gara no ahare ohoku sohi te, rei no, siba tumu hune no kasuka ni yuki-kahu ato no sira-nami, "Me-nare zu mo aru sumahi no sama kana!" to, iro naru mi-kokoro ni ha, wokasiku obosi nasa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.5 | 山の端の光やうやう見ゆるに、女君の御容貌のまほにうつくしげにて、「 限りなくいつき据ゑたらむ姫宮も、かばかりこそはおはすべかめれ。思ひなしの、 わが方ざまのいといつくしきぞかし。こまやかなる匂ひなど、うちとけて見まほしく」、なかなかなる心地す。 |
山の端の光がだんだんと見えるころに、女君のご器量が整っていてかわいらしくて、「この上なく大切に育てられた姫君も、これほどでいらっしゃろうか。気のせいで、こちらの身内の方がとても立派に思われる。きめ濃やかな美しさなどは、気を許して見ていたく」、かえって堪えがたい気がする。 |
東の山の上からほのめいてきた暁の微光に見る中の君の容姿は整いきった美しさで、最上の所にかしずかれた内親王もこれにまさるまいとお思われになった。現在の |
Yama-no-ha no hikari yau-yau miyuru ni, Womna-Gimi no ohom-katati no maho ni utukusige nite, "Kagirinaku ituki suwe tara m Hime-Miya mo, kabakari koso ha ohasu beka' mere. Omohi-nasi no, waga kata zama no ito itukusiki zo kasi. Komayaka naru nihohi nado, utitoke te mi mahosiku", naka-naka naru kokoti su. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.6 | 水の音なひなつかしからず、 宇治橋のいともの古りて見えわたさるるなど ★、霧晴れゆけば、いとど荒ましき岸のわたりを、「 かかる所に、いかで年を経たまふらむ」など、うち涙ぐまれたまへるを、いと 恥づかしと聞きたまふ。 |
水の音が騒がしく、宇治橋がたいそう古びて見渡されるなど、霧が晴れてゆくと、ますます荒々しい岸の辺りを、「このような所に、どのようにして年月を過ごしてこられたのだろう」などと、涙ぐんでおっしゃるのを、まことに恥ずかしいとお聞きになる。 |
「どうしてこんな土地に長い間いることができたのですか」 とお言いになり、宮の涙ぐんでおいでになるのを見て、女王は恥ずかしい気がした。 |
Midu no otonahi natukasikara zu, Udi-basi no ito mono-huri te miye watasa ruru nado, kiri hare-yuke ba, itodo aramasiki kisi no watari wo, "Kakaru tokoro ni, ikade tosi wo he tamahu ram." nado, uti-namida-gumi tamahe ru wo, ito hadukasi to kiki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.7 | 男の御さまの、限りなくなまめかしくきよらにて、この世のみならず契り頼めきこえたまへば、「 思ひ寄らざりしこととは思ひながら、なかなか、かの目馴れたりし中納言の恥づかしさよりは」とおぼえたまふ。 |
男君のご様子が、この上なく優雅で美しくて、この世だけでなく来世まで夫婦のお約束申し上げなさるので、「思い寄らなかったこととは思いながらも、かえって、あの目馴れた中納言の恥ずかしさよりは」と思われなさる。 |
そして今よく見る宮のお姿はきわめて |
Wotoko no ohom-sama no, kagirinaku namamekasiku kiyora nite, konoyo nomi nara zu tigiri tanome kikoye tamahe ba, "Omohi-yora zari si koto to ha omohi nagara, naka-naka, kano me-nare tari si Tyuunagon no hadukasisa yori ha." to oboye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.8 | 「 かれは思ふ方異にて、いといたく澄みたるけしきの、 見えにくく恥づかしげなりしに、 よそに思ひきこえしは、ましてこよなくはるかに、 一行書き出でたまふ御返り事だに、つつましくおぼえしを、久しく途絶えたまはむは、心細からむ」 |
「あの方は愛する方が別にいて、とてもたいそう澄ましていた様子が、会うのも気づまりであったが、お噂だけでお思い申し上げていた時は、いっそうこの上なく遠くに、一行お書きになるお返事でさえ。気後れしたが、久しく途絶えなさることは、心細いだろう」 |
あの人の熱愛している人は自分でなくもあったし、澄みきったような心の様子に現われて見える点でも親しまれないところがあった、しかもこの宮をそのころの自分はどう思っていたであろう、まして遠い遠い所の存在としていた。短いお手紙に返事をすることすら恥ずかしかった方であるのに、今の心はそうでない、久しくおいでにならぬことがあれば心細いであろう | "Kare ha omohu kata koto ni te, ito itaku sumi taru kesiki no, miye nikuku hadukasige nari si ni, yoso ni omohi kikoye si ha, masite koyonaku haruka ni, hito-kudari kaki-ide tamahu ohom-kaheri-goto dani, tutumasiku oboye si wo, hisasiku todaye tamaha m ha, kokoro-bosokara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.9 | と思ひならるるも、 我ながらうたて、と思ひ知りたまふ。 |
と思われるのも、我ながら嫌なと、思い知りなさる。 |
と思われるのも、われながら怪しく恥ずかしい変わりようであると中の君は心で思った。 | to omohi nara ruru mo, ware nagara utate, to omohi-siri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 第五段 匂宮と中の君和歌を詠み交して別れる |
4-5 Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchange waka , and part |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.1 | 人びといたく声づくり催しきこゆれば、 京におはしまさむほど、はしたなからぬほどにと、いと心あわたたしげにて、心より外ならむ夜がれを、返す返すのたまふ。 |
お供の者たちがひどく咳払いをしてお促し申し上げるので、京にお着きになる時刻が、みっともなくないころにと、たいそう気ぜわしそうに、心にもなく来られない夜もあろうことを、繰り返し繰り返しおっしゃる。 |
お供の人たちが次々に促しの声を立てるのを聞いておいでになって、京へはいって人目を引くように明るくならぬようにと、宮はおいでになろうとする際も御自身の意志でない通い |
Hito-bito itaku kowa-dukuri moyohosi kikoyure ba, Kyau ni ohasimasa m hodo, hasitanakara nu hodo ni to, ito kokoro-awatatasige ni te, kokoro yori hoka nara m yo-gare wo, kahesu-gahesu notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.2 | 「中絶えむものならなくに 橋姫の |
「中が切れようとするのでないのに |
「中絶えんものならなくに橋姫の | "Naka taye m mono nara naku ni Hasi-Hime no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.3 | 片敷く袖や夜半に濡らさむ」 |
あなたは独り敷く袖は夜半に濡らすことだろう」 |
片敷く |
kata-siku sode ya yoha ni nurasa m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.4 | 出でがてに、立ち返りつつやすらひたまふ。 |
帰りにくく、引き返しては躊躇していらっしゃる。 |
帰ろうとしてまた |
Ide-gate ni, tati-kaheri tutu yasurahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.5 | 「絶えせじのわが頼みにや宇治橋の |
「切れないようにとわたしは信じては |
「絶えせじのわが頼みにや宇治橋の | "Taye se zi no waga tanomi ni ya Udi-basi no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.6 | 遥けきなかを待ちわたるべき」 |
宇治橋の遥かな仲をずっとお待ち申しましょう」 |
はるけき中を待ち渡るべき」 |
harukeki naka wo mati-wataru beki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.7 | 言には出でねど、もの嘆かしき御けはひは、限りなく思されけり。 |
口には出さないが、何となく悲しいご様子は、この上なくお思いなさるのであった。 |
などとだけ言い、言葉は少ないながらも女王の様子に別れの悲しみの見えるのをお知りになり、たぐいもない愛情を宮は覚えておいでになった。 |
Koto ni ha ide ne do, mono-nagekasiki ohom-kehahi ha, kagirinaku obosa re keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.8 | 若き人の御心にしみぬべく、たぐひすくなげなる 朝けの御姿を見送りて、名残とまれる御移り香なども、人知れずものあはれなるは、 されたる御心かな。今朝ぞ、もののあやめ見ゆるほどにて、 人びと覗きて見たてまつる。 |
若い女性のお心にしみるにちがいない、世にも稀な朝帰りのお姿を見送って、後に残っている御移り香なども、人知れずなにやらせつない気がするのは、機微の分かるお心だこと。今朝は、物の見分けもつく時分なので、女房たちが覗いて拝する。 |
若い女性の心に感動を与えぬはずのない宮の御朝姿を見送って、あとに残ったにおいなどの身にしむ人にいつか女王はなっていた。お立ちのおそかった |
Wakaki hito no mi-kokoro ni simi nu beku, taguhi sukunage naru asake no ohom-sugata wo mi-okuri te, nagori tomare ru ohom-uturi-ga nado mo, hito-sire-zu mono-ahare naru ha, sare taru mi-kokoro kana! Kesa zo, mono no ayame miyuru hodo nite, hito-bito nozoki te mi tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.9 | 「 中納言殿は、なつかしく恥づかしげなるさまぞ、添ひたまへりける。 思ひなしの、今ひと際にや、この御さまは、いとことに」 |
「中納言殿は、優しく恥ずかしい感じが、加わった方であった。気のせいか、もう一段尊い身分なので、この方のお姿は、まことに格別で」 |
「中納言様はなつかしい御気品のよさに特別なところがおありになります。今一段上の御身分という思いなしからでしょうか、はなやかな御 |
"Tyuunagon-dono ha, natukasiku hadukasige naru sama zo, sohi tamahe ri keru. Omohi-nasi no, ima hito-kiha ni ya, kono ohom-sama ha, ito koto ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.10 | など、めできこゆ。 |
などと、お誉め申し上げる。 |
こんなことを言ってほめそやした。 |
nado, mede kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.11 | 道すがら、心苦しかりつる御けしきを思し出でつつ、立ちも返りなまほしく、さま悪しきまで思せど、世の聞こえを忍びて 帰らせたまふほどに、えたはやすくも紛れさせたまはず。 |
道すがら、お気の毒であったご様子をお思い出しになりながら、引き返したく、体裁悪くまでお思いになるが、世間の評判を我慢してお帰りあそばすことなので、たやすくお出かけになることはおできになれない。 |
京への道すがら、別れにめいったふうを見せた女王をお思い出しになって、このままもう一度山荘へ引き返したいと、御自身ながら見苦しく思召すまで恋しくお思われになるのであったが、世間の取り |
Miti sugara, kokoro-gurusikari turu mi-kesiki wo obosi-ide tutu, tati mo kaheri na mahosiku, sama asiki made obose do, yo no kikoye wo sinobi te kahera se tamahu hodo ni, e tahayasuku mo magire sase tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.12 | 御文は 明くる日ごとに、あまた返りづつたてまつらせたまふ。「 おろかにはあらぬにや」と思ひながら、おぼつかなき日数の積もるを、「 いと心尽くしに見じと思ひしものを、身にまさりて心苦しくもあるかな」と、 姫宮は思し嘆かるれど、いとどこの君の思ひ沈みたまはむにより、つれなくもてなして、「 みづからだに、なほかかること思ひ加へじ」と、いよいよ深く思す。 |
お手紙は毎日毎日に、たくさん書いて差し上げなさる。「いい加減なお気持ちではないのでは」と思いながら、訪れのない日数が続くのを、「まことに心配の限りを尽くすことはしまいと思っていたが、自分のこと以上においたわしいことだわ」と、姫宮はお悲しみになるが、ますますこの妹君がお悲しみに沈んでいらっしゃろうことから、平静を装って、「自分自身でさえ、やはりこのような心配を増やすまい」と、ますます強くお思いになる。 |
お手紙だけを日ごとに幾通もお送りになった。誠意がないのではおありになるまいと思いながらもお途絶えの日が積もっていくことで、姉の女王は思い悩んで、こんな結果を見て苦労をすることがないようにと願っていたものを、自身が当事者である以上に苦しいことであると歎かれるのであったが、これを表面に見せてはいっそう中の君が気をめいらせることになろうと思う心から、気にせぬふうを装いながらも、自分だけでも結婚しての苦を味わうまいといよいよ薫の望むことに心の離れていく大姫君であった。 |
Ohom-humi ha akuru hi-goto ni, amata kaheri dutu tatematura se tamahu. "Oroka ni ha ara nu ni ya?" to omohi nagara, obotukanaki hi-kazu no tumoru wo, "Ito kokoro-dukusi ni mi zi to omohi si mono wo, mi ni masari te kokoro-gurusiku mo aru kana!" to, Hime-Miya ha obosi nageka rure do, itodo kono Kimi no omohi sidumi tamaha m ni yori, turenaku motenasi te, "Midukara dani, naho kakaru koto omohi kuhahe zi." to, iyo-iyo hukaku obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.13 | 中納言の君も、「 待ち遠にぞ思すらむかし」と思ひやりて、我があやまちにいとほしくて、宮を聞こえおどろかしつつ、 絶えず御けしきを見たまふに、いといたく思ほし入れたるさまなれば、さりともと、うしろやすかりけり。 |
中納言の君も、「待ち遠しくお思いだろう」と想像して、自分の責任からおいたわしくて、宮をお促し申し上げながら、絶えずご様子を御覧になると、たいそうひどく打ち込んでいらっしゃる様子なので、そうはいってもと、安心であった。 |
薫も兵部卿の宮の宇治へおいでになれない事情を知っていて、山荘の女王が待ち遠しく思うことであろうと、自身の責任であるように思い、宮にそれとなくお促しもし、宮の御近状にも注意を怠らなかったが、宮が宇治の女王に愛情を傾倒しておいでになることは明らかになったために、今の状態はこうでも不安がることはないと中の君のために胸をなでおろす思いをした。 |
Tyuunagon-no-Kimi mo, "Mati-doho ni zo obosu ram kasi." to omohi-yari te, waga ayamati ni itohosiku te, Miya wo kikoye odorokasi tutu, taye zu mi-kesiki wo mi tamahu ni, ito itaku omohosi ire taru sama nare ba, saritomo to, usiroyasukari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | 第六段 九月十日、薫と匂宮、宇治へ行く |
4-6 September 10, Kaoru and Nio-no-miya visit to Uji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.1 | 九月十日のほどなれば、野山のけしきも思ひやらるるに、 時雨めきてかきくらし、空のむら雲恐ろしげなる夕暮、宮いとど静心なく眺めたまひて、 いかにせむと、御心一つを出で立ちかねたまふ ★。 折推し量りて、参りたまへり。「 ▼ ふるの山里いかならむ」と、おどろかしきこえたまふ。いとうれしと思して、もろともに誘ひたまへば、例の、一つ御車にておはす。 |
九月十日のころなので、野山の様子も自然と想像されて、時雨めいて暗くなり、空のむら雲が恐ろしそうな夕暮に、宮はますます落ち着きなく物思いに耽りなさって、どうしようかと、ご自身では決心をしかねていらっしゃる。そのところを推量して、参上なさった。「ふるの山里はどうでしょうか」と、お誘い申し上げなさる。まことに嬉しいとお思いになって、一緒にお出かけになるので、例によって、一車に相乗りしてお出かけになる。 |
九月の十日で、野山の秋の色がだれにも思いやられる時である、空は暗い 「山里のほうはどうでしょう」 中納言の言ったことはこれであった。お喜びになって、 「では今からいっしょに出かけよう」 とお言いになったため、 |
Ku-gwati towo-ka no hodo nare ba, noyama no kesiki mo omohi-yara ruru ni, sigure-meki te kaki-kurasi, sora no mura-kumo osorosige naru yuhu-gure, Miya itodo sidu-kokoro naku nagame tamahi te, ikani se m to, mi-kokoro hitotu wo ide-tati kane tamahu. Wori osihakari te, mawiri tamahe ri. "Huru no yama-zato ika nara m?" to, odorokasi kikoye tamahu. Ito uresi to obosi te, morotomo ni izanahi tamahe ba, rei no, hitotu mi-kuruma nite ohasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.2 | 分け入りたまふままにぞ、 まいて眺めたまふらむ心のうち、いとど推し量られたまふ。道のほども、 ただこのことの心苦しきを語らひきこえたまふ。 |
分け入りなさるにつれて、まして物思いしているだろう心中を、ますますご想像される。道中も、ただこのことのお気の毒さをお話し合いなさる。 |
山路へかかってくるにしたがって、山荘で物思いをしている恋人を多く哀れにお思いになる宮でおありになった。同車の人へもその点で御自身も苦しんでおいでになることばかりをお話しになった。 | Wake-iri tamahu mama ni zo, maite nagame tamahu ram kokoro no uti, itodo osihakara re tamahu. Miti no hodo mo, tada kono koto no kokoro-gurusiki wo katarahi kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.3 | たそかれ時のいみじく心細げなるに、雨は冷やかにうちそそきて、秋果つるけしきのすごきに、うちしめり濡れたまへる匂ひどもは、世のものに似ず艶にて、うち連れたまへるを、 山賤どもは、いかが心惑ひもせざらむ。 |
黄昏時のひどく心細いうえに、雨が冷たく降り注いで、秋の終わる気色がぞっとする感じなので、しっとりと濡れていらっしゃるお二方の芳気は、この世のものに似ず優艷で、連れ立っていらっしゃるのを、山賤連中は、どうしてうろたえぬことがあろうか。 |
行く秋の |
Tasokare-doki no imiziku kokoro-bosoge naru ni, ame ha hiyayaka ni uti-sosoki te, aki haturu kesiki no sugoki ni, uti-simeri nure tamahe ru nihohi-domo ha, yo no mono ni ni zu en nite, uti-ture tamahe ru wo, yamagatu-domo ha, ikaga kokoro-madohi mo se zara m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.4 | 女ばら、日ごろうちつぶやきつる、名残なく笑みさかえつつ、御座ひきつくろひなどす。 京に、さるべき所々に行き散りたる娘ども、姪だつ人、二、三人尋ね寄せて参らせたり。年ごろ あなづりきこえける心浅き人びと、めづらかなる客人と思ひ驚きたり。 |
女房らは、日頃ぶつぶつ言っていたが、そのあとかたもなくにこにことして、ご座所を整えたりなどする。京に、しかるべき家々に散り散りになっていた娘連中や、姪のような人を、二、三人呼び寄せて仕えさせていた。長年軽蔑申し上げてきた思慮の浅い人びとは、珍しい客人と思って驚いていた。 |
毎日毎日婿君の情の薄さをかこっていた山荘の女房たちは、 |
Womna-bara, higoro uti-tubuyaki turu, nagori naku wemi sakaye tutu, o-masi hiki-tukurohi nado su. Kyau ni, saru-beki tokoro-dokoro ni yuki-tiri taru musume-domo, mei-datu hito, hutari, mitari tadune yose te mawira se tari. Tosi-goro anaduri kikoye keru kokoro-asaki hito-bito, meduraka naru marauto to omohi odoroki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.5 | 姫宮も、折うれしく思ひきこえたまふに、 さかしら人の添ひたまへるぞ、 恥づかしくもありぬべく、なまわづらはしく思へど、心ばへの のどかにもの深くものしたまふを、「 げに、人はかくはおはせざりけり」と見あはせたまふに、 ありがたしと思ひ知らる。 |
姫宮も、ちょうどよい折柄と嬉しくお思い申し上げなさるが、利口ぶった方が一緒にいらっしゃるのが、気恥ずかしくもあり、何となく厄介にも思うが、人柄がゆったりと慎重でいらっしゃるので、「なるほど、宮はこのようではおいででない」とお見比べなさると、めったにない方だと思い知られる。 |
大姫君はこの寂しい夜を |
Hime-Miya mo, wori uresiku omohi kikoye tamahu ni, sakasira-bito no sohi tamahe ru zo, hadukasiku mo ari nu beku, nama-wadurahasiku omohe do, kokorobahe no nodoka ni mono-hukaku monosi tamahu wo, "Geni, hito ha kaku ha ohase zari keri." to mi-ahase tamahu ni, arigatasi to omohi sira ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | 第七段 薫、大君に対面、実事なく朝を迎える |
4-7 Kaoru meets Ohoi-kimi and they see a morning without sexual relation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.1 | 宮を、所につけては、いとことにかしづき入れたてまつりて、 この君は、主人方に心やすくもてなしたまふものから、 まだ客人居のかりそめなる方に出だし放ちたまへれば ★、いとからしと思ひたまへり。怨みたまふもさすがにいとほしくて、物越に対面したまふ。 |
宮を、場所柄によって、とても特別に丁重にお迎え入れ申し上げて、この君は、主人方に気安く振る舞っていらっしゃるが、まだ客人席の臨時の間に遠ざけていらっしゃるので、まことにつらいと思っていらっしゃった。お恨みなさるのも、そうはいってもお気の毒で、物越しにお会いなさる。 |
中の君の婿君として宮に山荘相当な御 |
Miya wo, tokoro ni tuke te ha, ito koto ni kasiduki ire tatematuri te, kono Kimi ha, aruzi-gata ni kokoro-yasuku motenasi tamahu monokara, mada marauto-wi no karisome naru kata ni idasi-hanati tamahe re ba, ito karasi to omohi tamahe ri. Urami tamahu mo sasuga ni itohosiku te, mono-gosi ni taimen si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.2 | 「 戯れにくくもあるかな。かくてのみや ★」と、いみじく怨みきこえたまふ。やうやうことわり知りたまひにたれど、 人の御上にても、ものをいみじく思ひ沈みたまひて、 いとどかかる方を憂きものに思ひ果てて、 |
「冗談ではありませんね。こうしてばかりいられましょうか」と、ひどくお恨み申し上げなさる。だんだんと道理をお分かりになってきたが、妹のお身の上についても、物事をひどく悲観なさって、ますますこのような結婚生活を嫌なものとすっかり思いきって、 |
自分の心の弱さからつまずいて、またも初めに恋は返されたではないか、こんな状態を続けていくことはもう自分には不可能であると思い、薫は言葉を尽くして恋人に恨みを告げようとした。ようやくこの人の尊敬すべき気持ちも悟った姫君であるが、中の君が結婚をしたために物思いに沈むことの多くなったことによって、いっそう恋愛というものをいとわしいものに思い込むようになり、 | "Tahabure nikuku mo aru kana! Kaku te nomi ya?" to, imiziku urami kikoye tamahu. Yau-yau kotowari siri tamahi ni tare do, hito no ohom-uhe nite mo, mono wo imiziku omohi sidumi tamahi te, itodo kakaru kata wo uki mono ni omohi-hate te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.3 | 「 なほ、ひたぶるに、いかでかくうちとけじ。 あはれと思ふ人の御心も、かならずつらしと思ひぬべきわざにこそあめれ。我も人も見おとさず、 心違はでやみにしがな」 |
「やはり、一途に、何とかこのようにはうちとけまい。うれしいと思う方のお気持ちも、きっとつらいと思うにちがいないことがあるだろう。自分も相手も幻滅したりせずに、もとの気持ちを失わずに、最後までいたいものだわ」 |
これ以上の接近は許すまい、清い愛を今では感じている相手であるが、この人を恨むことが結婚すれば生じるに違いない、自身もこの人も変わらぬ友情を続けていきたい | "Naho, hitaburu ni, ikade kaku utitoke zi. Ahare to omohu hito no mi-kokoro mo, kanarazu turasi to omohi wabi nu beki waza ni koso a' mere. Ware mo hito mo mi-otosa zu, kokoro tagaha de yami ni si gana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.4 | と思ふ心づかひ深くしたまへり。 |
と思う考えが深くおなりになっていた。 |
とこう深く心に決めているためであった。 | to omohu kokoro-dukahi hukaku si tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.5 | 宮の御ありさまなども 問ひきこえたまへば、 かすめつつ、「さればよ」とおぼしくのたまへば、いとほしくて、 思したる御さま、けしきを見ありくやうなど、 語りきこえたまふ。 |
宮のご様子などをお尋ね申し上げなさると、ちらっとほのめかしつつ、「そうであったのか」とお思いになるようにおっしゃるので、お気の毒になって、ご執心のご様子や、態度を窺っていることなどを、お話し申し上げなさる。 |
宮についての話になって、薫のほうから中の君の様子などを聞くと、少しずつ近ごろのことで、薫の想像していたようなことも姫君は語った。薫は気の毒になり、宮が深い愛着をお持ちになること、自分が探って知っている御自由のない近ごろの |
Miya no ohom-arisama nado mo tohi kikoye tamahe ba, kasume tutu, "Sarebayo." to obosiku notamahe ba, itohosiku te, obosi taru sama, kesiki wo mi ariku yau nado, katari kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.6 | 例よりは心うつくしく語らひて、 |
いつもよりは素直にお話しになって、 |
姫君は平生より |
Rei yori ha kokoro-utukusiku katarahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.7 | 「 なほ、かくもの思ひ加ふるほど、すこし心地も静まりて聞こえむ」 |
「やはり、このように物思いの多いころを、もう少し気持ちが落ち着いてからお話し申し上げましょう」 |
「こんなふうな、新たな心配にとらわれておりますことも終わりまして、気の静まりましたころにまたよくお話を伺いましょう」 |
"Naho, kaku mono-omohi kuhahuru hodo, sukosi kokoti mo sidumari te kikoye m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.8 | とのたまふ。人憎く気遠くは、もて離れぬものから、「障子の固めもいと強し。しひて破らむをば、つらくいみじからむ」と 思したれば、「 思さるるやうこそはあらめ。軽々しく異ざまになびきたまふこと、はた、世にあらじ」と、 心のどかなる人は、さいへど、いとよく思ひ静めたまふ。 |
とおっしゃる。小憎らしくよそよそしくは、あしらわないものの、「襖障子の戸締りもとても固い。無理に突破するのは、辛く酷いこと」とお思いになっているので、「お考えがおありなのだろう。軽々しく他人になびきなさるようなことは、また決してあるまい」と、心のおっとりした方は、そうはいっても、じつによく気を落ち着かせなさる。 |
と言った。反感を起こさせるような冷淡さはなくて、しかも |
to notamahu. Hito nikuku ke-dohoku ha, mote-hanare nu monokara, "Syauzi no katame mo ito tuyosi. Sihite yabura m wo ba, turaku imizikara m." to obosi tare ba, "Obosa ruru yau koso ha ara me. Karu-garusiku koto-zama ni nabiki tamahu koto, hata, yo ni ara zi." to, kokoro nodoka naru hito ha, sa ihe do, ito yoku omohi-sidume tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.9 | 「 ただ、いとおぼつかなく、もの隔てたるなむ、胸あかぬ心地するを。 ありしやうにて聞こえむ」 |
「ただ、とても頼りなく、物を隔てているのが、満足のゆかない気がしますよ。以前のようにお話し申し上げたい」 |
「あなたの御意志はどこまでも尊重しますが、こうして物越しでお話ししていることの不満足感を救ってだけはください。先日のように近くへまいってお話をさせていただきたいのです」 |
"Tada, ito obotukanaku, mono hedate taru nam, mune aka nu kokoti suru wo. Arisi yau nite kikoye m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.10 | とせめたまへど、 |
と責めなさると、 |
と責めてみたが、 |
to seme tamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.11 | 「 常よりも わが面影に恥づるころなれば ★、疎ましと見たまひてむも、さすがに苦しきは、いかなるにか」 |
「いつもよりも自分の容貌が恥ずかしいころなので、疎ましいと御覧になるのも、やはりつらく思われますのは、どうしたことでしょうか」 |
「このごろの私は平生よりも衰えていましてね、顔を御覧になって不愉快におなりになりはしないかと、どうしたのでしょう、そんなことの気になる心もあるのですよ」 |
"Tune yori mo waga omokage ni haduru koro nare ba, utomasi to mi tamahi te m mo, sasuga ni kurusiki ha, ika naru ni ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.12 | と、ほのかにうち笑ひたまへるけはひなど、あやしくなつかしくおぼゆ。 |
と、かすかにほほ笑みなさった様子などは、不思議と慕わしく思われる。 |
と言い、ほのかに総角の姫君の笑った |
to, honoka ni uti-warahi tamahe ru kehahi nado, ayasiku natukasiku oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.13 | 「 かかる御心にたゆめられたてまつりて、つひにいかになるべき身にか」 |
「このようなお心にだまされ申して、終いにはどのようになる身の上だろうか」 |
「そんなつきも離れもせぬお心に引きずられてまいって、私はしまいにどうなるのでしょう」 |
"Kakaru mi-kokoro ni tayume rare tatematuri te, tuhi ni ikani naru beki mi ni ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.14 | と嘆きがちにて、 例の、遠山鳥にて明けぬ ★。 |
と嘆きがちに、いつものように、遠山鳥で別々のまま明けてしまった。 |
こんなことを言い、男は歎息をしがちに夜を明かした。 |
to nageki-gati nite, rei no, tohoyama-dori nite ake nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.15 | 宮は、まだ旅寝なるらむとも思さで、 |
宮は、まだ独り寝だろうとはお思いならず、 |
|
Miya ha, mada tabine naru ram to mo obosa de, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.16 | 「 中納言の、主人方に心のどかなるけしきこそうらやましけれ」 |
「中納言が、主人方でゆったりとしている様子が羨ましい」 |
「中納言が主人がたぶって、寝室に長くいるのが恨めしい」 |
"Tyuunagon no, aruzi-gata ni kokoro nodoka naru kesiki koso urayamasikere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.17 | とのたまへば、 女君、あやしと聞きたまふ。 |
とおっしゃると、女君は、おかしなこととお聞きになる。 |
とお言いになるのを、不思議な言葉のように中の君はお聞きしていた。 |
to notamahe ba, Womna-Gimi, ayasi to kiki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | 第八段 匂宮、中の君を重んじる |
4-8 Nio-no-miya has great respect for Naka-no-kimi as his wife |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.1 | わりなくておはしまして、ほどなく帰り たまふが、飽かず苦しきに、宮ものをいみじく思したり。御心のうちを知りたまはねば、女方には、「 またいかならむ。人笑へにや」と思ひ嘆きたまへば、「 げに、心尽くしに苦しげなるわざかな」と見ゆ。 |
無理を押してお越しになって、長くもいずにお帰りになるのが、物足りなくつらいので、宮はひどくお悩みになっていた。お心の中をご存知ないので、女方には、「またどうなるのだろうか。物笑いになりはせぬか」と思ってお嘆きなると、「なるほど、心底からおつらそうな」と見える。 |
無理をしておいでになっても、すぐにまたお帰りにならねばならぬ苦しさに宮も深い悲しみを覚えておいでになった。こうしたお心を知らない中の君は、どうなってしまうことか、世間の物笑いになることかと歎いているのであるから、恋愛というものはして苦しむほかのないことであると思われた。 | Warinaku te ohasimasi te, hodo naku kaheri tamahu ga, akazu kurusiki ni, Miya mono wo imiziku obosi tari. Mi-kokoro no uti wo siri tamaha ne ba, womna-gata ni ha, "Mata ika nara m? Hito-warahe ni ya." to omohi nageki tamahe ba, "Geni, kokoro-dukusi ni kurusige naru waza kana!" to miyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.2 | 京にも、隠ろへて渡りたまふべき所もさすがになし。六条の院には、 左の大殿、片つ方には住みたまひて、さばかりいかでと思したる六の君の御ことを 思しよらぬに、なま恨めしと 思ひきこえたまふべかめり。好き好きしき御さまと、 許しなくそしりきこえたまひて、 内裏わたりにも愁へきこえたまふべかめれば、いよいよ、 おぼえなくて出だし据ゑたまはむも、憚ることいと多かり。 |
京にも、こっそりとお移しになる家もさすがに見当たらない。六条院には、左の大殿が、一画にお住みになって、あれほど何とかしたいとお考えの六の君の御事をお考えにならないので、何やら恨めしいとお思い申し上げていらっしゃるようである。好色がましいお振舞いだと、容赦なくご非難申し上げなさって、宮中あたりでもご愁訴申し上げていらっしゃるようなので、ますます、世間に知られない人をお囲いなさるのも、憚りがとても多かった。 |
京でも多情な名は取っておいでになりながら、ひそかに通ってお行きになる所とてはさすがにない宮でおありになった。六条院では左大臣が同じ邸内に住んでいて、匂宮の夫人に擬している六の君に何の興味もお持ちにならぬ宮をうらめしいようにも思っているらしかった。好色男的な生活をしていられるといって、容赦なく宮のことを御非難して |
Kyau ni mo, kakurohe te watari tamahu beki tokoro mo sasuga ni nasi. Rokudeu-no-win ni ha, Hidari-no-Ohoitono, kata-tu-kata ni ha sumi tamahi te, sabakari ikade to obosi taru Roku-no-Kimi no ohom-koto wo obosi-yora nu ni, nama-uramesi to omohi kikoye tamahu beka' meri. Suki-zukisiki ohom-sama to, yurusi naku sosiri kikoye tamahi te, Uti watari ni mo urehe kikoye tamahu beka' mere ba, iyo-iyo, oboye naku te idasi suwe tamaha m mo, habakaru koto ito ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.3 | なべてに思す人の際は、宮仕への筋にて、なかなか心やすげなり。さやうの並々には思されず、「 もし世の中移りて、 帝后の思しおきつるままにもおはしまさば、人より高きさまにこそなさめ」など、ただ今は、いとはなやかに、 心にかかりたまへるままに、もてなさむ方なく苦しかりけり。 |
普通にお思いの身分の女は、宮仕えの方面で、かえって気安そうである。そのような並の女にはお思いなされず、「もし御世が替わって、帝や后がお考えおいたままにでもおなりになったら、誰よりも高い地位に立てよう」などと、ただ今のところは、たいそうはなやかに、心に懸けていらっしゃるにつれて、して差し上げようともその方法がなくつらいのであった。 |
軽い恋愛相手にしておいでになる女性は、宮仕えの体裁で二条の院なり、六条院なりへお入れになることも自由にお計らいになることができて、かえってお気楽であった。そうした並み並みの情人とは少しも思っておいでにならないのであって、もし世の中が移り、 |
Nabete ni obosu hito no kiha ha, miya-dukahe no sudi ni te, naka-naka kokoro-yasuge nari. Sayau no nami-nami ni ha obosa re zu, "Mosi yononaka uturi te, Mikado Kisaki no obosi-oki turu mama ni mo ohasimasa ba, hito yori takaki sama ni koso nasa me." nado, tada-ima ha, ito hanayaka ni, kokoro ni kakari tamahe ru mama ni, motenasa m kata naku kurusikari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.4 | 中納言は、三条の宮造り果てて、「 さるべきさまにて渡したてまつらむ」と思す。 |
中納言は、三条宮を造り終えて、「しかるべき形をもってお迎え申そう」とお考えになる。 |
中納言は火災後再築している三条の宮のでき上がり次第によい方法を講じて大姫君を迎えようと考えていた。 | Tyuunagon ha, Samdeu-no-miya tukuri hate te, "Saru-beki sama nite watasi tatematura m." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.5 | げに、ただ人は心やすかりけり。かくいと心苦しき御けしきながら、やすからず忍びたまふからに、 かたみに思ひ悩みたまふべかめるも、心苦しくて、「 忍びてかく通ひたまふよしを、中宮などにも漏らし聞こし召させて、 しばしの御騒がれはいとほしくとも、女方の御ためは、咎もあらじ。いとかく夜をだに明かしたまはぬ苦しげさよ。いみじくもてなしてあらせたてまつらばや」 |
なるほど、臣下は気楽なのであった。このようにたいそうお気の毒なご様子でありながら、気をつかってお忍びになるために、お互いに思い悩んでいらっしゃるようなのも、おいたわしくて、「人目を忍んでこのようにお通いになっている事情を、中宮などにもこっそりとお耳に入れあそばして、暫くの間のお騒がれは気の毒だが、女方のためには、非難されることもない。たいそうこのように夜をさえお明かしにならないつらさよ。うまさく計らって差し上げたいものよ」 |
やはり人臣の列にある人は気楽だといってよい。 これほど愛しておいでになりながら、結婚を秘密のことにしておありになるために、宮にも中の君にも |
Geni, tadaudo ha kokoro-yasukari keri. Kaku ito kokoro-gurusiki mi-kesiki nagara, yasukara zu sinobi tamahu kara ni, katami ni omohi nayami tamahu beka' meru mo, kokoro-gurusiku te, "Sinobi te kaku kayohi tamahu yosi wo, Tyuuguu nado ni mo morasi kikosimesa se te, sibasi no ohom-sawagare ha itohosiku tomo, womna-gata no ohom-tame ni ha, toga mo ara zi. Ito kaku yo wo dani akasi tamaha nu kurusige sa yo. Imiziku motenasi te arase tatematura baya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.6 | など思ひて、あながちにも隠ろへず。 |
などと思って、無理して隠さない。 |
とこう思うようになった薫は、しいて内密事とはせずに、 | nado omohi te, anagati ni mo kakurohe zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.7 | 「 更衣など、はかばかしく 誰れかは扱ふらむ」など思して、御帳の帷、壁代など、三条の宮造り果てて、渡りたまはむ心まうけに、しおかせたまへるを、「 まづ、さるべき用なむ」など、いと忍びて聞こえたまひて、 たてまつれたまふ。さまざまなる女房の装束、御乳母などにも のたまひつつ、わざともせさせたまひけり。 |
「衣更など、てきぱきと誰がお世話するだろうか」などと心配なさって、御帳の帷子や、壁代などを、三条宮を造り終えて、お移りになる準備をなさっていたのを、「差し当たって、入用がございまして」などと、たいそうこっそりと申し上げなさって、差し上げなさる。いろいろな女房の装束、御乳母などにもご相談なさっては、特別にお作らせになったのであった。 |
このごろも冬の衣がえの季節になっているが、自分のほかにだれがその |
"Koromo-gahe nado, haka-bakasiku tare kaha atukahu ram?" nado obosi te, mi-tyau no katabira, kabesiro nado, Samdeu-no-miya tukuri hate te, watari tamaha m kokoro-mauke ni, si-oka se tamahe ru wo, "Madu, saru-beki you nam." nado, ito sinobi te kikoye tamahi te, tatemature tamahu. Sama-zama naru nyoubau no syauzoku, ohom-menoto nado ni mo notamahi tutu, wazato mo se sase tamahi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 3/28/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 3/28/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 3/28/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 10/26/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経