47 総角(大島本) |
AGEMAKI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の中納言時代 二十四歳秋から歳末までの物語 |
Tale of Kaoru's Chunagon era, from fall to the end of the year at the age of 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 大君の物語 薫と大君の実事なき暁の別れ |
1 Tale of Ohoi-kimi A parting at dawn without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 秋、八の宮の一周忌の準備 |
1-1 In fall, Sisters prepare for the first anniversary of their father's death |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | あまた年耳馴れたまひにし 川風も、この秋はいとはしたなくもの悲しくて、 御果ての事いそがせたまふ。おほかたのあるべかしきことどもは、中納言殿、阿闍梨などぞ仕うまつりたまひける。ここには法服の事、経の飾り、こまかなる御扱ひを、 人の聞こゆるに従ひて営みたまふも、いとものはかなくあはれに、「 かかるよその御後見なからましかば」と見えたり。 |
何年も耳馴れなさった川風も、今年の秋はとても身の置き所もなく悲しくて、一周忌の法要をご準備なさる。一通りの必要なことどもは、中納言殿と、阿闍梨などがご奉仕なさったのであった。こちらでは法服のこと、経の飾りや、こまごまとしたお仕事を、女房が申し上げるのに従ってご準備なさるのも、まことに頼りなさそうにお気の毒で、「このような他人のお世話がなかったら」と見えた。 |
長い年月 |
Amata tosi mimi-nare tamahi ni si kaha-kaze mo, kono aki ha ito hasitanaku mono-kanasiku te, ohom-hate no koto isoga se tamahu. Ohokata no aru bekasiki koto-domo ha, Tyuunagon-dono, Azyari nado zo tukau-maturi tamahi keru. Koko ni ha hohubuku no koto, kyau no kazari, komaka naru ohom-atukahi wo, hito no kikoyuru ni sitagahi te itonami tamahu mo, ito mono-hakanaku ahare ni, "Kakaru yoso no ohom-usiromi nakara masika ba." to miye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | みづからも参うでたまひて、今はと脱ぎ捨てたまふほどの御訪らひ、浅からず聞こえたまふ。 阿闍梨もここに参れり。名香の糸ひき乱りて、「 ▼ かくても経ぬる」など、うち語らひたまふほどなりけり。結び上げたるたたりの、簾のつまより、几帳のほころびに透きて見えければ、 そのことと心得て、「 ▼ わが涙をば玉にぬかなむ」とうち誦じたまへる、 伊勢の御もかくこそありけめと、をかしく聞こゆるも、 内の人は、聞き知り顔にさしいらへたまはむもつつましくて、「 ものとはなしに」とか ★、「貫之がこの世ながらの別れをだに、 心細き筋にひきかけけむも」など、げに古言ぞ、人の心をのぶるたよりなりけるを思ひ出でたまふ。 |
ご自身でも参上なさって、今日を限りに喪服をお脱ぎになるときのお見舞いを、丁重に申し上げなさる。阿闍梨もここちらに参上していた。名香の糸を引き散らして、「こうして過ごして来たことよ」などと、お話しなさっている時であった。結び上げた糸繰り台が、御簾の端から、几帳の隙間を通して見えたので、そのことだと察して、「わたしの涙を玉にして糸に通して下さい」と口ずさんでいらっしゃるのは、伊勢の御もこうであったろうと、興深くお思い申し上げるにつけても、内側の人は、知ったかぶりにお返事申し上げなさるようなのも遠慮されて、「糸ではないのに」とか、「貫之が生きていての別れでさえ、心細いものとして詠んだというのも」などと、なるほど古歌は、人の心を晴らすよすがであったのをお思い出しなさる。 |
薫は自身でも出かけて来て、除服後の姫君たちの衣服その他を周到にそろえた贈り物をした。その時に阿闍梨も寺から出て来た。二人の姫君は 「自身の涙を玉に こうした文学的なことを薫が言っても、それに応じたようなことで答えをするのも恥ずかしくて、心のうちでは |
Midukara mo maude tamahi te, ima ha to nugi sute tamahu hodo no ohom-toburahi, asakara zu kikoye tamahu. Azyari mo koko ni mawire ri. Myaugau no ito hiki-midari te, "Kaku te mo he nuru." nado, uti-katarahi tamahu hodo nari keri. Musubi-age taru tatari no, sudare no tuma yori, kityau no hokorobi ni suki te miye kere ba, sono koto to kokoro-e te, "Waga namida wo ba tama ni nuka nam." to uti-zyu-zi tamahe ru, Ise-no-go mo kaku koso ari keme to, wokasiku kikoyuru mo, uti no hito ha, kiki-siri-gaho ni sasi-irahe tamaha m mo tutumasiku te, "Mono to ha nasi ni." to ka, "Turayuki ga konoyo nagara no wakare wo dani, kokoro-bosoki sudi ni hiki-kake kem mo." nado, geni huru-koto zo, hito no kokoro wo noburu tayori nari keru wo omohi-ide tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 薫、大君に恋心を訴える |
1-2 Kaoru appeals to Ohoi-kimi on his love |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 御願文作り、経仏供養ぜらるべき心ばへなど書き出でたまへる硯のついでに、 客人、 |
御願文を作り、経や仏の供養なさる心づもりなどをお書き出しなさる筆のついでに、客人が、 |
|
Ohom-gwanmon tukuri, kyau Hotoke kuyau-ze raru beki kokoro-bahe nado kaki-ide tamahe ru suzuri no tuide ni, marauto, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
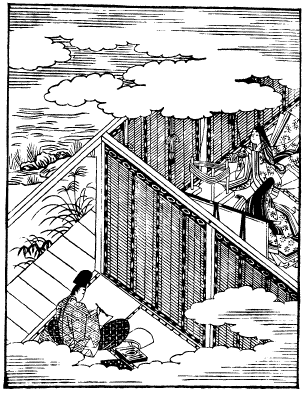 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 「 あげまきに長き契りを結びこめ |
「総角に末長い契りを結びこめて |
「あげまきに長き契りを結びこめ |
"Agemaki ni nagaki tigiri wo musubi-kome |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 同じ所に縒りも会はなむ」 |
一緒になって会いたいものです」 |
同じところに |
onazi tokoro ni yori mo aha nam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | と書きて、見せたてまつりたまへれば、 例の、とうるさけれど、 |
と書いて、お見せ申し上げなさると、いつもの、と煩わしいが、 |
と書いて大姫君に見せた。またとうるさく女王は思いながらも、 |
to kaki te, mise tatematuri tamahe re ba, rei no, to urusakere do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 「 ぬきもあへずもろき涙の玉の緒に |
「貫き止めることもできないもろい涙の玉の緒に |
「 |
"Nuki mo ahe zu moroki namida no tama-no-wo ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 長き契りをいかが結ばむ」 |
末長い契りをどうして結ぶことができましょう」 |
長き契りをいかが結ばん」 |
nagaki tigiri wo ikaga musuba m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | とあれば、「 ▼ あはずは何を」と、恨めしげに眺めたまふ。 |
とあるので、「一緒になれなかったら生きている甲斐もありません」と、恨めしそうに物思いにお耽りになる。 |
と返しを書いて出した。「逢はずば何を」(片糸をこなたかなたに縒りかけて合はずば何を玉の緒にせん)と薫は歎かれるのであるが、 |
to are ba, "Aha zu ha nani wo?" to, uramesige ni nagame tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | みづからの御上は、かくそこはかとなくもて消ちて恥づかしげなるに、すがすがともえのたまひよらで、 宮の御ことをぞまめやかに聞こえたまふ。 |
ご自身のお身の上については、このように何とはなしに話をそらせて相手をなさらないので、すらすらと意中を申し上げることもできず、宮のご執心を真面目に申し上げなさる。 |
自身のことを正面から言うことはできずに、 |
Midukara no ohom-uhe ha, kaku sokohakatonaku mote-keti te hadukasige naru ni, suga-suga to mo e notamahi-yora de, Miya no ohom-koto wo zo mameyaka ni kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 「 さしも御心に入るまじきことを、かやうの方にすこしすすみたまへる御本性に、聞こえそめたまひけむ負けじ魂にやと、とざまかうざまに、いとよくなむ御けしき見たてまつる。 まことにうしろめたくはあるまじげなるを、などかくあながちにしも、もて離れたまふらむ。 |
「それ程までご執心でないことを、このようなことに少し積極的でいらっしゃるご性格で、一度申し出されては後に引かない意地からかと、あれやこれやと、十分にお気持ちをお探り申し上げております。ほんとうに不安なようではありませんので、どうしてこのようにむやみに、お避けになるのでしょう。 |
「それほど深くお思いになるのでなく好奇心をお働かせになることが多くて、お申し込みになったのを、冷淡にお扱われになるために、負けぬ気を出しておいでになるだけではないかと、私は考えもしまして、いろいろにして御様子を見ていますが、どうも誠心誠意でお始めになった恋愛としか思われません。それをどうしてただ今のようなふうにばかりこちらではお扱いになるのでしょう。 |
"Sasimo mi-kokoro ni iru maziki wo, kayau no kata ni sukosi susumi tamahe ru ohom-honzyau ni, kikoye some tamahi kem make-zi-damasihi ni ya to, tozama-kauzama ni, ito yoku nam mi-kesiki mi tatematuru. Makoto ni usirometaku ha arumazige naru wo, nado kaku anagati ni simo, mote-hanare tamahu ram? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 世のありさまなど、思し分くまじくは見たてまつらぬを、うたて、遠々しくのみもてなさせたまへば、かばかりうらなく頼みきこゆる心に違ひて、恨めしくなむ。ともかくも思し分くらむさまなどを、さはやかに承りにしがな」 |
男女の仲の様子などを、ご存知でないようには拝見しませんのに、いやに、よそよそしくばかりおあしらいなさるので、これほど心から信頼申し上げている気持ちと違って、恨めしい気がします。どのようにお考えになっているのかなどを、はっきりとお聞き致したいものですね」 |
ものの判断がおできにならぬほどの少女ではおられない |
Yo no arisama nado, obosi-waku maziku ha mi tatematura nu wo, utate, toho-dohosiku nomi motenasa se tamahe ba, kabakari ura-naku tanomi kikoyuru kokoro ni tagahi te, uramesiku nam. Tomo-kakumo obosi-waku ram sama nado wo, sahayaka ni uketamahari ni si gana." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | と、いとまめだちて聞こえたまへば、 |
と、たいそう真面目になって申し上げなさるので、 |
薫はまじめであった。 |
to, ito mamedati te kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 「 違へじの心にてこそは、かうまであやしき世の例なるありさまにて、隔てなくもてなしはべれ。それを思し分かざりけるこそは、浅きことも混ざりたる心地すれ。 げに、かかる住まひなどに、心あらむ人は、思ひ残す事、あるまじきを、何事にも後れそめにけるうちに、 こののたまふめる筋は、 いにしへも、 さらにかけて、とあらばかからばなど、行く末のあらましごとに取りまぜて、のたまひ置くこともなかりしかば、なほ、 かかるさまにて、 世づきたる方を思ひ絶ゆべく 思しおきてける、となむ思ひ合はせはべれば、ともかくも聞こえむ方なくて。さるは、すこし世籠もりたるほどにて、 深山隠れには心苦しく見えたまふ人の御上を ★、いとかく朽木にはなし果てずもがなと、人知れず扱はしくおぼえはべれど、 いかなるべき世にかあらむ」 |
「お気持ちに背くまいとの気持ちなればこそ、こうしてまでおかしな世間の例にもなる状態で、隔てなくお相手しているのでございます。それをお分かりにならなかったことこそ、浅い気持ちがあるような気がします。おっしゃるように、このような住まいなどに、情けの深い人は、ありたけの物思いをし尽くすでしょうが、何事にも後れて育ちましたので、このおっしゃるような方面は、故人も、一向に何一つ、こういう場合にはああいう場合にはなどと、将来のことを予想して、おっしゃっておくこともなかったので、やはり、このような状態で、世間並みの生活を諦めるようお考え置きであった、と思い合わされますので、何ともお答え申し上げようがなくて。一方では、少し生い先長い年頃で、山奥暮らしはお気の毒にお見えになるお身の上を、まことにこのように枯木にはさせたくないものだと、人知れず面倒見ずにはいられなく思っているのですが、どのようになる縁なのでしょうか」 |
「あなたの御親切に感謝しておりますればこそ、こんなにまで世間に例のございませんほどにもお親しくおつきあい申し上げているのでございます。それがおわかりになりませんのは、あなたのほうに不純な点がおありになるのではないかと疑われます。少女でもないとおっしゃいますが、実際こんな寄るべない身の上になっていましては、ありとあらゆることを普通の人であれば考え尽くしていなければなりませんのに、どんなことにも幼稚で、ことに今のお話のようなことは、宮が生きておいでになりましたころにも、こんな話があればとかそうであればとか将来の問題としてほかの話の中ででもおっしゃらなかったことでしたから、やはり宮様のお心は、私たちはただこのままで、他の方のような結婚の幸福というようなことは念頭に置かずに一生を過ごすようにとお考えになったに違いないとそう思っているものですから、兵部卿の宮様のことにつきましても可否の言葉の出しようがないのでございます。けれど妹は若くて、こうした |
"Tagahe zi no kokoro nite koso ha, kau made ayasiki yo no tamesi naru arisama nite, hedate naku motenasi habere. Sore wo obosi-waka zari keru koso ha, asaki koto mo mazari taru kokoti sure. Geni, kakaru sumahi nado ni, kokoro ara m hito ha, omohi-nokosu koto, arumaziki wo, nani-goto ni mo okure some ni keru uti ni, kono notamahu meru sudi ha, inisihe mo, sarani kake te, toara-ba kakara-ba nado, yuku-suwe no aramasi-goto ni tori-maze te, notamahi-oku koto mo nakari sika ba, naho, kakaru sama ni te, yo-duki taru kata wo omohi-tayu beku obosi-oki te keru, to nam omohi-ahase habere ba, tomo-kakumo kikoye m kata naku te. Saruha, sukosi yo-gomori taru hodo nite, miyama-gakure ni ha kokoro-gurusiku miye tamahu hito no ohom-uhe wo, ito kaku kutiki ni ha nasi-hate zu mo gana to, hito-sire-zu atukahasiku oboye habere do, ika naru beki yo ni ka ara m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | と、うち嘆きてもの思ひ乱れたまひけるほどのけはひ、いとあはれげなり。 |
と、嘆息して途方に暮れていらっしゃったときの様子、たいそうおいたわしく感じられる。 |
と言って、物思わしそうに大姫君の歎息をするのが哀れであった。 |
to, uti-nageki te mono-omohi midare tamahi keru hodo no kehahi, ito aharege nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 薫、弁を呼び出して語る |
1-3 Kaoru calls and talks with Ben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | けざやかにおとなびても、いかでかは賢しがりたまはむと、ことわりにて、例の、 古人召し出でてぞ語らひたまふ。 |
てきぱきと一人前に振る舞っても、どうして賢くことをお決めになれようかと、もっともに思われて、いつものように、老女を召し出して相談なさる。 |
中の君の結婚談にもせよはっきりと年長者らしく、若い貴女は縁組みの話の賛否を言い切りうるはずはないのである、と同情した薫は、別の所で例の老女の弁を呼び出して、 |
Kezayaka ni otonabi te mo, ikadekaha sakasigari tamaha m to, kotowari nite, rei no, huru-hito mesi-ide te zo katarahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 「 年ごろは、ただ後の世ざまの心ばへにて進み参りそめしを、 もの心細げに思しなるめりし御末のころほひ、 この御事どもを、心にまかせてもてなしきこゆべくなむのたまひ契りてしを、思しおきてたてまつりたまひし御ありさまどもには違ひて、御心ばへどもの、いといとあやにくにもの強げなるは、 いかに、思しおきつる方の異なるにやと、疑はしきことさへなむ。 |
「今までは、ただ来世の事を願う気持ちで参っておりましたが、何となく心細そうにお思いであったようなご晩年に、この姫君たちのことを、考え通りにお世話申し上げるようにおっしゃり約束したのですが、お考え置き申されたご様子とは違って、お二人の気持ちが、とてもとても困ったことに強情なのは、どのようにお考え置きになっていた人が別であったのかと、疑わしくまで思われます。 |
「以前は宮様を仏道の導きとしてお |
"Tosi-goro ha, tada noti-no-yo-zama no kokoro-bahe ni te susumi mawiri some si wo, mono-kokoro-bosoge ni obosi naru meri si ohom-suwe no korohohi, ko no ohom-koto-domo wo, kokoro ni makase te motenasi kikoyu beku nam notamahi tigiri te si wo, obosi-oki te tatematuri tamahi si ohom-arisama-domo ni ha tagahi te, mi-kokorobahe-domo no, ito ito ayaniku ni mono-tuyoge naru ha, ikani, obosi-oki turu kata no koto naru ni ya to, utagahasiki koto sahe nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | おのづから聞き伝へたまふやうもあらむ。 いとあやしき本性にて、世の中に心をしむる方なかりつるを、さるべきにてや、かうまでも聞こえ馴れにけむ。世人もやうやう言ひなすやうあべかめるに、同じくは 昔の御ことも違へきこえず、 我も人も世の常に心とけて聞こえはべらばや、と思ひよるは、つきなかるべきことにても、 さやうなる例なくやはある」 |
自然とお聞き及びになっていることもありましょう。とても妙な性質で、世の中に執着することはなかったが、前世からの因縁でしょうか、こんなにまでお親しみ申したのでしょう。世間の人もだんだんと噂するらしくもあるから、同じことなら故人のご遺言にお背き申さず、わたしも姫君も、世間の普通の男女のように心をお交わし申したい、と思い寄りましたのは、不似合いなことであっても、そのような例もないわけではありません」 |
あなたは世間で言っていることも聞いておいでになるでしょう、変わった性情から私は人間並みに結婚をしようというような考えは全然捨てていたものでした。それが宿命というものなのでしょうか、こちらの姫君に心をお |
Onodukara kiki-tutahe tamahu yau mo ara m. Ito ayasiki honzyau nite, yononaka ni kokoro wo simuru kata nakari turu wo, saru-beki nite ya, kau made mo kikoye nare ni kem. Yo-hito mo yau-yau ihi-nasu yau a' beka' meru ni, onaziku ha mukasi no ohom-koto mo tagahe kikoye zu, ware mo hito mo yo no tune ni kokoro toke te kikoye habera baya, to omohi-yoru ha, tuki nakaru beki koto nite mo, sayau naru tamesi naku yaha aru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | などのたまひ続けて、 |
などとおっしゃり続けて、 |
と薫は話し続け、また、 |
nado notamahi tuduke te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | 「 宮の御ことをも、かく聞こゆるに、うしろめたくはあらじと、うちとけたまふさまならぬは、うちうちに、さりとも 思ほし向けたることのさまあらむ。なほ、いかに、いかに」 |
「宮のお身の上を、このように申し上げるのに、不安でないと、気をお許しにならないご様子なのは、内々で、やはり他にお考えの人がいるのでしょうか。さあ、どうなのですか、どうなのですか」 |
「兵部卿の宮様のことも、私がお勧めしている以上は安心して御承諾くだすっていいものを、そうでないのはお二方の女王様にそれぞれ別なお望みがあるのではないのですか。あなたからでもよく聞きたいものですよ。ねえ、どんなお望みがあるのだろう」 |
"Miya no ohom-koto wo mo, kaku kikoyuru ni, usirometaku ha ara zi to, uti-toke tamahu sama nara nu ha, uti-uti ni, saritomo omohosi muke taru koto no sama ara m. Naho, ikani, ikani?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | とうち眺めつつのたまへば、 例の、悪ろびたる女ばらなどは、かかることには、憎きさかしらも言ひまぜて、 言よがりなどもすめるを、いとさはあらず、心のうちには、「あらまほしかるべき御ことどもを」と思へど、 |
と嘆きながらおっしゃるので、いつもの、良くない女房連中などは、このようなことには、憎らしいおせっかいを言って、調子を合わせたりなどするようであるが、まったくそうではなく、心の中では、「理想的なお二人方の縁談だわ」と思うが、 |
とも、物思わしそうにして言うのであった。こんな時によくない女房であれば、姫君がたを批難したり、自身の立場を有利にしようとしたり試みるものであるが、弁はそんな女ではなかった。心の中では二人の女王の上にこの縁がそれぞれ成立すればどんなにいいであろうとは思っているのであるが、 |
to uti-nagame tutu notamahe ba, rei no, warobi taru womna-bara nado ha, kakaru koto ni ha, nikuki sakasira mo ihi-maze te, koto-yogari nado mo su meru wo, ito saha ara zu, kokoro no uti ni ha, "Aramahosikaru beki ohom-koto-domo wo." to omohe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 薫、弁を呼び出して語る(続き) |
1-4 Kaoru calls and talks with Ben (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 「 もとより、かく 人に違ひたまへる御癖どもにはべればにや、いかにもいかにも、世の常に何やかやなど、 思ひよりたまへる御けしきになむはべらぬ。 |
「もともと、このように人と違っていらっしゃるお二方のご性格のせいでしょうか、どうしてもどうしても、世間の普通の人のように、何やかやと世間並みの結婚を、お考えになっていらっしゃるご様子でございません。 |
「初めからそんなふうに少し変わった御性格なのでございますからね。どうして、どうしてほかの方を対象にお考えなどなさるものでございますか。 | "Motoyori, kaku hito ni tagahi tamahe ru ohom-kuse-domo ni habere ba ni ya, ikanimo-ikanimo, yo-no-tune ni naniya-kaya nado, omohi-yori tamahe ru mi-kesiki ni nam habera nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | かくて、さぶらふこれかれも、年ごろだに、何の 頼もしげある木の本の隠ろへも ★はべらざりき。身を捨てがたく思ふ限りは、ほどほどにつけてまかで散り、 昔の古き筋なる人も、多く見たてまつり捨てたるあたりに、 まして今は、しばしも立ちとまりがたげにわびはべりて、 おはしましし世にこそ、 限りありて、 かたほならむ御ありさまは、いとほしくもなど、古代なる御うるはしさに、思しもとどこほりつれ。 |
こうして、仕えております誰彼も、今まででさえ、何の頼りになる庇護もございませんでした。身を捨てがたく思う者たちだけは、身分身分に応じて暇をもらって離れ去り、昔からの古い縁故の人も、多くはお見限り申した邸に、まして今では、立ち止まりがたそうに困り合っておりまして、ご在世中にこそ、格式もあって、不釣合なご結婚は、お気の毒だわなどと、昔気質の律儀さから、おためらいになっていました。 |
女房なども宮様のおいでになりました当時と申しても何の頼もしいところのある親王家ではなかったのですから、わが身を犠牲にしますのを喜びません人たちは、それぞれに相当な行く先を作ってお暇をとってまいるのでございましてね。昔のいろいろな関係で切るにも切られぬ主従の御縁のある人でも、こんなにだれもが出て行ってしまいますのを見ておりましては、しばらくでも残っているのがいやでならぬふうを見せましてね、そしてまたその人たちは姫君がたに、『宮様の御在世中はお相手によって尊貴なお家を傷つけるかと御遠慮もあそばしたでしょうが、 | Kakute, saburahu kore-kare mo, tosi-goro dani, nani no tanomosige aru ko no moto no kakurohe mo habera zari ki. Mi wo sute-gataku omohu kagiri ha, hodo-hodo ni tuke te makade tiri, mukasi no huruki sudi naru hito mo, ohoku mi tatematuri sute taru atari ni, masite ima ha, sibasi mo tati-tomari gatage ni wabi haberi te, ohasimasi si yo ni koso, kagiri ari te, kataho nara m ohom-arisama ha, itohosiku mo nado, kotai naru ohom-uruhasisa ni, obosi mo todokohori ture. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | 今は、かう、また頼みなき御身どもにて、 いかにもいかにも、世になびきたまへらむを、あながちにそしりきこえむ人は、かへりてものの心をも知らず、言ふかひなきことにて こそはあらめ。いかなる人か、いとかくて世をば過ぐし果てたまふべき。 |
今では、このように、他に頼りのいないお身の上の方たちで、どのようにもどのようにも、成り行き次第に身を任せなさるのを、むやみに悪口を申し上げるような人は、かえって物の道理を知らず、言いようもないことでしょう。どのような人が、まことにこうして一生をお送りなさることができましょうか。 |
お心細いお二人きりにおなりになったのですもの、どんな結婚でもなすったらいいはずです、それをとやかくと言う人はもののわからぬ人間だとかえって軽蔑あそばしたらいいのです、どうしてこんなふうにばかりしておいでになることができますか、 | Ima ha, kau, mata tanomi naki ohom-mi-domo nite, ikanimo-ikanimo, yo ni nabiki tamahe ra m wo, anagati ni sosiri kikoye m hito ha, kaheri te mono no kokoro wo mo sira zu, ihukahinaki koto nite koso ha ara me. Ika naru hito ka, ito kaku te yo wo ba sugusi hate tamahu beki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 松の葉をすきて勤むる山伏だに、生ける身の捨てがたさによりてこそ、仏の御教へをも、道々別れては行ひなすなれ、などやうの、 よからぬことを聞こえ知らせ、若き御心ども乱れたまひぬべきこと多くはべるめれど、 たわむべくもものしたまはず、 中の宮をなむ、いかで人めかしくも扱ひなしたてまつらむ、と思ひきこえたまふべかめる。 |
松の葉を食べて修業する山伏でさえ、生きている身の捨て難いことによって、仏のお教えも、それぞれの流派をつくって行っている、などというような、よくないことをご忠告申し上げ、若いお二方のお気持ちがお迷いになることが多くございますようですが、志操を曲げようともなさらず、中の宮を、何とか一人前にして差し上げたい、とお思い申し上げていらっしゃるようでございます。 |
松の葉を食べて行をするという坊様たちでさえ、生きんがために都合のよい一派一派を開いていくものでございますから』などと、こんないやなことを申しましてね、若い姫君がたのお心を苦しめまして利己的に媒介者になろうといたしますが、女王様はそんな浮薄な言葉にお動きになるような方がたではございません。お妹様だけには人並みな幸福を得させたいとお考えになっているようでございます。 | Matu no ha wo suki te tutomuru yamabusi dani, ike ru mi no sute gatasa ni yori te koso, Hotoke no ohom-wosihe wo mo, miti-miti wakare te ha okonahi nasu nare, nado yau no, yokara nu koto wo kikoye sirase, wakaki mi-kokoro-domo midare tamahi nu beki koto ohoku haberu mere do, tawamu beku mo monosi tamaha zu, Naka-no-Miya wo nam, ikade hito-mekasiku mo atukahi-nasi tatematura m, to omohi kikoye tamahu beka' meru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | かく 山深く訪ねきこえさせたまふめる御心ざしの、 年経て見たてまつり馴れたまへるけはひも、 疎からず思ひきこえさせたまひ、今はとざまかうざまに、こまかなる筋聞こえ通ひたまふめるに、 かの御方を、さやうにおもむけて聞こえたまはば、 となむ思すべかめる。 |
このように山奥にお訪ね申し上げなさるようなお志の、幾年もお世話していただくご行為に対しても、親しくお思い申し上げなさって、今ではあれやこれやと、こまごまとした方面のこともご相談申し上げていらっしゃるようで、あの御方を、おっしゃるようお望み申してくださるならば、とお思いのようです。 |
こうした |
Kaku yama hukaku tadune kikoye sase tamahu meru mi-kokorozasi no, tosi he te mi tatematuri nare tamahe ru kehahi mo, utokara zu omohi kikoye sase tamahi, ima ha tozama-kauzama ni, komaka naru sudi kikoye kayohi tamahu meru ni, kano Ohom-kata wo, sayau ni omomuke te kikoye tamaha ba, to nam obosu beka' meru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 宮の御文などはべるめるは、さらにまめまめしき御ことならじ、とはべるめる」 |
宮のお手紙などがございますようなのは、全然真剣な気持ちからではあるまい、とお考えのようです」 |
兵部卿の宮様からお手紙は始終おいただきになるのですが、それは誠意のある求婚者だとも認めておられないようでございます」 |
Miya no ohom-humi nado haberu meru ha, sarani mame-mamesiki ohom-koto nara zi, to haberu meru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | と聞こゆれば、 |
と申し上げると、 |
弁は姫君の意志を伝えようとしただけである。 |
to kikoyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | 「 あはれなる御一言を聞きおき、露の世にかかづらはむ限りは、聞こえ通はむの心あれば、 いづ方にも見えたてまつらむ、同じことなるべきを、 さまではた、思しよるなる、いとうれしきことなれど、 心の引く方なむ、かばかり思ひ捨つる世に、 なほとまりぬべきものなりければ、 改めてさはえ思ひなほすまじくなむ。世の常になよびかなる筋にもあらずや。 |
「おいたわしいご遺言を聞きおき、露の世に生きている限りは、お付き合いを願いたいとの気持ちなので、どちらの方とご一緒になっても、同じことになるでしょうが、そのようにまで、お考えになっているというのは、まことに嬉しいことですが、心の惹かれる方は、これほど捨て切った世なのですが、やはり執着してしまうものなので、今さらそのようには考え改められません。世間並みのあだっぽい恋ではないのですよ。 |
「宮様の御遺言を身に |
"Ahare naru ohom-hito-koto wo kiki-oki, tuyu no yo ni kakaduraha m kagiri ha, kikoye kayoha m no kokoro are ba, idu-kata ni mo miye tatematura m, onazi koto naru beki wo, sa made hata, obosi-yoru naru, ito uresiki koto nare do, kokoro no hiku kata nam, kabakari omohi suturu yo ni, naho tomari nu beki mono nari kere ba, aratame te saha e omohi nahosu maziku nam. Yo-no-tune ni nayobika naru sudi ni mo ara zu ya. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | ただかやうにもの隔てて、こと残いたるさまならず、さし向ひて、とにかくに定めなき世の物語を、隔てなく聞こえて、つつみたまふ御心の隈残らず もてなしたまはむなむ、兄弟などのさやうに睦ましきほどなるもなくて、 いとさうざうしくなむ、世の中の思ふことの、あはれにも、をかしくも、愁はしくも、時につけたるありさまを、心に籠めてのみ過ぐる身なれば、さすがにたつきなくおぼゆるに、 疎かるまじく頼みきこゆる。 |
ただこのような物を隔てて、言い残した状態でなく、差し向かいで、とにもかくにも無常の世の話を、隔て心なく申し上げて、お隠しになるお心の中をすっかり打ち明けてお相手してくださるなら、兄弟などのように親しい人もなくて、とても淋しいので、世の中の思うことの、しみじみとしたこと、おもしろいこと、悲しいことも、その時々の思いを、胸一つに収めて過ごしてきた身の上なので、何と言っても頼りなく思われるので、親しくお頼み申し上げるのです。 |
ただ今のようなふうに何かを隔てたままでも、何事に限らず話し合う相手にいつまでもなっていていただきたいだけです。私には |
Tada kayau ni mono hedate te, koto nokoi taru sama nara zu, sasi-mukahi te, toni-kakuni sadame naki yo no monogatari wo, hedate naku kikoye te, tutumi tamahu mi-kokoro no kuma nokora zu motenasi tamaha m nam, harakara nado no sayau ni mutumasiki hodo naru mo naku te, ito sau-zausiku nam, yononaka no omohu koto no, ahare ni mo, wokasiku mo, urehasiku mo, toki ni tuke taru arisama wo, kokoro ni kome te nomi suguru mi nare ba, sasuga ni tatuki naku oboyuru ni, utokaru maziku tanomi kikoyuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | 后の宮は、なれなれしく、さやうにそこはかとなき思ひのままなるくだくだしさを、聞こえ触るべきにもあらず。 三条の宮は、親と思ひきこゆべきにもあらぬ御若々しさなれど、 限りあれば、たやすく馴れきこえさせずかし。 その他の女は、すべていと疎くつつましく、恐ろしくおぼえて、心からよるべなく心細きなり。 |
后の宮は、親しく、そのように何ということなく思いのままのこまごまとしたことを、申し上げられる方ではありません。三条の宮は、母親と申し上げるほどでもないお若々しさですが、分限がありますので、気安くお親しみ申し上げることはできません。その他の女性は、すべてたいそう疎々しく、気が引けて恐ろしく思われて、自ら求めて結婚相手もなく心細いのです。 |
Kisai-no-Miya ha, nare-naresiku, sayau ni sokohakatonaki omohi no mama naru kuda-kudasisa wo, kikoye huru beki ni mo ara zu. Samdeu-no-Miya ha, oya to omohi kikoyu beki ni mo ara nu waka-wakasisa nare do, kagiri are ba, tayasuku nare kikoye sase zu kasi. Sono hoka no womna ha, subete ito utomasiku tutumasiku, osorosiku oboye te, kokoro kara yorube naku kokoro-bosoki nari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | なほざりのすさびにても、 懸想だちたることは、いとまばゆくありつかず、はしたなきこちごちしさにて、 まいて 心にしめたる方のことは、うち出づる ことは難くて、怨めしくもいぶせくも思ひきこゆるけしきをだに 見えたてまつらぬこそ、我ながら限りなくかたくなしきわざなれ。 宮の御ことをも、さりとも悪しざまには聞こえじと、 まかせてやは見たまはぬ」 |
いい加減な好き心からも、懸想めいたことは、とても気恥ずかしくて性に合わず、体裁悪い不器用さで、まして心に思い詰めている方のことは、口に出すのも難しくて、恨めしくも鬱陶しくもお思い申し上げる様子をさえ見ていただけないのは、自分ながらこの上なく愚かしいことだ。宮のお事をも、悪くお計らい申し上げまいと、お任せ下さいませんか」 |
その場かぎりの戯れ事でも恋愛に関したことはまぶしい気がして、人から見れば見苦しい |
Nahozari no susabi nite mo, kesau-dati taru koto ha, ito mabayuku ari tuka zu, hasitanaki koti-gotisisa nite, maite kokoro ni sime taru kata no koto ha, uti-iduru koto ha kataku te, uramesiku mo ibuseku mo omohi kikoyuru kesiki wo dani miye tatematura nu koso, ware nagara kagirinaku katakunasiki waza nare. Miya no ohom-koto wo mo, saritomo asi-zama ni ha kikoye zi to, makase te yaha mi tamaha nu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.12 | など言ひゐたまへり。老い人、はた、 かばかり心細きに、 あらまほしげなる御ありさまを、いと切に、 さもあらせたてまつらばやと思へど、いづ方も恥づかしげなる御ありさまどもなれば、思ひのままにはえ聞こえず。 |
などとおっしゃっていた。老女は、老女で、これほど心細いので、理想的なご様子を、とても切に、そうして差し上げたいと思うが、どちらも気恥ずかしいご様子の方々なので、思いのままには申し上げられない。 |
こんなことを |
nado ihi wi tamahe ri. Oyi-bito, hata, kabakari kokoro-bosoki ni, aramahosige naru ohom-arisama wo, ito seti ni, sa mo ara se tatematura baya to omohe do, idu-kata mo hadukasige naru ohom-arisama-domo nare ba, omohi no mama ni ha e kikoye zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 薫、大君の寝所に迫る |
1-5 Kaoru slips into Ohoi-kimi's bedroom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 今宵は泊りたまひて、 物語などのどやかに聞こえまほしくて、 やすらひ暮らしたまひつ。あざやかならず、もの怨みがちなる御けしき、やうやうわりなくなりゆけば、 わづらはしくて、うちとけて聞こえたまはむことも、いよいよ苦しけれど、 おほかたにてはありがたくあはれなる人の御心なれば、こよなくももてなしがたくて、対面したまふ。 |
今夜はお泊まりになって、お話などをのんびりと申し上げたくて、ぐずぐずして日をお暮らしになった。はっきりとではないが、何か恨みがましいご様子、だんだんと無性に昂じて行くので、厄介になって、気を許してお話し申し上げることも、ますますつらいけれど、全体的にはめったにいない親切なご性格の方なので、ひどくすげないお扱いもできなくて、面会なさる。 |
薫は今夜を泊まることにして姫君とのどかに話がしたいと思う心から、その日を何するとなく山川をながめ暮らした。この人の態度が不鮮明になり、何かにつけて |
Koyohi ha tomari tamahi te, monogatari nado nodoyaka ni kikoye mahosiku te, yasurahi kurasi tamahi tu. Azayaka nara zu, mono-urami-gati naru mi-kesiki, yau-yau warinaku nari-yuke ba, wadurahasiku te, utitoke te kikoye tamaha m koto mo, iyo-iyo kurusikere do, ohokata nite ha arigataku ahare naru hito no mi-kokoro nare ba, koyonaku mo motenasi gataku te, taimen si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 仏のおはする中の戸を開けて、御燈明の火けざやかにかかげさせて、 簾に屏風を添へてぞおはする。 外にも大殿油参らすれど、「 悩ましうて無礼なるを。あらはに」など諌めて、かたはら臥したまへり。御くだものなど、わざとはなくしなして参らせたまへり。 |
仏のいらっしゃる間の中の戸を開けて、御燈明の光を明るく照らさせて、簾に屏風を添えておいでになる。外の間にも大殿油を差し上げるが、「疲れて無作法なので。丸見えでは」などと制止して、横に臥せっていらっしゃった。果物などを、特別なふうにではなく整えて差し上げさせなさった。 |
仏間と客室の間の戸をあけさせ、奥のほうの仏前には灯を明るくともし、隣との仕切りには 「少し疲れていて失礼な と言い、それをやめさせて薫は身を横たえていた。菓子などが客の |
Hotoke no ohasuru naka-no-to wo ake te, mi-akasi no hi kezayaka ni kakage sase te, sudare ni byaubu wo sohe te zo ohasuru. To ni mo oho-tonabura mawirasure do, "Nayamasiu te murai naru wo. Ahare ni." nado isame te, katahara husi tamahe ri. Ohom-kudamono nado, wazato ha naku si nasi te mawira se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | 御供の 人びとにも、 ゆゑゆゑしき肴などして出ださせたまへり。廊めいたる方に集まりて、 この御前は人げ遠くもてなして、しめじめと物語聞こえたまふ。うちとくべくもあらぬものから、なつかしげに愛敬づきて、もののたまへるさまの、なのめならず心に入りて、 思ひ焦らるるもはかなし。 |
お供の人びとにも、風流なお肴などをお出させなさった。廊のような所に集まって、こちらの御前は人の気配を遠ざけて、しみじみとお話申し上げなさる。気をお許しになるはずもないものの、優しそうに愛嬌がおありで、物をおっしゃる様子が、一方ならず心に染みいって、胸が切なくなるのもたわいない。 |
従者にも食事が出してあった。廊の座敷にあたるような |
Ohom-tomo no hito-bito ni mo, yuwe-yuwesiki sakana nado si te idasa se tamahe ri. Rau mei taru kata ni atumari te, kono o-mahe ha hito-ge tohoku motenasi te, sime-zime to monogatari kikoye tamahu. Utitoku beku mo ara nu monokara, natukasige ni aigyau-duki te, mono notamahe ru sama no, nanome nara zu kokoro ni iri te, omohi-ira ruru mo hakanasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 「 かくほどもなきものの隔てばかりを障り所にて、おぼつかなく思ひつつ過ぐす心おそさの、あまりをこがましくもあるかな」と思ひ続けらるれど、つれなくて、おほかたの世の中のことども、あはれにもをかしくも、さまざま聞き所多く語らひきこえたまふ。 |
「このように何でもない隔て物だけを障害にして、もどかしく思っては過ごしてきた不器用さが、あまりにも馬鹿らしいな」と思い続けられるが、さりげなく平静を装って、世間一般の事柄を、しみじみと興味を惹くように、いろいろとおもしろくたくさんお話し申し上げなさる。 |
この何でもないものを越えがたい障害物のように見なして恋人に接近なしえない心弱さは愚かしくさえ自分を見せているのではないかと、こんなことを心中では思うのであるが、素知らぬふうを作って、世間にあったことについて、身にしむ話も、おもしろく聞かされることもいろいろと語り続ける中納言であった。 | "Kaku hodo mo naki mono no hedate bakari wo sahari-dokoro nite, obotukanaku omohi tutu sugusu kokoro ososa no, amari wokogamasiku mo aru kana!" to omohi-tuduke rarure do, turenaku te, ohokata no yononaka no koto-domo, ahare ni mo wokasiku mo, sama-zama kiki-dokoro ohoku katarahi kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | 内には、「人びと、近く」などのたまひおきつれど、「 さしも、もて離れたまはざらなむ」と思ふべかめれば、いとしも護りきこえず、 さし退つつ、みな寄り臥して、仏の御燈火もかかぐる人もなし。ものむつかしくて、忍びて人召せど、おどろかず。 |
内側では、「女房たち、近くに」などとおっしゃっておいたが、「そんなにも、よそよそしくなさらないで欲しい」と思っているようなので、たいしてお守り申さず、尻ごみ尻ごみしながら、皆寄り臥して、仏の御燈明を明るくする人もいない。何となく気づまりで、こっそりと人をお呼びになるが、目を覚まさない。 |
女王は女房たちに近い所を離れずいるように命じておいたのであるが、今夜の客は交渉をどう進ませようと思っているか計られないところがあるように思う心から、姫君をさまで護ろうとはしていず、遠くへ退いていて、 |
Uti ni ha, "Hito-bito, tikaku." nado notamahi-oki ture do, "Sasimo, mote-hanare tamaha zara nam." to omohu beka' mere ba, ito simo mamori kikoye zu, sasi-sizoki tutu, mina yori-husi te, Hotoke no ohom-tomosibi mo kakaguru hito mo nasi. Mono-mutukasiku te, sinobi te hito mese do, odoroka zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | 「 心地のかき乱り、悩ましくはべるを、ためらひて、暁方にもまた聞こえむ」 |
「気分が悪く、苦しうございますので、少し休んで、明け方に再びお話し申し上げましょう」 |
「何ですか気分がよろしくなくなって困りますから、少し休みまして、夜明け方にまたお話を承りましょう」 |
"Kokoti no kaki-midari, nayamasiku haberu wo, tamerahi te, akatuki-gata ni mo mata kikoye m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | とて、入りたまひなむとするけしきなり。 |
と言って、お入りになろうとする様子である。 |
と、今や奥へはいろうとする様子が姫君に見えた。 |
tote, iri tamahi na m to suru kesiki nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.8 | 「 山路分けはべりつる人は、ましていと苦しけれど、かく聞こえ 承るに慰めてこそはべれ。うち捨てて入らせたまひなば、いと心細からむ」 |
「山路を分け入って来ましたわたしは、あなた以上にとても苦しいのですが、このようにお話し申し上げたりお聞きしたりすることによって慰められております。わたしを捨ててお入りになったら、たいそう心細いでしょう」 |
「遠く |
"Yamadi wake haberi turu hito ha, masite ito kurusikere do, kaku kikoye uketamaharu ni nagusame te koso habere. Uti-sute te ira se tamahi na ba, ito kokoro-bosokara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.9 | とて、屏風をやをら押し開けて入りたまひぬ。いとむくつけくて、 半らばかり入りたまへるに、引きとどめられて、いみじくねたく心憂ければ、 |
と言って、屏風を静かに押し開けてお入りになった。たいそう気味悪くて、半分程お入りになったところ、引き止められて、ひどく悔しく気にくわないので、 |
薫はこう言って |
tote, byaubu wo yawora osi-ake te iri tamahi nu. Ito mukutukeku te, nakara bakari iri tamahe ru ni, hiki-todome rare te, imiziku netaku kokoro-ukere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10 | 「 隔てなきとは、かかるをや言ふらむ。めづらかなる わざかな」 |
「隔てなくとは、このようなことを言うのでしょうか。変なことですね」 |
「隔てなくいたしますというのはこんなことを申すのでしょうか。奇怪なことではございませんか」 |
"Hedate naki to ha, kakaru wo ya ihu ram. Meduraka naru waza kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.11 | と、あはめたまへるさまの、 いよいよをかしければ、 |
と、非難なさる様子が、ますます魅力的なので、 |
と批難の言葉を発するのがいよいよ魅力を薫に覚えしめた。 |
to, ahame tamahe ru sama no, iyo-iyo wokasikere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.12 | 「 隔てぬ心をさらに思し分かねば、聞こえ知らせむとぞかし。 めづらかなりとも、いかなる方に、思しよるにかはあらむ。仏の御前にて誓言も立てはべらむ。うたて、な懼ぢたまひそ。御心破らじと思ひそめてはべれば。 人はかくしも推し量り思ふまじかめれど、 世に違へる痴者にて過ぐしはべるぞや」 |
「隔てない心を全然お分かりでないので、お教え申し上げましょうとね。変なことだとも、どのようなことに、お考えなのでしょうか。仏の御前で誓言も立てましょう。嫌な、お恐がりなさるな。お気持ちを損ねまいと初めから思っておりますので。他人はこのようにも推量して思うまいでしょうが、世間の人と違った馬鹿正直者で通しておりますからね」 |
「隔てないというお気持ちが少しも見えないあなたに、よくわかっていただこうと思うからです。奇怪であるとは、私が無礼なことでもするとお思いになるのではありませんか。仏のお前でどんな誓言でも私は立てます。決してあなたのお気持ちを破るような行為には出まいと初めから私は思っているのですから、お恐れになることはありませんよ。私がこんなに正直におとなしくしておそばにいることはだれも想像しないことでしょうが、私はこれだけで満足して夜を明かします」 |
"Hedate nu kokoro wo sarani obosi-waka ne ba, kikoye sirase m to zo kasi. Meduraka nari tomo, ika naru kata ni, obosi-yoru ni kaha ara m? Hotoke no o-mahe nite tika-koto mo tate habera m. Utate, na wodi tamahi so. Mi-kokoro yabura zi to omohi-some te habere ba. Hito ha kaku simo osihakari omohu mazika' mere do, yo ni tagahe ru sire-mono nite sugusi haberu zo ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.13 | とて、心にくきほどなる火影に、 御髪のこぼれかかりたるを、かきやりつつ見たまへば、人の御けはひ、思ふやうに香りをかしげなり。 |
と言って、奥ゆかしいほどの火影で、御髪がこぼれかかっているのを、掻きやりながら御覧になると、姫君のご様子は、申し分なくつやつやと美しい。 |
こう言って、薫は感じのいいほどな |
tote, kokoro-nikuki hodo naru hokage ni, mi-gusi no kobore kakari taru wo, kaki-yari tutu mi tamahe ba, hito no ohom-kehahi, omohu yau ni kawori wokasige nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 第六段 薫、大君をかき口説く |
1-6 Kaoru tries to win Ohoi-kimi's affection |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1 | 「 かく心細くあさましき御住み処に、好いたらむ人は障り所あるまじげなるを、我ならで尋ね来る人も あらましかば、さてや止みなまし。いかに口惜しきわざならまし」と、 来し方の心のやすらひさへ、あやふくおぼえたまへど、 言ふかひなく憂しと思ひて泣きたまふ御けしきの、いといとほしければ、「 かくはあらで、おのづから心ゆるびしたまふ折もありなむ」と思ひわたる。 |
「このように心細くひどいお住まいで、好色の男は邪魔者もないのだが、自分以外に訪ねて来る人もあったら、そのままにしておくだろうか。どんなに残念なことだろうに」と、将来はもちろんのこと今までの優柔不断さまで、不安に思われなさるが、言いようもなくつらいと思ってお泣きになるご様子が、たいそうおいたわしいので、「このようにではなく、自然と心がとけてこられる時もきっとあるだろう」と思い続ける。 |
何の厳重な締まりもないこの山荘へ、自分のような自己を抑制する意志のない男が |
"Kaku kokoro-bosoku asamasiki ohom-sumika ni, sui tara m hito ha sahari-dokoro arumazige naru wo, ware nara de tadune kuru hito mo ara masika ba, sate ya yami na masi. Ikani kutiwosiki waza nara masi." to, kisi-kata no kokoro-yasurahi sahe, ayahuku oboye tamahe do, ihukahinaku usi to omohi te naki tamahu mi-kesiki no, ito itohosikere ba, "Kaku ha ara de, onodukara kokoro-yurubi si tamahu wori mo ari na m." to omohi wataru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | わりなきやうなるも心苦しくて、さまよくこしらへきこえたまふ。 |
無理やり迫るのも気の毒なので、体裁よくおなだめ申し上げなさる。 |
男性の力で恋を得ようとはせず、初めの心は隠して相手を |
Wari naki yau naru mo kokoro-gurusiku te, sama yoku kosirahe kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | 「 かかる御心のほどを思ひよらで、あやしきまで聞こえ馴れにたるを、 ゆゆしき袖の色など、見あらはしたまふ心浅さに、みづからの言ふかひなさも思ひ知らるるに、さまざま慰む方なく」 |
「このようなお気持ちとは思いよらず、不思議なほど親しくさせて頂いたことを、不吉な喪服の色など、見ておしまいになられる思いやりの浅さに、また自分自身の言いようのなさも思い知らされるので、あれこれと気の慰めようもありません」 |
「こんな心を突然お起こしになる方とも知らず、並みに過ぎて親しく今までおつきあいをしておりました。喪の姿などをあらわに御覧になろうとなさいましたあなたのお心の思いやりなさもわかりましたし、また私の抵抗の役だたなさも思われまして悲しくてなりません」 |
"Kakaru mi-kokoro no hodo wo omohi-yora de, ayasiki made kikoye nare ni taru wo, yuyusiki sode no iro nado, mi arahasi tamahu kokoro-asasa ni, midukara no ihukahinasa mo omohi-sira ruru ni, sama-zama nagusamu kata naku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.4 | と恨みて、何心もなくやつれたまへる墨染の火影を、いとはしたなくわびしと思ひ惑ひたまへり。 |
と恨んで、何の用意もなく質素な喪服でいらっしゃる墨染の火影を、とても体裁悪くつらいと困惑していらっしゃった。 |
と恨みを言って、姫君は他人に見られる用意の何一つなかった自身の喪服姿を |
to urami te, nani-gokoro mo naku yature tamahe ru sumi-zome no hokage wo, ito hasitanaku wabisi to omohi madohi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.5 | 「 いとかくしも 思さるるやうこそはと、恥づかしきに、聞こえむ方なし。 袖の色をひきかけさせたまふはしも、ことわりなれど、ここら御覧じなれぬる心ざしのしるしには、 さばかりの忌おくべく、今始めたることめきてやは思さるべき。なかなかなる御わきまへ心になむ」 |
「まことにこのようにまでお嫌いになるわけもあるのかと、恥ずかしくて、申し上げようもありません。喪服の色を理由になさるのも、もっともなことですが、長年お親しみなさったお気持ちの表れとしては、そのような憚らねばならないような、今始まったような事のようにお思いなさってよいものでしょうか。かえってなさらなくてもよいご分別です」 |
「そんなにもお悲しみになるのは、私がお気に入らないからだと恥じられて、なんともお慰めのいたしようがありません。喪服を召していらっしゃる場合ということで私をお |
"Ito kaku simo obosa ruru yau koso ha to, hadukasiki ni, kikoye m kata nasi. Sode no iro wo hiki-kake sase tamahu ha simo, kotowari nare do, kokora go-ran-zi nare nuru kokorozasi no sirusi ni ha sabakari no imi-oku beku, ima hazime taru koto meki te yaha obosa ru beki. Naka-naka naru ohom-wakimahe-gokoro ni nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.6 | とて、 かの物の音聞きし有明の月影よりはじめて、折々の思ふ心の忍びがたくなりゆくさまを、いと多く聞こえたまふに、「 恥づかしくもありけるかな」と疎ましく、「 かかる心ばへながらつれなくまめだちたまひけるかな」と、聞きたまふこと多かり。 |
と言って、あの琴の音を聴いた有明の月の光をはじめとして、季節折々の思う心の堪えがたくなってゆく有様を、たいそうたくさん申し上げなさると、「気恥ずかしいことだわ」と疎ましく思って、「このような気持ちでありながら何喰わぬ顔で真面目顔していらっしゃっのだわ」と、お聞きになることが多かった。 |
薫はそれに続いてあの |
tote, kano mono-no-ne kiki si ariake no tuki-kage yori hazime te, wori-wori no omohu kokoro no sinobi-gataku nari-yuku sama wo, ito ohoku kikoye tamahu ni, "Hadukasiku mo ari keru kana!" to utomasiku, "Kakaru kokorobahe nagara turenaku mamedati tamahi keru kana!" to, kiki tamahu koto ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.7 | 御かたはらなる 短き几帳を、 仏の御方にさし隔てて、 かりそめに添ひ臥したまへり。名香のいと香ばしく匂ひて、樒のいとはなやかに薫れるけはひも、 人よりはけに仏をも思ひきこえたまへる御心にて、 わづらはしく、「 墨染の今さらに、折ふし心焦られしたるやうに、あはあはしく、 思ひそめしに違ふべければ、 かかる忌なからむほどに、この御心にも、さりともすこしたわみたまひなむ」など、せめてのどかに思ひなしたまふ。 |
お側にある低い几帳を、仏の方に立てて隔てとして、形ばかり添い臥しなさった。名香がたいそう香ばしく匂って、樒がとても強く薫っている様子につけても、人よりは格別に仏を信仰申し上げていらっしゃるお心なので、気が咎めて、「服喪中の今、折もあろうに堪え性もないようで、軽率にも、当初の気持ちと違ってしまいそうなので、このような喪中が明けたころに、姫君のお気持ちも、そうはいっても少しはお緩みになるだろう」などと、つとめて気長に思いなしなさる。 |
薫はその横にあった短い |
Ohom-katahara naru midikaki kityau wo, Hotoke no ohom-kata ni sasi-hedate te, karisome ni sohi-husi tamahe ri. Myaugau no ito kaubasiku nihohi te, sikimi no ito hanayaka ni kawore ru kehahi mo, hito yori ha keni Hotoke wo mo omohi kikoye tamahe ru mi-kokoro nite, wadurahasiku, "Sumi-zome no imasara ni, wori-husi kokoro-ira re si taru yau ni, aha-ahasiku, omohi-some si ni tagahu bekere ba, kakaru imi nakara m hodo ni, kono mi-kokoro ni mo, saritomo sukosi tawami tamahi na m." nado, semete nodoka ni omohi-nasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.8 | 秋の夜のけはひは、 かからぬ所だに、おのづからあはれ多かるを、まして 峰の嵐も籬の虫も、心細げにのみ聞きわたさる。常なき世の御物語に、 時々さしいらへたまへるさま、いと見所多くめやすし。 いぎたなかりつる人びとは、「 かうなりけり」と、けしきとりてみな入りぬ。 |
秋の夜の様子は、このような場所でなくてさえ、自然としみじみとしたことが多いのに、まして峰の嵐も籬の虫の音も、心細そうにばかり聞きわたされる。無常の世のお話に、時々お返事なさる様子、実に見ごたえのある点が多く無難である。眠たそうにしていた女房たちは、「こうなったのだわ」と、様子を察して皆下がってしまった。 |
|
Aki no yo no kehahi ha, kakara nu tokoro dani, onodukara ahare ohokaru wo, masite mine no arasi mo magaki no musi mo, kokoro-bosoge ni nomi kiki-watasa ru. Tunenaki yo no ohom-monogatari ni, toki-doki sasi-irahe tamahe ru sama, ito mi-dokoro ohoku meyasusi. Igitanakari turu hito-bito ha, "Kau nari keri." to, kesiki tori te mina iri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.9 | 宮ののたまひしさまなど思し出づるに、「 げに、ながらへば、心の外にかくあるまじきことも見るべきわざにこそは」と、もののみ悲しくて、 水の音に流れ添ふ心地したまふ ★。 |
父宮がご遺言なさったことなどをお思い出しなさると、「なるほど、生き永らえると、意外なこのようなとんでもない目に遭うものだわ」と、何もかも悲しくて、水の音に流れ添う心地がなさる。 |
召使は信じがたいものであると父宮の言ってお置きになったことも女王は思い出していて、親の保護がなくなれば女も男も自分らを軽侮して、すでにもう今夜のような目にあっているではないかと悲しみ、宇治の |
Miya no notamahi si sama nado obosi-iduru ni, "Geni, nagarahe ba, kokoro no hoka ni kaku arumaziki koto mo miru beki waza ni koso ha." to, mono nomi kanasiku te, midu no oto ni nagare sohu kokoti si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 第七段 実事なく朝を迎える |
1-7 It becomes morning without sexual relation between Kaoru and Ohoi-kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.1 | はかなく明け方になりにけり。御供の人びと起きて声づくり、 馬どものいばゆる音も、旅の宿りの ★あるやうなど 人の語るを、思しやられて、をかしく思さる。 光見えつる方の障子を押し開けたまひて、空のあはれなるを もろともに見たまふ。 女もすこしゐざり出でたまへるに、ほどもなき軒の近さなれば、しのぶの露もやうやう光見えもてゆく。かたみにいと艶なるさま、容貌どもを、 |
いつのまにか夜明け方になってしまった。お供の人びとが起きて合図をし、馬どもが嘶く声も、旅の宿の様子など供人が話していたのを、ご想像されて、おもしろくお思いになる。光が見えた方面の障子を押し開けなさって、空のしみじみとした様子を一緒に御覧になる。女も少しいざり出でなさったが、奥行きのない軒の近さなので、忍草の露もだんだんと光が見えて行く。お互いに実に優美な姿態、容貌を、 |
そして明け方になった。薫の従者はもう起き出して、主人に帰りを促すらしい作り 薫は明りのさしてくるのが見えたほうの |
Hakanaku ake-gata ni nari ni keri. Ohom-tomo no hito-bito oki te kowa-dukuri, muma-domo no ibayuru oto mo, tabi no yadori no aru yau nado hito no kataru wo, obosi-yara re te, wokasiku obosa ru. Hikari miye turu kata no syauzi wo osi-ake tamahi te, sora no ahare naru wo morotomoni mi tamahu. Womna mo sukosi wizari-ide tamahe ru ni, hodo mo naki noki no tikasa nare ba, sinobu no tuyu mo yau-yau hikari miye mote yuku. Katamini ito en naru sama, katati-domo wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.2 | 「 何とはなくて、ただかやうに月をも花をも、同じ心にもてあそび、はかなき世のありさまを聞こえ合はせてなむ、過ぐさまほしき」 |
「何というのではなくて、ただこのように月や花を、同じような気持ちで愛で、無常の世の有様を話し合って、過ごしたいものですね」 |
「同じほどの友情を持ち合って、こんなふうにいつまでも月花に慰められながら、はかない人生を送りたいのですよ」 |
"Nani to ha naku te, tada kayau ni tuki wo mo hana wo mo, onazi kokoro ni mote-asobi, hakanaki yo no arisama wo kikoye ahase te nam, sugusa mahosiki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.3 | と、いとなつかしきさまして語らひきこえたまへば、やうやう恐ろしさも慰みて、 |
と、たいそう親しい感じでお語らい申されると、だんだんと恐ろしさも慰められて、 |
薫がなつかしいふうにこんなことをささやくのを聞いていて、女王はようやく恐怖から放たれた気もするのであった。 |
to, ito natukasiki sama si te katarahi kikoye tamahe ba, yau-yau osorosisa mo nagusami te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.4 | 「 かういとはしたなからで、もの隔ててなど聞こえば、真に心の隔てはさらにあるまじくなむ」 |
「このように面と向かっての体裁の悪い恰好でなく、何か物を隔ててなどしてお答え申し上げるならば、ほんとうに心の隔てはまったくないのですが」 |
「こんなにあからさまにしてお目にかかるのでなく、何かを隔ててお話をし合うのでしたら、私はもう少しも隔てなどを残しておかない心でおります」 |
"Kau ito hasitanakara de, mono hedate te nado kikoye ba, makoto ni kokoro no hedate ha sarani aru maziku nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.5 | といらへたまふ。 |
とお答えなさる。 |
と女は言った。 | to irahe tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
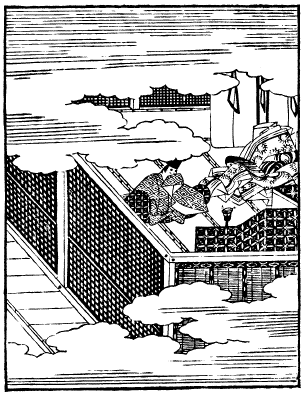 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.6 | 明くなりゆき、 むら鳥の立ちさまよふ羽風近く聞こゆ ★。夜深き朝の鐘の音かすかに響く。「 今は、いと見苦しきを」と、いとわりなく恥づかしげに思したり。 |
明るくなってゆき、群鳥が飛び立ち交う羽風が近くに聞こえる。まだ暗いうちの朝の鐘の音がかすかに響く。「今は、とても見苦しいですから」と、とても無性に恥ずかしそうにお思いになっていた。 |
外は明るくなりきって、幾種類もの川べの鳥が目をさまして飛び立つ羽音も近くでする。 |
Akaku nari-yuki, mura-tori no tati-samayohu ha-kaze tikaku kikoyu. Yo-bukaki asita no kane no oto kasuka ni hibiku. "Ima ha, ito mi-gurusiki wo." to, ito warinaku hadukasige ni obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.7 | 「 ことあり顔に朝露もえ分けはべるまじ。また、 人はいかが推し量りきこゆべき。 例のやうになだらかにもてなさせたまひて ★、ただ 世に違ひたることにて、今より後も、ただかやうにしなさせたまひてよ。よにうしろめたき心はあらじと思せ。かばかりあながちなる心のほども、あはれと思し知らぬこそかひなけれ」 |
「事あり顔に朝露を分けて帰ることはできません。また、人はどのように推量申し上げましょうか。いつものように穏便にお振る舞いになって、ただ世間一般と違った問題として、今から後も、ただこのようにしてくださいませ。まったく不安なことはないとお思いください。これほど一途に思い詰める心のうちを、いじらしいとお分かりくださらないのは効ないことです」 |
「私が恋の成功者のように朝早くは出かけられないではありませんか。かえってまた他人はそんなことからよけいな想像をするだろうと思われますよ。ただこれまでどおり普通に私をお扱いくださるのがいいのですよ。そして世間のとは内容の違った夫婦とお思いくだすって、今後もこの程度の接近を許しておいてください。あなたに礼を失うような |
"Koto-ari-gaho ni asa-tuyu mo e wake haberu mazi. Mata, hito ha ikaga osihakari kikoyu beki. Rei no yau ni nadaraka ni motenasa se tamahi te, tada yo ni tagahi taru koto nite, ima yori noti mo, tada kayau ni si-nasa se tamahi te yo. Yo ni usirometaki kokoro ha ara zi to obose. Kabakari anagati naru kokoro no hodo mo, ahare to obosi-sira nu koso kahinakere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.8 | とて、出でたまはむのけしきもなし。あさましく、かたはならむとて、 |
と言って、お帰りなるような様子もない。あきれて、見苦しいことと思って、 |
こんなことを言っていて、薫はなおすぐに出て行こうとはしない。それは非常に見苦しいことだと姫君はしていて、 |
tote, ide tamaha m no kesiki mo nasi. Asamasiku, kataho nara m tote, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.9 | 「 今より後は、さればこそ、もてなしたまはむままにあらむ。 今朝は、また聞こゆるに従ひたまへかし」 |
「今から後は、そのようなことなので、仰せの通りにいたしましょう。今朝は、またお願い申し上げていることを聞いてくださいませ」 |
「これからは今あなたがお言いになったとおりにもいたしましょう。 |
"Ima yori noti ha, sareba koso, motenasi tamaha m mama ni ara m. Kesa ha, mata kikoyuru ni sitagahi tamahe kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.10 | とて、 いとすべなしと思したれば、 |
と言って、ほんとうに困ったとお思いなので、 |
と言う。いかにも心を苦しめているのが見える。 |
tote, ito sube nasi to obosi tare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.11 | 「 あな、苦しや。 暁の別れや。まだ知らぬことにて、げに、惑ひぬべきを」 |
「ああ、つらい。暁の別れだ。まだ経験のないことなので、なるほど、迷ってしまいそうだ」 |
「私も苦しんでいるのですよ。朝の別れというものをまだ経験しない私は、昔の歌のように帰り |
"Ana, kurusi ya! Akatuki no wakare ya! Mada sira nu koto nite, geni, madohi nu beki wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.12 | と嘆きがちなり。鶏も、いづ方にかあらむ、ほのかにおとなふに、京思ひ出でらる。 |
と嘆きがちである。鶏も、どこのであろうか、かすかに鳴き声がするので、京が自然と思い出される。 |
|
to nageki-gati nari. Nihatori mo, idu-kata ni ka ara m, honoka ni otonahu ni, Kyau omohi-ide raru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.13 | 「 山里のあはれ知らるる声々に |
「山里の情趣が思い知られます鳥の声々に |
「山里の哀れ知らるる声々に |
"Yama-zato no ahare sira ruru kowe-gowe ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.14 | とりあつめたる朝ぼらけかな」 |
あれこれと思いがいっぱいになる朝け方ですね」 |
とりあつめたる朝ぼらけかな」 |
tori-atume taru asaborake kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.15 | 女君、 |
女君、 |
姫君はそれに答えて、 |
Womna-Gimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.16 | 「 鳥の音も聞こえぬ山と思ひしを |
「鳥の声も聞こえない山里と思っていましたが |
「鳥の音も聞こえぬ山と思ひしを |
"Tori no ne mo kikoye nu yama to omohi si wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.17 | 世の憂きことは訪ね来にけり」 |
人の世の辛さは後を追って来るものですね」 |
よにうきことはたづねきにけり」 |
yo no uki koto ha tadune ki ni keri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.18 | 障子口まで送りたてまつりたまひて、 昨夜入りし戸口より出でて、臥したまへれど、まどろまれず。 ▼ 名残恋しくて、「 いとかく思はましかば、月ごろも今まで心のどかならましや」など、帰らむことももの憂くおぼえたまふ。 |
障子口までお送り申し上げなさって、昨夜入った戸口から出て、お臥せりになったが、眠ることはできない。名残惜しくて、「ほんとにこのようにせつなく思うのだったら、幾月も今までのんびりと構えていられなかったろうに」などと、帰ることを億劫に思われなさる。 |
と言った。姫君の居間の |
Syauzi-guti made okuri tatematuri tamahi te, yobe iri si toguti yori ide te, husi tamahe re do, madoroma re zu. Nagori kohisiku te, "Ito kaku omoha masika ba, tuki-goro mo ima made kokoro nodoka nara masi ya!" nado, kahera m koto mo mono-uku oboye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 第八段 大君、妹の中の君を薫にと思う |
1-8 Ohoi-kimi desires her sister getting married to Kaoru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.1 | 姫宮は、人の思ふらむことのつつましきに、とみにもうち臥されたまはで、「 頼もしき人なくて世を過ぐす身の心憂きを、ある人どもも、よからぬこと何やかやと、次々に従ひつつ言ひ出づめるに、心よりほかのことありぬべき世なめり」と 思しめぐらすには、 |
姫宮は、女房がどう思っているだろうかと気が引けるので、すぐには横におなりになれず、「頼みにする親もなくて世の中を生きてゆく身の上のつらさを、仕えている女房連中も、つまらない縁談の事を何やかやと、次々に従って言い出すようだから、望みもしない結婚になってしまいそうだ」と思案なさる一方で、 |
姫君は人がどんな想像をしているかと思うのが恥ずかしくて、すぐにも |
Hime-Gimi ha, hito no omohu ram koto no tutumasiki ni, tomi ni mo uti-husa re tamaha de, "Tanomosiki hito naku te yo wo sugusu mi no kokoro-uki wo, aru hito-domo mo, yokara nu koto nani-ya ka-ya to, tugi-tugi ni sitagahi tutu ihi-idu meru ni, kokoro yori hoka no koto ari nu beki yo na' meri." to obosi-megurasu ni ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.2 | 「 この人の御けはひありさまの、疎ましくはあるまじく、故宮も、さやうなる心ばへあらばと、折々のたまひ思すめりしかど、 みづからは、なほかくて過ぐしてむ。我よりはさま容貌も盛りにあたらしげなる中の宮を、 人なみなみに見なしたらむこそうれしからめ。 人の上になしては、心のいたらむ限り思ひ後見てむ。みづからの上のもてなしは、 また誰れかは見扱はむ。 |
「この人のご様子や態度が、疎ましくはなさそうだし、故宮も、そのような気持ちがあったらと、時々おっしゃりお考えのようだったが、自分自身は、やはりこのように独身で過ごそう。自分よりは容姿も容貌も盛りで惜しい感じの中の宮を、人並みに結婚させたほうが嬉しいだろう。妹の身の上のことなら、心の及ぶ限り後見しよう。自分の身の世話は、他に誰が見てくれようか。 |
薫は |
"Kono hito no ohom-kehahi arisama no, utomasiku ha arumaziku, ko-Miya mo, sayau naru kokoro-bahe ara ba to, wori-wori notamahi obosu meri sika do, midukara ha, naho kakute sugusi te m. Ware yori ha sama katati mo sakari ni atarasige naru Naka-no-Miya wo, hito nami-nami ni mi-nasi tara m koso uresikara me. Hito no uhe ni nasi te ha, kokoro no itara m kagiri omohi usiromi te m. Midukara no uhe no motenasi ha, mata tare ka ha mi-atukaha m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.3 | この人の御さまの、なのめにうち紛れたるほどならば、かく見馴れぬる年ごろのしるしに、うちゆるぶ心もありぬべきを、 恥づかしげに見えにくきけしきも、なかなかいみじくつつましきに、 わが世はかくて過ぐし果ててむ」 |
この人のお振舞が、いい加減ででたらめならば、このように親しんできた年月のせいで、気を緩める気持ちもありそうなのだが、立派すぎて近づきがたい感じなのも、かえってひどく気後れするので、自分の人生はこうして独身で終えよう」 |
薫が今少し平凡な男であれば、長く持ち続けられた好意に対してむくいるために、妻になる気が起きたかもしれぬ。けれどあの人はそうでない、あまりにすぐれた男である、気品が高く近づきにくいふうもあるではないか、自分には不似合いに思われてならぬ、自分は今までどおりの寂しい運命のままで一人いよう | Kono hito no ohom-sama no, nanome ni uti-magire taru hodo nara ba, kaku mi-nare nuru tosi-goro no sirusi ni, uti-yurubu kokoro mo ari nu beki wo, hadukasige ni miye nikuki kesiki mo, naka-naka imiziku tutumasiki ni, waga yo ha kaku te sugusi-hate te m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.4 | と思ひ続けて、音泣きがちに明かしたまへるに、名残いと悩ましければ、中の宮の臥したまへる奥の方に添ひ臥したまふ。 |
と思い続けて、つい声を立てて泣き泣き夜を明かしなさったが、そのため気分がとても悪いので、中の宮が臥していらっしゃった奥の方に添ってお臥せりになる。 |
と、思い続けて朝まで泣いていたあとの |
to omohi tuduke te, ne naki-gati ni akasi tamahe ru ni, nagori ito nayamasikere ba, Naka-no-Miya no husi tamahe ru oku no kata ni sohi-husi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.5 | 例ならず、人のささめきしけしきもあやしと、 この宮は思しつつ寝たまへるに、かくておはしたれば、うれしくて、 御衣ひき着せたてまつりたまふに、 御移り香の紛るべくもあらず、くゆりかかる心地すれば、宿直人がもて扱ひけむ思ひあはせられて、「 まことなるべし」と、いとほしくて、寝ぬるやうにてものものたまはず。 |
いつもと違って、女房がささやいている様子が変だと、この宮はお思いになりながら寝ていらっしゃったが、こうしていらっしゃったので、嬉しくて、御衣を引き掛けて差し上げなさると、御移り香が隠れようもなく、薫ってくる感じがするので、宿直人がもてあましていたことが思い合わされて、「ほんとうなのだろう」と、お気の毒に思って、眠ってしまったようにして何もおっしゃらない。 |
昨夜は平常とは変わっておそくまで話し声がするのを怪しく思いながら、中の君は寝入ったのであったから、大姫君のこうして来たのがうれしくて、夜着を姉の上へ掛けようとした時に、高いにおいがくゆりかかるように立つのを知った。あの |
Rei nara zu, hito no sasameki si kesiki mo ayasi to, kono Miya ha, obosi tutu ne tamahe ru ni, kakute ohasi tare ba, uresiku te, ohom-zo hiki-kise tatematuri tamahu ni, ohom-uturi-ga no magiru beku mo ara zu, kuyuri kakaru kokoti sure ba, tonowi-bito ga mote-atukahi kem omohi ahase rare te, "Makoto naru besi." to, itohosiku te, ne nuru yau ni te mono mo notamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.6 | 客人は、弁のおもと呼び出でたまひて、こまかに語らひおき、御消息 すくすくしく聞こえおきて出でたまひぬ。「 総角を戯れにとりなししも ★、心もて、 ▼ 尋ばかりの隔ても対面しつるとや、この君も思すらむ」と、いみじく恥づかしければ、心地悪しとて、悩み暮らしたまひつ。人びと、 |
客人は、弁のおもとを呼び出しなさって、こまごまと頼みこんで、ご挨拶をしかつめらしく申し上げおいてお出になった。「総角の歌を戯れの冗談にとりなしても、自分から、一尋ほどの隔てはあったにしてもお会いしたものと、この君もお思いだろう」と、ひどく恥ずかしいので、気分が悪いといって、一日中横になっていらっしゃった。女房たちは、 |
薫は朝になってからまた老女の弁に 昨日は |
Marauto ha, Ben-no-Omoto yobi-ide tamahi te, komaka ni katarahi-oki, ohom-seusoko suku-sukusiku kikoye-oki te ide tamahi nu. "Agemaki wo tahabure ni torinasi si mo, kokoro-mote, hiro bakari no hedate mo taimen si turu to ya, kono Kimi mo obosu ram." to, imiziku hadukasikere ba, kokoti asi tote, nayami kurasi tamahi tu. Hito-bito, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.7 | 「 日は残りなくなりはべりぬ。はかばかしく、はかなきことをだに、また仕うまつる人もなきに、折悪しき御悩みかな」 |
「法事までの日数が少なくなりました。しっかりと、ちょっとしたことでさえも、他にお世話いたす人もいないので、あいにくのご病気ですこと」 |
「もう御仏事までに日がいくらもなくなりましたのに、そのほかには小さいこともはかばかしくできる人もない時のあやにくな姫君の御病気ですね」 |
"Hi ha nokori naku nari haberi nu. Haka-bakasiku, hakanaki koto wo dani, mata tukau-maturu hito mo naki ni, wori asiki ohom-nayami kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.8 | と聞こゆ。中の宮、 組などし果てたまひて、 |
と申し上げる。中の宮は、組紐など作り終えなさって、 |
などと言っていた。組紐が皆出来そろってから、中の君が来て、 |
to kikoyu. Naka-no-Miya, kumi nado si-hate tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.9 | 「 心葉など、えこそ思ひよりはべらね」 |
「心葉などを、どうしてよいか分かりません」 |
「飾りの |
"Kokoroba nado, e koso omohi-yori habera ne." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.10 | と、 せめて聞こえたまへば、 暗くなりぬる紛れに起きたまひて、もろともに結びなどしたまふ。中納言殿より御文あれど、 |
と、無理におせがみ申し上げなさるので、暗くなったのに紛れてお起きになって、一緒に結んだりなどなさる。中納言殿からお手紙があるが、 |
と訴えるのを聞いて、もうその時にあたりも暗くなっていたのに紛らして、姫君は起きていっしょに紐結びを作りなどした。 源中納言からの手紙の来た時、 |
to, semete kikoye tamahe ba, kuraku nari nuru magire ni oki tamahi te, morotomo ni musubi nado si tamahu. Tyuunagon-dono yori ohom-humi are do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.11 | 「今朝よりいと悩ましくなむ」 |
「今朝からとても気分が悪くて」 |
「 |
"Kesa yori ito nayamasiku nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.12 | とて、 人伝てにぞ聞こえたまふ。 |
と言って、人を介してお返事申し上げなさる。 |
と取り次ぎに言わせて、返事を出さなかったのを、 | tote, hito-dute ni zo kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.13 | 「さも、見苦しく、若々しくおはす」 |
「いかにも、見苦しく、子供っぽくいらっしゃいます」 |
あまりに苦々しい態度だ | "Samo, mi-gurusiku, waka-wakasiku ohasu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.14 | と、人びとつぶやききこゆ。 |
と、女房たちはぶつぶつ申し上げる。 |
と |
to, hito-bito tubuyaki kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 3/28/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 3/28/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 3/28/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 10/26/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経