38 鈴虫(大島本) |
SUZUMUSI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 五十歳夏から秋までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from summer to fall, at the age of 50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 女三の宮の物語 持仏開眼供養 |
1 Tale of Omna-Sam-no-Miya A new statue of Buddha service |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 持仏開眼供養の準備 |
1-1 A preparation for a new statue of Buddha service |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 夏ごろ、蓮の花の盛りに、 入道の姫宮の御持仏どもあらはしたまへる、供養ぜさせたまふ。 |
夏頃、蓮の花の盛りに、入道の姫宮が御持仏の数々をお造りになったのを、開眼供養を催しあそばす。 |
夏の |
Natu-goro, hatisu-no-hana no sakari ni, Nihudau-no-Hime-Miya no ohom-dibutu-domo arahasi tamahe ru, kuyau-ze sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | このたびは、大殿の君の御心ざしにて、御念誦堂の具ども、こまかに 調へさせたまへるを、やがてしつらはせたまふ。幡のさまなどなつかしう、心ことなる唐の錦を選び縫はせたまへり。 紫の上ぞ、急ぎせさせたまひける。 |
今回は、大殿の君のお志で、御念誦堂の道具類も、こまごまとご準備させていたのを、そっくりそのままお飾りあそばす。幡の様子など優しい感じで、特別な唐の錦を選んでお縫わせなさった。紫の上が、ご準備させなさったのであった。 |
|
Kono-tabi ha, Otodo-no-Kimi no mi-kokorozasi ni te, go-nenzyu-dau no gu-domo, komaka ni totonohe sase tamahe ru wo, yagate siturahase tamahu. Hata no sama nado natukasiu, kokoro koto naru Kara no nisiki wo erabi nuha se tamahe ri. Murasaki-no-Uhe zo, isogi se sase tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 花机の覆ひなどの をかしき目染もなつかしう、きよらなる匂ひ、染めつけられたる心ばへ、目馴れぬさまなり。夜の御帳の帷を、四面ながら上げて、後ろの方に法華の曼陀羅かけたてまつりて、銀の花瓶に、高くことことしき花の色を調へてたてまつり、名香に、唐の百歩の薫衣香を焚きたまへり。 |
花机の覆いなどの美しい絞り染も優しい感じで、美しい色艶が、染め上げられている趣向など、またとない素晴らしさである。夜の御帳台の帷子を、四面とも上げて、後方に法華の曼陀羅をお掛け申して、銀の花瓶に、高々と見事な蓮の花を揃えてお供えになって、名香には、唐の百歩の衣香を焚いていらっしゃる。 |
紫夫人の手もとで調製された |
Hana-dukuwe no ohohi nado no wokasiki me-zome mo natukasiu, kiyora naru nihohi, some-tuke rare taru kokorobahe, me nare nu sama nari. Yoru no mi-tyau no katabira wo, yo-omote nagara age te, usiro no kata ni Ho'ke no mandara kake tatematuri te, sirogane no hana-game ni, takaku koto-kotosiki hana no iro wo totonohe te tatematuri, myaugau ni, Kara no hyakubu no kunoekau wo taki tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 阿弥陀仏、脇士の菩薩、おのおの白檀して作りたてまつりたる、こまかにうつくしげなり。閼伽の具は、例の、きはやかに小さくて、青き、白き、紫の蓮を調へて、 荷葉の方を合はせたる名香、蜜を隠しほほろげて、焚き匂はしたる、一つ薫りに匂ひ合ひて、いとなつかし。 |
阿彌陀仏、脇士の菩薩、それぞれ白檀でお造り申してあるのが、繊細で美しい感じである。閼伽の道具は、例によって、際立って小さくて、青色、白色、紫の蓮の色を揃えて、荷葉香を調合したお香は、蜜を控えてぼろぼろに崩して、焚き匂わしているのが、一緒に匂って、とても優しい感じがする。 |
|
Amida-butu, keuzi no Bosati, ono-ono byakudan si te tukuri tatematuri taru, komaka ni utukusige nari. Aka no gu ha, rei no, kihayaka ni tihisaku te, awoki, siroki, murasaki no hatisu wo totonohe te, kaehu no hau wo ahase taru myaugau, miti wo kakusi hohoroge te, taki nihohasi taru, hitotu kawori ni nihohi-ahi te, ito natukasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | 経は、六道の衆生のために 六部書かせたまひて、 みづからの御持経は、院ぞ御手づから書かせたまひける。これをだに、この世の結縁にて、かたみに導き交はしたまふべき心を、願文に作らせたまへり。 |
経は、六道の衆生のために六部お書きあそばして、ご自身の御持経は、院がご自身でお書きあそばしたのであった。せめてこれだけでも、この世の結縁として、互いに極楽浄土に導き合いなさるようにとの旨を願文にお作りあそばした。 |
経巻は六道を行く |
Kyau ha, rokudau no syuzyau no tame ni roku-bu kaka se tamahi te, midukara no ohom-dikyau ha, Win zo ohom-tedukara kaka se tamahi keru. Kore wo dani, konoyo no ketien nite, katamini mitibiki-kahasi tamahu beki kokoro wo, gwanmon ni tukura se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | さては、阿弥陀経、唐の紙はもろくて、 朝夕の御手慣らしにもいかがとて、紙屋の人を召して、ことに仰せ言賜ひて、心ことにきよらに漉かせたまへるに、この春のころほひより、 御心とどめて急ぎ書かせたまへるかひありて、端を見たまふ人びと、目もかかやき惑ひたまふ。 |
その他には、阿彌陀経、唐の紙はもろいので、朝夕のご使用にはどのようなものかしらと考えて、紙屋院の官人を召して、特別にご命令を下して、格別美しく漉かせなさった紙に、この春頃から、お心を込めて急いでお書きあそばしたかいがあって、その片端を御覧になった方々、目も眩むほどに驚いていらっしゃる。 |
朝夕に |
Sateha, Amida-kyau, Kara-no-kami ha moroku te, asa-yuhu no ohom-tenarasi ni mo ikaga tote, Kamiya no hito mesi te, koto ni ohose-goto tamahi te, kokoro koto ni kiyora ni suka se tamahe ru ni, kono haru no korohohi yori, mi-kokoro todome te isogi kaka se tamahe ru kahi ari te, hasi wo mi tamahu hito-bito, me mo kakayaki madohi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | 罫かけたる金の筋よりも、墨つきの上にかかやくさまなども、いとなむめづらかなりける。 軸、表紙、筥のさまなど、いへば さらなりかし。 これはことに沈の花足の机に据ゑて、仏の 御同じ帳台の上に飾らせたまへり。 |
罫に引いた金泥の線よりも、墨の跡の方がさらに輝くように立派な様子などが、まことに見事なものであった。軸、表紙、箱の様子など、言うまでもないことである。これは特に沈の花足の机の上に置いて、仏と同じ御帳台の上に飾らせなさった。 |
|
Ke kake taru kane no sudi yori mo, sumi-tuki no uhe ni kakayaku sama nado mo, ito nam meduraka nari keru. Diku, heusi, hako no sama nado, ihe ba sara nari. Kore ha koto ni din no kesoku no tukuwe ni suwe te, Hotoke no ohom-onazi tyaudai no uhe ni kazara se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 源氏と女三の宮、和歌を詠み交わす |
1-2 Genji and Omna-Sam-no-Miya compose and change waka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 堂飾り果てて、講師参う上り、 行道の人びと参り集ひたまへば、院もあなたに出でたまふとて、 宮のおはします西の廂にのぞきたまへれば、狭き心地する仮の御しつらひに、所狭く暑げなるまで、 ことことしく装束きたる女房、五、六十人ばかり集ひたり。 |
お堂を飾り終わって、講師が壇上して、行道の人々も参集なさったので、院もそちらに出ようとなさって、宮のいらっしゃる西の廂の間にお立ち寄りなさると、狭い感じのする仮の御座所に、窮屈そうに暑苦しいほどに、仰々しく装束をした女房たちが五、六十人ほど集まっていた。 |
堂の準備ができて講師が座に着き |
Dau kazari hate te, kauzi mau-nobori, gyaudau no hito-bito mawiri tudohi tamahe ba, Win mo anata ni ide tamahu tote, Miya no ohasimasu nisi no hisasi ni nozoki tamahe re ba, sebaki kokoti suru kari no ohom-siturahi ni, tokoro-seku atuge naru made, koto-kotosiku syauzoki taru nyoubau, go, roku-zihu-nin bakari tudohi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 北の廂の簀子まで、童女などはさまよふ。 火取りどもあまたして、煙たきまで扇ぎ散らせば、さし寄りたまひて、 |
北の廂の間の簀子まで、女童などはうろうろしている。香炉をたくさん使って、煙いほど扇ぎ散らすので、近づきなさって、 |
童女などは北側の |
Kita no hisasi no sunoko made, warahabe nado ha samayohu. Hitori-domo amata si te, kebutaki made ahugi tirase ba, sasi-yori tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 「 空に焚くは、いづくの煙ぞと思ひ分かれぬこそよけれ。 富士の峰よりもけに、くゆり満ち出でたるは、本意なきわざなり。講説の折は、おほかたの鳴りを静めて、のどかにものの心も聞き分くべきことなれば、憚りなき衣の音なひ、人のけはひ、静めてなむよかるべき」 |
「空薫物は、どこで焚いているのか分からないくらいなのがよいのだ。富士山の噴煙以上に、煙がたちこめているのは、感心しないことだ。お経の御講義の時には、あたり一帯の音は立てないようにして、静かにお説教の意味を理解しなければならないことだから、遠慮のない衣ずれの音、人のいる感じは、出さないのがよいのです」 |
「 |
"Sora ni taku ha, iduku no keburi zo to omohi waka re nu koso yokere. Huzi no mine yori mo keni, kuyuri miti ide taru ha, ho'i-naki waza nari. Kauzeti no wori ha, ohokata no nari wo sidume te, nodoka ni mono no kokoro mo kiki-waku beki koto nare ba, habakari naki kinu no otonahi, hito no kehahi, sidume te nam yokaru beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | など、例の、もの深からぬ若人どもの用意教へたまふ。宮は、人気に圧されたまひて、いと小さくをかしげにて、ひれ臥したまへり。 |
などと、いつものとおり、思慮の足りない若い女房たちの心用意をお教えになる。宮は、人気に圧倒されなさって、とても小柄で美しい感じに臥せっていらっしゃった。 |
などと、例の軽率な若い女房などをお教えになった。宮は |
nado, rei no, mono-hukakara nu wakaudo-domo no youi wosihe tamahu. Miya ha, hitoke ni osa re tamahi te, ito tihisaku wokasige ni te, hire-husi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 「 若君、らうがはしからむ。抱き隠したてまつれ」 |
「若君が、騒がしかろう。抱いてあちらへお連れ申せ」 |
「若君をここへ置かずに、どちらか遠い |
"Waka-Gimi, raugahasikara m. Idaki kakusi tatemature." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | などのたまふ。 |
などとおっしゃる。 |
とまた院は女房へ注意をあそばされた。 |
nado notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
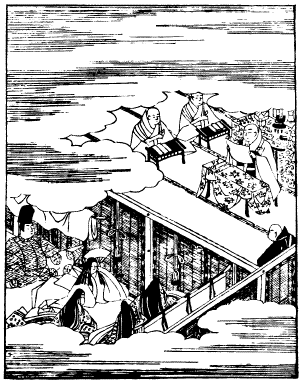 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 北の御障子も取り放ちて、御簾かけたり。 そなたに人びとは入れたまふ ★。静めて、宮にも、ものの心知りたまふべき 下形を聞こえ知らせたまふ、いとあはれに見ゆ。 御座を譲りたまへる仏の御しつらひ、 見やりたまふも、 さまざまに、 |
北の御障子も取り放って、御簾を掛けてある。そちらに女房たちをお入れになっている。静かにさせて、宮にも、法会の内容がお分かりになるように予備知識をお教え申し上げなさるのも、とても親切に見える。御座所をお譲りなさった仏のお飾り付け、御覧になるにつけても、あれこれと感慨無量で、 |
北側の座敷との間も今日は |
Kita no mi-syauzi mo tori hanati te, mi-su kake tari. Sonata ni hito-bito ha ire tamahu. Sidume te, Miya ni mo, mono no kokoro siri tamahu beki sitakata wo kikoye sira se tamahu, ito ahare ni miyu. O-masi yuduri tamahe ru Hotoke no ohom-siturahi, mi-yari tamahu mo, sama-zama ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | 「 かかる方の御いとなみをも、もろともに急がむものとは思ひ寄らざりしことなり。よし、後の世にだに、 かの花の中の宿りに、隔てなく、とを ★思ほせ」 |
「このような仏事の御供養を、ご一緒にしようとは思いもしなかったことだ。まあ、しかたない。せめて来世では、あの蓮の花の中の宿を、一緒に仲好くしよう、と思って下さい」 |
「こんな儀式をあなたのためにさせる日があろうなどとは予想もしなかったことですよ。これはこれとして来世の |
"Kakaru kata no ohom-itonami wo mo, morotomo ni isoga m mono to ha omohi-yora zari si koto nari. Yosi, noti no yo ni dani, kano hana no naka no yadori ni, hedate naku, to wo omohose." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | とて、うち泣きたまひぬ。 |
とおっしゃって、お泣きになった。 |
と言って院はお泣きになった。 |
tote, uti-naki tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 「 蓮葉を同じ台と契りおきて |
「来世は同じ蓮の花の中でと約束したが |
|
"Hatisuba wo onazi utena to tigiri-oki te |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | 露の分かるる今日ぞ悲しき」 |
その葉に置く露のように別々でいる今日が悲しい」 |
露の分かるる |
tuyu no waka ruru kehu zo kanasiki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | と、御硯にさし濡らして、 香染めなる御扇に書きつけたまへり。宮、 |
と、御硯に筆を濡らして、香染の御扇にお書き付けになった。宮は、 |
|
to, ohom-suzuri ni sasi-nurasi te, kau-zome naru ohom-ahugi ni kaki-tuke tamahe ri. Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | 「 隔てなく蓮の宿を契りても |
「蓮の花の宿を一緒に仲好くしようと約束なさっても |
隔てなく |
"Hedate naku hatisu no yado wo tigiri te mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.14 | 君が心や住まじとすらむ」 |
あなたの本心は悟り澄まして一緒にとは思っていないでしょう」 |
君が心やすまじとすらん |
Kimi ga kokoro ya suma zi to su ram |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.15 | と書きたまへれば、 |
とお書きになったので、 |
こうお書きになると、 |
to kaki tamahe re ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.16 | 「 いふかひなくも思ほし朽たすかな」 |
「せっかくの申し出をかいなくされるのですね」 |
「そんなに私が信用していただけないのだろうか」 |
"Ihukahinaku mo omohosi kutasu kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.17 | と、 うち笑ひながら、なほあはれとものを思ほしたる御けしきなり。 |
と、苦笑しながらも、やはりしみじみと感に堪えないご様子である。 |
笑いながら院は言っておいでになるのであるが身にしむものがある御様子であった。 |
to, uti-warahi nagara, naho ahare to mono wo omohosi taru mi-kesiki nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 持仏開眼供養執り行われる |
1-3 The new statue of Buddha service is held by Omna-Sam-no-Miya in summer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 例の、親王たちなども、いとあまた参りたまへり。 御方々より、我も我もと営み出でたまへる捧物のありさま、心ことに、所狭きまで見ゆ。七僧の法服など、すべておほかたのことどもは、皆 紫の上せさせたまへり。 綾のよそひにて、袈裟の縫目まで、見知る人は、世になべてならずとめでけりとや。むつかしうこまかなることどもかな。 |
例によって、親王たちなども、とても大勢参上なさった。御夫人方から、我も我もと作り出した御供物の様子、格別立派で、所狭しと見える。七僧の法服など、総じて一通りのことは、皆紫の上がご準備させなさった。綾織物で、袈裟の縫目まで、分かる人は、世間にはめったにない立派な物だと誉めたとか。うるさく細かい話であるよ。 |
例のことであるが親王がたも多く参会された。六条院の夫人たちから仏前へささげられた物の数も多かった。七僧の法服とか、この法事についての重だった布施は皆紫夫人が調製させたものである。 |
Rei no, Miko-tati nado mo, ito amata mawiri tamahe ri. Ohom-kata-gata yori, ware mo ware mo to itonami ide tamahe ru houmoti no arisama, kokoro koto ni, tokoro-seki made miyu. Siti-sou no hohubuku nado, subete ohokata no koto-domo ha, mina Murasaki-no-Uhe se sase tamahe ri. Aya no yosohi ni te, kesa no nuhime made, mi-siru hito ha, yo ni nabete nara zu to mede keri to ya! Mutukasiu komaka naru koto-domo kana! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 講師のいと尊く、ことの心を申して、 この世にすぐれたまへる盛りを厭ひ離れたまひて、 長き世々に絶ゆまじき御契りを、法華経に結びたまふ、尊く深きさまを表はして、ただ今の世の、 才もすぐれ、豊けきさきらを、いとど心して言ひ続けたる、いと尊ければ、皆人、しほたれたまふ。 |
講師が大変に尊く、法要の趣旨を申して、この世でご立派であった盛りのお身の上を厭い離れなさって、未来永劫にわたって絶えることのない夫婦の契りを、法華経に結びなさる、尊く深いお心を表わして、ただ現在、才学も優れ、豊かな弁舌を、ますます心をこめて言い続ける、とても尊いので、参会者全員、涙をお流しなさる。 |
講師が宮の御 |
Kauzi no ito tahutoku, koto no kokoro wo mausi te, kono yo ni sugure tamahe ru sakari wo itohi hanare tamahi te, nagaki yo-yo ni tayu maziki ohom-tigiri wo, Hokekyau ni musubi tamahu, tahutoku hukaki sama wo arahasi te, tada ima-no-yo no, zae mo sugure, yutakeki sakira wo, itodo kokorosi te ihi-tuduke taru, ito tahutokere ba, mina-hito, sihotare tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | これは、ただ忍びて、御念誦堂の初めと思したることなれど、 内裏にも、山の帝も聞こし召して、皆御使どもあり。御誦経の布施など、いと所狭きまで、にはかになむこと広ごりける。 |
この持仏開眼供養は、ただこっそりと、御念誦堂の開き初めとお考えになったことだが、帝におかせられても、また山の帝もお耳にあそばして、いずれもお使者があった。御誦経のお布施など、大変置ききれないほど、急に大げさになったのであった。 |
今日のはただ |
Kore ha, tada sinobi te, o-nenznu-dau no hazime to obosi taru koto nare do, Uti ni mo, Yama-no-Mikado mo kikosimesi te, mina ohom-tukahi-domo ari. Mi-zyukyau no huse nado, ito tokoro-seki made, nihaka ni nam koto hirogori keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 院にまうけさせたまへりけることどもも、削ぐと思ししかど、世の常ならざりけるを、まいて、今めかしきことどもの加はりたれば、 夕べの寺に置き所なげなるまで、所狭き勢ひになりてなむ、僧どもは帰りける。 |
院でご準備あそばしたことも、簡略にとはお思いになったが、それでも並々ではなかったのだが、それ以上に、華やかなお布施が加わったので、夕方のお寺に置き場もないほど沢山になって、僧たちは帰って行ったのであった。 |
初めの設けは簡単にしたように院は |
Win ni mauke sase tamahe ri keru koto-domo mo, sogu to obosi sika do, yo no tune nara zari keru wo, maite, imamekasiki koto-domo no kuhahari tare ba, yuhube no tera ni oki dokoro nage naru made, tokoro-seki ikihohi ni nari te nam, sou-domo ha kaheri keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 三条宮邸を整備 |
1-4 Suzaku orders men to repair Samjo-palace |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 今しも、心苦しき御心添ひて、はかりもなくかしづききこえたまふ。院の帝は、 この御処分の宮に住み離れたまひなむも、 つひのことにて、目やすかりぬべく聞こえたまへど、 |
今となって、おいたわしく思われる気持ちが加わって、この上もなく大切にお世話申し上げなさる。院の帝は、御相続なさった宮に離れてお住みになることも、結局のことなのだから、世間体がよいように申し上げなさるが、 |
御出家をあそばされた今になって宮を院がごたいせつにあそばすことは非常で、無限の御愛情が運ばれていると見えた。御寺の |
Ima simo, kokoro-gurusiki mi-kokoro sohi te, hakari mo naku kasiduki kikoye tamahu. Win-no-Mikado ha, kono go-soubun no Miya ni sumi hanare tamahi na m mo, tuhi no koto nite, me-yasukari nu beku kikoye tamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 「 よそよそにては、おぼつかなかるべし。明け暮れ見たてまつり、聞こえ承らむこと怠らむに、本意違ひぬべし。げに、 あり果てぬ世いくばくあるまじけれど、なほ生ける限りの心ざしをだに失ひ果てじ」 |
「離れ離れでいては、気掛かりであろう。毎日お世話申し上げて、こちらから申し上げたり用向きを承ることができないようでは、本意に外れることであろう。なるほど、いつまでも生きていられない世であるが、やはり生きている限りはお世話したい気持ちだけはなくしたくない」 |
「遠くなっては始終お目にかかることもできないので困ります。毎日お逢いしてお話ができたり、あなたの用を聞いたりすることができなくなっては、私の期していたことが皆 |
"Yoso-yoso ni te ha, obotukanakaru besi. Ake-kure mi tatematuri, kikoye uketamahara m koto okotara m ni, ho'i tagahi nu besi. Geni, ari hate nu yo ikubaku aru mazikere do, naho ike ru kagiri no kokorozasi wo dani usinahi hate zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | と 聞こえたまひつつ、 この宮をも いとこまかにきよらに造らせたまひ、御封の物ども、国々の御荘、御牧などより奉る物ども、はかばかしきさまのは、皆かの三条の宮の 御倉に納めさせたまふ。 またも、建て添へさせたまひて、さまざまの御宝物ども、院の御処分に数もなく賜はりたまへるなど、 あなたざまの物は、皆かの宮に運び渡し、こまかにいかめしうし置かせたまふ。 |
と申し上げ申し上げなさっては、あちらの宮も大変念入りに美しくご改築させなさって、御封の収入、国々の荘園、牧場などからの献上物で、これはと思われる物は、全てあちらの三条宮の御倉に納めさせなさる。さらに又、増築させて、いろいろな御宝物類、院の御遺産相続の時に無数にお譲り受けなさった物など、宮の関係の品物は、全てあちらの宮に運び移して、念を入れて厳重に保管させなさる。 |
とお言いになって賛成をあそばさないのである。院はまたそのほうの邸宅もきれいに修繕させてお置きになって、宮が官から給されておいでになる収入や、御私有の荘園や牧から上がって来る物の中でも、貯蔵しておく価値のある物は皆その三条の宮の |
to kikoye tamahi tutu, kono Miya wo mo ito komaka ni kiyora ni tukura se tamahi, mi-bu no mono-domo, kuni-guni no mi-syau, mi-maki nado yori tatematuru mono-domo, haka-bakasiki sama no ha, mina kano Samdeu-no-Miya no mi-kura ni wosame sase tamahu. Mata mo, tate sohe sase tamahi te, sama-zama no ohom-takara mono-domo, Win no go-soubun ni kazu mo naku tamahari tamahe ru nado, anata zama no mono ha, mina kano Miya ni hakobi watasi, komaka ni ikamesiu si-oka se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 明け暮れの御かしづき、 そこらの女房のことども、上下の 育みは、おしなべてわが御扱ひにてなど、 急ぎ仕うまつらせたまひける。 |
日常のお世話、大勢の女房の事ども、上下の人々の面倒は、全てご自分の経費のまかないでなどと、急いでお手入れをして差し上げる。 |
これは永久に宮の御家を経済的に保証する価値ある財産というべきものである。そして六条院における宮の御生活とおおぜいの女房、男女の召使に要する費用は院の御負担とお決めになったのである。 |
Ake-kure no ohom-kasiduki, sokora no nyoubau no koto-domo, kami-simo no hagukumi ha, osinabete waga ohom-atukahi ni te nado, isogi tukau-matura se tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 1/18/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 3/10/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 1/18/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 10/5/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経