37 横笛(大島本) |
YOKOBUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 四十九歳春から秋までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from spring to fall, at the age of 49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 光る源氏の物語 薫の成長 |
1 Tale of Genji Kaoru's babyhood |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 柏木一周忌の法要 |
1-1 A Buddhist service for the late Kashiwagi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 故権大納言のはかなく亡せたまひにし悲しさを、飽かず口惜しきものに、恋ひしのびたまふ人多かり。六条の院にも、おほかたにつけてだに、世にめやすき人の亡くなるをば、惜しみたまふ御心に、まして、これは、朝夕に親しく参り馴れつつ、人よりも御心とどめ思したりしかば、 いかにぞやと、思し出づることはありながら ★、あはれは多く、 折々につけてしのびたまふ。 |
故権大納言があっけなくお亡くなりになった悲しさを、いつまでも残念なことに、恋い偲びなさる方々が多かった。六条院におかれても、特別の関係がなくてさえ、世間に人望のある人が亡くなるのは、惜しみなさるご性分なので、なおさらのこと、この人は、朝夕に親しくいつも参上しいしい、誰よりもお心を掛けていらしたので、どうにもけしからぬと、お思い出しなさることはありながら、哀悼の気持ちは強く、何かにつけてお思い出しになる。 |
|
Ko-Dainagon no hakanaku use tamahi ni si kanasisa wo, akazu kutiwosiki mono ni, kohi-sinobi tamahu hito ohokari. Rokudeu-no-Win ni mo, ohokata ni tuke te dani, yo ni meyasuki hito no nakunaru woba, wosimi tamahu mi-kokoro ni, masite, kore ha, asa-yuhu ni sitasiku mawiri nare tutu, hito yori mo mi-kokoro todome obosi tari sika ba, ikani zo ya to, obosi-iduru koto ha ari nagara, ahare ohoku, wori-wori ni tuke te sinobi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 御果てにも、誦経など、取り分きせさせたまふ。 よろづも知らず顔にいはけなき御ありさまを見たまふにも、さすがにいみじくあはれなれば、 御心のうちに、また心ざしたまうて、黄金百両をなむ別にせさせたまひける。 大臣は、心も知らでぞかしこまり喜びきこえさせたまふ。 |
ご一周忌にも、誦経などを、特別おさせになる。何事も知らない顔の幼い子のご様子を御覧になるにつけても、何といってもやはり不憫でならないので、内中密かに、また志立てられて、黄金百両を別にお布施あそばすのであった。父大臣は、事情も知らないで恐縮してお礼を申し上げさせなさる。 |
四十九日の法事の際にも御厚志の見える |
Ohom-hate ni mo, zyukyau nado, toriwaki se sase tamahu. Yorodu mo sira zu gaho ni ihakenaki mi-arisama wo mi tamahu ni mo, sasuga ni imiziku ahare nare ba, mi-kokoro no uti ni, mata kokorozasi tamau te, kogane hyaku-ryau wo nam beti ni se sase tamahi keru. Otodo ha, kokoro mo sira de zo kasikomari yorokobi kikoye sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 大将の君も、ことども多くしたまひ、とりもちてねむごろに営みたまふ。 かの一条の宮をも、このほどの御心ざし深く訪らひきこえたまふ。兄弟の君たちよりもまさりたる御心のほどを、いとかくは思ひきこえざりきと、大臣、上も、喜びきこえたまふ。亡き後にも、世のおぼえ重くものしたまひけるほどの見ゆるに、いみじうあたらしうのみ、思し焦がるること、尽きせず。 |
大将の君も、供養をたくさんなさり、ご自身も熱心に法要のお世話をなさる。あの一条宮に対しても、一周忌に当たってのお心遣いも深くお見舞い申し上げなさる。兄弟の君たちよりも優れたお気持ちのほどを、とてもこんなにまでとはお思い申さなかったと、大臣、母上もお喜び申し上げなさる。亡くなった後にも、世間の評判の高くていらっしゃったことが分かるので、ひどく残念がり、いつまでも恋い焦がれること、限りがない。 |
兄弟以上の親切を故人のために尽くす大将を大臣も夫人も、これほどまでの志があるとは思わなかったと喜んでいた。故人の持っていた勢力が法事の際にはなやかに現われたことなどからも両親はまた |
Daisyau-no-Kimi mo, koto-domo ohoku si tamahi, torimoti te nemgoro ni itonami tamahu. Kano Itideu-no-Miya wo mo, kono hodo no mi-kokorozasi hukaku toburahi kikoye tamahu. Harakara no Kimi-tati yori mo masari taru mi-kokoro no hodo wo, ito kaku ha omohi kikoye zari ki to, Otodo, Uhe mo, yorokobi kikoye tamahu. Naki ato ni mo, yo no oboye omoku monosi tamahi keru hodo no miyuru ni, imiziu atarasiu nomi, obosi-kogaruru koto, tuki se zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 朱雀院、女三の宮へ山菜を贈る |
1-2 Suzaku sends a letter and edible wild plants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 山の帝は、 二の宮も、かく人笑はれなるやうにて眺めたまふなり、入道の宮も、この世の人めかしきかたは、 かけ離れたまひぬれば、さまざまに飽かず思さるれど、 すべてこの世を思し悩まじ、と忍びたまふ。御行なひのほどにも、「 同じ道をこそは勤めたまふらめ」など思しやりて、かかるさまになりたまて後は、はかなきことにつけても、絶えず聞こえたまふ。 |
山の帝は、二の宮も、このように人に笑われるような境遇になって物思いに沈んでいらっしゃるといい、入道の宮も、現世の普通の人らしい幸せは、一切捨てておしまいになったので、どちらも物足りなくお思いなさるが、総じてこの世の事を悩むまい、と我慢なさる。御勤行をなさる時にも、「同じ道をお勤めになっているのだろう」などとお思いやりになって、このように尼になられてから後は、ちょっとしたことにつけても、絶えずお便りを差し上げなさる。 |
Yama-no-Mikado ha, Ni-no-Miya mo, kaku hito-waraha re naru yau ni te nagame tamahu nari, Nihudau-no-Miya mo, kono yo no hito-mekasiki kata ha, kake-hanare tamahi nure ba, sama-zama ni akazu obosa rure do, subete konoyo wo obosi nayama zi, to sinobi tamahu. Ohom-okonahi no hodo ni mo, "Onazi miti wo koso ha tutome tamahu rame." nado obosi-yari te, kakaru sama ni nari tama' te noti ha, hakanaki koto ni tuke te mo, tayezu kikoye tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 御寺のかたはら近き林に抜き出でたる筍、そのわたりの山に掘れる野老などの、山里につけてはあはれなれば、たてまつれたまふとて、御文こまやかなる端に、 |
お寺近くの林に生え出した筍、その近辺の山で掘った山芋などが、山里の生活では風情があるものなので、差し上げようとなさって、お手紙を情愛こまやかにお書きになった端に、 |
御寺に近い林から抜いた竹の子と、その辺の山で掘られた |
Mi-tera no katahara tikaki hayasi ni nuki-ide taru takauna, sono watari no yama ni hore ru tokoro nado no, yamazato ni tuke te ha ahare nare ba, tatemature tamahu tote, ohom-humi komayaka naru hasi ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 「 春の野山、霞もたどたどしけれど、 心ざし深く堀り出でさせてはべる しるしばかりになむ。 |
「春の野山は、霞がかかってはっきりしませんが、深い心をこめて掘り出させたものでございます。 |
春の野山は |
"Haru no noyama, kasumi mo tado-tadosikere do, kokorozasi hukaku hori-ide sase te haberu sirusi bakari ni nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | 世を別れ入りなむ道はおくるとも |
この世を捨ててお入りになった道はわたしより遅くとも |
世を別れ入りなん道は |
Yo wo wakare iri na m miti ha okuru to mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 同じところを君も尋ねよ |
同じ極楽浄土をあなたも求めて来て下さい |
同じところを君も尋ねよ |
onazi tokoro wo Kimi mo tadune yo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | いと難きわざになむある」 |
とても難しい事ですよ」 |
それを成就させるためには、より多く仏の |
Ito kataki waza ni nam aru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | と聞こえたまへるを、涙ぐみて見たまふほどに、大殿の君渡りたまへり。例ならず、御前近き 櫑子どもを、「 なぞ、あやし」と御覧ずるに、院の御文なりけり。見たまへば、いとあはれなり。 |
とお便り申し上げなさったのを、涙ぐんで御覧になっているところに、大殿の君がお越しになった。いつもと違って、御前近くに櫑子がいくつもあるので、「何だろう、おかしいな」と御覧になると、院からのお手紙なのであった。御覧になると、とても胸の詰まる思いがする。 |
法皇のお手紙を涙ぐみながら宮が読んでおいでになる所へ院がおいでになった。宮が平生に違って寂しそうに手紙を読んでおいでになり、漆器の |
to kikoye tamahe ru wo, namida-gumi te mi tamahu hodo ni, Otodo-no-Kimi watari tamahe ri. Rei nara zu, o-mahe tikaki raisi-domo wo, "Nazo, ayasi?" to go-ran-zuru ni, Win no ohom-humi nari keri. Mi tamahe ba, ito ahare nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | 「 今日か、明日かの心地するを、対面の心にかなはぬこと」 |
「わが命も今日か、明日かの心地がするのに、思うままにお会いすることができないのが辛いことです」 |
もう今日か明日かのように老衰をしていながら、逢うことが困難なのを飽き足らず思う |
"Kehu ka, asu ka no kokoti suru wo, taimen no kokoro ni kanaha nu koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | など、こまやかに書かせたまへり。この「同じところ」の御ともなひを、ことにをかしき節もなき。聖言葉なれど、「 げに、さぞ思すらむかし。 我さへおろかなるさまに見えたてまつりて、いとどうしろめたき御思ひの添ふべかめるを、 いといとほし」と思す。 |
などと、情愛こまやかにお書きあそばしていらっしゃった。この「同じ極楽浄土」へ御一緒にとのお歌を、特別に趣があるものではない、僧侶らしい言葉遣いであるが、「いかにも、そのようにお思いのことだろう。自分までが疎略にお世話しているというふうをお目に入れ申して、ますます御心配あそばされることになろうことを、おいたわしい」とお思いになる。 |
というような章もある。この同じ所へ来るようにとのお言葉は何でもない僧もよく言うことであるが、この作者は御実感そのままであろうとお思いになると、法皇はそのとおりに思召すであろう、寄託を受けた自分が不誠実者になったことでもお気づかわしさが倍加されておいでになるであろうのがおいたわしいと院はお思いになった。 |
nado, komayaka ni kaka se tamahe ri. Kono "Onazi tokoro" no ohom-tomonahi wo, koto ni wokasiki husi mo naki. Hiziri-kotoba nare do, "Geni, sa zo obosu ram kasi. Ware sahe oroka naru sama ni miye tatematuri te, itodo usirometaki ohom-omohi no sohu beka' meru wo, ito itohosi." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 御返りつつましげに書きたまひて、御使には、青鈍の綾 一襲賜ふ。書き変へたまへりける紙の、御几帳の側よりほの見ゆるを、取りて見たまへば、御手はいとはかなげにて、 |
お返事は恥ずかしげにお書きになって、お使いの者には、青鈍の綾を一襲をお与えなさる。書き変えなさった紙が、御几帳の端からちらっと見えるのを、取って御覧になると、ご筆跡はとても頼りない感じで、 |
宮はつつましやかにお返事をお書きになって、お使いへは |
Ohon-kaheri tutumasige ni kaki tamahi te, ohom-tukahi ni ha, awo-nibi no aya hito-kasane tamahu. Kaki-kahe tamahe ri keru kami no, mi-kityau no soba yori hono miyuru wo, tori te mi tamahe ba, ohom-te ha ito hakanage ni te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | 「 憂き世にはあらぬところのゆかしくて |
「こんな辛い世の中とは違う所に住みたくて |
うき世にはあらぬところのゆかしくて |
"Ukiyo ni ha ara nu tokoro no yukasiku te |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 背く山路に思ひこそ入れ」 |
わたしも父上と同じ山寺に入りとうございます」 |
|
somuku yamadi ni omohi koso ire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | 「 うしろめたげなる御けしきなるに、 このあらぬ所求めたまへる、 いとうたて、心憂し」 |
「ご心配なさっているご様子なのに、ここと違う住み処を求めていらっしゃる、まことに嫌な、辛いことです」 |
とある。「あなたを御心配していらっしゃる所へ、あらぬ山路へはいりたいようなことを言っておあげになっては悪いではありませんか」 |
"Usirometage naru mi-kesiki naru ni, kono ara nu tokoro motome tamahe ru, ito utate, kokoro-usi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.14 | と聞こえたまふ。 |
と申し上げなさる。 |
こう院はお言いになるのであった。 |
to kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.15 | 今は、まほにも見えたてまつりたまはず、いとうつくしうらうたげなる御額髪、面つきのをかしさ、ただ稚児のやうに見えたまひて、いみじうらうたきを見たてまつりたまふにつけては、「 など、かうはなりにしことぞ」と、 罪得ぬべく思さるれば、御几帳ばかり隔てて、またいとこよなう気遠く、疎々しうはあらぬほどに、もてなしきこえてぞおはしける。 |
今では、まともにお顔をお合わせ申されず、とても美しくかわいらしいお額髪、お顔の美しさ、まるで子供のようにお見えになって、たいそういじらしいのを拝見なさるにつけては、「どうして、このようになってしまったことか」と、罪悪感をお感じになるので、御几帳だけを隔てて、また一方でたいそう隔たった感じで、他人行儀にならない程度に、お扱い申し上げていらっしゃるのだった。 |
出家後は前にいても顔をなるべく見られぬようにと宮はしておいでになった。美しい額の髪、きれいな顔つきも、全く子供のように見えて非常に |
Ima ha, maho ni mo miye tatematuri tamaha zu, ito utukusiu rautage naru ohom-hitahi-gami, turatuki no wokasisa, tada tigo no yau ni miye tamahi te, imiziu rautaki wo mi tatematuri tamahu ni tuke te ha, "Nado, kau ha nari ni si koto zo?" to, tumi e nu beku obosa rure ba, mi-kityau bakari hedate te, mata ito koyonau ke-dohoku, uto-utosiu ha ara nu hodo ni, motenasi kikoye te zo ohasi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 若君、竹の子を噛る |
1-3 Kaoru bites a bamboo shoot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 若君は、乳母のもとに寝たまへりける、起きて這ひ出でたまひて、 御袖を引きまつはれたてまつりたまふさま、いとうつくし。 |
若君は、乳母のもとでお寝みになっていたが、起きて這い出しなさって、お袖を引っ張りまとわりついていらっしゃる様子、とてもかわいらしい。 |
若君は |
Waka-Gimi ha, Menoto no moto ni ne tamahe ri keru, oki te hahi-ide tamahi te, ohom-sode wo hiki-matuha re tatematuri tamahu sama, ito utukusi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 白き羅に、唐の小紋の紅梅の御衣の裾、いと長くしどけなげに引きやられて、御身はいとあらはにて、うしろの限りに着なしたまへるさまは、 例のことなれど、いとらうたげに白くそびやかに、柳を削りて作りたらむやうなり。 |
白い羅に、唐の小紋の紅梅のお召し物の裾、とても長くだらしなく引きずられて、お身体がすっかりあらわに見えて、後ろの方だけが着ていらっしゃる恰好は、幼児の常であるが、とてもかわいらしく色白ですんなりとして、柳の木を削って作ったようである。 |
白い |
Siroki usumono ni, Kara no ko-mon no koubai no ohom-zo no suso, ito nagaku sidokenage ni hiki-yara re te, ohom-mi ha ito araha ni te, usiro no kagiri ni ki-nasi tamahe ru sama ha, rei no koto nare do, ito rautage ni siroku sobiyaka ni, yanagi wo keduri te tukuri tara m yau nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 頭は露草してことさらに色どりたらむ心地して、口つきうつくしうにほひ、まみのびらかに、恥づかしう薫りたるなどは、なほいとよく思ひ出でらるれど、 |
頭は露草で特別に染めたような感じがして、口もとはかわいらしく艶々として、目もとがおっとりと、気がひけるほど美しいのなどは、やはりとてもよく思い出さずにはいられないが、 |
頭は露草の |
Kasira ha tuyu-kusa si te kotosara ni irodori tara m kokoti si te, kutituki utukusiu nihohi, mami nobiraka ni, hadukasiu kawori taru nado ha, naho ito yoku omohi-ide rarure do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 「 かれは、いとかやうに際離れたるきよらはなかりしものを、いかでかからむ。宮にも似たてまつらず、今より気高くものものしう、さま異に見えたまへるけしきなどは、わが御鏡の影にも 似げなからず」見なされたまふ。 |
「あの人は、とてもこのようにきわだった美しさはなかったが、どうしてこんなに美しいのだろう。母宮にもお似申さず、今から気品があり立派で、格別にお見えになる様子などは、自分が鏡に映った姿にも似てはいないこともないな」というお気持ちになる。 |
彼はこれほどまでにすぐれた |
"Kare ha, ito kayau ni kiha hanare taru kiyora ha nakari si mono wo, ikade kakara m? Miya ni mo ni tatematura zu, ima yori kedakaku mono-monosiu, sama koto ni miye tamahe ru kesiki nado ha, waga ohom-kagami no kage ni mo nigenakara zu." mi-nasa re tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | わづかに歩みなどしたまふほどなり。この筍の櫑子に、何とも知らず立ち寄りて、いとあわたたしう取り散らして、食ひかなぐりなどしたまへば、 |
やっとよちよち歩きをなさる程である。この筍が櫑子に、何であるのか分からず近寄って来て、やたらにとり散らかして、食いかじったりなどなさるので、 |
立っても二足三足踏み出すほどになっているのである。この竹の子の置かれた |
Waduka ni ayumi nado si tamahu hodo nari. Kono takauna no raisi ni, nani to mo sira zu tatiyori te, ito awatatasiu tori-tirasi te, kuhi kanaguri nado si tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 「 あな、らうがはしや。いと 不便なり。かれ取り隠せ。食ひ物に目とどめたまふと、もの言ひさがなき女房もこそ言ひなせ」 |
「まあ、お行儀の悪い。いけません。あれを片づけなさい。食べ物に目がなくていらっしゃると、口の悪い女房が言うといけない」 |
「行儀が悪いね。いけない。あれをどちらへか隠させるといい。食い物に目をつけると言って、口の悪い女房は黙っていませんよ」 |
"Ana, raugahasi ya! Ito hu-bin nari. Kare tori-kakuse. Kuhi-mono ni me todome tamahu to, mono-ihi saganaki nyoubau mo koso ihi-nase." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | とて、笑ひたまふ。かき抱きたまひて、 |
と言って、お笑いになる。お抱き寄せになって、 |
とお笑いになる。若君を御自身の |
tote, warahi tamahu. Kaki-idaki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.8 | 「 この君のまみの いとけしきあるかな。小さきほどの稚児を、あまた見ねばにやあらむ、かばかりのほどは、ただいはけなきものとのみ見しを、 今よりいとけはひ異なるこそ、わづらはしけれ。 女宮ものしたまふめるあたりに、かかる人生ひ出でて、心苦しきこと、誰がためにもありなむかし ★。 |
「若君の目もとは普通と違うな。小さい時の子を、多く見ていないからだろうか、これくらいの時は、ただあどけないものとばかり思っていたが、今からとても格別すぐれているのが、厄介なことだ。女宮がいらっしゃるようなところに、このような人が生まれて来て、厄介なことが、どちらにとっても起こるだろうな。 |
「この子の |
"Kono Kimi no mami no ito kesiki aru kana! Tihisaki hodo no tigo wo, amata mi ne ba ni ya ara m, kabakari no hodo ha, tada ihakenaki mono to nomi mi si wo, ima yori ito kehahi koto naru koso, wadurahasikere. Womna-Miya monosi tamahu meru atari ni, kakaru hito ohi-ide te, kokoro-gurusiki koto, taga tame ni mo ari na m kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.9 | あはれ、そのおのおのの生ひゆく末までは、 見果てむとすらむやは。 ▼ 花の盛りは、ありなめど」 |
ああ、この人たちが育って行く先までは、見届けることができようか。花の盛りにめぐり逢うことは、寿命あってのことだ」 |
しかし皆のその遠い将来は私の見ることのできないものなのだ。『花の盛りはありなめど』(逢ひ見んことは命なりけり)だね」 |
Ahare, sono ono-ono no ohi-yuku suwe made ha, mi-hate m to su ram yaha! Hana no sakari ha, ari na me do." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.10 | と、うちまもりきこえたまふ。 |
と言って、じっとお見つめ申していらっしゃる。 |
こうお言いになって若君の顔を見守っておいでになった。 |
to, uti-mamori kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.11 | 「 うたて、ゆゆしき御ことにも」 |
「何とまあ、縁起でもないお言葉を」 |
「縁起のよろしくございませんことを、まあ」 |
"Utate, yuyusiki ohom-koto ni mo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.12 | と、人びとは聞こゆ。 |
と、女房たちは申し上げる。 |
と女房たちは言っていた。 |
to, hito-bito ha kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
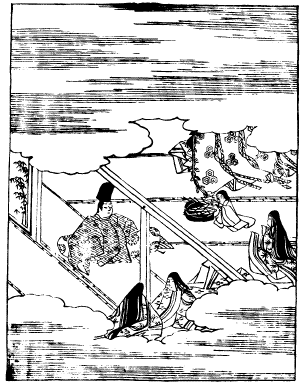 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.13 | 御歯の生ひ出づるに食ひ当てむとて、筍をつと握り待ちて、雫もよよと食ひ濡らしたまへば、 |
歯の生えかけたところに噛み当てようとして、筍をしっかりと握り持って、よだれをたらたらと垂らしてお齧りになっているので、 |
若君は歯茎から出始めてむずがゆい気のする歯で物が |
Ohom-ha no ohi-iduru ni kuhi-ate m tote, takauna wo tuto nigiri moti te, siduku mo yoyo to kuhi nurasi tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.14 | 「 いとねぢけたる色好みかな」とて、 |
「変わった色好みだな」とおっしゃって、 |
「変わった風流男だね」と院は |
"Ito nedike taru iro-gonomi kana!" tote, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.15 | 「 憂き節も忘れずながら呉竹の |
「いやなことは忘れられないがこの子は |
|
"Uki husi mo wasure zu nagara kuretake no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.16 | こは捨て難きものにぞありける」 |
かわいくて捨て難く思われることだ」 |
子は捨てがたき物にぞありける |
ko ha sute gataki mono ni zo ari keru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.17 | と、率て放ちて、のたまひかくれど、うち笑ひて、何とも思ひたらず、いとそそかしう、這ひ下り騷ぎたまふ。 |
と、引き離して連れて来て、お話しかけになるが、にこにことしていて、何とも分からず、とてもそそくさと、這い下りて動き回っていらっしゃる。 |
こんなことをお言いかけになるが、若君は笑っているだけで何のことであるとも知らない。そそくさと院のお |
to, wi te hanati te, notamahi-kakure do, uti-warahi te, nani to mo omohi tara zu, ito sosokasiu, hahi-ori sawagi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.18 | 月日に添へて、この君のうつくしうゆゆしきまで生ひまさりたまふに、まことに、 この憂き節、皆思し忘れぬべし。 |
月日が経つにつれて、この君がかわいらしく不吉なまでに美しく成長なさっていくので、本当に、あの嫌なことが、すべて忘れられてしまいそうである。 |
月日に添って顔のかわいくなっていくこの人に院は愛をお感じになって、過去の不祥事など忘れておしまいになりそうである。 |
Tukihi ni sohe te, kono Kimi no utukusiu yuyusiki made ohi masari tamahu ni, makoto ni, kono uki husi, mina obosi wasure nu besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.19 | 「 この人の出でものしたまふべき契りにて、さる思ひの外の事もあるにこそはありけめ。逃れ難かなるわざぞかし」 |
「この人がお生まれになるためのご縁で、あの思いがけない事件も起こったのだろう。逃れられない宿命だったのだ」 |
この愛すべき子を自分が得る因縁の過程として意外なことも起こったのであろう。すべて前生の約束事なのであろうと |
"Kono Hito no ide monosi tamahu beki tigiri ni te, saru omohi no hoka no koto mo aru ni koso ha ari keme. Nogare gataka' naru waza zo kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.20 | と、すこしは思し直さる。 みづからの御宿世も、なほ飽かぬこと多かり。 |
と、少しはお考えが改まる。ご自身の運命にもやはり不満のところが多かった。 |
ことに少しの慰めが見いだされた。自分の宿命というものも必ずしも完全なものではなかった。 |
to, sukosi ha obosi-nahosa ru. Midukara no ohom-sukuse mo, naho akanu koto ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.21 | 「 あまた集へたまへる中にも、この宮こそは、かたほなる思ひまじらず、人の御ありさまも、思ふに飽かぬところなくてものしたまふべきを、かく思はざりしさまにて見たてまつること」 |
「大勢集っていらっしゃるご夫人方の中でも、この宮だけは、不足に思うところもなく、宮ご自身のご様子も、物足りないと思うところもなくていらっしゃるはずなのに、このように思いもかけない尼姿で拝見するとは」 |
幾人かの |
"Amata tudohe tamahe ru naka ni mo, kono Miya koso ha, kataho naru omohi mazira zu, hito no mi-arisama mo, omohu ni akanu tokoro naku te monosi tamahu beki wo, kaku omoha zari si sama ni te mi tatematuru koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.22 | と思すにつけてなむ、 過ぎにし罪許し難く、なほ口惜しかりける。 |
とお思いになるにつけて、過去の二人の過ちを許し難く、今も無念に思われるのであった。 |
とお思いになると、今もなお誘惑にたやすく負けておしまいになった宮がお恨めしかった。 |
to obosu ni tuke te nam, sugi ni si tumi yurusi gataku, naho kutiwosikari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/4/2003 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 1/18/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 1/18/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 10/4/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経