35 若菜下(明融臨模本) |
WAKANA-NO-GE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 四十一歳三月から四十七歳十二月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from Mar. of 41 to Dec. the age of 47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 第八章 紫の上の物語 死と蘇生 |
8 Tale of Murasaki Death and revival |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 第一段 紫の上、絶命す |
8-1 A messenger said Genji that Murasaki died |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.1 | 大殿の君は、まれまれ渡りたまひて、えふとも立ち帰りたまはず、静心なく思さるるに、 |
大殿の君は、たまたまお渡りになって、すぐにはお帰りになることもできず、落ち着いていらっしゃれないところに、 |
院はまれにお |
Otodo-no-Kimi ha, mare-mare watari tamahi te, e huto mo tati-kaheri tamaha zu, sidu-kokoro naku obosa ruru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.2 | 「 絶え入りたまひぬ」 |
「息をお引きとりになりました」 |
急に息が絶えたと知らせた。 |
"Taye-iri tamahi nu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.3 | とて、人参りたれば、さらに何事も思し分かれず、御心も暮れて渡りたまふ。道のほどの心もとなきに、げにかの院は、ほとりの大路まで人立ち騒ぎたり。殿のうち泣きののしるけはひ、いとまがまがし。我にもあらで入りたまへれば、 |
と言って、使者が参上したので、まったく何を考えることもおできになれず、お心も真暗になってお帰りになる。その道中気が気でないところ、なるほどあちらの院は、周囲の大路まで人が騷ぎ立っていた。邸の中の泣きわめいている様子、まことに不吉である。無我夢中で中にお入りになると、 |
院はいっさいの世界が暗くなったようなお気持ちで二条の院へ帰ってお行きになるのであったが、車の速度さえもどかしく思っておいでになると、二条の院に近い大路はもう立ち騒ぐ人で満たされていた。邸内からは泣き声が多く聞こえて、大きな不祥事のあることは |
tote, hito mawiri tare ba, sarani nani-goto mo obosi waka re zu, mi-kokoro mo kure te watari tamahu. Miti no hodo no kokoro-motonaki ni, geni kano Win ha, hotori no oho-di made hito tati-sawagi tari. Tono no uti-naki nonosiru kehahi, ito maga-magasi. Ware ni mo ara de iri tamahe re ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.4 | 「 日ごろは、いささか隙見えたまへるを、にはかになむ、かくおはします」 |
「ここのところ数日は、少しよろしいようにお見えになったのですが、急に、このようにおなりになりました」 |
「この二、三日は少しお快いようでございましたのに、にわかに絶息をあそばしたのでございます」 |
"Higoro ha, isasaka hima miye tamahe ru wo, nihaka ni nam, kaku ohasimasu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.5 | とて、さぶらふ限りは、我も後れたてまつらじと、惑ふさまども、限りなし。御修法どもの檀こぼち、僧なども、 さるべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを見たまふに、「さらば限りにこそは」と思し果つるあさましさに、何事かはたぐひあらむ。 |
と言って、控えている女房たちは皆、自分も後を追おうと、うろうろしている者たちが、数限りない。いく壇もの御修法の壇を壊して、僧たちも残るべき人は残っているが、ばらばらと立ち騒ぐのを御覧になると、「それではもう最期なのだ」とお思い切りなさるその情けなさに、他にどのような比べるものがあろうか。 |
こんな報告をした女房らが、自分たちも、いっしょに死なせてほしいと泣きむせぶ様子も悲しかった。もう |
tote, saburahu kagiri ha, ware mo okure tatematura zi to, madohu sama-domo, kagirinasi. Mi-syuhohu-domo no dan koboti, sou nado mo, saru-beki kagiri koso makade ne, horo-horo to sawagu wo mi tamahu ni, "Sara ba kagiri ni koso ha." to obosi haturu asamasisa ni, nani-goto ka ha taguhi ara m? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.6 | 「 さりとも、もののけのするにこそあらめ。いと、かくひたぶるにな騷ぎそ」 |
「そうは言っても、物の怪のすることであろう。まことに、そんなにむやみに騒ぐな」 |
「しかしこれは |
"Saritomo, mononoke no suru ni koso ara me. Ito, kaku hitaburu ni na sawagi so." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.7 | と鎮めたまひて、いよいよいみじき願どもを立て添へさせたまふ。すぐれたる験者どもの限り召し集めて、 |
と皆をお静めになって、ますます大層ないくつもの願をお立て加えさせなさる。すぐれた験者たちをすべて召し集めて、 |
と院は泣く女房たちを制して、またまた幾つかの大願をお立てになった。そしてすぐれた修験の僧をお集めになり、 |
to sidume tamahi te, iyo-iyo imiziki gwan-domo wo tate-sohe sase tamahu. Sugure taru genzya-domo no kagiri mesi-atume te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.8 | 「 限りある御命にて、この世尽きたまひぬとも、ただ、今しばしのどめたまへ。 不動尊の御本の誓ひあり。その日数をだに、かけ止めたてまつりたまへ」 |
「有限なご寿命であるから、この世でのご寿命が終わったとしても、ただ、もう暫く延ばして下さい。不動尊の御本の誓いがあります。せめてその日数だけでも、この世にお引き止め申して下さい」 |
「これが |
"Kagiri aru ohom-inoti ni te, konoyo tuki tamahi nu to mo, tada, ima sibasi nodome tamahe. Hudouson no ohom-moto no tikahi ari. Sono hi-kazu wo dani, kake-todome tatematuri tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.9 | と、頭よりまことに黒煙を立てて、いみじき心を起こして加持したてまつる。院も、 |
と、頭から本当に黒い煙を立てて、大変な熱心さでご加持申し上げる。院も、 |
こう僧たちは言って、頭から黒煙を立てると言われるとおりの熱誠をこめて祈っていた。院も |
to, kasira yori makoto ni kuro-keburi wo tate te, imiziki kokoro wo okosi te kadi si tatematuru. Win mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.10 | 「 ただ、今一度目を見合はせたまへ。いとあへなく限りなりつらむほどをだに、え見ずなりにけることの、悔しく悲しきを」 |
「ただ、もう一度目と目を見合わせて下さい。まったくあっけなく臨終の時をさえ、会わずじまいであったことが、悔しく悲しいのですよ」 |
互いにただ一目だけ見合わす瞬間が与えられたい、最後の時に見合わせることのできなかった |
"Tada, ima hito-tabi me wo mi-ahase tamahe. Ito ahenaku kagiri nari tu ram hodo wo dani, e mi zu nari ni keru koto no, kuyasiku kanasiki wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.11 | と思し惑へるさま、止まりたまふべきにもあらぬを、 見たてまつる心地ども、 ただ推し量るべし。いみじき御心のうちを、 仏も見たてまつりたまふにや、月ごろさらに現はれ出で来ぬもののけ、小さき童女に移りて、呼ばひののしるほどに、やうやう生き出でたまふに、うれしくもゆゆしくも 思し騒がる。 |
と取り乱している様子は、生き残っていらっしゃることができそうにないのを、拝見する心地は、ただ想像できよう。大変なご悲痛を、仏も御照覧申されたのであろうか、このいく月もまったく現れなかった物の怪が小さい童に乗り移って、大声でわめくうちに、だんだんと生き返っていらっしゃって、嬉しくも不吉にもお心が騒がずにはいらっしゃれない。 |
残念さ悲しさから長く救われたいと言ってお |
to obosi madohe ru sama, tomari tamahu beki ni mo ara nu wo, mi tatematuru kokoti-domo, tada osihakaru besi. Imiziki mi-kokoro no uti wo, Hotoke mo mi tatematuri tamahu ni ya, tuki-goro sarani arahare ide ko nu mononoke, tihisaki waraha ni uturi te, yobahi nonosiru hodo ni, yau-yau iki-ide tamahu ni, uresiku mo yuyusiku mo obosi sawaga ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | 第二段 六条御息所の死霊出現 |
8-2 A gohst of Rokujo-Miyasumdokoro appears in front of Genji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.1 | いみじく調ぜられて、 |
ひどく調伏されて、 |
物怪は僧たちにおさえられながら言う、 |
Imiziku teu-ze rare te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.2 | 「 人は皆去りね。院一所の御耳に聞こえむ。おのれを月ごろ調じわびさせたまふが、情けなくつらければ、 同じくは思し知らせむと思ひつれど、さすがに 命も堪ふまじく、身を砕きて思し惑ふを見たてまつれば、 今こそ、かくいみじき身を受けたれ、 いにしへの心の残りてこそ、かくまでも参り来たるなれば、ものの心苦しさをえ見過ぐさで、つひに現はれぬること。さらに知られじと思ひつるものを」 |
「他の人は皆去りなさい。院お一人方のお耳に申し上げたい。自分をこのいく月も調伏し困らせなさるのが薄情で辛いので、同じことならお知らせしようと思ったが、そうは言っても命が耐えられないほど、身を粉にして悲嘆に暮れていらっしゃるご様子を拝見すると、今でこそ、このようなあさましい姿に変わっているが、昔の愛執が残っていればこそ、このように参上したので、お気の毒な様子を放って置くことができなくて、とうとう現れ出てしまったのです。決して知られまいと思っていたのに」 |
「皆ここから遠慮をするがよい。院お一人のお耳へ申し上げたいことがある。私の霊を長く法力で苦しめておいでになったのが無情な恨めしいことですから、懲らしめを見せようと思いましたが、さすがに御自身の命も危険なことになるまで悲しまれるのを見ては、今こそ私は物怪であっても、昔の恋が残っているために出て来る私なのですから、あなたの悲しみは見過ごせないで姿を現わしました。私は姿など見せたくなかったのだけれど」 |
"Hito ha mina sari ne. Win hito-tokoro no ohom-mimi ni kikoye m. Onore wo, tuki-goro teu-zi wabi sase tamahu ga, nasakenaku turakere ba, onaziku ha obosi-sira se m to omohi ture do, sasuga ni inoti mo tahu maziku, mi wo kudaki te obosi-madohu wo mi tatemature ba, ima koso, kaku imiziki mi wo uke tare, inisihe no kokoro no nokori te koso, kaku made mo mawiri ki taru nare ba, mono no kokoro-gurusisa wo e mi-sugusa de, tuhi ni arahare nuru koto. Sarani sira re zi to omohi turu mono wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
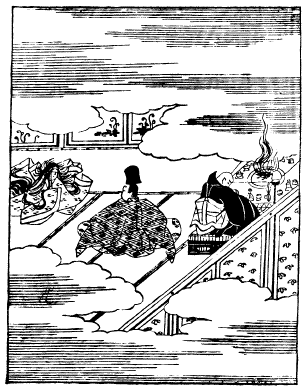 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.3 | とて、髪を振りかけて泣くけはひ、ただ 昔見たまひしもののけのさまと見えたり。あさましく、むくつけしと、思ししみにしことの変はらぬもゆゆしければ、この童女の手をとらへて、引き据ゑて、さま悪しくもせさせたまはず。 |
と言って、髪を振り掛けて泣く様子は、まったく昔御覧になった物の怪の恰好と見えた。こんなことがこの世にあろうか、恐ろしいことだと、心底お思い込みになったことが相変わらず忌まわしいことなので、この童女の手を捉えて、じっとさせて、体裁の悪いようにはおさせにならない。 |
と物怪は叫んだ。髪を顔に振りかけて泣く様子は、昔一度御覧になった覚えのある物怪であった。その当時と同じ無気味さがお心に |
tote, kami wo huri-kake te naku kehahi, tada mukasi mi tamahi si mononoke no sama to miye tari. Asamasiku, mukutukesi to, obosi-simi ni si koto no kahara nu mo yuyusikere ba, kono waraha no te wo torahe te, hiki-suwe te, sama asiku mo se sase tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.4 | 「 まことにその人か。よからぬ狐などいふなるものの、 たぶれたるが、亡き人の面伏なること言ひ出づるもあなるを、たしかなる名のりせよ。また人の知らざらむことの、心にしるく思ひ出でられぬべからむを言へ。さてなむ、いささかにても信ずべき」 |
「本当にあなたか。良くない狐などと言うもので、気の狂ったのが、亡くなった人の不名誉になることを言い出すということもあると言うから、はっきりと名乗りをせよ。また誰も知らないようなことで、心にはっきりと思い出されるようなことを言いなさい。そうすれば、少しは信じもしよう」 |
「ほんとうにその人なのか。悪い |
"Makoto ni sono hito ka? Yokara nu kitune nado ihu naru mono no, tabure taru ga, naki hito no omote-buse naru koto ihi-iduru mo a' naru wo, tasika naru nanori se yo. Mata hito no sira zara m koto no, kokoro ni siruku omohi-ide rare nu bekara m wo ihe. Sate nam, isasaka ni te mo sin-zu beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.5 | とのたまへば、ほろほろといたく泣きて、 |
とおっしゃると、ぽろぽろとひどく泣いて、 |
院がこうお言いになると、物怪はほろほろと涙を流しながら、悲しそうに泣いた。 |
to notamahe ba, horo-horo to itaku naki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.6 | 「 わが身こそあらぬさまなれそれながら |
「わたしはこんな変わりはてた身の上となってしまったが |
「わが身こそあらぬさまなれそれながら |
"Waga mi koso ara nu sama nare sore nagara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.7 | そらおぼれする君は君なり |
知らないふりをするあなたは昔のままですね |
空おぼれする君は君なり |
soraobore suru Kimi ha Kimi nari |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.8 | いとつらし、いとつらし」 |
とてもひどい方だわ、とてもひどい方だわ」 |
恨めしい、恨めしい」 |
ito turasi, ito turasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.9 | と泣き叫ぶものから、さすがにもの恥ぢしたるけはひ、変らず、なかなかいと 疎ましく、心憂けば、もの言はせじと思す。 |
と泣き叫ぶ一方で、そうはいっても恥ずかしがっている様子、昔に変わらず、かえってまことに疎ましい気がし、情けないので、何も言わせまいとお思いになる。 |
と泣き叫びながらもさすがに |
to naki-sakebu monokara, sasuga ni mono-hadi si taru kehahi, kahara zu, naka-naka ito utomasiku, kokoro-ukere ba, mono iha se zi to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.10 | 「 中宮の御事にても、いとうれしくかたじけなしとなむ、天翔りても見たてまつれど、道異になりぬれば、子の上までも深くおぼえぬにやあらむ、なほ、 みづからつらしと思ひきこえし心の執なむ、止まるものなりける。 |
「中宮の御事につけても、大変に嬉しく有り難いことだと、魂が天翔りながら拝見していますが、明幽境を異にしてしまったので、子の身の上までも深く思われないのでしょうか、やはり、自分自身がひどい方だとお思い申し上げた方への愛執が残るのでした。 |
「 |
"Tyuuguu no ohom-koto ni te mo, ito uresiku katazikenasi to nam, amagakeri te mo mi tatemature do, miti koto ni nari nure ba, ko no uhe made mo hukaku oboye nu ni ya ara m, naho, midukara turasi to omohi kikoye si kokoro-no-sihu nam, tomaru mono nari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.11 | その中にも、生きての世に、 人より落として思し捨てしよりも、 思ふどちの御物語のついでに ★、 心善からず憎かりしありさまをのたまひ出でたりしなむ、いと恨めしく。今はただ亡きに思し許して、異人の言ひ落としめむをだに、はぶき隠したまへとこそ思へ、とうち思ひしばかりに、かくいみじき身のけはひなれば、 かく所狭きなり。 |
その中でも、生きているうちに、人より軽いお扱いをなさってお見捨てになったことよりも、お親しい者どうしのお話の時に、性格が善くない扱いにくい女であったとおっしゃったのが、まことに恨めしくて。今はもう亡くなってしまったのだからとお許し下さって、他人が悪口を言うのでさえ、打ち消してかばって戴きたいと思うと、その思っただけで、このように恐ろしい身の上なので、このように大変なことになったのです。 |
その恨みの中でも、生きていますころにほかの人よりも軽くお扱いになったことよりも、夫婦のお話の中で私を悪くお言いになったことが私をくやしくさせました。もう私は死んでいるのですから、私が悪くってもあなたはよくとりなして言ってくだすっていいではありませんか。そうお恨みしただけで、こんな身になっていますと |
Sono naka ni mo, iki te no yo ni, hito yori otosi te obosi-sute si yori mo, omohu-doti no ohom-monogatari no tuide ni, kokoro yokara zu nikukari si arisama wo notamahi-ide tari si nam, ito uramesiku. Ima ha tada naki ni obosi yurusi te, koto-bito no ihi-otosime m wo dani, habuki kakusi tamahe to koso omohe, to uti omohi si bakari ni, kaku imiziki mi no kehahi nare ba, kaku tokoro-seki nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.12 | この人を、深く憎しと思ひきこゆることはなけれど、 守り強く、いと御あたり遠き心地して、え近づき参らず、御声をだにほのかに なむ聞きはべる。 |
この方を、心底憎いと思い申すことはないが、あなたの神仏の加護が強くて、とてもご身辺は遠い感じがして、近づき参ることができず、お声さえもかすかに聞くだけでおります。 |
奥様を深く恨んでいませんが、法の |
Kono hito wo, hukaku nikusi to omohi kikoyuru koto ha nakere do, mamori tuyoku, ito ohom-atari tohoki kokoti si te, e tikaduki mawira zu, ohom-kowe wo dani honoka ni nam kiki haberu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.13 | よし、今は、この罪軽むばかりのわざをせさせたまへ。修法、読経とののしることも、身には苦しくわびしき炎とのみまつはれて、さらに尊きことも聞こえねば、いと悲しくなむ。 |
よし、今はもう、この罪障を軽めることをなさって下さい。修法や読経の大声を立てることも、わが身には苦しく情けない炎となってまつわりつくばかりで、まったく尊いお経の声も聞こえないので、まことに悲しい気がします。 |
私の罪の軽くなるような方法を講じてください。修法、 |
Yosi, ima ha, kono tumi karomu bakari no waza wo se sase tamahe. Syuhohu, dokyau to nonosiru koto mo, mi ni ha kurusiku wabisiki honoho to nomi matuha re te, sarani tahutoki koto mo kikoye ne ba, ito kanasiku nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.14 | 中宮にも、このよしを伝へ聞こえたまへ。ゆめ御宮仕へのほどに、人ときしろひ嫉む心つかひたまふな。斎宮におはしまししころほひの御罪軽むべからむ功徳のことを、かならずせさせたまへ。 いと悔しきことになむありける」 |
中宮にも、この旨をお伝え申し上げて下さい。決して御宮仕え中に、他人と争ったり嫉妬したりする気をお持ちになってなりません。斎宮でいらっしゃったころのご罪障を軽くするような功徳のことを、必ずなさるように。ほんとうに残念なことでしたよ」 |
中宮にもこのことをお話しくださいませ。後宮の生活をするうちに人を |
Tyuuguu ni mo, kono yosi wo tutahe kikoye tamahe. Yume ohom-miyadukahe no hodo ni, hito to kisirohi sonemu kokoro tukahi tamahu na. Saiguu ni ohasimasi si korohohi no ohom-tumi karumu bekara m kudoku no koto wo, kanara zu se sase tamahe. Ito kuyasiki koto ni nam ari keru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2.15 | など、言ひ続くれど、もののけに向かひて物語したまはむも、かたはらいたければ、封じ込めて、上をば、また異方に、忍びて渡したてまつりたまふ。 |
などと、言い続けるが、物の怪に向かってお話なさることも、気が引けることなので、物の怪を封じ込めて、紫の上を、別の部屋に、こっそりお移し申し上げなさる。 |
などと言うが、物怪に向かってお話しになることもきまり悪くお思いになって、物怪がまた出ぬように法の力で封じこめておいて、病夫人を他の室へお移しになった。 |
nado, ihi-tudukure do, mononoke ni mukahi te monogatari si tamaha m mo, kataharaitakere ba, hun-zi-kome te, Uhe wo ba, mata koto-kata ni sinobi te watasi tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 第三段 紫の上、死去の噂流れる |
8-3 The rumor that Murasaki died has spread the whole streets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.1 | かく亡せたまひにけりといふこと、世の中に満ちて、御弔らひに聞こえたまふ人々あるを、いとゆゆしく思す。 今日の帰さ見に出でたまひける上達部など、帰りたまふ道に、かく人の申せば、 |
このようにお亡くなりになったという噂が、世間に広がって、ご弔問に参上なさる方々がいるのを、まことに縁起でもなくお思いになる。今日の祭の翌日の行列の見物にお出かけになった上達部などは、お帰りになる道すがら、このように人が申すので、 |
紫夫人が死んだという |
Kaku use tamahi ni keri to ihu koto, yononaka ni miti te, ohom-toburahi ni kikoye tamahu hito-bito aru wo, ito yuyusiku obosu. Kehu no kahesa mi ni ide tamahi keru Kamdatime nado, kaheri tamahu miti ni, kaku hito no mause ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.2 | 「 いといみじき ★ことにもあるかな。生けるかひありつる幸ひ人の、光失ふ日にて、雨は そほ降るなりけり」 |
「大変な事になったな。この世の生甲斐を満喫した幸福な方が、光を失う日なので、雨がしょぼしょぼ降るのだな」 |
「たいへんなことだ。生きがいのあった幸福な女性が光を隠される日だから小雨も降り出したのだ」 |
"Ito imiziki koto ni mo aru kana! Ike ru kahi ari turu saihahi-bito no, hikari usinahu hi ni te, ame ha soho-huru nari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.3 | と、うちつけ言したまふ人もあり。また、 |
と、思いつきの発言をなさる方もいる。また、 |
などと解釈を下す人もあった。また、 |
to, utitukegoto si tamahu hito mo ari. Mata, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.4 | 「 かく足らひぬる人は、かならずえ長からぬことなり。『 ▼ 何を桜に』といふ古言もあるは。かかる人の、いとど世にながらへて、世の楽しびを尽くさば、かたはらの人苦しからむ。 今こそ、二品の宮は、もとの御おぼえ現はれたまはめ。いとほしげに圧されたりつる御おぼえを」 |
「このようにすべてに満ち足りた方は、必ず寿命も長くはないことです。『何を桜に』と言う古歌もあることよ。このような方が、ますます世に長生きをして、この世の楽しみの限りを尽くしたら、はたの人が迷惑するだろう。これでやっと、二品の宮は、本来のご寵愛をお受けになられることだろう。お気の毒に圧倒されていたご寵愛であったから」 |
「あまりに何もかもそろった人というものは短命なものなのだ。『何をさくらに』(待てといふに散らでしとまるものならば何を桜に思ひまさまし)という歌のように、そうした人が長生きしておれば、一方で不幸に甘んじていなければならぬ人も多くできるわけだ。二品の宮が院の御 |
"Kaku tarahi nuru hito ha, kanarazu e nagakara nu koto nari. Nani wo sakura ni to ihu hurukoto mo aru ha! Kakaru hito no, itodo yo ni nagarahe te, yo no tanosibi wo tukusa ba, katahara no hito kurusikara m. Ima koso, Nihon-no-Miya ha, moto no ohom-oboye arahare tamaha me. Itohosige ni osa re tari turu ohom-oboye wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.5 | など、うちささめきけり。 |
などと、ひそひそ噂するのであった。 |
などとも言う人があった。 |
nado, uti-sasameki keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.6 | 衛門督、 昨日暮らしがたかりしを思ひて、今日は、御弟ども、左大弁、藤宰相など、奥の方に乗せて見たまひけり。 かく言ひあへるを聞くにも、胸うちつぶれて、 |
衛門督は、昨日一日とても過ごしにくかったことを思って、今日は、弟の方々の、左大弁、藤宰相など、車の奥の方に乗せて見物なさった。このように噂しあっているのを聞くにつけても、胸がどきっとして、 |
|
Wemon-no-Kami, kinohu kurasi gatakari si wo omohi te, kehu ha, ohom-otouto-domo, Sa-Daiben, Tou-Saisyau nado, oku no kata ni nose te mi tamahi keri. Kaku ihi-ahe ru wo kiku ni mo, mune uti-tubure te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.7 | 「 ▼ 何か憂き世に久しかるべき」 |
「どうして嫌な世の中に長生きしようか」 |
「散ればこそいとど桜はめでたけれ」(何か浮き世に久しかるべき) |
"Nanika uki yo ni hisasikaru beki" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.8 | と、うち誦じ独りごちて、かの院へ皆参りたまふ。たしかならぬことなればゆゆしくや、とて、ただおほかたの御訪らひに参りたまへるに、かく人の泣き騒げば、まことなりけりと、立ち騷ぎたまへり。 |
と、独り口ずさんで、あちらの院に皆で参上なさる。不確かなことなので縁起でもないことを言っては、と思って、ただ普通のお見舞いの形で参上したところ、このように人が泣き叫んでいるので、本当だったのだなと、驚きなさった。 |
などとも口ずさみながら同車の人々とともに二条の院へ参った。まだ確かでないことであるから、形式を病気見舞いにして行ったのであるが、女房の泣き騒いでいる時であったから、真実であったかとさらに驚かれた。 |
to, uti-zyu-zi hitorigoti te, kano Win he mina mawiri tamahu. Tasika nara nu koto nare ba yuyusiku ya, tote, tada ohokata no ohom-toburahi ni mawiri tamahe ru ni, kaku hito no naki sawage ba, makoto nari keri to, tati-sawagi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.9 | 式部卿宮も渡りたまひて、いといたく思しほれたるさまにてぞ入りたまふ。人の御消息も、え申し伝へたまはず。大将の君、涙を拭ひて立ち出でたまへるに、 |
式部卿宮もお越しになって、とてもひどくご悲嘆なさった様子でお入りになる。一般の方々のご弔問も、お伝え申し上げることがおできになれない。大将の君が、涙を拭って出ていらっしゃったので、 |
ちょうど式部卿の宮がお |
Sikibukyau-no-Miya mo watari tamahi te, ito itaku obosi-hore taru sama ni te zo iri tamahu. Hito no ohom-seusoko mo, e mausi tutahe tamaha zu. Daisyau-no-kimi, namida nogohi te tati-ide tamahe ru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.10 | 「 いかに、いかに。ゆゆしきさまに人の申しつれば、信じがたきことにてなむ。ただ久しき御悩みをうけたまはり嘆ぎて参りつる」 |
「いかがですか、いかがですか。縁起でもないふうに皆が申しましたので、信じがたいことです。ただ長い間のご病気と承って嘆いて参上しました」 |
「どんなふうでいらっしゃるのですか。不吉なことを言う人があるのを私たちは信じることができないで伺ったのです。ただ長い御疾患を御心配申し上げて参ったのです」 |
"Ikani, ikani? Yuyusiki sama ni hito no mausi ture ba, sin-zi-gataki koto ni te nam. Tada hisasiki ohom-nayami wo uketamahari nageki te mawiri turu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.11 | などのたまふ。 |
などとおっしゃる。 |
などと衛門督は言った。 |
nado notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.12 | 「 いと重くなりて、月日経たまへるを、この暁より絶え入りたまへりつるを、もののけのしたるになむありける。やうやう生き出でたまふやうに聞きなしはべりて、今なむ皆人心静むめれど、まだいと頼もしげなしや。心苦しきことにこそ」 |
「大変に重態になって、月日を送っていらっしゃったが、今日の夜明け方から息絶えてしまわれましたが、物の怪の仕業でした。だんだんと息を吹き返しなさったふうに聞きまして、今ちょうど皆安心したようですが、まだとても気がかりでなりません。おいたわしい限りです」 |
「重態のままで長く病んでおられたのですが、今朝の夜明けに絶息されたのは、それは |
"Ito omoku nari te, tuki-hi he tamahe ru wo, kono akatuki yori taye-iri tamahe ri turu wo, mononoke no si taru ni nam ari keru. Yau-yau iki-ide tamahu yau ni kiki-nasi haberi te, ima nam mina-hito kokoro sidumu mere do, mada ito tanomosigenasi ya! Kokoro-gurusiki koto ni koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.13 | とて、まことにいたく泣きたまへるけしきなり。目もすこし腫れたり。 衛門督、わがあやしき心ならひにや、 この君の、いとさしも親しからぬ継母の御ことを、いたく心しめたまへるかな、と目をとどむ。 |
と言って、本当にひどくお泣きになるご様子である。目も少し腫れている。衛門督は、自分のけしからぬ気持ちに照らしてか、この君が、大して親しい関係でもない継母のご病気を、ひどく悲嘆していらっしゃるなと、目を止める。 |
と言う大将には実際今まで泣き続けていたという様子が残っていた。目も少しは |
tote, makoto ni itaku naki tamahe ru kesiki nari. Me mo sukosi hare tari. Wemon-no-Kami, waga ayasiki kokoro-narahi ni ya, kono Kimi no, ito sasimo sitasikara nu mama-haha no ohom-koto wo, itaku kokoro-sime tamahe ru kana, to me wo todomu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.14 | かく、これかれ参りたまへるよし聞こし召して、 |
このように、いろいろな方々がお見舞いに参上なさった旨をお聞きになって、 |
こんなふうに高官らも見舞いに集まって来たことをお聞きになって、院からの御挨拶が伝えられた。 |
Kaku, kore-kare mawiri tamahe ru yosi kikosimesi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.15 | 「 重き病者の、にはかにとぢめつるさまなりつるを、女房などは、心もえ収めず、乱りがはしく騷ぎはべりけるに、みづからもえのどめず、心あわたたしきほどにてなむ。ことさらになむ、かくものしたまへるよろこびは聞こゆべき」 |
「重病人が、急に息を引き取ったふうになったのですが、女房たちは、冷静さを失って、取り乱して騷ぎましたが、自分自身も落ちつきをなくして、取り乱しております。後日改めて、このお見舞いにはお礼申し上げます」 |
「重い病人に急変が来たように見えましたために女房らが泣き騒ぎをいたしましたので、私自身もつい心の平静をなくしているおりからですから、またほかの日に改めて御好意に対するお礼を申しましょう」 |
"Omoki byauzya no, nihaka ni todime turu sama nari turu wo, nyoubau nado ha, kokoro mo e wosame zu, midari-gahasiku sawagi haberi keru ni, midukara mo e nodome zu, kokoro-awatatasiki hodo ni te nam. Kotosara ni nam, kaku monosi tamahe ru yorokobi ha kikoyu beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3.16 | とのたまへり。督の君は胸つぶれて、かかる折のらうろうならずはえ参るまじく、けはひ恥づかしく思ふも、 心のうちぞ腹ぎたなかりける。 |
とおっしゃった。督の君は胸がどきっとして、このようなのっぴきならぬ事情がなければ参上できそうになく、何がなし恐ろしい気がするのも、心中後ろめたいところがあるからなのであった。 |
院のお言葉というだけで、もう |
to notamahe ri. Kam-no-Kimi ha mune tubure te, kakaru wori no rau-rau nara zu ha e mawiru maziku, kehahi hadukasiku omohu mo, kokoro no uti zo hara-gitanakari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 第四段 紫の上、蘇生後に五戒を受く |
8-4 Murasaki revivals and receives Go-kai, Buddhist's ceremony |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.1 | かく生き出でたまひての後しも、恐ろしく思して、またまた、いみじき法どもを尽くして加へ行なはせたまふ。 |
このように生き返りなさった後は、恐ろしくお思いになって、再度、大変ないくつもの修法のあらん限りを追加して行わせなさる。 |
|
Kaku iki-ide tamahi te no noti simo, osorosiku obosi te, mata-mata, imiziki hohu-domo wo tukusi te, kuhahe okonaha se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.2 | うつし人にてだに、むくつけかりし人の御けはひの、まして 世変はり、妖しきもののさまになりたまへらむを思しやるに、いと心憂ければ、中宮を扱ひきこえたまふさへぞ、この折はもの憂く、 言ひもてゆけば、女の身は、皆同じ罪深きもとゐぞかしと、なべての 世の中厭はしく、かの、また人も聞かざりし御仲の睦物語に、すこし語り出でたまへりしことを言ひ出でたりしに、まことと思し出づるに、いとわづらはしく思さる。 |
生きていた時の人でさえ、嫌な気がしたご様子の方が、まして死後に、異形のものに姿を変えていらっしゃるのだろうことをご想像なさると、まことに気味が悪いので、中宮をお世話申し上げなさることまでが、この際は億劫になり、せんじつめれば、女性の身は、皆同様に罪障の深いものだと、すべての男女関係が嫌になって、あの、他人は聞かなかったお二人の睦言に、少しお話し出しになったことを言い出したので、確かにそうだとお思い出しになると、まことに厄介なことに思わずにはいらっしゃれない。 |
|
Utusi-bito ni te dani, mukutukekari si hito no ohom-kehahi no, masite yo kahari, ayasiki mono no sama ni nari tamahe ra m wo obosi-yaru ni, ito kokoro-ukere ba, Tyuuguu wo atukahi kikoye tamahu sahe zo, kono wori ha mono-uku, ihi-mote-yuke ba, womna no mi ha, mina onazi tumi hukaki motowi zo kasi to, nabete no yononaka itohasiku, kano, mata-hito mo kika zari si ohom-naka no mutu-monogatari ni, sukosi katari-ide tamahe ri si koto wo ihi-ide tari si ni, makoto to obosi-iduru ni, ito wadurahasiku obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.3 | 御髪下ろしてむと切に思したれば、 忌むことの力もやとて、御頂しるしばかり挟みて、 五戒ばかり受けさせたてまつりたまふ。御戒の師、忌むことのすぐれたるよし、仏に申すにも、あはれに尊きこと混じりて、人悪く御かたはらに添ひゐて、涙おし拭ひたまひつつ、仏を諸心に念じきこえたまふさま、世にかしこくおはする人も、いとかく御心惑ふことにあたりては、え静めたまはぬわざなりけり。 |
御髪を下ろしたいと切望なさっているので、持戒による功徳もあろうかと考えて、頭の頂を形式的に挟みを入れて、五戒だけをお受けさせ申し上げなさる。御戒の師が、持戒のすぐれている旨を仏に申すにつけても、しみじみと尊い文句が混じっていて、体裁が悪いまでお側にお付きなさって、涙をお拭いになりながら、仏を一緒にお念じ申し上げなさる様子は、この世に又となく立派でいらっしゃる方も、まことにこのようにご心痛になる非常時に当たっては、冷静ではいらっしゃれないものなのであった。 |
ぜひ尼になりたいと夫人が望むので、頭の頂の髪を少し取って、五戒だけをお受けさせになった。戒師が完全に仏の戒めを守る誓いを、仏前で尊い言葉で述べる時に、院は体面もお忘れになり、夫人に寄り添って涙を |
Mi-gusi orosi te m to seti ni obosi tare ba, imu koto no tikara mo ya tote, ohom-itadaki sirusi bakari hasami te, gokai bakari uke sase tatematuri tamahu. Gokai no si, imu koto no sugure taru yosi, Hotoke ni mausu ni mo, ahare ni tahutoki koto maziri te, hito-waruku ohom-katahara ni sohi-wi te, namida osi-nogohi tamahi tutu, Hotoke wo moro-gokoro ni nen-zi kikoye tamahu sama, yo ni kasikoku ohasuru hito mo, ito kaku mi-kokoro madohu koto ni atari te ha, e sidume tamaha nu waza nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4.4 | いかなるわざをして、これを救ひかけとどめたてまつらむとのみ、夜昼思し嘆くに、ほれぼれしきまで、御顔もすこし面痩せたまひにたり。 |
どのような手立てをしてでも、この方をお救い申しこの世に引き止めておこうとばかり、昼夜お嘆きになっているので、ぼうっとするほどになって、お顔も少しお痩せになっていた。 |
どんな方法を講じて夫人の病を救い、長く |
Ika naru waza wo si te, kore wo sukuhi kake-todome tatematura m to nomi, yoru hiru obosi nageku ni, hore-boresiki made, ohom-kaho mo sukosi omoyase tamahi ni tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 第五段 紫の上、小康を得る |
8-5 Murasaki gets a breathing space |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.1 | 五月などは、まして、晴れ晴れしからぬ空のけしきに、えさはやぎたまはねど、ありしよりはすこし良ろしきさまなり。されど、なほ絶えず悩みわたりたまふ。 |
五月などは、これまで以上に、晴々しくない空模様で、すっきりした気分におなりになれないが、以前よりは少し良い状態である。けれども、やはりずっと絶えることなくお悩みになっている。 |
五月などはまして気候が悪くて病夫人の容体がさわやいでいくとも見えなかったが、以前よりは少しいいようであった。しかもまだ苦しい日々が時々夫人にあった。 |
Go-gwati nado ha, masite, hare-baresikara nu sora no kesiki ni, e sahayagi tamaha ne do, arisi yori ha sukosi yorosiki sama nari. Saredo, naho tayezu nayami watari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.2 | もののけの罪救ふべきわざ、 日ごとに法華経一部づつ供養ぜさせたまふ。日ごとに何くれと尊きわざせさせたまふ。御枕上近くても、不断の御読経、声尊き限りして読ませたまふ。現はれそめては、折々悲しげなることどもを言へど、 さらにこのもののけ去り果てず ★。 |
物の怪の罪障を救えるような仏事として、毎日法華経を一部ずつ供養させなさる。毎日何やかやと尊い供養をおさせになる。御枕元近くでも、不断の御読経を、声の尊い人だけを選んでおさせになる。物の怪が正体を現すようになってからは、時々悲しげなことを言うが、まったくこの物の怪がすっかり消え去ったというわけではない。 |
院は物怪の罪を救うために、日ごとに |
Mononoke no tumi sukuhu beki waza, hi-goto ni Hokekyau iti-bu dutu kuyau-ze sase tamahu. Hi-goto ni nani-kure to tahutoki waza se sase tamahu. Ohom-makuragami tikaku te mo, hudan no mi-dokyau, kowe tahutoki kagiri si te yoma se tamahu. Arahare some te ha, wori-wori kanasige naru koto-domo wo ihe do, sarani kono mononoke sari-hate zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.3 | いとど暑きほどは、息も絶えつつ、いよいよのみ弱りたまへば、いはむかたなく思し嘆きたり。 なきやうなる御心地にも、 かかる御けしきを心苦しく見たてまつりたまひて、 |
ますます暑いころは、息も絶え絶えになって、ますますご衰弱なさるので、何とも言いようがないほどお嘆きになった。意識もないようなご病状の中でも、このようなご様子をお気の毒に拝見なさって、 |
暑い夏の日になっていよいよ病夫人の衰弱ははげしくなるばかりであるのを院は歎き続けておいでになった。病に弱っていながらも院のこの御様子を夫人は心苦しく思い、 |
Itodo atuki hodo ha, iki mo taye tutu, iyo-iyo nomi yowari tamahe ba, iha m kata naku obosi nageki tari. Naki yau naru mi-kokoti ni mo, kakaru mi-kesiki wo kokoro-gurusiku mi tatematuri tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.4 | 「 世の中に亡くなりなむも、わが身にはさらに口惜しきこと残るまじけれど、かく思し惑ふめるに、 空しく見なされたてまつらむが、いと思ひ隈なかるべければ」 |
「この世から亡くなっても、わたしには少しも残念だと思われることはないが、これほどご心痛のようなので、自分の亡骸をお目にかけるのも、いかにも思いやりのないことだから」 |
自分の死ぬことは何でもないがこんなにお悲しみになるのを知りながら死んでしまうのは思いやりのないことであろうから、その点で自分はまだ生きるように努めねばならぬ |
"Yononaka ni nakunari na m mo, waga mi ni ha sarani kutiwosiki koto nokoru mazikere do, kaku obosi-madohu meru ni, munasiku mi-nasa re tatematura m ga, ito omohi kumanakaru bekere ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5.5 | 思ひ起こして、御湯などいささか参るけにや、 六月になりてぞ、時々御頭もたげたまひける。めづらしく見たてまつりたまふにも、なほ、いとゆゆしくて、六条の院にはあからさまにもえ渡りたまはず。 |
と、気力を奮い起こして、お薬湯などを少し召し上がったせいか、六月になってからは、時々頭を枕からお上げになった。珍しいことと拝見なさるにつけても、やはり、とても危なそうなので、六条院にはわずかの間でもお出向きになることができない。 |
と、こんな気が起こったころから、 |
Omohi-okosi te, ohom-yu nado isasaka mawiru ke ni ya, Roku-gwati ni nari te zo, toki-doki mi-gusi motage tamahi keru. Medurasiku mi tatematuri tamahu ni mo, naho, ito yuyusiku te, Rokudeu-no-win ni ha akarasama ni mo e watari tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 3/10/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 3/10/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 12/29/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 9/30/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経