35 若菜下(明融臨模本) |
WAKANA-NO-GE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 四十一歳三月から四十七歳十二月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from Mar. of 41 to Dec. the age of 47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 第十一章 朱雀院の物語 五十賀の延引 |
11 Tale of Suzaku The celebrstion for Suzaku is put off |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | 第一段 女二の宮、院の五十の賀を祝う |
11-1 Omna-Ni-no-Miya celebrates for Suzaku 50 years old |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1.1 | かくて、山の帝の御賀も延びて、秋とありしを、 八月は大将の御忌月にて、楽所のこと行なひたまはむに、便なかるべし。 九月は、院の大后の崩れたまひにし月なれば、十月にと思しまうくるを、 姫宮いたく悩みたまへば、また延びぬ。 |
こうして、山の帝の御賀も延期になって、秋にとあったが、八月は大将の御忌月で、楽所を取り仕切られるのには、不都合であろう。九月は、院の大后がお崩れになった月なので、十月にとご予定を立てたが、姫宮がひどくお悩みになったので、再び延期になった。 |
紫夫人の大病のために法皇の賀宴も延びて秋ということになっていたが、八月は左大将の |
Kakute, Yama-no-Mikado no ohom-ga mo nobi te, aki to ari si wo, Hati-gwati ha Daisyau no ohom-ki-duki ni te, gakusyo no koto okonahi tamaha m ni, bin-nakaru besi. Ku-gwati ha, Win no Oho-Kisaki no kakure tamahi ni si tuki nare ba, Zihu-gwati ni to obosi maukuru wo, Hime-Miya itaku nayami tamahe ba, mata nobi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1.2 | 衛門督の御預かりの宮なむ、 その月には参りたまひける。太政大臣居立ちて、いかめしくこまかに、もののきよら、儀式を尽くしたまへりけり。督の君も、そのついでにぞ、思ひ起こして出でたまひける。なほ、悩ましく、例ならず病づきてのみ過ぐしたまふ。 |
衛門督がお引き受けになっている宮が、その月には御賀に参上なさったのだった。太政大臣が奔走して、盛大にかつこまごまと気を配って、儀式の美々しさ、作法の格式の限りをお尽くしなさっていた。督の君も、その機会には、気力を出してご出席なさったのだった。やはり、気分がすぐれず、普通と違って病人のように日を送ってばかりいらっしゃる。 |
|
Wemon-no-Kami no ohom-adukari no Miya nam, sono tuki ni ha mawiri tamahi keru. Ohoki-Otodo wi-tati te, ikamesiku komaka ni, mono no kiyora, gisiki wo tukusi tamahe ri keri . Kam-no-Kimi mo, sono tuide ni zo, omohi-okosi te ide tamahi keru. Naho, nayamasiku, rei nara zu yamahi-duki te nomi sugusi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1.3 | 宮も、うちはへてものをつつましく、いとほしとのみ 思し嘆くけにやあらむ、 月多く重なりたまふままに、いと苦しげにおはしませば、 院は、心憂しと思ひきこえたまふ方こそあれ、いとらうたげにあえかなるさまして、かく悩みわたりたまふを、いかにおはせむと嘆かしくて、さまざまに思し嘆く。 御祈りなど、今年は紛れ多くて過ぐしたまふ。 |
宮も、引き続いて何かと気がめいって、ただつらいとばかりお思い嘆いていられるせいであろうか、懐妊の月数がお重なりになるにつれて、とても苦しそうにいらっしゃるので、院は、情けないとお思い申し上げなさる気持ちはあるが、とても痛々しく弱々しい様子をして、このようにずっとお悩みになっていらっしゃるのを、どのようにおなりになることかと心配で、あれこれとお心をお痛めになられる。ご祈祷など、今年は取り込み事が多くてお過ごしになる。 |
女三の宮も御 |
Miya mo, uti-hahe te mono wo tutumasiku, itohosi to nomi obosi nageku ni ya ara m, tuki ohoku kasanari tamahu mama ni, ito kurusige ni ohasimase ba, Win ha, kokoro-usi to omohi kikoye tamahu kata koso are, ito rautage ni aeka naru sama si te, kaku nayami watari tamahu wo, ikani ohase m to nagekasiku te, sama-zama ni obosi nage ku. Ohom-inori nado, kotosi ha magire ohoku te sugusi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | 第二段 朱雀院、女三の宮へ手紙 |
11-2 Suzaku sends a letter to Omna-Sam-no-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.1 | 御山にも聞こし召して、らうたく恋しと 思ひきこえたまふ。月ごろかくほかほかにて、渡りたまふことも をさをさなきやうに、人の奏しければ、 いかなるにかと御胸つぶれて、 世の中も今さらに恨めしく思して、 |
お山におかせられてもお耳にあそばして、いとおしくお会いしたいとお思い申し上げなさる。いく月もあのように別居していて、お越しになることもめったにないように、ある人が奏上したので、どうしたことにかとお胸が騒いで、俗世のことも今さらながら恨めしくお思いになって、 |
法皇も宮の御妊娠のことをお聞きになって、かわいく想像をあそばされ、 |
Mi-yama ni mo kikosimesi te, rautaku kohisi to omohi kikoye tamahu. Tuki-goro kaku hoka-hoka ni te, watari tamahu koto mo wosa-wosa naki yau ni, hito no sau-si kere ba, ika naru ni ka to ohom-mune tubure te, yononaka mo imasara ni uramesiku obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.2 | 「 対の方のわづらひけるころは、なほその扱ひにと聞こし召してだに、なまやすからざりしを、 そののち、直りがたくものしたまふらむは、 そのころほひ、便なきことや出で来たりけむ。 みづから知りたまふことならねど、良からぬ御後見どもの心にて、 いかなることかありけむ。内裏わたりなどの、みやびを交はすべき仲らひなどにも、けしからず憂きこと言ひ出づるたぐひも聞こゆかし」 |
「対の方が病気であったころは、やはりその看病でとお聞きになってでさえ、心穏やかではなかったのに、その後も、変わらずにいらっしゃるとは、そのころに、何か不都合なことが起きたのだろうか。宮自身に責任がおありのことでなくても、良くないお世話役たちの考えで、どんな失態があったのだろうか。宮中あたりなどで、風雅なやりとりをし合う間柄などでも、けしからぬ評判を立てる例も聞こえるものだ」 |
紫夫人の病気のころは院があちらにばかり行っておいでになったのを、もっともなこととはいえ、思いやりのないこととして聞いておいでになったが、夫人の病後も院の御訪問はまれになったというのは、その間に不祥なことが起こったのではあるまいか。宮が自発的に堕落の傾向をおとりになったのではなく、軽薄な女房の |
"Tai-no-Kata no wadurahi keru koro ha, naho sono atukahi ni to kikosimesi te dani, nama-yasukara zari si wo, sono noti, nahori gataku monosi tamahu ram ha, sono korohohi, bin-naki koto ya ide-ki tari kem? Midukara siri tamahu koto nara ne do, yokara nu ohom-usiromi-domo no kokoro ni te, ika naru koto ka ari kem? Uti watari nado no, miyabi wo kahasu beki nakarahi nado ni mo, kesikara zu uki koto ihi iduru taguhi mo kikoyu kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.3 | とさへ思し寄るも、 こまやかなること思し捨ててし世なれど、なほ子の道は離れがたくて、宮に御文こまやかにてありけるを、大殿、おはしますほどにて、見たまふ。 |
とまでお考えになるのも、肉親の情愛はお捨てになった出家の生活だが、やはり親子の愛情は忘れ去りがたくて、宮にお手紙を心をこめて書いてあったのを、大殿も、いらっしゃった時なので、御覧になる。 |
と、こんなことまでも御想像あそばされるのは、いっさいをお捨てになった御心境にもなお御子をお思いになる愛情だけは影を残しているからである。法皇が愛のこもったお手紙を宮へお書きになったのを、六条院も来ておいでになる時で拝見されたのであった。 |
to sahe obosi-yoru mo, komayaka naru koto obosi-sute te si yo nare do, naho ko no miti ha hanare gataku te, Miya ni ohom-humi komayaka ni te ari keru wo, otodo, ohasimasu hodo ni te, mi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.4 | 「 そのこととなくて、しばしばも聞こえぬほどに、おぼつかなくてのみ年月の過ぐるなむ、 あはれなりける。悩みたまふなるさまは、詳しく聞きしのち、念誦のついでにも 思ひやらるるは、いかが。世の中寂しく思はずなることありとも、忍び過ぐしたまへ。 恨めしげなるけしきなど、おぼろけにて、見知り顔にほのめかす、いと品おくれたるわざになむ」 |
「特に用件もないので、たびたびはお便りを差し上げなかったうちに、あなたの様子も分からないままに歳月が過ぎるのは、気がかりなことです。お具合がよろしくなくいらっしゃるという様子は、詳しく聞いてからは、念仏誦経の時にも気にかかってならないが、いかがいらっしゃいますか。ご夫婦仲が寂しくて意に満たないことがあっても、じっと堪えてお過ごしなさい。恨めしそうな素振りなどを、いい加減なことで、心得顔にほのめかすのは、まことに品のないことです」 |
用事もないものですから |
"Sono koto to naku te, siba-siba mo kikoye nu hodo ni, obotukanaku te nomi tosi-tuki no suguru nam, ahare nari keru. Nayami tamahu naru sama ha, kuhasiku kiki si noti, nenzyu no tuide ni mo omohi-yara ruru ha, ikaga? Yononaka sabisiku omoha zu naru koto ari tomo, sinobi sugusi tamahe. Uramesige naru kesiki nado, oboroke ni te, mi-siri-gaho ni honomekasu, ito sina okure taru waza ni nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.5 | など、教へきこえたまへり。 |
などと、お教え申し上げていらっしゃった。 |
などと |
nado, wosihe kikoye tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.6 | いといとほしく心苦しく、「 かかるうちうちのあさましきをば、聞こし召すべきにはあらで、 わがおこたりに、本意なくのみ聞き思すらむことを」とばかり思し続けて、 |
まことにお気の毒で心が痛み、「このような内々の宮の不始末を、お耳にあそばすはずはなく、わたしの怠慢のせいにと、御不満にばかりお思いあそばすことだろう」とばかりにお思い続けて、 |
院はお気の毒で、心苦しくて、宮に秘密のあることなどはお知りあそばされずに、自分の不誠意とばかり解釈しておいでになるのであろうとお思いになって、 |
Ito itohosiku kokoro-gurusiku, "Kakaru uti-uti no asamasiki wo ba, kikosimesu beki ni ha ara de, waga okotari ni, ho'i-naku nomi kiki obosu ram koto wo." to bakari obosi tuduke te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.7 | 「 この御返りをば、いかが聞こえたまふ。心苦しき御消息に、 まろこそいと苦しけれ。 思はずに思ひきこゆることありとも、おろかに、人の見咎むばかりはあらじとこそ思ひはべれ。誰が聞こえたるにかあらむ」 |
「このお返事は、どのようにお書き申し上げなさいますか。お気の毒なお手紙で、わたしこそとても辛い思いです。たとえ心外にお思い申す事があったとしても、疎略なお扱いをして、人が変に思うような態度はとるまいと思っております。誰が申し上げたのでしょうか」 |
「お返事はどうお書きになりますか。心苦しいお手紙で私はつらい気がしますよ。あなたにどんなことがあっても、人に変わった様子は見せまいと私は努めているのですよ。だれがいろいろなことを申し上げたのだろう」 |
"Kono ohom-kaheri wo ba, ikaga kikoye tamahu. Kokoro-gurusiki ohom-seusoko ni, maro koso ito kurusikere. Omoha zu ni omohi kikoyuru koto ari tomo, oroka ni, hito no mi togamu bakari ha ara zi to koso omohi habere. Taga kikoye taru ni ka ara m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.8 | とのたまふに、恥ぢらひて背きたまへる御姿も、いとらうたげなり。 いたく面痩せて、もの思ひ屈したまへる、いとどあてにをかし。 |
とおっしゃると、恥ずかしそうに横を向いていらっしゃるお姿も、まことに痛々しい。ひどく面やつれして、物思いに沈んでいらっしゃるのは、ますます上品で美しい。 |
とお言いになると、恥じて顔をおそむけになる宮のお姿が |
to notamahu ni, hadirahi te somuki tamahe ru ohom-sugata mo, ito rautage nari. Itaku omo-yase te, mono-omohi kut-si tamahe ru, itodo ate ni wokasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3 | 第三段 源氏、女三の宮を諭す |
11-3 Genji admonishs Omna-Sam-no-miya about her behavior |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.1 | 「 いと幼き御心ばへを見おきたまひて、いたくはうしろめたがりきこえたまふなりけりと、思ひあはせたてまつれば、今より後も よろづになむ。かうまでもいかで聞こえじと思へど、上の、御心に背くと聞こし召すらむことの、やすからず、いぶせきを、 ここにだに聞こえ知らせでやはとてなむ。 |
「とても幼い御気性を御存知で、たいそう御心配申し上げていらっしゃるのだと、拝察されますので、今後もいろいろと心配でなりません。こんなにまでは決して申し上げまいと思いましたが、院の上が、御心中にわたしが背いているとお思いになろうことが、不本意であり、心の晴れない思いであるが、せめてあなたにだけは申し上げておかなくてはと思いまして。 |
「あなたの幼稚な性質を知っておいでになって、こんなにもお言いになるのだと、私は他のことと思い合わせてごもっともだと思われる点がありますよ。それで今後も |
"Ito wosanaki mi-kokorobahe wo mi-oki tamahi te, itaku ha usirometagari kikoye tamahu nari keri to, omohi ahase tatemature ba, ima yori noti mo yorodu ni nam. Kau made mo ikade kikoye zi to omohe do, Uhe no, mi-kokoro ni somuku to kikosimesu ram koto no, yasukara zu, ibuseki wo, koko ni dani kikoye sirase de ya ha tote nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.2 | いたり少なく、ただ、人の聞こえなす方にのみ寄るべかめる御心には、 ただおろかに浅きとのみ思し、また、 今はこよなくさだ過ぎにたるありさまも、あなづらはしく目馴れてのみ見なしたまふらむも、 かたがたに口惜しくもうれたくもおぼゆるを、 院のおはしまさむほどは、なほ心収めて、かの思しおきてたるやうありけむ、さだ過ぎ人をも、同じくなずらへきこえて、いたくな軽めたまひそ。 |
思慮が浅く、ただ、人が申し上げるままにばかりお従いになるようなあなたとしては、ただ冷淡で薄情だとばかりお思いで、また、今ではわたしのすっかり年老いた様子も、軽蔑し飽き飽きしてばかりお思いになっていられるらしいのも、それもこれも残念にも忌ま忌ましくも思われますが、院の御存命中は、やはり我慢して、あちらのお考えもあったことでしょうから、この年寄をも、同じようにお考え下さって、ひどく軽蔑なさいますな。 |
深く物をお考えにならないで、人のいいかげんな言葉にお動きになるあなたには、私のほんとうの愛が浅いものに見えもするでしょうし、またあなたとは |
Itari sukunaku, tada, hito no kikoye nasu kata ni nomi yoru beka' meru mi-kokoro ni ha, tada oroka ni asaki to nomi obosi, mata, ima ha koyonaku sada sugi ni taru arisama mo, anadurahasiku me nare te nomi mi-nasi tamahu ram mo, kata-gata ni kutiwosiku mo uretaku mo oboyuru wo, Win no ohasimasa m hodo ha, naho kokoro wosame te, kano obosi-oki te taru yau ari kem, sada-sugi-bito wo mo, onaziku nazurahe kikoye te, itaku na karume tamahi so. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.3 | いにしへより本意深き道にも、 たどり薄かるべき女方にだに、皆思ひ後れつつ ★、いとぬるきこと多かるを、みづからの心には、何ばかり思しまよふべきにはあらねど、 今はと捨てたまひけむ世の後見に 譲りおきたまへる御心ばへの、あはれにうれしかりしを、 ひき続き争ひきこゆるやうにて、 同じさまに見捨てたてまつらむことの、 あへなく思されむに つつみてなむ。 |
昔からの出家の本願も、考えの不十分なはずのご婦人方にさえ、みな後れを取り後れを取りして、とてものろまなことが多いのですが、自分自身の心には、どれほどの思いを妨げるものはないのですが、院がこれを最後と御出家なさった後のお世話役にわたしをお譲り置きになったお気持ちが、しみじみと嬉しかったが、引き続いて後を追いかけるようにして、同じようにお見捨て申し上げるようなことが、院にはがっかりされるであろうと差し控えているのです。 |
昔から願っている出家の志望も、自分よりは幼稚な宗教心しか持つまいと思っていた女の人たちが先に実行するのを傍観しているのも、私自身がこの世の欲を捨てえないのではなくて、出家をあそばす際にはあなたをお託しになった院のお志に感激した心が、すぐまた続いてあなたを捨てて行くような行動を取らせなかったのですよ。 |
Inisihe yori ho'i hukaki miti ni mo, tadori usukaru beki Womna-gata ni dani, mina omohi okure tutu, ito nuruki koto ohokaru wo, midukara no kokoro ni ha, nani bakari obosi mayohu beki ni ha ara ne do, ima ha to sute tamahi kem yo no usiromi ni yuzuri-oki tamahe ru mi-kokorobahe no, ahare ni uresikari si wo, hiki-tuduki arasohi kikoyuru yau ni te, onazi sama ni mi-sute tatematura m koto no, ahenaku obosa re m ni tutumi te nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.4 | 心苦しと思ひし人びとも、今はかけとどめらるるほだしばかりなるもはべらず。女御も、かくて、行く末は知りがたけれど、御子たち数添ひたまふめれば、 みづからの世だにのどけくはと見おきつべし。その他は、誰も誰も、あらむに従ひて、もろともに身を捨てむも、惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやうすずしく思ひはべる。 |
気にかかっていた人々も、今では出家の妨げとなるほどの者もおりません。女御も、あのようにして、将来の事は分かりませんが、皇子方がいく人もいらっしゃるようなので、わたしの存命中だけでもご無事であればと安心してよいでしょう。その他の事は、誰も彼も、状況に従って、一緒に出家するのも、惜しくはない年齢になっているのを、だんだんと気持ちも楽になっております。 |
以前は気がかりに思われた人も今ではもう出家の |
Kokoro-gurusi to omohi si hito-bito mo, ima ha kake todome raruru hodasi bakari naru mo habera zu. Nyougo mo, kakute, yukusuwe ha siri gatakere do, mi-ko-tati kazu sohi tamahu mere ba, midukara no yo dani nodokeku ha to mi-oki tu besi. Sono hoka ha, tare mo tare mo, ara m ni sitagahi te, morotomoni mi wo sute m mo, wosikaru maziki yohahi-domo ni nari ni taru wo, yau-yau suzusiku omohi haberu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.5 | 院の御世の残り久しくもおはせじ。いと篤しくいとどなりまさりたまひて、もの心細げにのみ思したるに、今さらに思はずなる 御名の漏り聞こえて、御心乱りたまふな。 この世はいとやすし。ことにもあらず。後の世の御道の妨げならむも、罪いと恐ろしからむ」 |
院の御寿命もそう長くはいらっしゃらないでしょう。とても御病気がちにますますなられて、何となく心細げにばかりお思いでいられるから、今さら感心しないお噂を院のお耳にお入れ申して、お心を乱したりなさらないように。現世はまことに気にかけることはありません。どうということもありません。が、来世の御成仏の妨げになるようなのは、罪障がとても恐ろしいでしょう」 |
院ももう長くはおいでにならないでしょう。以前よりいっそうお |
Win no mi-yo no nokori hisasiku mo ohase zi. Ito atusiku itodo nari masari tamahi te, mono-kokoro-bosoge ni nomi obosi taru ni, imasara ni omoha zu naru ohom-na no mori kikoye te, mi-kokoro midari tamahu na. Konoyo ha ito yasusi. Koto ni mo ara zu. Noti no yo no ohom-miti no samatage nara m mo, tumi ito osorosikara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.6 | など、 まほにそのこととは明かしたまはねど、つくづくと聞こえ続けたまふに、 涙のみ落ちつつ、我にもあらず思ひしみておはすれば、 我もうち泣きたまひて、 |
などと、はっきりとその事とはお明かしにならないが、しみじみとお話し続けなさるので、涙ばかりがこぼれては、正体もない様子で悲しみに沈んでいらっしゃるので、ご自分もお泣きになって、 |
そのことと露骨にお言いにならないのであるが、しみじみとお説きになるために、宮は涙ばかりがこぼれて、知らず知らずめいり込んでおしまいになったのを御覧になる院も、お泣きになって、 |
nado, maho ni sono koto to ha akasi tamaha ne do, tuku-duku to kikoye tuduke tamahu ni, namida nomi oti tutu, ware ni mo ara zu omohi-simi te ohasure ba, ware mo uti-naki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.7 | 「 人の上にても、もどかしく聞き思ひし古人のさかしらよ。身に代はることにこそ。いかにうたての翁やと、むつかしくうるさき 御心添ふらむ」 |
「他人の身の上でも、嫌なものだと思って聞いていた老人のおせっかいというものを。自分がするようになったことよ。どんなに嫌な老人かと、不愉快で厄介なと思うお気持ちがつのることでしょう」 |
「他の人がこうしたことを言うのを、聞く必要もない |
"Hito no uhe ni te mo, modokasiku kiki omohi si huru-bito no sakasira yo. Mi ni kaharu koto ni koso. Ikani utate no okina ya to, mutukasiku urusaki mi-kokoro sohu ram." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.8 | と、恥ぢたまひつつ、御硯引き寄せたまひて、手づから押し擦り、紙取りまかなひ、書かせたてまつりたまへど、御手もわななきて、え書きたまはず。 |
と、お恥になりながら、御硯を引き寄せなさって、自分で墨を擦り、紙を整えて、お返事をお書かせ申し上げなさるが、お手も震えて、お書きになることができない。 |
ともお言いになって、 |
to, hadi tamahi tutu, ohom-suzuri hiki-yose tamahi te, tedukara osi-suri, kami tori makanahi, kaka se tatematuri tamahe do, mi-te mo wananaki te, e kaki tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3.9 | 「 かのこまかなりし返事は、いとかくしもつつまず通はしたまふらむかし」と思しやるに、 いと憎ければ、よろづのあはれも冷めぬべけれど、言葉など教へて書かせたてまつりたまふ。 |
「あのこまごまと書いてあった手紙のお返事は、とてもこのように遠慮せずやりとりなさっていたのだろう」とご想像なさると、実に癪にさわるので、一切の愛情も冷めてしまいそうであるが、文句などを教えてお書かせ申し上げなさる。 |
あの濃厚な言葉の盛られてあった |
"Kano komaka nari si kaheri-goto ha, ito kaku simo tutuma zu kayohasi tamahu ram kasi." to obosi-yaru ni, ito nikukere ba, yorodu no ahare mo same nu bekere do, kotoba nado wosihe te kaka se tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 | 第四段 朱雀院の御賀、十二月に延引 |
11-4 The celebrstion for Suzaku is put off on December |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4.1 | 参りたまはむことは、 この月かくて過ぎぬ。 二の宮の御勢ひ殊にて参りたまひけるを、 古めかしき御身ざまにて、立ち並び顔ならむも、 憚りある心地しけり。 |
参賀なさることは、この月はこうして過ぎてしまった。二の宮が格別のご威勢で参賀なさったのに、身籠もられたお身体で、競うようなのも、遠慮され気が引けるのであった。 |
「お伺いになることはこんなことで今月もだめでしたね。それに新婚者の |
Mawiri tamaha m koto ha, kono tuki kakute sugi nu. Ni-no-Miya no ohom-ikihohi koto ni te, mawiri tamahi keru wo, hurumekasiki ohom-mi-zama ni te, tati narabi gaho nara m mo, habakari aru kokoti si keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4.2 | 「 霜月はみづからの忌月なり。年の終りはた、いともの騒がし。また、いとどこの御姿も見苦しく、待ち見たまはむをと思ひはべれど、さりとて、さのみ延ぶべきことにやは。むつかしくもの思し乱れず、あきらかにもてなしたまひて、このいたく面痩せたまへる、つくろひたまへ」 |
「十一月はわたしの忌月です。年の終わりは歳末で、とても騒々しい。また、ますますこのお姿も体裁悪く、お待ち受けあそばす院はいかが御覧になろうと思いますが、そうかと言って、そんなにも延期することはでません。くよくよとお思いあそばさず、明るくお振る舞いになって、このひどくやつれていらっしゃるのを、お直しなさい」 |
十一月はあなたのお母様の忌月でしょう。十二月はあまりに押しつまってよろしくないし、あなたの |
"Simo-tuki ha midukara no ki-duki nari. Tosi no wohari hata, ito mono sawagasi. Mata, itodo kono ohom-sugata mo mi-gurusiku, mati mi tamaha m wo to omohi habere do, saritote, sa nomi nobu beki koto ni ya ha. Mutukasiku mono obosi midare zu, akiraka ni motenasi tamahi te, kono itaku omo-yase tamahe ru, tukurohi tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4.3 | など、 いとらうたしと、さすがに見たてまつりたまふ。 |
などと、とてもおいたわしいと、それでもお思い申し上げていらっしゃる。 |
などとお言いになって、さすがにかわいくは思召すのであった。 |
nado, ito rautasi to, sasuga ni mi tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4.4 | 衛門督をば、 何ざまのことにも、ゆゑあるべきをりふしには、かならずことさらにまつはしたまひつつ、のたまはせ合はせしを、絶えてさる御消息もなし。人あやしと思ふらむと思せど、「 見むにつけても、いとどほれぼれしきかた恥づかしく、見むにはまたわが心もただならずや」と思し返されつつ、やがて月ごろ参りたまはぬをも咎めなし。 |
衛門督をどのような事でも、風雅な催しの折には、必ず特別に親しくお召しになっては、ご相談相手になさっていたのが、全然そのようなお便りはない。皆が変だと思うだろうとお思いになるが、「顔を見るにつけても、ますます自分の間抜けさが恥ずかしくて、顔を見てはまた自分の気持ちも平静を失うのではないか」と思い返され思い返されて、そのままいく月も参上なさらないのにもお咎めはない。 |
衛門督をどんな催し事にも必要な人物としてお招きになって御相談相手に今まではあそばす院でおありになったが、今度の法皇の賀に限って何の仰せもない。人が不審がるであろうとはお思いになるのであるが、その人が来てはずかしめられた老人である自分の見られることも不快であるし、自分が彼を見ては平静で心がありえなくなるかもしれぬと院はお思いになって、もう幾月も参殿しない人を、なぜかとお尋ねになることもないのである。 |
Wemon-no-Kami wo ba, nani zama no koto ni mo, yuwe aru beki wori husi ni ha, kanarazu kotosara ni matuhasi tamahi tutu, notamahase ahase si wo, tayete saru ohom-seusoko mo nasi. Hito ayasi to omohu ram to obose do, "Mi m ni tuke te mo, itodo hore-boresiki kata hadukasiku, mi m ni ha mata waga kokoro mo tadanara zu ya!" to obosi kahesa re tutu, yagate tuki-goro mawiri tamaha nu wo mo togame nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4.5 | おほかたの人は、なほ 例ならず悩みわたりて、 院にはた、御遊びなどなき年なれば、とのみ思ひわたるを、大将の君ぞ、「 あるやうあることなるべし。好色者は、さだめて わがけしきとりしことには、忍ばぬにやありけむ」と思ひ寄れど、いとかく定かに残りなきさまならむとは、思ひ寄りたまはざりけり。 |
世間一般の人は、ずっと普通の状態でなく病気でいらっしゃったし、院でもまた、管弦のお遊びなどがない年なので、とばかりずっと思っていたが、大将の君は、「何かきっと事情があることに違いない。風流者は、さだめし自分が変だと気がづいたことに、我慢できなかったのだろうか」と考えつくが、ほんとうにこのようにはっきりと何もかも知れるところにまでなっているとは、想像もおつきにならなかったのである。 |
ただの人たちは衛門督が病気続きであったし、六条院にもまた音楽その他のお催しの全くない年であるからと解釈していたが、左大将だけは何か理由のあることに違いない、多感多情な男であるから、自分が推測していたあの恋で自制の力を失うようなことがあったのではないかとは見ていても、まだこれほど不祥なことが暴露してしまったとは想像しなかった。 |
Ohokata no hito ha, naho rei nara zu nayami watari te, Win ni hata, ohom-asobi nado naki tosi nare ba, to nomi omohi wataru wo, Daisyau-no-Kimi zo, "Aru yau aru koto naru besi. Suki-mono ha, sadame te waga kesiki tori si koto ni ha, sinoba nu ni ya ari kem." to omohi-yore do, ito kaku sadaka ni nokori naki sama nara m to ha, omohi-yori tamaha zari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5 | 第五段 源氏、柏木を六条院に召す |
11-5 Genji invites Kashiwagi to Rokujo-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5.1 | 十二月になりにけり。十余日と定めて、舞ども習らし、殿のうちゆすりてののしる。二条の院の上は、まだ渡りたまはざりけるを、この試楽に よりてぞ、えしづめ果てで渡りたまへる。女御の君も里におはします。 このたびの御子は、また男にてなむおはしましける。すぎすぎいとをかしげにておはするを、明け暮れもて遊びたてまつりたまふになむ、過ぐる齢のしるし、 うれしく思されける。試楽に、 右大臣殿の北の方も渡りたまへり。 |
十二月になってしまった。十何日と決めて、数々の舞を練習し、御邸中大騒ぎしている。二条院の上は、まだお移りにならなかったが、この試楽のために、落ち着き払ってもいられずお帰りになった。女御の君も里にお下がりになっていらっしゃる。今度御誕生の御子は、また男御子でいらっしゃった。次々とおかわいらしくていらっしゃるのを、一日中御子のお相手をなさっていらっしゃるので、長生きしたお蔭だと、嬉しく思わずにはいらっしゃれないのだった。試楽には、右大臣殿の北の方もお越しになった。 |
十二月になった。十幾日と法皇の御賀の日が定められて六条院の中は用意に忙しくなった。二条の院の夫人はまだそのまま帰らずにいたが、御賀の試楽があるのに興味を覚えてもどってきた。 |
Zihuni-gwati ni nari ni keri. Zihu-yo-niti to sadame te, mahi-domo narasi, tono no uti yusuri te nonosiru. Nideu-no-win-no-Uhe ha, mada watari tamaha zari keru wo, kono sigaku ni yori te zo, e sidume hate de watari tamahe ru. Nyougo-no-Kimi mo sato ni ohasimasu. Kono tabi no Miko ha, mata wotoko ni te nam ohasimasi keru. Sugi-sugi ito wokasige ni te ohasuru wo, akekure mote-asobi tatematuri tamahu ni nam, suguru yohahi no sirusi, uresiku obosa re keru. Sigaku ni, U-Daizin-dono no Kitanokata mo watari tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5.2 | 大将の君、丑寅の町にて、まづうちうちに調楽のやうに、明け暮れ遊び習らしたまひければ、 かの御方は、御前の物は見たまはず。 |
大将の君は、丑寅の町で、まず内々に調楽のように、毎日練習なさっていたので、あの御方は、御前での試楽は御覧にならない。 |
左大将は東北の御殿でそれ以前にすでに毎日監督する舞曲の練習をさせていたから、 |
Daisyau-no-Kimi, Usitora-no-mati nite, madu uti-uti ni teugaku no yau ni, akekure asobi narasi tamahi kere ba, kano ohom-kata ha, o-mahe no mono ha mi tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5.3 | 衛門督を、かかることの折も交じらはせざらむは、いと栄なく、さうざうしかるべきうちに、人あやしと傾きぬべきことなれば、参りたまふべきよしありけるを、重くわづらふよし申して参らず。 |
衛門督を、このような機会に参加させないようなのは、まことに引き立たず、もの足りなく感じられるし、皆が変だと思うに違いないことなので、参上なさるようにお召しがあったが、重病である旨を申し上げて参上しない。 |
|
Wemon-no-Kami wo, kakaru koto no wori mo maziraha se zara m ha, ito haye naku, sau-zausikaru beki uti ni, hito ayasi to katabuki nu beki koto nare ba, mawiri tamahu beki yosi ari keru wo, omoku wadurahu yosi mausi te mawira zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5.4 | さるは、そこはかと苦しげなる病にもあらざなるを、思ふ心のあるにやと、 心苦しく思して、取り分きて御消息つかはす。父大臣も、 |
しかし、どこがどうと苦しい病気でもないようなのに、自分に遠慮してのことかと、気の毒にお思いになって、特別にお手紙をお遣わしになる。父の大臣も、 |
病気といっても何という名のある病をしているのでもないわけであるが、やましく思う点があるのであろうと、心苦しく思召して、特使をさえもおやりになって招こうとあそばされた。父の大臣も、 |
Saruha, sokohaka to kurusige naru yamahi ni mo ara za' naru wo, omohu kokoro no aru ni ya to, kokoro-kurusiku obosi te, toriwaki te ohom-seusoko tukahasu. Titi-Otodo mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5.5 | 「 などか返さひ申されける。ひがひがしきやうに、院にも聞こし召さむを、おどろおどろしき病にもあらず、助けて参りたまへ」 |
「どうしてご辞退申されたのか。いかにもすねているように、院におかれてもお思いあそばそうから、大した病気でもない、何とかして参上なさい」 |
「なぜ御辞退をしたかね。何か含むことでもあるように院がお思いになるだろうに。大病というのではないのだから、無理をしても参ったほうがよい」 |
"Nado ka kahesahi mausa re keru. Higa-higasiki yau ni, Win ni mo kikosimesa m wo, odoro-odorosiki yamahi ni mo ara zu, tasuke te mawiri tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5.6 | と そそのかしたまふに、かく重ねてのたまへれば、 苦しと思ふ思ふ参りぬ。 |
とお勧めなさっているところに、このように重ねておっしゃってきたので、苦しいと思いながらも参上した。 |
と勧めていたところへ再度のお使いが来たのであったから、つらい気持ちをいだきながら参った。 |
to sosonokasi tamahu ni, kaku kasane te notamahe re ba, kurusi to omohu omohu mawiri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.6 | 第六段 源氏、柏木と対面す |
11-6 Genji meets and talks with Kashiwagi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.6.1 | まだ上達部なども集ひたまはぬほどなりけり。 例の気近き御簾の内に入れたまひて、母屋の御簾下ろしておはします。 げに、いといたく痩せ痩せに青みて、例も誇りかにはなやぎたる方は、弟の君たちにはもて消たれて、 いと用意あり顔にしづめたるさまぞことなるを、いとどしづめてさぶらひたまふさま、「 などかは皇女たちの御かたはらにさし並べたらむに、さらに咎あるまじきを、 ただことのさまの、誰も誰もいと思ひやりなきこそ、 いと罪許しがたけれ」など、御目とまれど、さりげなく、いとなつかしく、 |
まだ上達部なども参上なさっていない時分であった。いつものようにお側近くの御簾の中に招き入れなさって、母屋の御簾を下ろしていらっしゃる。なるほど、実にひどく痩せて蒼い顔をしていて、いつもの陽気で派手な振る舞いは、弟の君たちに気圧されて、いかにも嗜みありげに落ち着いた態度でいるのが格別であるのを、いつもより一層静かに控えていらっしゃる様子は、「どうして内親王たちのお側に夫として並んでも、全然遜色はあるまいが、ただ今度の一件については、どちらもまことに思慮のない点に、ほんとうに罪は許せないのだ」などと、お目が止まりなさるが、平静を装って、とてもやさしく、 |
それはまだ他の高官などの集まって来ない時分であった。これまでのようにお座敷の |
Mada Kamdatime nado mo tudohi tamaha nu hodo nari keri. Rei no kedikaki mi-su no uti ni ire tamahi te, Moya no mi-su orosi te ohasimasu. Geni, ito itaku yase-yase ni awomi te, rei mo hokorika ni hanayagi taru kata ha, otouto no Kimi-tati ni ha mote-keta re te, ito youi ari gaho ni sidume taru sama zo koto naru wo, itodo sidume te saburahi tamahu sama, "Nadokaha Miko-tati no ohom-katahara ni sasi-narabe tara m ni, sarani toga aru maziki wo, tada koto no sama no, tare mo tare mo ito omohi-yari naki koso, ito tumi yurusi gatakere." nado, ohom-me tomare do, sarigenaku, ito natukasiku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.6.2 | 「 そのこととなくて、対面もいと久しくなりにけり。月ごろは、いろいろの病者を見あつかひ、心の暇なきほどに、院の御賀のため、ここにものしたまふ皇女の、 法事仕うまつりたまふべくありしを、次々とどこほることしげくて、かく年もせめつれば、え思ひのごとくしあへで、型のごとくなむ、斎の御鉢参るべきを、御賀などいへば、ことことしきやうなれど、家に生ひ出づる童べの数多くなりにけるを御覧ぜさせむとて、舞など習はしはじめし、そのことをだに果たさむとて。拍子調へむこと、また誰にかはと思ひめぐらしかねてなむ、月ごろ訪ぶらひものしたまはぬ恨みも捨ててける」 |
「特別の用件もなくて、お会いすることも久し振りになってしまった。ここいく月は、あちこちの病人を看病して、気持ちの余裕もなかった間に、院の御賀のために、こちらにいらっしゃる内親王が、御法事をして差し上げなさる予定になっていたが、次々と支障が続出して、このように年もおし迫ったので、思うとおりにもできず、型通りに精進料理を差し上げる予定だが、御賀などと言うと、仰々しいようだが、わが家に生まれた子供たちの数が多くなったのを御覧に入れようと、舞などを習わせ始めたが、その事だけでも予定どおり執り行おうと思って。調子をきちんと合わせることは、誰にお願いできようかと思案に窮していたが、いく月もお顔を見せにならなかった恨みも捨てました」 |
「機会がなくてあなたにも長く |
"Sono koto to naku te, taimen mo ito hisasiku nari ni keri. Tuki-goro ha, iro-iro no byauzya wo mi atukahi, kokoro no itoma naki hodo ni, Win no ohom-ga no tame, koko ni monosi tamahu Miko no, hohuzi tukau-maturi tamahu beku ari si wo, tugi-tugi todokohoru koto sigeku te, kaku tosi mo seme ture ba, e omohi no gotoku si-ahe de, kata no gotoku nam, imohi no mi-hati mawiru beki wo, ohom-ga nado ihe ba, koto-kotosiki yau nare do, ihe ni ohi-iduru warahabe no kazu ohoku nari ni keru wo go-ran-ze sase m tote. Mahi nado narahasi hazime si, sono koto wo dani hatasa m tote. Hausi totonohe m koto, mata tare ni ka ha to omohi-megurasi-kane te nam, tuki-goro toburahi monosi tamaha nu urami mo sute te keru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
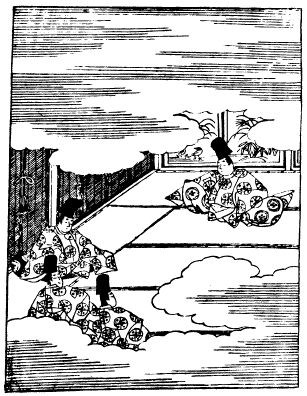 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.6.3 | とのたまふ御けしきの、うらなきやうなるものから、 いといと恥づかしきに、顔の色違ふらむとおぼえて、御いらへもとみに聞こえず。 |
とおっしゃるご様子が、何のこだわりないような一方で、とてもとても顔も上げられない思いに、顔色も変わるような気がして、お返事もすぐには申し上げられない。 |
とお言いになる院の御様子に、昔と変わった所もないのであるが、衛門督は |
to notamahu mi-kesiki no, uranaki yau naru monokara, ito ito hadukasiki ni, kaho no iro tagahu ram to oboye te, ohom-irahe mo tomi ni kikoye zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7 | 第七段 柏木と御賀について打ち合わせる |
11-7 Genji asks Kashiwagi for an advice about the celebrstion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.1 | 「 月ごろ、かたがたに思し悩む御こと、承り嘆きはべりながら、春のころほひより、例も患ひはべる乱り脚病といふもの、所狭く起こり患ひはべりて、はかばかしく踏み立つることもはべらず、月ごろに添へて沈みはべりてなむ、内裏などにも参らず、世の中跡絶えたるやうにて籠もりはべる。 |
「ここいく月、あちらの方こちらの方のご病気にご心配でいらっしゃったお噂を、お聞きいたしてお案じ申し上げておりましたが、春ごろから、普段も病んでおりました脚気という病気が、ひどくなって苦しみまして、ちゃんと立ち歩くこともできませんで、月日が経つにつれて臥せっておりまして、内裏などにも参内せず、世間とすっかり没交渉になったようにして家に籠もっておりました。 |
「長らく奥様がたが御病気をしておいでになりますことを承っておりまして、御心配を申し上げながら、前からございました |
"Tuki-goro, kata-gata ni obosi-nayamu ohom-koto, uketamahri nageki haberi nagara, haru no korohohi yori, rei mo wadurahi haberu midari kyakubyau to ihu mono, tokoro-seku okori wadurahi haberi te, haka-bakasiku humi taturu koto mo habera zu, tuki-goro ni sohe te sidumi haberi te nam, Uti nado ni mo mawira zu, yononaka ato taye taru yau ni te komori haberu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.2 | 院の御齢足りたまふ年なり、人よりさだかに数へたてまつり仕うまつるべきよし、致仕の大臣思ひ及び 申されしを、『 冠を掛け、車を惜しまず捨ててし身にて ★ ★、進み仕うまつらむに、つくところなし。げに、 下臈なりとも、同じごと深きところはべらむ。その心御覧ぜられよ』と、催し 申さるることのはべしかば、重き病を相助けてなむ、参りてはべし。 |
院のお年がちょうどにおなりあそばす年であり、誰よりも人一倍しっかりしたお祝いをして差し上げるよう、致仕の大臣も思って申されましたが、『冠を挂け、車を惜しまず捨てて官職を退いた身で、進み出てお祝い申し上げるようなのも身の置き所がない。なるほど、そなたは身分が低いと言っても、自分と同じように深い気持ちは持っていよう。その気持ちを御覧に入れなさい』と、催促申されることがございましたので、重病をあれこれ押して、参上いたしました。 |
院がおめでたい年に達せられますので、年来の御 |
Win no ohom-yohahi tari tamahu tosi nari, hito yori sadaka ni kazohe tatematuri tukau-maturu beki yosi, Tizi-no-Otodo omohi oyobi mausa re si wo, "Kauburi wo kake, kuruma wo wosima zu sute te si mi ni te, susumi tukau-matura m ni, tuku tokoro nasi. Geni, gerahu nari tomo, onazi goto hukaki tokoro habera m. Sono kokoro go-ran-ze rare yo." to, moyohosi mausa ruru koto no habe' sika ba, omoki yamahi wo ahi-tasuke te nam, mawiri te habe' si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.3 | 今は、いよいよいとかすかなるさまに思し澄まして、いかめしき御よそひを待ちうけたてまつりたまはむこと、願はしくも思すまじく見たてまつりはべしを、事どもをば削がせたまひて、 静かなる御物語の深き御願ひ叶はせたまはむなむ、まさりてはべるべき」 |
このごろは、ますますひっそりとしたご様子で俗世間のことはお考えにならずお過ごしあそばしていらっしゃいまして、盛大なお祝いの儀式をお待ち受け申されることは、お望みではありますまいと拝察いたしましたが、諸事簡略にあそばして、静かなお話し合いを心からお望みであるのを叶えて差し上げるのが、上策かと存じられます」 |
いよいよお寂しい静かな御生活のように拝見いたしましたあちらの御様子では、はなやかな賀宴をお持ち込みあそばすようなことは恐縮なされるだけではないかと拝察されまして、こちら様の御質素な御計画はかえって御満足になることかと存ぜられます」 |
Ima ha, iyo-iyo ito kasuka naru sama ni obosi-sumasi te, ikamesiki ohom-yosohi wo mati-uke tatematuri tamaha m koto, negahasiku mo obosu maziku mi tatematuri habe' si wo, koto-domo wo ba soga se tamahi te, siduka naru ohom-monogatari no hukaki ohom-negahi kanaha se tamaha m nam, masari te haberu beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.4 | と申したまへば、 いかめしく聞きし御賀の事を、女二の宮の御方ざまには言ひなさぬも、労ありと思す。 |
とお申し上げなさったので、盛大であったと聞いた御賀の事を、女二の宮の事とは言わないのは、大したものだとお思いになる。 |
と |
to mausi tamahe ba, ikamesiku kiki si ohom-ga no koto wo, Womna-Ni-no-Miya no ohom-kata zama ni ha ihi-nasa nu mo, rau ari to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.5 | 「 ただかくなむ。こと削ぎたるさまに世人は浅く見るべきを、さはいへど、心得てものせらるるに、 さればよとなむ、いとど思ひなられはべる。大将は、公方は、やうやう大人ぶめれど、かうやうに情けびたる方は、もとよりしまぬにやあらむ。 |
「ただこのとおりだ。簡略な様子に世間の人は浅薄に思うに違いないが、さすがに、よく分かってくれるので、思ったとおりで良かったと、ますます安心して来ました。大将は、朝廷の方では、だんだん一人前になって来たようだが、このように風流な方面は、もともと性に合わないのであろうか。 |
「私の所でやらせていただくことはこのとおりに簡単なことであるのを見て、一概に悪く言う人もあるであろうと思っていたが、理解のあるお言葉を聞いて、さすがにとあなたにはいよいよ敬意が払われる。大将は役人としては少しは経験ができたようでも、そうした繊細な観察をすることなどは、得意でもないだろうがいっこうだめですよ。 |
"Tada kaku nam. Koto-sogi taru sama ni yo-hito ha asaku miru beki wo, sa ha ihe do, kokoro-e te monose raruru ni, sare ba yo to nam, itodo omohi nara re haberu. Daisyau ha, ohoyake-gata ha, yau-yau otonabu mere do, kauyau ni nasakebi taru kata ha, moto yori sima nu ni ya ara m? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.6 | かの院、何事も心及びたまはぬことは、をさをさなきうちにも、楽の方のことは御心とどめて、いとかしこく知り調へたまへるを、 さこそ思し捨てたるやうなれ、静かに聞こしめし澄まさむこと、今しもなむ心づかひせらるべき。かの大将ともろともに見入れて、舞の童べの用意、心ばへ、よく加へたまへ。物の師などいふものは、ただわが立てたることこそあれ、いと口惜しきものなり」 |
あちらの院は、どのような事でもお心得のないことは、ほとんどない中でも、音楽の方面には御熱心で、まことに御立派に精通していらっしゃるから、そのように世をお捨てになっているようだが、静かにお心を澄まして音楽をお聞きになることは、このような時にこそ気づかいすべきでしょう。あの大将と一緒に面倒を見て、舞の子供たちの心構えや、嗜みをよく教えてやって下さい。音楽の師匠などというものは、ただ自分の専門についてはともかくも、他はまったくどうしようもないものです」 |
法皇はあらゆる芸術に通じておいでになるが、その中でも最も音楽の御 |
Kano Win, nani-goto mo kokoro oyobi tamaha nu koto ha, wosa-wosa naki uti ni mo, gaku no koto ha mi-kokoro todome te, ito kasikoku siri totonohe tamahe ru wo, sa koso obosi sute taru yau nare, siduka ni kikosimesi sumasa m koto, ima simo nam kokoro-dukahi se raru beki. Kano Daisyau to morotomoni mi-ire te, mahi no warahabe no youi, kokorobahe, yoku kuhahe tamahe. Mono-no-si nado ihu mono ha, tada waga tate taru koto koso are, ito kutiwosiki mono nari." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.7 | など、 いとなつかしくのたまひつくるを、うれしきものから、苦しくつつましくて、言少なにて、この御前をとく立ちなむと思へば、例のやうにこまやかにもあらで、やうやうすべり出でぬ。 |
などと、たいそうやさしくお頼みになるので、嬉しく思う一方で、辛く身の縮む思いがして、口数少なくこの御前を早く去りたいと思うので、いつものようにこまごまと申し上げず、やっとの思いで下がりになった。 |
などとお命じになるなつかしい味のある院の御様子をうれしく拝しながらもまた衛門督は恥ずかしく、きまり悪く思われて、言葉少なにしていて少しも早く御前を立って行きたいと願われる心から、以前のように細かい話しぶりは見せずにいるうち、ようやく願いどおりにここを去るによい時を見つけた。 |
nado, ito natukasiku notamahi tukuru wo, uresiki mono kara, kurusiku tutumasiku te, koto-sukuna ni te, kono o-mahe wo toku tati nam to omohe ba, rei no yau ni komayaka ni mo ara de, yau-yau suberi-ide nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7.8 | 東の御殿にて、大将のつくろひ出だしたまふ楽人、舞人の装束のことなど、またまた行なひ加へたまふ。あるべき限りいみじく 尽くしたまへるに、いとど詳しき心しらひ添ふも、 げにこの道は、いと深き人にぞものしたまふめる。 |
東の御殿で、大将が用意なさった楽人、舞人の装束のことなどを、さらに重ねて指図をお加えになる。できるかぎり立派になさっていた上に、ますます細やかな心づかいが加わるのも、なるほどこの道には、まことに深い人でいらっしゃるようである。 |
東北の御殿で大将が |
Himgasi no o-todo nite, Daisyau no tukurohi-idasi tamahu gaku-nin, mahi-bito no syauzoku no koto nado, mata mata okonahi kuhahe tamahu. Aru beki kagiri imiziku tukusi tamahe ru ni, itodo kuhasiki kokoro-sirahi sohu mo, geni kono miti ha, ito hukaki hito ni zo monosi tamahu meru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 3/10/2002 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 3/10/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 12/29/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 9/30/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経