34 若菜上(明融臨模本) |
WAKANA-NO-ZYAU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 三十九歳暮から四十一歳三月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from the end of 39 to March the age of 41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第七章 朧月夜の物語 こりずまの恋 |
7 Tale of Oborozukiyo The love of never knowing his failure to fall in it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | 第一段 源氏、朧月夜に今なお執心 |
7-1 Genji loves Oborozukiyo as eager as ever |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1 | 今はとて、女御、更衣たちなど、おのがじし別れたまふも、あはれなることなむ多かりける。 |
いよいよこれまでと、女御、更衣たちなど、それぞれお別れなさるのも、しみじみと悲しいことが多かった。 |
御出家の際に悲しがった |
Ima ha tote, Nyougo, Kaui-tati nado, onogazisi wakare tamahu mo, ahare naru koto nam ohokari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.2 | 尚侍の君は、故后の宮のおはしましし二条の宮にぞ住みたまふ。姫宮の御ことをおきては、この御ことをなむかへりみがちに、帝も思したりける。尼になりなむと思したれど、 |
尚侍の君は、故后の宮がいらっしゃった二条宮にお住まいになる。姫宮の御事をおいては、この方の御事を気がかりに、院の帝もお思いになっていたのであった。尼になってしまおうとお思いであったが、 |
|
Naisi no Kam-no-Kimi ha, ko-Kisai-no-Miya no ohasimasi si Nideu-no-miya ni zo sumi tamahu. Hime-Miya no ohom-koto wo oki te ha, kono ohom-koto wo nam kaheri-mi-gati ni, Mikado mo obosi tari keru. Ama ni nari na m to obosi tare do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.3 | 「 かかるきほひには、慕ふやうに心あわたたしく」 |
「そのように競って出家したのでは、後を追うようで気ぜわしいから」 |
この際それを実行するのは、人を慕って出家をすることで、悟った人のすることでない |
"Kakaru kihohi ni ha, sitahu yau ni kokoro-awatatasiku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.4 | と諌めたまひて、やうやう 仏の御ことなどいそがせたまふ。 |
と、お止めになって、だんだんと仏道の御事などをご準備おさせになる。 |
と院は御忠告をあそばして、ひたすら御自身の御寺の仏像の製作を急がせておいでになった。 |
to isame tamahi te, yau-yau Hotoke no ohom-koto nado isogase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.5 | 六条の大殿は、あはれに飽かずのみ思してやみにし御あたりなれば、年ごろも忘れがたく、 |
六条の大殿は、いとしく飽かぬ思いのままに別れてしまったお方の事なので、長年忘れがたく、 |
六条院はこの |
Rokudeu-no-Otodo ha, ahare ni aka-zu nomi obosi te yami ni si ohom-atari nare ba, tosi-goro mo wasure gataku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.6 | 「 いかならむ折に対面あらむ。今一たびあひ見て、その世のことも聞こえまほしく」 |
「どのような時に会えるだろう。もう一度お会いして、その当時の事もお話申し上げたい」 |
どんな機会にまた |
"Ika nara m wori ni taimen ara m? Ima hito-tabi ahi mi te, sono yo no koto mo kikoye mahosiku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.7 | のみ思しわたるを、かたみに世の聞き耳も憚りたまふべき身のほどに、いとほしげなりし世の騷ぎなども思し出でらるれば、よろづにつつみ過ぐしたまひけるを、 かうのどやかになりたまひて、 世の中を思ひしづまりたまふらむころほひの御ありさま、いよいよゆかしく、心もとなければ、あるまじきこととは思しながら、おほかたの御とぶらひにことつけて、あはれなるさまに常に聞こえたまふ。 |
と、ばかりお思い続けていらっしゃったが、お互いに世間の噂も遠慮なさらねばならないご身分であるし、お気の毒に思った当時の騷動なども、お思い出さずにはいらっしゃれないので、何事も心に秘めてお過ごしになったが、このようにのんびりとしたお身になられて、世の中を静かに御覧になっていらっしゃるこのごろのご様子を、ますますお会いしたく、気になってならないので、あってはならないこととはお思いになりながら、通例のお見舞いにかこつけて、心をこめた書きぶりで始終お便りを差し上げなさる。 |
と思召されるのであったが、双方とも世間の評のはばかられる身の上でもおありになって、女のためにも重い |
nomi obosi wataru wo, katami ni yo no kiki-mimi mo habakari tamahu beki mi no hodo ni, itohosige nari si yo no sawagi nado mo obosi-ide rarure ba, yorodu ni tutumi sugusi tamahi keru wo, kau nodoyaka ni nari tamahi te, yononaka wo omohi sidumari tamahu ram korohohi no ohom-arisama, iyo-iyo yukasiku, kokoro-motonakere ba, arumaziki koto to ha obosi nagara, ohokata no ohom-toburahi ni kototuke te, ahare naru sama ni tune ni kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.8 | 若々しかるべき御あはひならねば、御返りも時々につけて聞こえ交はしたまふ。昔よりもこよなくうち具し、 ととのひ果てにたる御けはひを見たまふにも、なほ忍びがたくて、 昔の中納言の君のもとにも、心深きことどもを常にのたまふ。 |
若い者どうしの色恋めいた間柄でもないので、お返事も時に応じてやりとりなさっていらっしゃる。若いころよりも格段に何もかもそなわって、すっかり円熟していらっしゃるご様子を御覧になるにつけても、やはり堪えがたくて、昔の中納言の君の許にも、切ない気持ちをいつもおっしゃる。 |
もう青春の男女のように、危険がる必要もないと思っては時々お返事も前尚侍は出した。昔に増してあらゆる点の完成されつつある跡の見える朧月夜の君の手紙がいっそうの魅力になって、昔の中納言の君の所へも、二人の逢う道を開かせようとする手紙を院は常に書いておいでになった。 |
Waka-wakasikaru beki ohom-ahahi nara ne ba, ohom-kaheri mo toki-doki ni tuke te kikoye-kahasi tamahu. Mukasi yori mo koyonaku uti-gusi, totonohi hate ni taru ohom-kehahi wo mi tamahu ni mo, naho sinobi-gataku te, mukasi no Tyuunagon-no-Kimi no moto ni mo, kokoro-hukaki koto-domo wo tune ni notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 第二段 和泉前司に手引きを依頼 |
7-2 Genji asks Izumi-no-Kami to lead to Oborozukiyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.1 | かの人の兄なる和泉の前の守を召し寄せて、若々しく、いにしへに返りて語らひたまふ。 |
その人の兄に当たる和泉前司を招き寄せて、若々しく、昔に返って相談なさる。 |
その女の兄である前 |
Kano hito no seuto naru Idumi-no-saki-no-Kami wo mesi-yose te, waka-wakasiku, inisihe ni kaheri te katarahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.2 | 「 ▼ 人伝てならで、物越しに聞こえ知らすべきことなむある。さりぬべく聞こえなびかして、いみじく忍びて参らむ。 |
「人を介してではなく、直接物越しに申し上げねばならないことがある。しかるべく申し上げご承知いただいた上で、たいそうこっそりと参上したい。 |
「取り次ぎをもって話をするようなことでなく、そして直接といっても物越しでいいのだが話さねばならぬ用が私にあるのだ。尚侍の承諾を得るようにしてくれれば、私はそっと |
"Hito-dute nara de, mono-gosi ni kikoye sirasu beki koto nam aru. Sarinubeku kikoye nabikasi te, imiziku sinobi te mawira m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.3 | 今は、さやうのありきも所狭き身のほどに、おぼろけならず忍ぶれば、そこにもまた人には漏らしたまはじと思ふに、 かたみにうしろやすくなむ」 |
今は、そのような忍び歩きも、窮屈な身分で、並々ならず秘密のことなので、そなたも他の人にはお漏らしなさるまいと思うゆえ、お互いに安心だ」 |
今はもう絶対にそんなこともできない身の上になっている私が、そうしようと思うのだから、あちらでも秘密にしていただけるだろうと安心はしている」 |
Ima ha, sayau no ariki mo tokoro-seki mi no hodo ni, oboroke nara zu sinobure ba, soko ni mo mata hito ni ha morasi tamaha zi to omohu ni, katami ni usiro-yasuku nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.4 | とのたまふ。尚侍の君、 |
とおっしゃる。尚侍の君は、 |
そのお話を中納言の君から聞いた時に、尚侍は、 |
to notamahu. Kam-no-Kimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.5 | 「 いでや。世の中を思ひ知るにつけても、昔よりつらき御心を、ここら思ひつめつる年ごろの果てに、 あはれに悲しき御ことをさし置きて、いかなる昔語りをか聞こえむ。 |
「さてどうしたものだろう。世間の事が分かって来たにつけても、昔から薄情なお心を、幾度も味わわされて来た長の年月の果てに、しみじみと悲しい御事をさしおいて、どのような昔話をお話し申し上げられようか。 |
「それは必要のない会見よ。私はもうあの時のような幼稚な心で人生を見ていない。昔から真実の欠けた愛しか私には持ってくださらなかった方の御誘惑などに今さらかからない。お気の毒な御生活に法皇様をお置きして、あの方とする昔の話など私にはない。 |
"Ide ya! Yononaka wo omohi-siru ni tuke te mo, mukasi yori turaki mi-kokoro wo, kokora omohi-tume turu tosi-goro no hate ni, ahare ni kanasiki ohom-koto wo sasi-oki te, ika naru mukasi-gatari wo ka kikoye m? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.6 | げに、人は漏り聞かぬやうありとも、 心の問はむこそいと恥づかしかるべけれ ★」 |
なるほど、他人は漏れ聞かないようにしたところで、良心に聞かれたら恥ずかしい気がするに違いない」 |
お言葉どおり秘密にはするとしても私自身の心に恥ずかしいことではないか」 |
Geni, hito ha mori kika nu yau ari to mo, kokoro no toha m koso ito hadukasikaru bekere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.7 | とうち嘆きたまひつつ、なほ、さらにあるまじきよしをのみ聞こゆ。 |
と嘆息をなさりながら、やはり、会うことはできない旨だけを申し上げる。 |
と |
to uti-nageki tamahi tutu, naho, sarani arumaziki yosi wo nomi kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 第三段 紫の上に虚偽を言って出かける |
7-3 Genji lies to Murasaki and goes out his house |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.1 | 「 いにしへ、わりなかりし世にだに、心交はしたまはぬことにもあらざりしを。げに、背きたまひぬる御ためうしろめたきやうにはあれど、あらざりしことにもあらねば、今しもけざやかにきよまはりて、 立ちにしわが名、今さらに取り返したまふべきにや ★」 |
「昔、逢瀬も難しかった時でさえ、お心をお通わしなさらないでもなかったものを。なるほど、ご出家なさったお方に対しては後ろ暗い気はするが、昔なかった事でもないのだから、今になって綺麗に潔白ぶっても、立ってしまった自分の浮名は、今さらお取り消しになることができるものでもあるまい」 |
すべてのものを無視して、苦しい中で愛し合った二人ではないか、出家をあそばされた院に対してやましいことではあるが、かつてなかったことではない関係なのだから、今になって清浄がっても昔の浮き名をあの人が取り返すことはできないのだ |
"Inisihe, wari nakari si yo ni dani, kokoro kahasi tamaha nu koto ni mo ara zari si wo. Geni, somuki tamahi nuru ohom-tame usirometaki yau ni ha are do, ara zari si koto ni mo ara ne ba, ima simo kezayaka ni kiyomahari te, tati ni si waga-na, imasara ni tori-kahesi tamahu beki ni ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.2 | と思し起こして、 この信太の森を ★道のしるべにて参うでたまふ。 女君には、 |
と、お思い起こして、この信太の森の和泉前司を道案内にしてお出かけになる。女君には、 |
と、こう院はお思いになって、にわかにこの和泉守を案内役として朧月夜の尚侍の二条の宮を訪ねる決心を院はあそばされたのであった。夫人の女王へは、 |
to obosi-okosi te, kono Sinoda-no-mori wo miti no sirube ni te maude tamahu. Womna-Gimi ni ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.3 | 「 東の院にものする常陸の君の、日ごろわづらひて久しくなりにけるを、もの騒がしき紛れに訪らはねば、いとほしくてなむ。昼など、けざやかに渡らむも便なきを、夜の間に忍びてとなむ、思ひはべる。人にもかくとも知らせじ」 |
「東の院にいらっしゃる常陸の君が、このところ久しく患っていましたのに、何かと忙しさに取り紛れて、お見舞いもしなかったので、お気の毒に思っております。昼間など、人目に立って出かけるのも不都合なので、夜の間にこっそりと、思っております。誰にもそうとは知らせまい」 |
「東の院にいる |
"Himgasi-no-win ni monosuru Hitati-no-Kimi no, hi-goro wadurahi te hisasiku nari ni keru wo, mono-sawagasiki magire ni toburaha ne ba, itohosiku te nam. Hiru nado, kezayaka ni watara m mo bin naki wo, yo no ma ni sinobi te to nam, omohi haberu. Hito ni mo kaku tomo sira se zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.4 | と聞こえたまひて、いといたく心懸想したまふを、 例はさしも見えたまはぬあたりを、あやし、と見たまひて、 思ひ合はせたまふこともあれど ★、 姫宮の御事の後は、何事も、いと過ぎぬる方のやうにはあらず、すこし隔つる心添ひて、見知らぬやうにておはす。 |
と申し上げなさって、とてもたいそう改まった気持ちでいらっしゃるのを、いつもはそれほどまでにはお思いでない方を、妙だ、と御覧になって、お思い当たりなさることもあるが、姫宮の御事の後は、どのような事も、まったく昔のようにではなく、少し隔て心がついて、見知らないようにしていらっしゃる。 |
と、お言いになって、院は外出の化粧におかかりになったが、ただ事とは思われなかった。平生はそんなにしてお行きになる所ではないのであるから夫人は不審をいだいたが、思い合わされることもないではないのを、 |
to kikoye tamahi te, ito itaku kokoro-gesau si tamahu wo, rei ha sasimo miye tamaha nu atari wo, ayasi, to mi tamahi te, omohi-ahase tamahu koto mo are do, Hime-Miya no ohom-koto no noti ha, nani-goto mo, ito sugi nuru kata no yau ni ha ara zu, sukosi hedaturu kokoro sohi te, mi sira nu yau ni te ohasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | 第四段 源氏、朧月夜を訪問 |
7-4 Genji visits to Oborozukiyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.1 | その日は、寝殿へも渡りたまはで、御文書き交はしたまふ。薫き物などに心を入れて暮らしたまふ。 |
その日は、寝殿へもお渡りにならず、お手紙だけを書き交わしなさる。薫物などを念入りになさって一日中お過ごしになる。 |
この日は寝殿へもお行きにならないでただ手紙をお書きかわしになっただけである。熱心に |
Sono hi ha, sin-den he mo watari tamaha de, ohom-humi kaki-kahasi tamahu. Taki-mono nado ni kokoro wo ire te kurasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.2 | 宵過ぐして、睦ましき人の限り、四、五人ばかり、網代車の、昔おぼえてやつれたるにて出でたまふ。和泉守して、御消息聞こえたまふ。かく渡りおはしましたるよし、ささめき聞こゆれば、驚きたまひて、 |
宵が過ぎるのを待って、親しい者ばかり、四、五人ほどで、網代車の、昔を思い出させる粗末なふうで、お出かけになる。和泉守を遣わして、ご挨拶を申し上げなさる。このようにいらっしゃった旨、小声で申し上げると、驚きなさって、 |
院は日の暮れるのを待っておいでになった。そしてきわめて親しい人を四、五人だけおつれになり、昔の |
Yohi sugusi te, mutumasiki hito no kagiri, si, go-nin bakari, aziro-guruma no, mukasi oboye te yature taru ni te ide tamahu. Idumi-no-Kami si te, ohom-seusoko kikoye tamahu. Kaku watari ohasimasi taru yosi, sasameki kikoyure ba, odoroki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.3 | 「 あやしく。いかやうに聞こえたるにか」 |
「変だこと。どのようにお返事申し上げたのだろうか」 |
「どうしてでしょう。私のお返事をどう聞き違えて申し上げたのだろう」 |
"Ayasiku. Ika yau ni kikoye taru ni ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.4 | とむつかりたまへど、 |
とご機嫌が悪いが、 |
尚侍は |
to mutukari tamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.5 | 「 をかしやかにて帰したてまつらむに、いと便なうはべらむ」 |
「気を持たせるようにしてお帰し申すのは、たいそう不都合でございましょう」 |
「いいかげんな口実を作りましてお帰しいたすことなどはもったいないことでございましょう」 |
"Wokasiyaka ni te kahesi tatematura m ni, ito bin-nau habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.6 | とて、あながちに思ひめぐらして、入れたてまつる。御とぶらひ など聞こえたまひて、 |
と言って、無理に工夫をめぐらして、お入れ申し上げる。お見舞いの言葉などを申し上げなさって、 |
と中納言の君は言って、無理な計らいまでして院を座敷へ御案内してしまった。院は見舞いの |
tote, anagati ni omohi-megurasi te, ire tatematuru. Ohom-toburahi nado kikoye tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.7 | 「 ただここもとに、物越しにても。さらに昔の あるまじき心などは、残らずなりにけるを」 |
「ただここまでお出ください、几帳越しにでも。まったく昔のけしからぬ心などは、無くなったのですから」 |
「ただここに近い所へまで出てくだすって、物越しでもお話しくださいませんか。今日はもう昔のような不都合なことをする心を持っていませんから」 |
"Tada kokomoto ni, mono-gosi ni te mo. Sarani mukasi no arumaziki kokoro nado ha, nokora zu nari ni keru wo!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.8 | と、わりなく聞こえたまへば、いたく嘆く嘆くゐざり出でたまへり。 |
と、切々と訴え申し上げなさるので、ひどく溜息をつきながらいざり出ていらっしゃった。 |
こう切に仰せられるので、尚侍はひどく |
to, warinaku kikoye tamahe ba, itaku nageku nageku wizari-ide tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.9 | 「 さればよ。なほ、気近さは」 |
「案の定だ。やはり、すぐに靡くところは」 |
だからこの人は軽率なのである |
"Sareba yo! Naho, ke-dikasa ha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.10 | と、かつ思さる。 かたみに、おぼろけならぬ御みじろきなれば、あはれも少なからず。 東の対なりけり。辰巳の方の廂に据ゑたてまつりて、御障子の しりばかりは固めたれば、 |
と、一方ではお思いになる。お互いに、知らないではない相手の身動きなので、感慨も浅からぬものがある。東の対だったのだ。辰巳の方の廂の間にお座りいただいて、御障子の端だけは固くとめてあるので、 |
と、満足を感じながらも院は批評をしておいでになった。これは二人にとって絶えて久しい場面であった。遠い世の思い出が女の心によみがえらないことでもないのである。東の対であった。東南の端の座敷に院はおいでになって、隣室の尚侍のいる所との間の |
to, katu obosa ru. Katami ni, oboroke nara nu ohom-miziroki nare ba, ahare mo sukunakara zu. Himgasi-no-tai nari keri. Tatumi no kata no hisasi ni suwe tatematuri te, mi-syauzi no siri bakari ha katame tare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.11 | 「 いと若やかなる心地もするかな。 年月の積もりをも、紛れなく数へらるる心ならひに、 かくおぼめかしきは、いみじうつらくこそ」 |
「とても若い者のような心地がしますね。あれからの年月の数をも、間違いなく数えられるほど思い続けているのに、このように知らないふりをなさるのは、たいそう辛いことです」 |
「何だか若者としての御待遇を受けているようで、これでは心が落ち着かないではありませんか。あれからどれだけの年月、日は幾つたつということまでも忘れない私としては、あなたのこの冷たさが恨めしく思われてなりませんよ」 |
"Ito wakayaka naru kokoti mo suru kana! Tosi-tuki no tumori wo mo, magire naku kazohe raruru kokoro-narahi ni, kaku obomekasiki ha, imiziu turaku koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.12 | と怨みきこえたまふ。 |
とお恨み申し上げなさる。 |
と、院はお恨みになった。 |
to urami kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 第五段 朧月夜と一夜を過ごす |
7-5 Genji spends a time in all night with Oborozukiyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.1 | 夜いたく更けゆく。 玉藻に遊ぶ鴛鴦の声々など ★、あはれに聞こえて、しめじめと人目少なき宮の内のありさまも、「 さも移りゆく世かな」と思し続くるに、 平中がまねならねど、まことに涙もろになむ。昔に変はりて、おとなおとなしくは聞こえたまふものから、「これをかくてや」と、引き動かしたまふ。 |
夜はたいそう更けて行く。玉藻に遊ぶ鴛鴦の声々などが、しみじみと聞こえて、ひっそりと人の少ない宮邸の中の様子を、「こうも変わってしまう世の中だな」とお思い続けると、平中の真似ではないが、ほんとうに涙が出てしまう。昔に変わって、落ち着いて申し上げなさる一方で、「この隔てをこのままでいられようか」と、引き動かしなさる。 |
夜はふけにふけてゆく。池の |
Yo itaku huke yuku. Tama-mo ni asobu wosi no kowe-gowe nado, ahare ni kikoye te, sime-zime to hitome sukunaki miya no uti no arisama mo, "Samo uturi-yuku yo kana!" to obosi tudukuru ni, Heityuu ga mane nara ne do, makoto ni namida-moro ni nam. Mukasi ni kahari te, otona-otonasiku ha kikoye tamahu mono kara, "Kore wo kaku te ya." to, hiki-ugokasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.2 | 「 年月をなかに隔てて逢坂の |
「長の年月を隔ててやっとお逢いできたのに |
年月を中に隔てて |
"Tosi-tuki wo naka ni hedate te Ahusaka no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.3 | さも 塞きがたく落つる涙か」 |
このような関があっては堰き止めがたく涙が落ちます」 |
さもせきがたく落つる涙か |
samo seki-gataku oturu namida ka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.4 | 女、 |
女、 |
院がこうお言いになっても、 |
Womna, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.5 | 「 涙のみ塞きとめがたきに清水にて |
「涙だけは関の清水のように堰き止めがたくあふれても |
涙のみせきとめがたき |
"Namida nomi seki-tome-gataki simidu ni te |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.6 | ゆき逢ふ道ははやく絶えにき」 |
お逢いする道はとっくに絶え果てました」 |
行き逢ふ道は早く絶えにき |
yuki-ahu miti ha hayaku taye ni ki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.7 | などかけ離れきこえたまへど、いにしへを思し出づるも、 |
などとまったくお受け付けにならないが、昔をお思い出しなさると、 |
というようなかけ離れた返辞を女はするにすぎなかったが、昔を思っては |
nado kake-hanare kikoye tamahe do, inisihe wo obosi-iduru mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.8 | 「 誰れにより、多うはさるいみじきこともありし世の騷ぎぞは」と思ひ出でたまふに、「 げに、今一たびの ★対面はありもすべかりけり」 |
「誰のせいで、あのような大変なことが起こり世の騷ぎもあったのか、この自分のせいではなかったか」とお思い出しなさると、「なるほど、もう一度会ってもいい事だ」 |
だれが原因になってこの方は遠い国に |
"Tare ni yori, ohou ha saru imiziki koto mo arisi yo no sawagi zo ha." to omohi-ide tamahu ni, "Geni, ima hito-tabi no taimen ha ari mo su bekari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.9 | と、思し弱るも、もとよりづしやかなるところはおはせざりし人の、年ごろは、さまざまに世の中を思ひ知り、来し方を悔しく、公私のことに触れつつ、数もなく思し集めて、いといたく過ぐしたまひにたれど、 昔おぼえたる御対面に、その世のことも遠からぬ心地して、え 心強くももてなしたまはず。 |
と、気弱におなりになるのも、もともと重々しい所がおありでなかった方で、この何年かは、あれこれと愛情の問題も分かるようになり、過去を悔やまれて、公事につけ私事につけ、数えきれないほど物思いが重なって、とてもたいそう自重してお過ごしなさって来たのだが、昔が思い出されるご対面に、その当時の事もそう遠くない心地がして、いつまでも気強い態度をおとりになれない。 |
と |
to, obosi-yowaru mo, motoyori dusiyaka naru tokoro ha ohase zari si hito no, tosi-goro ha, sama-zama ni yononaka wo omohi-siri, kisi-kata wo kuyasiku, ohoyake watakusi no koto ni hure tutu, kazu mo naku obosi atume te, ito itaku sugusi tamahi ni tare do, mukasi oboye taru ohom-taimen ni, sono yo no koto mo tohokara nu kokoti si te, e kokoro-duyoku mo motenasi tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.10 | なほ、らうらうじく、若うなつかしくて、一方ならぬ 世のつつましさをもあはれをも、思ひ乱れて、嘆きがちにてものしたまふけしきなど、今始めたらむよりもめづらしくあはれにて、明けゆくもいと口惜しくて、出でたまはむ空もなし。 |
昔に変わらず、洗練されて、若々しく魅力的で、並々でない世間への遠慮も思慕も、思い乱れて、溜息がちでいらっしゃるご様子など、今初めて逢った以上に新鮮で心が動いて、夜が明けて行くのもまことに残念に思われて、お帰りになる気もしない。 |
やはり最も |
Naho, rau-rauziku, wakau natukasiku te, hito-kata-nara-nu yo no tutumasisa wo mo ahare wo mo, omohi-midare te, nageki-gati ni te monosi tamahu kesiki nado, ima hazime tara m yori mo medurasiku ahare ni te, ake-yuku mo ito kutiwosiku te, ide tamaha m sora mo nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 第六段 源氏、和歌を詠み交して出る |
7-6 Genji goes out after exchanging waka with Oborozukiyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.1 | 朝ぼらけのただならぬ空に、 百千鳥の声もいとうららかなり。花は皆散り過ぎて、名残かすめる 梢の浅緑なる木立、「 昔、藤の宴したまひし、このころのことなりけりかし」と思し出づる、年月の積もりにけるほども、その折のこと、かき続けあはれに思さる。 |
朝ぼらけの美しい空に、百千鳥の声がとてもうららかに囀っている。花はみな散り終わって、その後に霞のかかった梢が浅緑の木立に、「昔、藤の宴をなさったのは、今頃の季節であったな」とお思い出される、あれからずいぶん歳月の過ぎ去った事も、その当時の事も、次から次へとしみじみと思い出される。 |
朝ぼらけの艶な空からは小鳥の声がうららかに聞こえてきた。花は皆散った春の暮れで、浅緑にかすんだ庭の木立ちをおながめになって、この家で昔 |
Asaborake no tada-nara-nu sora ni, momotidori no kowe mo ito uraraka nari. Hana ha mina tiri sugi te, nagori kasume ru kozuwe no asa-midori naru kodati, "Mukasi, hudi-no-en si tamahi si, konogoro no koto nari keri kasi." to obosi-iduru, tosituki no tumori ni keru hodo mo, sono wori no koto, kaki-tuduke ahare ni obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.2 | 中納言の君、見たてまつり送るとて、妻戸押し開けたるに、 立ち返りたまひて、 |
中納言の君、お見送り申し上げるために、妻戸を押し開けたが、立ち戻りなさって、 |
中納言の君がお見送りをするために妻戸をあけてすわっている所へ、いったん外へおいでになった院が帰って来られて、 |
Tyuunagon-no-Kimi, mi tatematuri okuru tote, tuma-do osi-ake taru ni, tati-kaheri tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.3 | 「 この藤よ。いかに染めけむ色にか。なほ、えならぬ心添ふ匂ひにこそ。いかでか、この 蔭をば立ち離るべき」 |
「この藤の花よ。どうしてこのように美しく染め出して咲いているのか。やはり、何とも言えない風情のある色あいだな。どうして、この花蔭を離れることができようか」 |
「この |
"Kono hudi yo! Ika ni some kem iro ni ka? Naho, e nara nu kokoro sohu nihohi ni koso. Ikade ka, kono kage wo ba tati-hanaru beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.4 | と、わりなく出でがてに思しやすらひたり。 |
と、どうしても帰りにくそうにためらっていらっしゃった。 |
こうお |
to, warinaku ide-gate ni obosi yasurahi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.5 | 山際よりさし出づる日のはなやかなるにさしあひ、目もかかやく心地する御さまの、こよなくねび加はりたまへる御けはひなどを、 めづらしくほど経ても見たてまつるは、まして世の常ならずおぼゆれば、 |
築山の端からさし昇ってくる朝日の明るい光に映えて、目も眩むように美しいお姿が、年とともにこの上なくご立派におなりになったご様子などを、久し振りに拝見するのは、いよいよ世の常の人とは思われない気がするので、 |
山から出た日のはなやかな光が院のお姿にさして目もくらむほどお美しい。この昔にもまさった御 |
Yamagiha yori sasi-iduru hi no hanayaka naru ni sasi-ahi, me mo kakayaku kokoti suru ohom-sama no, koyonaku nebi kuhahari tamahe ru ohom-kehahi nado wo, medurasiku hodo he te mo mi tatematuru ha, masite yo no tune nara zu oboyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.6 | 「 さる方にても、などか見たてまつり過ぐしたまはざらむ。 御宮仕へにも限りありて、際ことに離れたまふこともなかりしを。故宮の、よろづに心を尽くしたまひ、よからぬ世の騷ぎに、軽々しき御名さへ響きてやみにしよ」 |
「ご一緒になって、どうしてお暮らしにならなかったのだろうか。御宮仕えにも限度があって、特別のご身分になられることもなかったのに。故宮が、万事にお心を尽くしなさって、けしからぬ世の騷ぎが起こって、軽々しいお噂まで立って、それきりになってしまったことだわ」 |
過失のあったあとでは後宮に侍してはいても、表だった |
"Saru kata ni te mo, nado ka mi tatematuri sugusi tamaha zara m? Ohom-miya-dukahe ni mo kagiri ari te, kiha koto ni hanare tamahu koto mo nakari si wo! Ko-Miya no, yorodu ni kokoro wo tukusi tamahi, yokara nu yo no sawagi ni, karo-garosiki ohom-na sahe hibiki te yami ni si yo!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.7 | など思ひ出でらる。 名残多く残りぬらむ御物語の とぢめには、げに残りあらせまほしきわざ なめるを、御身、心にえまかせたまふまじく、ここらの人目もいと恐ろしくつつましければ、やうやうさし上がり行くに、 心あわたたしくて、 廊の戸に御車さし寄せたる人びとも、 忍びて声づくりきこゆ。 |
などと思い出される。尽きない思いが多く残っているだろうお話の終わりは、なるほど後を続けたいものであろうが、御身を、お心のままにおできになれず、大勢の人目に触れることもたいそう恐ろしく遠慮もされるので、だんだん日が上って行くので、気がせかれて、廊の戸に御車をつけ寄せた供人たちも、そっと催促申し上げる。 |
などとも尚侍は思っていた。 |
nado omohi-ide raru. Nagori ohoku nokori nu ram ohom-monogatari no todime ni ha, geni nokori ara se mahosiki waza na' meru wo, ohom-mi, kokoro ni e makase tamahu maziku, kokora no hito-me mo ito osorosiku tutumasikere ba, yau-yau sasi-agari yuku ni, kokoro-awatatasiku te, rau no to ni mi-kuruma sasi-yose taru hito-bito mo, sinobi te kowa-dukuri kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
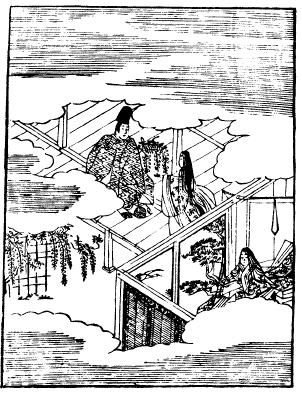 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.8 | 人召して、かの咲きかかりたる花、一枝折らせたまへり。 |
人を呼んで、あの咲きかかっている藤の花、一枝折らさせなさった。 |
院は庭にいた者に長くしだれた藤の花を一枝お折らせになった。 |
Hito mesi te, kano saki-kakari taru hana, hito-eda wora se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.9 | 「沈みしも忘れぬものを こりずまに |
「須磨に沈んで暮らしていたことを忘れないが |
沈みしも忘れぬものを懲りずまに |
"Sidumi si mo wasure nu mono wo korizuma ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.10 | 身も投げつべき宿の藤波」 |
また懲りもせずにこの家の藤の花に、淵に身を投げてしまいたい」 |
身も投げつべき宿の藤波 |
mi mo nage tu beki yado no hudi-nami |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.11 | いといたく思しわづらひて、寄りゐたまへるを、 心苦しう見たてまつる。女君も、今さらにいとつつましく、さまざまに思ひ乱れたまへるに、 花の蔭は、なほなつかしくて、 |
とてもひどく思い悩んでいらっしゃって、物に寄り掛かっていらっしゃるのを、お気の毒に拝し上げる。女君も、今さらにとても遠慮されて、いろいろと思い乱れていらっしゃるが、藤の花は、やはり慕わしくて、 |
と歌いながら院はお悩ましいふうで戸口によりかかっておいでになるのを、中納言の君はお気の毒に思っていた。尚侍は再び作られた関係を恥じて思い乱れているのであったが、やはり恋しく思う心はどうすることもできないのである。 |
Ito itaku obosi wadurahi te, yori-wi tamahe ru wo, kokoro-gurusiu mi tatematuru. Womna-Gimi mo, imasara ni ito tutumasiku, sama-zama ni omohi midare tamahe ru ni, hana no kage ha, naho natukasiku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.12 | 「 身を投げむ淵もまことの淵ならで |
「身を投げようとおっしゃる淵も本当の淵ではないのですから |
身を投げん |
"Mi wo nage m huti mo makoto no huti nara de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.13 | かけじやさらにこりずまの波」 |
性懲りもなくそんな偽りの波に誘われたりしません」 |
|
kake zi ya sarani korizuma no nami |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.14 | いと若やかなる 御振る舞ひを、心ながらもゆるさぬことに思しながら、 関守の固からぬたゆみに ★や、いとよく語らひおきて出でたまふ。 |
とても若々しいお振る舞いを、ご自分ながらも良くないこととお思いになりながら、関守が固くないのに気を許してか、たいそうよく後の逢瀬を約束してお帰りになる。 |
と女は言った。青年がするような行動を院は御自身も肯定できなくお思いになるのであるが、女の情熱の冷却してはいないことがうれしくて、またの会合を遂げうるようによく語っておゆきになった。 |
Ito wakayaka naru ohom-hurumahi wo, kokoro nagara mo yurusa nu koto ni obosi-nagara, seki-mori no katakara nu tayumi ni ya, ito yoku katarahi-oki te ide tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6.15 | そのかみも、人よりこよなく心とどめて思うたまへりし御心ざしながら、はつかにてやみにし御仲らひには、 いかでかはあはれも少なからむ。 |
その昔も、誰にも勝ってご執心でいらっしゃったご愛情であるが、わずかの契りで終わってしまったお二人の仲なので、どうして愛情の浅いことがあろうか。 |
昔も多くの中のすぐれた志で愛しておいでになりながら、やむなくお別れになった仲に、この一夜があったあとのお心はその人へ強くお |
Sono-kami mo, hito yori koyonaku kokoro todome te omou tamahe ri si mi-kokoro-zasi nagara, hatuka ni te yami ni si ohom-nakarahi ni ha, ikade ka ha ahare mo sukunakara m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 第七段 源氏、自邸に帰る |
7-7 Genji comes back to his home |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.1 | いみじく忍び入りたまへる御寝くたれのさまを待ち受けて、女君、 さばかりならむと心得たまへれど、おぼめかしくもてなしておはす。なかなかうちふすべなどしたまへらむよりも、 心苦しく、「 など、かくしも見放ちたまへらむ」と思さるれば、 ▼ ありしよりけに深き契りをのみ、長き世をかけて聞こえたまふ。 |
たいそう人目を忍んで入って来られたその寝乱れ髪の様子を待ち受けて、女君、そんなことだろうと、お悟りになっていたが、気づかないふりをしていらっしゃる。なまじやきもちを焼いたりなどなさるよりも、お気の毒で、「どうして、このように見放していられるのだろうか」と思わずにはいらっしゃれないので、以前よりもいっそう強い愛情を、永遠に変わらないことをお誓い申し上げなさる。 |
院は非常に静かに忍んで自室へおはいりになった。こうした女の所からのお帰り姿を見て、相手は尚侍あたりであろうと、夫人には想像されるのであったが、気のつかぬふうをしていた。かえって |
Imiziku sinobi-iri tamahe ru ohom-nekutare no sama wo mati-uke te, Womna-Gimi, sabakari nara m to kokoro-e tamahe re do, obomekasiku motenasi te ohasu. Naka-naka uti-husube nado si tamahe ra m yori mo, kokoro-gurusiku, "Nado, kaku simo mi-hanati tamahe ra m?" to obosa rure ba, arisi yori keni hukaki tigiri wo nomi, nagaki yo wo kake te kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.2 | 尚侍の君の御ことも、また漏らすべきならねど、いにしへのことも知りたまへれば、まほにはあらねど、 |
尚侍の君の御事も、他に漏らしてよいことではないが、昔のこともご存知でいらっしゃるので、ありのままではないが、 |
尚侍との間に復活させた情事は |
Kam-no-Kimi no ohom-koto mo, mata morasu beki nara ne do, inisihe no koto mo siri tamahe re ba, maho ni ha ara ne do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.3 | 「 物越しに、はつかなりつる対面なむ、残りある心地する。いかで人目咎めあるまじくもて隠しては、今一たびも」 |
「物越しに、ほんのちょっとお会いしましたので、物足りない気が致しています。何とか人に見咎められないように秘密にして、もう一度だけでも」 |
「物越しでやっと逢ってもらっただけでは心が残ってならない。人目を |
"Mono-gosi ni, hatuka nari turu taimen nam, nokori aru kokoti suru. Ikade hito-me togame aru maziku mote-kakusi te ha, ima hito-tabi mo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.4 | と、 語らひきこえたまふ。うち笑ひて、 |
と、打ち明けて申し上げなさる。軽く笑って、 |
とくらいにお話しになった。女王は笑って、 |
to, katarahi kikoye tamahu. Uti-warahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.5 | 「 今めかしくもなり返る御ありさまかな。 昔を今に改め加へたまふほど ★ ★、中空なる身のため苦しく」 |
「ずいぶん若返ったご様子ですこと。昔の恋を今さらむし返しなさるので、どっちつかずのよるべのないわたしには辛くて」 |
「お若返りにばかりなりますわね。昔を今にまた新しくお加えになっては、いよいよ私の影は薄くばかりなります」 |
"Imamekasiku mo nari kaheru ohom-arisama kana! Mukasi wo ima ni aratame kuhahe tamahu hodo, nakazora naru mi no tame kurusiku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.6 | とて、さすがに涙ぐみたまへるまみの、いと らうたげに見ゆるに、 |
とおっしゃって、そうはいうものの涙ぐんでいらっしゃる目もとが、とてもおいたわしく見えるので、 |
と言いながらも、涙ぐんだ目をしているのが |
tote, sasuga ni namidagumi tamahe ru mami no, ito rautage ni miyuru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.7 | 「 かう心安からぬ御けしきこそ苦しけれ。ただおいらかに引き抓みなどして、教へたまへ。隔てあるべくも、ならはしきこえぬを、思はずにこそなりにける御心なれ」 |
「このようにご機嫌の悪いご様子が辛いことです。いっそ素直に抓るなりなさって、叱ってください。他人行儀に思うこともおっしゃらないふうには、今までお仕向けしてこなかったのに、心外なお気持ちになってしまわれたお心ですね」 |
「いつもそんなふうに、寂しそうにばかりあなたがするから、私はたまらなく苦しくなる。もっと荒削りに、私を打つとか |
"Kau kokoro-yasukara nu mi-kesiki koso kurusikere. Tada oyiraka ni hiki-tumi nado si te, wosihe tamahe. Hedate aru beku mo, narahasi kikoye nu wo, omoha zu ni koso nari ni keru mi-kokoro nare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.8 | とて、よろづに御心とりたまふほどに、何ごとも え残したまはずなりぬめり。 |
とおっしゃって、いろいろとご機嫌をお取りになるうちに、何もかも残らず白状なさってしまったようである。 |
などとも言って、 |
tote, yorodu ni mi-kokoro tori tamahu hodo ni, nani-goto mo e nokosi tamaha zu nari nu meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.9 | 宮の御方にも、とみにえ渡りたまはず、 こしらへきこえつつおはします。姫宮は、何とも思したらぬを、御後見どもぞ 安からず聞こえける。わづらはしうなど見えたまふけしきならば、そなたもまして心苦しかるべきを、 おいらかにうつくしきもて遊びぐさに思ひきこえたまへり。 |
宮の御方にも、すぐにはお行きになることができずに、あれこれとおなだめ申してお過ごしになる。姫宮は、何ともお思いにならないが、ご後見人たちはご不満申し上げてるのであった。うるさいお方と思われなさるようなことであったら、あちらもこちら以上にお気の毒なはずだが、おっとりとしてかわいらしいお相手のようにお思い申し上げていらっしゃった。 |
姫宮のほうへお出かけにならずに、夫人をなだめるのに終日かかっておいでになった。それを宮は何ともお思いにならないのであるが、乳母たちだけは不快がっていろいろと言っていた。 |
Miya-no-Ohomkata ni mo, tomi ni e watari tamaha zu, kosirahe kikoye tutu ohasimasu. Hime-Miya ha, nani to mo obosi tara nu wo, ohom-usiromi-domo zo yasukara zu kikoye keru. Wadurahasiu nado miye tamahu kesiki nara ba, sonata mo masite kokoro-gurusikaru beki wo, oyiraka ni utukusiki mote-asobi-gusa ni omohi kikoye tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 11/15/2001 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 3/10/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 11/15/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 9/23/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経