34 若菜上(明融臨模本) |
WAKANA-NO-ZYAU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 三十九歳暮から四十一歳三月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from the end of 39 to March the age of 41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 朱雀院の物語 女三の宮の婿選び |
1 Tale of Suzaku Selection of Naishinno's bridegroom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 朱雀院、女三の宮の将来を案じる |
1-1 Suzaku is in anxiety about his daughter, Sam-no-Miya's future |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 朱雀院の帝、ありし御幸ののち、そのころほひより、例ならず悩みわたらせたまふ。もとよりあつしくおはしますうちに、このたびはもの心細く思し召されて、 |
朱雀院の帝、先日の行幸の後、そのころから、御不例でずっと御病気でおいであそばす。もともと御病気がちでいらせられるが、今回は何となく心細くお思いあさばされて、 |
あの六条院の |
Syuzyakuwin-no-Mikado, arisi mi-yuki no noti, sono korohohi yori, rei nara zu nayami watara se tamahu. Moto yori atusiku ohasimasu uti ni, kono tabi ha mono kokoro-bosoku obosimesa re te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 「 年ごろ行なひの本意深きを、后の宮おはしましつるほどは、よろづ 憚りきこえさせたまひて、今まで思しとどこほりつるを、なほその方にもよほすにやあらむ、世に久しかるまじき心地なむする」 |
「長年出家の願望は強いが、后の宮がご存命であった間は、いろいろと御遠慮申し上げなさって、今まで決意しないでいたが、やはりその方面に心が向くのだろうか、長くは生きていられないような気がする」 |
「私はもうずっと以前から信仰生活にはいりたかったのだが、太后がおいでになる間は自身の感情のおもむくままなことができないで今日に及んだのだが、これも仏の御催促なのか、もう余命のいくばくもないことばかりが思われてならない」 |
"Tosi-goro okonahi no ho'i hukaki wo, Kisai-no-Miya ohasimasi turu hodo ha, yorodu habakari kikoye sase tamahi te, ima made obosi-todokohori turu wo, naho sono kata ni moyohosu ni ya ara m, yo ni hisasikaru maziki kokoti nam suru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | などのたまはせて、さるべき御心まうけどもせさせたまふ。 |
などと仰せられて、しかるべきお心づもりをいろいろ御準備あそばす。 |
などと仰せになって、御出家をあそばされる場合の用意をしておいでになった。 |
nado notamahase te, saru-beki mi-kokoro mauke-domo se sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 御子たちは、春宮を おきたてまつりて、女宮たちなむ四所おはしましける。その中に、藤壷と聞こえしは、 先帝の源氏にぞおはしましける。 |
御子たちは、東宮を別に申して、女宮たちがお四方いらっしゃった。その中でも、藤壷と申し上げた方は、先帝の源氏でいらっしゃった。 |
皇子は東宮のほかに女宮様がただけが四人おいでになった。その中で |
Miko-tati ha, Touguu wo oki tatematuri te, Womna-Miya-tati nam yo-tokoro ohasimasi keru. Sono naka ni, Huditubo tokikoye si ha, Sendai no Genzi ni zo ohasimasi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | まだ坊と聞こえさせし時参りたまひて、高き位にも定まりたまべかりし人の、取り立てたる御後見もおはせず、母方もその筋となく、ものはかなき更衣腹にてものしたまひければ、御交じらひのほども心細げにて、大后の、尚侍を参らせたてまつりたまひて、かたはらに並ぶ人なくもてなしきこえたまひなどせしほどに、気圧されて、帝も御心のうちに、いとほしきものには思ひきこえさせたまひながら、下りさせたまひにしかば、かひなく口惜しくて、 世の中を恨みたるやうにて亡せたまひにし。 |
まだ東宮と申し上げた時代に入内なさって、高い地位にもおつきになるはずであった方が、これと言ったご後見役もいらっしゃらず、母方も名門の家柄でなく、微力の更衣腹でいらっしゃったので、ご交際ぶりも頼りなさそうで、大后が尚侍の君をお入れ申し上げなさって、側に競争相手がいないほど重くお扱い申し上げなさったりしたので、圧倒されて、帝も御心中に、お気の毒にはお思い申し上げあそばしながら、御譲位あそばしたので、入内した甲斐もなく残念で、世の中を恨むような有様でお亡くなりになった。 |
院がまだ東宮でいらせられた時代から侍していて、 |
Mada Bau to kikoye sase si toki mawiri tamahi te, takaki kurawi ni mo sadamari tama' bekari si hito no, tori-tate taru ohom-usiromi mo ohase zu, haha-kata mo sono sudi to naku, mono-hakanaki Kaui-bara nite monosi tamahi kere ba, ohom-mazirahi no hodo mo kokoro-bosoge ni te, Oho-Kisaki no, Naisi-no-Kami wo mawira se tatematuri tamahi te, katahara ni narabu hito naku motenasi kikoye tamahi nado se si hodo ni, keosa re te, Mikado mo mi-kokoro no uti ni, itohosiki mono ni ha omohi kikoye sase tamahi nagara, ori sase tamahi ni sika ba, kahinaku kutiwosiku te, yononaka wo urami taru yau ni te use tamahi ni si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | その御腹の女三の宮を、あまたの御中に、すぐれてかなしきものに思ひかしづききこえたまふ。 |
その腹の女三の宮を、大勢の御子たちの中で、特別にかわいがって大事になさっておいでになる。 |
その人のお生みした |
Sono ohom-hara no Womna-Sam-no-Miya wo, amata no ohom-naka ni, sugurete kanasiki mono ni omohi kasiduki kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | そのほど、御年、 十三、四ばかりおはす。 |
その当時、お年、十三、四歳ほどでいらっしゃる。 |
このころは十三、四でいらせられる。 |
Sono hodo, ohom-tosi, zihu-sam, si bakari ohasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8 | 「 今はと背き捨て、山籠もりしなむ後の世にたちとまりて、誰を ▼ 頼む蔭にてものしたまはむとすらむ」 |
「今を限りと世を捨てて、山籠もりした後に残って、誰を頼りとして行かれるのだろうか」 |
世の中を捨てて山寺へはいったあとに、残された内親王はだれをたよりに暮らすか |
"Ima ha to somuki-sute, yama-gomori si na m noti no yo ni tati-tomari te, tare wo tanomu kage ni te monosi tamaha m to su ram?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9 | と、ただこの御ことをうしろめたく思し嘆く。 |
と、ただこの御方のことだけが気がかりにお嘆きになる。 |
と思召されることが院の第一の御苦痛であった。 |
to, tada kono ohom-koto wo usirometaku obosi nageku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10 | 西山なる御寺造り果てて、移ろはせたまはむほどの御いそぎをせさせたまふに添へて、またこの宮の御裳着のことを思しいそがせたまふ。 |
西山にある御寺を完成させて、お移りあそばすための御準備をあそばすにつけても、またこの宮の御裳着の儀式を御準備あそばす。 |
西山に |
Nisi-yama naru mi-tera tukuri-hate te, uturoha se tamaha m hodo no ohom-isogi wo se sase tamahu ni sohe te, mata kono Miya no ohom-mogi no koto wo obosi isoga se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.11 | 院のうちにやむごとなく思す御宝物、御調度どもをばさらにもいはず、はかなき御遊びものまで、すこしゆゑある限りをば、ただこの御方に取りわたしたてまつらせたまひて、その次々をなむ、異御子たちには、御処分どもありける。 |
院の中に秘蔵していらっしゃる御宝物、御調度類は言うまでもなく、ちょっとしたお遊び道具類まで、少しでも由緒ある物は全て、ただこの御方にお譲り申し上げなさって、それに次ぐ品々を、他の御子たちには、御分配なさったのであった。 |
貴重な多くの御財産、美術の価値のあるお品々などはもとより、楽器や遊戯の具なども名品に近いような物は皆この宮へお譲りになって、その他の御財産、お道具類を他の宮がたへ御分配あそばされた。 |
Win no uti ni yamgotonaku obosu ohom-takara-nono, mi-teudo-domo wo ba sarani mo iha zu, hakanaki ohom-asobi mono made, sukosi yuwe aru kagiri wo ba, tada kono ohom-Kata ni tori watasi tatematura se tamahi te, sono tugi-tugi wo nam, koto-Miko-tati ni ha, ohom-syobun-domo ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 東宮、父朱雀院を見舞う |
1-2 Togu visits his father in Suzaku-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 春宮は、「かかる御悩みに添へて、世を背かせたまふべき御心づかひになむ」と聞かせたまひて、渡らせたまへり。母女御、添ひきこえさせたまひて参りたまへり。すぐれたる御おぼえにしもあらざりしかど、宮のかくておはします御宿世の、限りなくめでたければ、年ごろの御物語、こまやかに聞こえさせたまひけり。 |
東宮は、「このような御病気に加えて、御出家あそばすお心づもりだ」とお聞きあそばして、お越しあそばした。母女御、ご一緒申されておいでになった。格別のご寵愛というほどでもなかったが、東宮がこうしていらっしゃるご運勢が、この上なく素晴らしいので、久しぶりのお話、親しくお話し合いになったのであった。 |
東宮は院の重い御病気と、御出家の御用意のあることをお聞きになって、お見舞いの行啓をあそばされた。母君の女御もお付き添いして行った。 |
Touguu ha, "Kakaru ohom-nayami ni sohe te, yo wo somuka se tamahu beki mi-kokoro-dukahi ni nam." to kikase tamahi te, watara se tamahe ri. Haha-Nyougo, sohi kikoye sase tamahi te mawiri tamahe ri. Sugure taru ohom-oboye ni si mo ara zari sika do, Miya no kaku te ohasimasu ohom-sukuse no, kagiri naku medetakere ba, tosi-goro no ohom-monogatari, komayaka ni kikoye sase tamahi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 宮にも、よろづのこと、世をたもちたまはむ御心づかひなど、聞こえ知らせたまふ。 ▼ 御年のほどよりはいとよく大人びさせたまひて、御後見どもも、こなたかなた、軽々しからぬ仲らひにものしたまへば、いとうしろやすく思ひきこえさせたまふ。 |
東宮にも、いろいろなこと、国をお治めになる時の御注意など、お教え申し上げなさる。お年のわりにはとてもよくご成人あそばされていて、ご後見役たちも、あちらこちらと、重々しい立派なお間柄でいらっしゃるので、たいそう安心だとお思い申し上げていらっしゃる。 |
東宮にも帝王とおなりになる日のお心得事などをお教えあそばされるのであった。御 |
Miya ni mo, yorodu no koto, yo wo tamoti tamaha m mi-kokoro-dukahi nado, kikoye sira se tamahu. Ohom-tosi no hodo yori ha ito yoku otonabi sase tamahi kere ba, ohom-usiromi-domo mo, konata kanata, karo-garosikara nu nakarahi ni monosi tamahe ba, ito usiroyasuku omohi kikoye sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 「 この世に恨み残ることもはべらず。 女宮たちのあまた残りとどまる行く先を思ひやるなむ、 さらぬ別れにも ★ ほだしなりぬべかりける ★。さきざき、人の上に見聞きしにも、女は心よりほかに、あはあはしく、人に おとしめらるる宿世あるなむ、いと口惜しく悲しき。 |
「この世に不満の残ることはございません。女宮たちが大勢後に残るその行く末を思いやると、それがいざ別れとなる時にきっと障りとなることでしょう。これまで、他人事として見たり聞いたりしてきたことが、女は思いがけず、軽々しく、世間から批判される運命であるのが、たいそう残念で悲しいことだ。 |
「私はもうこの世に遺憾だと心に残るようなこともない。ただ内親王たちが幾人もいることで将来どうなるかと案ぜられることは、今の場合だけでなくこの世を離れる際にも |
"Kono yo ni urami nokoru koto mo habera zu. Womna-Miya tati no amata nokori todomaru yukusaki wo omohi-yaru nam, sara nu wakare ni mo hodasi nari nu bekari keru. Saki-zaki, hito no uhe ni mi-kiki si ni mo, womna ha kokoro yori hoka ni, aha-ahasiku, hito ni otosime raruru sukuse aru nam, ito kutiwosiku kanasiki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | いづれをも、 思ふやうならむ御世には、さまざまにつけて、御心とどめて思し尋ねよ。その中に、後見などあるは、さる方にも思ひ譲りはべり。 |
どなたをも、御即位なさった御代には、何かにつけて、お心にかけてお世話なさって下さい。その中で、後見人のいる方は、そちらに任せてよいと思います。 |
どの |
Idure wo mo, omohu yau nara m mi-yo ni ha, sama-zama ni tuke te, mi-kokoro todome te obosi-tadune yo. Sono naka ni, usiromi nado aru ha, saru kata ni mo omohi yuduri haberi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 三の宮なむ、いはけなき齢にて、ただ一人を頼もしきものとならひて、うち捨ててむ後の世に、ただよひさすらへむこと、いといとうしろめたく悲しくはべる」 |
三の宮は、幼いお年頃で、ただわたし一人をずっと頼りとしてきたので、出家した後の世に、寄るべもなく心細い生活をするだろうことを、とてもまことに気がかりで悲しく思っております」 |
女三の宮は年のゆかないのに母のない内親王なのだから、私だけをたよりにして育ってきたことを思うと、私が寺へはいったあとではどんな心細い身の上になることかと気がかりでならない」 |
Sam-no-Miya nam, ihakenaki yohahi ni te, tada hitori wo tanomosiki mono to narahi te, uti-sute te m noti no yo ni, tadayohi sasurahe m koto, ito ito usirometaku kanasiku haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | と、御目 おし拭ひつつ、聞こえ知らせさせたまふ。 |
と、お目を拭いながら、お聞かせ申し上げあそばす。 |
と、涙をお |
to, ohom-me osi-nogohi tutu, kikoye sira se sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 女御にも、 うつくしきさまに聞こえつけさせたまふ。 されど、女御の、人よりはまさりて時めきたまひしに、皆挑み交はしたまひしほど、御仲らひども、えうるはしからざりしかば、その名残にて、「 げに、今はわざと憎しなどはなくとも、まことに心とどめて思ひ後見むとまでは思さずもや」とぞ推し量らるるかし。 |
女御にも、やさしくして下さるようお頼み申し上げあそばす。けれども、母女御が、他の人よりは優れて御寵愛が厚かったために、皆が競争なさい合ったころ、お妃方の御仲も、あまりよろしくできなかったので、その影響で、「なるほど、今では特に憎いなどとは思わなくても、本当に心にかけてお世話しようとまではお思いでなかろう」と推量されるのである。 |
母君の女御にも信じ切ったようにして院は女三の宮のことを仰せになった。とはいっても昔宮中にあった時代には、内親王の御母の女御は格別な御 |
Nyougo ni mo, utukusiki sama ni kikoye tuke sase tamahu. Saredo, Nyougo no, hito yori ha masari te toki-meki tamahi si ni, mina idomi-kahasi tamahi si hodo, ohom-nakarahi-domo, e uruhasikara zari sika ba, sono nagori ni te, "Geni, ima ha wazato nikusi nado ha naku tomo, makoto ni kokoro todome te omohi usiromu to made ha omoha zu mo ya?" to zo osihakara ruru kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | 朝夕に、この御ことを思し嘆く。 年暮れゆくままに、御悩みまことに重くなりまさらせたまひて、御簾の外にも出でさせたまはず。御もののけにて、時々 悩ませたまふこともありつれど、いとかくうちはへをやみなきさまにはおはしまさざりつるを、「このたびは、なほ、限りなり」と思し召したり。 |
朝な夕なに、この方の御事を御心配なさる。年が暮れてゆくにつれて、御病気がほんとうに重くおなりあそばして、御簾の外にもお出ましにならない。御物の怪で、時々お悩みになったことはあったが、とてもこのようにいつまでもお悪いことはあり続けなかったが、「今度は、やはり、最期だ」とお思いでいらっしゃった。 |
院は明けても暮れても女三の宮の将来についてばかり御心配をあそばされるせいもあって、年末が近づいてから御容態がいちじるしくお悪くなり、 |
Asa-yuhu ni, kono ohom-koto wo obosi nageku. Tosi kure-yuku mama ni, ohom-nayami makoto ni omoku nari masara se tamahi te, mi-su no to ni mo ide sase tamaha zu. Ohom-mononoke ni te, toki-doki nayama se tamahu koto mo ari ture do, ito kaku uti-hahe wo-yami naki sama ni ha ohasimasa zari turu wo, "Kono tabi ha, naho, kagiri nari." to obosimesi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 御位を去らせたまひつれど、なほその世に頼みそめ たてまつりたまへる人びとは、今もなつかしくめでたき御ありさまを、心やりどころに参り仕うまつりたまふ限りは、心を尽くして惜しみきこえたまふ。 |
お位をお退きあそばしたが、やはりその当時にお頼り申し上げていらした方々は、今でもおやさしくご立派なお人柄を、心の慰め所にして参上しお仕えなさっている方々は、みな心の底からお悲しみ申し上げなさる。 |
御退位になってからも御在位時代に恩顧を受けた人たちは、今も優しく寛容な御性質をお慕い申し上げて、屈託なことのある時の慰安を賜わる所のようにして参候する |
Mi-kurawi wo sara se tamahi ture do, naho sono yo ni tanomi some tatematuri tamahe ru hito-bito ha, ima mo natukasiku medetaki ohom-arisama wo, kokoro-yari dokoro ni mawiri tukau-maturi tamahu kagiri ha, kokoro wo tukusi te wosimi kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 源氏の使者夕霧、朱雀院を見舞う |
1-3 Yugiri visits Suzaku as Genji's messenger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 六条院よりも、御訪らひしばしばあり。みづからも参りたまふべきよし、聞こし召して、院はいといたく喜びきこえさせたまふ。 |
六条院からも、お見舞いが頻繁にある。ご自身も参上なさる由、お聞きあそばして、院はとてもたいそうお喜び申し上げあそばす。 |
六条院からもお見舞いの使いが常に来た。そのうち御自身でもおいでになりたいという御通知のあった時、院は非常にお喜びになった。 |
Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-toburahi siba-siba ari. Midukara mo mawiri tamahu beki yosi, kikosi-mesi te, Win ha ito itaku yorokobi kikoye sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 中納言の君参りたまへるを、御簾の内に召し入れて、御物語こまやかなり。 |
中納言の君が参上なさったのを、御簾の中に招き入れて、お話を親密になさる。 |
六条院の御子の源中納言が参院した時に、御病室の |
Tyuunagon-no-Kimi mawiri tamahe ru wo, mi-su no uti ni mesi ire te, ohom-monogatari komayaka nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 「 故院の上の、今はのきざみに、あまたの御遺言ありし中に、この院の御こと、今の内裏の御ことなむ、取り分きてのたまひ置きしを、公けとなりて、こと限りありければ、うちうちの 御心寄せは、変らずながら、はかなきことのあやまりに、 心おかれたてまつることもありけむと思ふを、年ごろことに触れて、その恨み残したまへるけしきをなむ漏らしたまはぬ。 |
「故院の帝が、御臨終の際に、多くの御遺言があった中で、この院の御事と今上の帝の御事を、特別に仰せになったが、皇位に即くと、何かと自由にならないもので、心の中の好意は、変わらないものの、ちょっとした事の行き違いから、お恨まれ申されることもあっただろうと思うが、長年何かにつけて、その時の恨みが残っていらっしゃるご様子をお見せにならない。 |
「お |
"Ko-Win-no-Uhe no, ima ha no kizami ni, amata no go-yuigon ari si naka ni, kono Win no ohom-koto, Ima-no-Uti no ohom-koto nam, tori-waki te notamahi-oki si wo, Ohoyake to nari te, koto kagiri ari kere ba, uti-uti no mi-kokoro-yose ha, kahara zu nagara, hakanaki koto no ayamari ni, kokoro-oka re tatematuru koto mo ari kem to omohu wo, tosi-goro koto ni hure te, sono urami nokosi tamahe ru kesiki wo nam morasi tamaha nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 賢しき人といへど、身の上になりぬれば、こと違ひて、心動き、かならずその報い見え、ゆがめることなむ、 いにしへだに多かりける。 |
賢人と言っても、自分自身の事となると、話は違って、心が動揺し、必ずその報復をし、道を踏みはずす例は、昔でさえ多くあったのだ。 |
どんな賢人でも自身の問題になると恨むことも憎むことも凡人どおりにすることからいろいろな事件の起こるのは歴史の上にあることだからね。 |
Sakasiki hito to ihe do, mi no uhe ni nari nure ba, koto tagahi te, kokoro ugoki, kanarazu sono mukuyi miye, yugame ru koto nam, inisihe dani ohokari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | いかならむ折にか、その御心ばへほころぶべからむと、世の人もおもむけ疑ひけるを、つひに忍び過ぐしたまひて、 春宮などにも心を寄せきこえたまふ。今はた、またなく親しかるべき仲となり、睦び交はしたまへるも、限りなく心には思ひながら、本性の愚かなるに添へて、 子の道の闇にたち交じり ★、かたくななるさまにやとて、 なかなかよそのことに聞こえ放ちたるさまにてはべる。 |
どのような時にか、お恨みの心が漏れ出ることだろうかと、世間の人々もその気で疑っていたが、とうとう辛抱なさって、東宮などにもご好意をお寄せ申されていらっしゃる。今では、またとなく親しい姻戚関係になって交際していらっしゃるのも、この上なく有り難く心の中では思いながら、生来の愚かさに加えて、子を思う親心で目がくらみ、見苦しいことではないかと思って、かえってよそ事のようにお任せ申している有様でございます。 |
機会があれば私への復讐が姿になって現われることであろうと、世人も言うことだったし、私自身も罰を受ける気でいたのだが、あの方に見たのは絶対の愛だけだった。東宮などにも好意をお寄せになったり、また現在では |
Ika nara m wori ni ka, sono mi-kokorobahe hokorobu bekara m to, yo no hito mo omomuke utagahi keru wo, tuhini sinobi sugusi tamahi te, Touguu nado ni mo kokoro wo yose kikoye tamahu. Ima hata, mata naku sitasikaru beki naka to nari, mutubi-kahasi tamahe ru mo, kagiri naku kokoro ni ha omohi nagara, honzyau no oroka naru ni sohe te, ko no miti no yami ni tati-maziri, kataku naru sama ni ya tote, naka-naka yoso no koto ni kikoye hanati taru sama ni te haberu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 内裏の御ことは、かの御遺言違へず仕うまつりおきてしかば、かく 末の世の明らけき君として、来しかたの御面をも起こしたまふ。本意のごと、いとうれしくなむ。 |
帝の御事は、あの御遺言通りに致しましたので、このような末世の名君として、これまでの不面目を挽回して下さる。願い通りで、まことに嬉しく思います。 |
陛下のことは院の御遺言どおりに万事計らって位をお譲り申し上げたから、この聖天子を国民がいただきうることになり、私の不名誉まで取り返していただいている。これだけは意志を強くして遂行なしえた善事だと信じて満足している。 |
Uti no ohom-koto ha, kano go-yuigon tagahe zu tukau-maturi oki te sika ba, kaku suwe no yo no akirakeki Kimi to si te, ki-si-kata no ohom-omote wo mo okosi tamahu. Hoi no goto, ito uresiku nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | この秋の行幸の後 ★、いにしへのこととり添へて、ゆかしくおぼつかなくなむ おぼえたまふ。対面に聞こゆべきことどもはべり。かならずみづから訪らひものしたまふべきよし、もよほし申したまへ」 |
この秋の行幸の後は、昔のことがあれこれと思い出されて、懐かしくお会いしたく存じます。お目にかかって申し上げたいことどもがございます。必ずご自身お訪ね下さるよう、お勧め申し上げて下さい」 |
六条院にこの秋の行幸の節にお目にかかった時から、私の心にはしきりに青春時代の兄弟間の愛が再燃してお目にかかりたくてならない。直接お目にかかってお話し申したいこともある。ぜひ御自身でおいでくださるようにあなたからもお勧めしてほしい」 |
Kono aki no gyaugau no noti, inisihe no koto tori sohe te, yukasiku obotukanaku nam oboye tamahu. Taimen ni kikoyu beki koto-domo haberi. Kanara zu midukara toburahi monosi tamahu beki yosi, moyohosi mausi tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.8 | など、うちしほたれつつのたまはす。 |
などと、涙ぐみながら仰せになる。 |
などとしおれたふうで院が仰せられたのである。 |
nado, uti-sihotare tutu notamaha su. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 夕霧、源氏の言葉を言上す |
1-4 Yugiri leaves Genji's message for Suzaku |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
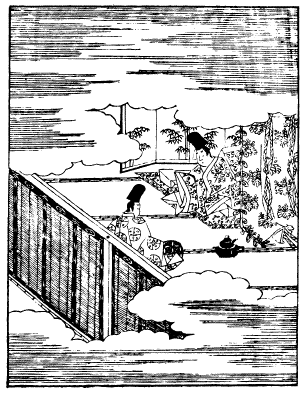 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 中納言の君、 |
中納言の君は、 |
Tyuunagon-no-Kimi, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 「 過ぎはべりにけむ方は、ともかくも思うたまへ分きがたくはべり。 年まかり入りはべりて、朝廷にも仕うまつりはべるあひだ、世の中のことを見たまへまかりありくほどには、大小のことにつけても、うちうちのさるべき物語などの ついでにも、『 いにしへのうれはしきことありてなむ』など、 うちかすめ申さるる折ははべらずなむ ★。 |
「過ぎ去りました昔の事は、何とも分りかねがたく存じます。成人いたしまして、朝廷にもお仕え致す間に、世間の事をあれこれと経験してまいりますうちに、大小の公事につけても、私的な打ち解けた話し合いの中でも、『昔の辛い思いをしたことがあって』などと、ほのめかされることはございませんでした。 |
「御過失でございましたか、正当な御処置でございましたか、昔のことは今になって御批評の申し上げようもございません。私が大人になりまして一官吏の職を奉じますようになりましてから、私のために院がいろいろの注意を実例によってお与えくださいます際などにも、自分は |
"Sugi haberi ni kem kata ha, tomo-kakumo omou tamahe waki gataku haberi. Tosi makari iri haberi te, Ohoyake ni mo tukau-maturi haberu ahida, yononaka no koto wo mi tamahe makari ariku hodo ni ha, dai-seu no koto ni tuke te mo uti-uti no saru-beki monogatari nado no tuide ni mo, "Inisihe no urehasiki koto ari te nam." nado, uti-kasume mausa ruru wori ha habera zu nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | 『 かく朝廷の御後見を ▼ 仕うまつりさして、静かなる思ひをかなへむと、ひとへに籠もりゐし後は、何ごとをも、知らぬやうにて、 故院の御遺言のごともえ仕うまつらず、 御位におはしましし世には、齢のほども、身のうつはものも及ばず、かしこき上の人びと多くて、その心ざしを遂げて御覧ぜらるることもなかりき。今、かく政事を去りて、静かにおはしますころほひ、心のうちをも隔てなく、参りうけたまはらまほしきを、 さすがに何となく所狭き身のよそほひにて、おのづから月日を過ぐすこと』 |
『このように朝廷の御後見を中途でご辞退申して、静かな暮らしをしようと、すっかり籠居して後は、どのような事をも、関係ないようにして、故院の御遺言通りにもお仕え申すことができず、御在位時代には、年齢も器量も不十分で、すぐれた上位の方々が多くて、わたしの思いを十分に尽くして御覧いただくこともありませんでした。今は、このように御退位なさって、静かにお暮らしになっていらっしゃるこの折に、思いのまま心おきなく、参上してお話を承りたいが、そうは言っても何やら大層な身分のために、ついつい月日を過ごしたていること』 |
一生を通じて陛下の御補佐をすべきであるのを、人生を静かに考えたい欲求から中途で閑散な地位に移らせていただいたために、故院の御遺言もお守りできぬことになり、またあなた様に対しては御在位の節には若輩であり、力もなく、上のかたがたが多くおいでにもなって、御自身の至誠をお尽くしする機会がなかったと申されまして、静かな御環境においでになります今日はせめてたびたび御訪問も申し上げてお話も承りたいのを、さすがに事の |
"Kaku Ohoyake no ohom-usiromi wo tukau-maturi sasi te, siduka naru omohi wo kanahe m to, hitohe ni komori wi si noti ha, nani-goto wo mo, sira nu yau ni te, ko-Win no go-yuigon no goto mo e tukau matura zu, mi-Kurawi ni ohasi masi si yo ni ha, yohahi no hodo mo, mi no utuha-mono mo oyoba zu, kasikoki kami no hito-bito ohoku te, sono kokorozasi wo toge te go-ran-ze raruru koto mo nakari ki. Ima, kaku maturigoto wo sari te, siduka ni ohasimasu korohohi, kokoro no uti wo mo hedate naku, mawiri uketamahara mahosiki wo, sasuga ni nani to naku tokoro-seki mi no yosohohi ni te, onodukara tuki-hi wo sugusu koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | となむ、折々嘆き申したまふ」 |
と、時々お嘆き申していらっしゃいます」 |
とこんなことをおりおり |
to nam, wori-wori nageki mausi tamahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | など、奏したまふ。 |
などと、奏上なさる。 |
などと中納言は申し上げた。 |
nado, sou-si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 二十にもまだわづかなるほどなれど ★、 いとよくととのひ過ぐして、容貌も盛りに匂ひて、いみじく きよらなるを、御目にとどめてうちまもらせたまひつつ、このもてわづらはせたまふ姫宮の御後見に、これをやなど、 人知れず思し寄りけり。 |
二十歳にもまだわずか足りない年齢であるが、まことに立派に年齢以上に成人して、器量も今を盛りに輝くばかりで、たいそう美しいので、お目に止めてじっと御覧あそばしながら、この御心中を悩ましていらっしゃる姫宮の御後見に、この人はどうかしらなどと、人知れずお考えよりになるのであった。 |
|
Ni-zihu ni mo mada waduka naru hodo nare do, ito yoku totonohi sugusi te, katati mo sakari ni nihohi te, imiziku kiyora naru wo, ohom-me ni todome te uti mamora se tamahi tutu, kono mote-waduraha se tamahu Hime-Miya no ohom-usiromi ni, kore wo ya nado, hito-sire-zu obosi-yori keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | 「 太政大臣のわたりに、今は住みつかれにたりとな。 年ごろ心得ぬさまに聞きしが、いとほしかりしを、耳やすきものから、 さすがにねたく思ふことこそあれ」 |
「太政大臣の邸に、今は落ちつかれたそうですね。長年わけの分からない話のように聞いたのは、気の毒に思ったが、ほっとしたものの、やはり残念に思うことがあります」 |
「太政大臣の家に行っているそうだね。長い間私なども大臣の態度を |
"Ohoki-Otodo no watari ni, ima ha sumi-tuka re ni tari to na. Tosi-goro kokoro-e nu sama ni kiki si ga, itohosikari si wo, mimi yasuki monokara, sasuga ni netaku omohu koto koso are." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | とのたまはする御けしきを、「いかにのたまはする にか」と、あやしく思ひめぐらすに、「 この姫宮をかく思し扱ひて、さるべき人あらば、預けて、心やすく世をも思ひ離ればや、となむ思しのたまはする」と、おのづから漏り聞きたまふ便りありければ、「 さやうの筋にや」とは思ひぬれど、 ふと心得顔にも、何かはいらへきこえさせむ。ただ、 |
と仰せになる御様子を、「何を仰せになろうとするのかしら」と、不思議に思って考えてみると、「こちらの姫宮をこのように御心配なさって、適当な人がいたら、頼んで、気楽に俗世を離れたい、とお思いになって仰せになるのだろう」と、自然と漏れ聞きなさる伝もあったので、「そのようなことではないか」とは思ったが、すぐさま分かったような顔をして、どうしてお答え申し上げられよう。ただ、 |
との院の仰せを不思議に思って中納言は考えてみたが、それは女三の宮のお身の上をとやかくとお案じになって、相当な人があれば結婚をさせて安心して宗教の中へはいりたいという |
to notamaha suru mi-kesiki wo, "Ikani notamaha suru ni ka?" to, ayasiku omohi-megurasu ni, "Kono Hime-Miya wo kaku obosi atukahi te, saru-beki hito ara ba, aduke te, kokoro-yasuku yo wo mo omohi hanare baya, to nam obosi notamahasuru." to, onodukara mori kiki tamahu tayori ari kere ba, "Sayau no sudi ni ya?" to ha omohi nure do, huto kokoro-e-gaho ni mo, nani ka ha irahe kikoye sase m? Tada, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | 「 はかばかしくもはべらぬ身には、寄るべもさぶらひがたくのみなむ」 |
「頼りにもならないわたしには、妻もなかなか得がたくございます」 |
「つまらない者でございますから、配偶者を得ますこともとかく困難でございまして」 |
"Haka-bakasiku mo habera nu mi ni ha, yorube mo saburahi gataku nomi nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | とばかり奏して止みぬ。 |
とだけお答え申し上げるにとどまった。 |
と申し上げるのにとどめた。 |
to bakari sou-si te yami nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 朱雀院の夕霧評 |
1-5 Suzaku criticizes Yugiri's personal character |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 女房などは、覗きて見きこえて、 |
女房などは、覗き見申して、 |
のぞき見をしていた若い女房たちが、 |
Nyoubau nado ha, nozoki te mi kikoye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 「 いとありがたくも見えたまふ容貌、用意かな」 |
「本当に立派にお見えになる容貌や、態度ですこと」 |
「珍しい美男でいらっしゃる。御様子だってねえ、 |
"Ito arigataku mo miye tamahu katati, youi kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | 「あな、めでた」 |
「ああ、素晴らしい」 |
なんというごりっぱさでしょう」 |
"Ana, medeta!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | など、集りて聞こゆるを、老いしらへるは、 |
などと、集まってお噂申し上げているのを、年輩の女房は、 |
集まってこんなことを言っているのを、聞いていた |
nado, atumari te kikoyuru wo, oyi-sirahe ru ha, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | 「 いで、さりとも、かの院のかばかりにおはせし御ありさまには、えなずらひきこえたまはざめり。いと目もあやにこそきらよにものしたまひしか」 |
「さあ、どうかしら、そうは言っても、あの院がこれぐらいお年でいらっしゃった時のご様子には、とてもお比べ申し上げることはおできになれません。実に眩しいほどお美しくいらっしゃいました」 |
「それでも六条院様のあのお年ごろのおきれいさというものはそんなものではありませんでしたよ。比較には、まあなりませんね、それはね、目もくらんでしまうほどお美しかったものですよ」 |
"Ide, saritomo, kano Win no kabakari ni ohase si ohom-arisama ni ha, e nazurahi kikoye tamaha za' meri. Ito me mo aya ni koso kiyora ni monosi tamahi sika." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | など、言ひしろふを聞こしめして、 |
などと、言い合うのをお耳にあそばして、 |
と言っても、若い人たちは承知をしない。こうした争いのお耳にはいった院が、 |
nado, ihi-sirohu wo kikosimesi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | 「 まことに、かれはいとさま異なりし人ぞかし。今はまた、その世にもねびまさりて、光るとはこれを言ふべきにやと見ゆる匂ひなむ、いとど加はりにたる。 うるはしだちて、はかばかしき方に見れば、いつくしくあざやかに、目も 及ばぬ心地するを、また、うちとけて、戯れごとをも言ひ乱れ遊べば、その方につけては、似るものなく愛敬づき、なつかしくうつきしきことの、 並びなきこそ、世にありがたけれ。 何ごとにも前の世推し量られて、めづらかなる人のありさまなり。 |
「本当に、あの方は特別の人であった。今はまた、あの当時以上に立派になって、光り輝くとはこれを言うべきなのかと見える輝きが、一段と加わっている。威儀を正して、公事に携わっているところを見ると、堂々として鮮やかで、目も眩ゆい気がするが、また一方に、うちくつろいで、冗談を言ってふざけるところは、その方面では、またとないほど愛嬌があって、親しみやすく愛らしいこと、この上ないのは、めったにいない人だ。何事につけても前世の果報が思いやられて、類稀な人柄だ。 |
「そのとおりだよ。あの人の美は普通の美の標準にはあてはまらないものだった。近ごろはまたいっそうりっぱになられて光彩そのもののような気がする。正しくしていられれば端麗であるし、打ち解けて |
"Makoto ni, kare ha ito sama kotonari si hito zo kasi. Ima ha mata, sono yo ni mo nebi masari te, hikaru to ha kore wo ihu beki ni ya to miyuru nihohi nam, itodo kuhahari ni taru. Uruhasi-dati te, haka-bakasiki kata ni mire ba, itukusiku azayaka ni, me mo oyoba nu kokoti suru wo, mata, utitoke te, tahabure goto wo mo ihi midare asobe ba, sono kata ni tuke te ha, niru mono naku aigyau-duki natukasiku utukusiki koto no, narabi naki koso, yo ni arigatakere. Nani goto ni mo saki-no-yo osihakara re te, meduraka naru hito no arisama nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.8 | 宮の内に生ひ出でて、帝王の限りなくかなしきものにしたまひ、さばかり 撫でかしづき、身に変へて思したりしかど、心のままにも驕らず、卑下して、二十がうちには、納言にもならずなりにきかし。一つ余りてや、宰相にて大将かけたまへりけむ。 |
宮中で成長して、帝王がこの上なくおかわいがりなさり、あれほど大事にし、わが身以上に大切になさったが、いい気になって増長することもなく、謙虚にして、二十歳までは、中納言にもならずじまいだった。一つ越してか、宰相で大将を兼官なさったろう。 |
宮廷で育って、帝王の愛を一身に集めるような幸福さがあって、まったくだよ。故院は御自身の命にも代えたいほど御大切にあそばしたものだが、それで慢心せず |
Miya no uti ni ohi-ide te, Teiwau no kagiri naku kanasiki mono ni si tamahi, sabakari nade kasiduki, mi ni kahe te obosi tari sika do, kokoro no mama ni mo ogora zu, hige si te, hatati ga uti ni ha, Nahugon ni mo nara zu nari ni ki kasi. Hito-tu amari te ya, Saisyau nite Daisyau kake tamahe ri kem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.9 | それに、これはいとこよなく進みにためるは、次々の子の世のおぼえのまさるなめりかし。まことに賢き方の才、心もちゐなどは、これもをさをさ劣るまじく、あやまりても、およすけまさりたるおぼえ、いと異 なめり」 |
それに比べて、こちらはこの上なく昇進しているのは、親から子へと次第に声望が高まっていくのであろう。本当に公事に関する才能、心構えなどは、こちらも決して父親に劣らず、たとい間違っても、年々老成してきたという評判は、たいそう格別なようだ」 |
それに比べると中納言の官等の上がり方は早い。子になり孫になりして威福の盛んになる家らしい。実際中納言は秀才であり、確かな教養を受けている点で昔の光源氏にあまり劣るまい。父君の昔に越えて幸福な道を踏んでもそれが不当とも思えない偉さが |
Sore ni, kore ha ito koyonaku susumi ni ta' meru ha, tugi-tugi no konoyo no oboye no masaru na' meri kasi. Makoto ni kasikoki kata no zae, kokoro-motiwi nado ha, kore mo wosa-wosa otoru maziku, ayamari te mo, oyosuke masari taru oboye, ito koto na' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10 | など、めでさせたまふ。 |
などと、お誉めあそばす。 |
と御 |
nado, mede sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 第六段 女三の宮の乳母、源氏を推薦 |
1-6 Sam-no-Miya's wet nurse recommends Genji for her bridegroom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1 | 姫宮のいとうつくしげにて、若く何心なき御ありさまなるを見たてまつりたまふにも、 |
姫宮がとてもかわいらしげで、幼く無邪気なご様子であるのを拝見なさるにつけても、 |
|
Hime-Miya no ito utukusige ni te, wakaku nani-gokoro-naki ohom-arisama naru wo mi tatematuri tamahu ni mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | 「 見はやしたてまつり、かつは、まだ片生ひならむことをば、見隠し教へきこえつべからむ人の、うしろやすからむに預けきこえばや」 |
「はなやかにお世話して上げ、また一方では、至らないところは、見知らない体でそっと教えて上げるような人で、安心な方にお預け申したいものだ」 |
「十分愛してくれて、足りない所は |
"Mi-hayasi tatematuri, katu ha, mada kata-ohi nara m koto wo ba, mi kakusi wosihe kikoye tu bekara m hito no, usiroyasukara m ni aduke kikoye baya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | など 聞こえたまふ。 |
などとお申し上げになる。 |
などと仰せられた。 |
nado kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.4 | 大人しき御乳母ども召し出でて、御裳着のほどのことなどのたまはするついでに、 |
年かさの御乳母たちを御前に召し出して、御裳着の時の事などを仰せになる折に、 |
|
Otonasiki ohom-menoto-domo mesi-ide te, ohom-mogi no hodo no koto nado notamaha suru tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.5 | 「 六条の大殿の、式部卿親王の女生ほし立てけむやうに、この宮を預かりて育まむ人もがな。ただ人の中にはありがたし。内裏には中宮さぶらひたまふ。次々の女御たちとても、いと やむごとなき限りものせらるるに、はかばかしき後見なくて、 さやうの交じらひ、いとなかなかならむ。 |
「六条の大殿が、式部卿の親王の娘を育て上げたというように、この姫宮を引き取って育ててくれる人がいないものか。臣下の中ではいそうにない。主上には中宮がいらっしゃる。それに次ぐ女御たちにしても、たいそう高貴な家柄の方ばかりが揃っていられるから、しっかりした御後見役がいなくて、そのような宮廷生活は、かえってしないほうがましだろう。 |
「六条院が |
"Rokudeu-no-Otodo no, Sikibukyau-no-Miko-no-Musume ohosi-tate kem yau ni, kono Miya wo adukari te hagukuma m hito mo gana. Tadaudo no naka ni ha ari-gatasi. Uti ni ha Tyuuguu saburahi tamahu. Tugi-tugi no Nyougo-tati tote mo, ito yamgotonaki kagiri monose raruru ni, haka-bakasiki usiromi naku te, sayau no mazirahi, ito naka-naka nara m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.6 | この権中納言の朝臣の独りありつるほどに、うちかすめてこそ試みるべかりけれ。若けれど、いと警策に、生ひ先 頼もしげなる 人にこそあめるを」 |
この権中納言の朝臣が独身でいた時に、こっそり打診してみるべきであった。若いけれど、たいそう有能で、将来有望な人と思えるから」 |
今日の権中納言が独身でいたころに話をしてみるのだった。若いがりっぱな秀才で将来の頼もしい人らしいのに」 |
Kono Gon-no-Tyuunagon-no-Asom no hitori ari turu hodo ni, uti-kasume te koso kokoromiru bekari kere. Wakakere do, ito kyauzaku ni, ohisaki tanomosige naru hito ni koso a' meru wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.7 | とのたまはす。 |
と仰せになる。 |
こんなこともお言いになった。 |
to notamahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.8 | 「 中納言は、もとよりいとまめ人にて、 年ごろも、かのわたりに心をかけて、ほかざまに思ひ移ろふべくもはべらざりけるに、その思ひ叶ひては、いとど揺るぐ方はべらじ。 |
「中納言は、もともとたいそう生真面目な方で、長年、あの方に心を懸けて、他の女性には心を移そうともしなかったのでございますから、その願いが叶ってからは、ますますお心の動くはずがございますまい。 |
「中納言は初めからまじめ一方な方でございますから、今までも初恋のあの奥様のことばかりを思いつめて、失恋時代にもほかの話に耳をかさなかった人でございました。そのお姫様とごいっしょにおなりになったただ今では、第二の結婚のお話があの方を動かしうるものでもございますまい。 |
"Tyuunagon ha, motoyori ito mame-bito nite, tosi-goro mo, kano watari ni kokoro wo kake te, hoka-zama ni omohi uturohu beku mo habera zari keru ni, sono omohi kanahi te ha, itodo yurugu kata habera zi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.9 | かの院こそ、なかなか、なほいかなるにつけても、 人をゆかしく思したる心は、絶えずものせさせたまふなれ。その中にも、 やむごとなき御願ひ深くて、前斎院などをも、今に忘れがたくこそ、聞こえたまふなれ」 |
あの院こそは、かえって、依然としてどのようなことにつけても、女性にご関心の心は、引き続きお持ちのようでいらっしゃると聞いております。その中でも、高貴な女性を得たいとのお望みが深くて、前斎院などをも、今でも忘れることができずに、お便りを差し上げていらっしゃると聞いております」 |
私どもはかえって六条院様にその可能性がおありになるように存じ上げます。恋愛好きで女性に好奇心をお持ちになることは今も昔のままのようだと申すことでございます。その中でも最高の貴女に趣味をお持ちあそばして、前斎院様などを今になっても思っておいでになるそうでございます」 |
Kano Win koso, naka-naka, naho ika naru ni tuke te mo, hito wo yukasiku obosi taru kokoro ha, taye zu monose sase tamahu nare. Sono naka ni mo, yamgotonaki ohom-negahi hukaku te, saki-no-Saiwin nado wo mo, ima ni wasure gataku koso, kikoye tamahu nare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.10 | と申す。 |
と申し上げる。 |
と女宮の乳母の一人が申し上げた。 |
to mausu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.11 | 「 いで、その旧りせぬあだけこそは、いとうしろめたけれ」 |
「いや、その変わらない好色心が、たいそう心配だ」 |
「その今でも恋愛好きである点はありがたくないことだね」 |
"Ide, sono huri se nu adake koso ha, ito usirometakere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.12 | とはのたまはすれど、 |
とは仰せになるが、 |
院はこう仰せられたが、 |
to ha notamahasure do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.13 | 「 げに、あまたの中にかかづらひて、めざましかるべき思ひはありとも、なほやがて親ざまに定めたるにて、さもや譲りおききこえまし」 |
「なるほど、大勢の婦人方の中に混じって、不愉快な思いをすることがあったとしても、やはり親代わりと決めたことにして、そのようにお譲り申そうか」 |
乳母が言うように六条院には多くの夫人や愛人があって、唯一の妻と認めさせることはできないでも、やはりその人を親代わりの |
"Geni, amata no naka ni kakadurahi te, mezamasikaru beki omohi ha ari tomo, naho yagate oya-zama ni sadame taru ni te, samoya yuduri-oki kikoye masi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.14 | なども、思し召すべし。 |
などとも、お考えになるのだろう。 |
というお考えを院はあそばしたようである。 |
nado mo, obosimesu besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.15 | 「 まことに、少しも世づきてあらせむと思はむ女子持たらば、同じくは、かの人のあたりにこそ、触ればはせまほしけれ。いくばくならぬこの世のあひだは、 さばかり心ゆくありさまにてこそ、過ぐさまほしけれ。 |
「ほんとうに、少しでも結婚させようと思うような女の子を持っていたら、同じことなら、あの院の側に、添わせたいものだ。長くもない人生では、あのように満ち足りた気持ちで、過ごしたいものだ。 |
「おまえの言うことはおもしろいよ。よい生き方をさせたいと思う女の子があって、配偶を求めるなら、あの院に愛されることを願うのがほんとうのようだ。人生は短いのだから、生きがいのあることをだれも願うべきだよ。 |
"Makoto ni, sukosi mo yoduki te ara se m to omoha m womna-go mo' tara ba, onaziku ha, kano hito no atari ni koso, hurebaha se mahosikere. Ikubaku nara nu konoyo no ahida ha, sabakari kokoro-yuku arisama ni te koso, sugusa mahosikere. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.16 | われ女ならば、同じはらからなりとも、かならず 睦び寄りなまし。若かりし時など、さなむおぼえし。まして、女の欺かれむは、いと、ことわりぞや」 |
わたしが女だったら、同じ姉弟ではあっても、きっと睦まじい仲になっていただろう。若かった時など、そのように思った。ましてや、女がだまされたりするようなのは、まことに、もっともなことだ」 |
私が女であれば兄弟であっても兄弟以上の接近もすることだろう。真実若い時に私はそう思ったのだ。そうなのだから女が誘惑にかかるのは道理で、また自然なことなのだよ」 |
Ware womna nara ba, onazi harakara nari tomo, kanarazu mutubi-yori na masi. Wakakari si toki nado, sa nam oboye si. Masite, Womna no azamuka re m ha, ito, kotowari zo ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.17 | とのたまはせて、 御心のうちに、尚侍の君の御ことも、思し出でらるべし。 |
と仰せになって、御心中に、尚侍の君の御事も、自然とお思い出しになっているのであろう。 |
院は |
to notamahase te, mi-kokoro no uti ni, Kam-no-Kimi no ohom-koto mo, obosi-ide raru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 11/15/2001 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 3/10/2002 渋谷栄一注釈(ver.1-1-3) |
Last updated 11/15/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 9/23/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経