25 蛍(大島本) |
HOTARU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の太政大臣時代 三十六歳の五月雨期の物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, rainy days in May at the age of 36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 玉鬘の物語 蛍の光によって姿を見られる |
1 Tale of Tamakazura She is shown her figure by Hyoubukyou-no-Miya through a light of fireflies |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 玉鬘、養父の恋に悩む |
1-1 Tamakazura is troubuled with her stepfather's love |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 今はかく重々しきほどに、よろづのどやかに思ししづめたる御ありさまなれば、 頼みきこえさせたまへる人びと、さまざまにつけて、皆思ふさまに定まり、ただよはしからで、あらまほしくて過ぐしたまふ。 |
今はこのように重々しい身分ゆえに、何事にももの静かに落ち着いていらっしゃるご様子なので、ご信頼申し上げていらっしゃる方々は、それぞれ身分に応じて、皆思いどおりに落ち着いて、不安もなく、理想的にお過ごしになっている。 |
Ima ha kaku omo-omosiki hodo ni, yorodu nodoyaka ni obosi-sidume taru mi-arisama nare ba, tanomi kikoye sase tamahe ru hito-bito, sama-zama ni tuke te, mina omohu sama ni sadamari, tadayohasi kara de, aramahoisiku te sugusi tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 対の姫君こそ、 いとほしく、思ひのほかなる思ひ添ひて、いかにせむと思し乱るめれ。 かの監が憂かりしさまには、なずらふべきけはひならねど、かかる筋に、かてけも人の思ひ寄りきこゆべきことならねば、 心ひとつに思しつつ、「様ことに疎まし」と思ひきこえたまふ。 |
対の姫君だけは、気の毒に、思いもしなかった悩みが加わって、どうしようかしらと困っていらしゃるようである。あの監が嫌だった様子とは比べものにならないが、このようなことで、夢にも回りの人々がお気づき申すはずのないことなので、自分の胸一つをお痛めになりながら、「変なことで嫌らしい」とお思い申し上げなさる。 |
Tai no Hime-Gimi koso, itohosiku, omohi no hoka naru omohi sohi te, ikani se m to obosi-midaru mere. Kano Gen ga ukari si sama ni ha, nazurahu beki kehahi nara ne do, kakaru sudi ni, kakete mo hito no omohi-yori kikoyu beki koto nara ne ba, kokoro hitotu ni obosi tutu, "Sama koto ni utomasi" to omohi kikoye tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 何ごとをも思し知りにたる御齢なれば、とざまかうざまに思し集めつつ、母君のおはせずなりにける口惜しさも、またとりかへし惜しく悲しくおぼゆ。 |
どのようなことでもご分別のついているお年頃なので、あれやこれやとお考え合わせになっては、母君がお亡くなりになった無念さを、改めて惜しく悲しく思い出される。 |
Nani-goto wo mo obosi siri ni taru ohom-yohahi nare ba, tozama kauzama ni obosi atume tutu, Haha-Gimi no ohase zu nari ni keru kutiwosisa mo, mata tori-kahesi wosiku kanasiku oboyu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 大臣も、うち出でそめたまひては、なかなか苦しく思せど、人目を憚りたまひつつ、はかなきことをもえ聞こえたまはず、苦しくも思さるるままに、しげく渡りたまひつつ、御前の人遠く、のどやかなる折は、 ただならずけしきばみきこえたまふごとに、 胸つぶれつつ、けざやかにはしたなく聞こゆべきにはあらねば、ただ見知らぬさまにもてなしきこえたまふ。 |
大臣も、お口にいったんお出しになってからは、かえって苦しくお思いになるが、人目を遠慮なさっては、ちょっとした言葉もお話しかけになれず、苦しくお思いになるので、頻繁にお越しになっては、お側に女房などもいなくて、のんびりとした時には、穏やかならぬ言い寄りをなさるたびごとに、胸を痛め痛めしては、はっきりとお拒み申し上げることができないので、ただ素知らぬふりをしてお相手申し上げていらっしゃる。 |
Otodo mo, uti-ide some tamahi te ha, naka-naka kurusiku obose do, hitome wo habakari tamahi tutu, hakanaki koto wo mo e kikoye tamaha zu, kurusiku mo obosa ruru mama ni, sigeku watari tamahi tutu, o-mahe no hito tohoku, nodoyaka naru wori ha, tada-nara-zu kesiki-bami kikoye tamahu goto ni, mune tubure tutu, kezayaka ni hasitanaku kikoyu beki ni ha ara ne ba, tada mi-sira nu sama ni motenasi kikoye tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | 人ざまのわららかに、気近くものしたまへば、 いたくまめだち、心したまへど、なほをかしく愛敬づきたるけはひのみ見えたまへり。 |
人柄が明朗で、人なつこくいらっしゃるので、とてもまじめぶって、用心していらっしゃるが、やはりかわいらしく魅力的な感じばかりが目立っていらっしゃる。 |
Hito-zama no wararaka ni, ke-dikaku monosi tamahe ba, itaku mamedati, kokoro si tamahe do, naho wokasiku aigyau-duki taru kehahi nomi miye tamahe ri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 兵部卿宮、六条院に来訪 |
1-2 Hyoubukyou-no-Miya visits to Rokujoin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 兵部卿宮などは、まめやかにせめきこえたまふ。御労のほどはいくばくならぬに、 ▼ 五月雨になりぬる愁へをしたまひて、 |
兵部卿宮などは、真剣になってお申し込みなさる。お骨折りの日数はそれほどたってないのに、五月雨になってしまった苦情を訴えなさって、 |
Hyaubukyau-no-Miya nado ha, mameyaka ni seme kikoye tamahu. Go-rau no hodo ha ikubaku nara nu ni, samidare ni nari nuru urehe wo si tamahi te, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 「 すこし気近きほどをだに許したまはば、思ふことをも、片端はるけてしがな」 |
「もう少しお側近くに上がることだけでもお許し下さるならば、思っていることも、少しは晴らしたいものですね」 |
"Sukosi ke-dikaki hodo wo dani yurusi tamaha ba, omohu koto wo mo, katahasi haruke te si gana!" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | と、聞こえたまへるを、殿御覧じて、 |
と、申し上げになさるのを、殿が御覧になって、 |
to, kikoye tamahe ru wo, Tono go-ran-zi te, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | 「 なにかは。この君達の好きたまはむは、見所ありなむかし。もて離れてな聞こえたまひそ。御返り、時々聞こえたまへ」 |
「何のかまうことがあろうか。この公達が言い寄られるのは、きっと風情があろう。そっけないお扱いをなさるな。お返事は、時々差し上げなさい」 |
"Nani ka ha? Kono Kim-dati no suki tamaha m ha, mi-dokoro ari na m kasi. Mote-hanare te na kikoye tamahi so. Ohom-kaheri, toki-doki kikoye tamahe." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | とて、教へて書かせたてまつりたまへど、いとどうたておぼえたまへば、「乱り心地悪し」とて、聞こえたまはず。 |
とおっしゃって、教えてお書かせ申し上げなさるが、ますます不愉快なことに思われなさるので、「気分が悪い」と言って、お書きにならない。 |
tote, wosihe te kaka se tatematuri tamahe do, itodo utate oboye tamahe ba, "Midari-gokoti asi." tote, kikoye tamaha zu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 人びとも、ことにやむごとなく寄せ重きなども、をさをさなし。ただ、 母君の御叔父なりける、宰相ばかりの人の娘にて、心ばせなど口惜しからぬが、世に衰へ残りたるを、尋ねとりたまへる、 宰相の君とて、手などもよろしく書き、おほかたも大人びたる人なれば、さるべき折々の 御返りなど書かせたまへば、召し出でて、言葉などのたまひて書かせたまふ。 |
女房たちも、特に家柄がよく声望の高い者などもほとんどいない。ただ一人、母君の叔父君であった、宰相程度の人の娘で、嗜みなどさほど悪くはなく、世に落ちぶれていたのを、探し出されたのが、宰相の君と言って、筆跡などもまあまあに書いて、だいたいがしっかりした人なので、しかるべき折々のお返事などをお書かせになっていたのを、召し出して、文言などをおっしゃって、お書かせになる。 |
Hito-bito mo, koto ni yamgotonaku yose omoki nado mo, wosa-wosa nasi. Tada, Haha-Gimi no ohom-wodi nari keru, Saisyau bakari no hito no musume ni te, kokorobase nado kutiwosikara nu ga, yo ni otorohe nokori taru wo, tadune tori tamahe ru, Saisyau-no-Kimi tote, te nado mo yorosiku kaki, ohokata mo otonabi taru hito nare ba, saru-beki wori-wori no ohom-kaheri nado kaka se tamahe ba, mesi-ide te, kotoba nado notamahi te kaka se tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | ものなどのたまふさまを、ゆかしと思すなるべし。 |
お口説きになる様子を御覧になりたいのであろう。 |
Mono nado notamahu sama wo, yukasi to obosu naru besi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | 正身は、かくうたてあるもの嘆かしさの後は、 この宮などは、あはれげに聞こえたまふ時は、すこし見入れたまふ時もありけり。何かと 思ふにはあらず、「 かく心憂き御けしき見ぬわざもがな」と、 さすがにされたるところつきて思しけり。 |
ご本人は、こうした心配事が起こってから後は、この宮などには、しみじみと情のこもったお手紙を差し上げなさる時は、少し心をとめて御覧になる時もあるのだった。特に関心があるというのではないが、「このようなつらい殿のお振る舞いを見ないですむ方法がないものか」と、さすがに女らしい風情がまじる思いにもなるのだった。 |
Syauzimi ha, kaku utate aru mono-nagekasisa no noti ha, kono Miya nado ha, aharege ni kikoye tamahu toki ha, sukosi mi-ire tamahu toki mo ari keri. Nani ka to omohu ni ha ara zu, "Kaku kokoro-uki mi-kesiki mi nu waza mo gana!" to, sasuga ni sare taru tokoro tuki te obosi keri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 殿は、あいなくおのれ心懸想して、宮を待ちきこえたまふも 知りたまはで、よろしき御返りのあるをめづらしがりて、いと忍びやかにおはしましたり。 |
殿は、勝手に心ときめかしなさって、宮をお待ち申し上げていらっしゃるのもご存知なくて、まあまあのお返事があるのを珍しく思って、たいそうこっそりといらっしゃった。 |
Tono ha, ainaku onore kokoro-gesau si te, Miya wo mati kikoye tamahu mo siri tamaha de, yorosiki ohom-kaheri no aru wo medurasi-gari te, ito sinobiyaka ni ohasimasi tari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 妻戸の間に御茵参らせて、御几帳ばかりを隔てにて、近きほどなり。 |
妻戸の間にお敷物を差し上げて、御几帳だけを間に隔てとした近い場所である。 |
Tumado no ma ni ohom-sitone mawira se te, mi-kityau bakari wo hedate ni te, tikaki hodo nari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | いといたう心して、空薫物心にくきほどに匂はして、つくろひおはするさま、親にはあらで、 むつかしきさかしら人の、さすがにあはれに見えたまふ。宰相の君なども、 人の御いらへ聞こえむこともおぼえず、恥づかしくてゐたるを、「 埋もれたり」と、ひきつみたまへば、いとわりなし。 |
とてもたいそう気を配って、空薫物を奥ゆかしく匂わして、世話をやいていらっしゃる様子、親心ではなくて、手に負えないおせっかい者の、それでも親身なお扱いとお見えになる。宰相の君なども、お返事をお取り次ぎ申し上げることなども分からず、恥ずかしがっているのを、「引っ込み思案だ」と、おつねりになるので、まこと困りきっている。 |
Ito itau kokoro si te, sora-dakimono kokoro-nikuki hodo ni nihohasi te, tukurohi ohasuru sama, oya ni ha ara de, mutukasiki sakasira-bito no, sasuga ni ahare ni miye tamahu. Saisyau-no-Kimi nado mo, hito no ohom-irahe kikoye m koto mo oboye zu, hadukasiku te wi taru wo, "Umore tari." to, hiki-tumi tamahe ba, ito warinasi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 玉鬘、夕闇時に母屋の端に出る |
1-3 Tamakazura moves near front of moya in the dusk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 夕闇過ぎて、おぼつかなき空のけしきの曇らはしきに、うちしめりたる 宮の御けはひも、いと艶なり。うちよりほのめく追風も、いとどしき御匂ひのたち添ひたれば、いと深く薫り満ちて、かねて 思ししよりもをかしき御けはひを、心とどめたまひけり。 |
夕闇のころが過ぎて、はっきりしない空模様も曇りがちで、物思わしげな宮のご様子も、とても優美である。内側からほのかに吹いてくる追い風も、さらに優れた殿のお香の匂いが添わっているので、とても深く薫り満ちて、予想なさっていた以上に素晴らしいご様子に、お心を惹かれなさるのだった。 |
Yuhuyami sugi te, obotukanaki sora no kesiki no kumorahasiki ni, uti-simeri taru Miya no ohom-kehahi mo, ito en-nari. Uti yori honomeku ohi-kaze mo, itodosiki ohom-nihohi no tati-sohi tare ba, ito hukaku kawori miti te, kanete obosi si yori mo wokasiki ohom-kehahi wo, kokoro todome tamahi keri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | うち出でて、思ふ心のほどを のたまひ続けたる言の葉、おとなおとなしく、ひたぶるに好き好きしくはあらで、いとけはひことなり。大臣、いとをかしと、ほの聞きおはす。 |
お口に出して、思っている心の中をおっしゃり続けるお言葉は、落ち着いていて、一途な好き心からではなく、とても態度が格別である。大臣は、とても素晴らしいと、ほのかに聞いていらっしゃる。 |
Uti-ide te, omohu kokoro no hodo wo notamahi tuduke taru kotonoha, otona-otonasiku, hitaburu ni suki-zukisiku ha ara de, ito kehahi koto nari. Otodo, ito wokasi to, hono-kiki ohasu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 姫君は、東面に引き入りて大殿籠もりにけるを、宰相の君の御消息伝へに、 ゐざり入りたるにつけて、 |
姫君は、東面の部屋に引っ込んでお寝みになっていらしたのを、宰相の君が宮のお言葉を伝えに、いざり入って行く後についていって、 |
Hime-Gimi ha, himgasi-omote ni hiki-iri te ohotono-gomori ni keru wo, Saisyau-no-Kimi no ohom-seusoko tutahe ni, wizari-iri taru ni tuke te, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 「 いとあまり暑かはしき御もてなしなり。よろづのこと、さまに従ひてこそめやすけれ。ひたぶるに若びたまふべきさまにもあらず。この宮たちをさへ、さし放ちたる人伝てに聞こえたまふまじきことなりかし。御声こそ惜しみたまふとも、すこし気近くだにこそ」 |
「とてもあまりに暑苦しいご応対ぶりです。何事も、その場に応じて振る舞うのがよろしいのです。むやみに子供っぽくなさってよいお年頃でもありません。この宮たちまでを、よそよそしい取り次ぎでお話し申し上げなさってはいけません。お返事をしぶりなさるとも、せめてもう少しお近くで」 |
"Ito amari atukahasiki ohom-motenasi nari. Yorodu no koto, sama ni sitagahi te koso meyasukere. Hitaburu ni wakabi tamahu beki sama ni mo ara zu. Kono Miya-tati wo sahe, sasi-hanati taru hitodute ni kikoye tamahu maziki koto nari kasi. Ohom-kowe koso wosimi tamahu tomo, sukosi ke-dikaku dani koso." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | など、諌めきこえたまへど、いとわりなくて、 ことづけてもはひ入りたまひぬべき御心ばへなれば、 とざまかうざまにわびしければ、すべり出でて、母屋の際なる御几帳のもとに、 かたはら臥したまへる。 |
などと、ご忠告申し上げなさるが、とても困って、注意するのにかこつけて中に入っておいでになりかねないお方なので、どちらにしても身の置き所もないので、そっとにじり出て、母屋との境にある御几帳の側に横になっていらっしゃった。 |
nado, isame kikoye tamahe do, ito warinaku te, kotoduke te mo hahi-iri tamahi nu beki mi-kokorobahe nare ba, tozama-kauzama ni wabisikere ba, suberi-ide te, moya no kiha naru mi-kityau no moto ni, katahara husi tamahe ru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 源氏、宮に蛍を放って玉鬘の姿を見せる |
1-4 Genji makes Tamakazura's figure shown by Hyoubukyou-no-Miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 何くれと言長き御いらへ聞こえたまふこともなく、思しやすらふに、 寄りたまひて、御几帳の帷子を一重うちかけたまふにあはせて、 さと光るもの。紙燭をさし出でたるかとあきれたり。 |
何やかやと長口舌にお返事を申し上げなさることもなく、ためらっていらっしゃるところに、お近づきになって、御几帳の帷子を一枚お上げになるのに併せて、ぱっと光るものが。紙燭を差し出したのかと驚いた。 |
Nanikureto koto nagaki ohom-irahe kikoye tamahu koto mo naku, obosi-yasurahu ni, yori tamahi te, mi-kityau no katabira wo hito-e uti-kake tamahu ni ahase te, sato hikaru mono. Sisoku wo sasi-ide taru ka to akire tari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 蛍を 薄きかたに、この夕つ方いと多く包みおきて、光をつつみ隠したまへりけるを、さりげなく、 とかくひきつくろふやうにて。 |
螢を薄い物に、この夕方たいそうたくさん包んでおいて、光を隠していらっしゃったのを、何気なく、何かと身辺のお世話をするようにして。 |
Hotaru wo usuki kata ni, kono yuhu-tu-kata ito ohoku tutumi-oki te, hikari wo tutumi kakusi tamahe ri keru wo, sarigenaku, tokaku hiki-tukurohu yau ni te. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | にはかにかく掲焉に光れるに、あさましくて、 扇をさし隠したまへるかたはら目、いとをかしげなり。 |
急にこのように明るく光ったので、驚きあきれて、扇をかざした横顔、とても美しい様子である。 |
Nihaka ni kaku ketien ni hiakre ru ni, asamasiku te, ahugi sasi-kakusi tamahe ru katahara-me, ito wokasige nari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 「 おどろかしき光見えば、宮も覗きたまひなむ。 わが女と思すばかりのおぼえに、かくまでのたまふなめり。 人ざま容貌など、いとかくしも具したらむとは、え推し量りたまはじ。いとよく好きたまひぬべき心、惑はさむ」 |
「驚くほどの光がさしたら、宮もきっとお覗きになるだろう。自分の娘だとお考えになるだけのことで、こうまで熱心にご求婚なさるようだ。人柄や器量など、ほんとうにこんなにまで整っているとは、さぞお思いでなかろう。夢中になってしまうに違いないお心を、悩ましてやろう」 |
"Odorokasiki hikari miye ba, Miya mo nozoki tamahi na m. Waga musume to obosu bakari no oboye ni, kaku made notamahu na' meri. Hito zama katati nado, ito kaku simo gu-si tara m to ha, e osihakari tamaha zi. Ito yoku suki tamahi nu beki kokoro, madoha sa m." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | と、かまへありきたまふなりけり。 まことのわが姫君をば、かくしも、もて騷ぎたまはじ、うたてある御心なりけり。 |
と、企んであれこれなさるのだった。ほんとうの自分の娘ならば、このようなことをして、大騷ぎをなさるまいに、困ったお心であるよ。 |
to, kamahe ariki tamahu nari keri. Makoto no waga Hime-Gimi wo ba, kaku simo, mote sawagi tamaha zi, utate aru mi-kokoro nari keri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | こと方より、やをらすべり出でて、渡りたまひぬ。 |
別の戸口から、そっと抜け出て、行っておしまいになった。 |
Kotokata yori, yawora suberi-ide te, watari tamahi nu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 兵部卿宮、玉鬘にますます執心す |
1-5 Hyoubukyou-no-Miya loves more and more to Tamakazura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
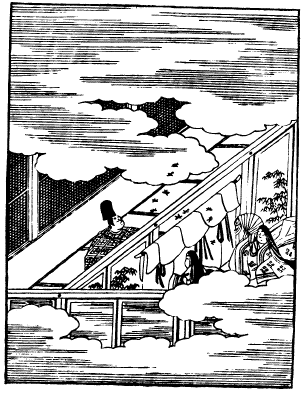 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 宮は、人のおはするほど、さばかりと推し量りたまふが、すこし気近きけはひするに、御心ときめきせられたまひて、えならぬ羅の帷子の隙より見入れたまへるに、一間ばかり隔てたる見わたしに、かくおぼえなき光のうちほのめくを、をかしと見たまふ。 |
宮は、姫のいらっしゃる所を、あの辺だと推量なさるが、割に近い感じがするので、つい胸がどきどきなさって、なんとも言えないほど素晴らしい羅の帷子の隙間からお覗きになると、柱一間ほど隔てた見通しの所に、このように思いがけない光がちらつくのを、美しいと御覧になる。 |
Miya ha, hito no ohasuru hodo, sabakari to osihakari tamahu ga, sukosi ke-dikaki kehahi suru ni, mi-kokoro tokimeki se rare tamahi te, e nara nu usumono no katabira no hima yori mi-ire tamahe ru ni, hito-ma bakari hedate taru mi-watasi ni, kaku oboye naki hikari no uti-honomeku wo, wokasi to mi tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | ほどもなく紛らはして隠しつ。されどほのかなる光、 艶なることのつまにもしつべく見ゆ。ほのかなれど、そびやかに臥したまへりつる様体のをかしかりつるを、飽かず思して、げに、このこと御心にしみにけり。 |
間もなく見えないように取り隠した。けれどもほのかな光は、風流な恋のきっかけにもなりそうに見える。かすかであるが、すらりとした身を横にしていらっしゃる姿が美しかったのを、心残りにお思いになって、なるほど、この趣向はお心に深くとまったのであった。 |
Hodo mo naku magirahasi te kakusi tu. Saredo honoka naru hikari, en-naru koto no tuma ni mo si tu beku miyu. Honoka nare do, sobiyaka ni husi tamahe ri turu yaudai no wokasikari turu wo, aka-zu obosi te, geni, kono koto mi-kokoro ni simi ni keri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | 「 鳴く声も聞こえぬ虫の思ひだに |
「鳴く声も聞こえない螢の火でさえ |
"Naku kowe mo kikoye nu musi no omohi dani |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 人の消つには消ゆるものかは |
人が消そうとして消えるものでしょうか |
hito no ketu ni ha kiyuru mono kaha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | 思ひ知りたまひぬや」 |
ご存知いただけたでしょうか」 |
Omohi-siri tamahi nu ya?" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | と聞こえたまふ。かやうの御返しを、思ひまはさむも ねぢけたれば、疾きばかりをぞ。 |
と申し上げなさる。このような場合のお返事を、思案し過ぎるのも素直でないので、早いだけを取柄に。 |
to kikoye tamahu. Kayau no ohom-kahesi wo, omohi mahasa m mo nedike tare ba, toki bakari wo zo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | 「 声はせで身をのみ焦がす蛍こそ |
「声には出さずひたすら身を焦がしている螢の方が |
"Kowe ha se de mi wo nomi kogasu hotaru koso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.8 | 言ふよりまさる思ひなるらめ」 |
口に出すよりもっと深い思いでいるでしょう」 |
ihu yori masaru omohi naru rame |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.9 | など、はかなく聞こえなして、御みづからは引き入りたまひにければ、いとはるかにもてなしたまふ愁はしさを、いみじく怨みきこえたまふ。 |
などと、さりげなくお答え申して、ご自身はお入りになってしまったので、とても疎々しくおあしらいなさるつらさを、ひどくお恨み申し上げなさる。 |
nado, hakanaku kikoye-nasi te, ohom-midukara ha hiki-iri tamahi ni kere ba, ito haruka ni motenasi tamahu urehasisa wo, imiziku urami kikoye tmahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10 | 好き好きしきやうなれば、ゐたまひも明かさで、 ▼ 軒の雫も苦しさに、濡れ濡れ夜深く出でたまひぬ。 時鳥などかならずうち鳴きけむかし。うるさければこそ聞きも止めね ★。 |
好色がましいようなので、そのまま夜をお明かしにならず、軒の雫も苦しいので、濡れながらまだ暗いうちにお出になった。ほととぎすなどもきっと鳴いたことであろう。わずらわしいので耳も留めなかった。 |
Suki-zukisiki yau nare ba, wi tamahi mo akasa de, noki no siduku mo kurusisa ni, nure-nure yo-bukaku ide tamahi nu. Hototogisu nado kanarazu uti-naki kem kasi. Urusakere ba koso kiki mo tome ne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.11 | 「 御けはひなどのなまめかしさは、いとよく大臣の君に似たてまつりたまへり」と、人びともめできこえけり。昨夜、いと女親だちてつくろひたまひし御けはひを、うちうちは知らで、「あはれにかたじけなし」と皆言ふ。 |
「ご様子などの優美さは、とてもよく大臣の君にお似申していらっしゃる」と、女房たちもお褒め申し上げるのであった。昨夜、すっかり母親のようにお世話やきなさったご様子を、内情は知らないで、「しみじみとありがたい」と女房一同は言う。 |
"Ohom-kehahi nado no namamekasisa ha, ito yoku Otodo-no-Kimi ni ni tatematuri tamahe ri." to, hito-bito mo mede kikoye keri. Yobe, ito me-oya-dati te tukurohi tamahi si ohom-kehahi wo, uti-uti ha sira de, "Ahare ni katazikenasi." to mina ihu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 第六段 源氏、玉鬘への恋慕の情を自制す |
1-6 Genji controls his mind to love Tamakazura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1 | 姫君は、 かくさすがなる御けしきを、 |
姫君は、このようなうわべは親のようにつくろうご様子を、 |
Hime-Gimi ha, kaku sasuga naru mi-kesiki wo, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | 「 わがみづからの憂さぞかし。 親などに知られたてまつり、世の人めきたるさまにて、 かやうなる御心ばへならましかば、などかはいと似げなくもあらまし。人に似ぬありさまこそ、つひに世語りにやならむ」 |
「自分自身の不運なのだ。親などに娘と知っていただき、人並みに大切にされた状態で、このようなご寵愛をいただくのなら、どうしてひどく不似合いということがあろうか。普通ではない境遇は、しまいには世の語り草となるのではないかしら」 |
"Waga midukara no usa zo kasi. Oya nado ni sira re tatematuri, yo no hito meki taru sama ni te, kayau naru mi-kokorobahe nara masika ba, nado ka ha ito nigenaku mo ara masi. Hito ni ni nu arisama koso, tuhi ni yo-gatari ni ya nara m?" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | と、起き臥し思しなやむ。 さるは、「まことにゆかしげなきさまにはもてなし果てじ」と、大臣は思しけり。なほ、さる御心癖なれば、 中宮なども、いとうるはしくや思ひきこえたまへる、ことに触れつつ、ただならず 聞こえ動かしなどしたまへど、 やむごとなき方の、およびなくわづらはしさに、 おり立ちあらはし聞こえ寄りたまはぬを、この君は、人の御さまも、気近く今めきたるに、おのづから思ひ忍びがたきに、折々、人見たてまつりつけば疑ひ負ひぬべき御もてなしなどは、うち交じるわざなれど、ありがたく思し返しつつ、 さすがなる御仲なりけり。 |
と、寝ても起きてもお悩みになる。一方では、「ほんとに世間にありふれたような悪い扱いにしてしまうまい」と、大臣はお思いになるのだった。が、やはり、そのような困ったご性癖があるので、中宮などにも、とてもきれいにお思い申し上げていられようか、何かにつけては、穏やかならぬ申しようで気を引いてみたりなどなさるが、高貴なご身分で、及びもつかない事面倒なので、身を入れてお口説き申すことはなさらないが、この姫君は、お人柄も、親しみやすく現代的なので、つい気持ちが抑えがたくて、時々、人が拝見したらきっと疑いを持たれるにちがいないお振る舞いなどは、あることはあるが、他人が真似のできないくらいよく思い返し思い返しては、危なっかしい仲なのであった。 |
to, oki-husi obosi nayamu. Saruha, "Makoto ni yukasige naki sama ni ha motenasi hate zi." to, Otodo ha obosi keri. Naho, saru mi-kokoro-guse nare ba, Tyuuguu nado mo, ito uruhasiku ya omohi kikoye tamahe ru, koto ni hure tutu, tada-nara-zu kikoye ugokasi nado si tamahe do, yamgotonaki kata no, oyobi naku wadurahasisa ni, ori-tati arahasi kikoye yori tamaha nu wo, kono Kimi ha, hito no ohom-sama mo, ke-dikaku imameki taru ni, onodukara omohi sinobi-gataki ni, wori-wori, hito mi tatematuri tuke ba utagahi ohi nu beki ohom-motenasi nado ha, uti-maziru waza nare do, arigataku obosi kahesi tutu, sasuga naru ohom-naka nari keri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 8/20/2001 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-2) Last updated 8/20/2001 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 8/20/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
Last updated 9/5/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.00: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経