10 賢木(大島本) |
SAKAKI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の二十三歳秋九月から二十五歳夏まで近衛大将時代の物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Daisho era from September at the age of 23 to summer at the age of 25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第五章 藤壷の物語 法華八講主催と出家 |
5 Tale of Fujitsubo She becommes a nun |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 第一段 十一月一日、故桐壷院の御国忌 |
5-1 The first anniversary of Kiritsbo's death on November 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1 | 中宮は、院の御はてのことにうち続き、 御八講のいそぎをさまざまに心づかひせさせたまひけり。 |
中宮は、故院の一周忌の御法事に引き続き、御八講の準備にいろいろとお心をお配りあそばすのであった。 |
Tyuuguu ha, Win no ohom-hate no koto ni uti-tuduki, mi-ha'kou no isogi wo sama-zama ni kokoro-dukahi se sase tamahi keri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2 | 霜月の朔日ごろ、御国忌なるに、雪いたう降りたり。大将殿より宮に聞こえたまふ。 |
霜月の上旬、御国忌の日に、雪がたいそう降った。大将殿から宮にお便り差し上げなさる。 |
Simotuki no tuitati-goro, mi-ko'ki naru ni, yuki itau huri tari. Daisyau-dono yori Miya ni kikoye tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.3 | 「 別れにし今日は来れども見し人に |
「故院にお別れ申した日がめぐって来ましたが、雪はふっても |
"Wakare ni si kehu ha kure domo mi si hito ni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.4 | 行き逢ふほどをいつと頼まむ」 |
その人にまた行きめぐり逢える時はいつと期待できようか」 |
yuki-ahu hodo wo itu to tanoma m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.5 | いづこにも、今日はもの悲しう思さるるほどにて、御返りあり。 |
どちらも、今日は物悲しく思わずにいらっしゃれない日なので、お返事がある。 |
Iduko ni mo, kehu ha mono-ganasiu obosa ruru hodo nite, ohom-kaheri ari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.6 | 「 ながらふるほどは憂けれど行きめぐり |
「生きながらえておりますのは辛く嫌なことですが |
"Nagarahuru hodo ha ukere do yuki-meguri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.7 | 今日はその世に逢ふ心地して」 |
一周忌の今日は、故院の在世中のような思いがいたしまして」 |
kehu ha sono yo ni ahu kokoti si te |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.8 | ことにつくろひてもあらぬ御書きざまなれど、あてに気高きは 思ひなしなるべし。 筋変はり今めかしうはあらねど、人にはことに書かせたまへり。今日は、 この御ことも思ひ消ちて、あはれなる雪の雫に濡れ濡れ行ひたまふ。 |
格別に念を入れたのでもないお書きぶりだが、上品で気高いのは思い入れであろう。書風が独特で当世風というのではないが、他の人には優れてお書きあそばしている。今日は、宮へのご執心も抑えて、しみじみと雪の雫に濡れながら御追善の法事をなさる。 |
Koto ni tukurohi te mo ara nu ohom-kaki-zama nare do, ate ni kedakaki ha omohi-nasi naru besi. Sudi kahari imamekasiu ha ara ne do, hito ni ha koto ni kaka se tamahe ri. Kehu ha, kono ohom-koto mo omohi-keti te, ahare naru yuki no siduku ni nure-nure okonahi tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 第二段 十二月十日過ぎ、藤壷、法華八講主催の後、出家す |
5-2 Fujitsubo becommes a nun after her Hokehako ceremony |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1 | 十二月十余日ばかり、中宮の御八講なり。いみじう尊し。日々に供養ぜさせたまふ御経よりはじめ、玉の軸、羅の 表紙、帙簀の飾りも、世になきさまにととのへさせたまへり。さらぬことのきよらだに、世の常ならずおはしませば、ましてことわりなり。仏の御飾り、花机のおほひなどまで、まことの極楽思ひやらる。 |
十二月の十日過ぎころ、中宮の御八講である。たいそう荘厳である。毎日供養なさる御経をはじめ、玉の軸、羅の表紙、帙簀の装飾も、この世にまたとない様子に御準備させなさっていた。普通の催しでさえ、この世のものとは思えないほど立派にお作りになっていらっしゃるので、まして言うまでもない。仏像のお飾り、花机の覆いなどまで、本当の極楽浄土が思いやられる。 |
Sihasu no towo-yo-ka bakari, Tyuuguu no mi-ha'kau nari. Imiziu tahutosi. Hi-bi ni kuyau-ze sase tamahu mi-kyau yori hazime, tama no diku, ra no heusi, disu no kazari mo, yo ni naki sama ni totonohe sase tamahe ri. Saranu koto no kiyora dani, yo no tune nara zu ohasimase ba, masite kotowari nari. Hotoke no ohom-kazari, hana-dukuye no ohohi nado made, makoto no Gokuraku omohi-yara ru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.2 | 初めの日は、先帝の御料。次の日は、母后の御ため。またの日は、院の御料。五巻の日なれば、上達部なども、 世のつつましさをえしも憚りたまはで、いとあまた参りたまへり。今日の講師は、心ことに選らせたまへれば、「 薪こる」ほどよりうちはじめ、同じう言ふ言の葉も、いみじう尊し。親王たちも、さまざまの捧物ささげてめぐりたまふに、大将殿の御用意など、なほ 似るものなし。 常におなじことのやうなれど、見たてまつるたびごとに、めづらしからむをば、いかがはせむ。 |
第一日は、先帝の御ため。第二日は、母后の御ため。次の日は、故院の御ため。第五巻目の日なので、上達部なども、世間の思惑に遠慮なさってもおれず、おおぜい参上なさった。今日の講師は、特に厳選あそばしていらっしゃるので、「薪こり」という讃歌をはじめとして、同じ唱える言葉でも、たいそう尊い。親王たちも、さまざまな供物を捧げて行道なさるが、大将殿のお心づかいなど、やはり他に似るものがない。いつも同じことのようだが、拝見する度毎に素晴らしいのは、どうしたらよいだろうか。 |
Hazime no hi ha, Sendai no go-reu. Tugi no hi ha, haha-Gisaki no ohom-tame. Mata no hi ha, Win no go-reu. Go-kwan no hi nare ba, Kamdatime nado mo, yo no tutumasisa wo e simo habakari tamaha de, ito amata mawiri tamahe ri. Kehu no Kauzi ha, kokoro koto ni era se tamahe re ba, "Takigi koru" hodo yori uti-hazime, onaziu ihu koto-no-ha mo, imiziu tahutosi. Miko-tati mo, sama-zama no houmoti sasage te meguri tamahu ni, Daisyau-dono no ohom-youi nado, naho niru mono nasi. Tune ni onazi koto no yau nare do, mi tatematuru tabi goto ni, medurasikara m wo ba, ikaga ha se m. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
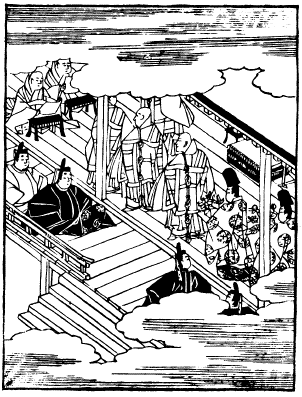 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.3 | 果ての日、わが御ことを結願にて、世を背きたまふよし、 仏に申させたまふに、皆人びと驚きたまひぬ。兵部卿宮、大将の御心も動きて、 あさましと思す。 |
最終日は、御自身のことを結願として、出家なさる旨、仏に僧からお申し上げさせなさるので、参集の人々はお驚きになった。兵部卿宮、大将がお気も動転して、驚きあきれなさる。 |
Hate no hi, waga ohom-koto wo keti-gwan nite, yo wo somuki tamahu yosi, Hotoke ni mausa se tamahu ni, mina hito-bito odoroki tamahi nu. Hyaubukyau-no-Miya, Daisyau no mi-kokoro mo ugoki te, asamasi to obosu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.4 | 親王は、なかばのほどに立ちて、入りたまひぬ。心強う思し立つさまのたまひて、果つるほどに、 山の座主召して、忌むこと受けたまふべきよし、のたまはす。 御伯父の横川の僧都、近う参りたまひて、御髪 下ろしたまふほどに、宮の内ゆすりて、ゆゆしう泣きみちたり。何となき老い衰へたる人だに、今はと世を背くほどは、あやしうあはれなるわざを、まして、かねての御けしきにも出だしたまはざりつることなれば、親王もいみじう泣きたまふ。 |
親王は、儀式の最中に座を立って、お入りになった。御決心の固いことをおっしゃって、終わりころに、山の座主を召して、戒をお受けになる旨、仰せになる。御伯父の横川の僧都、お近くに参上なさって、お髪を下ろしなさる時、宮邸中どよめいて、不吉にも泣き声が満ちわたった。たいしたこともない老い衰えた人でさえ、今は最後と出家をする時は、不思議と感慨深いものなのだが、まして、前々からお顔色にもお出しにならなかったことなので、親王もひどくお泣きになる。 |
Miko ha, nakaba no hodo ni tati te, iri tamahi nu. Kokoro-duyou obosi-tatu sama notamahi te, haturu hodo ni, Yama-no-Zasu mesi te, imu-koto uke tamahu beki yosi, notamaha su. Ohom-wodi no Yokaha-no-Soudu, tikau mawiri tamahi te, mi-gusi orosi tamahu hodo ni, Miya no uti yusuri te, yuyusiu naki-miti tari. Nani to naki oyi otorohe taru hito dani, ima ha to yo wo somuku hodo ha, ayasiu ahare naru waza wo, masite, kanete no mi-kesiki ni mo idasi tamaha zari turu koto nare ba, Miko mo imiziu naki tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.5 | 参りたまへる人々も、おほかたのことのさまも、あはれ尊ければ、みな、袖濡らしてぞ帰りたまひける。 |
参集なさった方々も、大方の成り行きも、しみじみ尊いので、皆、袖を濡らしてお帰りになったのであった。 |
Mawiri tamahe ru hito-bito mo, ohokata no koto no sama mo, ahare tahutokere ba, mina, sode nurasi te zo kaheri tamahi keru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.6 | 故院の御子たちは、昔の御ありさまを思し出づるに、いとど、あはれに悲しう思されて、みな、とぶらひきこえたまふ。 大将は、立ちとまりたまひて、聞こえ出でたまふべきかたもなく、暮れまどひて思さるれど、「 などか、さしも ★」と、人見たてまつるべければ、 親王など出でたまひぬる後にぞ、御前に参りたまへる。 |
故院の皇子たちは、在世中の御様子をお思い出しになると、ますます、しみじみと悲しく思わずにはいらっしゃれなくて、皆、お見舞いの詞をお掛け申し上げなさる。大将は、お残りになって、お言葉かけ申し上げるすべもなく、目の前がまっ暗闇に思われなさるが、「どうして、そんなにまで」と、人々がお見咎め申すにちがいないので、親王などがお出になった後に、御前に参上なさった。 |
Ko-Win no Miko-tati ha, mukasi no ohom-arisama wo obosi-iduru ni, itodo, ahare ni kanasiu obosa re te, mina, toburahi kikoye tamahu. Daisyau ha, tati-tomari tamahi te, kikoye-ide tamahu beki kata mo naku, kure-madohi te obosa rure do, "Nado ka, sasimo." to, hito mitatematuru bekere ba, Miko nado ide tamahi nuru noti ni zo, o-mahe ni mawiri tamahe ru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.7 | やうやう人静まりて、女房ども、鼻うちかみつつ、所々に群れゐたり。 月は隈なきに、雪の光りあひたる庭のありさまも、昔のこと思ひやらるるに、いと堪へがたう 思さるれど、いとよう思し静めて、 |
だんだんと人の気配が静かになって、女房連中、鼻をかみながら、あちこちに群れかたまっていた。月は隈もなく照って、雪が光っている庭の様子も、昔のことが遠く思い出されて、とても堪えがたく思われなさるが、じっとお気持ちを鎮めて、 |
Yau-yau hito sidumari te, nyoubau-domo, hana uti-kami tutu, tokoro-dokoro ni mure-wi tari. Tuki ha kuma naki ni, yuki no hikari-ahi taru niha no arisama mo, mukasi no koto omohi-yara ruru ni, ito tahe-gatau obosa rure do, ito you obosi sidume te, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.8 | 「 いかやうに思し立たせたまひて、かうにはかには」 |
「どのように御決意あそばして、このように急な」 |
"Ika yau ni obosi-tata se tamahi te, kau nihaka ni ha?" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.9 | と聞こえたまふ。 |
とお尋ね申し上げになる。 |
to kikoye tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.10 | 「 今はじめて、思ひたまふることにもあらぬを、ものさわがしきやうなりつれば、心乱れぬべく」 |
「今初めて、決意致したのではございませんが、何となく騒々しいようになってしまったので、決意も揺らいでしまいそうで」 |
"Ima hazime te, omohi tamahuru koto ni mo ara nu wo, mono-sawagasiki yau nari ture ba, kokoro-midare nu beku." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.11 | など、例の、命婦して聞こえたまふ。 |
などと、いつものように、命婦を通じて申し上げなさる。 |
nado, rei no, Myaubu site kikoye tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.12 | 御簾のうちのけはひ、そこら集ひさぶらふ人の衣の音なひ、しめやかに 振る舞ひなして、うち身じろきつつ、悲しげさの慰めがたげに漏り聞こゆるけしき、ことわりに、いみじと聞きたまふ。 |
御簾の中の様子、おおぜい伺候している女房の衣ずれの音、わざとひっそりと気をつけて、振る舞い身じろぎながら、悲しみが慰めがたそうに外へ漏れくる様子、もっともなことで、悲しいと、お聞きになる。 |
Mi-su no uti no kehahi, sokora tudohi saburahu hito no kinu no otonahi, simeyaka ni hurumahi-nasi te, uti-miziroki tutu, kanasigesa no nagusame gatage ni mori kikoyuru kesiki, kotowari ni, imizi to kiki tamahu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.13 | 風、はげしう吹きふぶきて、御簾のうちの匂ひ、いともの深き 黒方にしみて、 名香の煙もほのかなり。大将の御匂ひさへ薫りあひ、めでたく、極楽思ひやらるる夜のさまなり。 |
風、激しく吹き吹雪いて、御簾の内の匂い、たいそう奥ゆかしい黒方に染み込んで、名香の煙もほのかである。大将の御匂いまで薫り合って、素晴らしく、極楽浄土が思いやられる今夜の様子である。 |
Kaze, hagesiu huki-hubuki te, mi-su no uti no nihohi, ito mono-hukaki kurobou ni simi te, myaugau no keburi mo honoka nari. Daisyau no ohom-nihohi sahe kawori-ahi, medetaku, Gokuraku omohi-yara ruru yo no sama nari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.14 | 春宮の御使も参れり。 のたまひしさま、思ひ出できこえさせたまふにぞ、御心強さも堪へがたくて、御返りも聞こえさせやらせたまはねば、大将ぞ、言加はへ聞こえたまひける。 |
春宮からの御使者も参上した。仰せになった時のこと、お思い出しあそばされると、固い御決意も堪えがたくて、お返事も最後まで十分にお申し上げあそばされないので、大将が、言葉をお添えになったのであった。 |
Touguu no ohom-tukahi mo mawire ri. Notamahi si sama, omohi-ide kikoye sase tamahu ni zo, mi-kokoro-duyosa mo tahe-gataku te, ohom-kaheri mo kikoye sase yara se tamaha ne ba, Daisyau zo, koto kuhahe kikoye tamahi keru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.15 | 誰も誰も、ある限り心収まらぬほどなれば、思すことどもも、えうち出でたまはず。 |
どなたもどなたも、皆が悲しみに堪えられない時なので、思っていらっしゃる事なども、おっしゃれない。 |
Tare mo tare mo, aru kagiri kokoro wosamara nu hodo nare ba, obosu koto-domo mo, e uti-ide tamaha zu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.16 | 「 月のすむ雲居をかけて慕ふとも |
「月のように心澄んだ御出家の境地をお慕い申しても |
"Tuki no sumu kumo-wi wo kake te sitahu tomo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.17 | この世の闇になほや惑はむ |
なおも子どもゆえのこの世の煩悩に迷い続けるのであろうか |
kono yo no yami ni naho ya madoha m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.18 | と思ひたまへらるるこそ ★、かひなく。思し立たせたまへる恨めしさは、限りなう」 |
と存じられますのが、どうにもならないことで。出家を御決意なさった恨めしさは、この上もなく」 |
to omohi tamahe ra ruru koso, kahinaku. Obosi-tata se tamahe ru uramesisa ha, kagirinau." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.19 | とばかり聞こえたまひて、人々近うさぶらへば、さまざま乱るる心のうちをだに、え聞こえあらはしたまはず、いぶせし。 |
とだけお申し上げになって、女房たちがお側近くに伺候しているので、いろいろと乱れる心中の思いさえ、お表し申すことができないので、気が晴れない。 |
to bakari kikoye tamahi te, hito-bito tikau saburahe ba, sama-zama midaruru kokoro no uti wo dani, e kikoye arahasi tamaha zu, ibusesi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.20 | 「 おほふかたの憂きにつけては厭へども |
「世間一般の嫌なことからは離れたが、子どもへの煩悩は |
"Ohohukata no uki ni tuke te ha itohe domo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.21 | いつかこの世を背き果つべき |
いつになったらすっかり離れ切ることができるのであろうか |
ituka kono yo wo somuki hatu beki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.22 | かつ、濁りつつ」 |
一方では、煩悩を断ち切れずに」 |
Katu, nigori tutu." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.23 | など、 かたへは御使の心しらひなるべし。あはれのみ尽きせねば、胸苦しうてまかでたまひぬ。 |
などと、半分は取次ぎの女房のとりなしであろう。悲しみの気持ちばかりが尽きないので、胸の苦しい思いで退出なさった。 |
nado, katahe ha ohom-tukahi no kokoro-sirahi naru besi. Ahare nomi tukise ne ba, mune kurusiu te makade tamahi nu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 第三段 後に残された源氏 |
5-3 Genji is left behind Fujitsbo gotten into religion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.1 | 殿にても、わが御方に一人うち臥したまひて、御目もあはず、世の中厭はしう思さるるにも、春宮の御ことのみぞ心苦しき。 |
お邸でも、ご自分のお部屋でただ独りお臥せりになって、お眠りになることもできず、世の中が厭わしく思われなさるにつけても、春宮の御身の上のことばかりが気がかりである。 |
Tono ni te mo, waga ohom-kata ni hitori uti-husi tamahi te, ohom-me mo aha zu, yononaka itohasiu obosa ruru ni mo, Touguu no ohom-koto nomi zo kokoro-gurusiki. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.2 | 「 母宮をだに 朝廷がたざまにと、思しおきしを、世の憂さに堪へず、かくなりたまひにたれば、もとの御位にてもえおはせじ。我さへ 見たてまつり捨てては」など、思し明かすこと限りなし。 |
「せめて母宮だけでも表向きの御後見役にと、お考えおいておられたのに、世の中の嫌なことに堪え切れず、このようにおなりになってしまったので、もとの地位のままでいらっしゃることもおできになれまい。自分までがご後見申し上げなくなってしまったら」などと、お考え続けなさり、夜を明かすこと、一再でない。 |
"Haha-Miya wo dani ohoyake-gata zama ni to, obosi-oki si wo, yo no usa ni tahe zu, kaku nari tamahi ni tare ba, moto no mi-kurawi ni te mo e ohase zi. Ware sahe mi tatematuri sute te ha." nado, obosi-akasu koto kagirinasi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.3 | 「今は、かかるかたざまの御調度どもをこそは」と思せば、年の内にと、急がせたまふ。命婦の君も御供になりにければ、それも心深うとぶらひたまふ。 詳しう言ひ続けむに、ことことしきさまなれば、漏らしてけるなめり。さるは、 かうやうの折こそ、をかしき歌など出で来るやうもあれ、さうざうしや。 |
「今となっては、こうした方面の御調度類などを、さっそくに」とお思いになると、年内にと考えて、お急がせなさる。命婦の君もお供して出家してしまったので、その人にも懇ろにお見舞いなさる。詳しく語ることも、仰々しいことになるので、省略したもののようである。実のところ、このような折にこそ、趣の深い歌なども出てくるものだが、物足りないことよ。 |
"Ima ha, kakaru kata zama no mi-teudo-domo wo koso ha." to obose ba, tosi no uti ni to, isoga se tamahu. Myaubu-no-Kimi mo ohom-tomo ni nari ni kere ba, sore mo kokoro-hukau toburahi tamahu. Kuhasiu ihi-tuduke m ni, koto-kotosiki sama nare ba, morasi te keru na' meri. Saru ha, kau-yau no wori koso, wokasiki uta nado ide-kuru yau mo are, sau-zausi ya! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.4 | 参りたまふも、今はつつましさ薄らぎて、御みづから聞こえたまふ折もありけり。思ひしめてしことは、さらに御心に離れねど、まして、あるまじきことなりかし。 |
参上なさっても、今は遠慮も薄らいで、御自身でお話を申し上げなさる時もあるのであった。ご執心であったことは、全然お心からなくなってはないが、言うまでもなく、あってはならないことである。 |
Mawiri tamahu mo, ima ha tutumasisa usuragi te, ohom-midukara kikoye tamahu wori mo ari keri. Omohi-sime te si koto ha, sarani mi-kokoro ni hanare ne do, masite, aru maziki koto nari kasi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 5/19/2004 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-2-3) Last updated 5/19/2001 渋谷栄一注釈(ver.1-1-2) |
Last updated 5/19/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
Last updated 8/11/2002 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) (ver.1-3-2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.00: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経