05 若紫(大島本) |
WAKAMURASAKI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の十八歳春三月晦日から冬十月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from the last day in spring to October in winter at the age of 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 紫上の物語(2) 若紫の君、源氏の二条院邸に盗み出される物語 |
3 Tale of Murasaki(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 紫の君、六条京極の邸に戻る |
3-1 Murasaki comes back to her home in Rokujo-Kyogoku with her grandmother |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | かの山寺の人は、よろしくなりて 出でたまひにけり。京の 御住処尋ねて、時々の御消息などあり。同じさまにのみあるも道理なるうちに、 この月ごろは、ありしにまさる物思ひに、 異事なくて過ぎゆく。 |
あの山寺の人は、少しよくなってお出になられたのであった。京のお住まいを尋ねて、時々お手紙などがある。同じような返事ばかりであるのももっともであるが、ここ何か月は、以前にも増す物思いによって、他の事を思う間もなくて過ぎて行く。 |
北山へ養生に行っていた按察使大納言の未亡人は病が快くなって京へ帰って来ていた。源氏は惟光などに京の家を訪ねさせて時々手紙などを送っていた。先方の態度は春も今も変わったところがないのである。それも道理に思えることであったし、またこの数月間というものは、過去の幾年間にもまさった恋の煩悶が源氏にあって、ほかのことは何一つ熱心にしようとは思われないのでもあったりして、より以上積極性を帯びていくようでもなかった。 |
Kano yamadera no hito ha, yorosiku nari te ide tamahi ni keri. Kyau no ohom-sumika tadune te, toki-doki no ohom-seusoko nado ari. Onazi sama ni nomi aru mo, kotowari naru uti ni, kono tukigoro ha, arisi ni masaru mono-omohi ni, kotogoto naku te sugi-yuku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 秋の末つ方、 いともの心細くて嘆きたまふ。月のをかしき夜、忍びたる所に からうして思ひ立ちたまへるを、 時雨めいてうちそそく。 おはする所は六条京極わたりにて、内裏よりなれば、 すこしほど遠き心地するに、 荒れたる家の木立いともの古りて木暗く見えたるあり。例の御供に離れぬ惟光なむ、 |
秋の終わりころ、とても物寂しくお嘆きになる。月の美しい夜に、お忍びの家にやっとのことでお思い立ちになると、時雨めいてさっと降る。おいでになる先は六条京極辺りで、内裏からなので、少し遠い感じがしていると、荒れた邸で木立がとても年代を経て鬱蒼と見えるのがある。いつものお供を欠かさない惟光が、 |
秋の末になって、恋する源氏は心細さを人よりも深くしみじみと味わっていた。ある月夜にある女の所を訪ねる気にやっとなった源氏が出かけようとするとさっと時雨がした。源氏の行く所は六条の京極辺であったから、御所から出て来たのではやや遠い気がする。荒れた家の庭の木立ちが大家らしく深いその土塀の外を通る時に、例の傍去らずの惟光が言った。 |
Aki no suwe-tu-kata, ito mono kokoro-bosoku te nageki tamahu. Tuki no wokasiki yo, sinobi taru tokoro ni karausite omohi-tati tamahe ru wo, sigure-mei te, uti-sosoku. Ohasuru tokoro ha rokudeu kyaugoku watari ni te, uti yori nare ba, sukosi hodo tohoki kokoti suru ni, are taru ihe no kodati ito mono-huri te ko-guraku miye taru ari. Rei no ohom-tomo ni hanare nu Koremitu nam, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | 「 故按察使大納言の家にはべりて、もののたよりに とぶらひて はべりしかば、 かの尼上、いたう弱りたまひにたれば、何ごともおぼえず、 となむ申してはべりし」と聞こゆれば、 |
「故按察大納言の家でございまして、ちょっとしたついでに立ち寄りましたところ、あの尼上は、ひどくご衰弱されていらっしゃるので、どうして良いか分からないでいる、と申しておりました」と申し上げると、 |
「これが前の按察使大納言の家でございます。先日ちょっとこの近くへ来ました時に寄ってみますと、あの尼さんからは、病気に弱ってしまっていまして、何も考えられませんという挨拶がありました」 |
"Ko-Azeti-no-Dainagon no ihe ni haberi te, mono no tayori ni toburahi te haberi sika ba, kano Ama-uhe, itau yowari tamahi ni tare ba, nani-goto mo oboye zu, to nam mausi te haberi si." to kikoyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | 「 あはれのことや。 とぶらふべかりけるを。 などか、さなむとものせざりし。入りて消息せよ」 |
「お気の毒なことよ。お見舞いすべきであったのに。どうして、そうと教えなかったのか。入って行って、挨拶をせよ」 |
「気の毒だね。見舞いに行くのだった。なぜその時にそう言ってくれなかったのだ。ちょっと私が訪問に来たがと言ってやれ」 |
"Ahare no koto ya! Toburahu bekari keru wo. Nadoka, sa nam to monose zari si. Iri te seusoko se yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | とのたまへば、人入れて案内せさす。 わざとかう立ち寄りたまへることと言はせたれば、入りて、 |
とおっしゃるので、惟光は供人を入れて案内を乞わせる。わざわざこのようにお立ち寄りになった旨を言わせたので、入って行って、 |
源氏がこう言うので惟光は従者の一人をやった。この訪問が目的で来たと最初言わせたので、そのあとでまた惟光がはいって行って、 |
to notamahe ba, hito ire te a'nai-se sasu. Wazato kau tatiyori tamahe ru koto to iha se tare ba, iri te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | 「 かく御とぶらひになむおはしましたる」と言ふに、おどろきて、 |
「このようにお見舞いにいらっしゃいました」と言うと、驚いて、 |
「主人が自身でお見舞いにおいでになりました」 と言った。大納言家では驚いた。 |
"Kaku ohom-toburahi ni nam ohasimasi taru." to ihu ni, odoroki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.7 | 「 いとかたはらいたきことかな。この日ごろ、むげにいと頼もしげなく ならせたまひにたれば、御対面などもあるまじ」 |
「とても困ったことですわ。ここ数日、ひどくご衰弱あそばされましたので、お目にかかることなどはとてもできそうにありません」 |
「困りましたね。近ごろは以前よりもずっと弱っていらっしゃるから、お逢いにはなれないでしょうが、 |
"Ito kataharaitaki koto kana! Kono higoro, mugeni ito tanomosigenaku nara se tamahi ni tare ba, ohom-taimen nado mo aru mazi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.8 | と言へども、帰したてまつらむはかしこしとて、 南の廂ひきつくろひて ★、入れたてまつる。 |
とは言っても、お帰し申すのも恐れ多いということで、南の廂の間を片づけて、お入れ申し上げる。 |
お断わりするのはもったいないことですから」 などと女房は言って、南向きの縁座敷をきれいにして源氏を迎えたのである。 |
To ihe domo, kahesi tatematura m ha kasikosi, tote, minami no hisasi hiki-tukurohi te, ire tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.9 | 「 いとむつかしげにはべれど、かしこまりをだにとて。 ゆくりなう、 もの深き御座所になむ」 |
「たいそうむさ苦しい所でございますが、せめてお礼だけでもとのことで。何の用意もなく、鬱陶しいご座所で恐縮です」 |
「見苦しい所でございますが、せめて御厚志のお礼を申し上げませんではと存じまして、思召しでもございませんでしょうが、こんな部屋などにお通しいたしまして」 |
"Ito mutukasige ni habere do, kasikomari wo dani tote. Yukurinau, mono-hukaki o-masi-dokoro ni nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.10 | と聞こゆ。 げにかかる所は、例に違ひて思さる。 |
と申し上げる。なるほどこのような所は、普通とは違っているとお思いになる。 |
という挨拶を家の者がした。そのとおりで、意外な所へ来ているという気が源氏にはした。 |
to kikoyu. Geni kakaru tokoro ha, rei ni tagahi te obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.11 | 「 常に思ひたまへ立ちながら、かひなきさまにのみ もてなさせたまふに、 つつまれはべりてなむ。悩ませたまふこと、重くとも、 うけたまはらざりける おぼつかなさ」など聞こえたまふ。 |
「常にお見舞いにと存じながら、すげないお返事ばかりあそばされますので、遠慮いたされまして。ご病気でいらっしゃること、重いこととも、存じませんでしたもどかしさを」などと申し上げなさる。 |
「いつも御訪問をしたく思っているのでしたが、私のお願いをとっぴなものか何かのようにこちらではお扱いになるので、きまりが悪かったのです。それで自然御病気もこんなに進んでいることを知りませんでした」 と源氏が言った。 |
"Tune ni omohi tamahe tati nagara, kahinaki sama ni nomi motenasa se tamahu ni, tutuma re haberi te nam. Nayama se tamahu koto, omoku tomo, uketamahara zari keru obotukanasa." nado kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.12 | 「 乱り心地は、いつともなくのみはべるが、限りのさまになりはべりて、いとかたじけなく、立ち寄らせたまへるに、 みづから聞こえさせぬこと。 のたまはすることの筋、たまさかにも思し召し変はらぬやうはべらば、かくわりなき齢過ぎはべりて、 かならず数まへさせたまへ。いみじう 心細げに見たまへ置くなむ、 願ひはべる道のほだしに 思ひたまへられぬべき」 など聞こえたまへり。 |
「気分のすぐれませんことは、いつも変わらずでございますが、いよいよの際となりまして、まことにもったいなくも、お立ち寄りいただきましたのに、自分自身でお礼申し上げられませんこと。仰せられますお話の旨は、万一にもお気持ちが変わらないようでしたら、このような頑是ない時期が過ぎましてから、きっとお目をかけて下さいませ。ひどく頼りない身の上のまま残して逝きますのが、願っております仏道の妨げに存ぜずにはいられません」などと、申し上げなさった。 |
「私は病気であることが今では普通なようになっております、しかしもうこの命の終わりに近づきましたおりから、かたじけないお見舞いを受けました喜びを自分で申し上げません失礼をお許しくださいませ。あの話は今後もお忘れになりませんでしたら、もう少し年のゆきました時にお願いいたします。一人ぼっちになりますあの子に残る心が、私の参ります道の障りになることかと思われます」 |
"Midari-gokoti ha, itu to mo naku nomi haberu ga, kagiri no sama ni nari haberi te, ito katazikenaku, tatiyora se tamahe ru ni, midukara kikoye sase nu koto. Notamahasuru koto no sudi, tamasaka ni mo obosimesi kahara nu yau habera ba, kaku warinaki yohahi sugi haberi te, kanarazu kazumahe sase tamahe. Imiziu kokoro-bosoge ni mi tamahe oku nam, negahi haberu miti no hodasi ni omohi tamahe rare nu beki." nado kikoye tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.13 | いと近ければ、心細げなる御声絶え絶え聞こえて、 |
すぐに近いところなので、不安そうなお声が途切れ途切れに聞こえて、 |
取り次ぎの人に尼君が言いつけている言葉が隣室であったから、その心細そうな声も絶え絶え聞こえてくるのである。 |
Ito tikakere ba, kokoro-bosoge naru ohom-kowe taye-daye kikoye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.14 | 「 いと、かたじけなきわざにもはべるかな。 この君だに、かしこまりも聞こえたまつべき ほどならましかば」 |
「まことに、もったいないことでございます。せめてこの姫君が、お礼申し上げなされるお年でありましたならよいのに」 |
「失礼なことでございます。孫がせめてお礼を申し上げる年になっておればよろしいのでございますのに」 |
"Ito, katazikenaki waza ni mo haberu kana! Kono Kimi dani, kasikomari mo kikoye tama' tu beki hodo nara masika ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.15 | とのたまふ。あはれに聞きたまひて、 |
とおっしゃる。しみじみとお聞きになって、 |
とも言う。源氏は哀れに思って聞いていた。 |
to notamahu. Ahare ni kiki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.16 | 「 何か、浅う思ひたまへむことゆゑ ★、かう好き好きしきさまを見えたてまつらむ。いかなる契りにか、見たてまつりそめしより、あはれに思ひきこゆるも、あやしきまで、 この世のことにはおぼえはべらぬ」などのたまひて、「 かひなき心地のみしはべるを、かのいはけなうものしたまふ御一声、 いかで」とのたまへば、 |
「どうして、浅く思っております気持ちから、このような好色めいた態度をお見せ申し上げましょうか。どのような前世からの因縁によってか、初めてお目にかかった時から、愛しくお思い申しているのも、不思議なまでに、この世の縁だけとは思われません」などとおっしゃって、「いつも甲斐ない思いばかりしていますので、あのかわいらしくいらっしゃるお一声を、ぜひとも」とおっしゃると、 |
「今さらそんな御挨拶はなさらないでください。通り一遍な考えでしたなら、風変わりな酔狂者と誤解されるのも溝わずに、こんな御相談は続けません。どんな前生の因縁でしょうか、女王さんをちよっとお見かけいたしました時から、女王さんのことをどうしても忘れられないようなことになりましたのも不思議なほどで、どうしてもこの世界だけのことでない、約束事としか思われません」 などと源氏は言って、また、 「自分を理解していただけない点で私は苦しんでおります。あの小さい方が何か一言お言いになるのを伺えればと思うのですが」 と望んだ。 |
"Nani-ka, asau omohi tamahe m koto yuwe, kau suki-zukisiki sama wo miye tatematura m. Ikanaru tigiri ni ka, mi tatematuri some si yori, ahare ni omohi kikoyuru mo, ayasiki made, konoyo no koto ni ha oboye habera nu." nado notamahi te, "Kahinaki kokoti nomi si haberu wo, kano ihakenau monosi tamahu ohom hito-kowe, ikade." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
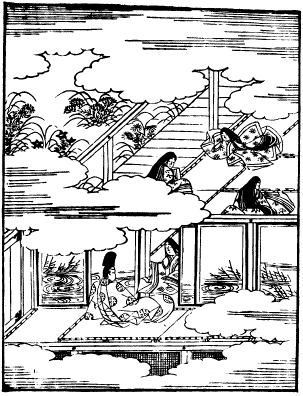 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.17 | 「 いでや、よろづ思し知らぬさまに、 大殿籠もり入りて」 |
「いやはや、何もご存知ないさまで、ぐっすりお眠りになっていらっしゃって」 |
「それは姫君は何もご存じなしに、もうお寝みになっていまして」 |
"Ideya, yorodu obosi sira nu sama ni, ohotono-gomori-iri te." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.18 | など聞こゆる折しも、 あなたより来る音して、 |
などと申し上げている、ちょうどその時、あちらの方からやって来る足音がして、 |
女房がこんなふうに言っている時に、向こうからこの隣室へ来る足音がして、 |
nado kikoyuru wori simo, anata yori kuru oto si te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.19 | 「 上こそ、 この寺にありし 源氏の君こそ おはしたなれ。 など見たまはぬ」 |
「祖母上さま、先日の寺にいらした源氏の君さまがいらしているそうですね。どうしてお会いさらないの」 |
「お祖母様、あのお寺にいらっしった源氏の君が来ていらっしゃるのですよ。なぜ御覧にならないの」 |
"Uhe koso, kono tera ni arisi Genzi-no-Kimi koso ohasi ta' nare. Nado mi tamaha nu?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.20 | とのたまふを、人びと、いとかたはらいたしと思ひて、「 あなかま」と聞こゆ。 |
とおっしゃるのを、女房たちは、とても具合悪く思って、「お静かに」と制止申し上げる。 |
と女王は言った。女房たちは困ってしまった。 「静かにあそばせよ」 と言っていた。 |
to notamahu wo, hito-bito, ito kataharaitasi to omohi te, "Ana-kama!" to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.21 | 「 いさ、『見しかば 心地の悪しさなぐさみき』 とのたまひしかばぞかし」 |
「あら、だって、『会ったので気分の悪いのも良くなった』とおっしゃったからよ」 |
「でも源氏の君を見たので病気がよくなったと言っていらしたからよ」 |
"Isa, 'Mi sika ba, kokoti no asisa nagusami ki.' to notamahi sika ba zo kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.22 | と、かしこきこと 聞こえたりと思してのたまふ。 |
と、利口なことを申し上げたとお思いになっておっしゃる。 |
自分の覚えているそのことが役に立つ時だと女王は考えている。 |
to, kasikoki koto kikoye tari to obosi te notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.23 | いとをかしと聞いたまへど、人びとの苦しと思ひたれば、聞かぬやうにて、まめやかなる御とぶらひを聞こえ置きたまひて、帰りたまひぬ。「 げに、言ふかひなのけはひや。 さりとも、いとよう教へてむ」と思す。 |
とてもおもしろいとお聞きになるが、女房たちが困っているので、聞かないようにして、行き届いたお見舞いを申し上げおかれて、お帰りになった。「なるほど、まるで子供っぽいご様子だ。けれども、よく教育しよう」とお思いになる。 |
源氏はおもしろく思って聞いていたが、女房たちの困りきったふうが気の毒になって、聞かない顔をして、まじめな見舞いの言葉を残して去った。子供らしい子供らしいというのはほんとうだ、けれども自分はよく教えていける気がすると源氏は思ったのであった。 |
Ito wokasi to kii tamahe do, hito-bito no kurusi to omohi tare ba, kika nu yau ni te, mameyaka naru ohom-toburahi wo kikoye-oki tamahi te, kaheri tamahi nu. "Geni, ihukahina no kehahi ya! Saritomo, ito you wosihe te m." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.24 | またの日も、いとまめやかにとぶらひきこえたまふ。例の、小さくて、 |
翌日も、とても誠実なお見舞いを差し上げなさる。いつものように、小さく結んで、 |
翌日もまた源氏は尼君へ丁寧に見舞いを書いて送った。例のように小さくしたほうの手紙には、 |
Mata-no-hi mo, ito mameyaka ni tobura hi kikoye tamahu. Rei no, tihisaku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.25 | 「 いはけなき鶴の一声聞きしより |
「かわいい鶴の一声を聞いてから |
いはけなき鶴の一声聞きしより |
"Ihakenaki tadu no hito-kowe kiki si yori |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.26 | 葦間になづむ舟ぞえならぬ |
葦の間を行き悩む舟はただならぬ思いをしています |
葦間になづむ船ぞえならぬ |
asima ni nadumu hune zo e nara nu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.27 | ▼ 同じ人にや」 |
同じ人を慕い続けるだけなのでしょうか」 |
いつまでも一人の人を対象にして考えているのですよ。 |
Onazi hito ni ya." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.28 | と、ことさら幼く書きなしたまへるも、いみじうをかしげなれば、「やがて御手本に」と、人びと聞こゆ。 少納言ぞ聞こえたる。 |
と、殊更にかわいらしくお書きになっているのも、たいそう見事なので、「そのままお手本に」と、女房たちは申し上げる。少納言がお返事申し上げた。 |
わざわざ子供にも読めるふうに書いた源氏のこの手紙の字もみごとなものであったから、そのまま姫君の習字の手本にしたらいいと女房らは言った。源氏の所へ少納言が返事を書いてよこした。 |
to, kotosara wosanaku kaki-nasi tamahe ru mo, imiziu wokasige nare ba, "Yagate ohom-tehon ni" to, hito-bito kikoyu. Seunagon zo kikoye taru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.29 | 「 問はせたまへるは、今日をも過ぐしがたげなるさまにて、 山寺にまかりわたるほどにて。かう問はせたまへるかしこまりは、 この世ならでも聞こえさせむ」 |
「お見舞いいただきました方は、今日一日も危いような状態なので、山寺に移るところでして。このよう緩お見舞いいただきましたお礼は、あの世からでもお返事をさせていただきましょう」 |
お見舞いくださいました本人は、今日も危いようでございまして、ただ今から皆で山の寺へ 移ってまいるところでございます。 かたじけないお見舞いのお礼はこの世界で果たしませんでもまた申し上げる時がございましょう。 |
"Toha se tamahe ru ha, kehu wo mo sugusi gatage naru sama ni te, yamadera ni makari wataru hodo ni te. Kau toha se tamahe ru kasikomari ha, konoyo nara de mo kikoyesase m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.30 | とあり。いとあはれと思す。 |
とある。とてもお気の毒とお思いになる。 |
というのである。 |
to ari. Ito ahare to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.31 | 秋の夕べは、まして、心のいとまなく 思し乱るる人の御あたりに心をかけて、あながちなる ゆかりも尋ねまほしき 心もまさりたまふなるべし。「 消えむ空なき」とありし夕べ思し出でられて、 恋しくも、また、見ば劣りやせむと、 さすがにあやふし。 |
秋の夕暮れは、常にも増して、心の休まる間もなく恋い焦がれている人のことに思いが集中して、無理にでもそのゆかりの人を尋ね取りたい気持ちもお募りなさるのであろう。尼君が「死にきれない」と詠んだ夕暮れを自然とお思い出しになられて、恋しく思っても、また、実際に逢ってみたら見劣りがしないだろうかと、やはり不安である。 |
秋の夕べはまして人の恋しさがつのって、せめてその人に縁故のある少女を得られるなら得たいという望みが濃くなっていくばかりの源氏であった。「消えん空なき」と尼君の歌った晩春の山の夕べに見た面影が思い出されて恋しいとともに、引き取って幻滅を感じるのではないかと危ぶむ心も源氏にはあった。 |
Aki no yuhube ha, masite, kokoro no itoma naku obosi midaruru hito no ohom-atari ni kokoro wo kake te, anagati naru yukari mo tadune mahosiki kokoro mo masari tamahu naru besi. "Kiye m sora naki" to arisi yuhube obosi-ide rare te, kohisiku mo, mata, mi ba otori ya se m to, sasuga ni ayahusi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.32 | 「 ▼ 手に摘みていつしかも見む紫の |
「手に摘んで早く見たいものだ |
手に摘みていつしかも見ん紫の |
"Te ni tumi te itusika mo mi m murasaki no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.33 | 根にかよひける野辺の若草」 |
紫草にゆかりのある野辺の若草を」 |
根に通ひける野辺の若草 このころの源氏の歌である。 |
ne ni kayohi keru nobe no wakakusa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 尼君死去し寂寥と孤独の日々 |
3-2 Her grandmother dies after a few monthes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 十月に朱雀院の行幸あるべし。舞人など、やむごとなき家の子ども、上達部、殿上人どもなども、その方につきづきしきは、 みな選らせたまへれば、親王達、大臣よりはじめて、とりどりの才ども習ひたまふ、いとまなし。 |
神無月に朱雀院への行幸が予定されている。舞人などを、高貴な家柄の子弟や、上達部、殿上人たちなどの、その方面で適当な人々は、皆お選びあそばされたので、親王たちや、大臣をはじめとして、それぞれ伎芸を練習をなさり、暇がない。 |
この十月の朱雀院へ行幸があるはずだった。その日の舞楽には貴族の子息たち、高官、殿上役人などの中の優秀な人が舞い人に選ばれていて、親王方、大臣をはじめとして音楽の素養の深い人はそのために新しい稽古を始めていた。それで源氏の君も多忙であった。 |
Kamnaduki ni Syuzyaku-win no gyaugau aru besi. Mahi-bito nado, yamgotonaki ihenoko-domo, kamdatime, tenzyau-bito-domo nado mo, sono kata ni tuki-dukisiki ha, mina era se tamahe re ba, miko-tati, daizin yori hazime te, tori-dori no zae-domo narahi tamahu, itoma nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 山里人にも、久しく訪れたまはざりけるを、思し出でて、 ふりはへ遣はしたりければ、僧都の返り事のみあり。 |
山里の人にも、久しくご無沙汰なさっていたのを、お思い出しになって、わざわざお遣わしになったところ、僧都の返事だけがある。 |
北山の寺へも久しく見舞わなかったことを思って、ある日わざわざ使いを立てた。山からは僧都の返事だけが来た。 |
Yamazato-bito ni mo, hisasiku otodure tamaha zari keru wo, obosi-ide te, hurihahe tukahasi tari kere ba, Soudu no kaheri-goto nomi ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | 「 立ちぬる月の二十日のほどになむ、つひに空しく見たまへなして、 世間の道理なれど、 悲しび思ひたまふる ★」 |
「先月の二十日ごろに、とうとう臨終をお見届けいたしまして、人の世の宿命だが、悲しく存じられます」 |
先月の二十日にとうとう姉は亡くなりまして、これが人生の掟であるのを承知しながらも悲しんでおります。 |
"Tati nuru tuki no hatu-ka no hodo ni nam, tuhini munasiku mi tamahe nasi te, seken no dauri nare do, kanasibi omohi tamahuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 | などあるを見たまふに、世の中のはかなさもあはれに、「 うしろめたげに思へりし人もいかならむ。幼きほどに、恋ひやすらむ。 故御息所に後れたてまつりし ★」など、 はかばかしからねど、思ひ出でて、浅からずとぶらひたまへり。少納言、ゆゑなからず御返りなど聞こえたり。 |
などとあるのを御覧になると、世の中の無常をしみじみと思われて、「心配していた人もどうしているだろう。子供心にも、尼君を恋い慕っているだろうか。わたしも亡き母御息所に先立たれた頃には」などと、はっきりとではないが、思い出して、丁重にお弔いなさった。少納言の乳母が、心得のある返礼などを申し上げた。 |
源氏は今さらのように人間の生命の脆さが思われた。尼君が気がかりでならなかったらしい小女王はどうしているだろう。小さいのであるから、祖母をどんなに恋しがってばかりいることであろうと想像しながらも、自身の小さくて母に別れた悲哀も確かに覚えないなりに思われるのであった。源氏からは丁寧な弔慰品が山へ贈られたのである。 そんな場合にはいつも少納言が行き届いた返事を書いて来た。 |
nado aru wo mi tamahu ni, yononaka no hakanasa mo ahare ni, "Usirometage ni omohe ri si hito mo ika nara m? Wosanaki hodo ni, kohi ya su ram? Ko-Miyasumdokoro ni okure tatematuri si." nado, haka-bakasikara ne do omohi-ide te, asakara zu toburahi tamahe ri. Seunagon, yuwe nakara zu ohom-kaheri nado kikoye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.5 | 忌みなど過ぎて 京の殿になど聞きたまへば、ほど経て、みづから、のどかなる夜おはしたり。いとすごげに 荒れたる所の、人少ななるに、 いかに幼き人恐ろしからむと見ゆ。 例の所に入れたてまつりて、少納言、御ありさまなど、うち泣きつつ聞こえ続くるに、 あいなう、御袖もただならず。 |
忌みなどが明けて京の邸に戻られたなどとお聞きになったので、暫くしてから、ご自身で、お暇な夜にお出かけになった。まことにぞっとするくらい荒れた所で、人気も少ないので、どんなに小さい子には怖いことだろうと思われる。いつもの所にお通し申して、少納言が、ご臨終の有様などを、泣きながらお話申し上げると、他人事ながら、お袖も涙でつい濡れる。 |
尼君の葬式のあとのことが済んで、一家は京の邸へ帰って来ているということであったから、それから少しあとに源氏は自身で訪問した。凄いように荒れた邸に小人数で暮らしているのであったから、小さい人などは怖しい気がすることであろうと思われた。以前の座敷へ迎えて少納言が泣きながら哀れな若草を語った。源氏も涙のこぼれるのを覚えた。 |
Imi nado sugi te kyau no tono ni nado kiki tamahe ba, hodo he te, midukara, nodoka naru yo ohasi tari. Ito sugoge ni are taru tokoro no, hito-zukuna naru ni, ikani wosanaki hito osorosikara m to miyu. Rei no tokoro ni ire tatematuri te, Seunagon, ohom-arisama nado, uti-naki tutu kikoye tudukuru ni, ainau, ohom-sode mo tada nara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.6 | 「 宮に渡したてまつらむとはべるめるを、『 故姫君の、いと情けなく憂きものに 思ひきこえたまへりしに、 いとむげに児ならぬ齢の、 まだはかばかしう人のおもむけをも見知りたまはず、中空なる御ほどにて、 あまたものしたまふなる中の、 あなづらはしき人にてや交じりたまはむ』など、 過ぎたまひぬるも、世とともに思し 嘆きつること、しるきこと多くはべるに、 かくかたじけなきなげの御言の葉は、後の御心もたどりきこえさせず、 いとうれしう思ひたまへられぬべき折節にはべりながら、すこしも なぞらひなるさまにもものしたまはず、御年よりも若びてならひたまへれば、いとかたはらいたくはべる」と聞こゆ。 |
「父兵部卿宮邸にお引き取り申し上げようとの事でございますようですが、『亡き姫君が、北の方をとても情愛のない嫌な人とお思い申していらしたのに、まったく子供というほどでもないお年で、まだしっかりと人の意向を聞き分けることもおできになれず、中途半端なお年頃で、大勢いらっしゃるという中で、軽んじられてお過ごしになるのではないか』などと、お亡くなりになった尼上も、始終ご心配されていらしたこと、明白なことが多くございましたので、このようにもったいないかりそめのお言葉は、後々のご配慮までもご推察申さずに、とても嬉しく存ぜずにはいられない時ではございますが、全く相応しい年頃でいらっしゃらないし、お年のわりには幼くていらっしゃいますので、とても見ていられない状態でございます」と申し上げる。 |
「宮様のお邸へおつれになることになっておりますが、お母様の御生前にいろんな冷酷なことをなさいました奥さまがいらっしゃるのでございますから、それがいっそずっとお小さいとか、また何でもおわかりになる年ごろになっていらっしゃるとかすればいいのでございますが、中途半端なお年で、おおぜいお子様のいらっしゃる中で軽い者にお扱われになることになってはと、尼君も始終それを苦労になさいましたが、宮様のお内のことを聞きますと、まったく取り越し苦労でなさそうなんでございますから、あなた様のお気まぐれからおっしゃってくださいますことも、遠い将来にまでにはたとえどうなりますにしましても、お救いの手に違いないと私どもは思われますが、奥様になどとは想像も許されませんようなお子様らしさでございまして、普通のあの年ごろよりももっともっと赤様なのでございます」 と少納言が言った。 |
"Miya ni watasi tatematura m to haberu meru wo, 'Ko-Hime-Gimi no, ito nasake naku uki mono ni omohi kikoye tamahe ri si ni, ito muge ni tigo nara nu yohahi no, mada haka-bakasiu hito no omomuke wo mo mi-siri tamaha zu, nakazora naru ohom-hodo ni te, amata monosi tamahu naru naka no, anadurahasiki hito ni te ya maziri tamaha m?' nado, sugi tamahi nuru mo, yo to tomo ni obosi-nageki turu koto, siruki koto ohoku haberu ni, kaku katazikenaki nage no ohom-kotonoha ha, noti no mi-kokoro mo tadori kikoyesase zu, ito uresiu omohi tamahe rare nu beki worihusi ni haberi nagara, sukosi mo nazorahi naru sama ni mo monosi tamaha zu, ohom-tosi yori mo wakabi te narahi tamahe re ba, ito kataharaitaku haberu." to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.7 | 「 何か、かう繰り返し聞こえ知らする心のほどを、つつみたまふらむ。その言ふかひなき 御心のありさまの、あはれに ゆかしうおぼえたまふも、契りことになむ、 心ながら思ひ知られける。なほ、人伝てならで、聞こえ知らせばや。 |
「どうして、このように繰り返して申し上げている気持ちを、気兼ねなさるのでしょう。その、幼いお考えの様子がかわいく愛しく思われなさるのも、宿縁が特別なものと、わたしの心には自然と思われてくるのです。やはり、人を介してではなく、直接お伝え申し上げたい。 |
「そんなことはどうでもいいじゃありませんか、私が繰り返し繰り返しこれまで申し上げてあることをなぜ無視しようとなさるのですか。その幼稚な方を私が好きでたまらないのは、こればかりは前生の縁に違いないと、それを私が客観的に見ても思われます。許してくだすって、この心持ちを直接女王さんに話させてくださいませんか。 |
"Nani ka, kau kurikahesi kikoye sirasuru kokoro no hodo wo, tutumi tamahu ram? Sono ihukahinaki mi-kokoro no arisama no, ahare ni yukasiu oboye tamahu mo, tigiri koto ni nam, kokoro nagara omohi-sira re keru. Naho, hitodute nara de, kikoye sirase baya. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.8 | あしわかの浦にみるめはかたくとも |
若君にお目にかかることは難しかろうとも |
あしわかの浦にみるめは難くとも |
Asiwaka no ura ni mirume ha kataku tomo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.9 | こは立ちながらかへる波かは |
和歌の浦の波のようにこのまま立ち帰ることはしません |
こは立ちながら帰る波かは |
ko ha tati nagara kaheru nami ka ha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.10 | めざましからむ」とのたまへば、 |
失礼でしょう」とおっしゃると、 |
私をお見くびりになってはいけません」 源氏がこう言うと、 |
Mezamasikara m." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.11 | 「 げにこそ、いとかしこけれ」とて、 |
「なるほど、恐れ多いこと」と言って、 |
「それはもうほんとうにもったいなく思っているのでございます。 |
"Geni koso, ito kasikokere." tote, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.12 | 「 寄る波の心も知らでわかの浦に |
「和歌の浦に寄せる波に身を任せる玉藻のように |
寄る波の心も知らで和歌の浦に |
"Yoru nami no kokoro mo sira de Waka-no-ura ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.13 | 玉藻 なびかむほどぞ浮きたる |
相手の気持ちをよく確かめもせずに従うことは頼りないことです |
玉藻なびかんほどぞ浮きたる |
tama-mo nabika m hodo zo uki taru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.14 | わりなきこと」 |
困りますこと」 |
このことだけは御信用ができませんけれど」 |
Warinaki koto." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.15 | と聞こゆるさまの馴れたるに、 すこし罪ゆるされたまふ。 「 なぞ越えざらむ」と、うち誦じたまへるを、身にしみて若き人びと思へり。 |
と申し上げる態度がもの馴れているので、すこし大目に見る気になられる。「どうして逢わずにいられようか」と、口ずさみなさるのを、ぞくぞくして若い女房たちは感じ入っていた。 |
物馴れた少納言の応接のしように、源氏は何を言われても不快には思われなかった。「年を経てなど越えざらん逢坂の関」という古歌を口ずさんでいる源氏の美音に若い女房たちは酔ったような気持ちになっていた。 |
to kikoyuru sama no nare taru ni, sukosi tumi yurusa re tamahu. "Nazo koye zara m" to, uti-zu'-zi tamahe ru wo, mi ni simi te wakaki hito-bito omohe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.16 | 君は、上を恋ひきこえたまひて泣き臥したまへるに、御遊びがたきどもの、 |
姫君は、祖母上をお慕い申されて泣き臥していらっしゃったが、お遊び相手たちが、 |
女王は今夜もまた祖母を恋しがって泣いていた時に、遊び相手の童女が、 |
Kimi ha, Uhe wo kohi kikoye tamahi te naki-husi tamahe ru ni, ohom-asobi-gataki-domo no, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.17 | 「 直衣着たる人のおはする、 宮のおはしますなめり」 |
「直衣を着ている方がいらっしゃってるのは、父宮さまがおいであそばしたのらしいわ」 |
一直衣を着た方が来ていらっしゃいますよ。宮様が来ていらっしゃるのでしょう」 |
"Nahosi ki taru hito no ohasuru, Miya no ohasimasu na' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.18 | と聞こゆれば、起き出でたまひて、 |
と申し上げると、起き出しなさって、 |
と言ったので、起きて来て、 |
to kikoyure ba, oki-ide tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.19 | 「 少納言よ。 直衣着たりつらむは、 いづら。宮のおはするか」 |
「少納言や。直衣を着ているという方は、どちら。父宮がいらしたの」 |
「少納言、直衣着た方どちら、宮様なの」 |
"Seunagon yo. Nahosi ki tari tu ram ha, idura? Miya no ohasuru ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.20 | とて、寄りおはしたる御声、 いとらうたし ★。 |
と言って、近づいて来るお声が、とてもかわいらしい。 |
こう言いながら乳母のそばへ寄って来た声がかわいかった。 |
tote, yori ohasi taru ohom-kowe, ito rautasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.21 | 「 宮にはあらねど、また思し放つべうもあらず。こち」 |
「宮さまではありませんが、必ずしも関係ない人ではありません。こちらへ」 |
これは父宮ではなかったが、やはり深い愛を小女王に持つ源氏であったから、心がときめいた。 「こちらへいらっしゃい」 |
"Miya ni ha ara ne do, mata obosi-hanatu beu mo arazu. Koti." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.22 | とのたまふを、 恥づかしかりし人と、さすがに聞きなして、悪しう言ひてけりと思して、乳母にさし寄りて、 |
とおっしゃると、あの素晴らしかった方だと、子供心にも聞き分けて、まずいことを言ってしまったとお思いになって、乳母の側に寄って、 |
と言ったので、父宮でなく源氏の君であることを知った女王は、さすがにうっかりとしたことを言ってしまったと思うふうで、乳母のそばへ寄って、 |
to notamahu wo, hadukasikari si hito to, sasuga ni kiki-nasi te, asiu ihi te keri to obosi te, Menoto ni sasi-yori te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.23 | 「 いざかし、ねぶたきに」とのたまへば、 |
「ねえ、行きましょうよ。眠いから」とおっしゃるので、 |
「さあ行こう。私は眠いのだもの」 と言う。 |
"Iza-kasi, nebutaki ni." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.24 | 「 今さらに、 など忍びたまふらむ。この膝の上に大殿籠もれよ。今すこし寄りたまへ」 |
「今さら、どうして逃げ隠れなさるのでしょう。わたしの膝の上でお寝みなさいませ。もう少し近くへいらっしゃい」 |
「もうあなたは私に御遠慮などしないでもいいんですよ。私の膝の上へお寝みなさい」 |
"Imasara ni, nado sinobi tamahu ram. Kono hiza no uhe ni ohotonogomore yo. Ima sukosi yori tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.25 | とのたまへば、乳母の、 |
とおっしゃると、乳母が、 |
と源氏が言った。 |
to notamahe ba, Menoto no, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.26 | 「 さればこそ。かう世づかぬ 御ほどにてなむ」 |
「これですから。このようにまだ頑是ないお年頃でして」 |
「お話しいたしましたとおりでございましょう。こんな赤様なのでございます」 |
"Sareba koso. Kau yoduka nu ohom-hodo ni te nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.27 | とて、 押し寄せたてまつりたれば、 何心もなくゐたまへるに、 手をさし入れて探りたまへれば、 なよらかなる御衣に、髪はつやつやとかかりて、末のふさやかに探りつけられたる、いとうつくしう思ひ ▼ やらる。手をとらへたまへれば、 うたて例ならぬ人の、かく近づきたまへるは、恐ろしうて、 |
と言って、押しやり申したところ、無心にお座りになったので、お手を差し入れてお探りになると、柔らかなお召物の上に、髪がつやつやと掛かって、末の方までふさふさしているのが、とてもかわいらしく想像される。お手を捉えなさると、気味の悪いよその人が、このように近くにいらっしゃるのは、恐ろしくなって、 |
乳母に源氏のほうへ押し寄せられて、女王はそのまま無心にすわっていた。源氏が御簾の下から手を入れて探ってみると柔らかい着物の上に、ふさふさとかかった端の厚い髪が手に触れて美しさが思いやられるのである。手をとらえると、父宮でもない男性の近づいてきたことが恐ろしくて、 |
tote, osi-yose tatematuri tare ba, nani-gokoro mo naku wi tamahe ru ni, te wo sasi-ire te saguri tamahe re ba, nayoraka naru ohom-zo ni, kami ha tuya-tuya to kakari te, suwe no husayaka ni saguri-tuke rare taru, ito utukusiu omohi-yara ru. Te wo torahe tamahe re ba, utate rei nara nu hito no, kaku tikaduki tamahe ru ha, osorosiu te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.28 | 「 寝なむ、と言ふものを」 |
「寝よう、と言っているのに」 |
「私、眠いと言っているのに」 |
"Ne na m, to ihu monowo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.29 | とて、強ひて引き入りたまふにつきてすべり入りて、 |
と言って、無理に奥に入って行きなさるのに後から付いて御簾の中にすべり入って、 |
と言って手を引き入れようとするのについて源氏は御簾の中へはいって来た。 |
tote, sihite hiki-iri tamahu ni tuki te suberi-iri te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.30 | 「 今は、 まろぞ思ふべき人。 な疎みたまひそ」 |
「今は、わたしが世話して上げる人ですよ。お嫌いにならないでね」 |
「もう私だけがあなたを愛する人なんですよ。私をお憎みになってはいけない」 |
"Ima ha, maro zo omohu beki hito. Na utomi tamahi so." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.31 | とのたまふ。乳母、 |
とおっしゃる。乳母が、 |
源氏はこう言っている。少納言が、 |
to notamahu. Menoto, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.32 | 「 いで、あなうたてや。ゆゆしうもはべるかな。 聞こえさせ知らせたまふとも、 さらに何のしるしもはべらじものを」とて、苦しげに思ひたれば、 |
「あら、まあ嫌でございますわ。あまりのなさりようでございますわ。いくらお話申し上げあそばしても、何の甲斐もございませんでしょうに」といって、つらそうに困っているので、 |
「よろしくございません。たいへんでございます。お話しになりましても何の効果もございませんでしょうのに」 と困ったように言う。 |
"Ide, ana utate ya! Yuyusiu mo haberu kana! Kikoyesase sira se tamahu tomo, sarani nani no sirusi mo habera zi monowo." tote, kurusige ni omohi tare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.33 | 「 さりとも、かかる御ほどを いかがはあらむ。なほ、ただ世に知らぬ心ざしのほどを 見果てたまへ」とのたまふ。 |
「いくらなんでも、このようなお年の方をどうしようか。やはり、ただ世間にないほどのわたしの愛情をお見届けください」とおっしゃる。 |
「いくら何でも私はこの小さい女王さんを情人にしようとはしない。まあ私がどれほど誠実であるかを御覧なさい」 |
"Saritomo, kakaru ohom-hodo wo ikaga ha ara m? Naho, tada yo ni sira nu kokorozasi no hodo wo mi-hate tamahe." to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.34 | 霰降り荒れて、すごき夜のさまなり。 |
霰が降り荒れて、恐ろしい夜の様子である。 |
外には霙が降っていて凄い夜である。 |
Arare huri are te, sugoki yo no sama nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.35 | 「 いかで、かう人少なに心細うて、過ぐしたまふらむ」 |
「どうして、このような少人数な所で頼りなく過ごしていらっしゃれようか」 |
「こんなに小人数でこの寂しい邸にどうして、住めるのですか」 |
"Ikade, kau hito-zukuna ni kokoro-bosou te, sugusi tamahu ram?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.36 | と、うち泣いたまひて、 いと見棄てがたきほどなれば、 |
と思うと、ついお泣きになって、とても見捨てては帰りにくい有様なので、 |
と言って源氏は泣いていた。捨てて帰って行けない気がするのであった。 |
to, uti-nai tamahi te, ito mi-sute gataki hodo nare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.37 | 「 御格子参りね。もの恐ろしき 夜のさまなめるを、宿直人にてはべらむ。 人びと、近うさぶらはれよかし」 |
「御格子を下ろしなさい。何となく恐そうな夜の感じのようですから、宿直人となってお勤めしましょう。女房たち、近くに参りなさい」 |
「もう戸をおろしておしまいなさい。こわいような夜だから、私が宿直の男になりましょう。女房方は皆女王さんの室へ来ていらっしゃい」 |
"Mi-kausi mawiri ne. Mono-osorosiki yo no sama na' meru wo, tonowi-bito ni te habera m. Hito-bito, tikau saburaha re yo kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.38 | とて、いと馴れ顔に 御帳のうちに入りたまへば、 あやしう思ひのほかにもと、あきれて、誰も誰もゐたり。乳母は、うしろめたなうわりなしと 思へど、荒ましう聞こえ騒ぐべきならねば、うち嘆きつつゐたり。 |
と言って、とても物馴れた態度で御帳の内側にお入りになるので、奇妙な思いも寄らないことをと、あっけにとられて、一同茫然としている。乳母は、心配で困ったことだと思うが、事を荒立て申すべき場合でないので、嘆息しながら見守っていた。 |
と言って、馴れたことのように女王さんを帳台の中へ抱いてはいった。だれもだれも意外なことにあきれていた。乳母は心配をしながらも普通の闖入者を扱うようにはできぬ相手に歎息をしながら控えていた。 |
tote, ito nare-gaho ni mi-tyau no uti ni iri tamahe ba, ayasiu omohi no hoka ni mo to, akire te, tare mo tare mo wi tari. Menoto ha, usirometanau warinasi to omohe do, aramasiu kikoye sawagu beki nara ne ba, uti-nageki tutu wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.39 | 若君は、いと恐ろしう、 いかならむとわななかれて、いとうつくしき御肌つきも、そぞろ寒げに思したるを、らうたくおぼえて、 単衣ばかりを押しくくみて、わが御心地も、 かつはうたておぼえたまへど、あはれにうち語らひたまひて、 |
若君は、とても恐ろしく、どうなるのだろうと自然と震えて、とてもかわいらしいお肌も、ぞくぞくと粟立つ感じがなさるのを、源氏の君はいじらしく思われて、肌着だけで包み込んで、ご自分ながらも、一方では変なお気持ちがなさるが、しみじみとお話なさって、 |
小女王は恐ろしがってどうするのかと慄えているので肌も毛穴が立っている。かわいく思う源氏はささやかな異性を単衣に巻きくるんで、それだけを隔てに寄り添っていた。この所作がわれながら是認しがたいものとは思いながらも愛情をこめていろいろと話していた。 |
Waka-Gimi ha, ito osorosiu, ika nara m to wananaka re te, ito utukusiki ohom-hadatuki mo, sozoro samuge ni obosi taru wo, rautaku oboye te, hitohe bakari wo osi-kukumi te, waga mi-kokoti mo, katu ha utate oboye tamahe do, ahare ni uti-katarahi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.40 | 「 いざ、たまへよ。をかしき絵など多く、雛遊びなどする所に」 |
「さあ、いらっしゃいよ。美しい絵などが多く、お人形遊びなどする所に」 |
「ねえ、いらっしゃいよ、おもしろい絵がたくさんある家で、お雛様遊びなんかのよくできる私の家へね」 |
"Iza, tamahe yo! Wokasiki we nado ohoku, hihina-asobi nado suru tokoro ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.41 | と、心につくべきことをのたまふけはひの、 いとなつかしきを、幼き心地にも、いといたう怖ぢず、 さすがに、むつかしう寝も入らずおぼえて、身じろき臥したまへり。 |
と、気に入りそうなことをおっしゃる様子が、とても優しいので、子供心にも、そう大して物怖じせず、とは言っても、気味悪くて眠れなく思われて、もじもじして横になっていらっしゃった。 |
こんなふうに小さい人の気に入るような話をしてくれる源氏の柔らかい調子に、姫君は恐ろしさから次第に解放されていった。しかし不気味であることは忘れずに、眠り入ることはなくて身じろぎしながら寝ていた。 |
to, kokoro ni tuku beki koto wo notamahu kehahi no, ito natukasiki wo, wosanaki kokoti ni mo, ito itau odi zu, sasuga ni, mutukasiu ne mo ira zu oboye te, miziroki husi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.42 | 夜一夜、風吹き荒るるに、 |
一晩中、風が吹き荒れているので、 |
この晩は夜通し風が吹き荒れていた。 |
Yo hito-yo, kaze huki-aruru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.43 | 「 げに、かう、おはせざらましかば、いかに心細からまし」 |
「ほんとうに、このように、お越し下さらなかったら、どんなに心細かったことでしょう」 |
「ほんとうにお客様がお泊まりにならなかったらどんなに私たちは心細かったでしょう。 |
"Geni, kau, ohase zara masika ba, ikani kokoro-bosokara masi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.44 | 「 同じくは、よろしきほどにおはしまさましかば」 |
「同じことなら、お似合いの年でおいであそばしたら」 |
同じことなら女王様がほんとうの御結婚のできるお年であればね」 |
"Onaziku ha, yorosiki hodo ni ohasimasa masika ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.45 | とささめきあへり。乳母は、うしろめたさに、いと近うさぶらふ。風すこし吹きやみたるに、 夜深う出でたまふも、 ことあり顔なりや。 |
とささやき合っている。少納言の乳母は、心配で、すぐ近くに控えている。風が少し吹き止んだので、夜の深いうちにお帰りになるのも、いかにもわけありそうな朝帰りであるよ。 |
などと女房たちはささやいていた。心配でならない乳母は帳台の近くに侍していた。風の少し吹きやんだ時はまだ暗かったが、帰る源氏はほんとうの恋人のもとを別れて行く情景に似ていた。 |
to sasameki-ahe ri. Menoto ha, usirometasa ni, ito tikau saburahu. Kaze sukosi huki yami taru ni, yo-bukau ide tamahu mo, koto-ari-gaho nari ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.46 | 「 いとあはれに見たてまつる御ありさまを、今はまして、片時の間もおぼつかなかるべし。 明け暮れ眺めはべる所に渡したてまつらむ。 かくてのみは、いかが。もの怖ぢしたまはざりけり」とのたまへば、 |
「とてもお気の毒にお見受け致しましたご様子を、今では以前にもまして、片時の間も見なくては気がかりでならないでしょう。毎日物思いをして暮らしている所にお迎え申し上げましょう。こうしてばかりいては、どんなものでしょうか。姫君はお恐がりにはならなかった」とおっしゃると、 |
「かわいそうな女王さんとこんなに親しくなってしまった以上、私はしばらくの間もこんな家へ置いておくことは気がかりでたまらない。私の始終住んでいる家へお移ししよう。こんな寂しい生活をばかりしていらっしゃっては女王さんが神経衰弱におなりになるから」 と源氏が言った。 |
"Ito ahare ni mi tatematuru ohom-arisama wo, ima ha masite, kata-toki no ma mo obotukanakaru besi. Akekure nagame haberu tokoro ni watasi tatematura m. Kakute nomi ha, ikaga? Mono-odi si tamaha zari keri." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.47 | 「 宮も御迎へになど聞こえのたまふめれど、 この御四十九日過ぐしてや、 など 思うたまふる」と聞こゆれば、 |
「父宮もお迎えになどと申していらっしゃるようですが、故尼君の四十九日忌が過ぎてからか、などと存じます」と申し上げると、 |
「宮様もそんなにおっしゃいますが、あちらへおいでになることも、四十九日が済んでからがよろしかろうと存じております」 |
"Miya mo ohom-mukahe ni nado kikoye notamahu mere do, kono ohom-nana-nanuka sugusi te ya? nado omou tamahuru." to kikoyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.48 | 「 頼もしき筋ながらも、よそよそにてならひたまへるは、同じうこそ疎うおぼえたまはめ。今より見たてまつれど、 浅からぬ心ざしはまさりぬべくなむ」 |
「頼りになる血筋ではあるが、ずっと別々に暮らして来られた方は、他人同様に疎々しくお思いでしょう。今夜初めてお会いしたが、わたしの深い愛情は父宮様以上でしょう」 |
「お父様のお邸ではあっても、小さい時から別の所でお育ちになったのだから、私に対するお気持ちと親密さはそう違わないでしょう。今からいっしょにいることが将来の障りになるようなことは断じてない。私の愛が根底の深いものになるだけだと思う」 |
"Tanomosiki sudi nagara mo, yoso-yoso ni te narahi tamahe ru ha, onaziu koso utou oboye tamaha me. Ima yori mi tatemature do, asakara nu kokorozasi ha masari nu beku nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.49 | とて、 かい撫でつつ、かへりみがちにて出でたまひぬ。 |
と言って、かき撫でかき撫でして、後髪を引かれる思いでお出になった。 |
と女王の髪を撫でながら源氏は言って顧みながら去った。 |
tote, kai-nade tutu, kaherimi-gati ni te ide tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.50 | いみじう霧りわたれる空もただならぬに、霜はいと白うおきて、 まことの懸想もをかしかりぬべきに、 さうざうしう思ひおはす。 いと忍びて通ひたまふ所の道なりけるを思し出でて、門うちたたかせたまへど、聞きつくる人なし。かひなくて、御供に声ある人して歌はせたまふ。 |
ひどく霧の立ちこめた空もいつもとは違った風情であるうえに、霜は真白に置いて、実際の恋であったら興趣あるはずなのに、何か物足りなく思っていらっしゃる。たいそう忍んでお通いになる方への道筋であったのをお思い出しになって、門を叩かせなさるが、聞きつける人がいない。しかたなくて、お供の中で声の良い者に歌わせなさる。 |
深く霧に曇った空も艶であって、大地には霜が白かった。ほんとうの恋の忍び歩きにも適した朝の風景であると思うと、源氏は少し物足りなかった。近ごろ隠れて通っている人の家が途中にあるのを思い出して、その門をたたかせたが内へは聞こえないらしい。しかたがなくて供の中から声のいい男を選んで歌わせた。 |
Imiziu kiri watare ru sora mo tadanaranu ni, simo ha ito sirou oki te, makoto no kesau mo wokasikari nu beki ni, sau-zausiu omohi ohasu. Ito sinobi te kayohi tamahu tokoro no miti nari keru wo obosi-ide te, kado uti-tataka se tamahe do, kiki-tukuru hito nasi. Kahinaku te, ohom-tomo ni kowe aru hito site utaha se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.51 | 「 朝ぼらけ霧立つ空のまよひにも |
「曙に霧が立ちこめた空模様につけても |
朝ぼらけ霧立つ空の迷ひにも |
"Asaborake kiri tatu sora no mayohi ni mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.52 | 行き過ぎがたき 妹が門かな」 |
素通りし難い貴女の家の前ですね」 |
行き過ぎがたき妹が門かな |
yukisugi-gataki imo-ga-kado kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.53 | と、 二返りばかり歌ひたるに、よしある下仕ひを出だして、 |
と、二返ほど歌わせたところ、心得ある下仕え人を出して、 |
二度繰り返させたのである。気のきいたふうをした下仕えの女中を出して、 |
to, huta-kaheri bakari utahi taru ni, yosi aru simo-dukahi wo idasi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.54 | 「 立ちとまり霧のまがきの過ぎうくは |
「霧の立ちこめた家の前を通り過ぎ難いとおっしゃるならば |
立ちとまり霧の籬の過ぎうくば |
"Tati-tomari kiri no magaki no sugi-uku ha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.55 | 草のとざしにさはりしもせじ」 |
生い茂った草が門を閉ざしたことぐらい何でもないでしょうに」 |
草の戸ざしに障りしもせじ |
kusa no tozasi ni sahari simo se zi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.56 | と言ひかけて、入りぬ。 また人も出で来ねば、帰るも情けなけれど、明けゆく空もはしたなくて殿へおはしぬ。 |
と詠みかけて、入ってしまった。他に誰も出て来ないので、帰るのも風情がないが、空が明るくなって行くのも体裁が悪いので邸へお帰りになった。 |
と言わせた。女はすぐに門へはいってしまった。それきりだれも出て来ないので、帰ってしまうのも冷淡な気がしたが、夜がどんどん明けてきそうで、きまりの悪さに二条の院へ車を進めさせた。 |
to ihi-kake te, iri nu. Mata hito mo ide-ko ne ba, kaheru mo nasakenakere do, ake-yuku sora mo hasitanaku te tono he ohasi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.57 | をかしかりつる人のなごり恋しく、独り笑みしつつ臥したまへり。日高う大殿籠もり起きて、 文やりたまふに、書くべき言葉も例ならねば、 筆うち置きつつすさびゐたまへり。をかしき絵などをやりたまふ。 |
かわいらしかった方の面影が恋しく、独り微笑みながら臥せっていらっしゃった。日が高くなってからお起きになって、手紙を書いておやりになる時、書くはずの言葉も普通と違うので、筆を書いては置き書いては置きと、気の向くままにお書きになっている。美しい絵などをお届けなさる。 |
かわいかった小女王を思い出して、源氏は独り笑みをしながら又寝をした。朝おそくなって起きた源氏は手紙をやろうとしたが、書く文章も普通の恋人扱いにはされないので、筆を休め休め考えて書いた。よい絵なども贈った。 |
Wokasikari turu hito no nagori kohisiku, hitori-wemi si tutu husi tamahe ri. Hi takau ohotonogomori oki te, humi yari tamahu ni, kaku beki kotoba mo rei nara ne ba, hude uti-oki tutu susabi wi tamahe ri. Wokasiki we nado wo yari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.58 | かしこには、 今日しも、宮わたりたまへり。 年ごろよりもこよなう荒れまさり、広うもの古りたる所の、いとど人少なに 久しければ、 見わたしたまひて、 |
あちらでは、ちょうど今日、父宮がおいでになった。数年来以上にすっかり荒れ行き、広く古めかしくなった邸が、ますます人数が少なくなって月日を経ているので、ずっと御覧になって、 |
今日は按察使大納言家へ兵部卿の宮が来ておいでになった。以前よりもずっと邸が荒れて、広くて古い家に小人数でいる寂しさが宮のお心を動かした。 |
Kasiko ni ha, kehu simo, Miya watari tamahe ri. Tosigoro yori mo koyonau are-masari, hirou mono-huri taru tokoro no, itodo hito-zukuna ni hisasikere ba, mi-watasi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.59 | 「 かかる所には、 いかでか、しばしも幼き人の過ぐしたまはむ。なほ、 かしこに渡したてまつりてむ。何の所狭きほどにもあらず。乳母は、 曹司などしてさぶらひなむ。君は、若き人びとあれば、もろともに遊びて、 いとようものしたまひなむ」などのたまふ。 |
「このような所には、どうして、少しの間でも幼い子供がお過しになれよう。やはり、あちらにお引き取り申し上げよう。けっして窮屈な所ではない。乳母には、部屋をもらって仕えればよい。姫君は、若い子たちがいるので、一緒に遊んで、とても仲良くやって行けよう」などとおっしゃる。 |
「こんな所にしばらくでも小さい人がいられるものではない。やはり私の邸のほうへつれて行こう。たいしたむずかしい所ではないのだよ。乳母は部屋をもらって住んでいればいいし、女王は何人も若い子がいるからいっしょに遊んでいれば非常にいいと思う」 などとお言いになった。 |
"Kakaru tokoro ni ha, ikadeka, sibasi mo wosanaki hito no sugusi tamaha m. Naho, kasiko ni watasi tatematuri te m. Nani no tokoro-seki hodo ni mo ara zu. Menoto ha, zausi nado si te saburahi na m. Kimi ha, wakaki hito-bito are ba, morotomoni asobi te, ito you monosi tamahi na m." nado notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.60 | 近う呼び寄せたてまつりたまへるに、 かの御移り香の、いみじう艶に 染みかへらせたまへれば、「 をかしの御匂ひや。御衣はいと萎えて」と、心苦しげに思いたり。 |
近くにお呼び寄せになると、あの源氏の君のおん移り香が、たいそうよい匂いに深く染み着いていらっしゃるので、「いい匂いだ。お召し物はすっかりくたびれているが」と、お気の毒にお思いになった。 |
そばへお呼びになった小女王の着物には源氏の衣服の匂いが深く沁んでいた。 「いい匂いだね。げれど着物は古くなっているね」 心苦しく思召す様子だった。 |
Tikau yobi-yose tatematuri tamahe ru ni, kano ohom-uturiga no, imiziu en ni simi-kahera se tamahe re ba, "Wokasi no ohom-nihohi ya! Ohom-zo ha ito nahe te." to, kokoro-gurusige ni oboi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.61 | 「 年ごろも、 あつしくさだ過ぎたまへる人に 添ひたまへるよ、かしこにわたりて見ならしたまへなど、ものせしを、 あやしう疎みたまひて、 人も心置くめりしを、かかる折にしもものしたまはむも、心苦しう」などのたまへば、 |
「これまでは、病気がちのお年寄と一緒においでになったことよ、あちらに引っ越してお馴染みなさいなどと、言っていましたが、変にお疎んじなさって、妻もおもしろからぬようでいたが、このような時に移って来られるのも、おかわいそうに」などとおっしゃると、 |
「今までからも病身な年寄りとばかりいっしょにいるから、時々は邸のほうへよこして、母と子の情合いのできるようにするほうがよいと私は言ったのだけれど、絶対的にお祖母さんはそれをおさせにならなかったから、邸のほうでも反感を起こしていた。そしてついにその人が亡くなったからといってつれて行くのは済まないような気もする」 と宮がお言いになる。 |
"Tosigoro mo, atusiku sada-sugi tamahe ru hito ni sohi tamahe ru yo, kasiko ni watari te mi-narasi tamahe nado, monose si wo, ayasiu utomi tamahi te, hito mo kokoro-oku meri si wo, kakaru wori ni si mo monosi tamaha m mo, kokoro-gurusiu." nado notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.62 | 「 何かは。心細くとも、しばしはかくて おはしましなむ。すこしものの心思し知りなむにわたらせたまはむ こそ、よくははべるべけれ」と聞こゆ。 |
「いえどう致しまして。心細くても、今暫くはこうしておいであそばしましょう。もう少し物の道理がお分かりになりましたら、お移りあそばされることが良うございましょう」と申し上げる。 |
「そんなに早くあそばす必要はございませんでしょう。お心細くても当分はこうしていらっしゃいますほうがよろしゅうございましょう。少し物の理解がおできになるお年ごろになりましてからおつれなさいますほうがよろしいかと存じます」 少納言はこう答えていた。 |
"Nani-kaha. Kokoro-bosoku tomo, sibasi ha kaku te ohasimasi na m. Sukosi mono no kokoro obosi-siri na m ni watara se tamaha m koso, yoku ha haberu bekere." to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.63 | 「 夜昼恋ひきこえたまふに ★、はかなきものもきこしめさず」 |
「夜昼となくお慕い申し上げなさって、ちょっとした物もお召し上がりになりません」 |
「夜も昼もお祖母様が恋しくて泣いてばかりいらっしゃいまして、召し上がり物なども少のうございます」 |
"Yoru hiru kohi kikoye tamahu ni, hakanaki mono mo kikosimesa zu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.64 | とて、 げにいといたう面痩せたまへれど、 いとあてにうつくしく、なかなか見えたまふ。 |
と申して、なるほど、とてもひどく面痩せなさっているが、まことに上品でかわいらしく、かえって美しくお見えになる。 |
とも歎いていた。実際姫君は痩せてしまったが、上品な美しさがかえって添ったかのように見える。 |
tote, geni ito itau omo-yase tamahe re do, ito ate ni utukusiku, naka-naka miye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.65 | 「 何か、さしも思す。今は世に亡き人の御ことはかひなし。 おのれあれば」 |
「どうして、そんなにお悲しみなさる。今はもうこの世にいない方のことは、しかたがありません。わたしがついているので」 |
「なぜそんなにお祖母様のことばかりをあなたはお思いになるの、亡くなった人はしかたがないんですよ。お父様がおればいいのだよ」 |
"Nani ka, sasimo obosu. Ima ha yo ni naki hito no ohom-koto ha kahinasi. Onore are ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.66 | など語らひきこえたまひて、 暮るれば帰らせたまふを、 いと心細しと思いて泣いたまへば、宮うち泣きたまひて、 |
などとやさしくお話申し上げなさって、日が暮れるとお帰りあそばすのを、とても心細いとお思いになってお泣きになると、宮ももらい泣きなさって、 |
と宮は言っておいでになった。日が暮れるとお帰りになるのを見て、心細がって姫君が泣くと、宮もお泣きになって、 |
nado katarahi kikoye tamahi te, kurure ba kahera se tamahu wo, ito kokoro-bososi to oboi te nai tamahe ba, Miya uti-naki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.67 | 「 いとかう 思ひな入りたまひそ。今日明日、渡したてまつらむ」など、返す返すこしらへおきて、出でたまひぬ。 |
「けっして、そんなにご心配なさるな。今日明日のうちに、お移し申そう」などと、繰り返しなだめすかして、お帰りになった。 |
「なんでもそんなに悲しがってはしかたがない。今日明日にでもお父様の所へ来られるようにしよう」 などと、いろいろになだめて宮はお帰りになった。 |
"Ito kau omohi na iri tamahi so. Kehu-asu, watasi tatematura m." nado, kahesu-gahesu kosirahe-oki te, ide tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.68 | なごりも慰めがたう泣きゐたまへり。行く先の身のあらむことなどまでも思し知らず、ただ年ごろ 立ち離るる折なうまつはしならひて、今は亡き人となりたまひにける、と思すがいみじきに、幼き御心地なれど、胸つとふたがりて、例のやうにも遊びたまはず、昼はさても紛らはしたまふを、夕暮となれば、いみじく屈したまへば、 かくてはいかでか過ごしたまはむと、慰めわびて、乳母も泣きあへり。 |
その後の寂しさも慰めようがなく泣き沈んでいらっしゃった。将来の身の上のことなどはお分りにならず、ただ長年離れることなく一緒にいて、今はお亡くなりになってしまったと、お思いになるのが悲しくて、子供心であるが、胸がいっぱいにふさがって、いつものようにもお遊びはなさらず、昼間はどうにかお紛らわしになるが、夕暮時になると、ひどくおふさぎこみなさるので、これではどのようにお過ごしになられようかと、慰めあぐねて、乳母たちも一緒に泣いていた。 |
母も祖母も失った女の将来の心細さなどを女王は思うのでなく、ただ小さい時から片時の間も離れず付き添っていた祖母が死んだと思うことだけが非常に悲しいのである。子供ながらも悲しみが胸をふさいでいる気がして遊び相手はいても遊ぼうとしなかった。それでも昼間は何かと紛れているのであったが、夕方ごろからめいりこんでしまう。こんなことで小さいおからだがどうなるかと思って、乳母も毎日泣いていた。 |
Nagori mo nagusame gatau naki wi tamahe ri. Yuku-saki no mi no ara m koto nado made mo obosi-sira zu, tada tosigoro tati-hanaruru wori nau matuhasi narahi te, ima ha naki-hito to nari tamahi ni keru, to obosu ga imiziki ni, wosanaki mi-kokoti nare do, mune tuto hutagari te, rei no yau ni mo asobi tamaha zu, hiru ha sate mo magirahasi tamahu wo, yuhugure to nare ba, imiziku ku'-si tamahe ba, kaku te ha ikade ka sugosi tamaha m to, nagusame wabi te, Menoto mo naki-ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.69 | 君の御もとよりは、惟光を たてまつれたまへり。 |
源氏の君のお邸からは、惟光をお差し向けなさった。 |
その日源氏の所からは惟光をよこした。 |
Kimi no ohom-moto yori ha, Koremitu wo tatemature tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.70 | 「 参り来べきを、 内裏より召あればなむ。 心苦しう見たてまつりしも、しづ心なく」とて、宿直人たてまつれたまへり。 |
「私自身参るべきところ、帝からお召しがありまして。お気の毒に拝見致しましたのにつけても、気がかりで」と伝えて、宿直人を差し向けなさった。 |
伺うはずですが宮中からお召しがあるので失礼します。おかわいそうに拝見した女王さんのことが気になってなりません。 源氏からの挨拶はこれで惟光が代わりの宿直をするわけである。 |
"Mawiri ku beki wo, Uti yori mesi are ba nam. Kokoro-gurusiu mi tatematuri si mo, sidu-kokoro naku." tote, tonowi-bito tatemature tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.71 | 「 あぢきなうもあるかな。戯れにても、 もののはじめにこの御ことよ」 |
「情けないことですわ。ご冗談にも結婚の最初からして、このようなお事とは」 |
「困ってしまう。将来だれかと御結婚をなさらなければならない女王様を、これではもう源氏の君が奥様になすったような形をお取りになるのですもの。 |
"Adikinau mo aru kana! Tahabure ni te mo, mono-no-hazime ni kono ohom-koto yo!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.72 | 「宮聞こし召しつけば、さぶらふ人びとのおろかなるにぞ さいなまむ」 |
「宮さまがお耳にされたら、お仕えする者の落度として叱られましょう」 |
宮様がお聞きになったら私たちの責任だと言っておしかりになるでしょう」 |
"Miya kikosimesi tuke ba, saburahu hito-bito no oroka naru ni zo sainama m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.73 | 「あなかしこ、もののついでに、いはけなく うち出できこえさせたまふ ★ な」 |
「ああ、大変だわ。何かのついでに、父宮にうっかりお口にあそばされますな」 |
「ねえ女王様、お気をおつけになって、源氏の君のことは宮様がいらっしゃいました時にうっかり言っておしまいにならないようになさいませね」 |
"Ana kasiko! Mono no tuide ni, ihakenaku uti-ide kikoyesase tmahu na!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.74 | など言ふも、 それをば何とも思したらぬぞ、あさましきや。 |
などと言うにつけても、そのことを何ともお分りでいらっしゃらないのは、困ったことであるよ。 |
と少納言が言っても、小女王は、それが何のためにそうしなければならないかがわからないのである。 |
nado ihu mo, sore wo ba nani to mo obosi tara nu zo, asamasi ki ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.75 | 少納言は、惟光に あはれなる物語どもして、 |
少納言の乳母は、惟光に気の毒な身の上話をいろいろとして、 |
少納言は惟光の所へ来て、身にしむ話をした。 |
Seunagon ha, Koremitu ni ahare naru monogatari-domo si te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.76 | 「 あり経て後や、 さるべき御宿世、 逃れきこえたまはぬやうもあらむ。ただ今は、かけてもいと似げなき御ことと見たてまつるを、あやしう 思しのたまはするも、いかなる御心にか、思ひ寄るかたなう乱れはべる。今日も、 宮渡らせたまひて、『 うしろやすく仕うまつれ。 心幼くもてなしきこゆな』とのたまはせつるも、いとわづらはしう、ただなるよりは、かかる御好き事も 思ひ出でられはべりつる」 |
「これから先いつか、ご一緒になるようなご縁から、お逃れ申されなさらいものかも知れません。ただ今は、まったく不釣り合いなお話と拝察致しておりますが、不思議にご熱心に思ってくださり、またおっしゃってくださいますのを、どのようなお気持ちからかと、判断つかないで悩んでおります。今日も、宮さまがお越しあそばして、『安心の行くように仕えなさい。うっかりしたことは致すな』と仰せられたのも、とても厄介で、なんでもなかった時より、このような好色めいたことも改めて気になるのでございました」 |
「将来あるいはそうおなりあそばす運命かもしれませんが、ただ今のところはどうしてもこれは不つりあいなお間柄だと私らは存じますのに、御熱心に御縁組のことをおっしゃるのですもの、御酔興か何かと私どもは思うばかりでございます。今日も宮様がおいでになりまして、女の子だからよく気をつけてお守りをせい、うっかり油断をしていてはいけないなどとおっしゃいました時は、私ども何だか平気でいられなく思われました。昨晩のことなんか思い出すものですから」 |
"Ari he te noti ya, saru-beki ohom-sukuse, nogare kikoye tamaha nu yau mo ara m. Tada ima ha, kakete mo ito nigenaki ohom-koto to mi tatematuru wo, ayasiu obosi notamaha suru mo, ika naru mi-kokoro ni ka, omohi-yoru kata nau midare haberu. Kehu mo, Miya watara se tamahi te, 'Usiro-yasuku tukau-mature. Kokoro-wosanaku motenasi kikoyu na.' to notamahase turu mo, ito wadurahasiu, tada naru yori ha, kakaru ohom-suki-goto mo omohi-ide rare haberi turu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.77 | など 言ひて、「 この人もことあり顔にや思はむ」など、 あいなければ、いたう嘆かしげにも言ひなさず。 大夫も、「いかなることにかあらむ」と、心得がたう思ふ。 |
などと言って、「この人も何か特別の関係があったように思うだろうか」など思われるのも、不本意なので、ひどく悲しんでいるようには言わない。惟光大夫も、「どのような事なのだろう」と、ふに落ちなく思う。 |
などと言いながらも、あまりに歎いて見せては姫君の処女であることをこの人に疑わせることになると用心もしていた。惟光もどんな関係なのかわからない気がした。 |
nado ihi te, "Kono hito mo koto-ari-gaho ni ya omoha m?" nado, ainakere ba, itau nagekasige ni mo ihi-nasa zu. Taihu mo, "Ika naru koto ni ka ara m?" to, kokoroe gatau omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.78 | 参りて、ありさまなど聞こえければ、 あはれに思しやらるれど、さて通ひたまはむも、さすがに すずろなる心地して、「 軽々しうもてひがめたると、 人もや漏り聞かむ」など、つつましければ、「 ただ迎へてむ」と思す。 |
帰参して、様子などをご報告すると、しみじみと思いをお馳せになるが、先夜のようにお通いなさるのも、やはり似合わしくない気持ちがして、「軽率な風変わりなことをしていると、世間の人が聞き知るかも知れない」などと、遠慮されるので、「いっそ迎えてしまおう」とお考えになる。 |
帰って惟光が報告した話から、源氏はいろいろとその家のことが哀れに思いやられてならないのであったが、形式的には良人らしく一泊したあとであるから、続いて通って行かねばならぬが、それはさすがに躊躇された。酔興な結婚をしたように世間が批評しそうな点もあるので、心がおけて行けないのである。二条の院へ迎えるのが良策であると源氏は思った。 |
Mawiri te, arisama nado kikoye kere ba, ahare ni obosi-yara rure do, sate kayohi tamaha m mo, sasuga ni suzuro naru kokoti si te, "Karu-garusiu mote-higame taru to, hito mo ya mori-kika m?" nado, tutumasikere ba, "Tada mukahe te m." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.79 | 御文はたびたびたてまつれたまふ。暮るれば、 例の大夫をぞたてまつれたまふ。「 障はる事どものありて、え参り 来ぬを、おろかにや」などあり。 |
お手紙は頻繁に差し上げなさる。暮れると、いつものように惟光大夫をお差し向けなさる。「差し障りがあって参れませんのを、不熱心なとでも」などと、伝言がある。 |
手紙は始終送った。日が暮れると惟光を見舞いに出した。 やむをえぬ用事があって出かけられないのを、私の不誠実さからだとお思いにならぬかと不安です。 などという手紙が書かれてくる。 |
Ohom-humi ha tabi-tabi tatemature tamahu. Kurure ba, rei no Taihu wo zo tatemature tamahu. "Saharu koto-domo no ari te, e mawiri ko nu wo, oroka ni ya?" nado ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.80 | 「 宮より、明日にはかに御迎へにとのたまはせたりつれば、 心あわたたしくてなむ。年ごろの 蓬生を離れなむも、さすがに心細く、さぶらふ人びとも 思ひ乱れて ★」 |
「宮さまから、明日急にお迎えに参ると仰せがありましたので、気ぜわしくて。長年住みなれた蓬生の宿を離れますのも、何と言っても心細く、お仕えする女房たちも思い乱れております」 |
「宮様のほうから、にわかに明日迎えに行くと言っておよこしになりましたので、取り込んでおります。長い馴染の古いお邸を離れますのも心細い気のすることと私どもめいめい申し合っております」 |
"Miya yori, asu nihaka ni ohom-mukahe ni to notamahase tari ture ba, kokoro-awatatasiku te nam. Tosigoro no yomogihu wo kare na m mo, sasuga ni kokoro-bosoku, saburahu hito-bito mo omohi-midare te." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.81 | と、言少なに言ひて、 をさをさあへしらはず、 もの縫ひいとなむけはひなどしるければ、参りぬ。 |
と、言葉数少なに言って、ろくにお相手もせずに、繕い物をする様子がはっきり分かるので、帰参した。 |
と言葉数も少なく言って、大納言家の女房たちは今日はゆっくりと話し相手になっていなかった。忙しそうに物を縫ったり、何かを仕度したりする様子がよくわかるので、惟光は帰って行った。 |
to, koto-zukuna ni ihi te, wosa-wosa ahe-siraha zu, mono nuhi itonamu kehahi nado sirukere ba, mawiri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 源氏、紫の君を盗み取る |
3-3 Genji steals Murasaki before her father takes her along to his home |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 君は大殿におはしけるに、例の、女君とみにも対面したまはず。 ものむつかしくおぼえたまひて、 あづまを すががきて ★、 「 常陸には田をこそ作れ」といふ歌を、声はいとなまめきて、すさびゐたまへり。 |
源氏の君は左大臣邸においでになったが、例によって、女君はすぐにはお会いなさらない。君は何となくおもしろくなくお思いになって、和琴を即興に掻き鳴らして、「常陸では田を作っているが」という歌を、声はとても優艶に、口ずさんでおいでになる。 |
源氏は左大臣家へ行っていたが、例の夫人は急に出て来て逢おうともしなかったのである。面倒な気がして、源氏は東琴(和琴に同じ)を手すさびに弾いて、「常陸には田をこそ作れ、仇心かぬとや君が山を越え、野を越え雨夜来ませる」という田舎めいた歌詞を、優美な声で歌っていた。 |
Kimi ha Ohoi-dono ni ohasi keru ni, rei no, Womna-Gimi tomi ni mo taimen si tamaha zu. Mono-mutukasiku oboye tamahi te, aduma wo sugagaki te, "Hitati ni ha ta wo koso tukure" to ihu uta wo, kowe ha ito namameki te, susabi wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 参りたれば、召し寄せてありさま問ひたまふ。 しかしかなど聞こゆれば、口惜しう思して、「 かの宮に渡りなば、わざと迎へ出でむも、好き好きしかるべし。幼き人を盗み出でたりと、 もどきおひなむ ★。そのさきに、しばし、人にも口固めて、 渡してむ」と思して、 |
参上したので、呼び寄せて様子をお尋ねになる。「これこれしかじかです」と申し上げるので、残念にお思いになって、「あの宮邸に移ってしまったら、わざわざ迎え取ることも好色めいたことであろう。子供を盗み出したと、きっと非難されるだろう。その前に、暫くの間、女房の口を封じさせて、連れて来てしまおう」とお考えになって、 |
惟光が来たというので、源氏は居間へ呼んで様子を聞こうとした。惟光によって、女王が兵部卿の宮邸へ移転する前夜であることを源氏は聞いた。源氏は残念な気がした。宮邸へ移ったあとで、そういう幼い人に結婚を申し込むということも物好きに思われることだろう。小さい人を一人盗んで行ったという批難を受けるほうがまだよい。確かに秘密の保ち得られる手段を取って二条の院へつれて来ようと源氏は決心した。 |
Mawiri tare ba, mesi-yose te arisama tohi tamahu. Sika-sika nado kikoyure ba, kutiwosiu obosi te, "Kano Miya ni watari na ba, wazato mukahe-ide m mo, suki-zukisikaru besi. Wosanaki hito wo nusumi-ide tari to, modoki ohi na m. Sono saki ni, sibasi, hito ni mo kuti-katame te, watasi te m." to obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | 「 暁かしこにものせむ。車の装束 さながら。随身一人二人 仰せおきたれ」とのたまふ。うけたまはりて立ちぬ。 |
「早朝にあちらに行こう。車の準備はそのままに。随身を一、二名を申し付けておけ」とおっしゃる。承知して下がった。 |
「明日夜明けにあすこへ行ってみよう。ここへ来た車をそのままにして置かせて、随身を一人か二人仕度させておくようにしてくれ」 という命令を受けて惟光は立った。 |
"Akatuki kasiko ni monose m. Kuruma no syauzoku sanagara. Zuizin hitori hutari ohose-oki tare." to notamahu. Uketamahari te tati nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | 君、「 いかにせまし。聞こえありて好きがましきやうなるべきこと。 人のほどだにものを思ひ知り、 女の心交はしけることと推し測られぬべくは、世の常なり。父宮の 尋ね出でたまへらむも、はしたなう、 すずろなるべきを」と、思し乱るれど、さて外してむは いと口惜しかべければ、まだ夜深う出でたまふ。 |
源氏の君は、「どうしようか。噂が広がって好色めいたことになりそうな事よ。せめて相手の年齢だけでも物の分別ができ、女が情を通じてのことだと想像されるようなのは、世間一般にもある事だ。もし父宮がお探し出された場合も、体裁が悪く、格好もつかないことになるだろうから」と、お悩みになるが、この機会を逃したら大変後悔することになるにちがいないので、まだ夜の深いうちにお出になる。 |
源氏はそののちもいろいろと思い悩んでいた。人の娘を盗み出した噂の立てられる不名誉も、もう少しあの人が大人で思い合った仲であればその犠牲も自分は払ってよいわけであるが、これはそうでもないのである。父宮に取りもどされる時の不体裁も考えてみる必要があると思ったが、その機会をはずすことはどうしても惜しいことであると考えて、翌朝は明け切らぬ間に出かけることにした。 |
Kimi, "Ika ni se masi? Kikoye ari te suki-gamasiki yau naru beki koto. Hito no hodo dani mono wo omohi-siri, womna no kokoro-kahasi keru koto to osi-hakara re nu beku ha, yo no tune nari. Titi-Miya no tadune-ide tamahe ra m mo, hasitanau, suzuro naru beki wo." to, obosi-midarure do, sate hadusi te m ha ito kuti-wosika' bekere ba, mada yobukau ide tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | 女君、例のしぶしぶに、 心もとけずものしたまふ。 |
女君は、いつものように気が進まない様子で、かしこまった感じでいらっしゃる。 |
夫人は昨夜の気持ちのままでまだ打ち解けてはいなかった。 |
Womna-Gimi, rei no sibu-sibu ni, kokoro mo toke zu monosi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 「 かしこに、いとせちに見るべきことのはべるを思ひたまへ出でて、 立ちかへり参り来なむ」とて、出でたまへば、さぶらふ人びとも知らざりけり。 わが御方にて、 御直衣などはたてまつる。 惟光ばかりを馬に乗せておはしぬ。 |
「あちらに、どうしても処理しなければならない事がございますのを思い出しまして、すぐに戻って来ます」と言って、お出になるので、お側の女房たちも知らないのであった。ご自分のお部屋の方で、お直衣などはお召しになる。惟光だけを馬に乗せてお出になった。 |
「一条の院にぜひしなければならないことのあったのを私は思い出したから出かけます。用を済ませたらまた来ることにしましょう」 と源氏は不機嫌な妻に告げて、寝室をそっと出たので、女房たちも知らなかった。自身の部屋になっているほうで直衣などは着た。馬に乗せた惟光だけを付き添いにして源氏は大納言家へ来た。 |
"Kasiko ni, ito seti ni miru beki koto no haberu wo omohi tamahe ide te, tati-kaheri mawiri ki na m." tote, ide tamahe ba, saburahu hito-bito mo sira zari keri. Waga ohom-kata ni te, ohom-nahosi nado ha tatematuru. Koremitu bakari wo muma ni nose te ohasi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.7 | 門うちたたかせたまへば、心知らぬ者の開けたるに、御車をやをら引き入れさせて、大夫、 妻戸を鳴らして、しはぶけば、少納言聞き知りて、出で来たり。 |
門を打ち叩かせなさると、何も事情を知らない者が開けたので、お車を静かに引き入れさせて、惟光大夫が、妻戸を叩いて、合図の咳払いをすると、少納言の乳母が察して、出て来た。 |
門をたたくと何の気なしに下男が門をあけた。車を静かに中へ引き込ませて、源氏の伴った惟光が妻戸をたたいて、しわぶきをすると、少納言が聞きつけて出て来た。 |
Kado uti-tataka se tamahe ba, kokro-sira nu mono no ake taru ni, mi-kuruma wo yawora hiki-ire sase te, Taihu, tumado wo narasi te, sihabuke ba, Seunagon kiki-siri te, ide-ki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8 | 「 ここに、おはします」と言へば、 |
「ここに、おいでになっています」と言うと、 |
「来ていらっしゃるのです」 と言うと、 |
"Koko ni, ohasimasu." to ihe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.9 | 「 幼き人は、 御殿籠もりてなむ。 などか、いと夜深うは出でさせたまへる」と、 もののたよりと思ひて言ふ。 |
「若君は、お寝みになっております。どうして、こんな暗いうちにお出あそばしたのでしょうか」と、どこかからの帰りがけと思って言う。 |
「女王様はやすんでいらっしゃいます。どちらから、どうしてこんなにお早く」 と少納言が言う。源氏が人の所へ通って行った帰途だと解釈しているのである。 |
"Wosanaki hito ha, ohotono-gomori te nam. Nado-ka, ito yobukau ha ide sase tamahe ru?" to, mono no tayori to omohi te ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.10 | 「 宮へ渡らせたまふべかなるを、そのさきに 聞こえ置かむとてなむ」とのたまへば、 |
「宮邸へお移りあそばすそうですが、その前にお話し申し上げておきたいと思って参りました」とおっしゃると、 |
「宮様のほうへいらっしゃるそうですから、その前にちょっと一言お話をしておきたいと思って」 と源氏が言った。 |
"Miya he watara se tamahu beka' naru wo, sono saki ni kikoye-oka m tote nam." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.11 | 「 ▼ 何ごとにかはべらむ。 いかにはかばかしき御答へ聞こえさせたまはむ」 |
「どのようなことでございましょうか。どんなにしっかりしたお返事ができましょう」 |
「どんなことでございましょう。まあどんなに確かなお返辞がおできになりますことやら」 |
"Nani-goto ni ka habera m? Ika ni haka-bakasiki ohom-irahe kikoye sase tamaha m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.12 | とて、 うち笑ひてゐたり。 君、入りたまへば、いとかたはらいたく、 |
と言って、微笑んでいた。源氏の君が、お入りになると、とても困って、 |
少納言は笑っていた。源氏が室内へはいって行こうとするので、この人は当惑したらしい。 |
tote, uti-warahi te wi tari. Kimi, iri tamahe ba, ito kataharaitaku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.13 | 「 うちとけて、あやしき 古人どものはべるに」と 聞こえさす。 |
「気を許して、見苦しい年寄たちが寝ておりますので」とお制し申し上げる。 |
「不行儀に女房たちがやすんでおりまして」 |
"Uti-toke te, ayasiki hurubito-domo no haberu ni." to kikoyesasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.14 | 「 まだ、おどろいたまはじな。いで、御目覚ましきこえむ。かかる朝霧を知らでは、 寝るものか」 |
「まだ、お目覚めではありますまいね。どれ、お目をお覚まし申しましょう。このような素晴らしい朝霧を知らないで、寝ていてよいものですか」 |
「まだ女王さんはお目ざめになっていないのでしょうね。私がお起こししましょう。もう朝霧がいっぱい降る時刻だのに、寝ているというのは」 |
"Mada, odoroi tamaha zi na. Ide, ohom-me samasi kikoye m. Kakaru asagiri wo sira de ha, nuru mono-ka!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.15 | とて、入りたまへば、「 や」とも、え聞こえず。 |
とおっしゃって、ご寝所にお入りになるので、「もし」とも、お止めできない。 |
と言いながら寝室へはいる源氏を少納言は止めることもできなかった。 |
tote, iri tamahe ba, "Ya!" to mo, e kikoye zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.16 | 君は何心もなく寝たまへるを、抱きおどろかしたまふに、おどろきて、 宮の御迎へにおはしたると、寝おびれて思したり。 |
紫の君は何も知らないで寝ていらっしゃったが、源氏の君が抱いてお起こしなさるので、目を覚まして、父宮がお迎えにいらっしゃったと、寝惚けてお思いになった。 |
源氏は無心によく眠っていた姫君を抱き上げて目をさまさせた。女王は父宮がお迎えにおいでになったのだと、まだまったくさめない心では思っていた。 |
Kimi ha nani-gokoro mo naku ne tamahe ru wo, idaki odorokasi tamahu ni, odoroki te, Miya no ohom-mukahe ni ohasi taru to, ne-obire te obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.17 | 御髪かき繕ひなどしたまひて、 |
お髪を掻き繕いなどなさって、 |
髪を撫でて直したりして、 |
Mi-gusi kaki-tukurohi nado si tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.18 | 「 いざ、たまへ。宮の御使にて参り来つるぞ」 |
「さあ、いらっしゃい。父宮さまのお使いとして参ったのですよ」 |
「さあ、いらっしゃい。宮様のお使いになって私が来たのですよ」 |
"Iza, tamahe. Miya no ohom-tukahi ni te mawiri ki turu zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.19 | とのたまふに、「 あらざりけり」と、あきれて、恐ろしと思ひたれば、 |
とおっしゃる声に、「違う人であったわ」と、びっくりして、恐いと思っているので、 |
と言う声を聞いた時に姫君は驚いて、恐ろしく思うふうに見えた。 |
to notamahu ni, "Ara zari keri!" to, akire te, osorosi to omohi tare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.20 | 「 あな、心憂。まろも同じ人ぞ」 |
「ああ、情けない。わたしも同じ人ですよ」 |
「いやですね。私だって宮様だって同じ人ですよ。鬼などであるものですか」 |
"Ana, kokoro-u! Maro mo onazi hito zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.21 | とて、かき抱きて出でたまへば、 大輔、少納言など、「 こは、いかに」と聞こゆ。 |
と言って、抱いてお出なさるので、大輔や少納言の乳母などは、「これは、どうなさいますか」と申し上げる。 |
源氏の君が姫君をかかえて出て来た。少納言と、惟光と、外の女房とが、 「あ、どうなさいます」 と同時に言った。 |
tote, kaki-idaki te ide tamahe ba, Taihu, Seunagon nado, "Ko ha, ika ni?" to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.22 | 「 ここには、常にもえ参らぬがおぼつかなければ、 心やすき所にと聞こえしを、 心憂く、渡りたまへるなれば、まして 聞こえがたかべければ。人一人参られよかし」 |
「ここには、常に参れないのが気がかりなので、気楽な所にと申し上げたが、残念なことに、宮邸にお移りになるそうなので、ますますお話し申し上げにくくなるだろうから。誰か一人付いて参られよ」 |
「ここへは始終来られないから、気楽な所へお移ししようと言ったのだけれど、それには同意をなさらないで、ほかへお移りになることになったから、そちらへおいでになってはいろいろ面倒だから、それでなのだ。だれか一人ついておいでなさい」 |
"Koko ni ha, tune ni mo e mawira nu ga obotukanakere ba, kokoro-yasuki tokoro ni to kikoye si wo, kokoro-uku, watari tamahe ru nare ba, masite kikoye gataka' bekere ba. Hito hitori mawira re yo kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.23 | とのたまへば、 心あわたたしくて、 |
とおっしゃるので、気がせかれて、 |
こう源氏の言うのを聞いて少納言はあわててしまった。 |
to notamahe ba, kokoro-awatatasiku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.24 | 「 今日は、 いと便なくなむはべるべき。 宮の渡らせたまはむには、いかさまにか聞こえやらむ。おのづから、ほど経て、 さるべきにおはしまさば、ともかうも はべりなむを、 いと思ひやりなきほどのことにはべれば、さぶらふ人びと苦しうはべるべし」と聞こゆれば、 |
「今日は、まことに都合が悪うございましょう。宮さまがお越しあそばした時には、どのようにお答え申し上げましょう。自然と、年月をへて、そうなられるご縁でいらっしゃれば、ともかくなられましょうが、何とも考える暇もない急な事でございますので、お仕えする者どももきっと困りましょう」と申し上げると、 |
「今日では非常に困るかと思います。宮様がお迎えにおいでになりました節、何とも申し上げようがないではございませんか。ある時間がたちましてから、ごいっしょにおなりになる御縁があるものでございましたら自然にそうなることでございましょう。まだあまりに御幼少でいらっしゃいますから。ただ今そんなことは皆の者の責任になることでございますから」 と言うと、 |
"Kehu ha, ito bin-naku nam haberu beki. Miya no watara se tamaha m ni ha, ika sama ni ka kikoye-yara m? Onodukara, hodo he te, saru-beki ni ohasimasa ba, tomo-kaumo haberi na m wo, ito omohi-yari naki hodo no koto ni habere ba, saburahu hito-bito kurusiu haberu besi." to kikoyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.25 | 「 よし、後にも人は参りなむ」とて、御車寄せさせたまへば、あさましう、いかさまにと思ひあへり。 |
「よし、後からでも女房たちは参ればよかろう」と言って、お車を寄せさせなさるので、驚きあきれて、どうしたらよいものかと困り合っていた。 |
「じゃいい。今すぐについて来られないのなら、人はあとで来るがよい」 こんなふうに言って源氏は車を前へ寄せさせた。 |
"Yosi, noti ni mo hito ha mawiri na m." tote, mi-kuruma yose sase tamahe ba, asamasiu, ika sama ni to omohi-ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.26 | 若君も、あやしと思して泣いたまふ。少納言、とどめきこえむかたなければ、昨夜縫ひし御衣どもひきさげて、自らもよろしき衣着かへて、乗りぬ。 |
若君も、変な事だとお思いになってお泣きになる。少納言の乳母は、お止め申し上げるすべもないので、昨夜縫ったご衣装類をひっさげて、自分も適当な着物に着替えて、車に乗った。 |
姫君も怪しくなって泣き出した。少納言は止めようがないので、昨夜縫った女王の着物を手にさげて、自身も着がえをしてから車に乗った。 |
Waka-Gimi mo, ayasi to obosi te nai tamahu. Seunagon, todome kikoye m kata nakere ba, yobe nuhi si ohom-zo-domo hiki-sage te, midukara mo yorosiki kinu ki-kahe te, nori nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.27 | 二条院は近ければ、まだ明うもならぬほどにおはして、 西の対に御車寄せて下りたまふ。若君をば、いと軽らかに かき抱きて下ろしたまふ。 |
二条院は近いので、まだ明るくならないうちにお着きになって、西の対にお車を寄せてお下りになる。若君を、とても軽々と抱いてお下ろしになる。 |
二条の院は近かったから、まだ明るくならないうちに着いて、西の対に車を寄せて降りた。源氏は姫君を軽そうに抱いて降ろした。 |
Nideu-no-win ha tikakere ba, mada akau mo nara nu hodo ni ohasi te, nisi-no-tai ni mi-kuruma yose te ori tamahu. Waka-Gimi wo ba, ito karoraka ni kaki-idaki te orosi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.28 | 少納言、 |
少納言の乳母が、 |
「夢のような気でここまでは参りましたが、私はどうしたら」 少納言は下車するのを躊躇した。 |
Seunagon, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.29 | 「 なほ、いと夢の心地しはべるを、 いかにしはべるべきことにか」と、やすらへば、 |
「やはり、まるで夢のような心地がしますが、どういたしましたらよいことなのでしょうか」と、ためらっているので、 |
「どうでもいいよ。もう女王さんがこちらへ来てしまったのだから、君だけ帰りたければ送らせよう」 |
"Naho, ito yume no kokoti si haberu wo, ikani si haberu beki koto ni ka?" to, yasurahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.30 | 「 そは、心ななり ★。 御自ら渡したてまつりつれば、 帰りなむとあらば、送りせむかし」 |
「それはあなたの考え次第でしょう。ご本人はお移し申し上げてしまったのだから、帰ろうと思うなら、送ってやろうよ」 |
源氏が強かった。しかたなしに少納言も降りてしまった。このにわかの変動に先刻から胸が鳴り続けているのである。宮が自分をどうお責めになるだろうと思うことも苦労の一つであった。それにしても姫君はどうなっておしまいになる運命なのであろうと思って、ともかくも母や祖母に早くお別れになるような方は紛れもない不幸な方であることがわかると思うと、涙がとめどなく流れそうであったが、しかもこれが姫君の婚家へお移りになる第一日であると思うと、縁起悪く泣くことは遠慮しなくてはならないと努めていた。 |
"So ha, kokoro na' nari. Ohom-midukara watasi tatematuri ture ba, kaheri na m to ara ba, okuri se m kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.31 | とのたまふに、 笑ひて下りぬ。にはかに、あさましう、胸も静かならず。「 宮の思しのたまはむこと、 いかになり果てたまふべき御ありさまにか、とてもかくも、頼もしき人びとに後れたまへるがいみじさ」と思ふに、涙の止まらぬを、 さすがにゆゆしければ ★、念じゐたり。 |
とおっしゃるので、苦笑して下りた。急な事で、驚きあきれて、心臓がどきどきする。「宮さまがお叱りになられることや、どうおなりになる姫君のお身の上だろうか、とにもかくにも、身内の方々に先立たれたことが本当にお気の毒」と思うと、涙が止まらないのを、何と言っても不吉なので、じっと堪えていた。 |
ここは平生あまり使われない御殿であったから帳台なども置かれてなかった。源氏は惟光を呼んで帳台、屏風などをその場所場所に据えさせた。これまで上へあげて掛けてあった几帳の垂れ絹はおろせばいいだけであったし、畳の座なども少し置き直すだけで済んだのである。東の対へ夜着類を取りにやって寝た。 |
to notamahu ni, warahi te ori nu. Nihaka ni, asamasiu, mune mo siduka nara zu. "Miya no obosi-notamaha m koto, ikani nari-hate tamahu beki ohom-arisama ni ka, totemo-kakutemo, tanomosiki hito-bito ni okure tamahe ru ga imizisa." to omohu ni, namida no tomara nu wo, sasuga ni yuyusikere ba, nen-zi wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.32 | こなたは住みたまはぬ対なれば、御帳などもなかりけり。惟光召して、御帳、御屏風など、 あたりあたり仕立てさせたまふ。御几帳の帷子引き下ろし、御座などただひき繕ふばかりにてあれば、東の対に、 御宿直物召しに遣はして、大殿籠もりぬ。 |
こちらはご使用にならない対の屋なので、御帳などもないのであった。惟光を呼んで、御帳や、御屏風など、ここかしこに整えさせなさる。御几帳の帷子を引き下ろし、ご座所など、ちょっと整えるだけで使えるので、東の対にお寝具類などを取り寄せに人をやって、お寝みになった。 |
姫君は恐ろしがって、自分をどうするのだろうと思うと慄えが出るのであったが、さすがに声を立てて泣くことはしなかった。 |
Konata ha sumi tamaha nu tai nare ba, mi-tyau nado mo nakari keri. Koremitu mesi te, mi-tyau, mi-byaubu nado, atari-atari sitate sase tamahu. Mi-kityau no katabira hiki-orosi, o-masi nado tada hiki-tukurohu bakari ni te are ba, himgasi-no-tai ni, ohom-tonowimono mesi ni tukahasi te, ohotonogomori nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.33 | 若君は、いとむくつけく、いかにすること ならむと、 ふるはれたまへど、さすがに声立ててもえ泣きたまはず。 |
若君は、とても気味悪くて、どうなさる気だろうと、ぶるぶると震えずにはいらっしゃれないが、やはり声を出してお泣きになれない。 |
「少納言の所で私は寝るのよ」 |
Waka-Gimi ha, ito mukutukeku, ikani suru koto nara m to, huruha re tamahe do, sasuga ni kowe tate te mo e naki tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.34 | 「 少納言がもとに寝む」 |
「少納言の乳母の所で寝たい」 |
子供らしい声で言う。 |
"Seunagon ga moto ni ne m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.35 | とのたまふ声、 いと若し。 |
とおっしゃる声は、まことに幼稚である。 |
「もうあなたは乳母などと寝るものではありませんよ」 |
to notamahu kowe, ito wakasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.36 | 「 今は、さは大殿籠もるまじきぞよ」 |
「今からは、もうそのようにお寝みになるものではありませんよ」 |
と源氏が教えると、悲しがって泣き寝をしてしまった。乳母は眠ることもできず、ただむやみに泣かれた。 |
"Ima ha, sa ha ohotonogomoru maziki zo yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.37 | と教へきこえたまへば、いとわびしくて泣き臥したまへり。 乳母はうちも臥されず、ものもおぼえず起きゐたり。 |
とお教え申し上げなさると、とても悲しくて泣きながら横におなりになった。少納言の乳母は横になる気もせず、何も考えられず起きていた。 |
明けてゆく朝の光を見渡すと、建物や室内の装飾はいうまでもなくりっぱで、庭の敷き砂なども玉を重ねたもののように美しかった。少納言は自身が貧弱に思われてきまりが悪かったが、この御殿には女房がいなかった。あまり親しくない客などを迎えるだけの座敷になっていたから、男の侍だけが縁の外で用を聞くだけだった。 |
to wosihe kikoye tamahe ba, ito wabisiku te naki-husi tamahe ri. Menoto ha uti mo husa re zu, mono mo oboye zu oki wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.38 | 明けゆくままに、 見わたせば、御殿の造りざま、しつらひざま、さらにも言はず、庭の砂子も玉を重ねたらむやうに見えて、 かかやく心地するに、 はしたなく思ひゐたれど、こなたには女などもさぶらはざりけり。け疎き客人などの参る折節の方なりければ、男どもぞ御簾の外にありける。 |
夜が明けて行くにつれて、見渡すと、御殿の造りざまや、調度類の様子は、改めて言うまでもなく、庭の白砂も宝石を重ね敷いたように見えて、光り輝くような感じなので、きまり悪い感じでいたが、こちらの対には女房なども控えていないのであった。たまのお客などが参った折に使う部屋だったので、男たちが御簾の外に控えているのであった。 |
そうした人たちは新たに源氏が迎え入れた女性のあるのを聞いて、 「だれだろう、よほどお好きな方なんだろう」 などとささやいていた。源氏の洗面の水も、朝の食事もこちらへ運ばれた。遅くなってから起きて、源氏は少納言に、 |
Ake-yuku mama ni, miwatase ba, otodo no tukuri-zama, siturahi-zama, sarani mo iha zu, niha no sunago mo tama wo kasane tara m yau ni miye te, kakayaku kokoti suru ni, hasitanaku omohi wi tare do, konata ni ha womna nado mo saburaha zari keri. Ke-utoki marauto nado no mawiru wori-husi no kata nari kere ba, wotoko-domo zo mi-su no to ni ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.39 | かく、人迎へたまへりと、聞く人、「 誰れならむ。おぼろけにはあらじ ★」と、ささめく。御手水、御粥など、こなたに参る。 日高う寝起きたまひて、 |
このように、女をお迎えになったと、聞いた人は、「誰であろうか。並大抵の人ではあるまい」と、ひそひそ噂する。御手水や、お粥などを、こちらの対に持って上がる。日が高くなってお起きになって、 |
「女房たちがいないでは不自由だろうから、あちらにいた何人かを夕方ごろに迎えにやればいい」 |
Kaku, hito mukahe tamahe ri to, kiku hito, "Tare nara m? Oboroke ni ha ara zi." to, sasameku. Mi-teudu, ohom-kayu nado, konata ni mawiru. Hi takau ne-oki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.40 | 「 人なくて、 悪しかめるを、さるべき人びと、夕づけてこそは 迎へさせたまはめ」 |
「女房がいなくて、不便であろうから、しかるべき人々を、夕方になってから、お迎えなさるとよいだろう」 |
と言って、それから特に小さい者だけが来るようにと東の対のほうへ童女を呼びにやった。しばらくして愛らしい姿の子が四人来た。 |
"Hito naku te, asika' meru wo, saru-beki hito-bito, yuhuduke te koso ha mukahe sase tamaha me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.41 | とのたまひて、対に童女召しにつかはす。「 小さき限り、ことさらに参れ」と ★ありければ、いとをかしげにて、四人参りたり。 |
とおっしゃって、東の対に童女を呼びに人をやる。「小さい子たちだけ、特別に参れ」と言ったので、とてもかわいらしい格好して、四人が参った。 |
女王は着物にくるまったままでまだ横になっていたのを源氏は無理に起こして、 |
to notamahi te, tai ni warahabe mesi ni tukahasu. "Tihisaki kagiri, kotosara ni mawire." to ari kere ba, ito wokasige ni te, yo-tari mawiri tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.42 | 君は御衣にまとはれて臥したまへるを、せめて起こして、 |
紫の君はお召物にくるまって臥せっていらっしゃったのを、無理に起こして、 |
「私に意地悪をしてはいけませんよ。薄情な男は決してこんなものじゃありませんよ。女は気持ちの柔らかなのがいいのですよ」 |
Kimi ha ohom-zo ni matohare te husi tamahe ru wo, semete okosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.43 | 「 かう、心憂くなおはせそ。すずろなる人は、 かうはありなむや。女は心柔らかなるなむよき」 |
「こんなふうに、お嫌がりなさいますな。いい加減な男は、このように親切にしましょうか。女性というものは、気持ちの素直なのが良いのです」 |
もうこんなふうに教え始めた。 |
"Kau, kokoro-uku na ohase so. Suzuro naru hito ha, kau ha ari na m ya? Womna ha kokoro yaharaka naru nam yoki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.44 | など、今より教へきこえたまふ。 |
などと、今からお教え申し上げなさる。 |
姫君の顔は少し遠くから見ていた時よりもずっと美しかった。気に入るような話をしたり、おもしろい絵とか遊び事をする道具とかを東の対へ取りにやるとかして、源氏は女王の機嫌を直させるのに骨を折った。 |
nado, ima yori wosihe kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.45 | 御容貌は、さし離れて見しよりも、清らにて、なつかしううち語らひつつ、をかしき絵、遊びものども 取りに遣はして、見せたてまつり、御心につくことどもをしたまふ。 |
ご容貌は、遠くから見ていた時よりも、美しいので、優しくお話をなさりながら、興趣ある絵や、遊び道具類を取りにやって、お見せ申し上げ、お気に入ることどもをなさる。 |
やっと起きて喪服のやや濃い鼠の服の着古して柔らかになったのを着た姫君の顔に笑みが浮かぶようになると、源氏の顔にも自然笑みが上った。 |
Ohom-katati ha, sasi-hanare te mi si yori mo, kiyora ni te, natukasiu uti-katarahi tutu, wokasiki we, asobimono-domo tori ni tukahasi te, mise tatematuri, mi-kokoro tuku koto-domo wo si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.46 | やうやう起きゐて見たまふに、 鈍色のこまやかなるが、うち萎えたるどもを着て、何心なくうち笑みなどしてゐたまへるが、いと うつくしきに、 我もうち笑まれて見たまふ。 |
だんだん起き出して座って御覧になるが、鈍色の色濃い喪服の、ちょっと柔らかくなったのを着て、無心に微笑んでいらっしゃるのが、とてもかわいらしいので、ご自身もつい微笑んで御覧になる。 |
源氏が東の対へ行ったあとで姫君は寝室を出て、木立ちの美しい築山や池のほうなどを御簾の中からのぞくと、ちょうど霜枯れ時の庭の植え込みが描いた絵のようによくて、平生見ることの少ない黒の正装をした四位や、赤を着た五位の官人がまじりまじりに出はいりしていた。源氏が言っていたようにほんとうにここはよい家であると女王は思った。屏風にかかれたおもしろい絵などを見てまわって、女王はたよりない今日の心の慰めにしているらしかった。 |
Yau-yau oki wi te mi tamahu ni, nibi-iro no komayaka naru ga, uti-naye taru-domo wo ki te, nani-gokoro-naku uti-wemi nado si te wi tamahe ru ga, ito utukusiki ni, ware mo uti-wema re te mi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.47 | 東の対に渡りたまへるに、 立ち出でて、庭の木立、池の方など覗きたまへば、霜枯れの前栽、絵に描けるやうにおもしろくて、見も知らぬ 四位、五位こきまぜに、 隙なう出で入りつつ、「 げに、をかしき所かな」と思す。御屏風どもなど、いとをかしき絵を見つつ、慰めておはするも はかなしや。 |
東の対にお渡りになったので、端に出て行って、庭の木立や、池の方などを、お覗きになると、霜枯れの前栽が、絵に描いたように美しくて、見たこともない四位や五位の人々の服装が色とりどりに入り乱れて、ひっきりなしに出入りしていて、「なるほど、素晴らしい所だわ」と、お思いになる。御屏風類などの、とても素晴らしい絵を見ては、機嫌を良くしていらっしゃるのも、あどけないことよ。 |
源氏は二、三日御所へも出ずにこの人をなつけるのに一所懸命だった。手本帳に綴じさせるつもりの字や絵をいろいろに書いて見せたりしていた。皆美しかった。「知らねどもむさし野と云へばかこたれぬよしやさこそは紫の故」という歌の紫の紙に書かれたことによくできた一枚を手に持って姫君はながめていた。また少し小さい字で、 |
Himgasi-no-tai ni watari tamahe ru ni, tati-ide te, niha no kodati, ike no kata nado nozoki tamahe ba, simogare no sensai, we ni kake ru yau ni omosiroku te, mi mo sira nu, si-wi, go-wi koki-maze ni, hima nau ide-iri tutu, "Geni, wokasiki tokoro kana!" to obosu. Mi-byaubu-domo nado, ito wokasiki we wo mi tutu, nagusame te ohasuru mo hakanasi ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.48 | 君は、二、三日、内裏へも参りたまはで、この人をなつけ語らひきこえたまふ。 やがて本にと思すにや、手習、絵など さまざまに書きつつ、見せたてまつりたまふ。いみじうをかしげに書き集めたまへり。 「 武蔵野と言へばかこたれぬ」と、紫の紙に書いたまへる墨つきの、いとことなるを 取りて見ゐたまへり。すこし小さくて、 |
源氏の君は、二、三日、宮中へも参内なさらず、この人を手懐けようとお相手申し上げなさる。そのまま手本にとのお考えか、手習いや、お絵描きなど、いろいろと書いては描いては、御覧に入れなさる。とても素晴らしくお書き集めになった。「武蔵野と言うと文句を言いたくなってしまう」と、紫の紙にお書きになった墨の具合が、とても格別なのを取って御覧になっていらっしゃった。少し小さくて、 |
ねは見ねど哀れとぞ思ふ武蔵野の |
Kimi ha, ni, sam-niti, uti he mo mawiri tamaha de, kono hito wo natuke katarahi kikoye tamahu. Yagate hon ni to obosu ni ya, tenarahi, we nado sama-zama ni kaki tutu, mise tatematuri tamahu. Imiziu wokasige ni kaki atume tamahe ri. "Musasino to ihe ba kakota re nu" to, murasaki no kami ni kai tamahe ru sumi-tuki no, ito koto naru wo tori te mi wi tamahe ri. Sukosi tihisaku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.49 | 「 ねは見ねどあはれとぞ思ふ武蔵野の |
「まだ一緒に寝てはみませんが愛しく思われます |
露分けわぶる草のゆかりを |
"Ne ha mi ne do ahare to zo omohu Musasino no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50 | 露分けわぶる草のゆかりを」 |
武蔵野の露に難儀する紫のゆかりのあなたを」 |
とも書いてある。 |
tuyu wake waburu kusa no yukari wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.51 | とあり。 |
とある。 |
「あなたも書いてごらんなさい」 と源氏が言うと、 |
to ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.52 | 「 いで、君も書いたまへ」とあれば、 |
「さあ、あなたもお書きなさい」と言うと、 |
「まだよくは書けませんの」 |
"Ide, Kimi mo kai tamahe." to are ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.53 | 「 まだ、ようは書かず」 |
「まだ、うまく書けません」 |
見上げながら言う女王の顔が無邪気でかわいかったから、源氏は微笑をして言った。 |
"Mada, you ha kaka zu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
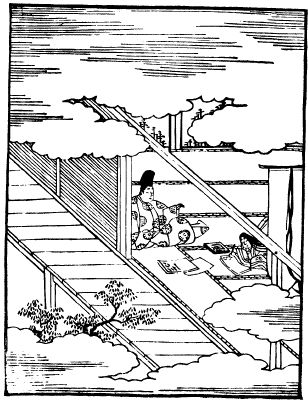 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.54 | とて、見上げたまへるが、何心なくうつくしげなれば、うちほほ笑みて、 |
と言って、顔を見上げていらっしゃるのが、無邪気でかわいらしいので、つい微笑まれて、 |
「まずくても書かないのはよくない。教えてあげますよ」 |
tote, miage tamahe ru ga, nani-gokoro-naku utukusige nare ba, uti-hohowemi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.55 | 「 よからねど、むげに書かぬこそ悪ろけれ。教えきこえむかし」 |
「うまくなくても、まったく書かないのは良くありません。お教え申し上げましょうね」 |
からだをすぼめるようにして字をかこうとする形も、筆の持ち方の子供らしいのもただかわいくばかり思われるのを、源氏は自分の心ながら不思議に思われた。 「書きそこねたわ」 と言って、恥ずかしがって隠すのをしいて読んでみた。 |
"Yokara ne do, mugeni kaka nu koso warokere. Wosihe kikoye m kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.56 | とのたまへば、うちそばみて書いたまふ手つき、筆とりたまへるさまの幼げなるも、らうたうのみおぼゆれば、 心ながらあやしと思す。「 書きそこなひつ」と恥ぢて隠したまふを、せめて見たまへば、 |
とおっしゃると、ちょっと横を向いてお書きになる手つきや、筆をお持ちになる様子があどけないのも、かわいらしくてたまらないので、我ながら不思議だとお思いになる。「書き損ってしまった」と、恥ずかしがってお隠しになるのを、無理に御覧になると、 |
かこつべき故を知らねばおぼつかな |
to notamahe ba, uti-sobami te kai tamahu tetuki, hude tori tamahe ru sama no wosanage naru mo, rautau nomi oboyure ba, kokoro-nagara ayasi to obosu. "Kaki sokonahi tu." to hadi te kakusi tamahu wo, semete mi tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.57 | 「 かこつべきゆゑを知らねばおぼつかな |
「恨み言を言われる理由が分かりません |
いかなる草のゆかりなるらん |
"Kakotu beki yuwe wo sira ne ba obotukana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.58 | いかなる草のゆかりなるらむ」 |
わたしはどのような方のゆかりなのでしょう」 |
子供らしい字ではあるが、将来の上達が予想されるような、ふっくりとしたものだった。死んだ尼君の字にも似ていた。現代の手本を習わせたならもっとよくなるだろうと源氏は思った。 |
ikanaru kusa no yukari naru ram |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.59 | と、 いと若けれど、生ひ先見えて、ふくよかに書いたまへり。故尼君のにぞ 似たりける。「 今めかしき手本習はば、 いとよう書いたまひてむ」と見たまふ。 |
と、とても幼稚だが、将来の成長が思いやられて、ふっくらとお書きになっている。亡くなった尼君の筆跡に似ているのであった。「当世風の手本を習ったならば、とても良くお書きになるだろう」と御覧になる。 |
雛なども屋根のある家などもたくさんに作らせて、若紫の女王と遊ぶことは源氏の物思いを紛らすのに最もよい方法のようだった。 |
to, ito wakakere do, ohisaki miye te, hukuyoka ni kai tamahe ri. Ko-Ama-Gimi no ni zo ni tari keru. "Imamekasiki tehon naraha ba, ito you kai tamahi te m." to mi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.60 | 雛など、わざと屋ども作り続けて、もろともに遊びつつ、 こよなきもの思ひの紛らはしなり。 |
お人形なども、特別に御殿をいくつも造り並べて、一緒に遊んでは、この上ない憂さ晴らしの相手である。 |
大納言家に残っていた女房たちは、宮がおいでになった時に御挨拶のしようがなくて困った。当分は世間へ知らせずにおこうと、源氏も言っていたし、少納言もそれと同感なのであるから、秘密にすることをくれぐれも言ってやって、少納言がどこかへ隠したように申し上げさせたのである。宮は御落胆あそばされた。尼君も宮邸へ姫君の移って行くことを非常に嫌っていたから、乳母の出すぎた考えから、正面からは拒まずにおいて、そっと勝手に姫君をつれ出してしまったのだとお思いになって、宮は泣く泣くお帰りになったのである。 「もし居所がわかったら知らせてよこすように」 宮のこのお言葉を女房たちは苦しい気持ちで聞いていたのである。宮は僧都の所へも捜しにおやりになったが、姫君の行くえについては何も得る所がなかった。美しかった小女王の顔をお思い出しになって宮は悲しんでおいでになった。 |
Hihina nado, wazato ya-domo tukuri tuduke te, morotomo ni asobi tutu, koyonaki mono-omohi no magirahasi nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.61 | かのとまりにし人びと、宮渡りたまひて、 尋ねきこえたまひけるに、聞こえやる方なくてぞ、わびあへりける。「 しばし、人に知らせじ」と君ものたまひ、少納言も思ふことなれば、せちに口固めやりたり。ただ、「 行方も知らず、少納言が率て隠しきこえたる」とのみ聞こえさするに、宮も言ふかひなう思して、「 故尼君も、かしこに渡りたまはむことを、いとものしと思したりしことなれば、乳母の、いとさし過ぐしたる心ばせのあまり、 おいらかに渡さむを、便なし、などは言はで、心にまかせ、率てはふらかしつるなめり」と、泣く泣く帰りたまひぬ。「 もし、聞き出でたてまつらば、告げよ」とのたまふも、 わづらはしく。僧都の御もとにも、尋ねきこえたまへど、あとはかなくて、あたらしかりし御容貌など、恋しく悲しと思す。 |
あの残った女房たちは、兵部卿宮がお越しになって、お尋ね申し上げなさったが、お答え申し上げるすべもなくて、困り合っているのであった。「暫くの間、他人に聞かせてはならぬ」と源氏の君もおっしゃるし、少納言の乳母も考えていることなので、固く口止めさせていた。ただ、「行く方も知れず、少納言の乳母がお連れしてお隠し申したことで」とばかりお答え申し上げるので、宮もしょうがないとお思いになって、「亡くなった尼君も、あちらに姫君がお移りになることを、とても嫌だとお思いであったことなので、乳母が、ひどく出過ぎた考えから、すんなりとお移りになることを、不都合だ、などと言わないで、自分の一存で、連れ出してどこかへやってしまったのだろう」と、泣く泣くお帰りになった。「もし、消息をお聞きつけ申したら、知らせなさい」とおっしゃる言葉も、厄介で。僧都のお所にも、お尋ね申し上げなさるが、はっきり分からず、惜しいほどであったご器量など、恋しく悲しいとお思いになる。 |
夫人はその母君をねたんでいた心も長い時間に忘れていって、自身の子として育てるのを楽しんでいたことが水泡に帰したのを残念に思った。 |
Kano tomari ni si hito-bito, Miya watari tamahi te, tadune kikoye tamahi keru ni, kikoye-yaru kata naku te zo, wabi-ahe ri keru. "Sibasi, hito ni sirase zi." to Kimi mo notamahi, Seunagon mo omohu koto nare ba, seti ni kuti-gatame yari tari. Tada, "Yukuhe mo sira zu, Seunagon ga wi te kakusi kikoye taru." to nomi kikoyesasuru ni, Miya mo ihukahinau obosi te, "Ko-Ama-Gimi mo, kasiko ni watari tamaha m koto wo, ito monosi to obosi tari si koto nare ba, Menoto no, ito sasi-sugusi taru kokoro-base no amari, oiraka ni watasa m wo, bin-nasi, nado ha iha de, kokoro ni makase, wi te hahurakasi turu na' meri." to naku-naku kaheri tamahi nu. "Mosi, kiki-ide tatematura ba, tuge yo." to notamahu mo, wadurahasiku. Soudu no ohom-moto ni mo, tadune kikoye tamahe do, ato hakanaku te, atarasikari si ohom-katati nado, kohisiku kanasi to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.62 | 北の方も、母君を憎しと思ひきこえたまひける心も失せて、 わが心にまかせつべう思しけるに違ひぬるは、 口惜しう思しけり。 |
北の方も、その母親を憎いとお思い申し上げなさっていた感情も消えて、自分の思いどおりにできようとお思いになっていた当てが外れたのは、残念にお思いになるのであった。 |
そのうち二条の院の西の対に女房たちがそろった。若紫のお相手の子供たちは、大納言家から来たのは若い源氏の君、東の対のはきれいな女王といっしょに遊べるのを喜んだ。 |
Kitanokata mo, Haha-Gimi wo nikusi to omohi kikoye tamahi keru kokoro mo use te, waga kokoro ni makase tu beu obosi keru ni tagahi nuru ha, kutiwosiu obosi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.63 | やうやう人参り集りぬ。御遊びがたきの童女、児ども、 いとめづらかに今めかしき御ありさまどもなれば、 思ふことなくて遊びあへり。 |
次第に女房たちが集まって来た。お遊び相手の童女や、幼子たちも、とても珍しく当世風なご様子なので、何の屈託もなくて遊び合っていた。 |
若紫は源氏が留守になったりした夕方などには尼君を恋しがって泣きもしたが、父宮を思い出すふうもなかった。初めから稀々にしか見なかった父宮であったから、今は第二の父と思っている源氏にばかり馴染んでいった。外から源氏の帰って来る時は、自身がだれよりも先に出迎えてかわいいふうにいろいろな話をして、懐の中に抱かれて少しもきまり悪くも恥ずかしくも思わない。こんな風変わりな交情がここにだけ見られるのである。 |
Yau-yau hito mawiri atumari nu. Ohom-asobigataki no warahabe, tigo-domo, ito meduraka ni imamekasiki ohom-arisama-domo nare ba, omohu koto naku te asobi-ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.64 | 君は、男君のおはせずなどして、さうざうしき 夕暮などばかりぞ、尼君を恋ひきこえたまひて、うち泣きなどしたまへど、 宮をばことに思ひ出できこえたまはず。もとより見ならひきこえたまはでならひたまへれば、今はただ この後の親を、いみじう睦びまつはしきこえたまふ。ものよりおはすれば、まづ出でむかひて、あはれにうち語らひ、御懐に入りゐて、いささか疎く恥づかしとも思ひたらず。 さるかたに、いみじうらうたきわざなりけり。 |
紫の君は、男君がおいでにならなかったりして、寂しい夕暮時などだけは、尼君をお思い出し申し上げなさって、つい涙ぐみなどなさるが、父宮は特にお思い出し申し上げなさらない。最初からご一緒ではなく過ごして来られたので、今ではすっかりこの後の親を、たいそう馴れお親しみ申し上げていらっしゃる。外出からお帰りになると、まっさきにお出迎えして、親しくお話をなさって、お胸の中に入って、少しも嫌がったり恥ずかしいとは思っていない。そうしたことでは、ひどくかわいらしい態度でなのあった。 |
大人の恋人との交渉には微妙な面倒があって、こんな障害で恋までもそこねられるのではないかと我ながら不安を感じることがあったり、女のほうはまた年じゅう恨み暮らしに暮らすことになって、ほかの恋がその間に芽ばえてくることにもなる。この相手にはそんな恐れは少しもない。ただ美しい心の慰めであるばかりであった。娘というものも、これほど大きくなれば父親はこんなにも接近して世話ができず、夜も同じ寝室にはいることは許されないわけであるから、こんなおもしろい間柄というものはないと源氏は思っているらしいのである。 |
Kimi ha, Wotoko-Gimi no ohase zu nado si te, sau-zausiki yuhugure nado bakari zo, Ama-Gimi wo kohi kikoye tamahi te, uti-naki nado si tamahe do, Miya wo ba koto ni omohi-ide kikoye tamaha zu. Motoyori mi-narahi kikoye tamaha de narahi tamahe re ba, ima ha tada kono noti no oya wo, imiziu mutubi matuhasi kikoye tamahu. Mono yori ohasure ba, madu ide-mukahi te, ahare ni uti-katarahi, ohom-hutokoro ni iri wi te, isasaka utoku hadukasi to mo omohi tara zu. Saru kata ni, imiziu rautaki waza nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.65 | さかしら心あり ★、何くれと むつかしき筋になりぬれば、わが心地もすこし違ふふしも出で来やと、心おかれ、人も恨みがちに、思ひのほかのこと、おのづから出で来るを、いとをかしきもてあそびなり。 女などはた、かばかりになれば、 心やすくうちふるまひ、隔てなきさまに臥し起きなどは、えしも すまじきを、 これは、いとさまかはりたるかしづきぐさなりと、 思ほいためり。 |
小賢しい智恵がつき、何かとうっとうしい関係となってしまうと、自分の気持ちと多少ぴったりしない点も出て来たのかしらと、心を置かれて、相手も嫉妬しがちになり、意外なもめ事が自然と出て来るものなのに、まことにかわいらしい遊び相手である。自分の娘などでも、これほどの年になったら、気安く振る舞ったり、一緒に寝起きなどは、とてもできないものだろうに、この人は、とても風変わりな大切な娘であると、お思いのようである。 |
Sakasira-gokoro ari, nani-kure to mutukasiki sudi ni nari nure ba, waga kokoti mo sukosi tagahu husi mo ide-ku ya to, kokoro-oka re, hito mo uramigati ni, omohi no hoka no koto, onodukara ide-kuru wo, ito wokasiki mote-asobi nari. Musume nado hata, kabakari ni nare ba, kokoro-yasuku uti-hurumahi, hedate naki sama ni husi-oki nado ha, e simo su maziki wo, kore ha, ito sama kahari taru kasiduki-gusa nari to, omohoi ta' meri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/24/2003 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-3-1) Last updated 9/24/2003 渋谷栄一注釈(ver.1-2-1) |
Last updated 9/24/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-3-1) |
|
Last updated 9/24/2003 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-4-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経