04 夕顔(大島本) |
YUHUGAHO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の十七歳夏から立冬の日までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from the summer to the first day in the winter at the age of 17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 夕顔の物語 夏の物語 |
1 Tale of Yugao in the summer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 源氏、五条の大弐乳母を見舞う |
1-1 Genji calls on his foster-mother who lives in Go-jo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 六条わたりの御忍び歩きのころ、内裏よりまかでたまふ 中宿に、 大弐の乳母のいたくわづらひて 尼になりにける、とぶらはむとて、 五条なる家尋ねておはしたり。 |
六条辺りのお忍び通いのころ、内裏からご退出なさる休息所に、大弍の乳母がひどく病んで尼になっていたのを、見舞おうとして、五条にある家を尋ねていらっしゃった。 |
源氏が六条に恋人を持っていたころ、御所からそこへ通う途中で、だいぶ重い病気をし尼になった大弐の乳母を訪ねようとして、五条辺のその家へ来た。 |
Rokudeu watari no ohom-sinobiariki no koro, uti yori makade tamahu nakayadori ni, Daini-no-Menoto no itaku wadurahi te ama ni nari ni keru, toburaha m tote, Godeu naru ihe tadune te ohasi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 御車入るべき門は鎖したりければ、人して 惟光召させて、 待たせたまひけるほど、 むつかしげなる大路のさまを 見わたしたまへるに、この家のかたはらに、 桧垣といふもの新しうして、 上は半蔀四五間ばかり上げわたして、 簾などもいと白う 涼しげなるに、 をかしき額つきの透影、あまた 見えて覗く。 立ちさまよふらむ下つ方思ひやるに、 あながちに丈高き心地ぞする。 いかなる者の集へるならむと、やうかはりて思さる。 |
お車が入るべき正門は施錠してあったので、供人に惟光を呼ばせて、お待ちあそばす間、むさ苦しげな大路の様子を見渡していらっしゃると、この家の隣に、桧垣という板垣を新しく作って、上方は半蔀を四、五間ほどずらりと吊り上げて、簾などもとても白く涼しそうなところに、美しい額つきをした簾の透き影が、たくさん見えてこちらを覗いている。立ち動き回っているらしい下半身を想像すると、やたらに背丈の高い感じがする。どのような者が集まっているのだろうと、一風変わった様子にお思いになる。 |
乗ったままで車を入れる大門がしめてあったので、従者に呼び出させた乳母の息子の惟光の来るまで、源氏はりっぱでないその辺の町を車からながめていた。惟光の家の隣に、新しい檜垣を外囲いにして、建物の前のほうは上げ格子を四、五間ずっと上げ渡した高窓式になっていて、新しく白い簾を掛け、そこからは若いきれいな感じのする額を並べて、何人かの女が外をのぞいている家があった。高い窓に顔が当たっているその人たちは非常に背の高いもののように思われてならない。どんな身分の者の集まっている所だろう。風変わりな家だと源氏には思われた。 |
Mi-kuruma iru beki kado ha sasi tari kere ba, hito site Koremitu mesa se te, mata se tamahi keru hodo, mutukasi-ge naru ohodi no sama wo mi-watasi tamahe ru ni, kono ihe no katahara ni, higaki to ihu mono atarasiu si te, kami ha hazitomi si, go-kem bakari age-watasi te, sudare nado mo ito sirou suzusige naru ni, wokasiki hitahi-tuki no suki-kage, amata miye te nozo ku. Tati-samayohu ram simo-tu-kata omoi-yaru ni, anagati ni take takaki kokoti zo suru. Ika naru mono no tudohe ru nara m to, yau kahari te obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 御車もいたくやつしたまへり、 前駆も追はせたまはず、 誰れとか知らむとうちとけたまひて、 すこしさし覗きたまへれば、 門は蔀のやうなる、押し上げたる、見入れのほどなく、ものはかなき住まひを、あはれに、「 ▼ 何処かさして」と思ほしなせば、 玉の台も同じことなり ★。 |
お車もひどく地味になさり、先払いもおさせにならず、誰と分かろうかと気をお許しなさって、少し顔を出して御覧になっていると、門は蔀のようなのを押し上げてあって、その奥行きもなく、ささやかな住まいを、しみじみと、「どの家を終生の宿とできようか」とお考えになってみると、立派な御殿も同じことである。 |
今日は車も簡素なのにして目だたせない用意がしてあって、前駆の者にも人払いの声を立てさせなかったから、源氏は自分のだれであるかに町の人も気はつくまいという気楽な心持ちで、その家を少し深くのぞこうとした。門の戸も蔀風になっていて上げられてある下から家の全部が見えるほどの簡単なものである。哀れに思ったが、ただ仮の世の相であるから宮も藁屋も同じことという歌が思われて、われわれの住居だって一所だとも思えた。 |
Mi-kuruma mo itaku yatusi tamahe ri, saki mo oha se tamaha zu, tare to ka sira m to uti-toke tamahi te, sukosi sasi-nozoki tamahe re ba, kado ha sitomi no yau naru, osi-age taru, mi-ire no hodo naku, mono-hakanaki sumahi wo, ahare ni, "Iduko ka sasi te?" to omohosi-nase ba, tama no utena mo onazi koto nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 切懸だつ物に、 いと青やかなる葛の心地よげに 這ひかかれるに、白き花ぞ、 おのれひとり笑みの眉開けたる。 |
切懸の板塀みたいな物に、とても青々とした蔓草が気持ちよさそうに這いまつわっているところに、白い花が、自分ひとり微笑んで咲いている。 |
端隠しのような物に青々とした蔓草が勢いよくかかっていて、それの白い花だけがその辺で見る何よりもうれしそうな顔で笑っていた。 |
Kirikake-datu mono ni, ito awoyaka naru kadura no kokoti-yoge ni hahi-kakare ru ni, siroki hana zo, onore hitori wemi no mayu hirake taru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
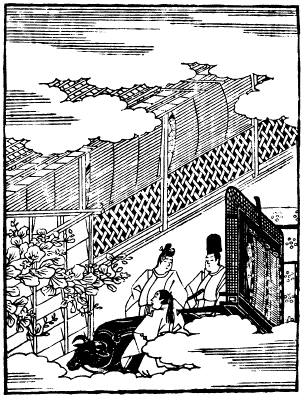 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | 「 ▼ 遠方人にもの申す」 |
「遠方の人にお尋ねする」 |
そこに白く咲いているのは何の花かという歌を口ずさんでいると、 |
"Oti-kata-bito ni mono mausu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | と 独りごちたまふを、 御隋身ついゐて、 |
と独り言をおっしゃると、御随身がひざまずいて、 |
中将の源氏につけられた近衛の随身が車の前に膝をかがめて言った。 |
to hitori-goti tamahu wo, mi-zuizin tui-wi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | 「 かの白く咲けるをなむ、夕顔と申しはべる。花の名は 人めきて、かうあやしき 垣根になむ咲きはべりける」 |
「あの白く咲いている花を、夕顔と申します。花の名は人並のようでいて、このような賤しい垣根に咲くのでございます」 |
「あの白い花を夕顔と申します。人間のような名でございまして、こうした卑しい家の垣根に咲くものでございます」 |
"Kano siroku sake ru wo nam, yuhugaho to mausi haberu. Hana no na ha hito-meki te, kau ayasiki kakine ni nam saki haberi keru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8 | と申す。 げにいと小家がちに、 むつかしげなるわたりの、 ▼ このもかのも、あやしくうちよろぼひて、むねむねしからぬ軒のつまなどに這ひまつはれたるを、 |
と申し上げる。なるほどとても小さい家が多くて、むさ苦しそうな界隈で、この家もかの家も、見苦しくちょっと傾いて、頼りなさそうな軒の端などに這いまつわっているのを、 |
その言葉どおりで、貧しげな小家がちのこの通りのあちら、こちら、あるものは倒れそうになった家の軒などにもこの花が咲いていた。 |
to mausu. Geni ito koihe-gati ni, mutukasige naru watari no, konomo-kanomo, ayasiku uti-yorobohi te, mune-munesikara nu noki no tuma nado ni hahi-matuhare taru wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9 | 「 口惜しの花の契りや。一房折りて参れ」 |
「気の毒な花の運命よ。一房手折ってまいれ」 |
「気の毒な運命の花だね。一枝折ってこい」 |
"Kutiwosi no hana no tigiri ya! Hito-husa wori te mawire." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10 | とのたまへば、この押し上げたる 門に入りて折る。 |
とおっしゃるので、この押し上げてある門から入って折る。 |
と源氏が言うと、蔀風の門のある中へはいって随身は花を折った。 |
to notamahe ba, kono osi-age taru kado ni iri te woru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.11 | さすがに、されたる 遣戸口に、黄なる生絹の単袴、長く着なしたる 童の、 をかしげなる出で来て、 うち招く。 白き扇のいたうこがしたるを、 |
そうは言うものの、しゃれた遣戸口に、黄色い生絹の単重袴を、長く着こなした女童で、かわいらしげな子が出て来て、ちょっと招く。白い扇でたいそう香を薫きしめたのを、 |
ちょっとしゃれた作りになっている横戸の口に、黄色の生絹の袴を長めにはいた愛らしい童女が出て来て随身を招いて、白い扇を色のつくほど薫物で燻らしたのを渡した。 |
Sasuga ni, sare taru yarido-guti ni, ki naru suzusi no hitohe-bakama, nagaku ki-nasi taru waraha no, wokasige naru ide-ki te, uti-maneku. Siroki ahugi no itau kogasi taru wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.12 | 「 これに置きて参らせよ。枝も 情けなげなめる花を」 |
「これに載せて差し上げなさいね。枝も風情なさそうな花ですもの」 |
「これへ載せておあげなさいまし。手で提げては不恰好な花ですもの」 |
"Kore ni oki te mawirase yo. Eda mo nasake-nage na' meru hana wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.13 | とて 取らせたれば、門開けて 惟光朝臣出で来たるして、奉らす。 |
と言って与えたところ、門を開けて惟光朝臣が出て来たのを取り次がせて、差し上げさせる。 |
随身は、夕顔の花をちょうどこの時門をあけさせて出て来た惟光の手から源氏へ渡してもらった。 |
tote torase tare ba, kado ake te Koremitu-no-Asom ide-ki taru site, tatematura su. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.14 | 「 鍵を置きまどはしはべりて、 いと不便なるわざなりや。もののあやめ見たまへ分くべき人もはべらぬわたりなれど、 らうがはしき大路に立ちおはしまして」とかしこまり申す。 |
「鍵を置き忘れまして、大変にご迷惑をお掛けいたしました。どなた様と分別申し上げられる者もおりませぬ辺りですが、ごみどみした大路にお立ちあそばして」とお詫び申し上げる。 |
「鍵の置き所がわかりませんでして、たいへん失礼をいたしました。よいも悪いも見分けられない人の住む界わいではございましても、見苦しい通りにお待たせいたしまして」 と惟光は恐縮していた。 |
"Kagi wo oki-madohasi haberi te, ito hubin naru waza nari ya! Mono no ayame mi tamahe waku beki hito mo habera nu watari nare do, raugahasiki ohodi ni tati ohasimasi te." to kasikomari mausu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.15 | 引き入れて、下りたまふ。 惟光が兄の阿闍梨、婿の三河守、娘など、渡り集ひたるほどに、かくおはしましたる喜びを、またなきことにかしこまる。 |
車を引き入れて、お下りになる。惟光の兄の阿闍梨や、娘婿の三河守、娘などが、寄り集まっているところに、このようにお越しあそばされたお礼を、この上ないことと恐縮して申し上げる。 |
車を引き入れさせて源氏の乳母の家へ下りた。惟光の兄の阿闍梨、乳母の婿の三河守、娘などが皆このごろはここに来ていて、こんなふうに源氏自身で見舞いに来てくれたことを非常にありがたがっていた。 |
Hiki-ire te, ori tamahu. Koremitu ga ani no Azyari, muko no Mikaha-no-Kami, musume nado, watari tudohi taru hodo ni, kaku ohasimasi taru yorokobi wo, mata naki koto ni kasikomaru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.16 | 尼君も起き上がりて、 |
尼君も起き上がって、 |
尼も起き上がっていた。 |
Ama-Gimi mo oki-agari te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.17 | 「 惜しげなき身なれど、 捨てがたく思うたまへつることは、ただ、 かく御前にさぶらひ、 御覧ぜらるることの 変りはべりなむことを口惜しく思ひたまへ、たゆたひしかど、忌むことのしるしに よみがへりてなむ、かく渡りおはしますを、 見たまへはべりぬれば、 今なむ 阿弥陀仏の御光も、心清く 待たれはべるべき」 |
「惜しくもない身の上ですが、出家しがたく存じておりましたことは、ただ、このようにお目にかかり、御覧に入れる姿が変わってしまいますことを残念に存じて、ためらっておりましたが、受戒の効果があって生き返って、このようにお越しあそばされましたのを、お目にかかれましたので、今は、阿弥陀様のご来迎も、心残りなく待つことができましょう」 |
「もう私は死んでもよいと見られる人間なんでございますが、少しこの世に未練を持っておりましたのはこうしてあなた様にお目にかかるということがあの世ではできませんからでございます。尼になりました功徳で病気が楽になりまして、こうしてあなた様の御前へも出られたのですから、もうこれで阿弥陀様のお迎えも快くお待ちすることができるでしょう」 |
"Wosi-ge naki mi nare do, sute-gataku omou tamahe turu koto ha, tada, kaku o-mahe ni saburahi, go-ran-ze raruru koto no kahari haberi na m koto wo kutiwosiku omohi tamahe, tayutahi sika do, imu koto no sirusi ni yomigaheri te nam, kaku watari ohasimasu wo, mi tamahe haberi nure ba, ima nam Amidabutu no ohom-hikari mo kokoro-kiyoku mata re haberu beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.18 | など聞こえて、弱げに泣く。 |
などと申し上げて、弱々しく泣く。 |
などと言って弱々しく泣いた。 |
nado kikoye te, yowage ni naku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.19 | 「 日ごろ、おこたりがたく ものせらるるを、 安からず嘆きわたりつるに、かく、世を離るるさまにものしたまへば、いとあはれに 口惜しうなむ。命長くて、 なほ位高くなど見なしたまへ。 さてこそ、 九品の上にも、障りなく生まれたまはめ。この世にすこし恨み残るは、悪ろきわざとなむ聞く」など、涙ぐみてのたまふ。 |
「いく日も、思わしくなくおられるのを、案じて心痛めていましたが、このように、世を捨てた尼姿でいらっしゃると、まことに悲しく残念です。長生きをして、さらにわたしの位が高くなるのなども御覧下さい。そうしてから、九品浄土の最上位にも、差し障りなくお生まれ変わりなさいさい。この世に少しでも執着が残るのは、悪いことと聞いております」などと、涙ぐんでおっしゃる。 |
「長い間恢復しないあなたの病気を心配しているうちに、こんなふうに尼になってしまわれたから残念です。長生きをして私の出世する時を見てください。そのあとで死ねば九品蓮台の最上位にだって生まれることができるでしょう。この世に少しでも飽き足りない心を残すのはよくないということだから」 源氏は涙ぐんで言っていた。 |
"Hi-goro, okotari-gataku monose raruru wo, yasukara zu nageki watari turu ni, kaku, yo wo hanaruru sama ni monosi tamahe ba, ito ahare ni kutiwosiu nam. Inoti nagaku te, naho kurawi takaku nado mi-nasi tamahe. Sate koso, kokono-sina no kami ni mo, sahari naku mumare tamaha me. Konoyo ni sukosi urami nokoru ha, waroki waza to nam kiku."nado, namidagumi te notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.20 | かたほなるをだに、乳母やうの思ふべき人は、あさましうまほに見なすものを、まして、 いと面立たしう、なづさひ仕うまつりけむ身も、いたはしうかたじけなく 思ほゆべかめれば、すずろに涙がちなり。 |
不出来な子でさえも、乳母のようなかわいがるはずの人には、あきれるくらいに完全無欠に思い込むものを、まして、まことに光栄にも、親しくお世話申し上げたわが身も、大切にもったいなく思われるようなので、わけもなく涙に濡れるのである。 |
欠点のある人でも、乳母というような関係でその人を愛している者には、それが非常にりっぱな完全なものに見えるのであるから、まして養君がこの世のだれよりもすぐれた源氏の君であっては、自身までも普通の者でないような誇りを覚えている彼女であったから、源氏からこんな言葉を聞いてはただうれし泣きをするばかりであった。 |
Kataho naru wo dani, menoto yau no omohu beki hito ha, asamasiu maho ni mi-nasu mono wo, masite ito omodatasiu, nadusahi tukaumaturi kem mi mo, itahasiu katazikenaku omohoyu beka' mere ba, suzuro ni namidagati nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.21 | 子どもは、いと見苦しと思ひて、「 背きぬる世の去りがたきやうに、みづからひそみ 御覧ぜられたまふ」と、つきしろひ目くはす。 |
子供たちは、とてもみっともないと思って、「捨てたこの世に未練があるようで、ご自身から泣き顔をお目にかけていなさる」と言って、突き合い目配せし合う。 |
息子や娘は母の態度を飽き足りない歯がゆいもののように思って、尼になっていながらこの世への未練をお見せするようなものである、俗縁のあった方に惜しんで泣いていただくのはともかくもだがというような意味を、肱を突いたり、目くばせをしたりして兄弟どうしで示し合っていた。 |
Kodomo ha, ito migurusi to omohi te, "Somuki nuru yo no sari-gataki yau ni, midukara hisomi go-ran-ze rare tamahu." to, tuki-sirohi me-kuhasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.22 | 君は、 いとあはれと思ほして、 |
源氏の君は、とてもしみじみと感じられて、 |
源氏は乳母を憐んでいた。 |
Kimi ha, ito ahare to omohosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.23 | 「 いはけなかりけるほどに、 思ふべき人びとのうち捨ててものしたまひにけるなごり、育む人あまた あるやうなりしかど、親しく思ひ睦ぶる筋は、 またなくなむ思ほえし。人となりて後は、 限りあれば、 朝夕にしもえ見たてまつらず、心のままに訪らひ参づることはなけれど、なほ久しう対面せぬ時は、心細くおぼゆるを、『 ▼ さらぬ別れはなくもがな』」 |
「幼かったころに、かわいがってくれるはずの方々が亡くなってしまわれた後は、養育してくれる人々はたくさんいたようでしたが、親しく甘えられる人は、他にいなく思われました。成人して後は、きまりがあるので、朝に夕にというようにもお目にかかれず、思い通りにお訪ね申すことはなかったが、やはり久しくお会いしていない時は、心細く思われましたが、『避けられない別れなどはあってほしくないものだ』と思われます」 |
「母や担母を早く失くした私のために、世話する役人などは多数にあっても、私の最も親しく思われた人はあなただったのだ。大人になってからは少年時代のように、いつもいっしょにいることができず、思い立つ時にすぐに訪ねて来るようなこともできないのですが、今でもまだあなたと長く逢わないでいると心細い気がするほどなんだから、生死の別れというものがなければよいと昔の人が言ったようなことを私も思う」 |
"Ihakenakari keru hodo ni, omohu beki hito-bito no uti-sute te monosi tamahi ni keru nagori, hagukumu hito amata aru yau nari sika do, sitasiku omohi mutuburu sudi ha, mata naku nam omohoye si. Hito to nari te noti ha, kagiri are ba, asa-yuhu ni simo e mi tatematura zu, kokoro no mama ni toburahi mauduru koto ha nakere do, naho hisasiu taimen se nu toki ha, kokoro-bosoku oboyuru wo, 'Sara nu wakare ha naku mo gana.'" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.24 | となむ、こまやかに語らひたまひて、おし拭ひたまへる袖のにほひも、いと 所狭きまで薫り満ちたるに、 げに、よに思へば、おしなべたらぬ人の御宿世ぞかしと、尼君をもどかしと見つる子ども、皆うちしほたれけり。 |
と、懇ろにお話なさって、お拭いになった袖の匂いも、とても辺り狭しと薫り満ちているので、なるほど、ほんとうに考えてみれば、並々の人でないご運命であったと、尼君を非難がましく見ていた子供たちも、皆涙ぐんだ。 |
しみじみと話して、袖で涙を拭いている美しい源氏を見ては、この方の乳母でありえたわが母もよい前生の縁を持った人に違いないという気がして、さっきから批難がましくしていた兄弟たちも、しんみりとした同情を母へ持つようになった。 |
to nam, komayaka ni katarahi tamahi te, osi-nogohi tamahe ru sode no nihohi mo, ito tokoro-seki made kawori-miti taru ni, geni, yoni omohe ba, osinabe tara nu hito no mi-sukuse zo kasi to, Ama-Gimi wo modokasi to mi turu kodomo, mina uti-sihotare keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.25 | 修法など、またまた始むべきことなど掟てのたまはせて、出でたまふとて、惟光に紙燭召して、 ありつる扇御覧ずれば、もて馴らしたる移り香、いと染み深うなつかしくて、をかしうすさみ書きたり。 |
修法などを、再び重ねて始めるべき事などをお命じあそばして、お立ちになろうとして、惟光に紙燭を持って来させて、先程の扇を御覧になると、使い慣らした主人の移り香が、とても深く染み込んで慕わしくて、美しく書き流してある。 |
源氏が引き受けて、もっと祈祷を頼むことなどを命じてから、帰ろうとする時に惟光に蝋燭を点させて、さっき夕顔の花の載せられて来た扇を見た。よく使い込んであって、よい薫物の香のする扇に、きれいな字で歌が書かれてある。 |
Syuhohu nado, mata mata hazimu beki koto nado okite notamahase te, ide tamahu tote, Koremitu ni sisoku mesi te, arituru ahugi go-ran-zure ba, mote-narasi taru uturiga, ito simi hukau natukasiku te, wokasiu susami kaki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.26 | 「 心あてにそれかとぞ見る白露の |
「当て推量に貴方さまでしょうかと思います |
心あてにそれかとぞ見る白露の |
"Kokoro-ate ni sore ka to zo miru sira-tuyu no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.27 | 光そへたる夕顔の花」 |
白露の光を加えて美しい夕顔の花は」 |
光添へたる夕顔の花 |
hikari sohe taru yuhugaho no hana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
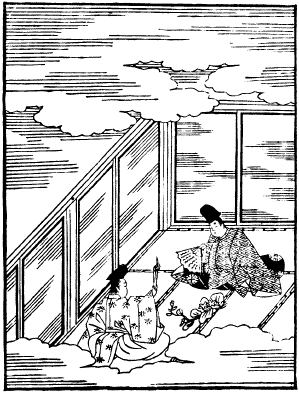 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.28 | そこはかとなく書き紛らはしたるも、あてはかに ゆゑづきたれば、いと思ひのほかに、をかしうおぼえたまふ。惟光に、 |
誰とも分からないように書き紛らわしているのも、上品に教養が見えるので、とても意外に、興味を惹かれなさる。惟光に、 |
散らし書きの字が上品に見えた。少し意外だった源氏は、風流遊戯をしかけた女性に好感を覚えた。惟光に、 |
Sokohakatonaku kaki magirahasi taru mo, atehaka ni yuwe-duki tare ba, ito omohi no hoka ni, wokasiu oboye tamahu. Koremitu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.29 | 「 この西なる家は 何人の住むぞ。 問ひ聞きたりや」 |
「この家の西にある家にはどんな者が住んでいるのか。尋ね聞いているか」 |
「この隣の家にはだれが住んでいるのか、聞いたことがあるか」 |
"Kono nisi naru ihe ha nani-bito no sumu zo? Tohi-kiki tari ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.30 | とのたまへば、 例のうるさき御心とは思へども、 えさは申さで、 |
とお尋ねになると、いつもの厄介なお癖とは思うが、そうは申し上げず、 |
と言うと、惟光は主人の例の好色癖が出てきたと思った。 |
to notamahe ba, rei no urusaki mi-kokoro to ha omohe domo, e sa ha mausa de, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.31 | 「 この五、六日ここにはべれど、 病者のことを 思うたまへ扱ひはべるほどに、隣のことはえ聞きはべらず」 |
「この五、六日この家におりますが、病人のことを心配して看護しております時なので、隣のことは聞けません」 |
「この五、六日母の家におりますが、病人の世話をしておりますので、隣のことはまだ聞いておりません」 |
"Kono go, roku-niti koko ni habere do, byauzya no koto wo omou tamahe atukahi haberu hodo ni, tonari no koto ha e kiki habera zu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.32 | など、 はしたなやかに聞こゆれば、 |
などと、無愛想に申し上げるので、 |
惟光が冷淡に答えると、源氏は、 |
nado, hasitanayaka ni kikoyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.33 | 「 憎しとこそ思ひたれな。 されど、この扇の、尋ぬべきゆゑありて 見ゆるを。なほ、このわたりの 心知れらむ者を召して問へ」 |
「気に入らないと思っているな。けれど、この扇について、尋ねなければならない理由がありそうに思われるのですよ。やはり、この界隈の事情を知っていそうな者を呼んで尋ねよ」 |
「こんなことを聞いたのでおもしろく思わないんだね。でもこの扇が私の興昧をひくのだ。この辺のことに詳しい人を呼んで聞いてごらん」 |
"Nikusi to koso omohi tare na. Saredo, kono ahugi no, tadunu beki yuwe ari te miyuru wo. Naho, kono watari no kokoro-sire ra m mono wo mesi te tohe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.34 | とのたまへば、 入りて、 この宿守なる男を呼びて問ひ聞く。 |
とおっしゃるので、入って行って、この家の管理人の男を呼んで尋ねる。 |
と言った。はいって行って隣の番人と逢って来た惟光は、 |
to notamahe ba, iri te, kono yadomori naru wonoko wo yobi te, tohi-kiku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.35 | 「 揚名介なる人の家になむはべりける。 男は田舎にまかりて ★、妻なむ若く事好みて、はらからなど宮仕人にて来通ふ、と申す。詳しきことは、下人の え知りはべらぬにやあらむ」と聞こゆ。 |
「揚名介である人の家だそうでございました。男は地方に下向して、妻は若く派手好きで、その姉妹などが宮仕え人として行き来している、と申します。詳しいことは、下人にはよく分からないのでございましょう」と申し上げる。 |
「地方庁の介の名だけをいただいている人の家でございました。主人は田舎へ行っているそうで、若い風流好きな細君がいて、女房勤めをしているその姉妹たちがよく出入りすると申します。詳しいことは下人で、よくわからないのでございましょう」 と報告した。 |
"Yaumei-no-suke naru hito no ihe ni nam haberi keru. Wotoko ha winaka ni makari te, me nam wakaku koto konomi te, harakara nado miyadukahe-bito nite ki-kayohu, to mausu. Kuhasiki koto ha, simo-bito no e siri habera nu ni ya ara m" to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.36 | 「 さらば、その 宮仕人ななり。したり顔にもの馴れて 言へるかな」と、「 めざましかるべき際にやあらむ」と思せど、さして聞こえかかれる心の、憎からず過ぐしがたきぞ、 例の、この方には重からぬ御心なめるかし。御畳紙にいたう あらぬさまに書き変へたまひて、 |
「それでは、その宮仕人のようだ。得意顔になれなれしく詠みかけてきたものよ」と、「きっと興覚めしそうな身分ではなかろうか」とお思いになるが、名指して詠みかけてきた気持ちが、憎からず見過ごしがたいのが、例によって、こういった方面には、重々しくないご性分なのであろう。御畳紙にすっかり別筆にお書きになって、 |
ではその女房をしているという女たちなのであろうと源氏は解釈して、いい気になって、物馴れた戯れをしかけたものだと思い、下の品であろうが、自分を光源氏と見て詠んだ歌をよこされたのに対して、何か言わねばならぬという気がした。というのは女性にはほだされやすい性格だからである。懐紙に、別人のような字体で書いた。 |
"Saraba, sono miyadukahe-bito na' nari. Sitari-gaho ni mono-nare te ihe ru kana!" to, "Mezamasikaru beki kiha ni ya ara m" to obose do, sasite kikoye kakare ru kokoro no, nikukara zu sugusi-gataki zo, rei no, kono kata ni ha omokara nu mi-kokoro na' meru kasi. Ohom-tataugami ni itau ara nu sama ni kaki-kahe tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.37 | 「 寄りてこそそれかとも見めたそかれに |
「もっと近寄って誰ともはっきり見たらどうでしょう |
寄りてこそそれかとも見め黄昏れに |
"Yori te koso sore ka to mo mi me tasokare ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.38 | ほのぼの見つる花の夕顔」 |
黄昏時にぼんやりと見えた花の夕顔を」 |
ほのぼの見つる花の夕顔 |
hono-bono mi turu hana no yuhugaho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.39 | ありつる御随身して遣はす。 |
先程の御随身をお遣わしになる。 |
花を折りに行った随身に持たせてやった。 |
Arituru mi-zuizin site tukahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.40 | まだ見ぬ御さまなりけれど、いとしるく思ひあてられたまへる御側目を見過ぐさで、さしおどろかしけるを、答へたまはでほど経ければ、なまはしたなきに、かくわざとめかしければ、あまえて、「いかに聞こえむ」など 言ひしろふべかめれど、めざましと思ひて、随身は参りぬ。 |
まだ見たことのないお姿であったが、まことにはっきりと推察されなさるおん横顔を見過ごさないで、さっそく詠みかけたのに、返歌を下さらないで時間が過ぎたので、何となく体裁悪く思っていたところに、このようにわざわざ来たというふうだったので、いい気になって、「何と申し上げよう」などと言い合っているようだが、生意気なと思って、随身は帰参した。 |
夕顔の花の家の人は源氏を知らなかったが、隣の家の主人筋らしい貴人はそれらしく思われて贈った歌に、返事のないのにきまり悪さを感じていたところへ、わざわざ使いに返歌を持たせてよこされたので、またこれに対して何か言わねばならぬなどと皆で言い合ったであろうが、身分をわきまえないしかただと反感を持っていた随身は、渡す物を渡しただけですぐに帰って来た。 |
Mada mi nu ohom-sama nari kere do, ito siruku omohi-ate rare tamahe ru ohom-sobame wo mi-sugusa de sasi-odorokasi keru wo, irahe tamaha de hodo he kere ba, nama-hasitanaki ni, kaku wazato-mekasi kere ba, amaye te, "Ikani kikoye m?" nado ihi-sirohu beka' mere do, mezamasi to omohi te, zuizin ha mawiri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.41 | 御前駆の 松明ほのかにて、 いと忍びて出でたまふ。 半蔀は下ろしてけり。隙々より見ゆる灯の光、 蛍よりけにほのかにあはれなり。 |
御前駆の松明を弱く照らして、とてもひっそりとお出になる。半蔀は既に下ろされていた。隙間隙間から見える灯火の明りは、蛍よりもさらに微かでしみじみとした思いである。 |
前駆の者が馬上で掲げて行く松明の明りがほのかにしか光らないで源氏の車は行った。高窓はもう戸がおろしてあった。その隙間から蛍以上にかすかな灯の光が見えた。 |
Ohom-saki no matu honoka nite, ito sinobi te ide tamahu. Hazitomi ha orosi te keri. Hima-hima yori miyuru hi no hikari, hotaru yori keni honoka ni ahare nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.42 | 御心ざしの所には、木立 前栽など、なべての所に似ず、いとのどかに心にくく住みなしたまへり。 うちとけぬ御ありさまなどの、気色ことなるに、 ありつる垣根 思ほし出でらるべくもあらずかし。 |
お目当ての所では、木立や前栽などが、世間一般の所とは違い、とてもゆったりと奥ゆかしく住んでいらっしゃる。気の置けるご様子などが、他の人とは格別なので、先程の垣根の女などはお思い出されるはずもない。 |
源氏の恋人の六条貴女の邸は大きかった。広い美しい庭があって、家の中は気高く上手に住み馴らしてあった。まだまったく源氏の物とも思わせない、打ち解けぬ貴女を扱うのに心を奪われて、もう源氏は夕顔の花を思い出す余裕を持っていなかったのである。 |
Mi-kokorozasi no tokoro ni ha, kodati sensai nado, nabete no tokoro ni ni zu, ito nodoka ni kokoro-nikuku sumi-nasi tamahe ri. Utitoke nu ohom-arisama nado no, kesiki koto naru ni, arituru kakine omohosi-ide raru beku mo ara zu kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.43 | 翌朝、すこし寝過ぐしたまひて、日さし出づるほどに出でたまふ。 朝明の姿は、げに人のめできこえむも、ことわりなる御さまなりけり。 |
翌朝、少しお寝過ごしなさって、日が差し出るころにお帰りになる。朝帰りの姿は、なるほど世間の人がお褒め申し上げるようなのも、ごもっともなお美しさであった。 |
早朝の帰りが少しおくれて、日のさしそめたころに出かける源氏の姿には、世間から大騒ぎされるだけの美は十分に備わっていた。 |
Tutomete, sukosi ne-sugusi tamahi te, hi sasi-iduru hodo ni ide tamahu. Asake no sugata ha, geni hito no mede kikoye m mo kotowari naru ohom-sama nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.44 | 今日もこの蔀の前渡りしたまふ。 来し方も過ぎたまひけむわたりなれど、 ただはかなき一ふしに御心とまりて、「 いかなる人の住み処ならむ」とは、往き来に御目とまりたまひけり。 |
今日もこの半蔀の前をお通り過ぎになる。今までにも通り過ぎなさった辺りであるが、わずかちょっとしたことでお気持ちを惹かれて、「どのような女が住んでいる家なのだろうか」と思っては、行き帰りにお目が止まるのであった。 |
今朝も五条の蔀風の門の前を通った。以前からの通り路ではあるが、あのちょっとしたことに興味を持ってからは、行き来のたびにその家が源氏の目についた。 |
Kehu mo kono sitomi no mahe-watari si tamahu. Kisi-kata mo sugi tamahi kem watari nare do, tada hakanaki hito-husi ni mi-kokoro tomari te, "Ika naru hito no sumika nara m?" to ha, yuki-ki ni ohom-me tomari tamahi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 数日後、夕顔の宿の報告 |
1-2 After several days |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 惟光、日頃ありて参れり。 |
惟光が、数日して参上した。 |
幾日かして惟光が出て来た。 |
Koremitu, higoro ari te mawire ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 「 わづらひはべる人、なほ弱げにはべれば、とかく 見たまへあつかひてなむ ★」 |
「患っております者が、依然として弱そうでございましたので、いろいろと看病いたしておりまして」 |
「病人がまだひどく衰弱しているものでございますから、どうしてもそのほうの手が離せませんで、失礼いたしました」 |
"Wadurahi haberu hito, naho yowage ni habere ba, tokaku mi tamahe atukahi te nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | など、聞こえて、 近く参り寄りて聞こゆ。 |
などと、ご挨拶申し上げて、近くに上って申し上げる。 |
こんな挨拶をしたあとで、少し源氏の君の近くへ膝を進めて惟光朝臣は言った。 |
nado, kikoye te, tikaku mawiri yori te kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | 「 仰せられしのちなむ、隣のこと知りてはべる者、呼びて問はせはべりしかど、はかばかしくも申しはべらず。『 いと忍びて、五月のころほひよりものしたまふ 人なむあるべけれど、その人とは、 さらに家の内の人にだに知らせず』 となむ申す。 |
「仰せ言のございました後に、隣のことを知っております者を、呼んで尋ねさせましたが、はっきりとは申しません。『ごく内密に、五月のころからおいでの方があるようですが、誰それとは、全然その家の内の人にさえ知らせません』と申します。 |
「お話がございましたあとで、隣のことによく通じております者を呼び寄せまして、聞かせたのでございますが、よくは話さないのでございます。この五月ごろからそっと来て同居している人があるようですが、どなたなのか、家の者にもわからせないようにしていますと申すのです。 |
"Ohose rare si noti nam, tonari no koto siri te haberu mono yobi te, toha se haberi sika do, haka-bakasiku mo mausi habera zu. 'Ito sinobi te satuki no korohohi yori monosi tamahu hito nam aru bekere do, sono hito to ha, sarani ihe no uti no hito ni dani sira se zu' to nam mausu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 時々、中垣のかいま見しはべるに、 げに若き女どもの透影見えはべり。 褶だつもの、 かごとばかり 引きかけて、 かしづく人はべるなめり。 |
時々、中垣から覗き見いたしますと、なるほど、若い女たちの透き影が見えます。褶めいた物を、申しわけ程度にひっかけているので、仕えている主人がいるようでございます。 |
時々私の家との間の垣根から私はのぞいて見るのですが、いかにもあの家には若い女の人たちがいるらしい影が簾から見えます。主人がいなければつけない裳を言いわけほどにでも女たちがつけておりますから、主人である女が一人いるに違いございません。 |
Toki-doki nakagaki no kaimami si haberu ni, geni wakaki womna-domo no sukikage miye haberi. Sibira-datu mono, kagoto bakari hiki-kake te, kasiduku hito haberu na' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 昨日、夕日のなごりなく さし入りてはべりしに、文書くとてゐてはべりし人の、 顔こそいとよくはべりしか。もの思へるけはひして、 ある人びとも忍びてうち泣く さまなどなむ、しるく見えはべる」 |
昨日、夕日がいっぱいに射し込んでいました時に、手紙を書こうとして座っていました女人の顔が、とてもようございました。憂えに沈んでいるような感じがして、側にいる女房たちも涙を隠して泣いている様子などが、はっきりと見えました」 |
昨日夕日がすっかり家の中へさし込んでいました時に、すわって手紙を書いている女の顔が非常にきれいでした。物思いがあるふうでございましたよ。女房の中には泣いている者も確かにおりました」 |
Kinohu, yuhuhi no nagori naku sasi-iri te haberi si ni, humi kaku tote wi te haberi si hito no, kaho koso ito yoku haberi sika. Mono-omohe ru kehahi si te, aru hito-bito mo sinobi te uti-naku sama nado nam, siruku miye haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | と聞こゆ。君うち笑みたまひて、「 知らばや」と 思ほしたり。 |
と申し上げる。源氏の君はにっこりなさって、「知りたいものだ」とお思いになった。 |
源氏はほほえんでいたが、もっと詳しく知りたいと思うふうである。 |
to kikoyu. Kimi uti-wemi tamahi te, "Sira baya" to omohosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | おぼえこそ重かるべき御身のほどなれど、御よはひのほど、人のなびきめできこえたる さまなど思ふには、 好きたまはざらむも、情けなく さうざうしかるべしかし、 人のうけひかぬほどにてだに、 なほ、さりぬべきあたりのことは、 このましうおぼゆるものを、 と思ひをり。 |
ご声望こそ重々しいはずのご身分であるが、ご年齢のほど、女性たちがお慕いしお褒め申し上げている様子などを考えると、興味をお感じにならないのも、風情がなくきっと物足りない気がするだろうが、世間の人が承知しない身分でさえ、やはり、しかるべき身分の人には、興味をそそられるものだから、と思っている。 |
自重をなさらなければならない身分は身分でも、この若さと、この美の備わった方が、恋愛に興味をお持ちにならないでは、第三者が見ていても物足らないことである。恋愛をする資格がないように思われているわれわれでさえもずいぶん女のことでは好奇心が動くのであるからと惟光は主人をながめていた。 |
Oboye koso omokaru beki ohom-mi no hodo nare do, ohom-yohahi no hodo, hito no nabiki mede kikoye taru sama nado omohu ni ha, suki tamaha zara m mo, nasakenaku sau-zausikaru besi kasi, hito no uke-hika nu hodo ni te dani, naho, sari-nu-beki atari no koto ha, konomasiu oboyuru mono wo, to omohi wori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 「 もし、見たまへ得ることもやはべると、 はかなきついで作り出でて、 消息など遣はしたりき。書き馴れたる手して、 口とく返り事などしはべりき。 いと口惜しうはあらぬ若人どもなむはべるめる」 |
「もしや、何か発見いたすこともありましょうかと、ちょっとした機会を作って、恋文などを出してみました。書きなれている筆跡で、素早く返事など寄こしました。たいして悪くはない若い女房たちがいるようでございます」 |
「そんなことから隣の家の内の秘密がわからないものでもないと思いまして、ちょっとした機会をとらえて隣の女へ手紙をやってみました。するとすぐに書き馴れた達者な字で返事がまいりました、相当によい若い女房もいるらしいのです」 |
"Mosi, mi tamahe uru koto mo ya haberu to, hakanaki tuide tukuri-ide te, seusoko nado tukahasi tari ki. Kaki-nare taru te site, kuti-toku kaheri-goto nado si haberi ki. Ito kutiwosiu ha ara nu wakaudo-domo nam haberu meru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | と聞こゆれば、 |
と申し上げると、 |
「おまえは、なおどしどし恋の手紙を送ってやるのだね。それがよい。その人の正体が知れないではなんだか安心ができない」 と源氏が言った。 |
to kikoyure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | 「 なほ言ひ寄れ。尋ね寄らでは、 さうざうしかりなむ」とのたまふ。 |
「さらに近づけ。突き止めないでは、きっと物足りない気がしよう」とおっしゃる。 |
家は下の下に属するものと品定めの人たちに言われるはずの所でも、そんな所から意外な趣のある女を見つけ出すことがあればうれしいに違いないと源氏は思うのである。 |
"Naho, ihi-yore. Tadune-yora de ha, sau-zausikari na m." to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | かの、下が下と、人の思ひ捨てし住まひなれど、 その中にも、思ひのほかに口惜しからぬを見つけたらばと、 めづらしく思ほすなりけり。 |
あの、下層の最下層だと、人が見下した住まいであるが、その中にも、意外に結構なのを見つけたらばと、心惹かれてお思いになるのであった。 |
Kano, simo-ga-simo to, hito no omohi-sute si sumahi nare do, sono naka ni mo, omohi no hoka ni kutiwosikara nu wo mituke tara ba to, medurasiku omohosu nari keri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 6/25/2003 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-3-1) Last updated 6/25/2003 渋谷栄一注釈(ver.1-2-1) |
Last updated 6/25/2203 渋谷栄一訳(C)(ver.1-3-1) |
|
Last updated 6/25/2003 Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-4-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経