02 帚木(明融臨模本) |
HAHAKIGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏 十七歳夏の参議(宰相)兼近衛中将時代の物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era in the summer at the age of 17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 空蝉の物語 |
3 Tale of Utsusemi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 天気晴れる |
3-1 One fine day |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | からうして今日は日のけしきも直れり。かくのみ籠もりさぶらひたまふも、 大殿の御心いとほしければ、まかでたまへり。 |
やっと今日は天気も好くなった。こうしてばかり籠っていらっしゃるのも、左大臣殿のお気持ちが気の毒なので、退出なさった。 |
やっと今日は天気が直った。源氏はこんなふうに宮中にばかりいることも左大臣家の人に気の毒になってそこへ行った。 |
Karausite kehu ha hi no kesiki mo nahore ri. Kaku nomi komori saburahi tamahu mo, Ohoidono no mi-kokoro itohosikere ba, makade tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | おほかたの気色、 人のけはひも、 けざやかにけ高く、乱れたるところまじらず、 なほ、これこそは、 かの、人びとの捨てがたく取り出でしまめ人には頼まれぬべけれ、と思すものから、 あまりうるはしき御ありさまの、とけがたく恥づかしげに思ひしづまりたまへるを さうざうしくて、 中納言の君、中務などやうの、おしなべたらぬ若人どもに、 戯れ言などのたまひつつ、 暑さに乱れたまへる御ありさま ★を、 見るかひありと思ひきこえたり。 |
邸内の有様や、姫君の様子も、端麗で気高く、くずれたところがなく、やはり、この女君こそは、あの、人びとが捨て置き難く取り上げた実直な妻としては信頼できるだろう、とお思いになる一方では、度を過ぎて端麗なご様子で、打ち解けにくく気づまりな感じにとり澄ましていらっしゃるのが物足りなくて、中納言の君や中務などといった、人並み優れている若い女房たちに、冗談などをおっしゃりおっしゃりして、暑さにお召し物もくつろげていらっしゃるお姿を、素晴らしく美しい、と思い申し上げている。 |
一糸の乱れも見えぬというような家であるから、こんなのがまじめということを第一の条件にしていた、昨夜の談話者たちには気に入るところだろうと源氏は思いながらも、今も初めどおりに行儀をくずさぬ、打ち解けぬ夫人であるのを物足らず思って、中納言の君、中務などという若いよい女房たちと冗談を言いながら、暑さに部屋着だけになっている源氏を、その人たちは美しいと思い、こうした接触が得られる幸福を覚えていた。 |
Ohokata no kesiki, hito no kehahi mo, kezayaka ni kedakaku, midare taru tokoro mazira zu, naho, kore koso ha, kano, hito-bito no sute-gataku tori-ide si mame-bito ni ha tanoma re nu bekere, to obosu mono-kara, amari uruhasiki ohom-arisama no, toke-gataku hadukasige ni omohi sidumari tamahe ru wo sau-zausiku te, Tyuunagon-no-Kimi, Nakatukasa nado yau no, osinabe tara nu wakaudo-domo ni, tahabure-goto nado notamahi tutu, atusa ni midare tamahe ru ohom-arisama wo, miru kahi ari to omohi kikoye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | 大臣も渡りたまひて、 うちとけたまへれば、 御几帳隔てておはしまして、 御物語聞こえたまふを、「 暑きに」とにがみたまへば、人びと笑ふ。「 あなかま」とて、脇息に寄り おはす。 いとやすらかなる御振る舞ひなりや。 |
左大臣殿もお渡りになって、くつろいでいらっしゃるので、御几帳を間に立ててお座りになって、お話を申し上げなさるのを、「暑いのに」と苦い顔をなさるので、女房たちは笑う。「お静かに」と制して、脇息に寄り掛かっていらっしゃる。いかにも大君らしい鷹揚なお振る舞いであるよ。 |
大臣も娘のいるほうへ出かけて来た。部屋着になっているのを知って、几帳を隔てた席について話そうとするのを、 「暑いのに」 と源氏が顔をしかめて見せると、女房たちは笑った。 「静かに」 と言って、脇息に寄りかかった様子にも品のよさが見えた。 |
Otodo mo watari tamahi te, utitoke tamahe re ba, mi-kityau hedate te ohasimasi te, ohom-monogatari kikoye tamahu wo, "Atuki ni" to nigami tamahe ba, hito-bito warahu. "Ana-kama" tote, kehusoku ni yori ohasu. Ito yasuraka naru ohom-hurumahi nari ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | 暗くなるほどに、 |
暗くなるころに、 |
暗くなってきたころに、 |
Kuraku naru hodo ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | 「 今宵、中神、内裏よりは塞がりてはべりけり」と聞こゆ。 |
「今夜は、天一神が、内裏からこちらの方角へは方塞がりになっております」と申し上げる。 |
「今夜は中神のお通り路になっておりまして、御所からすぐにここへ来てお寝みになってはよろしくございません」 という、源氏の家従たちのしらせがあった。 |
"Koyohi, Naka-gami, Uti yori ha hutagari te haberi keri." to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | 「 さかし、例は忌みたまふ方なりけり」 |
「そうですわ。普通は、お避けになる方角でありますよ」 |
「そう、いつも中神は避けることになっているのだ。 |
"Sakasi, rei ha imi tamahu kata nari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.7 | 「 二条の院にも同じ筋にて、いづくにか違へむ。いと悩ましきに」 |
「二条院も同じ方角であるし、どこに方違えをしようか。とても気分が悪いのに」 |
しかし二条の院も同じ方角だから、どこへ行ってよいかわからない。私はもう疲れていて寝てしまいたいのに」 |
"Nideu-no-win ni mo onazi sudi nite, iduku ni ka tagahe m. Ito nayamasiki ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.8 | とて大殿籠もれり。「 いと悪しきことなり」と、これかれ聞こゆ。 |
と言って寝所で横になっていらっしゃる。「大変に具合悪いことです」と、誰彼となく申し上げる。 |
そして源氏は寝室にはいった。 「このままになすってはよろしくございません」 また家従が言って来る。 |
tote ohotono-gomore ri. "Ito asiki koto nari." to, kore-kare kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.9 | 「 紀伊守にて親しく仕うまつる人の、 中川のわたりなる家なむ ★、このころ 水せき入れて、涼しき蔭にはべる」と聞こゆ。 |
「紀伊守で親しくお仕えしております者の、中川の辺りにある家が、最近川の水を堰き入れて、涼しい木蔭でございます」と申し上げる。 |
紀伊守で、家従の一人である男の家のことが上申される。 「中川辺でございますがこのごろ新築いたしまして、水などを庭へ引き込んでございまして、そこならばお涼しかろうと思います」 |
"Ki-no-kami nite sitasiku tukaumaturu hito no, Naka-gaha no watari naru ihe nam, kono-koro midu seki-ire te, suzusiki kage ni haberu." to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.10 | 「 いとよかなり。悩ましきに、 牛ながら引き入れつべからむ ★所を」 |
「とても良い考えである。気分が悪いから、牛車のままで入って行かれる所を」 |
「それは非常によい。からだが大儀だから、車のままではいれる所にしたい」 |
"Ito yoka nari. Nayamasiki ni, usi-nagara hiki-ire tu bekara m tokoro wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.11 | とのたまふ。 忍び忍びの御方違へ所は、あまたありぬべけれど、 久しくほど経て渡りたまへるに、方塞げて、ひき違へ他ざまへ と思さむは、いとほしきなるべし。 紀伊守に仰せ言賜へば、 承りながら、退きて、 |
とおっしゃる。内密の方違えのお邸は、たくさんあるに違いないが、長いご無沙汰の後にいらっしゃったのに、方角が悪いからといって、期待を裏切って他へ行ったとお思いになるのは、気の毒だと思われたのであろう。紀伊守に御用を言い付けなさると、お引き受けは致したものの、引き下がって、 |
と源氏は言っていた。隠れた恋人の家は幾つもあるはずであるが、久しぶりに帰ってきて、方角除けにほかの女の所へ行っては夫人に済まぬと思っているらしい。呼び出して泊まりに行くことを紀伊守に言うと、承知はして行ったが、同輩のいる所へ行って、 |
to notamahu. Sinobi-sinobi no ohom-katatagahe-dokoro ha, amata ari nu bekere do, hisasiku hodo he te watari tamahe ru ni, kata hutage te, hiki-tagahe hoka-zama he to obosa m ha, itohosiki naru besi. Ki-no-kami ni ohose-goto tamahe ba, uketamahari nagara, sirizoki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.12 | 「 伊予守の朝臣の家に慎むことはべりて、 女房なむまかり移れるころにて、狭き所にはべれば、 なめげなることやはべらむ」 |
「伊予守の朝臣の家に、慎み事がございまして、女房たちが来ている時なので、狭い家でございますので、失礼に当たる事がありはしないか」 |
「父の伊予守−伊予は太守の国で、官名は介になっているが事実上の長官である−の家のほうにこのごろ障りがありまして、家族たちが私の家へ移って来ているのです。もとから狭い家なんですから失礼がないかと心配です」 |
"Iyo-no-kami-no-asom no ihe ni tutusimu koto haberi te, nyoubau nam makari uture ru koro nite, sebaki tokoro ni habere ba, namege naru koto ya habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.13 | と、下に嘆くを聞きたまひて、 |
と、陰で嘆息しているのをお聞きになって、 |
と迷惑げに言ったことがまた源氏の耳にはいると、 |
to, sita ni nageku wo kiki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.14 | 「 その人近からむなむ、うれしかるべき。女遠き旅寝は、 もの恐ろしき心地すべきを。ただその几帳のうしろに」とのたまへば、 |
「そうした人が近くにいるのが、嬉しいのだ。女気のない旅寝は、何となく不気味な心地がするからね。ちょうどその几帳の後ろに」とおっしゃるので、 |
「そんなふうに人がたくさんいる家がうれしいのだよ、女の人の居所が遠いような所は夜がこわいよ。伊予守の家族のいる部屋の几帳の後ろでいいのだからね」 冗談混じりにまたこう言わせたものである。 |
"Sono hito tikakara m nam, uresikaru beki. Womna tohoki tabine ha, mono-osorosiki kokoti su beki wo! Tada sono kityau no usiro ni." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.15 | 「 げに、よろしき御座所にも」とて、 人走らせやる。いと忍びて、 ことさらにことことしからぬ所をと、急ぎ出でたまへば、 大臣にも聞こえたまはず、 御供にも睦ましき限りしておはしましぬ。 |
「なるほど、適当なご座所で」と言って、使いの者を走らせる。とてもこっそりと、格別に大げさでない所をと、急いでお出になるので、左大臣殿にもご挨拶なさらず、お供にも親しい者ばかり連れておいでになった。 |
「よいお泊まり所になればよろしいが」 と言って、紀伊守は召使を家へ走らせた。源氏は微行で移りたかったので、まもなく出かけるのに大臣へも告げず、親しい家従だけをつれて行った。 |
"Geni, yorosiki o-masi-dokoro ni mo" tote, hito hasirase yaru. Ito sinobi te, kotosara ni koto-kotosikara nu tokoro wo to, isogi-ide tamahe ba, Otodo ni mo kikoye tamaha zu, ohom-tomo ni mo mutumasiki kagiri site ohasimasi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 紀伊守邸への方違へ |
3-2 Genji goes to Ki-no-Kami's villa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 「 にはかに」とわぶれど、 人も聞き入れず。寝殿の東面払ひあけさせて、かりそめの御しつらひしたり。水の心ばへなど、さる方にをかしくしなしたり。 田舎家だつ柴垣して、 前栽など心とめて植ゑたり。風涼しくて、そこはかとなき虫の声々聞こえ、蛍しげく飛びまがひて、をかしきほどなり。 |
「あまりに急なことで」と迷惑がるが、誰も聞き入れない。寝殿の東面をきれいに片づけさせて、急拵えのご座所を設けた。遣水の趣向などは、それなりに趣深く作ってある。田舎家風の柴垣を廻らして、前栽など気を配って植えてある。風が涼しく吹いて、どこからともない微かな虫の声々が聞こえ、蛍がたくさん飛び交って、趣のある有様である。 |
あまりに急だと言って紀伊守がこぼすのを他の家従たちは耳に入れないで、寝殿の東向きの座敷を掃除させて主人へ提供させ、そこに宿泊の仕度ができた。庭に通した水の流れなどが地方官級の家としては凝ってできた住宅である。わざと田舎の家らしい柴垣が作ってあったりして、庭の植え込みなどもよくできていた。涼しい風が吹いて、どこでともなく虫が鳴き、蛍がたくさん飛んでいた。 |
"Nihaka ni" to wabure do, hito mo kiki-ire zu. Sinden no himgasi-omote harahi ake sase te, karisome no ohom-siturahi si tari. Midu no kokoro-bahe nado, saru kata ni wokasiku si-nasi tari. Winaka-ihe-datu sibagaki si te, sensai nado kokoro tome te uwe tari. Kaze suzusiku te, sokohakatonaki musi no kowe-gowe kikoye, hotaru sigeku tobi-magahi te, wokasiki hodo nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 人びと、渡殿より出でたる泉にのぞきゐて、酒呑む。 主人も肴求むと、こゆるぎのいそぎありくほど、君は ★のどやかに眺めたまひて、 かの、中の品に 取り出でて言ひし、 この並ならむかしと思し出づ。 |
供人たちは、渡殿の下から湧き出ている泉に臨んで座って、酒を飲む。主人の紀伊守もご馳走の準備に走り回っている間、源氏の君はゆったりとお眺めになって、あの人たちが、中の品の例に挙げていたのは、きっとこういう程度の家の女性なのだろう、とお思い出しになる。 |
源氏の従者たちは渡殿の下をくぐって出て来る水の流れに臨んで酒を飲んでいた。紀伊守が主人をよりよく待遇するために奔走している時、一人でいた源氏は、家の中をながめて、前夜の人たちが階級を三つに分けたその中の品の列にはいる家であろうと思い、その話を思い出していた。 |
Hito-bito, wata-dono yori ide taru idumi ni nozoki wi te, sake nomu. Aruzi mo sakana motomu to, koyurugi no isogi ariku hodo, Kimi ha nodoyaka ni nagame tamahi te, kano, naka-no-sina ni tori-ide te ihi si, kono nami nara m kasi to obosi-idu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | 思ひ上がれる気色に聞きおきたまへる女なれば、ゆかしくて耳とどめたまへるに、 この西面にぞ人のけはひする。 衣の音なひはらはらとして、 若き声どもにくからず。 さすがに忍びて、笑ひなどする けはひ、 ことさらびたり。 格子を上げたりけれど、守、「 心なし」とむつかりて下しつれば、火灯したる透影、 障子の上より漏りたるに、やをら寄りたまひて、「 見ゆや」と思せど、隙もなければ、しばし聞きたまふに、 この近き母屋に集ひゐたるなるべし、 うちささめき言ふことどもを聞きたまへば、 わが御上なるべし。 |
高い望みをもっていたようにお耳になさっていた女性なので、どのような女性かと知りたくて耳を澄ましていらっしゃると、この寝殿の西面に人のいる様子がする。衣ずれの音がさらさらとして、若い女性の声々が愛らしい。そうは言っても小声で、笑ったりなどする様子は、わざとらしい。格子を上げてあったが、紀伊守が、「不用意な」と小言を言って下ろしてしまったので、火を灯している明りが、襖障子の上から漏れているので、そっとお近寄りになって、「見えるだろうか」とお思いになるが、隙間もないので、少しの間お聞きになっていると、自分に近い方の母屋に集っているのであろう、ひそひそ話している内容をお聞きになると、ご自分の噂話のようである。 |
思い上がった娘だという評判の伊予守の娘、すなわち紀伊守の妹であったから、源氏は初めからそれに興味を持っていて、どの辺の座敷にいるのであろうと物音に耳を立てていると、この座敷の西に続いた部屋で女の衣摺れが聞こえ、若々しい、媚めかしい声で、しかもさすがに声をひそめてものを言ったりしているのに気がついた。わざとらしいが悪い感じもしなかった。初めその前の縁の格子が上げたままになっていたのを、不用意だといって紀伊守がしかって、今は皆戸がおろされてしまったので、その室の灯影が、襖子の隙間から赤くこちらへさしていた。源氏は静かにそこへ寄って行って中が見えるかと思ったが、それほどの隙間はない。しばらく立って聞いていると、それは襖子の向こうの中央の間に集まってしているらしい低いさざめきは、源氏自身が話題にされているらしい。 |
Omohi-agare ru kesiki ni kiki-oki tamahe ru musume nare ba, yukasiku te mimi todome tamahe ru ni, kono nisi-omote ni zo hito no kehahi suru. Kinu no otonahi hara-hara to si te, wakaki kowe-domo nikukara zu. Sasuga ni sinobi te, warahi nado suru kehahi, kotosarabi tari. Kausi wo age tari kere do, Kami, "Kokoro-nasi" to mutukari te orosi ture ba, hi tomosi taru suki-kage, syauzi no kami yori mori taru ni, yawora yori tamahi te, "Miyu ya?" to obose do, hima mo nakere ba, sibasi kiki tamahu ni, kono tikaki moya ni tudohi wi taru naru besi, uti-sasameki ihu koto-domo wo kiki tamahe ba, waga ohom-uhe naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 | 「 いといたうまめだちて。まだきに、やむごとなきよすが 定まりたまへるこそ、さうざうしかめれ」 |
「とてもたいそう真面目ぶって。まだお若いのに、高貴な北の方が定まっていらっしゃるとは、なんとつまらないのでしょう」 |
「まじめらしく早く奥様をお持ちになったのですからお寂しいわけですわね。 |
"Ito itau mame-dati te. Madaki ni, yamgotonaki yosuga sadamari tamahe ru koso, sau-zausika' mere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.5 | 「されど、さるべき隈には、 よくこそ、隠れ歩きたまふなれ」 |
「でも、人の知らない所では、うまくもまあ、隠れて通っていらっしゃるということですよ」 |
でもずいぶん隠れてお通いになる所があるんですって」 |
"Saredo, saru-beki kuma ni ha, yoku koso, kakure-ariki tamahu nare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.6 | など言ふにも、 思すことのみ心にかかりたまへば、まづ胸つぶれて、「 かやうのついでにも、 人の言ひ漏らさむを、 聞きつけたらむ時」などおぼえたまふ。 |
などと噂しているのにつけても、胸の内にあることばかりが気にかかっていらっしゃるので、まっさきにどきりとして、「このような噂話の折にも、人が言い漏らすようなことを、人が聞きつけるような事が起こったら」などとご心配なさる。 |
こんな言葉にも源氏ははっとした。自分の作っているあるまじい恋を人が知って、こうした場合に何とか言われていたらどうだろうと思ったのである。 |
nado ihu ni mo, obosu koto nomi kokoro ni kakari tamahe ba, madu, mune tubure te, "Kayau no tuide ni mo, hito no ihi-morasa m wo, kiki-tuke tara m toki." nado oboye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.7 | ことなることなければ、聞きさしたまひつ。 式部卿宮の姫君に朝顔奉りたまひし歌などを、 すこしほほゆがめて語るも聞こゆ。「 くつろぎがましく、 歌誦じがちにもあるかな、 なほ見劣りはしなむかし」と思す。 |
別段のこともないので、途中まで聞いてお止めになった。式部卿宮の姫君に、朝顔の花を差し上げなさった時の和歌などを、少し文句を違えて語るのが聞こえる。「ゆったりと和歌を口にすることよ、やはり見劣りすることだろう」とお思いになる。 |
でも話はただ事ばかりであったから皆を聞こうとするほどの興味が起こらなかった。式部卿の宮の姫君に朝顔を贈った時の歌などを、だれかが得意そうに語ってもいた。行儀がなくて、会話の中に節をつけて歌を入れたがる人たちだ、中の品がおもしろいといっても自分には我慢のできぬこともあるだろうと源氏は思った。 |
Kotonaru koto nakere ba, kiki-sasi tamahi tu. Sikibukyau-no-Miya-no-Hime-Gimi ni asagaho tatematuri tamahi si uta nado wo, sukosi hoho-yugame te kataru mo kikoyu. "Kuturogi-gamasiku, uta zun-zi-gati ni mo aru kana! Naho mi-otori ha si na m kasi." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.8 | 守出で来て、灯籠掛け添へ、灯明くかかげなどして、 御くだものばかり参れり。 |
紀伊守が出て来て、灯籠を掛け添え、灯火を明るく掻き立てたりして、お菓子ぐらいのものを差し上げた。 |
紀伊守が出て来て、灯籠の数をふやさせたり、座敷の灯を明るくしたりしてから、主人には遠慮をして菓子だけを献じた。 |
Kami ide-ki te, touro kake sohe, hi akaku kakage nado si te, ohom-kudamono bakari mawire ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.9 | 「 とばり帳も、いかにぞは ★。 さる方の心もとなくては、めざましき饗応ならむ」とのたまへば、 |
「帷帳の準備も、いかがなっておるか。そうした方面の趣向もなくては、興醒めなもてなしであろう」とおっしゃると、 |
「わが家はとばり帳をも掛けたればって歌ね、大君来ませ婿にせんってね、そこへ気がつかないでは主人の手落ちかもしれない」 |
"Tobari tyau mo, ika-ni-zo ha? Saru kata no kokoro-motonaku te ha, mezamasiki aruzi nara m." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.10 | 「 何よけむとも、えうけたまはらず」と、かしこまりてさぶらふ。端つ方の御座に、仮なるやうにて大殿籠もれば、人びとも静まりぬ。 |
「はて、何がお気に召しますやら、わかりませんので」と、恐縮して控えている。端の方のご座所に、うたた寝といったふうに横におなりになると、供人たちも静かになった。 |
「通人でない主人でございまして、どうも」 紀伊守は縁側でかしこまっていた。源氏は縁に近い寝床で、仮臥のように横になっていた。随行者たちももう寝たようである。 |
"Nani yoke m to mo, e uketamahara zu." to, kasikomari te saburahu. Hasi-tu-kata no o-masi ni, kari naru yau nite, ohotono-gomore ba, hito-bito mo sidumari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.11 | 主人の子ども、をかしげにてあり。 童なる、殿上のほどに御覧じ馴れたるもあり。 伊予介の子もあり。あまたある中に、いとけはひあてはかにて、 十二、三ばかりなるもあり。 |
主人の子供たちが、かわいらしい様子をしている。その子供で、童殿上している間に見慣れていらっしゃっるのもいる。伊予介の子もいる。大勢いる中で、とても感じが上品で、十二、三歳くらいになるのもいる。 |
紀伊守は愛らしい子供を幾人も持っていた。御所の侍童を勤めて源氏の知った顔もある。縁側などを往来する中には伊予守の子もあった。何人かの中に特別に上品な十二、三の子もある。 |
Aruzi no kodomo, wokasige ni te ari. Waraha naru, tenzyau no hodo ni go-ran-zi nare taru mo ari. Iyo-no-suke-no-ko mo ari. Amata aru naka ni, ito kehahi atehaka ni te, zihu-ni, sam bakari naru mo ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.12 | 「 いづれかいづれ」など問ひたまふに、 |
「どの子が誰の子か」などと、お尋ねになると、 |
どれが子で、どれが弟かなどと源氏は尋ねていた。 |
"Idure ka idure?" nado tohi tamahu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.13 | 「 これは、 故衛門督の末の子にて、いとかなしくしはべりけるを、幼きほどに後れはべりて、 姉なる人のよすがに、かくてはべるなり。才などもつきはべりぬべく、けしうははべらぬを、殿上なども思ひたまへかけながら、すがすがしうは え交じらひはべらざめる」 と申す。 |
「この子は、故衛門督の末っ子で、大変にかわいがっておりましたが、まだ幼いうちに親に先立たれまして、姉につながる縁で、こうしてここにいるわけでございます。学問などもできそうで、悪くはございませんが、童殿上なども考えておりますが、すらすらとはできませんようで」と申し上げる。 |
「ただ今通りました子は、亡くなりました衛門督の末の息子で、かわいがられていたのですが、小さいうちに父親に別れまして、姉の縁でこうして私の家にいるのでございます。将来のためにもなりますから、御所の侍童を勤めさせたいようですが、それも姉の手だけでははかばかしく運ばないのでございましょう」 と紀伊守が説明した。 |
"Kore ha, ko-Emon-no-kami no suwe no ko ni te, ito kanasiku si haberi keru wo, wosanaki hodo ni okure haberi te, Ane-naru-hito no yosuga ni, kakute haberu nari. Zae nado mo tuki haberi nu beku, kesiu ha habera nu wo, tenzyau nado mo omohi tamahe kake nagara, suga-sugasiu ha e mazirahi habera za' meru." to mausu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.14 | 「 あはれのことや。この姉君や、まうとの後の親」 |
「気の毒なことだ。この子の姉君が、そなたの継母か」 |
「あの子の姉さんが君の継母なんだね」 |
"Ahare no koto ya! Kono Ane-gimi ya, mauto no noti no oya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.15 | 「 さなむはべる」と申すに、 |
「さようでございます」と申し上げると、 |
「そうでございます」 |
"Sa nam haberu." to mausu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.16 | 「 似げなき親をも、まうけたりけるかな。主上にも聞こし召しおきて、『 宮仕へに出だし立てむと漏らし奏せし、いかになりにけむ』と、いつぞやのたまはせし。 世こそ定めなきものなれ」と、 いとおよすけのたまふ。 |
「年に似合わない継母を、持ったことだなあ。主上におかれてもお耳にお忘れにならず、『宮仕えに差し上げたいと、ちらと奏上したことは、その後どうなったのか』と、いつであったか仰せられた。人の世とは無常なものだ」と、とても大人びておっしゃる。 |
「似つかわしくないお母さんを持ったものだね。その人のことは陛下もお聞きになっていらっしって、宮仕えに出したいと衛門督が申していたが、その娘はどうなったのだろうって、いつかお言葉があった。人生はだれがどうなるかわからないものだね」 老成者らしい口ぶりである。 |
"Nigenaki oya wo mo, mauke tari keru kana! Uhe ni mo kikosimesi-oki te, 'Miyadukahe ni idasi-tate m to morasi souse si, ika ni nari ni kem?' to, ituzoya notamahase si. Yo koso sadame naki mono nare." to, ito oyosuke notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.17 | 「 不意に、かくてものしはべるなり。世の中といふもの、 さのみこそ、今も昔も、定まりたることはべらね。中についても、女の宿世は 浮かびたるなむ、あはれにはべる」など 聞こえさす。 |
「思いがけず、こうしているのでございます。男女の仲と言うものは、所詮、そのようなものばかりで、今も昔も、どうなるか分からないものでございます。中でも、女の運命は定めないのが、哀れでございます」などと申し上げて途中で止める。 |
「不意にそうなったのでございます。まあ人というものは昔も今も意外なふうにも変わってゆくものですが、その中でも女の運命ほどはかないものはございません」 などと紀伊守は言っていた。 |
"Hui ni, kakute monosi haberu nari. Yononaka to ihu mono, sa nomi koso, ima mo mukasi mo, sadamari taru koto habera ne. Naka ni tui te mo, womna no sukuse ha ukabi taru nam, ahare ni haberu." nado kikoye sasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.18 | 「 伊予介は、かしづくや。君と思ふらむな」 |
「伊予介は、大事にしているか。主君と思っているだろうな」 |
「伊予介は大事にするだろう。主君のように思うだろうな」 |
"Iyo-no-suke ha, kasiduku ya? Kimi to omohu ram na." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.19 | 「 いかがは。 私の主とこそは思ひてはべるめるを、好き好きしきことと、 なにがしよりはじめて、 うけひきはべらずなむ」と申す。 |
「どう致しまして。内々の主君として世話しておりますようですが、好色がましいことだと、わたくしめをはじめとして、納得できないほどでございます」などと申し上げる。 |
「さあ。まあ私生活の主君でございますかな。好色すぎると私はじめ兄弟はにがにがしがっております」 |
"Ikaga ha? Watakusi no syuu to koso ha omohi te haberu meru wo, suki-zukisiki koto to, nanigasi yori hazime te, uke-hiki habera zu nam." to mausu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.20 | 「 さりとも、まうとたちのつきづきしく今めき たらむに、 おろしたてむやは。 かの介は、いとよしありて気色ばめるをや」など、物語したまひて、 |
「そうは言っても、そなたたちのような年に相応しく当世風の人に、譲るであろうか。あの伊予介は、なかなか風流心があって、気取っているからな」などと、お話なさって、 |
「だって君などのような当世男に伊予介は譲ってくれないだろう。あれはなかなか年は寄ってもりっぱな風采を持っているのだからね」 などと話しながら、 |
"Saritomo, mauto-tati no tuki-dukisiku imameki tara m ni, orosi-tate m ya ha? Kano Suke ha, ito yosi ari te kesikibame ru wo ya!" nado, monogatari si tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.21 | 「 いづかたにぞ」 |
「で、どこに」 |
「その人どちらにいるの」 |
"Idu-kata ni zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.22 | 「 皆、下屋に おろしはべりぬるを、 えやまかりおりあへざらむ」と聞こゆ。 |
「皆、下屋に下がらせましたが、まだ下がりきらないで残っているかも知れません」と申し上げる。 |
「皆下屋のほうへやってしまったのですが、間にあいませんで一部分だけは残っているかもしれません」 と紀伊守は言った。 |
"Mina, simoya ni orosi haberi nuru wo, e ya makari ori-ahe zara m." to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.23 | 酔ひすすみて、皆人びと簀子に臥しつつ、静まりぬ。 |
酔いが回って、供人は皆は簀子にそれぞれ横になって、寝静まってしまった。 |
Wehi susumi te, mina hito-bito sunoko ni husi tutu, sidumari nu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 空蝉の寝所に忍び込む |
3-3 Genji creeps into Utsusemi's bedroom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 君は、 とけても寝られたまはず、 いたづら臥しと思さるるに御目覚めて、この北の障子のあなたに人のけはひするを、「 こなたや、かくいふ人の隠れたる方ならむ、あはれや」と御心とどめて、やをら起きて 立ち聞きたまへば、ありつる子の声にて、 |
源氏の君は、気を落ち着けてお寝みにもなれず、空しい一人寝だと思われるとお目も冴えて、この北の襖障子の向こう側に人のいる様子がするので、「ここが、話に出た女が隠れている所であろうか、かわいそうな」とご関心をもって、静かに起き上がって立ち聞きなさると、先程の子供の声で、 |
深く酔った家従たちは皆夏の夜を板敷で仮寝してしまったのであるが、源氏は眠れない、一人臥をしていると思うと目がさめがちであった。この室の北側の襖子の向こうに人のいるらしい音のする所は紀伊守の話した女のそっとしている室であろうと源氏は思った。かわいそうな女だとその時から思っていたのであったから、静かに起きて行って襖子越しに物声を聞き出そうとした。その弟の声で、 |
Kimi ha, toke te mo nera re tamaha zu, itadura-busi to obosa ruru ni ohom-me same te, kono kita no syauzi no anata ni hito no kehahi suru wo, "konata ya, kaku ihu hito no kakure taru kata nara m, ahare ya!" to mi-kokoro todome te, yawora oki te tati-kiki tamahe ba, arituru ko no kowe ni te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 「 ものけたまはる。いづくにおはしますぞ」 |
「もしもし。どこにいらっしゃいますか」 |
「ちょいと、どこにいらっしゃるの」 |
"Mono'ke-tamaharu. Iduku ni ohasimasu zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | と、 かれたる声のをかしきにて言へば、 |
と、かすれた声で、かわいらしく言うと、 |
と言う。少し涸れたきれいな声である。 |
to, kare taru kowe no wokasiki ni te ihe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | 「 ここにぞ臥したる。 客人は寝たまひぬるか。 いかに近からむと思ひつるを、されど、 け遠かりけり」 |
「ここに臥せっています。お客様はお寝みになりましたか。どんなにお近かろうかと心配していましたが、でも、遠そうだわね」 |
「私はここで寝んでいるの。お客様はお寝みになったの。ここと近くてどんなに困るかと思っていたけれど、まあ安心した」 |
"Koko ni zo husi taru. Marauto ha ne tamahi nuru ka? Ikani tikakara m to omohi turu wo, saredo ke-dohokari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | と言ふ。寝たりける 声のしどけなき、いとよく似通ひたれば、 いもうとと聞きたまひつ。 |
と言う。寝ていた声で取り繕わないのが、とてもよく似ていたので、その姉だなとお聞きになった。 |
と、寝床から言う声もよく似ているので姉弟であることがわかった。 |
to ihu. Ne tari keru kowe no sidokenaki, ito yoku ni-kayohi tare ba, imouto to kiki tamahi tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 「 廂にぞ大殿籠もりぬる。音に聞きつる御ありさまを 見たてまつりつる、 げにこそめでたかりけれ」と、みそかに言ふ。 |
「廂の間にお寝みになりました。噂に聞いていたお姿を拝見いたしましたが、噂通りにご立派でしたよ」と、ひそひそ声で言う。 |
「廂の室でお寝みになりましたよ。評判のお顔を見ましたよ。ほんとうにお美しい方だった」 一段声を低くして言っている。 |
"Hisasi ni zo ohotono-gomori nuru. Oto ni kiki turu ohom-arisama wo mi tatematuri turu, geni koso medetakari kere!" to, misoka ni ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.7 | 「 昼ならましかば、覗きて見たてまつりてまし」 |
「昼間であったら、覗いて拝見できるのにね」 |
「昼だったら私ものぞくのだけれど」 |
"Hiru nara masika ba, nozoki te mi tatematuri te masi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8 | とねぶたげに言ひて、顔ひき入れつる声す。「 ねたう、心とどめても問ひ聞けかし」とあぢきなく思す。 |
と眠そうに言って、顔を衾に引き入れた声がする。「惜しいな、気を入れてもっと聞いていろよ」と残念にお思いになる。 |
睡むそうに言って、その顔は蒲団の中へ引き入れたらしい。もう少し熱心に聞けばよいのにと源氏は物足りない。 |
to nebutage ni ihi te, kaho hiki-ire turu kowe su. "Netau, kokoro todome te mo tohi kike kasi." to adikinaku obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.9 | 「 まろは端に寝はべらむ。あなくるし」 |
「わたしは、端に寝ましょう。ああ、疲れた」 |
「私は縁の近くのほうへ行って寝ます。暗いなあ」 |
"Maro ha hasi ni ne habera m. Ana kurusi!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.10 | とて、 灯かかげなどすべし。女君は、ただこの障子口筋交ひたる ほどにぞ臥したるべき。 |
と言って、灯心を引き出したりしているのであろう。女君は、ちょうどこの襖障子口の斜め向こう側に臥しているのであろう。 |
子供は燈心を掻き立てたりするものらしかった。女は襖子の所からすぐ斜いにあたる辺で寝ているらしい。 |
tote, hi kakage nado su besi. Womna-Gimi ha, tada kono syauzi-guti sudikahi taru hodo ni zo husi taru beki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.11 | 「 中将の君は いづくにぞ。人げ遠き心地して、もの恐ろし」 |
「中将の君はどこですか。誰もいないような感じで、何となく恐い」 |
「中将はどこへ行ったの。今夜は人がそばにいてくれないと何だか心細い気がする」 |
"Tyuuzyau-no-Kimi ha, iduku ni zo? Hitoge tohoki kokoti si te, mono-osorosi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.12 | と 言ふなれば、長押の下に、人びと臥して 答へすなり。 |
と言うらしい、すると、長押の下の方で、女房たちは臥したまま答えているらしい。 |
低い下の室のほうから、女房が、 |
to ihu nare ba, nagesi no simo ni, hito-bito husi te irahe su nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.13 | 「 下に湯におりて。『ただ今参らむ』とはべる」と言ふ。 |
「下屋に、お湯を使いに下りていますが。『すぐに参ります』とのことでございます」と言う。 |
「あの人ちょうどお湯にはいりに参りまして、すぐ参ると申しました」 と言っていた。 |
"Simo ni yu ni ori te. 'Tada-ima mawira m' to haberu." to ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.14 | 皆静まりたるけはひなれば、掛金を試みに 引きあけたまへれば、 あなたよりは鎖さざりけり。几帳を障子口には立てて、 灯はほの暗きに、見たまへば唐櫃だつ物どもを置きたれば、乱りがはしき中を、分け入りたまへれば、ただ一人いとささやかにて臥したり。 なまわづらはしけれど、上なる衣押しやるまで、 求めつる人と思へり。 |
皆寝静まった様子なので、掛金を試しに開けて御覧になると、向こう側からは鎖してないのであった。几帳を襖障子口に立てて、灯火はほの暗いが、御覧になると唐櫃のような物どもを置いてあるので、ごたごたした中を、掻き分けて入ってお行きになると、ただ一人だけでとても小柄な感じで臥せっていた。何となく煩わしく感じるが、上に掛けてある衣を押しのけるまで、呼んでいた女房だと思っていた。 |
源氏はその女房たちも皆寝静まったころに、掛鉄をはずして引いてみると襖子はさっとあいた。向こう側には掛鉄がなかったわけである。そのきわに几帳が立ててあった。ほのかな灯の明りで衣服箱などがごたごたと置かれてあるのが見える。源氏はその中を分けるようにして歩いて行った。 小さな形で女が一人寝ていた。やましく思いながら顔を掩うた着物を源氏が手で引きのけるまで女は、さっき呼んだ女房の中将が来たのだと思っていた。 |
Mina sidumari taru kehahi nare ba, kake-gane wo kokoromi ni hiki-ake tamahe re ba, anata yori ha sasa zari keri. Kityau wo syauzi-guti ni ha tate te, hi ha hono-kuraki ni, mi tamahe ba, karabitu-datu mono-domo wo oki tare ba, midari-gahasiki naka wo, wake-iri tamahe re ba, tada hitori ito sasayaka ni te husi tari. Nama-wadurahasi kere do, uhe naru kinu osi-yaru made, motome turu hito to omohe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.15 | 「 中将召しつればなむ。人知れぬ思ひの、しるしある心地して」 |
「中将をお呼びでしたので。人知れずお慕いしておりました、その甲斐があった気がしまして」 |
「あなたが中将を呼んでいらっしゃったから、私の思いが通じたのだと思って」 |
"Tyuuzyau mesi ture ba nam. Hito sire nu omohi no, sirusi aru kokoti si te." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.16 | とのたまふを、ともかくも思ひ分かれず、物に襲はるる心地して、「や」とおびゆれど、 顔に衣のさはりて、音にも立てず。 |
とおっしゃるのを、すぐにはどういうことかも分からず、魔物にでも襲われたような気がして、「きゃっ」と脅えたが、顔に衣が触れて、声にもならない。 |
と源氏の宰相中将は言いかけたが、女は恐ろしがって、夢に襲われているようなふうである。「や」と言うつもりがあるが、顔に夜着がさわって声にはならなかった。 |
to notamahu wo, tomo-kakumo omohi-waka re zu, mono ni osoha ruru kokoti si te, "Ya!" to obiyure do, kaho ni kinu no sahari te, oto ni mo tate zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.17 | 「 うちつけに、深からぬ心のほどと 見たまふらむ、ことわりなれど、 年ごろ思ひわたる心のうちも、 聞こえ知らせむとてなむ。かかるをりを待ち出でたるも、 さらに浅くはあらじと、思ひなしたまへ」 |
「突然のことで、一時の戯れ心とお思いになるのも、ごもっともですが、長年、恋い慕っていましたわたしの気持ちを、聞いていただきたいと思いまして。このような機会を待ち受けていたのも、決していい加減な気持ちからではない深い前世からの縁と、お思いになって下さい」 |
「出来心のようにあなたは思うでしょう。もっともだけれど、私はそうじゃないのですよ。ずっと前からあなたを思っていたのです。それを聞いていただきたいのでこんな機会を待っていたのです。だからすべて皆前生の縁が導くのだと思ってください」 |
"Utituke ni, hukakara nu kokoro no hodo to mi tamahu ram, kotowari nare do, tosigoro omohi wataru kokoro no uti mo, kikoye sira se m tote nam. Kakaru wori wo mati-ide taru mo, sarani asaku ha ara zi to, omohi-nasi tamahe!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.18 | と、いとやはらかにのたまひて、 鬼神も荒だつまじきけはひなれば、はしたなく、「ここに、人」とも、 えののしらず。心地はた、 わびしく、 あるまじきことと思へば、あさましく、 |
と、とても優しくおっしゃって、鬼神さえも手荒なことはできないような態度なので、ぶしつけに「ここに、変な人が」とも、大声が出せない。気分は辛く、あってはならない事だと思うと、情けなくなって、 |
柔らかい調子である。神様だってこの人には寛大であらねばならぬだろうと思われる美しさで近づいているのであるから、露骨に、 「知らぬ人がこんな所へ」 ともののしることができない。 しかも女は情けなくてならないのである。 |
to, ito yaharaka ni notamahi te, oni-gami mo aradatu maziki kehahi nare ba, hasitanaku, "Koko ni, hito!" to mo, e nonosira zu. Kokoti hata , wabisiku, arumaziki koto to omohe ba, asamasiku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.19 | 「 人違へにこそはべるめれ」と言ふも息の下なり。 |
「お人違いでございましょう」と言うのもやっとである。 |
「人まちがえでいらっしゃるのでしょう」 やっと、息よりも低い声で言った。 |
"Hito-tagahe ni koso haberu mere." to ihu mo iki no sita nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.20 | 消えまどへる気色、いと心苦しくらうたげなれば、をかしと見たまひて、 |
消え入らんばかりにとり乱した様子は、まことにいたいたしく可憐なので、いい女だと御覧になって、 |
当惑しきった様子が柔らかい感じであり、可憐でもあった。 |
Kiye madohe ru kesiki, ito kokoro-gurusiku rautage nare ba, wokasi to mi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.21 | 「 違ふべくもあらぬ 心のしるべを、 思はずにもおぼめいたまふかな。好きがましきさまには、 よに見えたてまつらじ。思ふことすこし 聞こゆべきぞ」 |
「間違えるはずもない心の導きを、意外にも理解しても下さらずはぐらかしなさいますね。好色めいた振る舞いは、決して致しません。気持ちを少し申し上げたいのです」 |
「違うわけがないじゃありませんか。恋する人の直覚であなただと思って来たのに、あなたは知らぬ顔をなさるのだ。普通の好色者がするような失礼を私はしません。少しだけ私の心を聞いていただけばそれでよいのです」 |
"Tagahu beku mo ara nu kokoro no sirube wo, omoha zu ni mo obomei tamahu kana! Suki-gamasiki sama ni ha, yoni miye tatematura zi. Omohu koto sukosi kikoyu beki zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.22 | とて、 いと小さやかなれば、かき抱きて 障子のもと出でたまふにぞ、求めつる中将だつ人来あひたる。 |
と言って、とても小柄なので、抱き上げて襖障子までお出になるところへ、呼んでいた中将らしい女房が来合わせた。 |
と言って、小柄な人であったから、片手で抱いて以前の襖子の所へ出て来ると、さっき呼ばれていた中将らしい女房が向こうから来た。 |
tote, ito tihisayaka nare ba, kaki-idaki te syauzi no moto ide tamahu ni zo, motome turu Tyuuzyau-datu-hito ki-ahi taru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.23 | 「 やや」とのたまふに、 あやしくて探り寄りたるにぞ、いみじく匂ひみちて、顔にもくゆりかかる心地するに、 思ひ寄りぬ。あさましう、 こはいかなることぞと思ひまどはるれど、聞こえむ方なし。 並々の人ならばこそ、荒らかにも引きかなぐらめ、 それだに人のあまた知らむは、いかがあらむ。心も騷ぎて、慕ひ来たれど、 動もなくて、 奥なる御座に入りたまひぬ。 |
「これ、これ」とおっしゃると、不審に思って手探りで近づいたところ、大変に薫物の香があたり一面に匂っていて、顔にまで匂いかかって来るような感じがするので、理解がついた。意外なことで、これはどうしたことかと、おろおろしないではいられないが、何とも申し上げようもない。普通の男ならば、手荒に引き放すこともしようが、それでさえ大勢の人が知ったらどうであろうか。胸がどきどきして、後からついて来たが、平然として、奥のご座所にお入りになった。 |
「ちょいと」 と源氏が言ったので、不思議がって探り寄って来る時に、薫き込めた源氏の衣服の香が顔に吹き寄ってきた。中将は、これがだれであるかも、何であるかもわかった。情けなくて、どうなることかと心配でならないが、何とも異論のはさみようがない。並み並みの男であったならできるだけの力の抵抗もしてみるはずであるが、しかもそれだって荒だてて多数の人に知らせることは夫人の不名誉になることであって、しないほうがよいのかもしれない。こう思って胸をとどろかせながら従ってきたが、源氏の中将はこの中将をまったく無視していた。初めの座敷へ抱いて行って女をおろして、 |
"Ya ya!" to notamahu ni, ayasiku te saguri yori taru ni zo, imiziku nihohi miti te, kaho ni mo kuyuri kakaru kokoti suru ni, omohi-yori nu. Asamasiu, ko ha ika naru koto zo to omohi madoha rure do, kikoye m kata nasi. Nami-nami no hito nara ba koso, araraka ni mo hiki-kanagura me, sore dani hito no amata sira m ha, ikaga ara m? Kokoro mo sawagi te, sitahi-ki tare do, dou mo naku te, oku naru o-masi ni iri tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.24 | 障子をひきたてて、「 暁に御迎へにものせよ」とのたまへば、 女は、この人の思ふらむことさへ、死ぬばかりわりなきに、流るるまで汗になりて、 いと悩ましげなる、いとほしけれど、 例の、いづこより取う出たまふ言の葉にかあらむ、あはれ知らるばかり、情け情けしくのたまひ尽くすべかめれど、 なほいとあさましきに、 |
襖障子を引き閉てて、「明朝、お迎えに参られよ」とおっしゃるので、女は、この女房がどう思うかまでが、死ぬほど耐えられないので、流れ出るほどの汗びっしょりになって、とても悩ましい様子でいる、それは、気の毒であるが、例によって、どこから出てくる言葉であろうか、愛情がわかるほどに、優しく優しく、言葉を尽くしておっしゃるようだが、やはりまことに情けないので、 |
それから襖子をしめて、 「夜明けにお迎えに来るがいい」 と言った。中将はどう思うであろうと、女はそれを聞いただけでも死ぬほどの苦痛を味わった。流れるほどの汗になって悩ましそうな女に同情は覚えながら、女に対する例の誠実な調子で、女の心が当然動くはずだと思われるほどに言っても、女は人間の掟に許されていない恋に共鳴してこない。 |
Syauzi wo hiki-tate te, "Akatuki ni ohom-mukahe ni monose yo." to notamahe ba, womna ha, kono hito no omohu ram koto sahe, sinu bakari warinaki ni, nagaruru made ase ni nari te, ito nayamasige naru, ito itohosikere do, rei no, iduko yori tou'de tamahu kotonoha ni ka ara m, ahare sira ru bakari, nasake-nasakesiku notamahi-tukusu beka' mere do, naho ito asamasiki ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.25 | 「 現ともおぼえずこそ。数ならぬ身ながらも、 思しくたしける御心ばへのほども、 いかが浅くは思うたまへざらむ。いと かやうなる際は、際とこそはべなれ」 |
「真実のこととは思われません。しがない身の上ですが、お貶みなさったお気持ちのほどを、どうして浅いお気持ちと存ぜずにいられましょうか。まことに、このような身分の女には、それなりの生き方がございます」 |
「こんな御無理を承ることが現実のことであろうとは思われません。卑しい私ですが、軽蔑してもよいものだというあなたのお心持ちを私は深くお恨みに思います。私たちの階級とあなた様たちの階級とは、遠く離れて別々のものなのです」 |
"Ututu to mo oboye zu koso. Kazu nara nu mi nagara mo, obosi-kutasi keru mi-kokorobahe no hodo mo, ikaga asaku ha omou tamahe zara m. Ito kayau naru kiha ha, kiha to koso habe' nare." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.26 | とて、かくおし立ちたまへるを、深く情けなく憂しと思ひ入りたるさまも、 げにいとほしく、 心恥づかしきけはひなれば、 |
と言って、このように無体なことをなさっているのを、深く思いやりがなく嫌なことだと思い込んでいる様子も、なるほど気の毒で、気後れがするほど立派な態度なので、 |
こう言って、強さで自分を征服しようとしている男を憎いと思う様子は、源氏を十分に反省さす力があった。 |
tote, kaku ositati tamahe ru wo, hukaku nasakenaku usi to omohi-iri taru sama mo, geni itohosiku, kokoro-hadukasiki kehahi nare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.27 | 「 その際々を、まだ知らぬ、 初事ぞや。なかなか、おしなべたる列に思ひなしたまへるなむうたてありける。おのづから聞きたまふやうもあらむ。 あながちなる好き心は、さらにならはぬを。 さるべきにや、げに、かく あはめられたてまつるも、ことわりなる心まどひを、みづからも あやしきまでなむ」 |
「おっしゃる身分身分の違いを、まだ知りません、初めての事ですよ。かえって、わたしを普通の人と同じように思っていらっしゃるのが残念です。自然とお聞きになっているようなこともありましょう。むやみな好色心は、まったく持ち合わせておりませんものを。前世からの因縁でしょうか、おっしゃるように、このように軽蔑されいただくのも、当然なわが惑乱を、自分でも不思議なほどで」 |
「私はまだ女性に階級のあることも何も知らない。はじめての経験なんです。普通の多情な男のようにお取り扱いになるのを恨めしく思います。あなたの耳にも自然はいっているでしょう、むやみな恋の冒険などを私はしたこともありません。それにもかかわらず前生の因縁は大きな力があって、私をあなたに近づけて、そしてあなたからこんなにはずかしめられています。ごもっともだとあなたになって考えれば考えられますが、そんなことをするまでに私はこの恋に盲目になっています」 |
"Sono kiha-giha wo, mada sira nu, uhigoto zo ya! Naka-naka, osinabe taru tura ni omohi-nasi tamahe ru nam utate ari keru. Onodukara kiki tamahu yau mo ara m. Anagati naru suki-gokoro ha, sarani naraha nu wo! Saru-beki ni ya, geni, kaku ahame rare tatematuru mo, kotowari naru kokoro-madohi wo, midukara mo ayasiki made nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.28 | など、まめだちてよろづにのたまへど、 いとたぐひなき御ありさまの、いよいようちとけきこえむことわびしければ、 すくよかに心づきなしとは見えたてまつるとも、 さる方の言ふかひなきにて過ぐしてむと思ひて、 つれなくのみもてなしたり。人柄のたをやぎたるに、強き心をしひて加へたれば、 なよ竹の心地して、さすがに折るべくもあらず。 |
などと、真面目になっていろいろとおっしゃるが、まことに類ないご立派さで、ますます打ち解け申し上げることが辛く思われるので、無愛想な気にくわない女だとお見受け申されようとも、そうしたつまらない女として押し通そうと思って、ただそっけなく身を処していた。人柄がおとなしい性質なところに、無理に気強く張りつめているので、しなやかな竹のような感じがして、さすがにたやすく手折れそうにもない。 |
まじめになっていろいろと源氏は説くが、女の冷ややかな態度は変わっていくけしきもない。女は、一世の美男であればあるほど、この人の恋人になって安んじている自分にはなれない、冷血的な女だと思われてやむのが望みであると考えて、きわめて弱い人が強さをしいてつけているのは弱竹のようで、さすがに折ることはできなかった。 |
nado, mame-dati te yorodu ni notamahe do, ito taguhi naki ohom-arisama no, iyo-iyo uti-toke kikoye m koto wabisikere ba, sukuyoka ni kokoro-dukinasi to ha miye tatematuru tomo, saru kata no ihukahinaki ni te sugusi te m to omohi te, turenaku nomi motenasi tari. Hitogara no tawoyagi taru ni, tuyoki kokoro wo sihite kuhahe tare ba, nayotake no kokoti si te, sasuga ni woru beku mo ara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.29 | まことに心やましくて、 あながちなる御心ばへを、 言ふ方なしと思ひて、泣くさまなど、いとあはれなり ★。 心苦しくはあれど、見ざらましかば口惜しからまし、と思す。 慰めがたく、憂しと思へれば、 |
本当に辛く嫌な思いで、無理無体なお気持ちを、何とも言いようがないと思って、泣いている様子など、まことに哀れである。気の毒ではあるが、逢わなかったら心残りであったろうに、とお思いになる。気持ちの晴らしようもなく、情けないと思っているので、 |
真からあさましいことだと思うふうに泣く様子などが可憐であった。気の毒ではあるがこのままで別れたらのちのちまでも後悔が自分を苦しめるであろうと源氏は思ったのであった。 もうどんなに勝手な考え方をしても救われない過失をしてしまったと、女の悲しんでいるのを見て、 |
Makoto ni kokoro-yamasiku te, anagati naru mi-kokorobahe wo, ihukatanasi to omohi te, naku sama nado, ito ahare nari. Kokoro-gurusiku ha are do, mi zara masika ba kutiwosikara masi, to obosu. Nagusame-gataku, usi to omohe re ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.30 | 「 など、かく 疎ましきものにしも思すべき。おぼえなきさまなるしもこそ、 契りあるとは思ひたまはめ。むげに 世を思ひ知らぬやうに、 おぼほれたまふなむ、いとつらき」と 恨みられて、 |
「どうして、こうお嫌いになるのですか。思いがけない逢瀬こそ、前世からの因縁だとお考えなさい。むやみに男女の仲を知らない者のように、泣いていらっしゃるのが、とても辛い」と、恨み言をいわれて、 |
「なぜそんなに私が憎くばかり思われるのですか。お嬢さんか何かのようにあなたの悲しむのが恨めしい」 と、源氏が言うと、 |
"Nado, kaku utomasiki mono ni simo obosu beki? Oboye naki sama naru simo koso, tigiri aru to ha omohi tamaha me. Mugeni yo wo omohi-sira nu yau ni, obohore tamahu nam, ito turaki." to urami rare te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.31 | 「 いとかく憂き身のほどの定まらぬ、 ▼ ありしながらの身にて、 かかる御心ばへを見ましかば、 あるまじき我が頼みにて、見直したまふ ▼ 後瀬をも 思ひたまへ慰めましを、いとかう仮なる浮き寝のほどを思ひはべるに、 たぐひなく思うたまへ惑はるるなり。 よし、今は見きとなかけそ ★」 |
「とてもこのような情けない身の運命が定まらない、昔のままのわが身で、このようなお気持ちを頂戴したのならば、とんでもない身勝手な希望ですが、愛していただける時もあろううかと存じて慰めましょうに、とてもこのような、一時の仮寝のことを思いますと、どうしようもなく心惑いされてならないのです。たとえ、こうとなりましても、逢ったと言わないで下さいまし」 |
「私の運命がまだ私を人妻にしません時、親の家の娘でございました時に、こうしたあなたの熱情で思われましたのなら、それは私の迷いであっても、他日に光明のあるようなことも思ったでございましょうが、もう何もだめでございます。私には恋も何もいりません。ですからせめてなかったことだと思ってしまってください」 |
"Ito kaku uki mi no hodo no sadamara nu, arisi-nagara no mi ni te, kakaru mi-kokoro-bahe wo mi masika ba, arumaziki waga tanomi ni te, minahosi tamahu notise wo mo omohi tamahe nagusame masi wo, ito kau kari naru ukine no hodo wo omohi haberu ni, taguhi naku omou tamahe madoha ruru nari. Yosi, ima ha mi ki to na kake so." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.32 | とて、思へるさま、 げにいとことわりなり。 おろかならず契り慰めたまふこと多かるべし。 |
と言って、悲しんでいる様子は、いかにも道理である。並々ならず行く末を約束し慰めなさる言葉は、きっと多いことであろう。 |
と言う。悲しみに沈んでいる女を源氏ももっともだと思った。真心から慰めの言葉を発しているのであった。 |
tote, omohe ru sama, geni ito kotowari nari. Oroka nara zu tigiri nagusame tamahu koto ohokaru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.33 | 鶏も鳴きぬ。人びと起き出でて、 |
鶏も鳴いた。供びとが起き出して、 |
鶏の声がしてきた。家従たちも起きて、 |
Tori mo naki nu. Hito-bito oki-ide te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.34 | 「いといぎたなかりける夜かな」 |
「ひどく寝過ごしてしまったなあ」 |
「寝坊をしたものだ。 |
"Ito igitanakari keru yo kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.35 | 「御車ひき出でよ」 |
「お車を引き出せよ」 |
早くお車の用意をせい」 |
"Mi-kuruma hiki-ide yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.36 | など言ふなり。守も出で来て、 |
などと言っているようだ。紀伊守も起き出して来て、 |
そんな命令も下していた。 |
nado ihu nari. Kami mo ide-ki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.37 | 「 女などの御方違へこそ。夜深く 急がせたまふべきかは」など言ふもあり。 |
「女性などの方違えならばともかく。暗いうちからお急きあそばさずとも」などと言っているのも聞こえる。 |
「女の家へ方違えにおいでになった場合とは違いますよ。早くお帰りになる必要は少しもないじゃありませんか」 と言っているのは紀伊守であった。 |
"Womna nado no ohom-katatagahe koso. Yobukaku isoga se tamahu beki kaha!" nado ihu mo ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.38 | 君は、 またかやうのついであらむこともいとかたく、 さしはへては いかでか、御文なども通はむことの いとわりなきを思すに、いと胸いたし。 奥の中将も出でて、いと苦しがれば、 許したまひても、また引きとどめたまひつつ、 |
源氏の君は、再びこのような機会があろうこともとても難しいし、わざわざ訪れることはどうしてできようか、お手紙などもを通わすことはとても無理なことをお思いになると、ひどく胸が痛む。奥にいた中将の君も出て来て、とても困っているので、お放しになっても、再びお引き留めになっては、 |
源氏はもうまたこんな機会が作り出せそうでないことと、今後どうして文通をすればよいか、どうもそれが不可能らしいことで胸を痛くしていた。女を行かせようとしてもまた引き留める源氏であった。 |
Kimi ha, mata kayau no tuide ara m koto mo ito kataku, sasihae te ha ikade ka, ohom-humi nado mo kayoha m koto no ito warinaki wo obosu ni, ito mune itasi. Oku no Tyuuzyau mo ide te, ito kurusigare ba, yurusi tamahi te mo, mata hiki-todome tamahi tutu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.39 | 「いかでか、聞こゆべき。 世に知らぬ 御心のつらさも、あはれも、 浅からぬ世の思ひ出では、さまざまめづらかなるべき例かな」 |
「どのようにして、お便りを差し上げたらよかろうか。ほんとうに何とも言いようのない、あなたのお気持ちの冷たさといい、慕わしさといい、深く刻みこまれた思い出は、いろいろとめったにないことであったね」 |
「どうしてあなたと通信をしたらいいでしょう。あくまで冷淡なあなたへの恨みも、恋も、一通りでない私が、今夜のことだけをいつまでも泣いて思っていなければならないのですか」 |
"Ikade ka, kikoyu beki. Yoni sira nu mi-kokoro no turasa mo, ahare mo, asakara nu yo no omohi-ide ha, sama-zama meduraka naru beki tamesi kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.40 | とて、うち泣きたまふ気色、いとなまめきたり。 |
と言って、お泣きになる様子は、とても優美である。 |
泣いている源氏が非常に艶に見えた。 |
tote, uti-naki tamahu kesiki, ito namameki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.41 | 鶏もしばしば鳴くに、心あわたたしくて、 |
鶏もしきりに鳴くので、気もせかされて、 |
何度も鶏が鳴いた。 |
Tori mo siba-siba naku ni, kokoro awatatasiku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.42 | 「 つれなきを恨みも果てぬしののめに |
「あなたの冷たい態度に恨み言を十分に言わないうちに夜もしらみかけ |
つれなさを恨みもはてぬしののめに |
"Turenaki wo urami mo hate nu sinonome ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.43 | とりあへぬまでおどろかすらむ」 |
鶏までが取るものも取りあえぬまであわただしく鳴いてわたしを起こそうとするのでしょうか」 |
とりあへぬまで驚かすらん |
tori-ahe nu made odorokasu ram |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.44 | 女、身のありさまを思ふに、 いとつきなくまばゆき心地して、めでたき御もてなしも、何ともおぼえず、常はいとすくすくしく心づきなしと思ひあなづる伊予の方の 思ひやられて、「 夢にや見ゆらむ」と、そら恐ろしくつつまし。 |
女は、わが身の上を思うと、まことに不似合いで眩しい気持ちがして、源氏の君の素晴らしいお持てなしも、何とも感ぜず、平生はとても生真面目過ぎて嫌な男だと侮っている伊予国の方角が思いやられて、「夢に現われやしないか」と思うと、何となく恐ろしくて気がひける。 |
あわただしい心持ちで源氏はこうささやいた。 女は己を省みると、不似合いという晴がましさを感ぜずにいられない源氏からどんなに熱情的に思われても、これをうれしいこととすることができないのである。それに自分としては愛情の持てない良人のいる伊予の国が思われて、こんな夢を見てはいないだろうかと考えると恐ろしかった。 |
Womna, mi no arisama wo omohu ni, ito tukinaku mabayuki kokoti si te, medetaki ohom-motenasi mo, nani to mo oboye zu, tune ha ito suku-sukusiku kokorodukinasi to omohi anaduru Iyo no kata no omohi-yara re te, "Yume ni ya miyu ram?" to, sora-osorosiku tutumasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.45 | 「 身の憂さを嘆くにあかで明くる夜は |
「わが身の辛さを嘆いても嘆き足りないうちに明ける夜は |
身の憂さを歎くにあかで明くる夜は |
"Mi no usa wo nageku ni aka de akuru yo ha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.46 | とり重ねてぞ音もなかれける」 |
鶏の鳴く音に取り重ねて、わたしも泣かれてなりません」 |
とり重ねても音ぞ泣かれける |
tori-kasane te zo ne mo naka re keru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
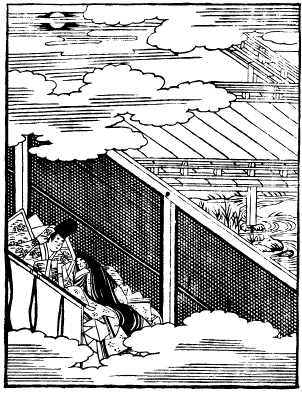 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.47 | ことと明くなれば、障子口まで送りたまふ。内も外も人騒がしければ、 引き立てて、別れたまふほど、心細く、 ▼ 隔つる関と見えたり。 |
ずんずんと明るくなるので、襖障子口までお送りになる。家の内も外も騒がしいので、引き閉てて、お別れになる時、心細い気がして、仲を隔てる関のように思われた。 |
と言った。 ずんずん明るくなってゆく。女は襖子の所へまで送って行った。奥のほうの人も、こちらの縁のほうの人も起き出して来たんでざわついた。襖子をしめてもとの席へ帰って行く源氏は、一重の襖子が越えがたい隔ての関のように思われた。 |
Koto to akaku nare ba, syauzi-guti made okuri tamahu. Uti mo to mo hito sawagasikere ba, hiki-tate te, wakare tamahu hodo, kokorobosoku, hedaturu seki to miye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.48 | 御直衣など着たまひて、 南の高欄にしばしうち眺めたまふ。西面の格子そそき上げて、 人びと覗くべかめる。簀子の中のほどに立てたる小障子の上より仄かに見えたまへる御ありさまを、身にしむばかり思へる 好き心どもあめり。 |
御直衣などをお召しになって、南面の高欄の側で少しの間眺めていらっしゃる。西面の格子を忙しく上げて、女房たちが覗き見しているようである。簀子の中央に立ててある小障子の上から、わずかにお見えになるお姿を、身に感じ入っている好色な女もいるようである。 |
直衣などを着て、姿を整えた源氏が縁側の高欄によりかかっているのが、隣室の縁低い衝立の上のほうから見えるのをのぞいて、源氏の美の放つ光が身の中へしみ通るように思っている女房もあった。 |
Ohom-nahosi nado ki tamahi te, minami no kauran ni sibasi uti-nagame tamahu. Nisi-omote no kausi sosoki-age te, hito-bito nozoku beka' meru. Sunoko no naka no hodo ni tate taru ko-syauzi no kami yori honoka ni miye tamahe ru ohom-arisama wo, mi ni simu bakari omohe ru suki-gokoro-domo a' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.49 | 月は有明にて、光をさまれるものから、 かげけざやかに見えて、なかなかをかしき曙なり。何心なき空のけしきも、ただ見る人から、 艶にもすごくも見ゆるなりけり。人知れぬ御心には、いと胸いたく、 言伝てやらむよすがだになきをと、かへりみがちにて出でたまひぬ。 |
月は有明で、光は弱くなっているとはいうものの、面ははっきりと見えて、かえって趣のある曙の空である。無心なはずの空の様子も、ただ見る人によって、美しくも悲しくも見えるのであった。人に言われぬお心には、とても胸痛く、文を通わす手立てさえないものをと、後ろ髪引かれる思いでお出になった。 |
残月のあるころで落ち着いた空の明かりが物をさわやかに照らしていた。変わったおもしろい夏の曙である。だれも知らぬ物思いを、心に抱いた源氏であるから、主観的にひどく身にしむ夜明けの風景だと思った。言づて一つする便宜がないではないかと思って顧みがちに去った。 |
Tuki ha ariake ni te, hikari wosamare ru monokara, kage kezayaka ni miye te, naka-naka wokasiki akebono nari. Nanigokokoronaki sora no kesiki mo, tada miru hito kara, en ni mo sugoku mo miyuru nari keri. Hito sire nu mi-kokoro ni ha, ito mune itaku, koto-dute yara m yosuga dani naki wo to, kaherimi-gati ni te ide tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50 | 殿に帰りたまひても、とみにも まどろまれたまはず。また あひ見るべき方なきを、 まして、かの人の思ふらむ心の中、いかならむと、心苦しく思ひやりたまふ。「 すぐれたることはなけれど、めやすくもてつけてもありつる中の品かな。 隈なく見集めたる人の言ひしことは、げに」と 思し合はせられけり。 |
お邸にお帰りになっても、すぐにもお寝みになれない。再び逢える手立てのないのが、自分以上に、あの女が悩んでいるであろう心の中は、どんなであろうかと、気の毒にご想像なさる。「特に優れた所はないが、見苦しくなく身嗜みもとりつくろっていた中の品の女であったな。何でもよく知っている人の言ったことは、なるほど」とうなずかれるのであった。 |
家へ帰ってからも源氏はすぐに眠ることができなかった。再会の至難である悲しみだけを自分はしているが、自由な男でない人妻のあの人はこのほかにもいろいろな煩悶があるはずであると思いやっていた。すぐれた女ではないが、感じのよさを十分に備えた中の品だ。だから多くの経験を持った男の言うことには敬服される点があると、品定めの夜の話を思い出していた。 |
Tono ni kaheri tamahi te mo, tomi ni mo madoroma re tamaha zu. Mata ahi-miru beki kata naki wo, masite, kano hito no omohu ram kokoro no uti, ika-nara m to, kokoro-gurusiku omohiyari tamahu. "Sugure taru koto ha nakere do, meyasuku motetuke te mo ari turu naka-no-sina kana! Kumanaku mi atume taru hito no ihi si koto ha, geni." to obosi-ahase rare keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.51 | このほどは 大殿にのみおはします。 なほいとかき絶えて、思ふらむことのいとほしく御心にかかりて、苦しく思しわびて、紀伊守を召したり。 |
最近は左大臣邸にばかりいらっしゃる。やはり、すっかりあれきり途絶えているので、思い悩んでいるであろうことが、気の毒にお心にかかって、心苦しく思い悩みなさって、紀伊守をお召しになった。 |
このごろはずっと左大臣家に源氏はいた。あれきり何とも言ってやらないことは、女の身にとってどんなに苦しいことだろうと中川の女のことがあわれまれて、始終心にかかって苦しいはてに源氏は紀伊守を招いた。 |
Kono hodo ha, Ohoidono ni nomi ohasimasu. Naho ito kaki-taye te, omohu ram koto no itohosiku mi-kokoro ni kakari te, kurusiku obosi-wabi te, Ki-no-Kami wo mesi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.52 | 「 かの、ありし中納言の子は、 得させてむや。 らうたげに見えしを。身近く使ふ人にせむ。主上にも我奉らむ」とのたまへば、 |
「あの、先日の故中納言の子は、わたしに下さらないか。かわいらしげに見えたが。身近に使う者としたい。主上にも、わたしが差し上げたい」とおっしゃると、 |
「自分の手もとへ、この間見た中納言の子供をよこしてくれないか。かわいい子だったからそばで使おうと思う。御所へ出すことも私からしてやろう」 と言うのであった。 |
"Kano, arisi Tyuunagon-no-ko ha, e sase te m ya? Rautage ni miye si wo. Mi-dikaku tukahu hito ni se m. Uhe ni mo ware tatematura m." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.53 | 「 いとかしこき仰せ言にはべるなり。 姉なる人にのたまひみむ」 |
「とても恐れ多いお言葉でございます。姉に当たる人に仰せ言を申し聞かせてみましょう」 |
「結構なことでございます。あの子の姉に相談してみましょう」 |
"Ito kasikoki ohose-goto ni haberu nari. Ane-naru-hito ni notamahi mi m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.54 | と申すも、 胸つぶれて思せど、 |
と、申し上げるにつけても、どきりとなさるが、 |
その人が思わず引き合いに出されたことだけででも源氏の胸は鳴った。 |
to mausu mo, mune tubure te obose do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.55 | 「 その姉君は、朝臣の弟や持たる」 |
「その姉君は、そなたの弟をお持ちか」 |
「その姉さんは君の弟を生んでいるの」 |
"Sono Ane-gimi ha, Asom no otouto ya mo' taru?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.56 | 「 さもはべらず。この二年ばかりぞ、かくてものしはべれど、 親のおきてに違へりと思ひ嘆きて、心ゆかぬやうになむ、 聞きたまふる」 |
「いえ、ございません。この二年ほどは、こうして暮らしておりますが、父親の意向と違ったと嘆いて、気も進まないでいるように、聞いております」 |
「そうでもございません。この二年ほど前から父の妻になっていますが、死んだ父親が望んでいたことでないような結婚をしたと思うのでしょう。不満らしいということでございます」 |
"Sa mo habera zu. Kono huta-tose bakari zo, kaku te monosi habere do, oya no okite ni tagahe ri to omohi nageki te, kokoro-yuka nu yau ni nam, kiki tamahuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.57 | 「 あはれのことや。 よろしく聞こえし人ぞかし。 まことによしや」とのたまへば、 |
「気の毒なことよ。まあまあの評判であった人だ。本当に、器量が良いか」とおっしゃると、 |
「かわいそうだね、評判の娘だったが、ほんとうに美しいのか」 |
"Ahare no koto ya! Yorosiku kikoye si hito zo kasi. Makoto ni yosi ya?" to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.58 | 「 けしうははべらざるべし。もて離れてうとうとしくはべれば、 世のたとひにて、睦びはべらず」と申す。 |
「悪くはございませんでしょう。離れて疎遠に致しておりますので、世間の言い草のとおり、親しくしておりません」と申し上げる。 |
「さあ、悪くもないのでございましょう。年のいった息子と若い継母は親しくせぬものだと申しますから、私はその習慣に従っておりまして何も詳しいことは存じません」 と紀伊守は答えていた。 |
"Kesiu ha habera zaru besi. Mote-hanare te uto-utosiku habere ba, yo no tatohi ni te, mutubi habera zu." to mausu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 第四段 それから数日後 |
3-4 Several days later |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | さて、五六日ありて、 この子率て参れり。こまやかにをかしとはなけれど、 なまめきたるさまして、あて人と見えたり。召し入れて、いとなつかしく語らひたまふ。童心地に、いとめでたくうれしと思ふ。 いもうとの君のことも詳しく問ひたまふ。さるべきことは答へ聞こえなどして、 恥づかしげにしづまりたれば、うち出でにくし。されど、 いとよく言ひ知らせたまふ。 |
そうして、五、六日が過ぎて、この子を連れて参上した。きめこまやかに美しいというのではないが、優美な姿をしていて、良家の子弟と見えた。招き入れて、とても親しくお話をなさる。子供心に、とても素晴らしく嬉しく思う。姉君のことも詳しくお尋ねになる。答えられることはお答え申し上げなどして、こちらが恥ずかしくなるほどきちんとかしこまっているので、ちょっと言い出しにくい。けれど、とても上手にお話なさる。 |
紀伊守は五、六日してからその子供をつれて来た。整った顔というのではないが、艶な風采を備えていて、貴族の子らしいところがあった。そばへ呼んで源氏は打ち解けて話してやった。子供心に美しい源氏の君の恩顧を受けうる人になれたことを喜んでいた。姉のことも詳しく源氏は聞いた。返辞のできることだけは返辞をして、つつしみ深くしている子供に、源氏は秘密を打ちあけにくかった。けれども上手に嘘まじりに話して聞かせると、 |
Sate, itu-ka mui-ka ari te, kono ko wi te mawire ri. Komayaka ni wokasi to ha nakere do, namameki taru sama si te, ate-bito to miye tari. Mesi-ire te, ito natukasiku katarahi tamahu. Waraha-gokoti ni, ito medetaku uresi to omohu. Imouto-no-Kimi no koto mo kuhasiku tohi tamahu. Saru-beki koto ha irahe kikoye nado si te, hadukasi-ge ni sidumari tare ba, uti-ide nikusi. Saredo, ito yoku ihi-sira se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 | かかることこそはと、ほの心得るも、思ひの外なれど、幼な心地に深くしもたどらず。 御文を持て来たれば、女、 あさましきに涙も出で来ぬ。この子の思ふらむこともはしたなくて、さすがに、御文を面隠しに広げたり。いと多くて、 |
このようなことであったかと、ぼんやりと分かるのも、意外なことではあるが、子供心に深くも考えない。お手紙を持って来たので、女は、あまりのことに涙が出てしまった。弟がどう思っていることだろうかときまりが悪くて、そうは言っても、お手紙で顔を隠すように広げた。とてもたくさん書き連ねてあって、 |
そんなことがあったのかと、子供心におぼろげにわかればわかるほど意外であったが、子供は深い穿鑿をしようともしない。 源氏の手紙を弟が持って来た。女はあきれて涙さえもこぼれてきた。弟がどんな想像をするだろうと苦しんだが、さすがに手紙は読むつもりらしくて、きまりの悪いのを隠すように顔の上でひろげた。さっきからからだは横にしていたのである。手紙は長かった。終わりに、 |
Kakaru koto koso ha to, hono-kokoro-uru mo, omohi no hoka nare do, wosana-gokoti ni hukaku simo tadora zu. Ohom-humi wo mote-ki tare ba, Womna, asamasiki ni namida mo ide-ki nu. Kono ko no omohu ram koto mo hasitanaku te, sasuga ni, ohom-humi wo omo-gakusi ni hiroge tari. Ito ohoku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
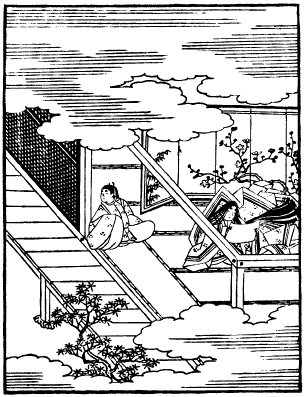 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.3 | 「 見し夢を逢ふ夜ありやと嘆くまに |
「夢が現実となったあの夜以来、再び逢える夜があろうかと嘆いているうちに |
見し夢を逢ふ夜ありやと歎く間に |
"Mi si yume wo ahu yo ari ya to nageku ma ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.4 | 目さへあはでぞころも経にける |
目までが合わさらないで眠れない夜を幾日も送ってしまいました |
目さへあはでぞ頃も経にける |
me sahe aha de zo koro mo he ni keru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.5 | ▼ 寝る夜なければ」 |
眠れる夜がないので」 |
安眠のできる夜がないのですから、夢が見られないわけです。 |
Nuru yo nakere ba" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.6 | など、目も及ばぬ御書きざまも、 霧り塞がりて、心得ぬ宿世うち添へりける 身を思ひ続けて臥したまへり ★ ★。 |
などと、見たこともないほどの、素晴らしいご筆跡も、目も涙に曇って、不本意な運命がさらにつきまとう身の上を思い続けて臥せってしまわれた。 |
とあった。目もくらむほどの美しい字で書かれてある。涙で目が曇って、しまいには何も読めなくなって、苦しい思いの新しく加えられた運命を思い続けた。 |
nado, me mo oyoba nu ohom-kaki-zama mo, kiri hutagari te, kokoroe nu sukuse uti-sohe ri keru mi wo omohi tuduke te husi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.7 | またの日、小君召したれば、参るとて御返り乞ふ。 |
翌日、小君をお召しになっていたので、参上しますと言って、お返事を催促する。 |
翌日源氏の所から小君が召された。出かける時に小君は姉に返事をくれと言った。 |
Mata no hi, Ko-Gimi mesi tare ba, mawiru tote ohom-kaheri kohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.8 | 「 かかる御文見るべき人もなし、と聞こえよ」 |
「このようなお手紙を見るような人はいません、と申し上げなさい」 |
「ああしたお手紙をいただくはずの人がありませんと申し上げればいい」 |
"Kakaru ohom-humi miru beki hito mo nasi, to kikoye yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.9 | と のたまへば、 うち笑みて、 |
とおっしゃると、にこっと微笑んで、 |
と姉が言った。 |
to notamahe ba, uti-wemi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.10 | 「 違ふべくものたまはざりしものを。いかが、さは申さむ」 |
「人違いのようにはおっしゃらなかったのに。どうして、そのように申し上げられましょうか」 |
「まちがわないように言っていらっしったのにそんなお返辞はできない」 |
"Tagahu beku mo notamaha zari si mono wo. Ikaga, sa ha mausa m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.11 | と言ふに、 心やましく、 残りなくのたまはせ、知らせてけると思ふに、つらきこと限りなし。 |
と言うので、不愉快に思い、すっかりおっしゃられ、知らせてしまったのだ、と思うと、辛く思われること、この上ない。 |
そう言うのから推せば秘密はすっかり弟に打ち明けられたものらしい、こう思うと女は源氏が恨めしくてならない。 |
to ihu ni, kokoro-yamasiku, nokorinaku notamahase, sira se te keru to omohu ni, turaki koto kagirinasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.12 | 「 いで、およすけたることは言はぬぞよき。 さは、 な参りたまひそ」と むつかられて ★、 |
「いいえ、ませた口をきくものではありませんよ。それなら、もう参上してはいけません」と不機嫌になられたが、 |
「そんなことを言うものじゃない。大人の言うようなことを子供が言ってはいげない。お断わりができなければお邸へ行かなければいい」 無理なことを言われて、弟は、 |
"Ide, oyosuke taru koto ha iha nu zo yoki. Saha, na mawiri tamahi so." to mutukara re te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.13 | 「 召すには、いかでか」とて、参りぬ。 |
「お召しになるのに、どうして」と言って、参上した。 |
「呼びにおよこしになったのですもの、伺わないでは」 と言って、そのまま行った。 |
"Mesu ni ha, ikade ka." tote, mawiri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.14 | 紀伊守、好き心にこの継母のありさまをあたらしきものに思ひて、追従しありけば、この子をもてかしづきて、 率てありく。 |
紀伊守は、好色心をもってこの継母の様子をもったいない人と思って、何かとおもねっているので、この子も大切にして、連れて歩いている。 |
好色な紀伊守はこの継母が父の妻であることを惜しがって、取り入りたい心から小君にも優しくしてつれて歩きもするのだった。 |
Ki-no-Kami, suki-gokoro ni kono mama-haha no arisama wo atarasiki mono ni omohi te, tuisyou-si arike ba, kono ko wo mote-kasiduki te, wi te ariku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.15 | 君、召し寄せて、 |
源氏の君は、お召しになって、 |
小君が来たというので源氏は居間へ呼んだ。 |
Kimi, mesi-yose te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.16 | 「 昨日 待ち暮らししを。なほ あひ思ふまじきなめり」 |
「昨日一日中待っていたのに。やはり、わたしほどには思ってくれないようだね」 |
「昨日も一日おまえを待っていたのに出て来なかったね。私だけがおまえを愛していても、おまえは私に冷淡なんだね」 |
"Kinohu mati kurasi si wo. Naho ahi omohu maziki na' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.17 | と怨じたまへば、 顔うち赤めてゐたり。 |
とお恨みになると、顔を赤らめて畏まっている。 |
恨みを言われて、小君は顔を赤くしていた。 |
to wen-zi tamahe ba, kaho uti-akame te wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.18 | 「 いづら」とのたまふに、 しかしかと申すに、 |
「どこに」とおっしゃると、これこれしかじかです、と申し上げるので、 |
「返事はどこ」 小君はありのままに告げるほかに術はなかった。 |
"Idura?" to notamahu ni, sika-sika to mausu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.19 | 「 言ふかひなのことや。あさまし」とて、 またも賜へり。 |
「だめだね。呆れた」と言って、またもお与えになった。 |
「おまえは姉さんに無カなんだね、返事をくれないなんて」 そう言ったあとで、また源氏から新しい手紙が小君に渡された。 |
"Ihukahi-na no koto ya! Asamasi." tote, mata mo tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.20 | 「 あこは知らじな。その伊予の翁よりは、 先に見し人ぞ。されど、 頼もしげなく頚細しとて、ふつつかなる後見まうけて、 かく侮りたまふなめり。さりとも、 あこはわが子にてをあれよ。この頼もし人は、 行く先短かりなむ」 |
「おまえは知らないのだね。わたしはあの伊予の老人よりは、先に関係していた人だよ。けれど、頼りなく弱々しいといって、不恰好な夫をもって、このように馬鹿になさるらしい。そうであっても、おまえはわたしの子でいてくれよ。あの頼りにしている人は、どうせ老い先短いでしょう」 |
「おまえは知らないだろうね、伊予の老人よりも私はさきに姉さんの恋人だったのだ。頸の細い貧弱な男だからといって、姉さんはあの不恰好な老人を良人に持って、今だって知らないなどと言って私を軽蔑しているのだ。けれどもおまえは私の子になっておれ。姉さんがたよりにしている人はさきが短いよ」 |
"Ako ha sira zi na. Sono Iyo-no-okina yori ha, saki ni mi si hito zo. Saredo, tanomosigenaku kubi hososi tote, hututuka naru usiromi mauke te, kaku anaduri tamahu na' meri. Sari-tomo, Ako ha waga ko ni te wo are yo! Kono tanomosi-bito ha, yukusaki mizikakari na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.21 | とのたまへば、「 さもやありけむ、いみじかりけることかな」 と思へる、「をかし」と思す。 |
とおっしゃると、「そういうこともあったのだろうか、大変なことだな」と思っているのを、「かわいいい」とお思いになる。 |
と源氏がでたらめを言うと、小君はそんなこともあったのか、済まないことをする姉さんだと思う様子をかわいく源氏は思った。 |
to notamahe ba, "Samo ya ari kem, imizikari keru koto kana!" to omohe ru, "Wokasi" to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.22 | この子をまつはしたまひて、内裏にも率て参りなどしたまふ。わが 御匣殿にのたまひて、 装束などもせさせ、 まことに親めきてあつかひたまふ。 |
この子を連れて歩きなさって、内裏にも連れて参上などなさる。ご自分の御匣殿にお命じになって、装束なども調達させ、本当に親のように面倒見なさる。 |
小君は始終源氏のそばに置かれて、御所へもいっしょに連れられて行ったりした。源氏は自家の衣裳係に命じて、小君の衣服を新調させたりして、言葉どおり親代わりらしく世話をしていた。 |
Kono ko wo matuhasi tamahi te, Uti ni mo wi te mawiri nado si tamahu. Waga mikusige-dono ni notamahi te, syauzoku nado mo se sase, makoto ni oya-meki te atukahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.23 | 御文は常にあり。されど、 この子もいと幼し、 心よりほかに散りもせば、 軽々しき名さへとり添へむ、身のおぼえをいと つきなかるべく思へば、 めでたきこともわが身からこそと思ひて、うちとけたる御答へも聞こえず。 ほのかなりし御けはひありさまは、「 げに、なべてにやは」と、思ひ出できこえぬにはあらねど、「 をかしきさまを見えたてまつりても、 何にかはなるべき」など、思ひ返すなりけり。 |
お手紙はいつもある。けれど、この子もとても幼い、うっかり落としでもしたら、軽々しい浮名まで背負い込む、我が身の風評も相応しくなく思うと、幸せも自分の身分に合ってこそはと思って、心を許したお返事も差し上げない。ほのかに拝見した感じやご様子は、「本当に、並々の人ではなく素晴らしかった」と、思い出し申さずにはいられないが、「お気持ちにお応え申しても、今さら何になることだろうか」などと、考え直すのであった。 |
女は始終源氏から手紙をもらった。けれども弟は子供であって、不用意に自分の書いた手紙を落とすようなことをしたら、もとから不運な自分がまた正しくもない恋の名を取って泣かねばならないことになるのはあまりに自分がみじめであるという考えが根底になっていて、恋を得るということも、こちらにその人の対象になれる自信のある場合にだけあることで、自分などは光源氏の相手になれる者ではないと思う心から返事をしないのであった。ほのかに見た美しい源氏を思い出さないわけではなかったのである。真実の感情を源氏に知らせてもさて何にもなるものでないと、苦しい反省をみずから強いている女であった。 |
Ohom-humi ha tune ni ari. Saredo, kono ko mo ito wosanasi, kokoro yori hoka ni tiri mo se ba, karo-garosiki na sahe tori-sohe m, mi no oboye wo ito tukinakaru beku omohe ba, medetaki koto mo waga mi kara koso to omohi te, utitoke taru ohom-irahe mo kikoye zu. Honoka nari si ohom-kehahi arisama ha, "Geni, nabete ni yaha!" to, omohi-ide kikoye nu ni ha ara ne do, "Wokasiki sama wo miye tatematuri te mo, nani ni ka ha naru beki." nado, omohi-kahesu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.24 | 君は思しおこたる時の間もなく、心苦しくも恋しくも思し出づ。 思へりし気色などのいとほしさも、晴るけむ方なく思しわたる。軽々しく這ひ紛れ立ち寄りたまはむも、 人目しげからむ所に、便なき振る舞ひや あらはれむと、人のためもいとほしく、と思しわづらふ。 |
源氏の君は、お忘れになる時の間もなく、心苦しくも恋しくもお思い出しになる。悩んでいた様子などのいじらしさも、払い除けようもなく思い続けていらっしゃる。軽々しくひそかに隠れてお立ち寄りなさるのも、人目の多い所で、不都合な振る舞いを見せはしまいかと、相手にも気の毒である、と思案にくれていらっしゃる。 |
源氏はしばらくの間もその人が忘られなかった。気の毒にも思い恋しくも思った。女が自分とした過失に苦しんでいる様子が目から消えない。本能のおもむくままに忍んであいに行くことも、人目の多い家であるからそのことが知れては困ることになる、自分のためにも、女のためにもと思っては煩悶をしていた。 |
Kimi ha obosi-okotaru toki no ma mo naku, kokoro-gurusiku mo kohisiku mo obosi-idu. Omohe ri si kesiki nado no itohosisa mo, haruke m kata naku obosi-wataru. Karo-garosiku hahi-magire tati-yori tamaha m mo, hito-me sigekara m tokoro ni, bin-naki hurumahi ya arahare m to, hito no tame mo itohosiku, to obosi wadurahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.25 | 例の、内裏に日数経たまふころ、 さるべき方の忌み待ち出でたまふ。 にはかにまかでたまふまねして、道のほどよりおはしましたり。 |
例によって、内裏に何日もいらっしゃるころ、都合のよい方違えの日をお待ちになる。急に退出なさるふりをして、途中からお越しになった。 |
例のようにまたずっと御所にいた頃、源氏は方角の障りになる日を選んで、御所から来る途中でにわかに気がついたふうをして紀伊守の家へ来た。 |
Rei no, Uti ni hi-kazu he tamahu koro, saru-beki kata no imi mati-ide tamahu. Nihaka ni makade tamahu mane si te, miti no hodo yori ohasimasi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.26 | 紀伊守おどろきて、 遣水の面目とかしこまり喜ぶ。小君には、昼より、「 かくなむ思ひよれる」とのたまひ契れり。明け暮れまつはし馴らしたまひければ、今宵もまづ召し出でたり。 |
紀伊守は驚いて、先日の遣水を光栄に思い、恐縮し喜ぶ。小君には、昼から、「こうしようと思っている」とお約束なさっていた。朝に夕に連れ従えていらっしゃったので、今宵も、まっさきにお召しになっていた。 |
紀伊守は驚きながら、 「前栽の水の名誉でございます」 こんな挨拶をしていた。小君の所へは昼のうちからこんな手はずにすると源氏は言ってやってあって、約束ができていたのである。 始終そばへ置いている小君であったから、源氏はさっそく呼び出した。 |
Ki-no-Kami odoroki te, yarimidu no meiboku to kasikomari yorokobu. Ko-Gimi ni ha, hiru yori, "Kaku nam omohi-yore ru." to notamahi tigire ri. Ake-kure matuhasi narasi tamahi kere ba, koyohi mo madu mesi-ide tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.27 | 女も、 さる御消息ありけるに、 思したばかりつらむほどは、 浅くしも思ひなされねど、 さりとて、うちとけ、人げなきありさまを見えたてまつりても、 あぢきなく、夢のやうにて過ぎにし嘆きを、またや加へむ、と思ひ乱れて、 なほさて待ちつけ きこえさせむことのまばゆければ、小君が出でて往ぬるほどに、 |
女も、そのようなお手紙があったので、工夫をこらしなさるお気持ちのほどは、浅いものとは思われないが、そうだからといって、気を許して、みっともない様をお見せ申すのも、つまらなく、夢のようにして過ぎてしまった嘆きを、さらにまた味わおうとするのかと、思い乱れて、やはりこうしてお待ち受け申し上げることが気恥ずかしいので、小君が出て行った間に、 |
女のほうへも手紙は行っていた。自身に逢おうとして払われる苦心は女の身にうれしいことではあったが、そうかといって、源氏の言うままになって、自己が何であるかを知らないように恋人として逢う気にはならないのである。夢であったと思うこともできる過失を、また繰り返すことになってはならぬとも思った。妄想で源氏の恋人気どりになって待っていることは自分にできないと女は決めて、小君が源氏の座敷のほうへ出て行くとすぐに、 |
Womna mo, saru ohom-seusoko ari keru ni, obosi-tabakari tu ram hodo ha, asaku simo omohi-nasa re ne do, saritote, utitoke, hitogenaki arisama wo miye tatematuri te mo, adikinaku, yume no yau ni te sugi ni si nageki wo, mata ya kuhahe m, to omohi midare te, naho sate mati-tuke kikoyesase m koto no mabayukere ba, Ko-Gimi ga ide te inuru hodo ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.28 | 「 いとけ近ければ、かたはらいたし。なやましければ、忍びてうち叩かせなどせむに、 ほど離れてを」 |
「とても近いので、気が引けます。気分が悪いので、こっそりと肩腰を叩かせたりしたいので、少し離れた所でね」 |
「あまりお客様の座敷に近いから失礼な気がする。私は少しからだが苦しくて、腰でもたたいてほしいのだから、遠い所のほうが都合がよい」 |
"Ito ke-dikakere ba, kataharaitasi. Nayamasikere ba, sinobi te uti-tataka se nado se m ni, hodo hanare te wo!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.29 | とて、渡殿に、 中将といひしが局したる隠れに、移ろひぬ。 |
と言って、渡殿に、中将の君といった者が部屋を持っていた奥まった処に、移ってしまった。 |
と言って、渡殿に持っている中将という女房の部屋へ移って行った。 |
tote, wata-dono ni, Tyuuzyau to ihi si ga tubone si taru kakure ni, uturohi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.30 | さる心して、人とく静めて、御消息あれど、小君は尋ねあはず。よろづの所求め歩きて、渡殿に分け入りて、 からうしてたどり来たり。 いとあさましくつらし、と思ひて、 |
そのつもりで、供人たちを早く寝静まらせて、お便りなさるが、小君は尋ね当てられない。すべての場所を探し歩いて、渡殿に入りこんで、やっとのことで探し当てた。ほんとうにあんまりなひどい、と思って、 |
初めから計画的に来た源氏であるから、家従たちを早く寝させて、女へ都合を聞かせに小君をやった。小君に姉の居所がわからなかった。やっと渡殿の部屋を捜しあてて来て、源氏への冷酷な姉の態度を恨んだ。 |
Saru kokoro si te, hito toku sidume te, ohom-seusoko are do, Ko-Gimi ha tadune aha zu. Yorodu no tokoro motome ariki te, wata-dono ni wake-iri te, karausite, tadori ki tari. Ito asamasiku turasi, to omohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.31 | 「 いかにかひなしと思さむ」と、泣きぬばかり言へば、 |
「どんなにか、役立たずな者と、お思いになるでしょう」と、泣き出してしまいそうに言うと、 |
「こんなことをして、姉さん。どんなに私が無力な子供だと思われるでしょう」 もう泣き出しそうになっている。 |
"Ika ni kahinasi to obosa m." to, naki nu bakari ihe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.32 | 「 かく、けしからぬ心ばへは ★、 つかふものか。幼き人のかかること言ひ伝ふるは、いみじく 忌むなるものを」と言ひおどして、「『 心地悩ましければ、 人びと避けず おさへさせてなむ』と 聞こえさせよ。 あやしと誰も誰も見るらむ」 |
「このような、不埒な考えは、持っていいものですか。子供がこのような事を取り次ぐのは、ひどく悪いことと言うのに」ときつく言って、「『気分がすぐれないので、女房たちを側に置いて揉ませております』とお伝え申し上げなさい。変だと皆が見るでしょう」 |
「なぜおまえは子供のくせによくない役なんかするの、子供がそんなことを頼まれてするのはとてもいけないことなのだよ」 としかって、 「気分が悪くて、女房たちをそばへ呼んで介抱をしてもらっていますって申せばいいだろう。皆が怪しがりますよ、こんな所へまで来てそんなことを言っていて」 |
"Kaku, kesikara nu kokoro-bahe ha, tukahu mono-ka. Wosanaki hito no kakaru koto ihi tutahuru ha, imiziku imu naru monowo!" to ihi-odosi te, "'Kokoti nayamasikere ba, hito-bito sake zu osahe sase te nam' to kikoye sase yo. Ayasi to tare-mo tare-mo miru ram." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.33 | と 言ひ放ちて、心の中には、「 いと、かく品定まりぬる身のおぼえならで、過ぎにし親の御けはひとまれるふるさとながら、たまさかにも待ちつけたてまつらば、 をかしうもやあらまし。しひて思ひ知らぬ顔に見消つも、いかにほど知らぬやうに思すらむ」と、 心ながらも、胸いたく、さすがに思ひ乱る。「 とてもかくても、今は言ふかひなき宿世なりければ、無心に心づきなくて止みなむ」と思ひ果てたり。 |
とつっぱねたが、心中では、「ほんとうに、このように身分の定まってしまった身の上でなく、亡くなった親の御面影の残っている邸にいたままで、たまさかにでもお待ち申し上げるならば、喜んでそうしたいところであるが。無理にお気持ちを分からないふうを装って無視したのも、どんなにか身の程知らぬ者のようにお思いになるだろう」と、心に決めたものの、胸が痛くて、そうはいってもやはり心が乱れる。「どっちみち、今はどうにもならない運命なのだから、非常識な気にくわない女で、押しとおそう」と思い諦めた。 |
取りつくしまもないように姉は言うのであったが、心の中では、こんなふうに運命が決まらないころ、父が生きていたころの自分の家へ、たまさかでも源氏を迎えることができたら自分は幸福だったであろう。しいて作るこの冷淡さを、源氏はどんなにわが身知らずの女だとお思いになることだろうと思って、自身の意志でしていることであるが胸が痛いようにさすがに思われた。どうしてもこうしても人妻という束縛は解かれないのであるから、どこまでも冷ややかな態度を押し通して変えまいという気に女はなっていた。 |
to ihi-hanati te, kokoro no uti ni ha, "Ito, kaku sina sadamari nuru mi no oboye nara de, sugi ni si oya no ohom-kehahi tomare ru hurusato nagara, tamasaka ni mo mati-tuke tatematura ba, wokasiu mo ya ara masi. Sihite omohi-sira nu kaho ni mi-ketu mo, ika ni hodo sira nu yau ni obosu ram." to, kokoro-nagara mo, mune itaku, sasuga ni omohi-midaru. "Totemo-kakutemo, ima ha ihukahinaki syukuse nari kere ba, musin ni kokorodukinaku te yami na m." to omohi-hate tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.34 | 君は、 いかにたばかりなさむと、まだ幼きをうしろめたく待ち臥したまへるに、不用なるよしを聞こゆれば、あさましくめづらかなりける心のほどを、「 身もいと恥づかしくこそなりぬれ」と、いといとほしき御気色なり。とばかりものものたまはず、いたくうめきて、憂しと思したり。 |
源氏の君は、どのように手筈を調えるかと、まだ小さいので不安に思いながら横になって待っていらっしゃると、不首尾である旨を申し上げるので、驚くほどにも珍しかった強情さなので、「わが身までがまことに恥ずかしくなってしまった」と、とてもお気の毒なご様子である。しばらくは何もおっしゃらず、ひどく嘆息なさって、辛いとお思いになっていた。 |
源氏はどんなふうに計らってくるだろうと、頼みにする者が少年であることを気がかりに思いながら寝ているところへ、だめであるという報せを小君が持って来た。女のあさましいほどの冷淡さを知って源氏は言った。 「私はもう自分が恥ずかしくってならなくなった」 気の毒なふうであった。それきりしばらくは何も言わない。そして苦しそうに吐息をしてからまた女を恨んだ。 |
Kimi ha, ika ni tabakari-nasa m to, mada wosanaki wo usirometaku mati-husi tamahe ru ni, huyou naru yosi wo kikoyure ba, asamasiku meduraka nari keru kokoro no hodo wo, "Mi mo ito hadukasiku koso nari nure." to, ito itohosiki mi-kesiki nari. Tobakari mono mo notamaha zu, itaku umeki te, usi to obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.35 | 「 帚木の心を知らで園原の |
「近づけば消えるという帚木のような、あなたの心も知らないで |
帚木の心を知らでその原の |
"Hahakigi no kokoro wo sira de Sonohara no |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.36 | 道にあやなく惑ひぬるかな |
園原への道に、空しく迷ってしまったことです |
道にあやなくまどひぬるかな |
miti ni ayanaku madohi nuru kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.37 | 聞こえむ方こそなけれ」 |
申し上げるすべもありません」 |
今夜のこの心持ちはどう言っていいかわからない、と小君に言ってやった。 |
Kikoye m kata koso nakere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.38 | とのたまへり。 女も、さすがに、まどろまざりければ、 |
と詠んで贈られた。女も、やはり、まどろむこともできなかったので、 |
女もさすがに眠れないで悶えていたのである。それで、 |
to notamahe ri. Womna mo, sasuga ni, madoroma zari kere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.39 | 「 数ならぬ伏屋に生ふる名の憂さに |
「しがない境遇に生きるわたしは情けのうございますから |
数ならぬ伏屋におふる身のうさに |
"Kazu nara nu huseya ni ohuru na no usa ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.40 | あるにもあらず消ゆる帚木」 |
見えても触れられない帚木のようにあなたの前から姿を消すのです」 |
あるにもあらず消ゆる帚木 |
aru ni mo ara zu kiyuru Hahakigi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.41 | と聞こえたり。 |
とお答え申し上げた。 |
という歌を弟に言わせた。 |
to kikoye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.42 | 小君、 いといとほしさに眠たくもあらで まどひ歩くを、 人あやしと見るらむ、と わびたまふ。 |
小君が、とてもお気の毒に思って眠けを忘れてうろうろと行き来するのを、女房たちが変だと思うだろう、と心配なさる。 |
小君は源氏に同情して、眠がらずに往ったり来たりしているのを、女は人が怪しまないかと気にしていた。 |
Ko-Gimi, ito itohosisa ni nebutaku mo ara de madohi-ariku wo, hito ayasi to miru ram, to wabi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.43 | 例の、 人びとはいぎたなきに、 一所すずろにすさまじく思し続けらるれど、 人に似ぬ心ざまの、なほ 消えず立ち上れりける、とねたく、 かかるにつけてこそ心もとまれと、かつは思しながら、めざましくつらければ、さばれと思せども、さも思し果つまじく、 |
例によって、供人たちは眠りこけているが、お一方はぼうっと白けた感じで思い続けていらっしゃるが、他の女と違った気の強さが、やはり消えるどころかはっきり現れている、と悔しく、こういう女であったから心惹かれたのだと、一方ではお思いになるものの、癪にさわり情けないので、ええいどうともなれとお思いになるが、そうともお諦めきれず、 |
いつものように酔った従者たちはよく眠っていたが、源氏一人はあさましくて寝入れない。普通の女と変わった意志の強さのますます明確になってくる相手が恨めしくて、もうどうでもよいとちょっとの間は思うがすぐにまた恋しさがかえってくる。 |
Rei no, hito-bito ha igitanaki ni, hito-tokoro suzuro ni susamaziku obosi-tuduke rarure do, hito ni ni nu kokoro-zama no, naho kiye zu tati nobore ri keru, to netaku, kakaru ni tuke te koso kokoro mo tomare to, katu ha obosi nagara, mezamasiku turakere ba, sabare to obose domo, sa-mo obosi-hatu maziku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.44 | 「 隠れたらむ所に、なほ率て行け」とのたまへど、 |
「隠れている所に、それでも連れて行け」とおっしゃるが、 |
「どうだろう、隠れている場所へ私をつれて行ってくれないか」 |
"Kakure tara m tokoro ni, naho wi te ike!" to notamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.45 | 「 いとむつかしげにさし籠められて、 人あまたはべるめれば、 かしこげに」 |
「とてもむさ苦しい所に籠もっていて、女房が大勢いますようなので、恐れ多いことで」 |
「なかなか開きそうにもなく戸じまりがされていますし、女房もたくさんおります。そんな所へ、もったいないことだと思います」 |
"Ito mutukasige ni sasi-kome rare te, hito amata haberu mere ba, kasikoge ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.46 | と聞こゆ。 いとほしと思へり。 |
と申し上げる。気の毒にと思っていた。 |
と小君が言った。源氏が気の毒でたまらないと小君は思っていた。 |
to kikoyu. Itohosi to omohe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.47 | 「 よし、あこだに、な捨てそ」 |
「それでは、おまえだけは、わたしを裏切るでないぞ」 |
「じゃあもういい。おまえだけでも私を愛してくれ」 |
"Yosi, Ako dani, na sute so." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.48 | とのたまひて、 御かたはらに臥せたまへり。 若くなつかしき御ありさまを、 うれしくめでたしと思ひたれば、 つれなき人よりは、 なかなかあはれに思さるとぞ。 |
とおっしゃって、お側に寝かせなさった。お若く優しいご様子を、嬉しく素晴らしいと思っているので、あの薄情な女よりも、かえってかわいく思われなさったということである。 |
と言って、源氏は小君をそばに寝させた。若い美しい源氏の君の横に寝ていることが子供心に非常にうれしいらしいので、この少年のほうが無情な恋人よりもかわいいと源氏は思った。 |
to notamahi te, ohom-katahara ni huse tamahe ri. Wakaku natukasiki ohom-arisama wo, uresiku medetasi to omohi tare ba, turenaki hito yori ha, naka-naka ahare ni obosa ru to zo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 6/25/2003 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-4-1) Last updated 6/25/2003 渋谷栄一注釈(C)(ver.1-3-1) |
Last updated 6/25/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-4-1) |
|
Last updated 6/25/2003 Written in Japnese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-5-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経