02 帚木(明融臨模本) |
HAHAKIGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏 十七歳夏の参議(宰相)兼近衛中将時代の物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era in the summer at the age of 17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 雨夜の品定めの物語 |
1 Tales on men's experiences with girl friends in a rainy night |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 長雨の時節 |
1-1 A rainy night in the summer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 光源氏、名のみことことしう、 言ひ消たれたまふ咎 多かなるに、 いとど、かかる好きごとどもを、末の世にも聞き伝へて、 軽びたる名をや流さむと、忍びたまひける隠ろへごとをさへ、 語り伝へけむ人の もの言ひさがなさよ。 さるは、いといたく世を憚り、まめだちたまひけるほど、なよびかにをかしきことはなくて、 交野少将には 笑はれたまひけむかし。 |
光る源氏と、名前だけはご大層だが、非難されなさる取り沙汰が多いというのに、ますます、このような好色沙汰を、後世にも聞き伝わって、軽薄である浮き名を流すことになろうかと、隠していらっしゃった秘密事までを、語り伝えたという人のおしゃべりの意地の悪いことよ。とは言うものの、大変にひどく世間を気にし、まじめになさっていたところは、艶っぽくおもしろい話はなくて、交野少将からは笑われなさったことであろうよ。 |
光源氏、すばらしい名で、青春を盛り上げてできたような人が思われる。自然奔放な好色生活が想像される。しかし実際はそれよりずっと質素な心持ちの青年であった。その上恋愛という一つのことで後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと、異性との交渉をずいぶん内輪にしていたのであるが、ここに書く話のような事が伝わっているのは世間がおしゃべりであるからなのだ。自重してまじめなふうの源氏は恋愛風流などには遠かった。好色小説の中の交野の少将などには笑われていたであろうと思われる。 |
Hikaru-Genzi, na nomi koto-kotosiu, ihi-keta re tamahu toga ohoka' naru ni, itodo, kakaru suki-goto-domo wo, suwe-no-yo ni mo kiki tutahe te, karobi taru na wo ya nagasa m to, sinobi tamahi keru kakurohe-goto wo sahe, katari tutahe kem hito no mono-ihi saganasa yo. Sa'ru ha, ito itaku yo wo habakari, mamedati tamahi keru hodo, nayobika ni wokasiki koto ha naku te, Katano-no-Seusyau ni ha waraha re tamahi kem kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | まだ中将などにものしたまひし時は、 内裏にのみさぶらひようしたまひて、 大殿には絶え絶えまかでたまふ。 忍ぶの乱れや ★と、疑ひきこゆることもありしかど、さしもあだめき目馴れたるうちつけの好き好きしさなどは好ましからぬ御本性にて、まれには、あながちに引き違へ心尽くしなることを、御心に思しとどむる 癖なむ、 あやにくにて、さるまじき御振る舞ひも うち混じりける。 |
まだ近衛中将などでいらっしゃったころは、内裏にばかりよく伺候していらっしゃって、大殿邸には途切れ途切れに退出なさる。お浮気事かと、お疑い申すこともあったが、そんなふうに浮気っぽいありふれた思いつきの色恋事などは好きでないご性格で、時たまには、やむにやまれない予想を狂わせる気苦労の多い恋を、お心に思いつめなさる性癖が、あいにくおありで、よろしくないご素行もないではなかった。 |
中将時代にはおもに宮中の宿直所に暮らして、時たまにしか舅の左大臣家へ行かないので、別に恋人を持っているかのような疑いを受けていたが、この人は世間にざらにあるような好色男の生活はきらいであった。まれには風変わりな恋をして、たやすい相手でない人に心を打ち込んだりする欠点はあった。 |
Mada Tyuuzyau nado ni monosi tamahi si toki ha, uti ni nomi saburahi you si tamahi te, Ohoi-dono ni ha taye-daye makade tamahu. Sinobu no midare ya to, utagahi kikoyuru koto mo ari sika do, sasimo adameki me nare taru utituke no suki-zukisisa nado ha konomasikara nu go-honzyau nite, mare ni ha, anagati ni hiki-tagahe kokoro-dukusi naru koto wo, mi-kokoro ni obosi-todomuru kuse nam, ayaniku nite, sa'rumaziki ohom-hurumahi mo uti-maziri keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 宮中の宿直所、光る源氏と頭中将 |
1-2 A night duty room in the Imperial Court |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 長雨晴れ間なきころ、内裏の御物忌さし続きて、いとど長居さぶらひたまふを、大殿にはおぼつかなく恨めしく思したれど、よろづの御よそひ何くれとめづらしきさまに 調じ出でたまひつつ、御息子の君たちただ この御宿直所の宮仕へを勤めたまふ。 |
長雨の晴れ間のないころ、宮中の御物忌みが続いて、ますます長々と伺候なさるのを、大殿邸では待ち遠しく恨めしいとお思いになっていたが、すべてのご装束を何やかやと新しい様相に新調なさっては、ご子息の公達がひたすらこのご宿直所の宮仕えをお勤めになる。 |
梅雨のころ、帝の御謹慎日が幾日かあって、近臣は家へも帰らずに皆宿直する、こんな日が続いて、例のとおりに源氏の御所住まいが長くなった。大臣家ではこうして途絶えの多い婿君を恨めしくは思っていたが、やはり衣服その他贅沢を尽くした新調品を御所の桐壼へ運ぶのに倦むことを知らなんだ。左大臣の子息たちは宮中の御用をするよりも、源氏の宿直所への勤めのほうが大事なふうだった。 |
Nagaame harema naki koro, Uti no ohom-monoimi sasi-tuduki te, itodo nagawi saburahi tamahu wo, Ohoi-dono ni ha obotukanaku uramesiku obosi tare do, yorodu no ohom-yosohi nanikure to medurasiki sama ni teu-zi-ide tamahi tutu, ohom-musuko no kimi-tati tada kono ohom-tonowi-dokoro no miyadukahe wo tutome tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 宮腹の中将は、なかに親しく馴れきこえたまひて、遊び戯れをも人よりは心安く、なれなれしく振る舞ひたり。右大臣のいたはりかしづきたまふ住み処は、この君もいともの憂くして、 好きがましきあだ人なり。 |
宮がお生みになった中将は、中でも親しくお馴染み申されて、遊び事や戯れ事においても誰よりも気安く、親密に振る舞っていた。右大臣が気を配ってお世話なさる住居には、この君もとても何となく気が進まずにいて、いかにも好色人らしい浮気人なのである。 |
そのうちでも宮様腹の中将は最も源氏と親しくなっていて、遊戯をするにも何をするにも他の者の及ばない親交ぶりを見せた。大事がる舅の右大臣家へ行くことはこの人もきらいで、恋の遊びのほうが好きだった。 |
Miya-bara-no-Tyuuzyau ha, naka ni sitasiku nare kikoye tamahi te, asobi tahabure wo mo hito yori ha kokoro-yasuku, nare-naresiku hurumahi tari. Migi-no-otodo no itahari kasiduki tamahu sumika ha, kono Kimi mo ito mono-uku si te, suki-gamasiki adabito nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 里にても、わが方のしつらひまばゆくして、君の出で入りしたまふに うち連れきこえたまひつつ、夜昼、 学問をも遊びをももろともにして、 をさをさ立ちおくれず、いづくにてもまつはれきこえたまふほどに、おのづから かしこまりもえおかず、心のうちに思ふことをも隠しあへずなむ、睦れきこえたまひける。 |
実家でも、ご自分の部屋の装飾を眩しくして、源氏の君がお出入りなさるのにいつもお供申し上げなさっては、昼も夜も、学問をも音楽をもご一緒申して、少しもひけをとらず、どこにでも親しくご一緒申し上げなさるうちに、自然と遠慮もしていられず、胸の中に思うことをも隠しきれず、お親しみ申されるのであった。 |
結婚した男はだれも妻の家で生活するが、この人はまだ親の家のほうにりっぱに飾った居間や書斎を持っていて、源氏が行く時には必ずついて行って、夜も、昼も、学問をするのも、遊ぶのもいっしょにしていた。謙遜もせず、敬意を表することも忘れるほどぴったりと仲よしになっていた。 |
Sato nite mo, waga kata no siturahi mabayuku si te, Kimi no ide-iri si tamahu ni uti-ture kikoye tamahi tutu, yoru hiru, gakumon wo mo asobi wo mo morotomoni si te, wosa-wosa tati-okure zu, iduku nite mo matuha re kikoye tamahu hodo ni, onodukara kasikomari mo e oka zu, kokoro no uti ni omohu koto wo mo kakusi-ahe zu nam, muture kikoye tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
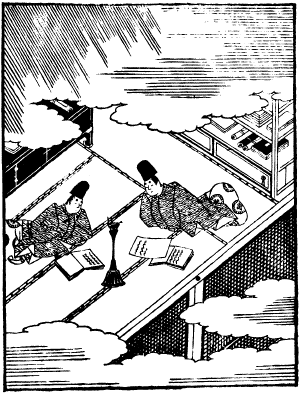 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | つれづれと降り暮らして、しめやかなる宵の雨に、殿上にもをさをさ人少なに、 御宿直所も例よりはのどやかなる心地するに、大殿油近くて 書どもなど見たまふ。近き御厨子なる 色々の紙なる文どもを引き出でて、中将わりなく ゆかしがれば、 |
所在なく雨が一日中降り続いて、しっとりした夜の雨に、殿上の間でもろくに人少なで、ご宿直所もいつもよりはのんびりとした気分なので、大殿油を近くに寄せて漢籍などを御覧になる。近くの御厨子にあるさまざまな色彩の紙に書かれた手紙類を取り出して、中将がひどく見たがるので、 |
五月雨がその日も朝から降っていた夕方、殿上役人の詰め所もあまり人影がなく、源氏の桐壼も平生より静かな気のする時に、灯を近くともしていろいろな書物を見ていると、その本を取り出した置き棚にあった、それぞれ違った色の紙に書かれた手紙の殻の内容を頭中将は見たがった。 |
Turedure to huri kurasi te, simeyaka naru yohi no ame ni, tenzyau ni mo wosawosa hito-zukuna ni, ohom-tonowi-dokoro mo rei yori ha nodoyaka naru kokoti suru ni, ohotonabura tikaku te humi-domo nado mi tamahu. Tikaki mi-dusi naru iro-iro no kami naru humi-domo hiki-ide te, Tyuuzyau warinaku yukasigare ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 「 さりぬべき、すこしは見せむ。 かたはなるべきもこそ」 |
「差し支えのないのを、少しは見せよう。不体裁なものがあってはいけないから」 |
「無難なのを少しは見せてもいい。見苦しいのがありますから」 |
"Sa'ri-nu-beki, sukosi ha mise m. Kataha naru beki mo koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | と、許したまはねば、 |
と、お許しにならないので、 |
と源氏は言っていた。 |
to, yurusi tamaha ne ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 「 そのうちとけてかたはらいたしと思されむこそゆかしけれ。おしなべたるおほかたのは、 数ならねど、程々につけて、 書き交はしつつも見はべりなむ。おのがじし、恨めしき折々、待ち顔ならむ夕暮れなどのこそ、見所はあらめ」 |
「その気を許していて人に見られたら困ると思われなさ文こそ興味があります。普通のありふれたのは、つまらないわたしでも、身分相応に、互いにやりとりしては見ておりましょう。それぞれが、恨めしく思っている折々や、心待ち顔でいるような夕暮などの文が、見る価値がありましょう」 |
「見苦しくないかと気になさるのを見せていただきたいのですよ。平凡な女の手紙なら、私には私相当に書いてよこされるのがありますからいいんです。特色のある手紙ですね、怨みを言っているとか、ある夕方に来てほしそうに書いて来る手紙、そんなのを拝見できたらおもしろいだろうと思うのです」 |
"Sono utitoke te kataharaitasi to obosa re m koso yukasikere. Osinabe taru ohokata no ha, kazu nara ne do, hodo-hodo ni tuke te, kaki-kahasi tutu mo mi haberi na m. Onogazisi, uramesiki wori-wori, mati-gaho nara m yuhugure nado no koso, mi-dokoro ha ara me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | と怨ずれば、 やむごとなくせちに隠したまふべきなどは、かやうにおほざうなる御厨子などにうち置き散らしたまふべくもあらず、深くとり置きたまふべかめれば、二の町の心安きなるべし。 片端づつ見るに、「 かくさまざまなる物どもこそはべりけれ」とて、 心あてに「 それか、かれか」など問ふなかに、言ひ当つるもあり、もて離れたることをも思ひ寄せて疑ふも、 をかしと思せど、言少なにて とかく紛らはしつつ、とり隠したまひつ。 |
と怨み言をいうので、高貴な方からの絶対にお隠しにならねばならない文などは、このようになおざりな御厨子などにちょっと置いて散らかしていらっしゃるはずはなく、奥深く別にしまって置かれるにちがいないようだから、これらは二流の気安いものであろう。少しずつ見て行くと、「こんなにも、いろいろな手紙類がございますなあ」と言って、当て推量に「これはあの人か、あれはこの人か」などと尋ねる中で、言い当てるものもあり、外れているのをかってに推量して疑ぐるのも、おもしろいとお思いになるが、言葉少なに答えて何かと言い紛らわしては、取ってお隠しになった。 |
と恨まれて、初めからほんとうに秘密な大事の手紙などは、だれが盗んで行くか知れない棚などに置くわけもない、これはそれほどの物でないのであるから、源氏は見てもよいと許した。 中将は少しずつ読んで見て言う。 「いろんなのがありますね」 自身の想像だけで、だれとか彼とか筆者を当てようとするのであった。上手に言い当てるのもある、全然見当違いのことを、それであろうと深く追究したりするのもある。そんな時に源氏はおかしく思いながらあまり相手にならぬようにして、そして上手に皆を中将から取り返してしまった。 |
to wen-zure ba, yamgotonaku seti ni kakusi tamahu beki nado ha, kayau ni ohozau naru mi-dusi nado ni uti-oki tirasi tamahu beku mo ara zu, hukaku tori-oki tamahu beka' mere ba, ni-no-mati no kokoro-yasuki naru besi. Katahasi-dutu miru ni, "Kaku sama-zama naru mono-domo koso haberi kere" tote, kokoro-ate ni "Sore ka? Kare ka?" nado tohu naka ni, ihi-aturu mo ari, mote-hanare taru koto wo mo omohi-yose te utagahu mo, wokasi to obose do, koto-zukuna nite, tokaku magirahasi tutu, tori kakusi tamahi tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 「 そこにこそ多く集へたまふらめ。 すこし見ばや。さてなむ、この厨子も 心よく開くべき」とのたまへば、 |
「そなたこそ、たくさんお有りだろう。少し見たいね。そうしたら、この厨子も気持ちよく開けよう」とおっしゃると、 |
「あなたこそ女の手紙はたくさん持っているでしょう。少し見せてほしいものだ。そのあとなら棚のを全部見せてもいい」 |
"Soko ni koso ohoku tudohe tamahu rame. Sukosi mi baya. Sate nam, kono dusi mo kokoro-yoku hiraku beki." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 「 御覧じ所あらむこそ、 難くはべらめ」など 聞こえたまふついでに、「 女の、これはしもと難つくまじきは、難くもあるかなと、やうやうなむ 見たまへ知る。ただうはべばかりの情けに、手走り書き、をりふしの答へ心得て、うちしなどばかりは、 随分によろしきも多かりと 見たまふれど、そもまことにその方を取り出でむ選びに かならず漏るまじきは、いと難しや。わが心得たることばかりを、おのがじし心をやりて、人をば落としめなど、かたはらいたきこと多かり。 |
「御覧になる値打のものは、ほとんどないしょう」などと申し上げなさる、そのついでに、「女性で、これならば良しと難点を指摘しようのない人は、めったにいないものだなあと、だんだんと分かってまいりました。ただ表面だけの風情で、手紙をさらさらと走り書きしたり、時節に相応しい返答を心得て、ちょっとするぐらいのは、身分相応にまあまあ良いと思う者は多くいると拝見しますが、それも本当にその方面の優れた人を選び出そうとすると、絶対に選に外れないという者は、本当にめったにないものですね。自分の得意なことばかりを、それぞれ得意になって、他人を貶めたりなどして、見ていられないことが多いです。 |
「あなたの御覧になる価値のある物はないでしょうよ」 こんな事から頭中将は女についての感想を言い出した。 「これならば完全だ、欠点がないという女は少ないものであると私は今やっと気がつきました。ただ上っつらな感情で達者な手紙を書いたり、こちらの言うことに理解を持っているような利巧らしい人はずいぶんあるでしょうが、しかもそこを長所として取ろうとすれば、きっと合格点にはいるという者はなかなかありません。自分が少し知っていることで得意になって、ほかの人を軽蔑することのできる厭味な女が多いんですよ。 |
"Go-ran-zi-dokoro ara m koso, kataku habera me." nado kikoye tamahu tuide ni, "Womna no, kore ha simo to nan tuku maziki ha, kataku mo aru kana to, yauyau nam mi tamahe siru. Tada uhabe bakari no nasake ni, te hasiri-kaki, worihusi no irahe kokoroe te, uti-si nado bakari ha, zuibun ni yorosiki mo ohokari to mi tamahure do, somo makoto ni sono kata wo tori-ide m erabi ni kanarazu moru maziki ha, ito katasi ya! Waga kokoroe taru koto bakari wo, onogazisi kokoro wo yari te, hito woba otosime nado, kataharaitaki koto ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | 親など立ち添ひもてあがめて、 ▼ 生ひ先籠れる窓の内なるほどは、ただ片かどを聞き伝へて、 心を動かすこともあめり。 容貌をかしくうちおほどき、若やかにて紛るることなきほど、はかなき すさびをも、人まねに心を入るることもあるに、おのづから一つゆゑづけてし出づることもあり。 |
親などが側で大切にかわいがって、将来性のある箱入娘時代は、ちょっとの才能の一端を聞き伝えて、関心を寄せることもあるようです。容貌が魅力的でおっとりしていて、若々しくて家事にかまけることのないうちは、ちょっとした芸事にも、人まねに一生懸命に稽古することもあるので、自然と一芸をもっともらしくできることもあります。 |
親がついていて、大事にして、深窓に育っているうちは、その人の片端だけを知って男は自分の想像で十分補って恋をすることになるというようなこともあるのですね。顔がきれいで、娘らしくおおようで、そしてほかに用がないのですから、そんな娘には一つくらいの芸の上達が望めないこともありませんからね。 |
Oya nado tati-sohi mote-agame te, ohisaki-komore ru mado no uti naru hodo ha, tada kata-kado wo kiki-tutahe te, kokoro wo ugokasu koto mo a' meri. Katati wokasiku uti-ohodoki, wakayaka nite magiruru koto naki hodo, hakanaki susabi wo mo, hitomane ni kokoro wo iruru koto mo aru ni, onodukara, hito-tu yuwe-duke te si-iduru koto mo ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 見る人、後れたる方をば言ひ隠し、 さてありぬべき方をばつくろひて、まねび出だすに、『それ、しかあらじ』と、そらにいかがは推し量り思ひくたさむ。まことかと見もてゆくに、見劣りせぬやうは、 なくなむあるべき」 |
世話をする人は、劣った方面は隠して言わず、まあまあと言った方面をとりつくろって、それらしく言うので、『それは、そうではあるまい』と、見ないでどうしてあて推量で貶めることができましょう。本物かと思って付き合って行くうちに、がっかりしないというのは、きっとないでしょう」 |
それができると、仲に立った人間がいいことだけを話して、欠点は隠して言わないものですから、そんな時にそれはうそだなどと、こちらも空で断定することは不可能でしょう、真実だろうと思って結婚したあとで、だんだんあらが出てこないわけはありません」 |
Miru hito, okure taru kata wo ba ihi-kakusi, sate ari nu beki kata wo ba tukurohi te, manebi-idasu ni, 'Sore, sika ara zi' to, sora ni ikagaha osi-hakari omohi-kutasa m. Makoto ka to mi mote yuku ni, mi-otori se nu yau ha, naku nam aru beki." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | と、うめきたる気色も 恥づかしげなれば、いとなべてはあらねど、 われ思し合はすることやあらむ、うちほほ笑みて、 |
と言って、嘆息している様子も気遅れするようなので、全部が全部というのではないが、ご自身でもなるほどとお思いになることがあるのであろうか、ちょっと笑みを浮かべて、 |
中将がこう言って歎息した時に、そんなありきたりの結婚失敗者ではない源氏も、何か心にうなずかれることがあるか微笑をしていた。 |
to, umeki taru kesiki mo hadukasige nare ba, ito nabete ha ara ne do, ware obosi-ahasuru koto ya ara m, uti-hohowemi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.14 | 「 その、片かどもなき人は、あらむや」とのたまへば、 |
「その、一つの才能もない人というのは、いるものだろうか」とおっしゃると、 |
「あなたが今言った、一つくらいの芸ができるというほどのとりえね、それもできない人があるだろうか」 |
"Sono, kata-kado mo naki hito ha, ara m ya?" to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.15 | 「 いと、さばかりならむあたりには、 誰れかはすかされ寄りはべらむ。取るかたなく口惜しき際と、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数等しくこそはべらめ。人の 品高く生まれぬれば、人にもてかしづかれて、隠るること多く、自然にそのけはひこよなかるべし。中の品になむ、人の心々、おのがじしの立てたるおもむきも見えて、分かるべきことかたがた多かるべき。下のきざみといふ際になれば、ことに耳たたずかし」 |
「さあ、それほどのような所には、誰が騙されて寄りつきましょうか。何の取柄もなくつまらない身分の者と、素晴らしいと思われるほどに優れた者とは、同じくらいございましょう。家柄が高く生まれると、家人に大切に育てられて、人目に付かないことも多く、自然とその様子が格別でしょう。中流の女性にこそ、それぞれの気質や、めいめいの考え方や趣向も見えて、区別されることがそれぞれに多いでしょう。下層の女という身分になると、格別関心もありませんね」 |
「そんな所へは初めからだれもだまされて行きませんよ、何もとりえのないのと、すべて完全であるのとは同じほどに少ないものでしょう。上流に生まれた人は大事にされて、欠点も目だたないで済みますから、その階級は別ですよ。中の階級の女によってはじめてわれわれはあざやかな、個性を見せてもらうことができるのだと思います。またそれから一段下の階級にはどんな女がいるのだか、まあ私にはあまり興味が持てない」 |
"Ito, sabakari nara m atari ni ha, tare kaha sukasa re yori habera m. Toru kata naku kutiwosiki kiha to, iu nari to oboyu bakari sugure taru to ha, kazu hitosiku koso habera me. Hito no sina takaku mumare nure ba, hito ni mote-kasiduka re te, kakururu koto ohoku, zinen ni sono kehahi koyonakaru besi. Naka-no-sina ni nam, hito no kokoro-gokoro, onogazisi no tate taru omomuki mo miye te, wakaru beki koto kata-gata ohokaru beki. Simo no kizami to ihu kiha ni nare ba, kotoni mimi tata zu kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.16 | とて、 いと隈なげなる気色なるも、 ゆかしくて、 |
と言って、何でも知っている様子であるのも、興味が惹かれて、 |
こう言って、通を振りまく中将に、源氏はもう少しその観察を語らせたく思った。 |
tote, ito kumanage naru kesiki naru mo, yukasiku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.17 | 「 その品々や、いかに。いづれを三つの品に置きてか分くべき。元の品高く生まれながら、身は沈み、位みじかくて 人げなき。また 直人の 上達部など までなり上り、我は顔にて家の内を飾り、人に劣らじと思へる。そのけぢめをば、いかが分くべき」 |
「その身分身分というのは、どのように考えたらよいのか。どれを三つの階級に分け置くことができるのか。元の階層が高い生まれでありながら、今の身の上は落ちぶれ、位が低くて人並みでない人。また一方で普通の人で上達部などまで出世して、得意顔して邸の内を飾り、人に負けまいと思っている人。その区別は、どのように付けたらよいのだろうか」 |
「その階級の別はどんなふうにつけるのですか。上、中、下を何で決めるのですか。よい家柄でもその娘の父は不遇で、みじめな役人で貧しいのと、並み並みの身分から高官に成り上がっていて、それが得意で贅沢な生活をして、初めからの貴族に負けないふうでいる家の娘と、そんなのはどちらへ属させたらいいのだろう」 |
"Sono sina-zina ya, ika-ni? Idure wo mi-tu no sina ni oki te ka waku beki? Moto no sina takaku mumare nagara, mi ha sidumi, kurawi mizikaku te hitoge-naki. Mata naho-bito no kamdatime nado made nari-nobori, ware-ha-gaho nite ihe no uti wo kazari, hito ni otora zi to omohe ru. Sono kedime woba, ikaga waku beki?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.18 | と問ひたまふほどに、左馬頭、 藤式部丞、御物忌に籠もらむとて参れり。世の好き者にて物よく言ひとほれるを、中将待ちとりて、この品々をわきまへ定め争ふ。 いと聞きにくきこと多かり。 |
とお尋ねになっているところに、左馬頭や藤式部丞が御物忌に籠もろうとして参上した。当代の好色者で弁舌が達者なので、中将は待ち構えて、これらの品々の区別の議論を戦わす。まことに聞きにくい話が多かった。 |
こんな質問をしている所へ、左馬頭と藤式部丞とが、源氏の謹慎日を共にしようとして出て来た。風流男という名が通っているような人であったから、中将は喜んで左馬頭を問題の中へ引き入れた。不謹慎な言葉もそれから多く出た。 |
to tohi tamahu hodo ni, Hidari-no-Muma-no-kami, Tou-Sikibu-no-zyou, ohom-monoimi ni komora m tote mawire ri. Yo no suki-mono nite mono yoku ihi-tohore ru wo, Tyuuzyau mati-tori te, kono sina-zina wo wakimahe sadame arasohu. Ito kiki-nikuki koto ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 左馬頭、藤式部丞ら女性談義に加わる |
1-3 Sama-no-Kami and Tou-Shikibu-no-Jo join them |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 「 なり上れども、もとよりさるべき筋ならぬは、世人の思へることも、さは言へど、なほことなり。また、元はやむごとなき筋なれど、世に経るたづき少なく、 時世に移ろひて、おぼえ衰へぬれば、心は心としてこと足らず、悪ろびたることども 出でくるわざなめれば、とりどりにことわりて、中の品にぞ置くべき。 |
「成り上がっても、元々の相応しいはずの家柄でない者は、世間の人の心証も、そうは言っても、やはり格別です。また、元は高貴な家筋であるが、世間を渡る手づるが少なく、時勢におし流されて、声望も地に落ちてしまうと、気位だけは高くても思うようにならず、不体裁なことなどが生じてくるもののようですから、それぞれに分別して、中の品に置くのが適当でしょう。 |
「いくら出世しても、もとの家柄が家柄だから世間の思わくだってやはり違う。またもとはいい家でも逆境に落ちて、何の昔の面影もないことになってみれば、貴族的な品のいいやり方で押し通せるものではなし、見苦しいことも人から見られるわけだから、それはどちらも中の品ですよ。 |
"Nari-nobore domo, motoyori saru-beki sudi nara nu ha, yohito no omohe ru koto mo, saha ihe do, naho koto nari. Mata, moto ha yamgotonaki sudi nare do, yo ni huru taduki sukunaku, tokiyo ni uturohi te, oboye otorohe nure ba, kokoro ha kokoro to si te koto tara zu, warobi taru koto-domo ide-kuru waza na' mere ba, tori-dori ni kotowari te, naka-no-sina ni zo oku beki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 受領と言ひて、人の国のことにかかづらひ営みて、品定まりたる中にも、またきざみきざみありて、中の品の けしうはあらぬ、選りで出でつべきころほひなり。 なまなまの上達部よりも非参議の四位どもの、世のおぼえ口惜しからず、もとの根ざし卑しからぬ、やすらかに身をもてなしふるまひたる、いとかはらかなりや。 |
受領と言って、地方の政治に掛かり切りにあくせくして、階層の定まった中でも、また段階段階があって、中の品で悪くはない者を、選び出すことができる時勢です。なまじっかの上達部よりも非参議の四位連中で、世間の信望もまんざらでなく、元々の生まれも卑しくない人が、あくせくせずに暮らしているのが、いかにもさっぱりした感じですよ。 |
受領といって地方の政治にばかり関係している連中の中にもまたいろいろ階級がありましてね、いわゆる中の品として恥ずかしくないのがありますよ。また高官の部類へやっとはいれたくらいの家よりも、参議にならない四位の役人で、世間からも認められていて、もとの家柄もよく、富んでのんきな生活のできている所などはかえって朗らかなものですよ。 |
Zuryau to ihi te, hito-no-kuni no koto ni kakadurahi itonami te, sina sadamari taru naka ni mo, mata kizami-kizami ari te, naka-no-sina no kesiu ha ara nu, eri-ide tu beki korohohi nari. Nama-nama no kamdatime yori mo hi-samgi no si-wi-domo no, yo no oboye kutiwosikara zu, moto no nezasi iyasikara nu, yasuraka ni mi wo motenasi hurumahi taru, ito kaharaka nari ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 家の内に足らぬことなど、 はたなかめるままに、省かずまばゆきまでもてかしづける女などの、おとしめがたく生ひ出づるもあまたあるべし。 宮仕へに出で立ちて、思ひかけぬ幸ひとり出づる例ども多かりかし」 など言へば、 |
暮らしの中で足りないものなどは、やはりないようなのにまかせて、けちらずに眩しいほど大切に世話している娘などが、非難のしようがないほどに成長しているのもたくさんいるでしょう。宮仕えに出て来て、思いもかけない幸運を得た例などもたくさんあるものです」などと言うと、 |
不足のない暮らしができるのですから、倹約もせず、そんな空気の家に育った娘に軽蔑のできないものがたくさんあるでしょう。宮仕えをして思いがけない幸福のもとを作ったりする例も多いのですよ」 左馬頭がこう言う。 |
Ihe no uti ni tara nu koto nado, hata naka' meru mama ni, habuka zu mabayuki made mote-kasiduke ru musume nado no, otosime-gataku ohi-iduru mo amata aru besi. Miya-dukahe ni ide-tati te, omohi-kake nu saihahi tori-iduru tamesi-domo ohokari kasi." nado ihe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 「 すべて、にぎははしきによるべきななり」とて、 笑ひたまふを、 |
「およそ、金持ちによるべきだということだね」と言って、お笑いになるのを、 |
「それではまあ何でも金持ちでなければならないんだね」 と源氏は笑っていた。 |
"Subete, nigihahasiki ni yoru beki na' nari." tote, warahi tamahu wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | 「 異人の言はむように、心得ず仰せらる」と、 中将憎む。 |
「他の人が言うように、意外なことをおっしゃる」と言って、中将は憎らしがる。 |
「あなたらしくないことをおっしゃるものじゃありませんよ」 中将はたしなめるように言った。左馬頭はなお話し続けた。 |
"Koto-hito no iha m yau ni, kokoroe zu ohose raru." to, Tyuuzyau nikumu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 「 元の品、時世のおぼえうち合ひ、やむごとなきあたりの内々のもてなしけはひ後れたらむは、 さらにも言はず、何をしてかく生ひ出でけむと、言ふかひなくおぼゆべし。うち合ひてすぐれたらむもことわり、これこそは さるべきこととおぼえて、めづらかなることと心も驚くまじ。 なにがしが及ぶべきほどならねば、上が上は うちおきはべりぬ。 |
「元々の階層と、時勢の信望が兼ね揃い、高貴な家で内々の振る舞いや様子が劣っているようなのは、まったく今更言うまでもないが、どうしてこう育てたのだろうと、残念に思われましょう。兼ね揃って優れているのも当たり前で、この女性こそは当然のことだと思われて、珍しいことだと気持ちも動かないでしょう。わたくしごとき者の手の及ぶ範囲ではないので、上の品の上は措いておきましょう。 |
「家柄も現在の境遇も一致している高貴な家のお嬢さんが凡庸であった場合、どうしてこんな人ができたのかと情けないことだろうと思います。そうじゃなくて地位に相応なすぐれたお嬢さんであったら、それはたいして驚きませんね。当然ですもの。私らにはよくわからない社会のことですから上の品は省くことにしましょう。 |
"Moto no sina, tokiyo no oboye uti-ahi, yamgotonaki atari no uti-uti no motenasi kehahi okure tara m ha, sarani mo iha zu, nani wo si te kaku ohi-ide kem to, ihukahinaku oboyu besi. Uti-ahi te sugure tara m mo kotowari, kore koso ha saru-beki koto to oboye te, meduraka naru koto to kokoro mo odoroku mazi. Nanigasi ga oyobu beki hodo nara ne ba, kami ga kami ha uti-oki haberi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | さて、世にありと人に知られず、 さびしくあばれたらむ 葎の門に、思ひの外にらうたげならむ人の閉ぢられたらむこそ、限りなくめづらしくはおぼえめ。 いかで、はたかかりけむと、思ふより違へることなむ、あやしく心とまるわざなる。 |
ところで、世間で人に知られず、寂しく荒れたような草深い家に、思いも寄らないいじらしいような女性がひっそり閉じ籠められているようなのは、この上なく珍しく思われましょう。どうしてまあ、こんな人がいたのだろうと、想像していたことと違って、不思議に気持ちが引き付けられるものです。 |
こんなこともあります。世間からはそんな家のあることなども無視されているような寂しい家に、思いがけない娘が育てられていたとしたら、発見者は非常にうれしいでしょう。意外であったということは十分に男の心を引くカになります。 |
Sate, yo ni ari to hito ni sira re zu, sabisiku abare tara m mugura no kado ni, omohi no hoka ni rauta-ge nara m hito no todira re tara m koso, kagirinaku medurasiku ha oboye me. Ikade, hata kakari kem to, omohu yori tagahe ru koto nam, ayasiku kokoro tomaru waza naru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.8 | 父の年老い、ものむつかしげに太りすぎ、兄の顔憎げに、 思ひやりことなることなき閨の内に、 いといたく思ひあがり、はかなくし出でたることわざも、ゆゑなからず見えたらむ、片かどにても、 いかが思ひの外にをかしからざらむ。 |
父親が年を取り、見苦しく太り過ぎ、兄弟の顔が憎々しげで、想像するにたいしたこともない家の奥に、とてもたいそう誇り高く、ちょっとした芸事でも、雅趣ありげに見えるようなのは、生かじりの才能であっても、どうして意外なことでおもしろくないことがありましょうか。 |
父親がもういいかげん年寄りで、醜く肥った男で、風采のよくない兄を見ても、娘は知れたものだと軽蔑している家庭に、思い上がった娘がいて、歌も上手であったりなどしたら、それは本格的なものではないにしても、ずいぶん興味が持てるでしょう。 |
Titi no tosi oyi, mono-mutukasige ni hutori-sugi, seuto no kaho nikuge ni, omohi-yari koto naru koto naki neya no uti ni, ito itaku omohi-agari, hakanaku si-ide taru koto-waza mo, yuwe nakara zu miye tara m, kata-kado nite mo, ikaga omohi no hoka ni wokasikara zara m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.9 | すぐれて疵なき方の選びにこそ及ばざらめ、 さる方にて 捨てがたきものをは」 |
特別に欠点のない方面の女性選びは実現難しいでしょうが、それはそうした者として捨てたものではないな」 |
完全な女の選にははいりにくいでしょうがね」 |
Sugurete kizu naki kata no erabi ni koso oyoba zara me, saru kata nite sute-gataki mono wo ha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.10 | とて、式部を見やれば、 わが妹どものよろしき聞こえあるを思ひてのたまふにや、とや心得らむ、ものも言はず。 |
と言って、式部を見やると、自分の妹たちがまあまあの評判であることを思っておっしゃるのか、と受け取ったのであろうか、何とも言わない。 |
と言いながら、同意を促すように式部丞のほうを見ると、自身の妹たちが若い男の中で相当な評判になっていることを思って、それを暗に言っているのだと取って、式部丞は何も言わなかった。 |
tote, Sikibu wo miyare ba, waga imouto-domo no yorosiki kikoye aru wo omohi te notamahu ni ya, to ya kokorou ram, mono mo iha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.11 | 「 いでや、上の品と思ふにだに難げなる世を」と、君は思すべし ★。 白き御衣どもの ▼ なよらかなるに、直衣ばかりを しどけなく着なしたまひて、紐なども うち捨てて、添ひ臥したまへる御火影、いとめでたく、 女にて見たてまつらまほし。 この御ためには上が上を選り出でても、なほ飽くまじく見えたまふ。 |
「さてどんなものか、上の品と思う中でさえ難しい世の中なのに」と、源氏の君はお思いのようである。白いお召物で柔らかな物の上に、直衣だけを気楽な感じにお召しになって、紐なども結ばずに、物に寄り掛かっていらっしゃる灯影は、とても素晴らしく、女性として拝したいくらいだ。この源氏の君のおんためには、上の上の女性を選び出しても、猶も満足ではなさそうにお見受けされる。 |
そんなに男の心を引く女がいるであろうか、上の品にはいるものらしい女の中にだって、そんな女はなかなか少ないものだと自分にはわかっているがと源氏は思っているらしい。柔らかい白い着物を重ねた上に、袴は着けずに直衣だけをおおように掛けて、からだを横にしている源氏は平生よりもまた美しくて、女性であったらどんなにきれいな人だろうと思われた。この人の相手には上の上の品の中から選んでも飽き足りないことであろうと見えた。 |
"Ideya, kami-no-sina to omohu dani katage naru yo wo!" to, Kimi ha obosu besi. Siroki ohom-zo-domo no nayoraka naru ni, nahosi bakari wo sidokenaku ki-nasi tamahi te, himo nado mo uti-sute te, sohi-husi tamahe ru ohom-hokage, ito medetaku, womna nite mi tatematura mahosi. Kono ohom-tame ni ha kami ga kami wo eri-ide te mo, naho aku maziku miye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.12 | さまざまの人の上どもを 語り合はせつつ、 |
さまざまな女性について議論し合っていって、 |
「ただ世間の人として見れば無難でも、実際自分の妻にしようとすると、合格するものは見つからないものですよ。男だって官吏になって、お役所のお勤めというところまでは、だれもできますが、実際適所へ適材が行くということはむずかしいものですからね。しかしどんなに聡明な人でも一人や二人で政治はできないのですから、上官は下僚に助けられ、下僚は上に従って、多数の力で役所の仕事は済みますが、 |
Sama-zama no hito-no-uhe-domo wo katari-ahase tutu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.13 | 「 おほかたの世につけて見るには咎なきも、わがものとうち頼むべきを選らむに、多かる中にも、 えなむ思ひ定むまじかりける。 男の朝廷に仕うまつり、はかばかしき 世のかためとなるべきも、まことの器ものとなるべきを取り出ださむには、かたかるべしかし。されど、賢しとても、一人二人世の中をまつりごちしるべきならねば、 上は下に輔けられ、下は上になびきて、こと広きに譲ろふらむ。 |
「通り一遍の仲として付き合っているには欠点がなくい女でも、わが伴侶として信頼できる女性を選ぼうとするには、たくさんいる中でも、なかなか決め難いものですなあ。男性が朝廷にお仕えし、しっかりとした世の重鎮となるような方々の中でも、真の優れた政治家と言えるような人物を数え上げるとなると、難しいことでしょうよ。しかし、賢者と言っても、一人や二人で世の中の政治を執り行えるものではありませんから、上の人は下の者に助けられ、下の者は上の人に従って、政治の事は広いものですから互いに委ね合っていくのでしょう。 |
一家の主婦にする人を選ぶのには、ぜひ備えさせねばならぬ資格がいろいろと幾つも必要なのです。これがよくてもそれには適しない。少しは譲歩してもまだなかなか思うような人はない。世間の多数の男も、いろいろな女の関係を作るのが趣味ではなくても、生涯の妻を捜す心で、できるなら一所懸命になって自分で妻の教育のやり直しをしたりなどする必要のない女はないかとだれも思うのでしょう。 |
"Ohokata no yo ni tuke te miru ni ha toga naki mo, waga mono to uti-tanomu beki wo era m ni, ohokaru naka ni mo, e nam omohi-sadamu mazikari keru. Wonoko no ohoyake ni tukaumaturi, haka-bakasiki yo-no-katame to naru beki mo, makoto no utuha-mono to naru beki wo tori-idasa m ni ha, katakaru besi kasi. Saredo, kasikosi tote mo, hitori hutari yononaka wo maturi-goti siru beki nara ne ba, kami ha simo ni tasuke rare, simo ha kami ni nabiki te, koto hiroki ni yudurohu ram. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.14 | 狭き家の内の主人とすべき人一人を思ひめぐらすに、足らはで悪しかるべき大事どもなむ、かたがた多かる。 ▼ とあればかかり、あふさきるさにて、 なのめにさてもありぬべき人の 少なきを、好き好きしき心のすさびにて、人のありさまをあまた見合はせむの好みならねど、ひとへに思ひ定むべきよるべとすばかりに、同じくは、わが力入りをし直しひきつくろふべき所なく、心にかなふやうにもやと、選りそめつる人の、定まりがたきなるべし。 |
狭い家の中の主婦とすべき女性一人について思案すると、できないでは済まされないいくつもの大事が、こまごまと多くあります。ああ思えばこうであったり、何かと食い違って、不十分ながらにもまあまあやって行けるような女性が少ないので、浮気心の勢いのままに、世の女性の有様をたくさん見比べようとの好奇心ではないが、ひたすら伴侶としたいばかりに、同じことなら、自ら骨を折って直したり教えたりしなければならないような所がなく、気に入るような女性はいないものかと、選り好みしはじめた人が、なかなか相手が決まらないのでしょう。 |
必ずしも理想に近い女ではなくても、結ばれた縁に引かれて、それと一生を共にする、そんなのはまじめな男に見え、また捨てられない女も世間体がよいことになります。しかし世間を見ると、そう都合よくはいっていませんよ。お二方のような貴公子にはまして対象になる女があるものですか。私などの気楽な階級の者の中にでも、これと打ち込んでいいのはありませんからね。 |
Sebaki ihe no uti no aruzi to su beki hito hitori wo omohi-megurasu ni, taraha de asikaru beki daizi-domo nam, kata-gata ohokaru. Toareba-kakari, ahusa-kirusa ni te, nanome ni sate mo ari nu beki hito no sukunaki wo, suki-zukisiki kokoro no susabi ni te, hito no arisama wo amata mi-ahase m no konomi nara ne do, hitohe ni omohi sadamu beki yorube to su bakari ni, onaziku ha, waga tikara-iri wo si nahosi hiki-tukurohu beki tokoro naku, kokoro ni kanahu yau ni mo ya to, eri-some turu hito no, sadamari-gataki naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.15 | かならずしもわが思ふにかなはねど、 見そめつる契りばかりを捨てがたく思ひとまる人は、ものまめやかなりと見え、さて、保たるる女のためも、 心にくく 推し量らるるなり。 されど、何か、世のありさまを見たまへ集むるままに、心に及ばずいとゆかしきこともなしや。 君達の上なき御選びには、まして、いかばかりの人かは 足らひたまはむ。 |
必ずしも自分の理想通りではないが、いったん見初めた前世の約束だけを破りがたく思い止まっている人は、誠実であると見え、そうして、一緒にいる女性のためにも、奥ゆかしいものがあるのだろうと自然と推量されるものです。しかし、なあに、世の中の夫婦の有様をたくさん拝見していくと、想像以上にたいして羨ましいと思われることもありませんよ。公達の最上流の奥方選びには、なおさらのこと、どれほどの女性がお似合いになりましょうか。 |
見苦しくもない娘で、それ相応な自重心を持っていて、手紙を書く時には蘆手のような簡単な文章を上手に書き、墨色のほのかな文字で相手を引きつけて置いて、もっと確かな手紙を書かせたいと男をあせらせて、声が聞かれる程度に接近して行って話そうとしても、息よりも低い声で少ししかものを言わないというようなのが、男の正しい判断を誤らせるのですよ。なよなよとしていて優し味のある女だと思うと、あまりに柔順すぎたりして、またそれが才気を見せれば多情でないかと不安になります。そんなことは選定の最初の関門ですよ。 |
Kanarazu-simo waga omohu ni kanaha ne do, mi-some turu tigiri bakari wo sute-gataku omohi tomaru hito ha, mono-mameyaka nari to miye, sate, tamota ruru womna no tame mo, kokoro-nikuku osihakara ruru nari. Saredo, nani ka, yo no arisama wo mi tamahe atumuru mama ni, kokoro ni oyoba zu ito yukasiki koto mo nasi ya! Kimdati no kami naki ohom-erabi ni ha, masite, ikabakari no hito kaha tarahi tamaha m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.16 | 容貌きたなげなく、 若やかなるほどの、おのがじしは塵もつかじと身をもてなし、文を書けど、おほどかに言選りをし、墨つきほのかに心もとなく 思はせつつ、またさやかにも見てしがなとすべなく待たせ、わづかなる声聞くばかり言ひ寄れど、息の下にひき入れ 言少ななるが、いとよく もて隠すなりけり。なよびかに女しと見れば、あまり情けにひきこめられて、 とりなせば、あだめく。これをはじめの難とすべし。 |
容貌がこぎれいで、若々しい年頃で、自分自身では塵もつけまいと身を振る舞い、手紙を書いても、おっとりと言葉選びをし、墨付きも淡く関心を持たせ持たせし、もう一度はっきりと見たいものだとじれったく待たせ、わずかばかりの声を聞く程度に言い寄っても、息を殺して声小さく言葉少ななのが、とてもよく欠点を隠すものですなあ。艶っぽくて女性的だと見えると、度を越して情趣にこだわって、調子を合わせると、浮わつきます。これを、第一の難点と言うべきでしょう。 |
妻に必要な資格は家庭を預かることですから、文学趣味とかおもしろい才気などはなくてもいいようなものですが、まじめ一方で、なりふりもかまわないで、額髪をうるさがって耳の後ろへはさんでばかりいる、ただ物質的な世話だけを一所懸命にやいてくれる、そんなのではね。 |
Katati kitanage naku, wakayaka naru hodo no, onogazisi ha tiri mo tuka zi to mi wo motenasi, humi wo kake do, ohodoka ni kotoeri wo si, sumi-tuki honoka ni kokoromotonaku omohase tutu, mata sayaka ni mo mi te si gana to subenaku mata se, waduka naru kowe kiku bakari ihiyore do, iki no sita ni hiki-ire koto-zukuna naru ga, ito yoku mote-kakusu nari keri. Nayobika ni womnasi to mire ba, amari nasake ni hiki-kome rare te, torinase ba, adameku. Kore wo hazime no nan to su besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.17 | 事が中に、なのめなるまじき人の後見の方は、 もののあはれ知り過ぐし、はかなきついでの情けあり、をかしきに進める方なくてもよかるべしと 見えたるに、また、 まめまめしき筋を立てて耳はさみがちに美さうなき家刀自の、ひとへにうちとけたる後見 ばかりをして。 |
家事の中で、疎かにできない夫の世話という点では、物の情趣が度を過ごし、ちょっとした折の風情があり、趣味性に過度になるのはなくてもよいことだろうと思われますが、また一方で、家事一点張りで、額髪を耳挟みがちに飾り気のない主婦で、ひたすら世帯じみた世話だけをして。 |
お勤めに出れば出る、帰れば帰るで、役所のこと、友人や先輩のことなどで話したいことがたくさんあるんですから、それは他人には言えません。理解のある妻に話さないではつまりません。この話を早く聞かせたい、妻の意見も聞いて見たい、こんなことを思っているとそとででも独笑が出ますし、一人で涙ぐまれもします。また自分のことでないことに公憤を起こしまして、自分の心にだけ置いておくことに我慢のできぬような時、けれども自分の妻はこんなことのわかる女でないのだと思うと、横を向いて一人で思い出し笑いをしたり、かわいそうなものだなどと独言を言うようになります。そんな時に何なんですかと突っ慳貧に言って自分の顔を見る細君などはたまらないではありませんか。 |
Koto ga naka ni, nanome naru maziki hito no usiromi no kata ha, mono no ahare siri sugusi, hakanaki tuide no nasake ari, wokasiki ni susume ru kata naku te mo yokaru besi to miye taru ni, mata, mame-mamesiki sudi wo tate te mimi hasami-gati ni bisau naki ihetouzi no, hitohe ni utitoke taru usiromi bakari wo si te. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.18 | 朝夕の出で入りにつけても、公私の人のたたずまひ、善き悪しきことの、目にも耳にもとまるありさまを、 疎き人に、わざとうちまねばむやは。 近くて 見む人の聞きわき思ひ知るべからむに語りも合はせばやと、うちも笑まれ、涙もさしぐみ、もしは、あやなき おほやけ腹立たしく ★、心ひとつに思ひあまること など多かるを、 何にかは聞かせむと思へば、うちそむかれて、人知れぬ思ひ出で笑ひもせられ、『あはれ』とも、 うち独りごたるるに、『何ごとぞ』など、あはつかにさし仰ぎ ゐたらむは、 いかがは口惜しからぬ。 |
朝夕の出勤や帰宅につけても、公事や私事での他人の振る舞いや、善いこと悪いことで、目にも耳にも止まった有様を、親しくもない他人にわざわざそっくり話して聞かせたりしましょうか。親しい妻で理解してくれそうな者とこそ語り合いたいものだと思われ、つい微笑まれたり、涙ぐんだり、あるいはまた、無性に公憤をおぼえたり、胸の内に収めておけないことが多くあるのを、理解のない妻に、何で聞かせようか、聞かせてもしかたがない、と思いますと、ついそっぽを向きたくなって、人知れない思い出し笑いがこみ上げ、『ああ』とも、つい独り言を洩らすと、『何事ですか』などと、間抜けた顔で見上げるようなのは、どうして残念に思われないでしょうか。 |
ただ一概に子供らしくておとなしい妻を持った男はだれでもよく仕込むことに苦心するものです。たよりなくは見えても次第に養成されていく妻に多少の満足を感じるものです。一緒にいる時は可憐さが不足を補って、それでも済むでしょうが、家を離れている時に用事を言ってやりましても何ができましょう。遊戯も風流も主婦としてすることも自発的には何もできない、教えられただけの芸を見せるにすぎないような女に、妻としての信頼を持つことはできません。ですからそんなのもまただめです。平生はしっくりといかぬ夫婦仲で、淡い憎しみも持たれる女で、何かの場合によい妻であることが痛感されるのもあります」 |
Asa-yuhu no ide-iri ni tuke te mo, ohoyake watakusi no hito no tatazumahi, yoki asiki koto no, me ni mo mimi ni mo tomaru arisama wo, utoki hito ni, wazato uti-maneba m ya ha. Tikaku te mi m hito no kiki-waki omohi-siru bekara m ni katari mo ahase baya to, uti mo wema re, namida mo sasigumi, mosi ha, ayanaki ohoyake haradatasiku, kokoro hitotu ni omohi-amaru koto nado ohokaru wo, nani ni ka ha kika se m to omohe ba, uti-somuka re te, hito sire nu omohi-ide-warahi mo se rare, 'Ahare' to mo, uti-hitori-gota ruru ni, 'Nani-goto zo?' nado, ahatuka ni sasi-ahugi wi tara m ha, ikaga ha kutiwosikara nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.19 | ただひたふるに子めきて柔らかならむ人を、とかくひきつくろひては などか見ざらむ。心もとなくとも、直し所ある心地すべし。げに、さし向ひて見むほどは、 さてもらうたき方に罪ゆるし見るべきを、立ち離れてさるべきことをも言ひやり、 をりふしにし出でむわざのあだ事にもまめ事にも、わが心と思ひ得ることなく深きいたりなからむは、いと口惜しく頼もしげなき咎や、なほ苦しからむ。常はすこしそばそばしく心づきなき人の、 をりふしにつけて出でばえするやうもありかし」 |
ただひたすら子供っぽくて柔軟な女を、いろいろと教え諭してはどうして妻としないでいられようか。心配なようでも、きっと直し甲斐のある気持ちがするでしょう。なるほど、一緒に生活するぶんには、そんなふうでもかわいらしさに欠点も許され世話をしてやれようが、離れていては必要な用事などを言いやり、時節に行なうような事柄の風流事にも実用事などにも、自分では判断ができず深い思慮がないのは、まことに残念で頼りにならない欠点が、やはり困ったものでしょう。普段はちょっと無愛想で親しみの持てない女性が、何かの事に思わぬでき映えを発揮するようなこともありますからね」 |
こんなふうな通な左馬頭にも決定的なことは言えないと見えて、深い歎息をした。 |
Tada hitahuru ni ko-meki te yaharaka nara m hito wo, tokaku hiki-tukurohi te ha nado ka mi zara m. Kokoro-motonaku tomo, nahosi-dokoro aru kokoti su besi. Geni, sasi-mukahi te mi m hodo ha, satemo rautaki kata ni tumi yurusi miru beki wo, tati-hanare te saru-beki koto wo mo ihi-yari, worihusi ni si-ide m waza no ada-goto ni mo mame-goto ni mo, waga kokoro to omohi-uru koto naku hukaki itari nakara m ha, ito kutiwosiku tanomosige naki toga ya, naho kurusikara m. Tune ha sukosi soba-sobasiku kokoro-dukinaki hito no, worihusi ni tuke te ide-baye suru yau mo ari kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.20 | など、 隈なきもの言ひも、定めかねていたくうち嘆く。 |
などと、至らない所のない論客も、結論を出しかねて大きく溜息をつく。 |
nado, kumanaki mono-ihi mo, sadame-kane te itaku uti-nageku. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 女性論、左馬頭の結論 |
1-4 Sama-no-Kami's conclusion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 「 今は、ただ、品にもよらじ。容貌をば さらにも言はじ。いと口惜しく ねぢけがましきおぼえだになくは、ただひとへにものまめやかに、静かなる心のおもむきならむ よるべをぞ、つひの頼み所には思ひおくべかりける。 あまりのゆゑよし心ばせ うち添へたらむをば、よろこびに思ひ、すこし 後れたる方あらむをも、あながちに求め加へじ。うしろやすくのどけき 所だに強くは、うはべの情けは、おのづから もてつけつべきわざをや。 |
「今は、ただもう、家柄にもよりません。容貌はまったく問題ではありません。ひどく意に満たないひねくれた性格でさえなければ、ただひたすら実直で、落ち着いた心の様子がありそうな女性を、生涯の伴侶としては考え置くのがよいですね。余分な情趣を解する心や気立てのよさが加わっているようなのを、それを幸いと思い、少し足りないところがあるようなのも、無理に期待し要求するまい。安心できてのんびりとした性格さえはっきりしていれば、表面的な情趣は、自然と身に付けることができるものですからね。 |
「ですからもう階級も何も言いません。容貌もどうでもいいとします。片よった性質でさえなければ、まじめで素直な人を妻にすべきだと思います。その上に少し見識でもあれば、満足して少しの欠点はあってもよいことにするのですね。安心のできる点が多ければ、趣味の教育などはあとからできるものですよ。 |
"Ima ha, tada, sina ni mo yora zi. Katati wo ba sarani mo iha zi. Ito kutiwosiku nedike-gamasiki oboye dani naku ha, tada hitohe ni mono-mameyaka ni, siduka naru kokoro no omomuki nara m yorube wo zo, tuhi no tanomi-dokoro ni ha omohi-oku bekari keru. Amari no yuwe-yosi kokoro-base uti-sohe tara m wo ba, yorokobi ni omohi, sukosi okure taru kata ara m wo mo, anagati ni motome kuhahe zi. Usiro-yasuku nodokeki tokoro dani tuyoku ha, uhabe no nasake ha, onodukara mote-tuke tu beki waza wo ya. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 艶に もの恥ぢして、恨み言ふべきことをも見知らぬさまに忍びて、上はつれなくみさをづくり、心一つに思ひあまる時は、言はむかたなくすごき言の葉、あはれなる歌を詠みおき、しのばるべき形見をとどめて、深き山里、世離れたる海づらなどに はひ隠れぬるをり。 |
思わせぶりにはにかんで見せて、恨み言をいうべきことをも見知らないふうに我慢して、表面は何げなく平静を装い、胸に収めかね思いあまった時には、何とも言いようのないほどの恐ろしい言葉や、哀切な和歌を詠み残し、思い出になるにちがいない形見を残して、深い山里や、辺鄙な海浜などに姿を隠してしまう女がいます。 |
上品ぶって、恨みを言わなければならぬ時も知らぬ顔で済ませて、表面は賢女らしくしていても、そんな人は苦しくなってしまうと、凄文句や身にしませる歌などを書いて、思い出してもらえる材料にそれを残して、遠い郊外とか、まったく世間と離れた海岸とかへ行ってしまいます。 |
En ni mono-hadi si te, urami ihu beki koto wo mo mi-sira nu sama ni sinobi te, uhe ha turenaku misawo dukuri, kokoro-hitotu ni omohi-amaru toki ha, ihamkata-naku sugoki kotonoha, ahare naru uta wo yomi-oki, sinoba ru beki katami wo todome te, hukaki yamazato, yo-banare taru umidura nado ni hahi-kakure nuru wori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | 童にはべりし時、 女房などの物語読みしを聞きて、いとあはれに悲しく、心深きことかなと、 涙をさへなむ落としはべりし。今思ふには、いと軽々しく、ことさらびたることなり。心ざし深からむ男をおきて、 見る目の前につらきことありとも、人の心を見知らぬやうに逃げ隠れて、人をまどはし、 心を見むとするほどに、長き世のもの思ひになる、いとあぢきなきことなり。『心深しや』など、ほめたてられて、あはれ進みぬれば、 ▼ やがて尼になりぬかし。思ひ立つほどは、いと心澄めるやうにて、世に 返り見すべくも思へらず。『 いで、あな悲し。かくはた思しなりにけるよ』などやうに、あひ知れる人来とぶらひ、ひたすらに憂しとも思ひ離れぬ男、聞きつけて涙落とせば、使ふ人、古御達など、『君の御心は、あはれなりけるものを。あたら御身を』など言ふ。みづから額髪をかきさぐりて、 あへなく心細ければ、うちひそみぬかし。忍ぶれど涙こぼれそめぬれば、 折々ごとにえ念じえず、悔しきこと多かめるに、仏もなかなか心ぎたなしと、見たまひつべし。 濁りにしめるほどよりも、なま浮かびにては ★、かへりて悪しき道にも漂ひぬべくぞおぼゆる。絶えぬ宿世浅からで、尼にもなさで 尋ね取りたらむも、 やがてあひ添ひて、とあらむ折もかからむきざみをも、 見過ぐしたらむ仲こそ、契り深くあはれならめ、我も人も、うしろめたく 心おかれじやは。 |
子供でございましたころ、女房などが物語を読んでいたのを聞いて、とても気の毒に悲しく、何と深く思いつめたことかと、涙までを落としました。今から思うと、とても軽薄で、わざとらしいことです。愛情の深い夫を残して、たとえ目の前に薄情なことがあっても、夫の気持ちを分からないかのように姿をくらまして、夫を慌てさせ、本心を見ようとするうちに、一生の後悔となるのは、大変につまらないことです。『深い考えだ』などと、褒め立てられて、気持ちが昂じてしまうと、そのまま尼になってしまいますよ。思い立った当座は、まことに気持ちも悟ったようで、世俗の生活を振り返ってみようなどとは思わない。『まあ、何とおいたわしい。こうもご決心されたとは』などと言ったように、知り合いの人が見舞いに来たり、すっかり嫌だとも諦めてない夫が、聞きつけて涙を落とすと、召使いや、老女たちなどが、『殿のお気持ちは、愛情深かったのに。惜しいおん身を』などと言う。自分でも額髪を触って、手応えなく心細いので、泣顔になってしまう。堪えても涙がこぼれ出してしまうと、何かの時々には我慢もできず、後悔も多いようなので、仏もかえって未練がましいと、きっと御覧になるでしょう。濁世に染まっている間よりも、生悟りは、かえって悪道に堕ちさ迷うことになるに違いなく思われます。切っても切れない前世からの宿縁も浅くなく、尼にもさせず捜し出したような仲も、そのまま連れ添うことになって、あのような時にもこのような時にも、知らないふうにしているような夫婦仲こそ、宿縁も深く愛情も厚いと言えましょうに、自分も相手も、不安で自然と気をつかわずにいられましょうか。 |
子供の時に女房などが小説を読んでいるのを聞いて、そんなふうの女主人公に同情したものでしてね、りっぱな態度だと涙までもこぼしたものです。今思うとそんな女のやり方は軽佻で、わざとらしい。自分を愛していた男を捨てて置いて、その際にちょっとした恨めしいことがあっても、男の愛を信じないように家を出たりなどして、無用の心配をかけて、そうして男をためそうとしているうちに取り返しのならぬはめに至ります。いやなことです。りっぱな態度だなどとほめたてられると、図に乗ってどうかすると尼なんかにもなります。その時はきたない未練は持たずに、すっかり恋愛を清算した気でいますが、まあ悲しい、こんなにまであきらめておしまいになってなどと、知った人が訪問して言い、真底から憎くはなっていない男が、それを聞いて泣いたという話などが聞こえてくると、召使や古い女房などが、殿様はあんなにあなたを思っていらっしゃいますのに、若いおからだを尼になどしておしまいになって惜しい。こんなことを言われる時、短くして後ろ梳きにしてしまった額髪に手が行って、心細い気になると自然に物思いをするようになります。忍んでももう涙を一度流せばあとは始終泣くことになります。御弟子になった上でこんなことでは仏様も末練をお憎みになるでしょう。俗であった時よりもそんな罪は深くて、かえって地獄へも落ちるように思われます。また夫婦の縁が切れずに、尼にはならずに、良人に連れもどされて来ても、自分を捨てて家出をした妻であることを良人に忘れてもらうことはむずかしいでしょう。悪くてもよくてもいっしょにいて、どんな時もこんな時も許し合って暮らすのがほんとうの夫婦でしょう。一度そんなことがあったあとでは真実の夫婦愛がかえってこないものです。 |
Waraha ni haberi si toki, nyoubau nado no monogatari yomi si wo kiki te, ito ahare ni kanasiku, kokoro-hukaki koto kana to, namida wo sahe nam otosi haberi si. Ima omohu ni ha, ito karu-garusiku, kotosarabi taru koto nari. Kokorozasi hukakara m wotoko wo oki te, miru me no mahe ni turaki koto ari tomo, hito no kokoro wo mi-sira nu yau ni nige-kakure te, hito wo madohasi, kokoro wo mi m to suru hodo ni, nagaki yo no mono-omohi ni naru, ito adikinaki koto nari. 'Kokoro hukasi ya!' nado, home-tate rare te, ahare susumi nure ba, yagate ama ni nari nu kasi. Omohi-tatu hodo ha, ito kokoro sume ru yau ni te, yo ni kaherimi su beku mo omohe ra zu. 'Ide, ana kanasi! Kaku hata obosi nari ni keru yo!' nado yau ni, ahi-sire ru hito ki toburahi, hitasura ni usi to mo omohi-hanare nu wotoko, kiki-tuke te namida otose ba, tukahu hito, huru-gotati nado, 'Kimi no mi-kokoro ha, ahare nari keru mono wo! Atara ohom-mi wo!' nado ihu. Midukara hitahi-gami wo kaki-saguri te, ahenaku kokoro-bosokere ba, uti-hisomi nu kasi. Sinobure do namida kobore-some nure ba, wori-wori goto ni e nen-zi e zu, kuyasiki koto ohoka' meru ni, hotoke mo naka-naka kokoro-gitanasi to, mi tamahi tu besi. Nigori ni sime ru hodo yori mo, nama-ukabi nite ha, kaherite asiki miti ni mo tadayohi nu beku zo oboyuru. Taye nu sukuse asakara de, ama ni mo nasa de tadune tori tara m mo, yagate ahi-sohi te, to-ara m wori mo kakara m kizami wo mo, mi-sugusi tara m naka koso, tigiri hukaku ahare nara me, ware mo hito mo, usirometaku kokoro-oka re zi yaha! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | また、なのめに移ろふ方 あらむ人を恨みて、 気色ばみ背かむ、 はたをこがましかりなむ。 心は移ろふ方ありとも、 見そめし心ざしいとほしく思はば、 さる方のよすがに 思ひてもありぬべきに、 さやうならむたぢろきに、絶えぬべきわざなり。 |
また、いいかげんに愛情も冷めてきたような夫を恨んで、態度に表わして離縁するようなのは、これまたばかげたことでしょう。愛情が他の女に移ることがあったとしても、結婚した当初の愛情をいとしく思うならば、そうした縁の伴侶と思っていることもきっとあるでしょうに、そのようなごたごたから、夫婦の仲まで切れてしまうのです。 |
また男の愛がほんとうにさめている場合に家出をしたりすることは愚かですよ。恋はなくなっていても妻であるからと思っていっしょにいてくれた男から、これを機会に離縁を断行されることにもなります。 |
Mata, nanome ni uturohu kata ara m hito wo urami te, kesikibami somuka m, hata wokogamasikari na m. Kokoro ha uturohu kata ari tomo, misome si kokorozasi itohosiku omoha ba, saru-kata no yosuga ni omohi te mo ari nu beki ni, sayau nara m tadiroki ni, taye nu beki waza nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | すべて、よろずのことなだらかに、怨ずべきことをば見知れるさまにほのめかし、恨むべからむふしをも憎からずかすめなさば、それにつけて、あはれもまさりぬべし。多くは、 わが心も見る人からをさまりもすべし。あまりむげにうちゆるべ見放ちたるも、心安くらうたきやうなれど、おのづから 軽き方にぞおぼえはべるかし。 ▼ 繋がぬ舟の浮きたる例も、 げにあやなし。さははべらぬか」 |
総じて、どのようなことでも心穏やかに、嫉妬することは知っている様子にほのめかし、恨み言をいうべき場合にもかわいらしくそれとなく言えば、それによって、愛情も一段と増すことでしょう。一般に、自分の浮気心も妻の態度から収まりもするのです。あまりやたらに勝手にさせ放任しておくのも、気が楽でかわいらしいようだが、いつのまにか軽く見られるものです。繋がない舟の譬えもあり、なるほど思慮がない。そうではございませんか」 |
なんでも穏やかに見て、男にほかの恋人ができた時にも、全然知らぬ顔はせずに感情を傷つけない程度の怨みを見せれば、それでまた愛を取り返すことにもなるものです。浮気な習慣は妻次第でなおっていくものです。あまりに男に自由を与えすぎる女も、男にとっては気楽で、その細君の心がけがかわいく思われそうでありますが、しかしそれもですね、ほんとうは感心のできかねる妻の態度です。つながれない船は浮き歩くということになるじゃありませんか、ねえ」 |
Subete, yorodu no koto nadaraka ni, wen-zu beki koto wo ba mi-sire ru sama ni honomekasi, uramu bekara m husi wo mo nikukara zu kasume-nasa ba, sore ni tuke te, ahare mo masari nu besi. Ohoku ha, waga kokoro mo miru hito kara wosamari mo su besi. Amari muge ni uti-yurube mihanati taru mo, kokoro-yasuku rautaki yau nare do, onodukara karoki kata ni zo oboye haberu kasi. Tunaga nu hune no uki taru tamesi mo, geni ayanasi. Sa ha habera nu ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | と言へば、 中将うなづく。 |
と言うと、中将は頷く。 |
中将はうなずいた。 |
to ihe ba, Tyuuzyau unaduku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | 「 さしあたりて、 をかしともあはれとも心に入らむ人の、頼もしげなき疑ひあらむこそ、大事なるべけれ。 わが心あやまちなくて見過ぐさば、 さし直してもなどか見ざらむとおぼえたれど、 それさしもあらじ。ともかくも、 違ふべきふしあらむを、のどやかに見忍ばむよりほかに、ますこと あるまじかりけり」 |
「今さし当たって、美しいとも気立てがよいとも思って気に入っているような男が、不安な疑いがあるのは重大でしょう。自分が乱心せずに大目に見てやっていたら、気持ちを変えて添い遂げないこともないだろうと思われますが、そうとばかりも言えまい。いずれにしても、夫婦仲がうまくいかないようことがあってもそれを、気長にじっと堪えているより以外に、良い手段はないようですな」 |
「現在の恋人で、深い愛着を覚えていながらその女の愛に信用が持てないということはよくない。自身の愛さえ深ければ女のあやふやな心持ちも直して見せることができるはずだが、どうだろうかね。方法はほかにありませんよ。長い心で見ていくだけですね」 |
"Sasiatari te, wokasi to mo ahare to mo kokoro ni ira m hito no, tanomosi-ge naki utagahi ara m koso, daizi naru bekere. Waga kokoro ayamati naku te mi-sugusa ba, sasi-nahosi te mo nadoka mi zara m to oboye tare do, sore sasimo ara zi. Tomo-kakumo, tagahu beki husi ara m wo, nodoyaka ni mi-sinoba m yori hoka ni, masu koto aru mazikari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | と言ひて、 わが妹の姫君は、 この定めにかなひたまへりと思へば、 君のうちねぶりて言葉まぜたまはぬを、さうざうしく 心やましと思ふ。馬頭、物定めの博士になりて、 ひひらきゐたり。中将は、このことわり聞き果てむと、心入れて、 あへしらひゐたまへり。 |
と言って、自分の妹の姫君は、この結論に当てはまっていらっしゃると思うと、源氏の君が居眠りをして意見をさし挟みなさらないのを、物足りなく不満に思う。左馬頭がこの評定の博士になって、さらに弁じ立てていた。頭中将は、この弁論を最後まで聴こうと、熱心になって、受け答えしていらっしゃった。 |
と頭中将は言って、自分の妹と源氏の中はこれに当たっているはずだと思うのに、源氏が目を閉じたままで何も言わぬのを、物足らずも口惜しくも思った。左馬頭は女の品定めの審判者であるというような得意な顔をしていた。中将は左馬頭にもっと語らせたい心があってしきりに相槌を打っているのであった。 |
to ihi te, waga imouto no Hime-Gimi ha, kono sadame ni kanahi tamahe ri to omohe ba, Kimi no uti-neburi te, kotoba maze tamaha nu wo, sau-zausiku kokoro-yamasi to omohu. Muma-no-Kami, mono sadame no hakase ni nari te, hihiraki wi tari. Tyuuzyau ha, kono kotowari kiki-hate m to, kokoro ire te, ahesirahi wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | 「 よろづのことによそへて思せ。 木の道の匠のよろづの物を心にまかせて 作り出だすも ★、 臨時のもてあそび物の、その物と 跡も定まらぬは、 そばつきさればみたるも、げにかうもしつべかりけりと、時につけつつさまを変へて、今めかしきに目 移りてをかしきもあり。大事として、まことに うるはしき人の調度の飾りとする、定まれるやうある物を難なく し出づることなむ、なほまことの物の上手は、さまことに見え分かれはべる。 |
「いろいろのことに引き比べてお考えくだされ。木工の道の匠がいろいろの物を思いのままに作り出すのも、その場限りの趣向の物で、そうした型ときまりのないものは、見た目には洒落ているのも、なるほどこういうふうにも作るのだと、時々に従って趣向を変えて、目新しいのに目が移って趣のあるものもあります。重大な物として、本当にれっきとした人の調度類で装飾とする、一定の様式というようなのがあるものを立派に作り上げることは、やはり本当の名人は、違ったものだと見分けられるものでございます。 |
「まあほかのことにして考えてごらんなさい。指物師がいろいろな製作をしましても、一時的な飾り物で、決まった形式を必要としないものは、しゃれた形をこしらえたものなどに、これはおもしろいと思わせられて、いろいろなものが、次から次へ新しい物がいいように思われますが、ほんとうにそれがなければならない道具というような物を上手にこしらえ上げるのは名人でなければできないことです。 |
"Yorodu no koto ni yosohe te obose. Ki no miti no takumi no yorodu no mono wo kokoro ni makase te tukuri-idasu mo, rinzi no mote-asobi mono no, sono mono to ato mo sadamara nu ha, soba-tuki sare-bami taru mo, geni kau mo si tu bekari keri to, toki ni tuke tutu sama wo kahe te, imamekasiki ni me uturi te wokasiki mo ari. Daizi to si te, makoto ni uruhasiki hito no teudo no kazari to suru, sadamare ru yau aru mono wo nan naku si-iduru koto nam, naho makoto no mono-no-zyauzu ha, sama koto ni miye-wakare haberu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | また 絵所に上手多かれど、 墨がきに選ばれて、 次々にさらに劣りまさるけぢめ、ふとしも見え分かれず。かかれど、人の見及ばぬ蓬莱の山、荒海の怒れる 魚の姿、唐国のはげしき獣の形、 目に見えぬ鬼の顔などの、おどろおどろしく作りたる物は、心にまかせてひときは目驚かして、実には似ざらめど、 さてありぬべし。 |
また、画工司に名人が多くいますが、墨描きに選ばれて、順々に見るとまったく優劣の判断は、ちょっと見ただけではつきません。けれども、人の見ることもできない蓬莱山や、荒海の恐ろしい魚の形や、唐国の猛々しい獣の形や、目に見えない鬼の顔などで、仰々しく描いた物は、想像のままに格別に目を驚かして、実物には似ていないでしょうが、それはそれでよいでしょう。 |
また絵所に幾人も画家がいますが、席上の絵の描き手に選ばれておおぜいで出ます時は、どれがよいのか悪いのかちょっとわかりませんが、非写実的な蓬莱山とか、荒海の大魚とか、唐にしかいない恐ろしい獣の形とかを描く人は、勝手ほうだいに誇張したもので人を驚かせて、それは実際に遠くてもそれで通ります。 |
Mata we-dokoro ni zyauzu ohokare do, sumi-gaki ni eraba re te, tugi-tugi ni sarani otori masaru kedime, huto simo miye wakare zu. Kakaredo, hito no mi oyoba nu Hourai-no-yama, ara-umi no ikare ru iwo no sugata, Karakuni no hagesiki kedamono no katati, me ni miye nu oni no kaho nado no, odoro-odorosiku tukuri taru mono ha, kokoro ni makase te hitokiha me odorokasi te, ziti ni ha ni zara me do, sate ari nu besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | 世の常の山のたたずまひ、水の流れ、目に近き人の家居ありさま、 げにと見え、なつかしくやはらいだる方などを静かに描きまぜて、すくよかならぬ山の景色、木深く世離れて畳みなし、 け近き籬の内をば、その心しらひおきてなどをなむ、上手はいと勢ひことに、悪ろ者は及ばぬ所多かめる。 |
どこでも見かける山の姿や、川の流れや、見なれた人家の様子は、なるほどそれらしいと見えて、親しみやすくおだやかな方面などを心落ち着いた感じに配して、険しくない山の風景や、こんもりと俗塵を離れて幾重にも重ねたり、近くの垣根の中については、それぞれの心配りや配置などを、名人は大変に筆力も格別で、未熟な者は及ばない点が多いようです。 |
普通の山の姿とか、水の流れとか、自分たちが日常見ている美しい家や何かの図を写生的におもしろく混ぜて描き、われわれの近くにあるあまり高くない山を描き、木をたくさん描き、静寂な趣を出したり、あるいは人の住む邸の中を忠実に描くような時に上手と下手の差がよくわかるものです。 |
Yo no tune no yama no tatazumahi, midu no nagare, me ni tikaki hito no ihewi arisama, geni to miye, natukasiku yaharaidaru kata nado wo siduka ni kaki maze te, sukuyoka nara nu yama no kesiki, ko-bukaku yo-banare te tatami-nasi, ke-dikaki magaki no uti wo ba, sono kokoro sirahi okite nado wo nam, zyauzu ha ito ikihohi koto ni, waro-mono ha oyoba nu tokoro ohoka' meru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 手を書きたるにも、深きことはなくて、 ここかしこの、 点長に走り書き、そこはかとなく 気色ばめるは、うち見るにかどかどしく気色だちたれど、なほまことの筋をこまやかに 書き得たるは、うはべの筆消えて見ゆれど、今ひとたび とり並べて見れば、なほ 実になむよりける。 |
文字を書いたものでも、深い素養はなくて、あちらこちらが、点長にしゃれた走り書きをし、どことなく気取っているようなのは、ちょっと見ると才気がありひとかどのように見えますが、やはり正当の書法を丹念に習得しているものは、表面的な筆法は隠れていますが、もう一度取り比べて見ると、やはり本物の方に心が惹き付けられるものですな。 |
字でもそうです。深味がなくて、あちこちの線を長く引いたりするのに技巧を用いたものは、ちょっと見がおもしろいようでも、それと比べてまじめに丁寧に書いた字で見栄えのせぬものも、二度目によく比べて見れば技巧だけで書いた字よりもよく見えるものです。 |
Te wo kaki taru ni mo, hukaki koto ha naku te, koko-kasiko no, ten-naga ni hasiri-kaki, sokohakatonaku kesikibame ru ha, uti-miru ni kado-kadosiku kesikidati tare do, naho makoto no sudi wo komayaka ni kaki e taru ha, uhabe no hude kiye te miyure do, ima hito-tabi tori narabe te mire ba, naho ziti ni nam yori keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.13 | はかなきことだにかくこそはべれ。 まして人の心の、時にあたりて気色ばめらむ見る目の情けをば、 え頼むまじく思うたまへ得てはべる。 そのはじめのこと、好き好きしくとも申しはべらむ」 |
つまらない芸事でさえこうでございます。まして人の気持ちの、折々に様子ぶっているような見た目の愛情は、信用がおけないものと存じております。その最初の例を、好色がましいお話ですが申し上げましょう」 |
ちょっとしたことでもそうなんです、まして人間の問題ですから、技巧でおもしろく思わせるような人には永久の愛が持てないと私は決めています。好色がましい多情な男にお思いになるかもしれませんが、以前のことを少しお話しいたしましょう」 |
Hakanaki koto dani kaku koso habere. Masite hito no kokoro no, toki ni atari te kesikibame ra m miru me no nasake wo ba, e tanomu maziku omou tamahe e te haberu. Sono hazime no koto, suki-zukisiku to mo mausi habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.14 | とて、近くゐ寄れば、 君も目覚ましたまふ。 中将いみじく信じて、頬杖をつきて向かひゐたまへり。 法の師の世のことわり説き聞かせむ所の心地するも、かつはをかしけれど、 かかるついでは、おのおの睦言もえ忍びとどめずなむありける。 |
と言って、にじり寄るので、源氏の君も目をお覚ましになる。中将はひどく本気になって、頬杖をついて向かい合いに座っていらっしゃる。法師が世の中の道理を説いて聞かせているような所の感じがするのも、もう一方ではおもしろいが、このような折には、それぞれがうちとけたお話などを隠しておくことができないのであった。 |
と言って、左馬頭は膝を進めた。源氏も目をさまして聞いていた。中将は左馬頭の見方を尊重するというふうを見せて、頬杖をついて正面から相手を見ていた。坊様が過去未来の道理を説法する席のようで、おかしくないこともないのであるが、この機会に各自の恋の秘密を持ち出されることになった。 |
tote, tikaku wi yore ba, Kimi mo me samasi tamahu. Tyuuzyau imiziku sin-zi te, tura-due wo tuki te, mukahi wi tamahe ri. Nori-no-si no yo no kotowari toki kikase m tokoro no kokoti suru mo, katu ha wokasikere do, kakaru tuide ha, ono-ono mutugoto mo e sinobi todome zu nam ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 6/25/2003 渋谷栄一校訂(C)(ver.1-4-1) Last updated 6/25/2003 渋谷栄一注釈(C)(ver.1-3-1) |
Last updated 6/25/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-4-1) |
|
Last updated 6/25/2003 Written in Japnese roman letters by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-5-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 2.06: Copyrighy (c) 2003,2005 宮脇文経